|
|
|
 |
|
|
- 東京電力の過去の最大電力。
- 2001年を境に暫時現象の方向に向かっていたが、
- 平成19年(2007年)は6,147万kWに達した。
- 折からの猛暑が原因だった。
- 2011年東北地方太平洋沖地震が起き、以後消費電力のピークは5000万kWを割る時代が続いている。2016年は5332万kWに増えた。
|
|
- 東京電力のホームページより
- (2018年7月24日)
|
|
|
|
|
|
|
|
6000万kWというと、100万kW級の発電所60基分だ。関東地区にそれだけの発電設備はあったっけか?いずれにしてもやりくりが大変だ。
2018年7月現在、東京電力が保有する発電所と出力能力は以下の通りである。
新潟 - 柏崎刈羽原子力7基821万kW
福島 - 福島第一原子力6基470万kW、福島第二原子力4基440万kW、広野火力5基380万kW
茨城 - 鹿島火力6基440万kW、常陸那珂火力1基100万kW
千葉 - 五井火力6基189万kW、袖ヶ浦火力4基360万kW、千葉火力2号系ACC 288万kW、
姉ヶ崎火力6基360万kW、富津火力ACC3号系 504万kW、
神奈川 - 横浜火力8基 333万kW、東扇島火力2基200万kW、
横須賀火力8基 227万KW、南横浜火力3基115万kW、
川崎火力ACC 150万kW
東京 - 品川火力3基114万kW、大井火力3基105万kW
水力発電は、164箇所あり総合出力は987万kW。
一番大きい出力をもつ水力発電所は、新高瀬川発電所で128万kW。
50万kWクラスの水力発電所は7箇所しかない。
2007年8月 水量などの使用データに改ざんがあったとして稼働停止処分をを受けていたのに
電力不足で緊急稼働した塩原発電所は、90万kW。
風力発電は、東伊豆(11基、1,670kW)
地熱発電は、八丈島に1基3,300kW
太陽光発電は、浮島(7,000kW)、扇島(13,000kW)、米倉山(10,000kW)の合計30,000kW
以上を合計すると、東京電力は総合計6,618万kWの発電能力を持つことになる。
東京電力が持つ原子力発電所は、福島の第一原子力発電所が6基で470万kW、福島第二が4基で440万kW、柏崎刈羽が7基821万kW、合計1,731万kWの電力を供給する。
原子力発電は、細かな電力発生ができないので(原子炉内の核分裂によってエネルギーを取り出しているため、簡単に反応を制御することができない)、原子力発電を基本電力として、必要に応じて火力発電を稼働して需要電力に対応している。
この原子力発電は、2011年3月の東北大震災後発電を停止している。
原子力発電(1,731万kW)を除くと4,887万kWとなる。
近年の東京電力の最大電力は、ここ7年ほど5,000万kWで推移している。民間と個人からの太陽光発電の買い上げが700万kWあるので、原子力発電がなくてもこれらを合計すると5600万kWの発電量は確保でき、急場であるならば関連電力会社から購入も可能であろう。
しかし、いずれにしても夏場はギリギリの電力供給には違いない。
夏の電気使用量の40%は、冷房需要と言われている。(各家庭のエアコン、事業所の空調、コンピュータルームの空調、飲料用自動販売機)。
水力発電所は1基当たり100万kWの発電を行い、原子力発電所も100万kWの発電が可能である。
火力発電所は100万〜300万kWのプラントが可能で、これらを考えても、関東地区では60基程度の発電所が必要となる。発電所1基当たりの建設費用がいくらなのかはよくわからないが、土地代、変電設備、維持管理費、燃料などを考えるとかなりの高額な設備投資となる。ピークの電力消費を抑えて、平均化して電気を作り出したいとする努力が大いに理解できる。
1993年に電力10社が発電設備の設備投資に使ったお金は5兆100億円といわれている。
国民一人当たり50,000円の投資である
-
|
|
|
 |
|
|
東京電力ホームページより(2007.08.22) |
|
|
- 2007年8月22日の一日の東京電力の消費電力の推移。
- この日は、気温がグングン上がって(東京の最高気温37℃となり)残暑が厳しかった。
- この時期は、お盆休みも終わって企業では仕事を通常の軌道に乗せはじめた時である。
-
- このグラフは、そんな東京の消費電力の時間別に見たものである。
- 2007年8月は記録的な猛暑火が続き、この日の東京は37度を記録した。
- 気温が33度を超えると1度当たり170万kWの消費が増えるそうである。
- 東京電力は、夏の最高気温を35度と見積もって最大ピークを6150万kWと算出し、柏崎刈羽原子力発電所群が中越沖地震で発電停止に追い込まれてもやりくりする算段をしていた。
- しかし実際は、午前10時より気温がグングン上がり、最終的に摂氏37度となった。
-
- 上のグラフを見るとおもしろいことに気がつく。
- つまり、午前10時から午後4時まで、電力がほぼ一定に推移していることである。
- 一般的に電力の消費は、12時のお昼休みには電力が一息つき午後1時から3時にピークを迎えそうなものである。
- 山なりの曲線が自然である。
- それがこのグラフからは見て取れない。
- これは、つまり、電力会社が大口顧客(工場など)に対して電力のカットをお願いしているからにほかならない。
- 実際のところ、東京電力は、この日までに東北電力、中部電力、北海道電力にお願いして電力を120万kW譲ってもらい、長年の取水データ改ざんが公になって水の取り入れを禁止していた東京電力塩原水力発電所(那須塩原市、90万kW)までも緊急稼働させて6400万kWを確保した。
- 一方、随時調整契約を結んでいる大口顧客(大手メーカや役所)に対しては契約履行を実行した。
- 随時調整契約とは、電気料金を割り引く代わりに電力需給が窮迫した際には電気の使用を控えてもらうもので、1990年8月17日に履行されて以来17年ぶりという。
-
- このような努力によって頭打ち電力供給により、上のグラフに見るような電力使用グラフとなった。
- 翌日の東京地方は、前日までの気温とはうって違って最高気温が7度も低かった。
- そのおかげで使用電力は大幅に下がり、5,079万kWがピークとなった。
- この値は、上のグラフの午前7時台の消費電力である。
-
- 温度によって使用電力が1000万kWも変わってくるのは、冷房でいかにたくさんの電力を使っているかを如実に物語っている事柄といえよう。
|
|
|
|
|
|
|
-
-
-
-
-
- ■ 日本の電力使用 (2009.04.25追記)
- 日本は世界でも有数の電気食い虫国家だそうである。
- 一番電気を使用している国はもちろん米国。
- ピーク時の需要は、7億5000万kWだそうである。
- これは日本のざっと4倍である。
- 日本はどのくらいの電力を使っているかと言うと、夏のピーク時に(ピーク時に電力が十分にまかなえるように初電設備をする必要があるので、発電設備とも言い換えられる)1億8900万kW必要である。
- 各地区の電力は、2008年の資料によると
-
- 北海道: 570万kW (3.02%)
- 東北: 1,520万kW (8.05%)
- 東京: 6,4000万kW (33.9%)
- 中部: 2,800万kW (14.8%)
- 北陸: 560万kW (2.97%)
- 関西: 3,300万kW (17.5%)
- 中国: 1,230万kW (6.52%)
- 四国: 590万kW (3.13%)
- 九州: 1,760万kW (9.32%)
- 沖縄: 150万kW(0.79%)
- 合計: 18,880万kW となっている。
-
- 関東は、日本の1/3の電力を消費している。
- 人口9,000万人(10才以下の子供は電気を使う資格から外した)とすると、ひとり当たり1.9kWである。
- 部屋の明かり(照明器具=100W)をつけて、調理器(1kW)使って電子レンジ(1kw)使って、エアコン(800W)使って、テレビ(300W)見て、コンピュータ(100W)立ち上げて、オーディオ(300W)で音楽聞いていれば、そのくらいはおしなべて使っているかなという感じを受ける。
- それに、みんなが利用する新幹線や電車、ビルのエレベータ、空調、街路灯などをひっくるめれば、真夏の昼下がりにはそのぐらい行くのだろう。
- この電気を石油でまかなうと、1時間で、4千400万リットル(44,000立方メートル、タンクローリ4,400台分)が必要である。
- 実際は、火力発電は昼間の需要が多い時に運転され、その時の稼動は水力発電、原子力発電を含めた全発電量の約20%程度である。
-
-
■ 日本の電力使用量 (2006.01.17)(2006.04.05追記)
- 2005年あたりから、東京電力は「switch」という大々的なキャンペーンを行って家庭のエネルギーの電化を押し進めている。
- 電気を大切に使おうと呼び掛ける傍ら、ガスや灯油を使った熱源の使用を止めて、電気に替えましょうと呼びかけている。
- そんなキャンペーンをせずに、共存しても良いじゃない、停電したとき熱源が断たれてしまうのはとても不安だよ、という考えもなんのその、電気に替えましょうと煽る。
-
- その電力が、2005年暮れの記録的な厳冬をまともに受けて暖房需要が伸び、冬季最高の単月消費量を記録した。
- 2005年12月の消費電力は、806億kW時で、昨年同月に比べて11.1%も伸びたと言う。ちなみに、今までで一番消費電力量が多かったのは、2004年の7月で927億kW時であった。今回の消費量は、夏場に多く消費する通年を通して見てみても過去6番目の高い消費電力量となっている。806億kW時と言うと、1ヶ月31日で4000万世帯のうち1世帯一日あたり65kW時の消費量で、3kW弱の電気を一日中つけっぱなしにしていた計算である。(エアコン2基、大型冷蔵庫、大型テレビをガンガン使っても3kWにはいかないなぁ。) とは言っても、総電力消費量は家庭よりも事業所や新幹線、在来線などの公共施設の使用量が多いので、家庭で常時3kWを消費しているとまではいかなくても、とにかくすごい電力量である。
2005年の12月は、日本海側に記録的な積雪があり、送電線にも雪が積もって海岸からの湿った海水が絶縁碍子に付着し(塩害)、折からの強風で電線が揺れて(ギャロッピング)、送電線同士が重なりショートして停電が起きた。新潟ではこのため65万戸の大停電となった。吹雪のため送電線の復旧に時間がかかり、停電が長い所では丸1日以上続き、電気のない寒い生活を強いられた。
2006年2月に、仕事で新潟回りで富山にいく用事があり、越後湯沢から在来線に乗り換えて新潟平野を日本海目指して走っていった。十日町を過ぎる当たりで日本海からの強い風を体験し、快速特急が一時緊急停止した。あの重い電車が揺れてふぁっと浮き上がるような感触を受けた。その時、車窓からみた鉄塔から渡されている高圧電線が、縄跳びの縄のように大きく揺れていた。強い風の力で煽られているのだと実感した。
■ 発電所建設計画
2001.2.9日付の朝日新聞朝刊によると、「東京電力は今後5年間の新規発電所の建設計画を凍結した」、と興味ある記事を掲載していた。つまり、現行のままの発電設備で十分に電力がまかなえると東京電力は考えていて、お金のかかる建設計画は一時停止するというものであった。この記事の内容に私は少々ビックリした。私は、電力は右肩上がりで年々増えていくものとばかりと思っていたので、新聞の見出しを見た瞬間は事の真相がうまく飲み込めなかった。記事の詳細をよく見てみると、ここ4年の供給電力は、1996年の5,940万kWを最高に以後その電力を上回ることがなく、エアコンなどの省エネルギー製品の開発や自家発電設備、ガス冷房の普及などがあって、電力会社に依存する割合が減ってきたことを示唆していることがわかった。
東京電力では、1996年の電力ピーク以降も約500万kWの発電設備を整備し、現在では7,000万kWの供給能力を持っているといわれている。この電力が常時フル稼働するわけではなく定期点検で停止する場合も見込んで供給予備力は8%程度が目安とされているが、それでも現在の供給能力は需要電力の13%増しと過剰気味であると言う。
一方で、工場などの自家発電設備は年に45万kW、業務ビルなどのガス冷房設備も年に20万kWのベースで加わり、家庭用のエアコン1台あたりの消費電力も最近10年間で半分以下になった。これに、下で述べる太陽電池が年10万kWの生産を行って、徐々に配備されている事情を見ると大口の発電設備の必要性はなくなってきている。
2000.03月に日本の政府は、電力の小売りの部分自由化を2003年に拡大する方針を出していて、NTTグループ、東京ガス、米国エンロン・グループが発電設備建設を表明しているという背景もある。また、発電設備には巨大投資が必要で、東京電力は例年1兆5000億円(1993年は1兆6800億円)の投資予算をおこなってきていた。この需要減の見通しを受け、2001年には1兆円に抑える予定という。
■ 原子力発電所ショック (2003.4.29)
2003年4月に新潟、福島にある東京電力所有の原子力発電所17基がすべて止まった。安全を優先して点検を前倒しにしたため、この時期すべての原子力発電所からの送電がストップしたのである。関東圏内の電力の約40%をまかなう原子力発電がストップするため、夏場の電力ピークに需要がまかなえない危険が出てきている。話は遡って1987年7月23日午後1時過ぎ、「首都圏大停電」が起きた。東京をはじめとする埼玉、山梨、神奈川、静岡地区280万戸が停電したのである。この復旧に3時間を費やした。この大停電の原因は、冷房設備の稼働で需要が上がり発電所の電力供給が間に合わず、電圧が低下して送電網がダウンしたことによる。
2003年夏、原子力発電がストップしたままだと、夏場のピーク時の6450万kWの電力需要がまかなえない不安が出てくる。東京電力では、こうした事態にそなえ横須賀、川崎火力の計6基と、住友金属工業と共同出資の鹿島共同火力1基を合わせた7基を再稼働し、ほかの電力会社から融通して5500万kWを確保するという。しかしそれでもまだ950万kW不足する。再稼働する火力発電所は、高度成長期1960-1970年に操業を開始したが、脱石油政策や老朽化によって2000年以降6基が長期計画での停止になっていたものである。
- ■ 発電量統計 (2015.07.18)
-
- 国立情報学研究所 北本朝展氏のサイト(発電所データベース)に日本の発電実績の興味深いデータが紹介されている。
- 下のグラフは氏が掲載している2005年から10年間の実績グラフである。
- このグラフから総発電量が2005年から10年間で減ってきていることが読み取れる。グラフの波線は1年の四季における発電量変動であり、1年のうち二つのピークがある。夏と冬である。2005年から2010年までは夏のほうが発電量が多いのが顕著に認められたのに、2011年以降夏と冬のピークが同じになった来ているのは興味深い。冬場の暖房を電力に依存しているようである。また、2011年は歴史的大震災があった年であり、その年以降原子力発電がが皆無となって主な発電量を火力発電に頼って来ていることが読み取れる。
-

- グラフは、国立情報学研究所 北本朝展氏のサイト(発電所データベース)。
-
■ 電気を作るエネルギー (2001.03.11追記)
- 家庭用の電気を作るのにどれだけの燃料が必要なのであろうか?
- 過日、電力関係の訪問者から貴重なご情報をいただいたので紹介しておく。
- 火力発電所の主要な燃料は石油でミナス原油(精製前のとれたままの石油)を使用している。
-
- 結論から言うと、家庭で使っている電気は1kWhで250ml(缶ジュース一杯分)のミナス原油を使用している。
- 1ヶ月500kWhを使用する家庭では発電所はポリ缶(灯油缶)7個程度の油を使う。
- 原油から電気を取り出す熱効率が41%というからかなり効率が良い。
- ガソリンエンジンでも、ディーゼルエンジンでも熱効率は20%かそれ以下である。
-
- 【計算の詳細】
- 火力発電所の熱効率・燃料消費量と燃料の発熱量・発電機出力の関係は、次式で示される。
-
- η = (860P/H*W)*100 [%]
- P = H*W*η/(860*100) [kW]
- W = 860P/(H(η*100)) [kg/h]
- ここで、η:火力(汽力)発電所の(発電端)熱効率
- P:発電機出力 (kW)
- H:燃料の発熱量 (kcal/kg)
- W:ボイラーの燃料消費量 (kg)
-
-
- 代表的な例として、100万kW(1000MW)の発電所でミナス原油を使って、
- 熱効率41%で1時間発電(運転)を行うと、
- (ちなみにミナス原油の燃料の比重は0.86、発熱量10,700kcal/kg、もしくは9,200kcal/kl)
-
-
- W = 860P/[H(η*100)]
- =(860×1000*103)/(9.2*103*41*100)
- = 8600/377.2≒230 [kl]
- = 23万リットル/1時間
-
-
- 23万リットルの原油が消費される。
- 実際には、プラントの運転の為に使う動力や、変圧器や送電するときのいろいろの損失(ロス)があり、工場や家庭で使われる電力で換算すると1時間に25万リットル程度が必要になる。
-
- 覚えやすくするためには、1kWh当たり0.25リットル、即ちジュース缶1本の油がいると思えばよい。
-
- また、家庭で使用する電力量が1か月で500kWhとすれば、約125リットル、即ちポリ缶(17リットル灯油缶)7個程度の油を焚いているということになる。
- 火力発電所の場合、燃料には石油(原油)を使用するケースが最も多いという。
- しかし、石油は有限であり、資源の有効活用から現在も埋蔵量が豊富にある石炭の使用が研究テーマとして挙げられている。
- 石炭を使用する場合、石炭は固形物であるため燃料ボイラーに入れるのが液体(石油、天然ガス)に比べて手間がかかる。
- そこで、石炭を微粉化し水と混ぜてスラリーとしてパイプで搬送する手法が考え出されている。
- 石炭の場合、どれだけの量が発電につかわれるかというと、石炭の発熱量は標準で6,500kcal/kg前後なので
- 9,200/6,500=1.4
-
- 即ち油の約1.4倍、100万kWh当たり約35万kg=350トンとなる。
- つまり石炭で電気を起こした場合、1kWhあたり350g、1ヶ月500kWhの電気消費で175kgの石炭を消費することになる。
- 石炭は燃やすと灰が残る。その灰は、以前は埋め立て地に廃棄していたが、最近ではセメントの原料の一部にしたり、舗装の材料等に混和させたりして、再利用する方向に向かっている。
-
-
-
- ■ 電圧調整
-
- 電力会社は各家庭や事業所へ電圧と電源周波数を一定に保って電力を送電している。
- また、負荷変動に対してもAC100Vで50Hzの電源を保つように供給している。
-
- たくさんの電力が使われる場合、発電所からの電流が流れすぎて供給が間に合わず電圧が降下することがある。
- 電力会社は変動する電力に合わせて負荷に見合った発電を強いられることになる。
- 家庭用の電気機器は、一般にAC100V+/-10%の電圧でも正常に動くように作られている。
- つまり、電力会社から90V〜110Vの電圧が入力されても電気機器が正常に働くように設計・製造されていることになる。電力会社では、もう少し厳しく電力を作っている。電力関係者の話によるとAC100V+/-3V、60±0.2Hzを保ちながら電力を作っているそうである。
-
- こうした精度のよい電力はどのようにして作られているのであろうか? それも数百台もある発電所の発電機を寸部違わず電圧と周波数を同じにして、同期運転を行うのである。私は元来好奇心の旺盛な質(たち)なので、どうやってこうした精密な電気を作っているのかかねがね不思議に思っている。電力の需要は時々刻々変化している。新幹線が動く時、工場のラインが動くとき、夏場エアコンを一斉に付けるとき、政府研究所で大型風洞実験を行う際に起動する大電力モータが大電流を必要とする時、工場で大事故が起きて一瞬に大きな電流が流れたとき、そして、雷が発電所や変電所に落ちて電力がストップした時、などなど、こうしたときに電力会社はどう対処しているのか、興味はつきない。
-
- 電力会社では、管轄地域内の送電系統をループ状にし、(水力・火力)発電所の出力を変化させて、系統の周波数・電圧をできるだけ一定に保つようにしている。これを電力の世界では、「電力系統=Power System」と呼んで電力の供給ループを構築している。電力供給は、当然、負荷需要量の予測を立てる。大型コンピューターを使って、過去の実績や気象データ等をもとに、細かく寸断無くどれだけの電力が必要かの予測を行っている。デマンドとか給電司令所とかいうような言葉を聞いたことがあるかもしれないが、そうした需要の予測とそれに伴った発電の指令をここで行っている。電力の生産(=発電)を時時刻々需要に合わせて供給している。原子力発電も需要に従って発生電力を変化させることは十分可能であるが、日本ではまだ認められいないため、定格出力一定で運転している。たぶん運用上の危険を最低限に抑えたいという狙いと思われる。従って、発電量を変えるのは火力発電と水力発電がメインとなる。
-
- 春・秋の夜間時、電力消費が少なくて原子力発電が消費量を上回るようなときは、他の電力会社に送電して(原価割れで?)使ってもらうようなケースも出ているようである。
-
- 電力会社にとって、一定量の電力供給を行うことがどれほど難しく、逆に消費者が昼夜問わずにコンスタントに電気を使ってくれることがどれほど楽なことかを示してくれる事例である。
-
-
-
- ■ 電気の買い取り
-
- 最近、テレビの報道などで小口ユーザーが電力会社に対して電力を売っているトピックを耳にする。小口ユーザーがこうした電力を電力会社に売ることは喜ばしいことなのであろうか。電力は蓄えることが難しい代物であるからピーク電力を緩和することは切実な願いである。もしピーク時に逆に電気を戻してくれるユーザがいて、それが安定して長期間続くのであれば大歓迎なのであろう。小口ユーザーが電力会社に電気を売るときは何らかの条件があるものと思っている。たとえば電圧と電源周波数のしっかりした質のよい電力を作り出せる能力があるか、だとかノイズを含まないきれいな電源で、しかもある程度まとまった量と時間を確保してくれるものであるか、とかである。残念ながら現状では、太陽光はお天道様任せ、風力も風任せ、大型自家発は一定の電力しか出さない、という具合にホントに歓迎と言えるものはまだ無いといって良いだろう。
-
- 彼らが本音で本当に嬉しいと言えるのは、電力会社が時間帯別に一定の発電量(需要の負荷変動が極力抑えられるような予測ができる小口ユーザーからの供給)を確保できて、電力会社の発電設備の運転がスムーズにできるようなシステムが構築できた時、と電力関係者はコメントしている。現状で近いものとしては、バッテリー(レドックスフロー電池など含む、将来的にはキャパシター:電気二重層コンデンサーも含む)を組合せて、単独運転防止機能を組み込み、必要時のみ消費すると共に、昼間の指定時間だけ売電(電力会社に供給)してもらうようなシステムであるという。理想的なシステムができれば、電力会社として、新たな電源開発は殆ど必要なく、原子力を多用するとともに、効率の良い火力発電所を運転してしてCO2も減らせる、というメリットが出て来るという。
- 1-3-1. 発電の種類

-
- 【パーソナル発電】
- 屋台で使われている250ccガソリンエンジンを使った発々(はつはつ:発動発電機)は、100V5A(500W)程度の発電をができる。250ccエンジンは15馬力程度なので10%程度の効率で電気エネルギーが取り出だせる計算になる。建設現場や映画撮影ロケなどで電気が必要になる際には大型ディーゼルエンジン(5000cc〜10,000cc)を搭載した発々が使用される。大形の発々は、電気溶接、電動サンダー、ドリル、照明装置などに使用される。溶接などで電気を大量に使う時、発々に負荷がかかって黒い煙を吐きながら苦しい音を出して発動機がよがる。こうした状況を見ると仕事をしているな、と感じる。大量に負荷がかかると発動機の回転数が落ちる。この時電圧も落ちる。負荷変動でも電圧が落ちないためには発電機の側にレギュレータ回路が必要となる。
-
-
- 【発電所】
- 大型発電機は、今のところ蒸気と蒸気タービンを使った発電方式が主流である。蒸気タービンはスケーラビリティが良い(出力の大きな発電所が作りやすく効率も良い)ため、100万kWから300万kWのプラントが建設されている。蒸気タービンで蒸気を作るのに石油などを使うのが火力発電で、原子力の反応熱エネルギーで蒸気を作るのが原子力発電である。火力発電では大きなプラント建設が可能であり、最大のものは、愛知県知多発電所の原油・重油・天然ガス混合の396.6万kWがある(1997.8現在)。
- 原子力発電は、現在日本の総発電量の35%を賄っている。火力発電のように二酸化炭素、酸化窒素の発熱がでないため理想の発電エネルギーといえるが、燃料が放射性物質であるため維持管理に危険が伴い、使用済み核燃料の管理もやっかいである。発電量は100万kW程度がほとんどで、国内で最大のものは柏崎刈羽発電所6号機、7号機の135.6万kWである。
-
-
- 【原子力発電】
- 原子力は、安定した電力を得る上で必要不可欠。2011年3月の東北大震災までは電気量の35%を原子力に頼ってた。世界的に安全性が問われ風当たりも強いが、フランスでは70%強を原子力発電に頼っており、アメリカ、日本、ロシア、イギリス、中国、韓国も依存が高い。
- 決定的なエネルギー不足に悩む北朝鮮が「ゴネまくり外交」を展開して、韓国、アメリカ、日本から軽水炉の原子力発電所建設にこぎ着けさせたのは記憶に新しい。
- イタリア、スエーデンでは原子力撤廃を決めて原子力発電は姿を消した。日本でも原子力発電の研究開発は伸び悩んでおり、関係研究機関でも研究費の見直しを迫られたり、大学の原子力関連の学科では人気が落ちてきている。
- プラズマ、高速増殖炉など具体的な代替電気発電方式が安定しない現在のエネルギー事情では、原子力発電に依存せざるを得ないと思われるのだが・・・。
-
-
- 【水力発電】
- 水力発電は建設設備費用がかかることから発電力シェアは伸び悩み、10%(838億kWh)から9%(1,013億kWh)のシェアとなっている。発電所規模も100万kWが最高である。(日本で大きな水力発電所は揖斐川水系の奥美濃発電所で、1994年に運転が開始され6台の発電機が150万kWの発電を行っている。二番目は、信濃川水系の新高瀬川発電所であり、4基の発電機で128万kWの発電を行っている。)
- 私は愛知県の山あいで生まれた関係上、水力発電には深い思い入れがある。足助香嵐渓には山の頂上から大きなパイプが川に導かれていて水力発電(巴川、足助発電所、1,000kW)を行っていた。旭町の笹戸地区(矢作川、笹戸発電所、9,400kW)にも水力発電所があった。牛地地区には100m級のアーチ式ダムが作られ、地下には大型発電設備(奥矢作第二発電所、780,000kW、奥矢作第一発電所、315,000kW)が設けられていた。佐久間ダムも近くにあった。私の親父は矢作川上流の牛地地区で生まれ育った。その生家はダム建設で水没した。私が育った家の近くには佐久間ダムから名古屋地区へ送られると思われる高圧送電線(鉄塔)が通っていた。雨の日その近くを通るとジィージィーと音を立てていた。ダムと送電線、山あい地区の一風景である。
-
-
- 【火力発電】
- 石油発電は1,391億kWhの16%から1,053億kWh(10%)と減ずる方向にある。1981年の石油発電は、42%で2,094億kWhを発生していた。石油にかわる燃料として、石炭20%(2147億kWh)、LNG23%(2468億kWh)が注目されている。
- エアコンや冷蔵庫、ドライヤーやテレビ、コピーマシンなどの普及に伴って、生活が豊かになればなるほどエネルギー消費量が増える。電気エネルギーは深刻な曲面を迎えている。なにせ電気はエネルギーを蓄えることがおそろしく苦手だ。パワープラント(発電所)では、ピークの消費電力に合わせて発電所を作らなくてはならない。夏場など、朝10時頃から3時までの電力ピークを睨みながら、発電所関係の人たちはなんとかこのピークを乗り切ろうと躍起になる。パーソナルユースでの冷房が普及し、個人が200V15A(3kW)の電気を使うのだからたまったものではない。日本人1億人の1/4がこの冷房にスイッチを入れたら、
- 2,500万人 x 3kW = 7,500万kW
- 7,500万kWの電気を供給しなくてはならない。この数字は、100万kWクラスの発電所が75基必要な事を示している。夏場には、日本の原子力発電設備のほとんどがこの日本人の涼のサービスをするために稼働することになる。
-
-
- 【ゴミ発電】(1998.10)
- 生活が豊かになると、色々なものを消費するようになる。経済が進んでくると自営生活が廃り、貨幣を仲立ちとして物を購入する生活になる。自然、消費の後には排泄物が発生する。それがゴミである。紙、ポリエチレン、鉄、アルミ、木材、コンクリート、など。従来は、こうしたゴミは海に計画的に投棄して土と混ぜ埋め立てていた。生ものでも土と混ぜバクテリアの働きで自然に帰す方式だった。
- 近年、埋め立てる海がなくなってきて、ゴミを燃やすようになってきた。それも各自治体が焼却炉を設備してこまめに焼却し、熱エネルギーを他用途に還元する方針を取っている。ゴミ焼却はダイオキシン、CO2、NOx発生などの問題を抱えているが熱エネルギーを得ることができ、発電することもできるようになっている。
-
-
- 【風力発電・地熱発電・波発電】(2001.02)
- 化石燃料や原子力に頼らずに、自然のエネルギーを電気に代える試みが地道に続けられている。化石燃料は有限であり大気に炭酸ガスが放出されるという問題を抱える。原子力の喧しい(かまびすしい)是非は先刻ご承知の通り。自然に優しい電力ということで風の力を利用してプロペラを回しプロペラにとりつけた発電機で電気を起こすのが風力発電。温泉などに見られる温水、地熱を利用して発電機を回す地熱発電、波の高低で空気をタービンに送り発電機を回す波発電機などが建設されている。これらの問題は建設費もさることながら安定した供給ができるかどうかである。これらの発電は、大電力を確保するのも難しい。ドイツでは、風力発電に熱心であると聞く。これらの発電は、地域ごとの管理で運営してある程度の電力をアシストする設備という位置づけが正しいように思う。
-
-
- 【自家発電・太陽電池】(2001.02)
- 絶対に停電しては困る事業所や設備では、自らが発電設備を持つことがある。発電設備の規模はそれぞれであるが発電機を回すのにディーゼルエンジンを用いたり、ジェットエンジンを用いたり、ガスを用いたりと様々である。最近流行になっているコジェネレーション設備というのは、暖房設備と発電設備を併せ持った設備で地域用設備として注目され始めている。その熱源は天然ガスであったり、石油であったり、メタノールであったり様々であるが、効率の良いエネルギーを活用できるという特徴を持っている。
- 太陽電池の躍進が著しい。人工衛星は大きな羽根を広げて太陽電池で衛星内の電力をまかなっている。太陽の光エネルギーを電気に代えるにはシリコンを使う。シリコンは光エネルギーを電子に代える20世紀が生み出した大発明である。ビデオカメラに使われているCCDと呼ばれる電子の目もシリコン基板に光が当たりこれを電子に代えて電気信号を取り出している。シリコンを使った太陽電池を用いて電気を起こすのが太陽発電である。
- 2001.02.09の朝日新聞によれば、太陽電池の年間生産で日本は連続世界一になったと伝えていた。2000年の国別の太陽電池生産で日本が生産量で一位になり、企業別でも一位がSHARPで前年の3位から1位になり、54,000kWを生産した。2位は京セラで42,000kW、3位が前年トップであったBPソーラー、6位に三洋電機が入っている。日本全体の生産量は、前年比46%増の116,700kW(家庭用システム換算で約29,000軒分)で、二位の米国の78,500kWを大きく引き離しているという。新聞の情報から換算すると1軒あたり4kWの出力をまかなっており、この値は注目できる数値である。我が家の契約電気料が100V、40Aであるからちょうど4kWなのである。つまり太陽電池で一家の電気がまかなえるまでに性能が進んできたことを示しているのである。もっとも太陽電池は太陽が沈めば発電しなくなるわけであるが昼間や夏の暑い日には威力を発揮しそうな気がした。こうした太陽電池の躍進は1994年から始まった国の補助金制度によって、一般家庭に設置する場合に費用の1/3相当が補助されるのが大きく効いているという。
-
-
- 【朝シャンの罪】
- 「朝シャン」の文化が日本に根づいて久しい。12才から30才のうら若き女性が朝の6時から8時の間に髪を洗い、一斉にドライヤーを使用する。ドライヤーは1kW。東京に住むうら若き女性は90万人、この内の30%が「朝シャン」をしドライヤを20分使用するとすると、
- 1kW x 900,000 x 0.3 = 270,000 kW
- 270,000 kw x 1/3 h = 90 kWJ
- 27万kWの電気を必要とする。金額にして約200万円。この発電能力は、原子力発電所1/3基分の発電容量となる。もっとも27万人が一斉に使用するわけではなく2時間の間に20分間ずつ使うわけだから瞬間には50,000人から100,000人の使用ということになる。それにしたところが、「朝シャン」のために10万kWの電気を確保しなければならない。この文化が真夏の2時頃だったら日本の電源はパンクしてしまうだろう。民宿の主人が若い女性を宿泊させると、「朝シャン」の時に電気ブレーカが飛ぶのではないかとヒヤヒヤすると言っていたことを想い出す。
-
- 我が家でも風呂から上がってドライヤーを手にするとき家族の者は細心の注意を払ってスイッチをONにする。同じ電気系統で電子レンジを使っていないか、電気乾燥機は使っていないか、エアコンはフル稼働でないか、ホットカーペットは使っていないか、などである。電源ブレーカが飛べば、コンピュータのメモリが消え、電気製品の時計を再度セットしなければならなくなる。私は、自慢ではないが、ドライヤーを使ったことが無い。必要ないと言えばそれまでであるが、髪がフサフサしていた若い頃から必要としなかった。ドライヤーももう少し低消費電力で家庭に優しい製品になれば良いのにと思う。
-
- 【水素燃料電池】 (2001.07.09)(2015.07.27追記)
- 環境がとやかく言われて久しくなっている。人がエネルギーを使えば副次的に排出物を伴う。
- エネルギーは、熱を伴うから必ずと言っていいほど二酸化炭素が排出される。
- 火力発電は燃料に石油や天然ガスを使ってそれらを燃やし、水を沸騰させその水蒸気を使って発電機のタービンを回す。
- 燃やされた燃料による炭酸ガスの放出は並大抵の量ではない。
- 水力発電は、水の位置エネルギーを利用して(水の高低差)発電機を回すので炭酸ガスは排出されないものの、河川の自然水系に与える影響は大きいと言われている。
- 原子力発電も炭酸ガス抑制の効果がある反面、安全上の問題が世界的に論議されヨーロッパ諸国では暫時廃止の方向にある。
- これらの発電施設から排出される二酸化炭素にもまして交通手段それも化石燃料を使ったエンジンから排出される二酸化炭素は、世界の人々が豊になっていけば指数関数的に増えていくことが容易に想像される。
- 排ガスの一部からはNOxが排出され、これが大気中の酸素と結合(酸化)して硝酸になる。
- また燃料中に含まれるイオウ成分によって排ガスが大気中に放出されると、酸素と反応して硫酸が生成され酸性雨となる。
- 水素燃料電池は、車の環境問題から浮上し、石油を使った内燃機関(ガソリン、ディーゼルエンジン)に代わる未来の自動車エネルギーと言われている。
- そのエネルギー効率は50%と言われ、夢のようなエネルギー変換効率を持つ輸送機関である。
- 水素燃料の骨子は、電気バッテリーである。
- 電気バッテリーによって電気モータを回しクルマを走らせる。エネルギー源は水素である。
-
- 水素反応の化学式は、
- 2H2 → 4H + 4e-
- 4H+ 4e- + O2→ 2H2O(水) + (2 x 286)kJ
-
- で表される。水素は反応しやすい元素でたくさんの化合物を作る。酸素とも化合し水を作る。水素は適当な触媒を介して上の式に示すような水素イオンと電子に分離される。不安定になった水素イオンは他の元素と結びつきやすくなり、近くに酸素があればそれと結合して水となる。水の電気分解の逆作用である。
- 水素と酸素の化学反応では反応エネルギーが発生し、液体の水では1モル当たり286kJのエネルギーとなる。これがすべて電気エネルギーに変われば100%の効率となり、100%が熱になれば電気効率は0となる。激しい水素燃焼ではこれだけの熱量が発生する。
- 水素燃料電池では、どれだけの効率で電気を発生させているか明確ではないけれど、通常40%と言われているので60%が熱となる。
- 水素燃料電池車MIRAIは87,000リットル(常圧)の水素がタンクに入っているので、
- 87000/22.4 = 3884mol
- の水素がタンクの中に充填されていることになり、
- 286 kJ x 0.4 x 3884 = 444MJ
- の潜在電気エネルギーを持持つことになる。
- 一方、ガソリンエンジンの燃料タンク60リットルを考えると、ガソリンの熱量は、34.5MJ/リットル x 60リットル = 2070 MJである。機械効率を16%としガソリンの発熱量の16%が動力エネルギーに変わるとすると、ガソリン60リットルは331MJの仕事をすることになる。(燃費の良い車とそうでない車により機械効率は変わる。)
- MIRAIの水素燃料電池から効率82%の電気モータで動力を出すとすると、444MJ x 0.82 = 364 MJとなるので、MIRAIの水素燃料は60リットルの燃料タンクと同程度となる。
-
- 一方、水素を自動車の燃料として使う試みは古くからあり、水素自体を内燃機関に送り込んでその燃焼エネルギーでクルマを動かすエンジンが提案され開発が続けられているが、水素燃料電池とは構造が異なっている。
- 水素燃料電池は水素の化学反応で電気を起こすため燃料として水素をクルマに載せて長距離を走らせなければならない。
- その実用化には未だ解決する問題が残っておりいろいろな論議が取り沙汰されることになろう。
-
- 水素燃料電池車の実用化への一番の問題点は価格。
- 市販のクルマの2、3倍の値段を余儀なくされる。
- 高価格な次世代のクルマが一般大衆車として普及をして行くには障害が多い。
- それとインフラ整備。エネルギーを不自由なく利用できるガスステーションの整備をしなければ普及は望めない。
- しかしいろいろな問題があったとしても、環境を考えた現在、水素燃料電池は時代を託す技術であると思われる。
-
-
- ■水素燃料電池の歴史:
- (水素)燃料電池は、1839年に英国の物理学者ウィリアム・グローブが2枚の白金電極にそれぞれ水素と酸素を送ると発電作用があることを発見したのに始まる。歴史的は随分早い時代に燃料電池が発明されたことになる。
- 燃料電池を簡単に説明すると、負極に水素を送り込みこれを燃料とし、酸素は正極に送り込み酸化剤とさせる。電池と言うよりも必要に応じて化学反応させて電気を取り出す電器という方が正しいかもしれない。
- しかし、このアイデアは水素を使うという理由から一般的にはならなかった。水素を使うには危険が多かった。それに、ややもすると爆発的に反応する両者の反応をいかに抑制を利かせて行うか、耐久性のある触媒をどうするか、など解決すべき問題が当時の技術レベルではたくさんあり過ぎたのである。
-
 ▼宇宙開発と水素燃料電池
▼宇宙開発と水素燃料電池- 燃料電池を実用化(といってもプロジェクトに使用しただけ)したのは、1960年代のアメリカの宇宙計画ジェミニとアポロである。有人宇宙船は、大量の電気と水を必要としたので、ロケット燃料の水素と酸素を使って電気と水が作れるこの方式が注目され、発電装置が作られた。
- 1965年、ジェミニ5号で使われた燃料電池は、ポリスチレン系樹脂をもとにしたプラスチックイオン交換膜を使用して、水素をイオンと電子に分離した。アポロ計画とスペースシャトル計画ではイオン交換樹脂に代えて電解液に水酸化カリウム水溶液が使われた。このほか電解質にリン酸や炭酸塩、固体アイオニクスを用いたものも開発され発電設備として実験機が作られた。
-
- 1984年、東京電力五井火力発電所では出力4,500kWの発電に成功した。この発電設備は、米国のユナイテッド・テクノロジー社の手によりリン酸型の電解質を用いられ、燃料はメタン・ナフサ・メタノールを水蒸気で改質して反応室に送り込んだ。
- 動作温度は177度である。ナトリウムやリチウムなどの炭酸塩の方式は温度が630-670度になるという。これが固体アイオニクスを使うと1,000度の高温になる。
-
- ▼ 自動車燃料としての水素燃料電池
- 燃料電池は開発費がかさむため、その後は表舞台から遠ざかっていた。しかし1990年代に入って、カナダのバラードパワーシステムズ(Ballard Power Systems、カナダ・バーナビー市)社が高性能の電池を開発した。これをドイツのダイムラーベンツ(現ダイムラークライスラー)が目をつけたのをきっかけに、車の動力源として一躍注目を集めるようになった。(バラード社は2007年燃料電池開発から撤退し、事業部門をダイムラー社とフォード社に売却した。)
-
- ■水素燃料電池の構造
- 水素燃料電池自動車は、普通のガソリン車のようにエンジン内で燃料を爆発的に燃やすことはない。ジワリジワリとした化学反応で電気を作り出す。また予めバッテリーを積んだ電気自動車とも趣を異にする。
- 水素燃料電池自動車は、燃料を積んで必要に応じて電気を作り出し、その電気で電動モータを回しクルマを動かす。電気をどのように作るかというと、水素と酸素を常温で静かに化学反応させて作る。水素と酸素を混ぜて火をつけると爆発する。このような化学反応はさせない。特殊な反応膜に通して化学変化を起こさせ水を生成して電気を取り出す。燃料電池自動車は、自ら発電する電気自動車といえる。
- 電池の構造は簡単で、陽子は通すが電子は通さない特殊な膜を電極ではさみ、一方に水素を送り込む。膜には触媒が張ってあり、水素は電子と陽子に分かれる。膜を通った陽子は反対側の電極で、電線を迂回してきた電子と再び結合。これを、大気中から取り込んだ酸素と反応させて水にする。こうすると、電子がひっきりなしに流れるようになり、電気が流れる。電気は必要な分だけ必要に応じて作られるので、電気自動車のように走る前にあらかじめ充電しておく必要はない。
-
- 水素燃料電池の基本構造は、水素を特殊な薄膜(触媒と陽子を透過させる膜)に通してイオン化させて分離させ、イオン化した水素を酸素と結合させて水にする。分離した電子は電気として取り出す。
-
- ■水素燃料電池車の市販化
- 開発で先行していたダイムラー・クライスラーが、いち早く2004年に燃料電池の乗用車を市販すると宣言したことをきっかけに、主要メーカーがそろって2003年か4年の発売を目標、として設定した。ダイムラーはバラードと提携し、1994年に最初の試作車を出して以来、計四つの試作車を作った。1997年にはバラード社(Ballard Power Systems、カナダ)に出資し、翌年同じようにバラードに出資したフォードとともに業界を一歩リードする。もう一社、開発への着手が早かったのはトヨタ。1997年までに2種類の試作車を発表。1999年春には世界最大の自動車メーカー、ゼネラル・モーターズ(GM)と共同研究することで合意した。(国内ではこのほか、三菱自動車が独自に電池自体から開発を進めている→現在はダイムラー・クライスラーの傘下に入ったためベンツとの共同歩調と思われる。日産自動車や本田技研工業はバラードと供給契約を結び、とりあえず電池本体はバラード製を使う計画。)(バラード社は2007年、一般自動車向けの水素燃料電池の開発から撤退した。)
-
- 一方、コストの高さから、開発競争に冷めた見方をするメーカーもある。仏プジョーの開発責任者は「燃料電池が普及するのは価格より環境を重視するドイツや日本、米カリフォルニア州くらいだろう」という。ドイツの高級車メーカーBMWの担当役員は製造コストが高いことを理由に、「動力源としては水素を直接エンジンで燃焼させる水素自動車が本命だ」と話す。
-
- ■実用化への課題
- 燃料電池自動車の実用化への課題は「製造コストがとても高くつくこと」である。現時点での車一台分の電池の値段が、300万とも500万ともいわれる。実験バスはすでに米シカゴやカナダのバンクーバーで走っているが、市販の乗用車が登場するには、電池の価格を十分の一程度に下げる必要があるとされる。
- トヨタ自動車の関係者によると、電池の膜や電極をもっと安く作る技術や、触媒として使う白金の使用量を減らす技術開発が必要だという。
-
- もう一つの課題は、かさばる水素をどうやって大量に車に積むかである。米フォードモーターの試作車P2000は、後部座席の裏とトランクに大きな圧縮タンクを二つ積む。この試作車のトランクには荷物はほとんど入らない。おまけに、一回の燃料補給で走行できる距離は、普通のガソリン車の三分の一の160kmしか走れない。
- このため、圧縮水素に代えて重さ当りの水素の量を多く含む天然ガスや液体のメタノールを車に積む方法も考えられている。「原料」そのものを積み込んで、車の中で水素を取り出し、電池に供給する方式である。この方法を採ったダイムラーのネカー3は38リットルのメタノールで400km走る。ただ、水素の貯蔵方法が改善されていけば、装置が複雑なメタノール型にこだわる必要はなくなる。各メーカーとも方式を絞りきっていないが、いずれの場合も実用化になればガソリンスタンドに代わる供給設備の整備が必要で、これには巨額の資金がかかる。
- (参考資料:『水素燃料電池』 - 朝日新聞1999年11月27日 4面)
-
-
- ■トヨタの水素燃料電池自動車への取り組み
- トヨタが電気自動車のプロジェクトを起こしたのは1991年である。翌1992年には、鉛蓄電池搭載の電気自動車タウンエースを売り出した。燃料電池は、1990年に東冨士研究所で開発が始まり、1992年に本格化した。燃料電池自動車開発のプロジェクトリーダは木村良雄氏*だった。
-
- 世界的に見てみると、燃料電池はそれまでカナダやイタリアが取り組んでいたが成功していなかった。GMは燃料電池に30年間取り組んでいるが未だ成果が出ていなかった。燃料電池の原理は燃料である水素と酸素をある触媒に送り込んで水の電気分解の逆の反応を起こさせる。この反応によって電気が生じ、排気ガスは水蒸気だけになる。
-
- 水素燃料電池開発にあたって、トヨタは電極にカーボンを焼き固めたものを使用した。これはうまく成功した。開発期間は1年半で完成した。この電池の出力は5kWで、電池重量は200kgだった。
- 開発当時の課題は、設計的に無理をした炭素電極の部分の亀裂割れやシール部分のガス漏れだった。また、連続定格5kWの発電量でクルマに搭載すると、発進時の急加速時の負荷要求が高くてパワー不足が露呈した。50-60km/hで走ることは走るがビンビンには走らない。ブレーキは「回生ブレーキ」といって、ブレーキ時にモータが発電機になり電力を回収できる。都内で走行すると20%のエネルギーが回収できる。このエネルギー回収のために通常のバッテリーも搭載している。
-
- 1996年に搭載したRAV4で燃料電池の小型化を図った。小型化の決め手は、電極に使用する高分子の膜。この膜の「ハム」をカーボンの布に触媒をつけた2つの「パン」が挟むサンドイッチ構造とした。このハムは程々に濡れていないと絶縁体になってしまい電気エネルギーが取り出せない。また、濡れすぎても化学反応が起こらず電気が取り出せない。この濡れには水素と酸素の反応でできた水を使った。ハムを濡らすのに極細のチューブのような中空糸を使用した。水に浸した中空糸に空気を通すと、水蒸気が適当に浸透して空気の湿度が上がり、膜の濡れをコントロールする。
-
- 今後の問題は、水素の供給。クルマの中で水素を作る方法(メタノールを使用する方法)も考えている。
- (参考資料:燃料電池開発 トヨタ自動車 木村良雄氏第四開発センターEHV技術部主査
- - メタルカラーの時代[週刊ポスト3.13日号1998年小学館])
- *木村良雄氏:1945年群馬県生まれ。東京大学院工学系研究科博士課程修了。
- トヨタ自動車工業(株)(現:トヨタ自動車(株))入社。排ガス技術対策、
- モータースポーツなどの企画担当を経て、1982年より電気自動車の研究開発に取り組む。
- 1992年よりFCEV(燃料電池電気自動車)の開発責任者としてプロジェクトを指揮。
-
- 化石燃料に代わる自動車エンジンの試みは昔から行われてきた。アルコールで走る自動車。天然ガスで走る自動車。熱効率の良いガスタービンエンジン(冷却を必要としないセラミクスガスタービン)の自動車。太陽電池で走るソラーカー、などなど。上のトヨタの開発した燃料電池によるモータは5kWとある。馬力換算でいくと6.8馬力である。ガソリンエンジンでいうと250ccクラスである。
-
 ■ MIRAI トヨタ水素燃料電池車 発売 (2015.07.22記)
■ MIRAI トヨタ水素燃料電池車 発売 (2015.07.22記)- 2014年12月、トヨタから水素燃料電池車MIRAIが発売された。
- 待ちに待った次世代自動車の登場である。
- 水素を燃料とし大気中の酸素との化学反応で電気を発生させてモータ(動力)に送る。
- 1840年代に着想された水素燃料電池が170年の時を経て形になった。
- 実用化までの道のりは平坦では無く、他社に先駆けてトヨタが市販化した。
- インフラの問題や、安全性の問題、燃料電池のコストなど懸念材料は事欠かないけれど、それでもとにかく形になって販売までこぎ着けた。
- 販売価格は7,250,000円。
- 動力性能も良いと言われ最高時速175km/hで走る。重量物のレイアウトがフロア下部に配置されているため、旋回性能も良好らしい。
- 受注も好調(2015年の販売台数は700台)で、初年度の目標販売を早々にクリアしてしまった。
- MIRAIは大型セダンのサイズに属し重量が1900kgある。
- エンジンに相当するのは、水素燃料電池(= FC stack)と電動機(モータ)である。
- 高圧水素タンクに貯蔵されている水素と外気の酸素の化学変化で電気を取り出すスタックは固体高分子型FCスタックと呼ばれ、114kW(155馬力)の発電能力がある。
 スタック(stack)とは積層されたという意味で、薄いフィルム状の化学変化膜(セル)が何百層も重ね合わさっている。
スタック(stack)とは積層されたという意味で、薄いフィルム状の化学変化膜(セル)が何百層も重ね合わさっている。- セル1枚では1V程度の電圧しか発生できない。
- ヴォルタの電たいと考え方は同じである。
- FCで発生した電気はバッテリと駆動モータに配分される。
- 駆動モータは113kW(154馬力)の交流同期モータで走らせる。
- 燃料は、700気圧の高圧タンクに水素を充填して650kmの走行距離を得る。
- 水素ステーションでの燃料の充填は約3分。
- 水素タンクは700気圧の高圧タンクだ。
- この圧力は相当の高圧であり、安全性が強く懸念される要素である。
- プロパンガスの容器の耐圧が30気圧。
- それよりもはるかに圧力の高い水素が61リットル容器2つに充填される。
- 700気圧で充填されるから、常圧での水素は87kリットルということになる。
- このときの水素の総重量は約7.8kg。
ガソリン10リットル程度の重さである。
-
-
- 1-3-1a. 電池について (2001.09.020)(2010.01.18追記)
(2015.07.18)
- 上記で燃料電池について触れた。
- また先の章で、たびたびヴォルタ(ボルタ)の電堆(でんたい)について触れた。
- 電気科学は、ボルタによって発明された電池がなければこれほどまでの発展を見なかったに違いない。
- 発電機が無い時代、電気を得る唯一の電源がボルタの電堆であった 。
- (摩擦で電気を貯めるライデン瓶と起電機はあったが持続的なものではなかった。)
- ヴォルタの電池の登場によって、イギリスの化学者ディビーもその弟子マイケル・ファラディーもその電源を使って次々に新しい電気化学の分野を開拓していくことができた。
【参考文献】
- ・『電池の科学』-生物電流から太陽電池まで-、ブルーバックスB-678、橋本尚 著、昭和62年2月20日第1刷、講談社
- ・『図解 電池のはなし』 池田宏之助、武島源二、梅尾良之、1996年12月20日初版、日本実業出版社
- ・『新しい電池の科学』 梅尾良之、ブルーバックス B-1530、2006年9月20日初版、講談社
-
- ▼ 生活の中の電池
- 今日の我々の身の回りには、たくさんの種類の電池が出回っている。
- 電池の小型高性能化の恩恵を受けて、身のまわりの電子機器製品、例えば、携帯電話やノートブックコンピュータ、電動ドリル、自動車、ビデオカメラ、ウォークマンなどが大いなる活況を呈している。
-
- 過日(1998年)、ニッケル水素バッテリを内蔵した電気ドリルを使った。
- ドリルの力強い回転に感嘆した。
- 1980年代より大工屋さんや電気工事屋さんは、バッテリ式の電動工具をたくさん使っている。
- それだけ安定性が良く使い勝手が良いのだと思う。
- ACコードを引っ張りながらの現場作業は作業性が悪い。
- それに悪い姿勢でボルトを閉めるには力が入らない場合が多い。
- 何回もドライバーを回すのは疲れる。
- だからバッテリ内蔵のドリルはドライバーは作業性が格段に良い。(バッテリ分だけ重いけれど。)
- バッテリの保ちはたしかに問題だけれど1回の充電で半日保てば作業性が良いと言うことなのだろうと合点した。
- ニッケル・水素バッテリは、強力な電気を取り出せるんだ!とあらためて思い知らされた。
-
- 世界初のハイブリッドカー「プリウス」のバッテリーにも、ニッケル・水素バッテリが使われている。
- 2009年発売の三代目プリウスまではニッケル・水素バッテリである。
- 2015年11月に発売される四代目プリウスはリチウム・イオンバッテリだと言われている。
- 三代目ではプリウスα7人乗りがリチウムイオンバッテリを採用している。
- ここ数年、携帯電話の普及に伴って、バッテリの性能がグンと上がったような感じを受ける。携帯電話は、超小型になり、電話の機能をバックアップする電池も薄くなった。
- 薄くなって、小さくなったにも関わらず、長時間の使用が可能になった。
-
- 携帯電話のバッテリーには、リチウムイオンバッテリーが使われている。
- リチウムバッテリの持続時間は、一般的な使い方で1週間程度は持つ。(スマートフォンは一日程度)
- ボタン電池と呼ばれる丸くて薄い電池も小型機器に使われている。
- ボタン電池は、腕時計やカメラ、電卓、アクセサリー小物などに入っている。
- これらは昔、酸化銀電池、水銀電池などが使われていた。
- 聞くからに高そうな電池である。
- 今は、アルカリボタン電池、リチウム電池などに置き換わっている。
- 1980年代は、ニッカド電池(これは三洋電機の登録商標の名前らしい、正式にはニッケル・カドミウム蓄電池)が興隆を極め、ビデオ装置やひげ剃り(シェーバー)、懐中電灯に使われていた。
-
- こうした多種多様な電池は、どのようにして作られてきたのだろうか?
- あまりに種類が多いので、わけがわからなくなっている、というのが正直なところである。
- 私の小学校時代(1960年代)の電池といえば、単一(直径34.2mm、高さ61.5mm)サイズのマンガン乾電池が一般的であった。
- 単三乾電池は、1970年代前半頃からラジオやおもちゃ、トランシーバー、家庭電化製品に普及した感じを受ける。
- アルカリ乾電池が開発されて、小さくてもパワーが取り出せるようになり、より小さな乾電池サイズ(単四、単五)のものが出回るようになった。
-
- 1979年7月1日に発売されたウォークマンTPS-L2(Sonyの登録商標)は、単三乾電池2本で動いた。
- 3Vの電圧でカセットテープが回り、質の良い音がそれもすごい音量でイアホンから流れた。
- 私は、その初モデルを秋葉原で\31,000(定価は\33,000)で購入した。
- ウォークマンから流れる音を聞いたとき、その音質の良さと3V電圧の力、装置の携帯性に驚嘆した。
- 以後、ウォークマンを4回代えて現在に至っている。
- 記録メディアもフィリップスオーディオテープからMDに代わり、電池もガム型のニッケル水素電池になった。
-
- しかし、2001年に発売されたアップル社のiPodの登場により、時代は半導体メモリ(もしくは小型ハードディスク)を使った携帯オーディオ機器に移行していくことになる。バッテリも内蔵のLi-ion(リチウムイオン)になった。
- 2015年7月の時点で、iPod touchの半導体メモリは128GBである。
- 1曲3MB容量として42,000曲を保存できる。内蔵バッテリは連続使用で40時間可能である。
-
-
- ▼ 1960年代の乾電池
 私が最初に記憶に留めた乾電池は、家庭にあった懐中電灯が主な活躍場所であった。
1960年代である。
鉄の薄板をメッキ処理した懐中電灯の筒の中に単一乾電池を直列に2本落とし込み、お尻の部分からバネのついた締めキャップを回して締めた。
私が最初に記憶に留めた乾電池は、家庭にあった懐中電灯が主な活躍場所であった。
1960年代である。
鉄の薄板をメッキ処理した懐中電灯の筒の中に単一乾電池を直列に2本落とし込み、お尻の部分からバネのついた締めキャップを回して締めた。
- 乾電池は、当時マンガン電池しかなかった。
- 単二や単三電池は1960年代前半はあまり普及しておらず、60年代後半から携帯ラジオやオモチャなどに登場するようになったと記憶する。
- ボタン電池は私が大学時代頃からなので1970年代後半頃からと思う。
- ボタン電池は補聴器などには使われていたと思うけれど、私の周りに補聴器を持っている老人はいなかった。
- 小型電池が普及するのは乾電池の性能が大きく向上したからと記憶する。
- 性能の悪い乾電池の小さいものはすぐ電池が無くなってしまう。これでは使い物にならない。
-
 単一、単二などの「単」は単層のからきた言葉であろう。
単一、単二などの「単」は単層のからきた言葉であろう。- 電極が1対で化学反応層が1層という意味である。
- ヴォルタの電たいのように電池は複数を直列につなげて積層するのが一般的だったのかもしれない。
- 今も販売している「006P」という四角い乾電池は9Vの電圧を持っている。
- 6P = 6pilesで6層、1.5V x 6層 = 9Vなのだと理解している。
- これは電圧は高いけれど小さいので容量が少なく大電流が取り出せない。
-
- 話を戻して単一乾電池。
- ナショナル(現:パナソニック)は、密封式の単一乾電池「ナショナルハイパー」を1954年(昭和29年)に発売した。
- 上左の写真にある「ハイトップ」は 1963年 (昭和38年)に発売された。
- 私自身一番馴染みの深かった乾電池である。
-
- 1960年代の家庭の電池は、この他に積層電池(空気電池)というのがあって電話機に使われていた。
- 積層乾電池は、紙製の小ぶりな箱で電話機の近くに置かれていた。
- この電池は数十Vの起電力があった。
- 当時の電話回線の電源が貧弱で、特に我が家は山合いの集落で電話を持っている家はほとんどなかった。
- 電話交換局との距離が遠かったのでその補助の装置だったのだろうとのちのちに合点した。
- 1960年代前半の話である。
- 当時の黒い電話機は、AC電源を接続していない。
- だから家庭に配電される電気が停電になっても正常に機能していた愉快な家庭製品でもあったが、それくらい当時は停電がしばしばあった。
- しかし、この空気電池は一般家庭で他の目的に利用するものではなかった。
-
- またこの他にも、クルマに乗っている鉛蓄電池が一般的になっていたが、この電池も我々が多目的に使うという代物ではなかった。
- 当時としては高価であったし充電装置も高価であった。
- それに電解液に硫酸が使われていて大電流が流れるから一般の人が手軽に使うというわけにはいかなかった。
-


-
- 日常生活で懐中電灯の単一マンガン電池を交換することはしばしばあった。
- 新しく入れた当初は気持ちよく明るい光を発して闇を照らしたが、使わずにそのままにしておくとすぐ出力が低下してしまい、いざ使おうとすると弱々しい光を発してしばらくすると今にも消え入りそうな光となった。
- 当時のマンガン乾電池は、電池からの液漏れも頻繁にあった。
- 懐中電灯の電池を収納する筒の内部は、電池の液漏れで独特の酸の匂いがして配線電極が容易に腐食した。
- たいていの家庭は、懐中電灯に入っている乾電池のケアなどしない。
- 入れっぱなしが普通である。
- その入れっぱなし状態で、乾電池は自己放電し液漏れを起こし、いざというときにまったく使いものにならなかった。
- これが、私の幼心の乾電池に対する印象であった。
- 1960年当時、家庭に届く電気はちょくちょく停電した。
- 半年に1度くらいは停電していたような気がする。
- 夏の夜など雷があると電気が途絶えた。
- そうなると懐中電灯の登場であるが、往々にして乾電池が放電してしまっていて青色吐息の光を放った。
- そんなとき、祖父はため息をつきながら懐中電灯を諦めろうそくを取り出していたことを思い出す。
-
- 1960年後半、三洋電機から手のひらに入るような小さな充電式(ニッカド電池式)懐中電灯が発売された。
- 光量は絶対的に足りなかったが、輝度が高く結構明るかった記憶がある。
- 電池を入れなくても充電するだけで明るい光を出す充電式の新しい電池に強烈な印象を覚えた。
-
- ワクワクするおもちゃにも、単二、単三の電池を必要とした。
- しかしこうした電池はすぐ消耗しておもちゃに遊び興じる刺激を萎ませた。
- 子供のお小遣いではふんだんに乾電池は買えなかった。
- 100Vの交流電源から3Vの直流電源がとれる電源装置がとても欲しかった。
- 当時高価だったが充電式のニッカド電池がほしかった。
- 当時ニッカド電池は単三型しかなくて単一、単二型はなかった。
-
- そんな電池に対する思い出とともに、現代の電池を見ると隔世の感を持つ。
- スマートに電池が社会の一翼を担っている。
- コンピュータをはじめいろいろな製品の中にさりげなく入り込んで快適な社会生活の脇役を演じている。
-
- これまで開発された様々な電池を体系づけたのが下の模式図である。
- これは、斉藤春男氏が「新しい電池の話」(日本放送協会、1972年)に載せられているものを参考にして書き直した。
- 氏のチャートは実に良くまとめられている。
- この体系図をもとに、電池の歴史とその役割についてボチボチと話を進めていこうと思う。
-

-
-
- 電池は、私たちの身のまわりにあらゆる所でお目にかかる。
- マンガン乾電池に水銀が使われていて、廃棄に問題が生じた時期があった。
-
- ■ 一次乾電池(使い捨て乾電池)になぜ水銀が使われていたのか?
- ■ アルカリ電池がマンガン電池より保ちが良いというのは何故か?
- ■ 酸化銀電池と呼ばれる見るからに高そうな電池はどんな特徴があるのか?
- ■ リチウムと呼ばれる反応の強そうな金属を使った電池は最近使われているがかなり強い電気が流せるのか
- ■ バッテリ(二次電池)は何が一番良いのか?
-
- などなど素朴な疑問は尽きない。 そうした電池についての基本的な事から話題を進めていこうと思う。
- 電池も歴史的な流れがあって標準化があって、そして技術革新があったことが上の図からも見て取ることができる。
- 一次電池は使い終わってしまうと捨てなければならず資源の無駄遣いのような気がしてならない。
- アルカリ電池は、名前からして簡単に捨てられないような気がして気が引ける。
- バッテリに使われている硫酸や鉛、カドミウム、リチウムなどは簡単に捨ててはいけない金属であろう。
- 問題山積の中で、それでも我々は電池に埋もれて生活している、というのが偽らざるところではないかと考える。
-
■ ボルタの電池(Voltaic Pile)の歴史的意味とその後

-
-
-
- ▼電池の本質は化学変化(イオンの電解作用)
-
- 電池は化学反応作用で電気を作る。
- 電池の根元はここである。
- 小学校の理科の時間に、水溶液の電気分解という実験を行った。
- 科学が大好きでたまらなかった私は、この実験を強烈な印象として記憶している。
- 水溶液に浸した電極から電気を流すと泡の気体が電極にまとわりついた。
- 電池は、この電気分解の逆なのである。
- イオン化しやすい金属を使ってイオン化した溶液(電解質溶液)に浸すと、金属はその水溶液中に溶けだしイオン化によって遊離した電子が電極を伝って相手方の電極に流れていく。
- これが電池の根本である。
- これをイタリア人の化学者ボルタ(ヴォルタ)が突き止めた。
- この基本原理をもとに化学反応を持続する物質を突き止めれば、反応によって遊離した電子が電子の道(導体)を伝って長時間流れるようになる。
-
-
- ▼電池の基本要素(正極、電解質、セパレータ、負極)
-
- 電池のしくみは、言ってしまえば簡単な事であるが、問題はその化学反応をいかに持続させて強い電流を作り出すかである。
- 電池に応用される化学反応は主にイオン反応を元としている。
- 酸とアルカリの反応である。
- リチウム電池を除き、殆どの電池での反応には水素と酸素が介在する。
-
- 電池には、プラスとマイナスの二つの電極が存在する。
- 電極の間でイオン反応を起こす物質を電池用語で活物質と呼んでいる。
- 負極にあてる活物質は、電解質(通常は溶液)に溶けやすい物質が使われる。
- つまりイオン化しやすい金属が選ばれる。
- 亜鉛、リチウム、鉛、カドミウムがこれにあたる。
- これが電池の第一の本質である。
- 電解質にどんどん進んで解けていく金属(亜鉛、鉛、リチウム、カドミウム)のおかげで(化学エネルギーによって)電気が発生するのである。
- 電解質は、従っていかに気持ちよく負極活物質が溶けてくれるかという環境を整える場でもある。
- 正極には、負極活物質がどんどん電解質中にイオンとして解け出すので電子がたまり導電線を伝ってここに集まる。
- すると溶液中の水素イオン(H+)が引きつけられ負極から流れてきた電子と結合して水素分子ができ水素の気泡ができる。
- これを「分極」と言う。
- 分極が起きると電気はとたんに流れなくなる。
- したがって、正極の活物質には予め酸素を持った酸素合金(二酸化マンガン、酸化銀、酸化水銀、二酸化鉛、オキシ二酸化ニッケル、など)が使われ、電極に集まった水素を酸素を反応させて水にさせてしまう方法が取られている。
- ボルタの電池は銅(正極)と亜鉛(負極)を使用していた。
- この場合、水素イオンは正極(銅板)に集まり水素泡を発生した。
- ボルタの電池の最大の悩みが分極だったのである。
-
- こうしたイオン反応を起こす材料を探して、この反応が長く続き安定した出力が出せる電池の開発が続けられていった。
- 電池の歴史は、この反応の高効率化への戦いであった。
-
- 右図は興味ある図である。
- これは、
-
- 電池の発生する電圧は、使用する電極の種類によって決まる
-
 と言う図である。
と言う図である。- 例えば、ボルタは、亜鉛と銅という二つの金属を用いた。
-
- 亜鉛は硫酸の電解液に対して-0.76Vの電位を持ち、銅は逆に+0.34Vとう電位を持つ。
- この両金属の電位差[+0.34 - (-0.76) = 1.1V]が電池の電圧となるのである。
- ちなみに、金属はイオン化するときに固有の電位を持ち、イオン化しやすい金属ほど電位差が大きい。
- 金や水銀、銀はイオンになりにくいが亜鉛やマグネシウム、ナトリウム、リチウムはイオンになりやすい。
- これらを電圧値で表すと、
-
- 金+1.498V、白金+1.118V、水銀+0.851V、銀+0.800V、銅+0.342V、水素0V
- 鉄(3価)-0.036V、鉛-0.126V、すず-0.138V、ニッケル-0.257V、
- コバルト-0.28V、カドミウム-0.403V、鉄(2価)-0.447V、
- クロム-0.744V、亜鉛-0.762V、マンガン-1.185V、
- アルミニウム-1.662V、マグネシウム-1.55V、ナトリム-2.71V、
- カルシウム-2.93V、カリウム-2.93V、リチウム-3.04V
-
- という値になっている。
- リチウム(-3.04V)が電池の負極材料としていかに有効であるかこの値から知ることができる。
-
- 電池の性能をもう一つ左右する要素にセパレータというのがある。
- 電池の中に入っていて外には出てこないのであまり聞き慣れないものだが、このセパレータによって電池が長続きするのである。
- セパレータを簡単にいってしまうと、「正極」世界と「負極」世界を分離させてイオンだけ通過させる選択透過膜のことである。
- このセパレータがない時代には、電池内部での反応は即座に終わってしまった。
- セパレータの出現により正極と負極を近づけることができるようになり、シート状のセパレータをクルクルと巻物のように巻くことによって小さな容積でも面積を多く取ることができるようになった。
- セパレータは電解質に対して安定していて、電解液をたくさん含む能力を持つものが適している。
-
- セパレータとして最もよく使用されているのは不織布である。
- この他に細かい孔があいた微多孔フィルムが使われる。
- 代表的なセパレータの材質としては、鉛蓄電池では微孔樹脂やガラスマットが使われ、ニッケル・カドミウム蓄電池ではナイロン不織布、ポリプロピレン不織布が使われている。
- リチウム電池では、ポロプロピレン微孔性フィルム、ポリエチレン微孔性フィルムが使われている。
種類 |
名称 |
|
|
活物質 |
電解質 |
特徴 |
使用例 |
正極 |
負極 |
- 一
- 次
- 電
- 池
|
- マンガン
- 乾電池
|
- 筒状
|
1.5 |
- 二酸化
- マンガン
|
- 亜鉛
|
- 塩化亜鉛
|
- 安価
- 乾電池の基本
|
- 懐中電灯、ラジオ、
- 時計
|
- アルカリ
- 乾電池
|
- 筒状
|
1.5 |
↑ |
↑ |
- 水酸化
- カリウム
|
- 強電流
- 連続放電
|
- モータ駆動用
- (ウォークマンなど)
|
- アルカリ
- ボタン電池
|
- ボタン
|
1.5 |
↑ |
↑ |
↑ |
- ↑
- 小型、電圧安定
|
-
カメラ
-
電卓
|
- 酸化銀
- 電池
|
↑ |
1.55 |
|
↑ |
↑ |
↑ |
|
- 水銀
- 電池
|
↑ |
1.35
1.4 |
- 酸化水銀
|
↑ |
↑ |
↑ |
|
- 空気電池
|
↑ |
1.4 |
|
↑ |
↑ |
|
補聴器 |
- リチウム
- 電池
|
- コイン
-
- ↑
- ボタン
- 筒形
|
3
3
1.55
3.6 |
- 二酸化マンガン
- フッ化黒鉛
- 酸化銅
- 塩化チオニル
|
- リチウム
|
- 有機電解液
- ↑
- ↑
- 塩化チオニル
|
- 安定電圧・出力電流小・長期保存可能
|
-
カメラ、電卓
-
時計、メモリバックアップ
-
ICカード
|
- 二次
- 電池・蓄電池
|
- リチウム
- バッテリ
|
|
3〜2 |
|
|
|
|
|
↑ |
2〜1.5 |
|
|
↑ |
↑ |
↑ |
|
|
2.4〜1.3 |
|
|
↑ |
↑ |
↑ |
- 鉛蓄電池
- (
- 鉛酸
- 電池)
|
- 普通
- 密閉
|
2/セル |
|
|
|
|
自動車、など |
- ニッケル
- カドミウム電池
|
- ↑
- ↑
|
1.2/セル |
|
|
|
- 強電流
- 連続放電可能
- 空状態での保存可能
- メモリ効果あり
|
|
- ニッケル
- 水素電池
|
- 円筒
- プレート
|
↑ |
- ニッケル
|
- MN*Ni5*H
- 金属水酸化物
|
- 苛性カリ
- 水溶液
|
- ニッケルカドミウムよりエネルギー密度高
- 電気容量高
- メモリ効果小
|
- ニッケルカドミウム電池
- の代替
- 携帯製品
- ハイブリッドカー
|
参考:『電池の科学』ブルーバックスB-678、橋本尚 著、講談社
【一次電池】 ■ マンガン乾電池とアルカリ乾電池
- 一次電池は、もっとも馴染みの深い一般的な電池である。
- 単一乾電池の太さは、これを発明したフランス人の電気技術師ルクランシェ(Georges Leclanche:1839 - 1882)が1868年に亜鉛板で筒を作る時に、近くにあったスコップの柄に板を巻き付けて筒を作ったためにこの大きさになったと言われている。
- ルクランシェは、2年前の1866年に以下に示すような瓶タイプのマンガン電池を発明している。
- この電池は水溶液であり瓶形状のため使い勝手が悪かった。いわゆる「湿電池」であった。
- そこで電解溶液をのこぎりくずや砂、ゼラチン、小麦粉、デンプンなどのり状にして固定化して使いやすくし「乾電池」とした。
- ルクランシェのマンガン電池は発明後2年間で20,000個もの電池が作られ電信機装置に使われた。
- 通信設備に電池が切望されていた証しである。
-

- ルクランシェが発明した当初の電池は、電極である負極を亜鉛、正極を二酸化マンガンとし、電解液に塩化アンモニウムを用いていた。
- 二酸化マンガンは、溶解度が小さく電解液に溶け出さないためセパレータ無しでも比較的長時間の発電ができた。
-
- 1975年には、このマンガン乾電池の電解質を塩化アンモニウムから塩化亜鉛に変えた。
- 従来の乾電池は大電流を流そうとすると内部抵抗が高いために電池の消耗が激しかった。
- (発電の多くを電池自らの抵抗で消耗してしまった。)
- 電解液を塩化亜鉛に代えたことにより、大電流の耐久時間が2倍以上伸びている。
-
- マンガン電池を作っているメーカーのデータによると、負荷抵抗10Ωで一日4時間の放電を20度の環境でテストした結果、終止電圧1.0Vに達するまで62時間の使用ができるようになった。
- 16日間の使用に耐えたということである。
- 電流も150mA〜100mA程度流せたということである。
- このデータをもとに全体の電気量を計算すると、
- 平均電圧1.25V、電流125mA、時間62時間で、
-
- 1.25V x 0.125A x 62h
- = 9.69 Wh
- = 7.75 Ah
-
- という性能になる。
- Whという単位は、エネルギーと時間(hour)の積で全エネルギー量を表す。
- 全エネルギーにはJ(ジュール)という単位があるがこれはW・s(ワット・セコンド)である。
- Whは、1時間あたりの仕事量であるから、1 Wh=3600Jということになる。
- 1 Whは、1ワットのエネルギーを1時間流せるという感覚的なもので、乾電池の能力を表すのには都合が良い。
- もっとも、この値はだいたいの目安であって厳密ではない。
- 使用する温度や湿度によって能力が変わるし、1A流すのと0.01A流すのでは耐久力も変わってくる。
- ちなみに、単三乾電池は上記の単一乾電池の1/10程度の電気容量になり、単二乾電池は1/3程度の容量である。
-
-
- ▼ アルカリ電池
- アルカリマンガン乾電池は、マンガン乾電池と外観、電圧が同じで電気容量が4〜5倍の性能を持つものである。
- 乾電池自体の内部抵抗が少ないためにマンガン電池より大電流を流すことができる。
- 日本では、1960年代の終わりに製品化された(松下電器[Panasonic]により1967年に発売した)。
- しかし、当時のアルカリ電池は一般のマンガン電池に比べて高かったのでおいそれとは買えなかった。
- アルカリ乾電池が普及を見るのはウォークマンやカメラ用ストロボなど大電流を必要とする電化製品が市場に出るようになり、その有効性が認められるようになった1970年代後半からだと記憶する。
- アルカリ電池は、マンガン乾電池の電解溶液が塩化亜鉛という酸を使用しているのに対して、アルカリを示す水酸化カリウムを使っている。
- これはかなり強いアルカリ溶液で、腐食性も高いため液漏れやそれに伴う人体や装置への傷害を防ぐ必要上、マンガン電池より強固な密封構造を取っている。
- また、アルカリ電池はマンガン電池に比べて大きな電流を取り出すことができるので、電池を短絡させると大電流が流れて電池が発熱し破裂しやすくなる。
- この事故を防ぐために、アルカリ電池はさらに防爆装置をそなえた構造になっている。
- 現在、アルカリ乾電池は価格も安くなり、マンガン電池を総生産数で上回っていると言われている。
-
-
- ▼ なぜマンガン乾電池とアルカリ乾電池に水銀が使われていたか
-
- 最近(1990年代以降)の電池を見ると「水銀0(ゼロ)使用」と明記されている。
- 乾電池の仕組みを述べてきた上記では水銀の説明はなかった。
- しかし、現実には従来のマンガン電池、アルカリ電池に水銀が使われていた。
- 1991年を境に、これらの乾電池に水銀を使うことがなくなった。
- 水銀は、常温で唯一の液体金属である。水銀には、他の金属には見られない特筆すべき特性がある。それが「アマルガム」と呼ばれる性質である。
- アマルガムについては、『光と光の記録 - 水銀、アマルガム』を参照されたい。
- マンガン乾電池・アルカリ乾電池には、亜鉛に水銀を混ぜてアマルガムとして負極に利用していた。
- 水銀を用いた亜鉛アマルガムは、ペースト状の亜鉛となり、負極表面を覆い腐食を防ぐ大切な働きをなしてきた。
- つまり、水銀を使うことにより電池の寿命が格段に延びたのである。
- 乾電池にアマルガムとして使われた水銀は、重量比で亜鉛の10%程度であった。
- それが1985年には3%、1987年に1.5%となり1990年代前半には全廃となっていった。
-
-
-
- ■ 酸化銀電池(Silver Oxide Battery)
-
 名前からして高価そうな電池である。
名前からして高価そうな電池である。- この電池は、安定した電気出力が得られる電池として注目され、1883年に一次電池が発表され、4年後の1887年に二次電池(バッテリー)が発表された。
- 市販化が難しく、売り出されたのは80年後の1961年に米国で口火が切られ、日本では1965年から製造されたと言われている。
- この電池は、正極に酸化銀(酸化第一銀)を用い、負極には亜鉛を使っている。
- 電圧は、1.55Vであった。酸化銀電池の特徴は、
-
- ・電圧が高い(公称電圧1.55V)
- ・出力が平坦で安定している
- ・電池容量が大きい
- ・温度特性が優れている
-
- などが挙げられる。
- この電池は、当時主流であった酸化水銀電池(水銀電池)よりも高性能版という位置づけが強い。
- 酸化水銀電池が環境問題もあって自然と姿を消していったのに対し、酸化銀電池は未だ現役で活躍している。
-
- 私が勤務していた計測器の製造会社での体験であるが、南極で使用する計測装置にアキュトロンの音叉発振時計を使用した特注品を作ったことがある。
- 1970年代はじめのことで、私が入社するずっと前のことである。
- その後、その保守のために国立極地研究所から酸化銀電池の注文が来た。
- 1980年ごろと記憶している。
- この電池は、特殊でなかなか手に入らず、当時40,000円でやっと入手した記憶がある。
- 酸化銀電池は高いなぁと思った。
- その後、1990年後半になって、電卓やラジオ、腕時計用としてこうした電池の需要が増えるに伴って酸化銀電池も安くなっていったが、それでもアルカリボタン電池やリチウム電池に比べると高価だった。
-
- 1982年の夏(約30年以上前)、プログラムカリキュレータを購入した。
- YHP(現ヒューレット・パッカード社)のHP-11Cという関数・プログラム電卓である。
- 当時、そのカリキュレータは40,000円近くしたと記憶する。
- この電卓は非常に使いやすく、今(〜2009年)でも現役でバリバリと使っている。(2017年からはスマホのアプリに入ったため使用することがなくなった。)
- この電卓に使われている電池は酸化銀電池のSR44というタイプである。
- この電卓はこのボタン電池を3個直列に使っている。
- 取扱説明書では、アルカリボタン電池LR44でも使用できるが、使用時間が半分になると書いてあった。
-
-
- ■ 水銀電池
-
- 酸化電池と同じようなジャンルに水銀電池と呼ばれるものがある。1942年に米国のルーベンによって開発された。
- ルーベン電池とかRM電池と呼ばれた。
- RMというのは、この電池がマロリー商会から販売されルーベンはこの会社の共同出資者であったことから両者の頭文字を取って名付けられた。開発された時よりボタン型電池としての位置づけが強く出力電圧が安定し、耐久性も良かった。

- 水銀電池の特筆すべき大きな特徴は、完全密封化ができることであった。
- 水銀のもつ特性が、水素の発生(分極)を抑えることができるため、完全密封化ができ、最も信頼性の高い乾電池とすることができたのである。
- 水銀電池は、正確には酸化水銀電池という言い方が正しく、正極活物質に酸化銀、負極活物質に金属亜鉛、その亜鉛に水銀を添加した亜鉛アマルガムを用いていた。
- アルカリ電解質には、酸化亜鉛を用いて飽和近くまで飽和させ、これらのコンビネーションで亜鉛からの水素の発生を抑え、液漏れのない完全な密封構造とすることが可能になった。
- 出力は1.35Vであった
- 水銀電池は、放電すると正極の酸化水銀が還元されて(酸素を奪われて)金属水銀となり、内部抵抗が下がるので、酸化銀電池よりも電圧を一定に保ちやすいという特徴があった。
- この電池は、第二次大戦中の軍事用通信機の電源から、小型カメラ用、補聴器用、時計用、電卓用と幅広く使われた。1960年代から1980年代は主に一眼レフカメラのバッテリとして使われて来た。公害の問題もあり2000年を境に姿を消した。
-
-
- ■ リチウム電池
-

 リチウム一次電池は、民生用としては日本で初めて実用化された電池である。
リチウム一次電池は、民生用としては日本で初めて実用化された電池である。- リチウム電池は、1970年代軍事用の目的に開発された。
- 電圧が高く電流も多く流せて長期間安定しているのでコンピュータのメモリバックアップとして良く使われている。
- 二次電池としての利用も多く、携帯電話やコンピュータの電源として活路を拡げている。
-
- ▼リチウム - 三番目の元素、水より軽い金属
- リチウムは、水素、ヘリウムに続く三番目の元素で、もっとも軽い(水よりも軽い)金属であり活性化の強い金属でもある。
- 電位は-3.045Vで、金属中もっとも低くイオン化しやすい性質を持っている。
- 水とは激しく反応し水酸化物を作るので、水溶液タイプの電解質は使えず、有機物の溶媒を使っている。
- リチウムの重量あたりの電気容量は、3.83Ah/gと最大で(亜鉛の電気容量は0.81Ah/gで、4.6倍)潜在的に小型軽量、高電圧出力の電池が作れることを示している。
-
リチウム金属の物理的性質
- ・原子量 : 6.939
- ・密度(g/cm3) : 0.534
- ・融点(℃) : 180.5
- ・比熱(25℃、cal/g) : 0.852
- ・比抵抗(20℃、Ω・cm) : 9.35x10-5
- ・硬度(モース) : 0.6
-
- リチウムは潜在的に高いポテンシャルを持ちながらも製品化にいたらなかった理由は、水を使わずにそれでいて内部抵抗の低い電解質の開発が難しかったことや、外部からの水を遮断するための密封度の高いシール技術が確立されなかっためであある。
- 今でもこの理由から、特に大電流を使用目的とする分野では、内部抵抗が大きく発熱の危険があるリチウム電池は慎重な検討がなされる。
- 2006年〜2007年にかけてノートパソコンのバッテリが火を噴いて、パソコンやその回りのものを焼損する事故が報告され大きな社会問題となっているが、これはリチウムイオンのエネルギー密度の高さを物語った出来事と言えよう。
- ハイブリッドカーにこのバッテリが使われた場合、安全対策は相当なレベルで行われていると想像する。事故などでバッテリが水と反応したときのことを考えるとぞっとする。
-
- ▼ 薄い
- リチウム電池は、薄くできるという特徴を持っている。
- 形状を薄く作ることで、内部抵抗が高い有機溶媒の欠点がカバーできる利点ができた。
-
- ▼ 出力電圧は3V
- リチウム電池は、他の乾電池と違って出力電圧が高い。
- 電池一個で他の電池の2個分の電圧を発生させる。
- したがって、電池容積を小さくできるのがこの電池の大きな特徴になっている。
- しかし、最近は、半導体素子の方でも1.5Vで駆動するLSIが開発されてきているため、正極に酸化銅を用いて出力電圧を1.55Vにしたリチウム電池も開発されている。
- 出力電圧が3.6Vを示すリチウム電池は、電解質と正極活物質に塩化チオニルを使用している。
- 東芝電池が1983年に発表した「ER6」というリチウム電池は、単三サイズで7Whという電気量をもち、従来のマンガン電池の70倍(アルカリ乾電池の20倍)の電気量だったと言われている。
-
- ▼ 放電特性が良い(自己放電、出力電圧)
- リチウム電池は、自己放電自己放電が極めて少なく長時間使用しても無駄な自己放電をすることがない。
- 10年以上使用する機器にも搭載されて十分にその責務を全うしている。
- 東芝電池の開発した「ER6」というリチウム電池は、使用温度特性がかなり良好で、-50℃〜+85℃でも安定した電気出力をするという。
- リチウム電池の発明のおかげで、IC技術をさらに高度に発展させることができ、コンピュータ文明の現在ではなくてはならない存在となっている。
- コンピュータのバックアップメモリ用の電池には、長期間安定して電圧を供給するリチウム電池が大活躍している。
-
- ▼ ノーベル化学賞(2019.10.08)参照
-
-
-
【バッテリー = 蓄電池 (二次電池)】
- 我々の生活の中でもっとも馴染みやすいバッテリーと言えば、自動車用のバッテリ(鉛蓄電池)、それに最近では携帯用電話のバッテリ(リチウムイオンバッテリ)、ハイブリッドカーに使われ、電動ドリル、ウォークマン用に使われるニッケル・水素バッテリを思い浮かべる。
- 1970年代には、ニッケル・カドミウム(ニカド)充電電池が家庭電化製品に使われた。
-

- ■ 鉛蓄電池
-
- 鉛蓄電池は、1859年にフランスのプランテ(Gaston Plante: 1834 - 1889)によって発明された。
- 同国人のルクランシェが乾電池を発明する9年前の事である。
- フランスは、電池にかけては随分と熱心な国であった感じを受ける。
- 鉛蓄電池は、二次電池のもっとも一般的なバッテリであり、世間一般にも良く知られ、特に自動車のバッテリーとしてよく使われている。
- このタイプの蓄電池は、1セルあたり2Vの電圧を得ることができ、自動車などでは6セルで12V、大型トラックは12セル24Vのバッテリを使用している。
-
- 鉛蓄電池は、正極、負極ともに鉛を用いる。
- 電解液は硫酸で活物質は硫酸鉛である。
- 鉛と硫酸鉛の化学反応が可逆的で、電気を通せば(充電すれば)、正極は酸化鉛、負極は鉛となり、放電すれば正極、負極ともに硫酸鉛となる。
-
- 正極反応: PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- ←/→ PbSO4 + 2H2O
- 負極反応: Pb + SO42- ←/→ PbSO4 + 2e-
- 全体反応: PbO2 + Pb + 2H2SO4 ←/→ 2PbSO4 + 2H2O
- ←:充電 →:放電
-
- 上の式では、鉛蓄電池は放電によって電解質の硫酸が両極の鉛と反応して硫酸鉛となり水が作られるため、電解液は薄くなり比重が下がることを教えている。
-
-
-
- 充電過程では、活物質が鉛と酸化鉛になるため、硫酸が電解質に戻り硫酸濃度が逆に濃くなり比重が上がる。
- 充電中の正極は、硫酸鉛が電気により硫酸と酸化鉛に変わるが、充電を続けすぎると酸素の化合が終わり酸素ガスを発生するようになる(従って、充電は気泡が出始めた頃合いが充電停止の目安である)。
-
- 酸素ガスが発生すると相方である負極にも水素イオンがガスとして大気に放出されるようになる。つまり、水の電気分解が起きることなる。バッテリ内で水素ガスと酸素ガスが発生したらとても危険である。爆発の危険がある。過去、鉛蓄電池の異常充電による爆発事故があったと聞く。鉛蓄電池の充放電を繰り返していくとどうしてもわずかであるが水素ガスが発生しそれに伴って水が無くなってくる。従って鉛蓄電池では希硫酸溶液を絶えず監視して液が減ってきたら蒸留水を足してやる必要がある。鉛蓄電池の主成分である鉛は、レアメタル(ニッケル、カドミウム、リチウム)のように高価なものを使わないないため比較的安価で、二次電池(バッテリ)の代名詞として主流の座を占めてきた。現在では、ニッケルカドミウム、ニッケル・水素、リチウムイオンバッテリが出てたため、絶対的な地位にはなり得ていないけれど自動車用のバッテリは現在でもこの鉛蓄電池である。何よりも安価で大容量の電源が確保できるので管理のできる応用範囲では現在もまだよく使われている。
-
-
-
- ▼ 鉛蓄電池の欠点
-
- 鉛蓄電池の問題点は、電解液に硫酸を使うことであった。硫酸は液体でしかも強い酸であるため液漏れを起こすと周囲を激しく侵す。この取扱がやっかいであった。それと液の管理も必要であった。鉛蓄電池は充電時、水素と酸素が発生するのである。したがって充電を繰り返していくと硫酸の水成分が減り硫酸の濃度が高くなる。
-
- 【鉛蓄電池の長所】
- ・出力電圧が約2V/セルと比較的高く、かつ出力電流、エネルギーも高い←使いやすい
- ・たくさん出回って製品が安定している。
- ・安価
- ・スケーラビリティが良い ←大型蓄電池も安価に対応可能。バックアップ電力として有望。
-
- 【鉛蓄電池の短所】
- ・自己放電しやすい ←長期間使わないと使用不可能になる。
- (自己放電で正・負極性活物質が硫酸鉛となって充電しにくくなる = サルフェーション)
- ・密閉型でない鉛蓄電池は管理が厄介 ←水の補給、設置場所が限定
- ・重い ← 活物質に鉛を使用しているので重い。携帯性に問題あり。
-
-
- ▼ 密閉型鉛蓄電池
-
- 鉛蓄電池の使い勝手を払拭した製品に密閉型(シール型)鉛蓄電池がある。
- 鉛蓄電池を密閉型にする上で問題になったのは、流動的な硫酸溶液をどう固着させるかということと、不可避な水素ガス発生、それに伴う水の補給の対策の二つであった。
- 現在、これらの問題はクリアされて、逆さにしても自由に使え(ポジションフリー)、かつ、水の補給のいらない(メンテナンスフリー)鉛蓄電池が登場している。
-
- 希硫酸の流動化を防ぐために、電極の間をガラス繊維で作った不織布を使ってマット状のセパレータを作り、これに希硫酸を染みこませる方式(リテーナー方式)で硫酸をしっかりと固着化させた。
- ガス発生を抑える方式としては、ニッケル・カドミウム蓄電池と同じ方式を採用した。
- つまり、正極より負極の活物質の量を多めにしておき充電の終わりによって先に正極で酸素を発生しやすくしておく。
- 密閉された容器内では、先に発生した酸素ガスがセパレータを介して負極に拡散されて吸収されるという。
- 吸収という意味は、正極で発生した酸素分子が負極に渡って電子を受けてOHイオンになることである。
- こうしてガスの発生が抑えられる。
- この負極吸収式の完全密閉化は、1948年にノイマンによって提案されニッケル・カドミウム蓄電池の実用化に応用された。
-
-
-
- ▼ 蓄電池の充電
-
- 鉛蓄電池の充電はどのような方式で行ったらよいのであろうか。やみくもに電源を端子に接続しても十分な充電ができないばかりか、最悪のケースでは蓄電池が再起不能になるような不測の事態に陥ることも考えられる。一般的に蓄電池には専用の充電器が用意されていて、それを使えばなんの手当も必要なく充電を行ってくれる。鉛蓄電池は可逆的な反応であるから、放電と同じ電圧と電流で電気を流してやれば元に戻りそうである。基本的な考え方はこれで良いのではないか。ただし、充電は放電よりも少し電圧を高くして、つまり、放電しようとする電気的な力より少し強めの電圧をかけてやれば良さそうである。充電電流は速やかに電流を流し、充電満了間際は過充電を防ぐために電流値を制限してやればよいのでないか。そんな考え方で充電をすればよさそうである。バッテリの充電の基本は、電極活物質表面積あたりの電流密度を一定に保つという観点から、初期は大電流で、中期、終期と電流を減少させて行うのが原則であるという。実際の充電は、いろいろな手法があり、ここでは全てを書ききれないが、一般的には、バッテリーの残量(どれだけの電気容量が残っているか)と充電する際の温度によって充電する電流を決めているようである。
- 12V鉛蓄電池を摂氏25度で充電する場合を例に取ると、充電電圧14.4Vで、
- → バッテリに半分しか電気容量がないときは、30A
- → 75%の電気容量の時は、14A
- → 100%充電が完了したときは、2A
- という値がバッテリに流しうる電流値であるという。
- また、充電する際の電流値は温度によっても変わり、充電電圧14.4Vで、容量が50%ある時、
- → 50度Cの時は、35A以上
- → 25度Cで、30A
- → -15度Cの時は、2A
- という値が得られている。充電は温度が高い方が電流を多く流せることを示唆している。充電器はこれらの鉛蓄電池の充電特性をもとにいろいろな手法の充電方法を用いているバッテリがすっかり電気を消費してカラカラの状態であるときは、目一杯の電流を流して(但し、定電流電源回路を用いて)充電を行い、電源容量が回復して来たら徐々に電流を下げていき、満杯になったら2A、もしくはストップさせてしまう方式が取られている。
- これが急速充電という方式である。これらの充電器は価格が高価であるため、初めから2Aで流す充電器もある。この手法は、バッテリの充電容量をチェックする必要がなくずっと流しておけるため充電器が安価にできる。8時間程度の充電が必要な充電器はこのタイプである。
-
- ▼ 浮動充電(フロート充電)とトリクル充電(補償充電)
-
- 浮動充電は、バッテリと負荷が並列に接続されていて通常は充電器からの電源で負荷をまかない、充電器からでは足りない負荷のとき(電流を必要とするとき)にバッテリから電気を負荷側に補充してそのあと不足分を充電器から充電する方式を言う。この方式はバッテリが充電回路に附属しているような形で接続され、回路上「浮き上がった」ような状態になっていることから「浮動充電(フロート充電)」と呼ばれている。トリクル充電のTrickleとはぽたりぽたりと水が滴り落ちるとかチョロチョロと水が流れるという意味で、このような状況でバッテリーを充電する方式である。バッテリは常時負荷にはつながれておらず、チョビリチョビリと充電され、電源に不測の事態が起きたときにバッテリが負荷側に接続されて働き出す。
-
- ▼ 急速充電
-
- 急速充電が行える身近なバッテリは、シール型の鉛蓄電池とニッケルカドミウム蓄電池である。おおよそ1時間で充電することを急速充電と言っている。
- 急速充電をする方法には、
-
- ・ 定電圧充電方式、
- ・ 電流低減方式、
- ・ -ΔV(マイナスデルタV)方式、
- ・ 温度検出方式、
- ・ ガスセンサー方式、
- ・ パルス充電方式、
- ・ クーロメーター方式、
-
- などが上げられる。いずれもバッテリの充電容量を細かくチェックしながら、必要十分な電流を制御して送り込むことを基本としている。
-
- 【定電圧充電方式】
- 一定の電圧をバッテリに印加して、バッテリの持つ電圧との差を利用して充電電流を自動的に加減する方法である。
-
- 【電流低減方式】
- 充電完了間際になる充電末期の電圧を検出したら、充電電流を次第に減らしている方式。
- 「Vテーパー方式」とも呼ばれている。 電池の中のガス発生を抑え効率よく充電できる特徴がある。
-
- 【-ΔV(マイナスデルタV)方式】
- ニッケルカドミウム電池では、充電の終わりに電池電圧がピークに達した後に 下がる降下電圧(これをマイナスデルタVと呼ぶ)を検出して充電を終了させる方式。
- ポータブル電気製品のニッケルカドミウム電池の充電に採用されている。
-
- 【温度検出方式】
- ニッケルカドミウム電池で、過充電になったとき発生する酸素を 負極(カドミウム)が吸収するときに生ずる化学反応熱による温度上昇を 利用するもので、一定温度で働く温度センサーを用いる。
-
- 【ガスセンサー方式】
- 複数のセルで構成されているニッケルカドミウム電池群のうちの 一つのセルに酸素ガスセンサーを埋め込み、充電の終わり(90%)に 発生する酸素をキャッチして充電電流をコントロールする。
-
- 【パルス充電方式】
- ジョグル(揺さぶり)充電方式とも呼ばれ、パルス状に電流を流して 充電を行い充電が完了する間際にはその充電パルス間隔を長くする方式。 過充電を避けられるため鉛蓄電池によく利用される。
-
- 【クーロメーター方式】
- クーロメータ(クーロンメーター)とは電量計のことで、 電池に充電した電気量(クーロンか、アンペア・アワー = Ah)を測るものである。
- クーロメータは、両極がカドミウムを使った特殊な電池で 電圧がなくて容量だけがたまるものである。
- このクーロメータを充電する電池に直列に挿入し充電を行うと、 充電の終わりや放電の終わりに急に電圧変化を起こして1.5V程度になる。
- この変化をキャッチして電流をコントロールする。
-
-
- ■ ニッケルカドミウム蓄電池(Ni-Cd、Nickel-Cadmium rechargeable Battery)
-
- ニッケルカドミウムバッテリは、1899年、スエーデンのユングナー(Waldemar Jungner)によって発明された。1906年ユングナーは、このバッテリを市販化するために会社を興し、NiFe(ニッフェ)というブランドで製品化した。工業化したのは1910年でSaft社である。鉛蓄電池が電解液に硫酸を使っているのに対し、ニッケルカドミウム電池は水酸化カリウム(または水酸化ナトリウム)のアルカリ性水溶液を使っている。名前からしておっかなそうな電池であるが、1960年代後半から国産化が進み家庭用の二次電池として急速に普及していった。このバッテリは、1899年に原理が発見されながら広く行き渡るまでに60年の歳月がかかっている。
- カドミウム(Cadmium):
- 1817年ドイツのシュトロマイヤーによって発見。 当時、医薬品である炭酸亜鉛を熱して亜鉛華を作っている時、 本来無色であるはずの亜鉛華が黄色を呈するすることから、 不純物として含まれていたカドミウムを発見した。 これにより、ギリシャ語の亜鉛華の意味である Kadmeiaからカドミウムと命名された。 カドミウムは、主に亜鉛を精製するときに析出する。 カドミウムは、青みを帯びた銀白色、光沢のある金属で 柔らかくナイフで容易に削れるという。 水銀とはアマルガムをつくりやすい。 空気中に放置すると表面が酸化し内部を保護する。 カドミウムは仕上げ面がきれいで耐食性がよいので 通信機材料やその他のメッキに用いられる。 ビスマスに添加した低融点合金、銀、ニッケル、 銅などに入れて軸受け合金に用いられている。 また、ハンダや歯の治療に使うアマルガムとしても 使われている。 硫化物はブラウン管の発光体として使われ、硫化物、 ヒ化物は顔料として用いられている。カドミウム化合物やカドミウム蒸気は有毒である。 富山県神通川流域および群馬県安中市でのイタイイタイ病は、 亜鉛精錬工場などから排出されたカドミウムの汚染によって生じたものとされている。
-
- ・元素記号: Cd
- ・原子番号: 48
- ・原子量: 112.41
- ・融点: 320.9℃
- ・沸点: 765℃
- ・比重: 8.65
-
- ニッケルカドミウム電池が普及したのは、鉛蓄電池に比べて取扱が格段に良かったためと考えられる。すなわち、開発の早くからシール型電池として発売できた。これは鉛蓄電池の所でも述べたが、1948年のノイマンによる「負極吸収式の完全密封化」の発明に寄るところが大きい。この発明によって、鉛蓄電池もその恩恵を受けることになった。しかし、歴史的には鉛蓄電池のほうが早く実用化されて広く行き渡ったため、鉛蓄電池は取扱が楽、というイメージはなかなか定着しなかった。ニッケルカドミウム電池は、その間隙を縫って一般家庭電化製品の脇役として普及していった。ニッケルカドミウム電池の二番目の大きな特徴は、完全放電しても回復が可能である点であった。このほか作りが堅牢、効率よく充放電ができる、使用期間が長く長寿命という特徴がある。
- 反面、ニッカド電池の短所は、
-
- ・ 鉛蓄電池に比べて原材料が高価、
- ・ 使わないと電池が放電しやすい(自己放電大)、
- ・ メモリー効果がある、
-
- という点である。

- ニッカド電池は、負極にカドミウム、正極にオキシ水酸化ニッケルを使用して
-
- 負極: カドミウム ←→ 水酸化カドミウム
- 正極: オキシ水酸化ニッケル ←→ 水酸化ニッケル
-
- の可逆反応を行っている。
- 鉛蓄電池は、希硫酸が積極的に関与するため反応によって濃度が変わったが、
- ニッカド電池では生成物を作らないので水酸化カリウムの濃度変化はない。
- 公称電圧は、1.2V、理論エネルギー密度は、209Wh/kgである。
-
- 正極反応: NiOOH + H2O + e- ←/→ Ni(OH)2 + OH-
- 負極反応: Cd + 2OH- ←/→ Cd(OH)2 + 2
- 全体反応: 2NiOOH + Cd + 2H2O ←/→ Ni(OH)2+ Cd(OH)2
- ←:充電 →:放電
-
-
- ▼ メモリー効果
-
 ニッケルカドミウム電池の欠点の一つにメモリー効果がある。
ニッケルカドミウム電池の欠点の一つにメモリー効果がある。- これはあまり良い効果ではなく、電池の容量が見かけ上少なくなってバッテリの電圧が急速に落ちてしまい、購入した時の性能ができない現象である。
- この現象は、電池を少ししか使わず(全容量の1/4程度)その間で充・放電を繰り返すと起きる。
- 通常は、充電完了から終止電圧までほぼ一定の電圧で推移し、容量がなくなってくると、徐々に電圧が降下する。
- メモリー効果を生じると普段使っていた容量近辺で電圧が落ちそのままの電圧でしか放電を行なわなくなる。
- メモリー効果は、普段、緩やかな使い方をしていて、あるとき大容量の使い方をした場合にバッテリー上がりの症状を示す。
- この症状は、負極の活物質が結晶化し小さい粒が大きくなって活物質の表面積が小さくなるためと言われている。
- こうしたメモリー効果を出さないためには、ニッカド電池を半年に1回大容量放電して空っぽにして充電し「リフレッシュ」してやればよい。
- ニッカド電池は、使わないときはむしろ電気を空っぽにして放電しきっておくとよい。
- 鉛蓄電池では完全放電は御法度であるが、ニッカド電池にとってこれは問題ない。
- ちなみに鉛蓄電池にはメモリー効果はない。
-
- ▼ ニカド電池ライト(サンヨー カドニカライト)の思い出
-
 カドニカライトは昭和40年(1965年)販売された。
カドニカライトは昭和40年(1965年)販売された。- 当時の懐中電灯は耐久性のない一次電池しかなかった。 それが、充電によって何回も使えるカドニカライトが世の中に出た。 夢のような代物だったと小学校時代を思い出す。
- カドニカライトによってサンヨーの名前が一気に消費者に知られていくようになった出来事だった気がする。我が家にはそのカドニカライトはやってこなかった。我が両親はそうしたものに無頓着であった。知り合いの家にはカドニカライトがあって、夜その懐中電灯を持ってやって来ると、しげしげとそれを眺めたことを思い出す。 とても小さくてポケットに入る大きさだった。
- だがそのライトは、残念ながらあまり明るくなかった。 反射鏡が小さくて米粒のような投光レンズが頼りなげに見えた。 単一電池を4本入れた大きい懐中電灯の方が何倍も光量があって夜の道を照らしてくれた。きれいに磨かれた反射鏡から投光する大型懐中電灯は、モヤのある夜などビーム光線が浮かび上がって50m先まで照らし出した。 カドニカライトは残念ながらそれほどのビームの強さは無かった。 コンパクトなパーソナルな懐中電灯であった。
- 資料によると、電球は2.4Vで200mAの消費電力であり、光束が1.5lm、バッテリは16時間の充電で50分間の連続点灯ができたとある。1.5ルーメンは暗い。道を照らすのに1メートル四方で1.5ルクスとなる。バッテリも50分しか保たなかったのだな。そして、丸一日程度の充電が必要だったのだ。(2015.07.20記)
-
-
-
-
-
- ■ ニッケル水素電池(Nickel Metal Hydride Battery)
-
 ニッケル水素電池は、コンピュータの普及に伴って脚光を浴びた二次電池である。ノートパソコンタイプのバッテリや、自動車のハイブリッドカーで一躍その名を馳せた。
ニッケル水素電池は、コンピュータの普及に伴って脚光を浴びた二次電池である。ノートパソコンタイプのバッテリや、自動車のハイブリッドカーで一躍その名を馳せた。- ニッケル水素電池をみると、形状や使い方などニッケルカドミウム電池の代替え品であることを強く感じる。私が使っていたノートブックパソコンも、1994年当時はニッケルカドミウムバッテリであったが、1997年に購入したノートブックにはニッケル・水素バッテリ(Ni-MH)が装着されていた。もっとも、1999年に新しく買ったノートブックはリチウム・イオン電池になっていた。
- ニッケル水素電池は、充放電の繰り返しが安定していて、ニッカド電池よりもパワフルで長持ちというイメージを強く受ける。ノートブックのCPUが高性能化し、液晶モニターもカラー大型になって消費電力も大きくなったのに、使用時間が2時間程度確保できた。
- 上左の写真のニッケル水素バッテリは、MDウォークマン用のガム電池で1997年に購入したものである。この電池は、1.2V1200mAhである。購入後5年目に入るが実にパワフルに活躍している。この電池1本で、MD約2本(約2時間)が聞ける。ということは、私のMDウォークマンMZ-E50は、1.2V600mA(0.72W)で駆動していることになる。アルカリ電池は、約3Ah程度なので6本程度のMDが聞ける。これは経験値と合致する。それにしても、ウォークマンは1W足らずの電力でMDのディスクを回し、イアホンを力強く鳴らす力がよくあるものだ、と感心する。しかし、ノートブックに使っていたニッケル水素電池は、何回か使っているとヘタリ(疲労)が起きて新品ほどには働いてくれなくなった。使い方にバッテリの消耗の度合いがあるのであろうか、それとも製造上の問題であろうか?バッテリは、結構高価である。ノートブック用のニッケル・水素電池で、当時15,000円ほどした。それが、1年くらいでダメになるからかなり痛手だった。おまけに、ノートブックパソコンの製品寿命が短いため、バッテリを追加購入しようにも販売中止になっていたりする。
- パソコン用のバッテリは、2000年を境にリチウム・イオンバッテリに移行して行った。
-
-
-
- ▼ニッケル水素電池の開発
-
- ニッケル水素電池の発明は、1960年にNASAの宇宙開発の一環で発明された。水素燃料電池もNASAの宇宙開発の一環で開発されたことを思うと、興味深い。現在の大事な電池の二つが、こうした宇宙開発の一環から作り上げられたのである。この電池の開発のキーポイントは、水素が電気の力によって自由に出し入れができる材質、すなわち効率良い水素吸蔵合金の開発であった。NASAは、当時、燃料電池を開発していて水素ガス拡散電極を使って宇宙開発用の高圧ボンベ型ニッケル・水素蓄電池を造った。その電池の水素を蓄える高圧ボンベの代わりに、取扱の便利な水素をたくさん吸収するAB5型水素吸蔵合金(例えば、LaNi:ランタンとニッケルの合金)を開発した。この水素吸蔵合金を開発をする過程でニッケル水素電池が開発されたのである。
- その後、多くの研究の結果、1992年には、低圧で充放電のできるバッテリが開発された。これは、NASAで開発されたAB5型のAに相当するLa(ランタン)の代わりに、Mm(メッシュメタル)を用いるMmNiH(金属水素化物)を負極として、苛性カリ水溶液中でニッケル正極と組み合わせたものであった。これも、もちろん充放電におけるガスが発生しない密閉型の電池となった。
- この電池は、構造、作動電圧、作動温度範囲などほとんどニッケルカドミウム電池と同じであるにも関わらず、2倍以上の容量を確保できた。しかもニッケルカドミウム電池の欠点であったメモリー効果を持たないという特徴を持っていたため、ニッケル・カドミウム蓄電池の領域に入り始めた。ただし、現在のところ、あまり大型のものが作られず小型電池に的を絞った形で作られている
-
-
-
- ▼ ニッケル水素の原理
- 電池の問題点は、「分極」に見られるように電極に現れる水素ガスとの葛藤の歴史であることが、上の様々な電池の紹介で理解いただけると思う。ニッケル・水素蓄電池は、負極に予め水素をイッパイ蓄えておいて、必要に応じて電解質中に放出し、必要がなくなれば再び貯蔵するという仕組みをもったものである。
- 電気反応の究極の媒体である水素を使っているので、直接的である。
- この電池は、最終的には、いかに効率よく水素を蓄えられる水素貯蔵合金を開発するかにかかっているようである。
-
- 正極反応: NiOOH + H2O + e- ←/→ Ni(OH)2 + OH-
- 負極反応: MH + OH- ←/→ M + H2O
- 全体反応: NiOOH + MH ←/→ Ni(OH)2+ M
- ←:充電 →:放電
-
- 上の反応では、放電時、水素吸蔵合金負極に吸蔵されている水素が水素イオンとなって(同時に電子を放出し)正極に達し、オキシ二酸化ニッケル(NiOOH)と反応して(電子を受けて)水酸化ニッケル(Ni(OH)2)となる。充電時は、負極に電子を受けて再び水素を取り込み、正極では水酸化ニッケルがオキシ二酸化ニッケルに変わる。正極反応はニッケルカドミウム電池と同じ反応である。公称出力は1.2Vである。
-
-
-
-
- ■ リチウムイオンバッテリ (2003.07.20記)(2015.07.21)(2019.01.05追記)
-
- リチウム・イオンバッテリ(Lithium Ion Battery)は、携帯電話用のバッテリとして急速に需要を伸ばしている二次電池である。最近は、携帯電話用のみならずノートブックパソコン用のバッテリ、デジカメ用電池として幅広く使われている。比較的高価であるにも関わらず、このバッテリが採用されているのは、リチウム電池固有の安定した電気出力と、放電特性が良くて使わなくても自己放電が少ないこと、エネルギー密度が高いので小型コンパクトに設計できること、そして、3.6Vという高い放電電圧を有する特徴があるためである。
-


- 写真左:DoCoMo携帯電話に使われている薄型リチウムイオンバッテリ
- (3.7Vで550mAh)(109mm x 38mm x 4.8mm)
-
- 写真右:SONYのデジタルカメラ DSC-F1に使われているリチウムイオンバッテリ(3.6Vで750mAh)
- (右の電池は、1996年に購入したデジタルカメラのバッテリで、初期型のため容量の割にサイズが大きい。
- 疲労も激しく購入3年で寿命が尽きた。
-
-
- リチウム(一次)電池は、先にも述べたが1970年代に実用化された。これを二次電池として応用する試みがなされてきたが、負極の再充電時の問題点がネックとなり、10年以上を経た1981年に開発された。
-
- 正極反応: CoO2 + Li+ + e- ←/→ LiCoO2
- 負極反応: LiC6 ←/→ Li+ + e-+ C6
- 全体反応: CoO2 + LiC6 ←/→ LiCoO2+ C6
- ←:充電 →:放電
-
-

-
-
- リチウム一次電池は、負極に金属リチウムそのものを使っているが、充電を可能とする二次電池では金属リチウムをそのまま利用することはできない。
- リチウムは、放電することによって電解液中にイオンとなって溶け出し、充電時に金属リチウムに戻るとき、デンドライト(樹枝状結晶)が析出し、内部短絡のおそれが生じる。
- この現象が起きると電池がショートし、電池の寿命を著しく短くしてしまう。そこで、この問題を解決するためにいろいろな合金が試された。
- 結論的には、リチウムの反応性や電気容量を抑えるような合金しか当面の問題を解決するものがなく、それでも実用化に十分に耐えるということで市販化がなされた。
- 負極材料としては、当初、LiAl合金、ウッド合金(この場合、電圧が50mV低下した)が用いられていた。
-
- 1981年、日本の三洋電機の池田宏之助氏らにより、黒鉛に混ぜて使用する黒鉛積層化合物LiC6が開発された。この電極の開発により、リチウムイオン電池の実用化が一気に進んでいった。しかし、この材料は、理論容量密度が1/10になってしまうという問題を抱えていた。
- 正極材料としては、LiCoO2(コバルト酸リチウム)が使用されており、今後、酸化物ではα-NaFeO2構造、スピネル構造(LiMm2O4)などが検討されているという。
-
- リチウムイオン電池は、充電の時は、正極からリチウムがイオンとして電解液に溶解し、負極の黒鉛層間に入る。このように層状またはトンネル構造をもつ化合物にリチウムなどのイオンが入り込む現象をインサーションと呼んでいる。放電ではこの逆の現象が起きる。
-
- このように、リチウムイオン電池の充・放電反応は機構的に単にリチウムがイオンとして正極・負極間を往復するだけの反応となっている。
- このリチウムイオン電池は、ソニーによって初めて市販化された。
- リチウムイオン電池は、寿命、耐久性、安全性などまだまだ解決しなければならない問題も多いと言われる。しかしながら、それでも近年のこの電池を使う機器が増えていることは、この電池のもつ潜在能力が他の蓄電池とはかけ離れて優れていることを物語っている。
-
- リチウムイオン電池は、新しい電池であり日々進化を遂げている。逆に言えば問題点を克服しながら改良を重ねていると言えなくもない。
-
- 1990年代に入って、4ボルトのリチウムイオン蓄電池が開発され広く普及するようになった。リチウムイオン蓄電池の特徴は何度も言うが小型にでき、出力が安定していて、耐漏液性、長寿命化、相対的に経済的というメリットを持っていることである。
-
- リチウムイオン蓄電池の代表的なものを以下に挙げる。
-
- 1. リチウム含有二酸化マンガン・リチウムアルミニウム合金二次電池
- 1988年頃より実用化。メモリバックアップ用電源として利用。
- 2. バナジウム・リチウム二次電池
- 正極活物質に結晶化バナジウム(c-V2O5)を用い、負極としてLiAlを使用。
- 放電電圧約2.85V、エネルギー密度高。
- 3. パナジウム・ニオブ・リチウム二次電池
- 放電電圧約1.5V。信頼性の高い充・放電特性の優れたバッテリ。時計用1.5V用ムーブメントに使用。
- 4. 高分子固体電解質を用いたリチウム二次電池
- 薄膜の固体電解質を用いた蓄電池。安全性の向上、高エネルギー密度化の要求から開発が進む。
-
- 【ノーベル化学賞受賞 - 2019.10.08】(2019.10.12記)
-
- 2019年のノーベル化学賞は、リチウムイオン電池開発の功績を称えて三氏に授与された。
- 三氏は、米国テキサス大学オースティン校のジョン・B・グッドナフ教授(97)(John Bannister Goodenough : 1922.07.25 - )、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校のM・スタンリー・ウィッティンガム教授(77)(Michael Stanley Whittingham : 1941)、そして、日本の旭化成名誉フェローで名城大学教授の吉野彰氏(71)である。
- リチウムイオン電池は、1970年代に研究が始められた。
- 1970年代は、石油危機が叫ばれ石油エネルギーに代わるものとして新しいエネルギーが注目されていた。
- 英国ノッティンガム生まれのWhittingham(ウィッティンガム)氏は、エネルギーの豊富な二硫化チタンに注目しリチウム電池のカソード(正極)として利用した。アノード(負極)には金属製のリチウムを使用した。
-
- リチウムは強力な化学反応をもつ金属で、爆発をも伴う危険な物質であった。その問題点を改善するため、ドイツ生まれのアメリカ人Goodenough(グッドイナフ)氏が1980年に二硫化チタンに代えて金属酸化物であるコバルト酸リチウム(Liを用いて安全でかつ4Vの出力をもつリチウムイオン電池)を開発した。
- この研究は、1979年、氏がオックスフォード大学教授の時代に始まり、同大学に留学していた東京大学の水島公一氏(後に東芝)とともに電極活物質にリチウムコバルト酸化物が利用できることを発見したことに始まる。
- グッドイナフ氏の研究をもとに日本の旭化成に勤務していた吉野彰氏は、グッドイナフ博士らが発見したリチウムコバルト酸化物を正極活物質として、白川英樹氏(1936.08.20 - 、2000年ノーベル化学賞受賞)が発見したポリアセチレンを負極活物質とする安定した二次電池を開発した。
- 同氏はさらに開発を続け、特定の結晶構造を持つ炭素材料を負極活物質を用いて世界で初めて商業化に耐えられるリチウムイオン電池開発に成功した。
- 吉野氏の研究成果を受けてソニーが1991年に商品化し発売した。ソニーは、実は独自にリチウムイオン電池を開発していた経緯がある。
-
- 【電気自動車電池としてのリチウムイオンバッテリ】
-
- ENAX(エナックス)というリチウムバッテリを作っている会社のホームページに、リチウムイオンバッテリを使った一人乗りの電気自動車の紹介があった。(その記事は1998年当時のことで、今は販売を終了している。)
- 電池は、116Ahで25.6V出力、電池エネルギー3kWh(寸法:320(W)×140(H)×320(D) mm、重量30 kg)を出す。
- モータはDCブラシモータで600W。
- これを車両総重量100 kgの一人乗り小型自動車を引っ張って、150kmを走行する。
- トヨタのプリウスが30kWのACサーボモータを使って288Vのニッケル・水素バッテリとエンジンで駆動するのに比べて随分と小ぶりな感じを与える。
- モーターは1/50の力しか発生しない。600W全開でモータを回すと5時間で電池が消耗する換算になる。
- 通常は全開で回すことは少ないが、それでも毎日乗れば2、3日に1回の充電を必要とする換算になる。
- プリウスは、当初、バッテリにニッケル・水素を採用した。
- これはおそらくリチウムイオンバッテリがまだ十分に安定していないと想定しての判断であったろうと思う。
- 2003.04月には、二代目プリウス、THS-II(THS = Toyota Hybrid System)が発売された。
- 2世代目のプリウスは、500VのブラシレスDCモータを採用し、出力を45psから68psと1.5倍に高めている。
- エンジンも従来のミラーサイクルエンジンを改良し、5000rpmで78psの出力(従来は、4,500rpmで72ps)と高めている。
- バッテリは、従来のニッケル水素バッテリであるが、内部抵抗を低減し、入出力密度を35%向上させた。
- 2世代目のプリウスは、エンジンの燃焼効率が88%であり、車両効率を37%とし、総合効率を32%まで高めている。
- 初代プリウスが25%であったのに対し7%も向上した。
- 最新のガソリンエンジン車のエネルギー効率が14%と言われる中、驚異的な効率である。
- 2代目プリウスは、モータアシストの働きもあって加速がすばらしくよく軽快に走ると言う。
- トータルバランスのとれた2代目プリウスは、自動車業界の2003年の各賞(米国カー・オブザイヤーなど)を総なめにした。
- 話がそれたが、リチウムイオンバッテリは、とにかく小型にできるというメリットがある。
- ENAXのホームページを見て、近い将来リチウムイオンバッテリを乗せた本格的な電気自動車、もしくはハイブリッドカーが登場するかもしれないと思った。
- (2010年、日産からリーフと呼ばれる24kWh容量リチウムイオンバッテリー搭載の電気自動車が発売された。2008年には米国西海岸のテスラ社がスポーツカータイプのテスラ・ロードスターを発売した。ノートパソコン用のリチウムイオンバッテリ(18650規格)を6,831個搭載して総容量53kWhとしていた。)
- 2009年に登場した三代目プリウス(ZVW30)は、従来と同じニッケル・水素電池でありリチウム・イオンバッテリではなかった。
- 2015年9月に発表された四代目プリウス(ZVW5#)では、同シリーズで始めてリチウムイオンバッテリが搭載された。
-
-
- 【全固体化電池】
-
- これまで説明したバッテリーは、正極と負極の間は液体(もしくはゲル状)の電解液で満たされている。物質がイオン化して化学反応を起こすのには液体状の方が活性化しやすいたためである。
- この液体電解質を固体にするのが全固体化電池である。
- 電池全体を固体化することのメリットは、
- ・充電時間が極端に短くなること。
- ・液漏れがなくなること(耐久性)、真空領域でも使えること、
- ・高温度(100℃)でも低温(-30℃)でも使用できること、
- ・内部抵抗が低いため効率がよく発熱を低く抑えることができること、
- ・高じて容積を小さくすることができること(1/5〜1/10)
- である。このような長所が注目されて国家プロジェクトも始動しNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)は2018年6月全固体リチウムイオン電池の早期実用化のための研究開発プロジェクトの第二期をスタートさせた。
- このプロジェクトには自動車・電池・材料メーカー23社と大学・公的研究機関15組織が参画している。
- このプロジェクトでは、
- ・体積エネルギー密度3倍(600Wh/L)
- ・急速充電時間 1/3(10分)
- ・コスト1/3(1万円/kWh)
- を目標に掲げている。バッテリーは充電に時間がかかるため、自動車などのエネルギーに使う場合には充電時間の短いバッテリーは特に望まれる性能である。
-
-
-
-
- 1-3-2. 直流発電と交流発電
-
- 電気を作る。社会の中で一番大事なエネルギーの一つである電気。
- それを作ってみよう。と言っても、個人で作る電気などたかが知れている。
- 電気は、蓄えられるものとそうでないものがある。
- 上で述べたバッテリは、電気を蓄えられるもので、すべて直流電源として使用される。
- 電気を複雑なものにしていることの一つに、直流と交流がある。
- 電気を作る手段にも、直流発電と交流発電がある。
- 作り方は、双方とも極めて簡単、モータを使う。電車に使われているモータ。これと似たような構造で、でかいものを使う。
-
- モータ?
- モータは電動機であり、発電機ではないでないか?
- そう、役割は違う。しかし、構造は同じだ。
- 内部構造は、モータと全く同じの発電機。外部から電気を流せば自ら回転し、外部からモータを回転させれば電気を発生する。
- したがって、発電機には、直流発電機と交流発電機がある。
-
- 交流と直流については以下のACとDC(交流と直流)を参照していただきたい。
-
- なぜ、発電の方式に交流発電と直流発電があるのか?
-
- このことに関しては、結構長い歴史がある。
- 最初に電気を発生する電源を確保したのは、イタリア人のヴォルタである。彼は「バッテリーの元祖」とも呼ばれるべき人で、ヴォルタの電堆(でんたい)を発明した。
- 電圧のV(ボルト)は彼の名前に由来する。
- 電気を貯めるバッテリーは、ほとんど例外なく(もちろん乾電池も)直流電源である。
- 直流電源はまことに理解がいい。水圧や水流と考えをダブらせられるので納得がいく。
- 中学までの理科で習う電気の説明は、直流一本槍ですまされる。
- しかし、学校で習って意気揚々と家に帰っても、家庭には理解に難しい交流電源がある。
- これが、中学当時の私には理解できなかった。
- 「なぜ交流電源なのか?」、
- 「直流だったら簡単に説明がつくのに」。
-
- 学校で習っていることは、家庭ではまったく応用できなかった。
- それに、家庭の電気は恐ろしかった。簡単には触ることができなかった。
- 乾電池は、手で触ってもなにもビリビリ来ないのに、家庭用の電源は飛び上がるほどの刺激を受ける。
- ほんとに手強かった。
- 歴史的に電源の発達を見てみると、電気は、ヴォルタの電堆に代表される直流電源から始まり、それが広く使われていた。ファラディーもこの電堆を使って化学分解をおこなった。
- 直流電源は、当時も理解が簡単であったため、複雑な電磁誘導を駆使した発電機も発明当初は無理をして直流発電機にしていた、というのがホントの所である
- エジソンもそうした。
- そして電灯会社を発展させた。
- 以下の項で述べるように、電灯会社は必死になって発電設備や発電機を作った。
- 直流発電所も勿論作った。
- しかし、交流電源の方が、大きな発電機が作りやすく、変圧などの送電がしやすいことや、発電機の後のモータの出現によって(モータは交流の方が作りやすいこともあって)交流電源の方がはるかに利用価値が高いことが認められ、交流発電が主流になっていった。
- 発電と送電は、交流で行っているけれど、我々の身の回りの電気製品は直流電源で動く機器が多い。
- それらの機器は全て装置の中に交流→直流変換装置(コンバータ)を内蔵している。
- 例を挙げると、直流による電気製品は以下のものが上げられる。
-
- 【機器に直流電源装置を内蔵しているもの】
- オーディオアンプ、コンピュータ電源、テレビ、
- ラジオ、シェーバー、時計、電話機、
- オーディオウォークマン
-
- もちろん交流電源をそのまま使う機器もある。
- 強力なモータを使う家庭電化製品やヒータの類である。
- 例えば、以下の家庭電化製品が交流を直接利用している。
-
- 【交流周波数電源をそのまま利用しているもの】
- ドライヤー、冷蔵庫、洗濯機、扇風機、掃除機、エアコン、
- 電球、蛍光灯、街路灯、ミキサー、電気ヒータ、ホットカーペット
- (しかし、最近の冷蔵庫やエアコンなどの性能の良いモータは、商用電源周波数を直接利用する
- モータを使わずに回転数が自由に変えられるインバータモータを使用している。)
これらの機器は、交流電源が重要な役割を果たしている。電圧が周期的に変わることにより、交流電源につながれた電動機(モータ)が回転する。
- 交流電動機を使った機器は交流電源がなければ動かない。
- 工場で稼動しているモータ(ベルトコンベア装置、旋盤、空調用コンプレッサなど)は、出力の大きいもので大電力での交流電源をしようしている。
- この他、蛍光灯は、交流電源だからこそできた放電灯である。
- 蛍光灯の原理は、交流電源を学ぶ上で格好の材料であろう。(参考:『光と光の記録 - 蛍光灯』)
-
- もっとも最近は、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどで周波数を変えて出力を任意に取り出せるインバータモータが使われ始め、こまめな電力管理を行う機器が出始めた。 周波数変換は、インバータと呼ばれ、電力会社から送られている交流周波数をいったん直流に直し、パワートランジスタと高周波発振器を組み合わせて希望する周波数に変えている。 インバータ装置が安価に出回る前は、モータはONとOFFしか制御できなかったために、冷蔵庫やエアコンなどでは強く冷やされたり、暖かくなるまで装置が作動できなかったりで、細かな制御はできなかった。 その上、暖かくなった室内を強く冷やさなけらればならない関係上、ON時のモータは強く回転し、音も大きくて電気もたくさん必要とした。 インバータの発明によって、必要十分な回転数と出力が得られるようになったので、電気も少なくてすむようになり作動音も静粛になった。
- ヒーターは、実際の所、交流でも直流でもどちらでもよい。 電気を流して発熱させてやれば良いだけなのだから。 ただ、発熱のためにはかなりの電流を流す必要があり、送られてくる交流電源を直流電源に直して使ったのでは付帯設備が高価なものになるので、そのまま交流電源で使用している 。白熱電球も直流でも良いのだが交流電源で使用している。 交流電源周波数以上の周波数を使用している機器もたくさんある。
- 例えば、
- 【電源周波数を変えて利用しているもの】
- 電子レンジ、高周波インバータ蛍光灯など
- (最近のインバータエアコン、インバータ冷蔵庫、インバータ洗濯機、など)
- これらは、機器の内部に周波数を作る回路があって、これで希望する周波数を作っている。 周波数の高い装置は、家庭から離れればありとあらゆるところで見つけることができる。
- 【高周波発振器を使っているもの】
- 無線、テレビ・ラジオ放送、高周波焼き付け装置
-
●交流発電と直流発電についてエジソンにまつわるエピソード:
 電灯を発明したエジソンは、電灯に電気を送るため発電所建設に取り組んだ。
電灯を発明したエジソンは、電灯に電気を送るため発電所建設に取り組んだ。- 大規模な電力供給システムは、電灯事業から始まったのである。
- 電灯を発明したエジソンは、電灯に電気を送るため発電所建設に取り組んだ。
- 大規模な電力供給システムは、電灯事業から始まったのである。
- 右写真は、エジソンの直流発電機である。
- 右下の写真を見ると、整流ブラシが見えて、この発電機が直流であることを雄弁に物語っている。
- この発電の性能は、以下の通り。
- ・ 出力: 17kW
- ・ 電圧: DC110V・ メーカ: Edison Machine Works Builders
- (東京電力 電気の史料館 展示)
-
- エジソンが推進した白熱電灯の企業化は、1878年、「エジソン電気照明会社」に始まる。
- 資本は、すでに早くから企業として成立していた電信業界(その背後には鉄道資本があった)から集められた。
- 電力を送る送配電システムには、スイッチから始めて、プラグやソケット、ヒューズ、電力メータ、発電機、配電線、電柱などあらゆる付帯設備を規格に従って作らねばならない。
 供給する電圧についてエジソンは、ファーマーの並列方式を採用して110Vに決めた。
供給する電圧についてエジソンは、ファーマーの並列方式を採用して110Vに決めた。-
- ■ファーマー(Moses G. Farmer:1820 - 1893):
- 電話機を発明したベルの技術相談相手。
- 電信技術に明るく、多重通信を提案した一人。
- 初期の白熱電球の研究にも従事。自分の家で白熱電球を最初に灯した。
-
- 彼が採用した電気を送る送電方式は、もちろん直流方式であった。電力送電の始まりは、1882年エジソン電灯会社の幹部ジョンソンによってロンドンで作られた。操業を開始したのは、1月24日。3台の発電機が3,000個の白熱電球に電力を供給した。
-
- 同年9月4日、ニューヨークのパール街の発電所が操業を開始し、6,000〜7,000個の電球を点灯するようになった。この事業は、直流発電による距離がわずか数100mという近距離であった。電力の送電の関係上、町の中心部に発電所を置いたため、この発電所は「中央発電所」と呼ばれた。発電機は16燭光電灯(71W相当)を1,400個つなげる発電機(100kW相当)が12台、この発電機を回すための蒸気機関は、2,000馬力のバブコック・ウィルコックス社のボイラー8台が投入されたといわれている。操業当時は、エジソン自らが監督して運営したが、はじめは故障ばかりだった。発電機が無事に一日中運転し続けることは奇跡に近く、当初、年間2万5000ドルと見積もられていた運営費用も実際は25万ドル(10倍)もかかってしまった。
-
- 1882年10月の電灯顧客は、59件、電灯数8,573灯であった。電気料金は、ガス灯の使用ガスに比べて安かったので、利用者も暫時増えていった。 直流送電は、発電所を中央に配置したにもかかわらず、末端にいけばいくほど電圧が落ちて暗い電灯になった。この問題は、直流の根本的な弱点であった(交流送電では、変圧という技術が使えるので、末端では希望する電圧に調整することができるのである)。やむを得ず、エジソンとホプキンソン(英国、John Hopkinson:1840 - 1903)は、それぞれ独立に「3線式」配電法を考え出すことで当座をしのいだ。三線式とは、中性点から線を引き出し、これと + 110Vの間、および-110Vの間に同程度の負荷(電灯)をかける方法である。そうすれば、中央の中性点にはわずかの電流しか流れず(後には + 側と-側の負荷の変動によって生じる差を補正するため小さな発電機をつけた)、しかも電圧は2倍の220Vが利用できる。発電電圧460Vをまずフィーダーで440Vに落とし、中性線と外側の幹線間を220Vとする方式がこれ以後エジソン社で推し進められた。
-
- ●遠距離送電
-
- 送電と呼べる本格的なものは、1882年、ミュンヘンで開かれた電気技術博覧会からである。会場から57km離れたミスバッハから出力2.5KW、電圧2,000Vの直流発電機によって送電実験が行われたのが最初とされている。この実験は、ドプレ(M. Marcel Deprez)が担当した。その会場には、発電機と同型の電動機(モータ)が設置され、この電動機によって高さ2.5mの人工滝が作られた。使用された導線は、直径4.5mmの電信用鋼線で、このときの送電効率は25%と非常に低く、発電された電力の75%は送電途中の電線を加熱して大気へ逃げ去った。その後、各地で直流発電機による長距離送電が試みられたが、送電ロスをいかに防ぐかが大きな課題として残った。 実際問題、遠距離送電に関する電力のロスはいかんともしがたいもので、1873年のウィーン万国博覧会でフランスの技術者フォンテーヌが1kmの送電実験をグラム発電機を使って行ったが、彼自身、長距離送電の可能性を信じていなかった。送電ロスは、電流の二乗に比例して増えるので、送電の際の電流はできるだけ低く抑えたかった。電流を低く抑えて同じ電力を送るためには、抵抗の少ない太い電線を使うか、電圧を高くしなければならない。 ロシアのピロッキーやドイツのジーメンスも長距離送電の問題を取り上げ、誤った見通しを立て否定的な立場をとった。 ピロッキーは、送電損失をなくすために、送電線は当時使われている電信線の600倍の断面積を持つ電線が必要と考えていたし、ジーメンスは、1876年にナイヤガラの滝の水力を発電に利用できることを見抜いたものの、50km離れた都市へ電力を送信するにはφ75mmという巨大な電線が必要であると見積もった。 ミュンヘンで行ったドプレの実験は、長距離送電の可能性を示唆していた。が、同時に問題点も指摘していた。送電損失である。ここにきて直流方式による限界が見えてきた。 直流方式では、発電機で発電した電圧をそのまま送電するしかない。送電効率を上げるには、高圧発電機を作らねばならないが、これには限界がある。また、高圧は取扱上で、とくに受電端での危険が伴う。これは、直流機器の本質に根ざすもので、これを克服するには、交流を使う以外に方法がなかった。
-
- ●交流発電機
-
- 交流は、直流と同じ時期に発案されていたが、エジソンらの電灯事業の前にはかすんでしまっていた。アーク灯が発明された当時、直流のアーク灯では電極が片ベリするため、1876年、ロシアのヤブロチコフが炭素電極を平行に並べてこれに交流電源を与えて放電を起こさせ、両電極を均一に消耗するように工夫した。この電気蝋燭(でんきろうそく)は1灯で約2時間照明でき、灯体には4〜6個の電極が接続されていて、一灯が消えると順に次の電気蝋燭が点灯するようになっていた。この電気蝋燭のために交流発電機が使われた。この電気蝋燭は結局すたれ、交流も一緒に忘れ去られてしまった。 この交流発電機に、再び命を吹き入れたのがイギリスの電気工学者フェランティ(Sebastian Ziani de Ferranti、1864-1930)である。彼は、早熟の青年で、17歳(1881年)で最初の発電機を作った。その直後より、交流機器の理論的設計に着手した。大英博物館での電気工学者の集まりに参加し、ここで多くの優れた技術者との知遇を得た。ジーメンスともここで会い、二人の共同作業はこの時から始まった。交流の発電機の改造に着手した彼は、画期的な発電機電機子(ロータ)を開発し交流15,000Vという高電圧を発生させた。
-
- この開発には、イギリスの科学者ケルビン卿の示唆を得たと言われている。仲間作りがうまかったのがフェランティだった。ちなみにケルビン卿は直流推進者だった。 フェランティ(Ferranti)のほかに、交流発電機を研究していた人たちは以下の通りである。
-
- 米国のウェスチングハウス(Westinghouse)、
- カップ(Kapp)、
- バーカー、
- モーディ(Mordey)、
- タベストのガンツ(GANZ)社、
- ゴードン。
- ●変圧器の開発
-
- 交流の一番の利点は、電圧を自由に変えられることである。
- この原理は、1831年、イギリスの物理化学者ファラディーの発見した誘導理論によるもので、コイルの巻線比を変えるだけで電圧を高くしたり低くしたりできる。
- 夢のような事が交流で可能なのである。

- 変圧機能がどうして便利かというと、電力を送電する際に、電圧を高くすると送電線の線径を小さくすることができ、送電ロスを少なくすることができるからである。送電を数KVの高圧で行い、発電と受電は適正な電圧で使用する。送電によって電圧が下がっても、最終的に希望する電圧を変圧器によって調整することが可能となる。
- 変圧器の初期のものは、電気通信用として開発され、ヤコブやリュームコイフが考えた誘導コイルであったといわれる。実用的に使われた変圧器は、ヤブロチコフの電気蝋燭の点火用として作られたもので、高圧電気を得るためにイギリス人モリスが1862年に考案したものだと言われている。
-
 1882年、フランスのゴラール(Lucien Gaulard)とイギリス人ギブス(John Gibbs)が、照明用・動力用の電気配分方式の特許の中で開磁路式変圧器を開発している。2,000Vの高圧送電を想定して開発された。彼らはこれを二次発電機と呼んだ(現在では変圧器と呼んでいるのだが、当時は電圧を変えて新しい電圧が生まれるので二次発電機 = Secondary Generatorと呼んだ)。
1882年、フランスのゴラール(Lucien Gaulard)とイギリス人ギブス(John Gibbs)が、照明用・動力用の電気配分方式の特許の中で開磁路式変圧器を開発している。2,000Vの高圧送電を想定して開発された。彼らはこれを二次発電機と呼んだ(現在では変圧器と呼んでいるのだが、当時は電圧を変えて新しい電圧が生まれるので二次発電機 = Secondary Generatorと呼んだ)。-
- この二次発電機は、翌年の1883年、ロンドンのメトロポリタン鉄道の停車場の照明用として採用されたという。エジソンの直流配電システムに対抗する最初のことであった。しかし、この二次発電機は、ノイズをまき散らすという弊害も生まれた。1885年、ロンドンのボンド街にあったグロスベナー画廊のオーナーが近所の建物オーナーと話し合って、二次発電機を使って1,200Vの環状母線を敷設して、各に直列につながれた変圧器で電圧を落とした電源を使おうと工事したところ、地域内の電話交換局がまったく機能しなくなり、全市に雑音が広がるという失敗があった。
-
- この変圧器の不具合を解消して、性能の良い二次発電機を作ったのが、ハンガリーのブダペストにあったGANZ(ガンツ)社であった。ガンツ社の技術者オットー・ブラッシーとジッパーノスキー(Zipernowsky)、マックス・デリーの3人は、イタリアのトリノで開かれた博覧会でゴラールとギブスの変圧器を見て、これに改良を施し現在の変圧器の原型を完成させた。GANZ社は、これらの変圧システムで1885年特許を申請し、このとき、従来から使われていた二次発電機という名前に代えて「トランスフォーマー(変圧器)」という言葉を採用した。 方やアメリカでは、変圧器の存在を知った米国のウェスチングハウス社は、ヨーロッパからジーメンスの発電機と数台のゴラールとギブスの変圧器を輸入した。これをもとに、1885年、ウェスチングハウスの工場の顧問スタンレー(William Stanley: 1858 - 1916)が、実用的な変圧器の製作に成功する。ウェスチングハウスは、これを使えば交流方式を実現できるとして、1886年にウェスチングハウス電機会社を創立したのである。
-
- この会社が、ニューヨーク - バッファロー間にアメリカで最初の交流による送電システムを完成させた。使われた交流発電機は、出力125kW、1000V、駆動蒸気機関の回転数250-280rpmであった。彼らは、そこで得られた電力を送電し最終的に使用電圧を50Vに落として使った。これはエジソンの電圧の半分であった。 上の写真は、ゴラールとギブスの変圧器である。(東京電力 電気の史料館 展示) ゴラールとギブスは、最初、開磁路型と呼ばれる一本の鉄棒に、一次巻き線と二次巻き線を巻き付ける変圧器を考案したが、効率が悪かった。上の変圧器は、閉磁路型と呼ばれるもので、丸い導線(磁路)の回りに一次巻き線と二次巻き線が巻かれている。
-
- ゴラールとギブスは開磁路型の変圧器の発明者であり、上のものは閉磁路型のようにも見受けられる。 閉磁路型は、GANZ社のエンジニアが開発したもので、現在の変圧器の原型をなしているものであるから、この写真の正しいところは追って更新したい (2004.01.11)。 開磁路型の変圧器は、電気を通した時に発生する磁束が磁気抵抗の大きい空気中を通らねばならないので、磁力が発散し大きな起磁力を必要とする。閉磁路型のように磁束が閉じ込められた系で変圧器を作ると、鉄芯の中を磁束が通るため効率が良くなる。この方法を採ったGANZ社の変圧器によって電圧変換効率が格段に向上した。GANZ社ではまた、各装置に接続される変圧器が従来直列であったのを並列接続とした。直列接続では(豆電球を直列に接続して実験をされたことがある人は簡単に理解できるかと思うが)、負荷(装置)の変動により連なった負荷に直接影響を与えてしまう。並列接続ではそのような不具合が起きない。そして並列接続と同時に発電所から送られてくる電圧を高めに設定して、負荷側で希望する電圧に変換できるようにし、負荷側の要求する電圧設定が可能にした。こうした配電システムを構築して1885年に特許を申請したのである。(この時、採用した変圧器の名前がトランスフォーマーであった。)ガンツ方式は、1885年、ブダペストで開かれたハンガリー博覧会の照明方式として具体的に採用され博覧会の目玉として注目を集めた。このイベントが評判になって、ローマ市のガス照明事業会社が1889年にこの方式を採用し、中央発電所で2,000Vの発電を行ってローマ市にある変電所に配電し電気照明システムを完成させた。このようにしてヨーロッパでは高圧送電の基礎が出来上がって、1890年の5年間の間に60余りの都市で交流電化事業が始められた。
-
-
-
- ●交流送電
-
- 交流発電による送電は、1889年、イギリスロンドン近郊デッドフォード(Deptford)にあるグロスビエナ(Grosvenor)発電所で実施された。当時の発電は、1250馬力(約938kW)のコーリス(George Henry Corliss : 1817-1888) 蒸気機関を使って、これに出力1,000KW、電圧5KVの交流発電機2基(フェランティ製)を接続して運転された。発電周波数は83Hzで、変圧器により10,000Vに昇圧して送電し、受電端で2,500Vと100Vに2段階減圧して、電灯負荷に電気を供給することに成功した。
-
- この立ち上げにイギリス人電気工学者フェランティ(Sebastian Ziani de Ferranti、1864-1930)が活躍する。フェランティはもともと高電圧送電の推進者であった。遡ること1885年、ゴラール(Lucien Gaulard)とギブス(John Gibbs)の変圧器を使用していたグロスビエナ発電所で事故が起きた。フェランティが修理のために招かれ、翌年から技術主任に迎えられた。彼が25歳の時である。ロンドン配電会社(London Electric Supply Corporation = LESCo)は、100万ポンドの資金を使って大規模な発電所の建設を計画した。これが先に述べた1889年の新生グロスビエナ発電所であった。当時は変圧器も何もかもようやく手が着けられはじめたばかりで、ケーブルも2,500V以上のものは作れなかった。フェランティは、変圧器からケーブル、発電機に至るまで次々と高圧に耐える装置を開発していった。
-
-
-
-
-
- 1-3-3. 三相交流の萌芽
-
 1891年、ドイツのフランクフルト・アム・マイマンで開催された国際電気技術博覧会で、ネッカー河から博覧会会場までの170km区間を三相交流発電機により、15kVで送電する実験に成功し、交流送電の実用化が見えてきた。この実験を行ったのは、ドイツA.E.G.社のドリヴォ・ドブロウォルスキー(Michael von Dolivo - Dobrowolski: 1862-1919)だった。
1891年、ドイツのフランクフルト・アム・マイマンで開催された国際電気技術博覧会で、ネッカー河から博覧会会場までの170km区間を三相交流発電機により、15kVで送電する実験に成功し、交流送電の実用化が見えてきた。この実験を行ったのは、ドイツA.E.G.社のドリヴォ・ドブロウォルスキー(Michael von Dolivo - Dobrowolski: 1862-1919)だった。-
- 交流送電と直流送電論争の布陣は以下の通り;
-
- 交流: アメリカのウェスチングハウス、テスラ、スプレーグ、
- C.P.スタインメッツ、イギリスのフェランティ、ゴードン、
- 発電機設計の権威S.P.トムソン、モーディ。
-
- 直流: イギリスのケルヴィン卿、クロプトン、A.B.W.ケネディ、
- ジョン・ホプキンソン、アメリカのエジソン。
-
- そうそうたる有識者たちの布陣による直流・交流の是非論争が激しく続いた。
- 特に、エジソンの交流送電方式の罵倒、非難は尋常ではなく憎悪に近かった。それは、彼が白熱電球を発明し、直流発電機を開発して送電からランプに至る一切の利権を自らの陣営に引き込もうとする野望が見え隠れしていた。彼は、この論争にかなり深入りしたために発明家としての名誉を著しく傷つけることにもなる。
- 【エジソン陣営の攻撃例】
エジソン陣営は、国に死刑執行をする際に交流電気を使うことを提唱。その装置には、ライバルであるウェスチングハウス社の交流機器を購入するように画策した(1889年)。その上で、エジソン陣営は、死刑執行に使われる交流電気は危険きわまりないと吹聴し、交流への法規制を要求した。
また、ウェストオレンジのエジソン研究所に新聞記者や客を招き、エジソンとバチェラーが1,000Vの交流発電機にブリキ板をつなぎ、ネコやイヌを近づけて殺し、「交流の危険性」を宣伝した。
- 「新版 電気の技術史」、山崎俊雄、木元忠昭 共著、オーム社 1992年12月18日初版
エジソン社には多相交流発電機や多相交流電動機の開発で知られるテスラという優秀な交流電気の技術者がいた。彼はユーゴスラビア生まれでプラハ大学を卒業した。勤勉で、大学時代は朝3時から夜11時まで勉強し、エジソン社時代は9ヶ月間朝10時から翌朝5時まで働いたという人物であった。そうした優秀なスタッフを抱えていたエジソン陣営であったので交流部門への進出は容易にできたはずであった。
しかし、エジソンの頑迷さはそれを許さず、そのためにテスラはエジソン社を辞して、ライバルであるウェスチングハウス社に2相交流方式の特許を売り渡すことになる。
ウェスチングハウス社は、テスラの特許をもとに二相交流発電機を製作した。
1893年、シカゴ博覧会で採用された照明装置の送電は、ウェスチングハウスに任された。この発電機に、テスラの二相交流発電機が採用された。1896年、同社はナイアガラの瀑布を利用した大規模な交流式水力発電所に、二相交流発電機を12台設置し、それぞれ4,000kW、5,000Vで発電し、11KVに昇圧して40km離れたバッファロー市へ送電した。バッファロー市は、この電気の供給を受け、冶金工業、アルミニウム電解工業、カーボランダムなどの電気化学工業が発展する。この発電・送電システムには、13件の特許が使われたそうであるが、その中の9件はテスラが発明したものであった。
技術的にも経営的にも硬直化したエジソン社は、同社を金融面から支援していたモルガン資本によって、交流方式を進めていたトムソン・ハウストン( = ヒューストン)社と合併を余儀なくされた。こうしてできあがった会社が、ゼネラル・エレクトリック社(GE)であり、同社は、電力部門で交直両方式を備えることになった。GE社の躍進は、いまさら語るまでのないくらい大会社になった(最近[2000年]は、物づくりよりも資本を利用して金融面で事業を展開している感を受ける)。
ともあれ、エジソンはこのプロジェクトに敗れ、ウェスチングハウス社は、発電プラントの大会社となった。
こうして、アメリカでは、エジソン、トムソン、スプレーグ、ブラッシュ、ヴァンテンポール、ブラドレーなどが持つ特許をはじめ、数百の特許を支配するGE(General Electric)社と、マックス、ソーセー、マン、ファーマー、ウエストン、テスラ、スタンレーなどの特許を持つWH(ウェスチングハウス)社の二大独占体制が成立することになる。
- 【エジソンの敗北】
- エジソンは過去の名誉や栄光を捨て、発電の利権で争い致命的な敗北を負う。かってのように眠る時間さえ惜しんで新しいものに挑戦し、発明を続ける姿勢はなかった。
- 発明家精神を投げ捨てて、頑強に「新しい技術」として抵抗した裏には、経済的問題が絡んでいた。たしかに複雑な交流現象は、数学教育を受けなかったエジソンにとっては理解が困難ではあったが、交流に反対した理由の主なものは、これまで営々と築いてきた直流発電所システムがすべて無駄、すなわち投下資本が無に帰する危険にさらされたからである。
- - 「新版 電気の技術史」、山崎俊雄、木元忠昭 共著、オーム社 1992年12月18日初版
-
-
- 【ニコラ・テスラ、Nikola Tesla 1856 - 1943】
 ニコラ・テスラは、1856年、ユーゴスラビア(現クロアチア共和国クライナ地方Smiljan)に生まれる。父親はセルビア教会の牧師で知識人であったという。テスラは、幼少より神童として数学の素養が高かった。
ニコラ・テスラは、1856年、ユーゴスラビア(現クロアチア共和国クライナ地方Smiljan)に生まれる。父親はセルビア教会の牧師で知識人であったという。テスラは、幼少より神童として数学の素養が高かった。- 高校を卒業した後、病気と放浪生活を数年送り、オーストリアのグラーツ工科大学に入った。そこで、グラムの直流電動機を見て、その電動機が逆転する際に整流子から発する火花から効率の悪さを見抜き、交流電動機を着想する。
- 回転磁界を取り入れた彼の誘導モータの原型は、大学を卒業してブタペストの国営電話局に技師として勤務していた時に出来上がる。
- 彼は当時、神経障害を患っていた時があり、その時、ひらめきが走ったと回想している。
- 病気回復後、友人と公園を散歩している時に回転磁界、多層交流の設計図が頭の中に出来上がったと言う。
- その後、1882年、テスラはエジソン社のヨーロッパ事業所(パリ)に職を得て交流の理論に磨きをかけるようになるが、直流発電と送電を主事業としているエジソン社での彼は異端であった。
- それでも、彼はいつかエジソン社が交流発電、送電事業を始めると期待していたようだ。
- 1884年、単身海を渡ってアメリカのエジソン社に勤めるようになる。彼は、彼なりに交流事業を本格的に進めるために米国へ渡るのであったが、エジソン社は、聡明な彼に直流モータの改良発展の仕事をさせたかったようだ。思惑の違う両者が歩み寄れるはずがなく、特に、エジソンの頑固とも言えるべき直流事業の推進に失望し(エジソンは、すでにその事業のために大量の資本を注ぎ込んでいた)、エジソン社を去ることになる。
- エジソン社を退職したテスラは、出資者を得てアーク灯製造会社を設立し、交流システム事業の機会をうかがっていたが、不況の波に押されて倒産してしまう。
- テスラは、1年間の日雇い生活の後、新しいパートナーを得て、交流電動機を始めとする交流システムの研究所をマンハッタンに設立した。彼は、そこで彼の理論にもどづくシステムの特許を取得して行く。
- 彼の仕事に注目した米国電気工学者協会(AIEE)は、彼を招いて講演会を開いた。
- こうした活動を経て、ウェスチングハウス社の創業者で発明家であるジョージ・ウェスチングハウス(George Westinghouse)の目に止まった。エジソン社と激しくシステム受注の競争をして交流システムに注目していた同社は、テスラとテスラの特許を巨額の金で買い取った。
- エジソン社とウェスチングハウス社の誹謗を織りまぜた競争は凄まじい展開を見せたが、1893年、シカゴ博覧会で採用された照明装置の送電には、ウェスチングハウスが受注し、この発電機にテスラの二相交流発電機が採用された。
- 1896年、同社はナイアガラの瀑布を利用した大規模な交流式水力発電所に、二相交流発電機を12台設置し、40km離れたバッファロー市へ送電した。
- この実績をもとに、送電事業、電動機は交流が普及して行った。
- 電気の単位で磁束密度を表すテスラ(T)は、彼の業績をたたえてつけられたものである。
- テスラは、交流システムで一時代を切り開いた発明家であるが、この発明以外にも、無線の発明としても良く知られている。
- もっとも、無線はマルコーニが事業としてテスラよりも早く立ち上げたため、その恩恵には預からなかった。
- 彼の晩年は芳しくない。
- 交流システムで名を馳せた後、研究を無線理論に向けた。
- 無線事業は、多額な事業費とリスクを負った。無線事業のスポンサーが途絶えた後の彼は空想的になっていき、パートナーから見放され、窮乏生活を余儀無くされた。
- 彼は生涯独身を通し、1943年にニューヨークのホテルの一室で一人寂しく息を引き取った。87才であった。
-
- 【Westinghouse Electric Corporation】
 Westinghouse社は、George Westinghouse(ジョージ・ウェスチングハウス:1846 - 1914)が1886年に設立した米国の電機会社。
Westinghouse社は、George Westinghouse(ジョージ・ウェスチングハウス:1846 - 1914)が1886年に設立した米国の電機会社。- ジョージ・ウェスチングハウスは発明家でもあり、鉄道のブレーキ装置を発明し、Westinghouse Air Brake Companyを経営していた。
- ウェスチングハウスは、ニコラ・テスラの交流システムのパテントを買い取り、電気照明事業を始めるべく、マサチューセッツ州Great Barringtonに会社を起こした。
- ウェスチングハウス社は、電力の長距離伝送と高圧伝送のパイオニアで、彼の会社には、William Stanley、Nikola Tesla、Oliver Schallenbergerなどの天才技術者が集まり、GE社と歴史的なライバル関係を続けて行った。
-
- 同社は、1999年にバイアコム社に買収され、2006年から東芝の傘下に入った。
- ウェスチングハウス社は、原子力発電に秀でた技術を持っていた。
-
- 私が大学3年生の夏(1977年)、夏季実習の一環として4単位取得のため、3週間兵庫県高砂市にある三菱重工業高砂製作所に実習に行った。
- この事業所は、発電プラントのタービンを製作している有名な事業所だった。
- ここで、生まれて初めてWestinghouseという会社を知った。
- 三菱は、米国Westinghouseと技術提携して、水力発電に使用するタービンなどの技術供与を同社から受けていた。
-
- さて、直流送電と交流送電方式であるが、開発当初は直流送電の方が技術的に有利といわれていた。
- 交流送電は、電圧と電流が時間的に変化し変化する際のエネルギーロスが多いためである。
- 直流電源は、絶えず一定に送ることができ交番電力による送電ロスが少ない。
- 日本の電力研究所でも、送電時のロスは無視できないとして、高圧送電の研究を進める傍ら高圧直流送電の研究を進めている。
- しかし、発電のそもそもの原理は交流であり、直流発電機では電気の流れを一定にするために直流ブラシ(整流ブラシ)を用いなければならない。
- このブラシは、電気的負荷がかかり消耗が激しかった。
- また、送電する際に同じ電力を送る場合、電圧をできるだけ高くした方が流す電流が少なくてすみ、送電線の線径を小さくすることができる。
-
- こうした送電の際の電圧を上げたり下げたりすることは、交流の方がいともたやすくできる。
- また、交流発電でできた電源は、最終ユーザ(工場)でモータを介して動力として用いられ、大型の電動機(モータ)は交流モータが多く交流方式が普及する原因となった。
- 送電ロスというデメリットはあるものの、総じて交流発電と交流送電の利点は高かったといえる。
-
- 電気利用の多くは、
-
- 1. 照明(光)と、
- 2. 熱エネルギー(熱)、それに
- 3. 回転機械であるモータ(動力)
-
- である。
- 最近では、上の三つに、テレビ、ラジオ、インターネットに見られる通信が加わる。
- 1800年代後半の電動機が登場した頃は、直流モータが主流であったが、ドイツAEG社のドリヴォ・ドブロウォルスキーの三相交流が確立してからは交流モータが主流になった。三相交流電源は、モータを回すのにとても都合が良いものであった。
-
- 【現代のモータ事情】
- 1970年までの動力として使われたモータは、交流モータが一般的であったため、交流周波数がモータの回転数を決定していた。モータの回転数を変えるにはギアで行うか、さもなくば直流モータを使って電圧を制御してモータの回転を制御していた。
- 直流モータは、電車は別として、大型モータとしては普及しなかった。直流モータは、回転によって電気の流れを変える必要上、電気ブラシ(整流ブラシ)が必要であったが、これの消耗が激しくメンテナンスを強いられた。また回転制御も交流モータより複雑であった。
- そんな直流モータ(直巻直流モータ)が電車に使われた理由は、車両が非常に重く起動のための力(トルク)が必要で、これには直流モータが優れていて且つ回転が一定になると電気を食わないという電車にとってまことに都合の良い特徴があるためであった。
-
- ● 電気機関車の電力事情
- 日本の鉄道の電化は、1,500Vの直流電化で始まった。
- 発電所から交流を受けて線路の電化区間を変電設備によって直流に直して直流モータで機関車を走らせた。
- 電気機関車は直流が基本、というとそうでもない事例がある。
- フランスである。
- フランス国鉄の交流電化への取り組みは、なかなか見事だそうである。交流電化といっても交流モータを使うわけではない。駆動モータはあくまでも直流モータである。
- ではどこで交流を直流に直すのか?
- その答えは、機関車の中である。交流の利点は、送電電圧を比較的楽に変えられ、高圧送電は電力ロスが少なくてすむ。この利点を生かして、鉄道架線には高圧交流を送電し、パンタグラフで交流を集電する。集電した交流を、機関車内部に設置した変電設備で希望する電圧に落とし、かつ整流して直流としてモーターに加える。
- フランスはこれをやった。
- 我が国は、交流電化を採用するにあたって、東海道本線のような多量の車両が走る区間は、機関車が簡単な構造の(変電設備を機関車にもたない)直流電化を採用し、走る車両の数が中程度と想定された東北、北陸、鹿児島本線級の区間は交流電化とした。
- さらに支線のようにわずかの車両しか走らない区間では、電化の設備が運営に見合わないためディーゼル機関車とした。
- しかし、現実には複雑な電化のために、いろいろなしわ寄せが機関車や電車につきまとった。たとえば、本州の下関までは直流機関車で走れるのに、関門トンネルを越えると門司からは交流電気機関車でないと走れなくなる。
- 同じように上野から出発した常磐線は、取手から交流電化となるため、こうした区間では交直両用電気機関車が使われた。
- 日本の幹線区間では、直流電化がなされていたが、東海道新幹線を開通するに当たっては交流電化が採用された。その理由は、新幹線は高速で走るためパンタグラフから取り入れる電流はできるだけ少なくし、パンタグラフと架線の消耗を少なくする必要から高圧が必要であったためである。
- 高電圧、小電流の必要上、新幹線には25,000VACの電化がなされ、電車内部で直流に直し直流モータで運転された。
-
- 直流モータは、新幹線0系列車に採用されていたが、300系の「のぞみ」からは交流誘導モータに変わった。
- 電車内部で、モータに加える周波数や電圧を自由に変えられる技術(VVVF = Varialbe Voltage and Variable Frequency、可変電圧可変周波数制御)が確立したため、従来の直流モータの問題であった保守の手間と大消費電力を解消した。
- 今後、電車には、インバータ式ACモータ(交流モータ)が主流になっていくものと思われる。
-
- 1980年代からは、パワーエレクトロニクスが急速に発達し、モータ側で周波数を変換する電源が確保できるようになり、周波数を任意に変えながらモータを回す(AC)インバータモータが普及してきた。
- このモータは、最近では、エアコン、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気掃除機など家庭電化製品にも使われだして来ている。
- 古いタイプのエアコンや電気冷蔵庫は、コンプレッサを回すのにACモータを使用し、温度が一定になるとモータの電源を切り設定温度以上になるとスイッチがONになるようになっていた。この方法だと、モータが回るか止まるかの2種類の選択しかできない。
- インバータモータは、周波数が連続して変えられ、モータがその周波数で回るので常時最適な出力をモータに与えることができる。
- エアコンで言えば、そよ風から強い風まで任意の風を任意の温度で送ることができる。
- 冷蔵庫やエアコンに使われるコンプレッサモータも、任意に回転することができるため、静かで効率の良い運転が可能となる。
-
- ● 電気機関車のモータ制御
- 電気機関車に限らず全てのモータに言えることであるが、モータを回転させる際に、単にモータの入力端子間に電圧を加えただけでは危険である。始動には十分な配慮が必要である。電気機関車のような高電圧で大出力を得るモータに、始動抵抗もなく一度に高い電圧をかけたらどのようなことになるか。結論から言えば、まずドカンと大きな音がして車輪が空転し、歯車の歯が折れて飛び散り、モータが火を吹いてパンタグラフの接合部で架線が溶け、機関車も火を吹き出す危険性をはらんでいる。もっとも電気機関車自体には、電気回路を切る遮断機が装備されているため、ドカンという音だけですむはずである。
- 電気機関車を動かすモータの制御装置は、機関車がスムーズに列車を引いて走るようモータにどれだけの電圧と電流をかければよいかを調整する装置である。この装置は、半導体のない昔の時代と半導体の発達による大進歩をした時代とでは構造が大きく異なり、また、直流電気機関車と交流電気機関車によっても、全く異なった構造、機能を持っている。
-
-
- 【直流電化のモータ制御】
- 電気機関車の場合、制御されるモータは、直流モータで1,500Vの架線電圧が2個のモータに最終的にかかるようになっている。つまり、2個のモータが直列に接続され、1,500Vの電圧が半分づつ割り当てられるので、モータはそれぞれが750V用として作られている。
- 旧形式の6個のモータを使った機関車では、モータの結線を走り方に応じて変えている。スタート時には6個のモータを全て直列に接続される。こうすることにより、架線から入る電圧、1500Vの6分の1の250Vが一つのモータにかかる電圧となり、電圧を抑えることができるようになっている。しかし、それでもなお250Vを一度にかけると電流が流れすぎてドカンということになるので、始動電流を抑えるために直列接続したモータに対して直列に抵抗器に入れ、モータにせいぜい数十ボルト程度の電圧がかかるようにして動き始める。
- 機関車の速度が上がってゆくにつれ、抵抗器は順次接触器を短絡させて(徐々に抵抗値を下げ)モータにかかる電圧を上げていく。直列最終段に達すると(すなわち1個のモータに加わる電圧が250Vになると)、モータは、直列と並列の配線を組み替えて(3個のモータを直列、それを2組作ってその組を並列に接続する。1個のモータに加わる最大電圧500Vとなる)、再度抵抗を入れて電圧を上昇させる。電気機関車の速度が増してきたら並列に接続させて(2個のモータを直列にして3組作りその組を並列に接続して)750Vがモータにかかるようにする。これが抵抗制御式の制御装置の基本となっている。
- モータに加える電圧を任意に調節できなかった時代には、モータの接続や大型抵抗器(もちろんかなりの熱を発生する)を使ってモータを制御していた。
- 交流電化が発足した当時は、性能の良い高電圧大電流制御ができる半導体素子がなかった時代であった。架線から来る二万ボルトの電気を直接モータにかけるのにはあまりにも高圧すぎる。そこで変圧器側で多数のタップを用意し電圧を変換し極低圧から直流電気機関車と同じ750Vまで取り出せるようにした。しかし、変圧器からでてくる電気はまだ交流で、直流モータを動かすことはできない。そこで初期のころの電気機関車には水銀整流器と呼ばれる水銀を封じ込んだチューブ状の(たこの頭のような形をした)、大型でかつ旧式の整流器を搭載して、それで直流に直して直流モータを駆動させていた。水銀整流器(mercury arc rectifier)は、水銀アークの弁作用(電流を一定に流す作用)を利用して整流を行わせるもので、主体の水銀整流管にはガラス製のものと鉄製のものがありガラス製は500Aまでの小容量、鉄製のものでは数千Aの大容量のものが製作された。
- その後、半導体を使って、単に一方向にだけ電流を流すことのできるシリコン整流器が作られ、水銀整流器はシリコン整流器に代わって行った。
- 交流を使う電気機関車のモータでは、先に述べた直流電気機関車のような直列、直並列、並列にモータを接続して運転の制御を行うことはしていない。
- 【交流電化のモータ制御】
- 交流電源を使って、直流モータを動かすには二通りの方法がある。
- まず一つめは、変圧器の出力側に数多くのタップを出して、何段階もの電圧を出せるようにし、速度に応じた電圧をモータにかける方法である。
- 二つめは、位相制御と呼ばれる制御方法である。これは、交流の電圧がサイン波状に変わるので、波形のどの位置で電流を流し始めるかを制御して、小さな電流から大きな電流まで流す方法である。
-
しかし、タップによる制御でも、位相制御でも、電圧は凸凹状(サイン状)となっている。ましてや、位相制御を採用した時には、電圧はまるでノコギリの歯のような波形になって、ひどい脈流電流が流れる。極度の脈流電流は、電気品に損失を増大させ、音が出たり、時には周辺に電磁波を放出し、ノイズとして周辺の制御回路に影響を与える。この問題を解決するために、回路の途中に主平滑リアクトルと呼ばれるコイル状の装置を入れる。すると、モータ自体とこの主平滑リアクトルの持つリアクタンスと呼ばれる電流の急変を妨げる作用が働き、電流は急激には変化しにくくなり、滑らかなものとなる。
半導体技術の急速な進歩によって、電流をただ一方向に流すだけでなく、指令をだすと一方向に流す機能を持つサイリスタと呼ばれるシリコン素子の開発が行われ、電流制御に大きな役割を果たしている。サイリスタとは、3極真空管のサイラトロンからつけられた名前で、ゲート信号で電流を流したり止めたりする働きを持つものである。1958年、米国GE社が、p型半導体とn型半導体をそれぞれ4層以上重ね合わせて作ったSCR(Silicon Controlled Rectifier)と呼ばれる半導体スイッチング素子を開発した。この素子がそれまでの3極真空管サイラトロンに極めて似ていたことからサイリスタ(Thyristor)という言葉が生まれた。このサイリスタは小さいので、寸法的に制限のある鉄道車両では好都合であった。サイリスタを利用した電気機関車の代表には、ED77、ED78、EF71などがある。
サイリスタ制御が発達してくると、さらに、チョッパー制御装置ができるようになった。この方式は、E電の中央線などで走っているモハ201系の電車に使われている。これは、直流を一定の周波数で流したり切ったりし、一回の通電中の時間を変化させて、直流モータにいろいろな電圧をかけることができるものである。この手法は現在のスイッチングレギュレータ(AC100VからDC電源を作るときに採用されている回路)にも幅広く使われている。
このようなサイリスタからさらに進歩した半導体技術で、GTO(Gate Turn Off)サイリスタと呼ばれる素子が作られている。通常のサイリスタがいったんONになると陽極電圧をゼロにしてやるか、ゼロ近くにして保持電流以下にしてやらなとオフにならないが、GTOは素子のゲート電極にマイナス電圧を加えるだけでTurn Offさせることができる。非常に制御性のよい素子である。これを使って、直流から、周波数を自由に変えられる三相交流電気を使うことも可能になってきた。将来の機関車には三相モータを使った機関車も出てくるものと考えられる。
- 参考: 『電気機関車をつくる』斎間 亨(さいま とおる)、ちくまプリマーブックス43、筑摩書房 -
- 【ハイブリッドカー プリウス(トヨタ)に使われている電気モータ】(2001.07.09)(2001.07.15)(2019.01.05追記)
- プリウスが世に出たのは、1997年12月。ガソリンエンジンと電気モータを両方載せ、互いの良いところを取って燃費向上(省エネルギー)につなげた。
- プリウスは、発売以来3年で30,000台を売っている。プリウスが成功したのはパッケージングの良さ(使いやすさ、乗りやすさ)と言われている。価格も、赤字覚悟で低価格(215万円)に設定しユーザに乗る気を促した。それだけ、トヨタが次世代に対するクルマ作りの姿勢を世に問うたとも言える。
- プリウス(ハイブリッドカー)の基本的な考え方は、クルマの発進時を電気モータで行い、加速時、高速走行時はエンジンを併用する。さらに減速時にはモーターを回生制動によって(つまりモーターを発電機に変え)発電した電気を蓄電し、エネルギーを有効に利用しロスを極力抑える設計となっている。
-
- 初代プリウスのパワーユニット:
- ■ エンジン
- ・水冷直列4気筒DOHC。ミラーサイクルエンジン、EFI(Electronic Fuel Injection)
- ・排気量: 1500cc
- ・馬力: 58馬力(42.63kW)/4,000回
- ・トルク: 10.4kg・m
- ・燃費: 28km/リットル
- ・排ガス規制: 53年規制ガス値の1/10を実現。CO2排出量は同クラスの1/2の排出量を達成
-
- ■ 電動モータ
- ・形式: 交流同期式(交流モータ)
- ・出力: 30.0kW(40.8馬力)
- ・トルク: 31.1kg・m
- ・電池:ニッケル水素。40個直列。280ボルト
-
- トルク(車の発進時、加速時に威力を発揮する力)は電動モータの方が3倍強く、馬力(高速で走る場合に必要とする力)はエンジンの方が高い諸元となっている。
-
- ■ エンジン
- プリウスでは、クルマの発進時はトルクが大きい電動モータを使っている。実際のガソリンエンジンやディーゼルエンジンは、クルマの発進時黒い煙とともに発進するため、かなり汚れた排ガスが大気に出される。黒い煙は、燃料から遊離した炭素(カーボン)で、本来ならそのカーボンがエンジン燃焼室内で酸素と結びついて二酸化炭素を作り、この化学反応で膨張ガスを作ってその膨張エネルギーでエンジン内のピストンを押し下げて力を出すはずのものである。カーボン(黒煙)が出るというのは、完全に燃焼していない証拠であり燃費の悪さにもつながっている。車が発進するときは、燃料(ガソリン)を多く使ってエンジンの回転を高めて加速をするのだが、車が重いためエンジン内では思うような燃焼ができずに回転が上がってくれない。燃焼が理想の形で行われないのである。
- プリウスでは、発進時に電気モータを使うことで(アシストすることで)こうした排ガスや燃費の悪さを排除している。エンジンは、常時一定回転、低負荷で運転させ排ガスや燃費の向上を狙っている。なおかつ、プリウスのエンジンは、ミラーサイクルエンジンと呼ばれるタイプのエンジンを搭載させ、エンジンそのものにも燃費を改善させている。
- ミラーサイクルエンジンとは、エンジンの燃焼サイクルでピストンが圧縮をする際の圧縮行程で圧縮のタイミングを遅らせて(燃焼室内に蓋をする働きを持つ吸気バルブの閉じるタイミングを遅らせて、圧縮に入る時期を遅らせ)圧縮容積を小さくし、膨張行程の容積との変化を持たせる方式のエンジンことである。通常のエンジンでは、ピストンの上下する行程は同じ距離であるため、吸気と排気の容積は同じになる。ミラーサイクルエンジンでは、吸気タイミングで吸気バルブを閉じるのを遅らせて見かけ上の吸気容積を小さくさせている。圧縮行程では、ピストンがシリンダー内に入った空気を押し上げるため、ここでエネルギーの損失が起きる。爆発行程では燃焼ガスがピストンを押し下げてその力により出力を取り出すことができるが、ピストンが下死点(最下点)に到達するとそれ以上ピストンは下がらないから、燃焼ガスにピストンを押し下げる力があってもガスは排出されざるを得ない。ミラーサイクルエンジンでは、このジレンマを吸気行程の容積を小さくして見かけ上の膨張行程容積を大きくしエネルギーを効率よく回収しようという発想からきている。
- このアイデアでは、瞬発力のあるエンジンとはならずマイルドなエンジンになるが、エネルギー効率はよくなる。瞬発力を出すためにミラーエンジンに空気をたくさん送り込む過給器を取り付けたエンジンも作り出されている。
- プリウスのエンジンでは、エンジンそのものに幅広い出力やエンジン回転数を要求しないために、常時4,000回転/分で回るエンジンとしてエンジン強度や各部品を見直して、軽量化と高効率化を図ったという。
-
- ■ ミラーサイクル(アトキンソンサイクル)エンジン
- ミラーサイクルエンジンの原型は、英国ジェームズ・アトキンソン(James Atokinson)が提唱した熱サイクルシステムに始まる。
- このエンジンの特徴は、機構的に燃料を着火爆発させる圧縮行程と膨張行程が独立して設定できる機構を持たせている。
- このアイデアを米国人ミラー(R.H.Miller)がより実用化に近づけ、吸気バルブの開閉時期の調整する機構を開発し、これを実現するシステム(ミラーサイクル)としてミラーエンジンの名前で知られるようになった。
- このエンジンは、熱効率が高くエネルギーを有効に使えるという特徴を持っている反面、高出力が得にくいという欠点を持っている。
- 従って、ミラーエンジンの多くは、過給機(ターボチャージャーやリショルム)と組合わせて市販されている。
- プリウスの場合は、エンジンには発進、加速などの力を要求せず電動モータがメインで動作するから、過給器をつけない(過給器の代わりが電動モータ)標準のミラーサイクルエンジンでの利用価値は高いと言える。
-
- その結果、プリウスは極めて静かなクルマとなった。交差点などで停止する毎にエンジンが切れ、室内は全く静寂に包まれ、発進する際は電動モータが駆動して静粛に、かつスムーズにスタートする。加速は、1500ccクラスのカローラと比べて遜色なく、むしろ良いくらいだそうである。燃費は、都内で何不自由なく乗り回して、17km/hを記録したと言う。通常のクルマの2倍以上の燃費である。
-
- ■ 電動モーター
- プリウスに使われている電気モータは、交流同期モータ(交流永久磁石式同期型モータ)を使用している。
- トヨタがプリウスのために内製したモータだそうである。
- このモータは、ACサーボモータというものである。このモータは、現在主流になりつつある可変周波数技術と強磁性体材料による交流モータのことで、任意の回転速度で力強いトルクが得られる。
- 電車のモータも最近はACモータが使われだしてきている。
- ACモータは、元来、ステータとロータに すべりというものがあって始動トルクは低かった。交流誘導モータでは、ロータは界磁せずにステータの界磁でつられるようにして回る(誘導される)ので、始動時は強く回らないのである。
- 反面、直流モータはステータとロータに強い界磁があるので強い力が働く。特に永久磁石を使ったモータではすべりがないため始動時のトルクが高い。従来はこうした観点から始動時のトルクが欲しい応用では直流モータが使われてきたが、最近になって、周波数が任意に変えられる電源装置が作られたことと、ブラシを使わなくてもスイッチング電源で任意タイミングで電流をロータに流せるようになったことから、直流モータと交流モータの両方の良さを兼ね備えたACサーボモータが普及してきた。このモータは価格は高いけれど、制御性、始動性、保守性が良好なためにパワーエレクトロニクス分野で急速な発展を見ている。
- プリウスではこのACサーボモータに加え、このモータを任意に動かすための周波数変換装置(インバータ) = IGBT(Insulated Gated Bipolar Transistor)を開発した。IGBTは弁当箱ほどの大きさで、その中にモータ、発電機用にそれぞれ6個のパワートランジスタが入っていてこのトランジスタのスイッチングにより任意の電流をモータ及び発電機に配電する。
- このIGBTの開発は、自らの発熱と信頼性の飽くなき戦いだったと言われている。
-
- ■ バッテリー
- プリウスには、ニッケル水素電池が240個直列につなげられている。この電池で288Vを発生しモータに電力を供給する。モータは30kWの出力を発生するので、効率を考えなくても110Aの電気がモータに流れ込むことになる。効率(0.8程度)を考慮すると入力電流は140Aを超えるのではないか?このような大電流を流す電気回路および付帯設備をコンパクトにまとめるのは大変だろうと想像する。しかも、エンジンから発電される電気も288V以上にしなければならない。そうしなければバッテリに充電できないからである。
-
- トヨタが採用したニッケル水素電池の一つのセルは、単一乾電池と同じ大きさで1.2Vを起電する。単一乾電池ほどの大きさのセルを6個直列につないで1モジュール(7.2V)としてこれを20モジュール直列につないで(120セル、144V)、これを2セット用意し(240セル、288V)、1パック構成となっている。
-
- 288個のセルが均一に大電流の放電と充電を繰り返し、しかも劣悪な使用環境を考えるとバッテリの開発は並大抵ではなかったと思う。
-
- 彼らは、バッテリの開発を進めるうち大きな発見を行う。バッテリの高寿命化、フラットな性能特性(品質)に悩ましていたとき、セルの充電を満杯にせず、また放電も使い切るまでにせずに充電状態をある範囲に収める使い方をすると、セルの容量のバラツキが極めて小さくなることを発見したのである。
-
- 数あるブレークスルーを持ったプリウスであるが、電池の開発もプリウスの次代の価値を高める一つとなっている。
-
-
-
- 【新型プリウス】 (2004.01.12)
- 2003年9月に発売された2第目プリウスは、初代よりも動力性能が増しているという。
- 試乗もしていなくて述べることは気が引けるが、電気的な面で変更された点は、以下の通りである。
- 1. 電源が274Vから500Vに上がり、電動モータがパワフルになった。
- 500Vになったのは昇圧回路であって、バッテリそのものではない。
- 2. モータの出力を1.5倍に向上。軽量化による駆動レスポンスを向上させた。
- 3. 電動モータは、500V仕様のDCブラシレスモータ。出力は1.5倍の68馬力に向上。
- 4. バッテリは、従来のニッケル水素バッテリであるが、内部抵抗を低減し、入出力密度を35%向上させた。
- 5. エンジンは、DOHC4気筒、1500ccで初代と同じ構成であるが、
- 出力が77馬力/5000rpm、トルクが11.7kgm / 4200rpmと向上。
- エンジンの燃焼効率88%。車両効率を37%として総合効率を32%まで高めた。(初代プリウスは25%)
- 6. 回生ブレーキとメカニカルブレーキの相性が良くなって、ブレーキング時の違和感がなくなった。
- 7. 高速運転するとバッテリが減りぎみだった初代に比べ、180km/hの走行でも十分に充電する改良が施された。
- 8. 総合性能で、10モードの燃費35.5km/リットルを達成。
-
-
- 【三世代目のプリウス】 (2009.04.26)(2009.05.06追記)
- 2009年5月に発売される3代目プリウスは、さらに進化して、燃費と運転性能の向上を果たしていると言われている。
- 彼らが開発したハイブリッドシステムは、THS II (TOYOTA Hybrid System II)と呼ばれている。
-
- 二世代からの主な変更点は、以下の通りである。
- 1. ガソリンエンジンが、1.5リットルから1.8リットルと大きくなった。
- 2. エンジンの出力が、73kW(98馬力)と17kW(21馬力)アップした。
- 3. 電動モータも、最高出力60kW(80馬力)と10kW(12馬力)とアップした。
- 4. エンジンに付帯している補機類(エアコンプレッサー、ウォータポンプ)などを電動化してエンジン負荷を軽減
- 5. 通常の2.4リットルエンジン搭載ガソリン車と同じパワー性能を持った。
- 6. モータ駆動を500Vから650Vに上げた。
- 7. 総合馬力が、113馬力から136馬力になった。
- 8. 屋根にソーラーパネルを配置して、太陽エネルギーを電気エネルギーに変えてこの電力で室内換気を行う。
- 9. バッテリは、リチウムイオンバッテリが期待されたが、今回も前回と同じニッケル・水素バッテリが使われている。
-
- 【四世代目のプリウス】 (2019.01.05)
- 2015年9月に発表された4代目プリウスは、さらに進化した。1997年登場以来4度目のモデルチェンジである。2000年からの20年間の自動車業界はハイブリッド一人勝ちという感が否めない。それだけ大衆に対する訴求力があったということだと思う。手頃な価格で燃費が驚くほど良い、ステータスもそこそこあり、プリウスに乗っていると言えば、環境に配慮している善良な市民というイメージを人々に与えた。私の回りの紳士淑女の多くがこの思いを抱いていることを感じた。私地震はプリウスに乗っていない(乗っているのはターボ付のガソリンエンジン車である)。プリウスは、レンタカーで都合4回、走行距離1000km程度乗った。関連会社の人達も営業車として使っているのでよく乗せてもらった。燃費は、郊外走行で18km/L程度だった。燃費もよく出足も良い。ただ、スポーティカーに比べるとカーブなどでの腰砕けがあり長時間の運転は退屈だった。毎日の「足」として使うには十分なものであろう。同クラスのガソリン車と比べると、街乗りで10万km走行以上乗れば初期費用を回収でき、費用効果が上回ると言われている。
-
- 三世代からの主な変更点は、以下の通りである。
- 1. 車体構造を見直した(TNGA)。
- 2. 初めてリチウムイオンバッテリーが採用された。
- 3. ガソリンエンジンは、先代と同じ。しかし、最大熱効率40%を達成(先代は32%)。
- 4. 4輪駆動のモデルが追加された。
- 5. 前輪モータは、交流同期電動機、1NM型で53kW(72馬力)、トルク162Nm(16.6kg-m)。
- 6. 4輪モデルの後輪モータは、交流同期電動機、1MM型で5.3kW(7.2馬力)、トルク55Nm(5.6kg-m)。
- 7. 総合馬力が170馬力になった。
-
-
- 1-3-4. 日本の発電所事情 50Hzと60Hz
-
- 日本では、明治になって白熱電球を使った照明と工場用動力としてのモータの利用が始まると、これに電力を供給する発電所の建設に迫られた。1883年(明治16年)2月15日、工部大学(東京大学工学部の前身)の電気工学部博士 藤岡市助氏によって電気事業会社、東京電灯会社が設立された。エジソンが電灯会社を設立した1881年より2年後のことである。業務内容は、東京市内へのアーク灯(電灯)普及を目的とした。当時は、消費電力もそれほど大きくはなく、大口需要顧客を見つけてはその近くに小規模の発電所を設置した。東京電灯は、1890年(明治23年)までに小規模な発電設備を日本橋、浅草、吉原の遊郭など5箇所の需要顧客に対して、その近くに電燈局を建設し操業を始めた。発電所は、往復蒸気機関(直立汽缶)30馬力の横置汽機を使って25kWエジソン式直流発電機1台を設置し、210V、直流三線式の電源を供給した。直流発電のために供給距離は限られていて、電燈局の近傍数kmという限られた地域にしか電気を供給できなかった。
-
- 【米国GE(General Electric)社】

-
- 日本で電気事業用として最初に水力発電設備を備えたのは、京都電灯の蹴上(けあげ)水力発電所であり、明治24年(1891年)のことである。琵琶湖疎水工事の一環として行われたこの発電所建設は(右写真は、京都市東山地区にある蹴上発電所の水管)、120馬力のペルトン水車2基と80kWの直流発電機2基という装備だった。水車は、米国ペルトン社製の腰掛直立水車で、発電機は米国GE社製500V直流発電機だった。
-
- 明治30年(1896年)になると、水車20基、発電機19基に拡張され、総合出力も1,760kWとなった。採用された発電機もGE社製をはじめ、トムソン・ハウストン社、スタンレー社、シーメンス社といろいろで、国産では明治28年に60kWの発電機が芝浦製作所によって納入された。
-
- 電力の需要増大に伴い、大型発電所の必要性が出てきた。それまで、地域地域でチマチマと発電していたのを集約して、電力を管理、確保しようというものであった。
-
- 東京電灯会社は、明治29年(1896年)、浅草に火力発電所を建設した。発電設備は、石川造船所の単相交流発電機(2,000V、200kW)4基。それにドイツアルゲマイネ(Allgemeine)の三相交流式発電機(3,000V、265kW)6基というものだった。石川島造船所の発電機は、日本における大容量発電機製作の先駆とされている。当時、米国でさえ100kW以上の発電機を作るのは難しいといわれていた時代に、日本でこれらの技術革新が行えたのは、日清戦争期の国産化奨励の風潮のおかげだったようだ。
- 米国General Electric社は、GE(じーいー)と言う社名で有名な米国を代表する総合電機メーカである。GEの前身は、1876年にThomas Alva Edisonがニュージャージ州メロンパークに開いたエジソン研究所(1890年にEdison General Electric Companyと改名)と、1879年にElihu ThomsonとE.J.Houstonが設立したThomson-Houston Company の2社であり、これらが1892年に合併してGE社となった。
-
- 【ドイツ・アルゲマイネ社】
-
- ドイツ・アルゲマイネ(Allgemeine:AEG社、Allgemeine Elektrizitaets Gesellschaft)社の発電機が50Hzだったことが、関東を含める東日本の電源周波数50Hzを決定づけることになる。
-
- ちなみにアルゲマイネ(Argemeine)社は、1912年、碓氷峠を走らせた我が国最初の電気機関車(1000型アプト式電気機関車=後のEC40形)の製造会社としても知られている。アルゲマイネ(Argemeine)社の発電機が画期的だったのは、交流発電もさることながらドブロウオルスキー(Michael von Dolivo - Dobrowolski: 1862-1919)師長が3相交流発電方式を考案したことだった。
- 3相交流というのは、3本の電力線にそれぞれ120°の位相がずれた交流を流し、モータのステータに結線する。ステータには、120°ずれたコイルが配置されていて、電気が流れるとモータ内のステータ磁界はグルグルと回転するようになる。この回転磁界につられて回転子(ロータ)が回る。
-
- 高校時代、物理の時間にこの考えを聞いたときは良くわからなかったが、社会人になって交流モータを間の当たりにして再度勉強したとき、目からウロコが落ちる思いがした。世の中には、ホントに賢い人がいるものだと身震いした記憶がある。
-
- さて、電源周波数の話に戻る。関東以東の東日本が50HZの周波数を採用する契機になったのが浅草火力発電所のドイツ製発電機設置であったのに対し、西日本では、明治30年(1896年)の大阪電灯の幸町発電所の増設に米国のGE社製150kW発電機4基を導入し、これが60Hzだったことに由来する。幸町発電所は、運開時の設備は、米国トムソン・ハウストン社(Thomson-Houston Company)製単相交流120kW、1,155V、125Hz発電機3基であったが、増設に当たりトムソン・ハウストン社がエジソン社と吸収合併されGE社となったため、GE社製の発電機が採用となった。こうして、大阪電灯が60Hzを採用したため、距離的に近い神戸電灯や、名古屋電灯もアメリカから発電機を購入していくようになり、西日本が60Hzとなっていった。
-
- ちなみに、大阪電燈は、他の電灯会社と違っていち早く交流発電の優位性を見通していたと言われる。
- 1887年(明治20年)、東京電燈による日本初の電気供給事業は直流で始められた。それに続く神戸電燈、京都電燈、名古屋電燈、横浜電燈も直流方式が採用された。
- しかし、大阪電燈の岩垂邦彦だけは将来の需要の増大とそれに伴う長距離送電の必要性から高圧交流送電の方が有利と判断し、1889年の開業当初から交流方式を採用した。
- こうして大阪電燈は、トムソン・ハウストン社製の単相交流発電機1,155Vで発電して、需要家に52Vに降圧して供給した。
-
-
-
- 1-3-5. 電力送電 (2004.01.11)
-
- 私達の家庭に送られる電気は、電力会社から作られる発電所からの電力によってまかなわれている。家庭で使われる電気は、
-
- 1. 単相100V
-
- 2. 単相200V
-
- の二つである。工場などでは、三相200Vが大型モータや電気炉に使われている。大口の需要家(大きな工場)になると、送電線から高圧線を直接引き込んで、需要家が自ら変電設備を設けて自分の所の電力需要をまかなっている。
- ちなみに、電気設備の低圧電源は、直流750V以下、交流600V以下で、日本ではAC100V、AC200V、AC230V、AC400Vが低圧電源と取り決められている。
- 100、200、400の値は分かりやすい電圧であるが、AC230Vはわかりの悪い値である。
- この他に、米国ではAC110V/AC115Vという規格があり、日本とは若干電圧の相違がある。
- 米国でなぜAC110Vだったり、AC115Vだったりするのかがよくわからない。日本の電圧規格と10%から15%もの電圧の開きがあり、電圧を直接引き込んで使う古いタイプの電気掃除機や電気洗濯機、冷蔵庫などを輸入して使ったら性能がでないんじゃないかと考えさせられる。
-
- 過日、米国のエンジニアと商用電源について話し合う機会があった。彼らが言うには、日本の電源は実にわかりずらいという。なんで同じ国なのに50Hzと60Hzがあるのか理解できないと言う。さらに、米国とは異なるAC100Vという低い電圧を採用している。我々からすればAC110VやAC115Vの方が問題だと思うのだが、お国が違えば考える観点が異なるものだと考えさせられた。
-
- 各家庭に入る電力は、屋外の電柱(電信柱、正確には配電柱というらしい)から引き込まれる。電柱には、円筒状の重たそうなヒダのついた鉄の箱(柱状トランス)が乗っかっていて、その箱から電力線が分岐して家庭に入っている。電柱の送電電圧は6,600Vであり、電柱の柱上トランス(円筒状の鉄の箱)で100V、200Vに電圧を落としている。
-
- 電柱の風上である変電所間では66,000Vの10倍高い電圧で送電が行われ、工場などの大口需要家には、そのままの66kVを渡したり、その1/3の電圧である22kVの電圧に変圧して工場に送り込んでいる。
- 変電所も大規模なものと小規模なものがあるが、大規模な変電所で電力送電の中枢をになう大動脈では、500kV(500,000V)の送電が行われている。この電圧は発電所から超高圧変電所に送られてくる電力がこの電圧であり、この超高圧変電所から一次変電所までは、154kVで送電されている。
- また、都市部近郊で発電される比較的小さな発電所は、154kVで直接一次変電所に送られている。都市部から離れた大型の発電所では、先にも述べた500kV送電の他に、275kVで送られており、将来に向けて1000kV(100万ボルト)送電の研究が続けられている。
-
-
- ■ なぜ高圧送電なのか
- 水道管における水圧と水量でも似たような問題を抱えているが、電力を送るとき、電力が需要家の手元に届くまでに何割かの電力が漏れたり電線の抵抗で消費される。そうしたロスをできるだけ防ぐためにいろいろな工夫がなされている。送電のロスを防ぐためには、送電の電線を太くすればロスが少なくなりそうである。これは水道管でも太いほどたくさん流れるからなんとなく理解できる。また、電気が漏れないように、電線の接続部に抵抗の高い絶縁体(碍子など)を使う。絶縁体がしっかりしていれば電気は漏れない。水道管もパイプの接続がしっかりパッキンなどでシールドされていれば高圧をかけても漏れないのと同じである。
- これらの対策の他に、もっと効率良く送電を行う方法として高圧送電がある。自動車のボンネットをあけてバッテリに繋がれているケーブルを見たことがあるだろうか。自動車のバッテリは12VDCと電圧が低い。しかしバッテリにつながれているケーブルには太い電線が使われている。たくさんの電流を流すためには、低い電圧であっても太い電線を使わないと抵抗成分が大きくなり、自らの抵抗で電力を消費して消費したエネルギーが熱となって発熱する。発熱は、暖房に用いない限り百害あって一利なしであり、電線による抵抗成分を抑えるために必要かつ十分な電線の太さを使って配線する。
-
- 自動車のバッテリに繋がれている電気パーツは、ヘッドランプ、ブレーキランプ、エアコンモータ、点火プラグ、ワイパー、ラジオなどトータル600W程度がバッテリから供給される(ヘッドランプ180W、スモールランプ40W、ブレーキランプ60W、ワイパー50W、エアコン200W、オーディオ・カーナビ50W、エンジン50W、リア・デフォッガ150Wですべて合わせると770W)。自動車のバッテリは12VDCなので、600Wの消費電力は、供給電圧のDC12Vで割ってやると50Aとなり、かなり大量の電流が流れることになる。家庭用電源ではAC100Vなので、600Wの消費電力では6Aの電流ですむ。従って家庭用の電源コードはそれほど太くなくても(電線の太さで1.25mm 2程度で)1500Wまでの電気を流すことができる。
-
- 電線が仮に0.05Ωの抵抗を持っていたとしたら、その電線に50A流れる際に発生するジュール熱は、
-
- I 2 x R= 50 x 50 x0.05 = 125W
- I: 電流(A)
- R: 抵抗(Ω)
-
- となり、白熱電球2ヶ分の消費電力がケーブル内で無駄に消費される。同じ電線(抵抗)を使って100Vの電圧にすれば電線に流れる電流は6Aですみ、これで600Wの電力を供給できるから、電線で消費される電力は、
-
- I 2 x R=6 x6 x0.05 = 1.8W
-
- となり、1/70に電気ロスが抑えられる。
- つまり、同じ抵抗の電線を使うならば電圧を高くした方が電圧の二乗分の電力ロスが軽減されることになる。
- AC100VよりAC1,000Vの方が100倍送電ロスが少なくなるし、AC100kVなら100万倍もの送電ロスが抑えられる。
- 高圧送電は危険が伴うけれども送電ロスが抑えられるという大きなメリットがあるため、電力送電での高圧送電は常識となっている。
- 交流は、変圧器で電圧を自由に変えられるので、送電ロスを抑えるためには交流によって電圧を変えて高電圧で送電しているのである。
-
-
-
- ■ 高電圧送電線
-
- 電力の送電に使われる送電線は、電気抵抗の少ない銀(1.47×10 -8 Ω・m)が使われているかと思うとそうではない。銀は高価だからである。
- ならば銀の次に電気抵抗の低い銅(1.55×10 -8 Ω・m)が使われているかと言うと、案外そうでもない。たしかに家庭内の配電線や電源コード、自動車の電源ケーブルには銅線が使われている。
- しかし、鉄塔に使われている電線には、なんとアルミニウム導線(2.5×10 -8 Ω・m)が使われているのである。
- アルミニウムは、銅に比べると非常に軽く、比重は銅の1/3である。数100kmにも及ぶ距離を電力送電する場合に、鉄塔工事や敷設工事にかかる費用や材料費は無視できない問題となる。電気抵抗が1.6倍高いアルミを使っても、その分だけ電圧を高めれば送電電流が減ぜられるため、アルミの軽さを考慮するとアルミニウム送電線を使うことの方がメリットが出てくる。
- 現在では、高圧送電線の99%にアルミニウム送電線が使われているという。
-
-


-
- 高圧送電線:電線を懸架する碍子(左)と高圧送電線(右)。
- 高圧送電線はアルミでできていて、被覆はないのだなぁ。
- これらの電線と絶縁碍子、鉄塔を組み上げて、500,000Vの送電を行っている。
- (東京電力 電気の史料館 展示)
-

1-4. 電気の三要素: 電圧、電流、抵抗
1-4-1. ACとDC(交流と直流)
- 電気を送る手段には、電圧と電流が一定の直流(DC = Direct Current)と、サイン波のように交番する交流(AC = Alternating Current)の二種類ある。
- 発電機も、交流発電機と直流発電機の2種類あるが、発電効率と発電機そのものの構造がシンプルな交流発電機が主流になっている。
- 直流は、原理がわかりやすく回路を追いかけやすいが、交流はチョット難しい。
- なにせ、発明王エジソンだって交流の考え方が難しすぎてついていけなかったのだから。
- 交流には、独特の考え方がある。下の図を見てもわかるように、交流は電流も電圧も一方向に流れない。行ったり来たりしている。波のような感じだ。波の上下するエネルギーを使うと言うように考えた方がわかりがいいかも知れない。 交流で、独特の役割を果たすのがコイルである。電線がグルグル巻いてある電気素子がそれである。モータや発電機には、これがいっぱい巻いてあるし、ラジオの中身を開けると髪の毛ほどの細い線でグルグル円筒状に巻かれたコイルを見ることができる。これは、電波を取り込むための重要なコイルである。また電信柱には、送電線から家庭に電気を引く際に電圧を200Vや100Vに降圧させる変圧器(柱上トランス)がある。ここにもコイルが使われている。

-
- 私は、高校生になるまで、世の中に交流電気が何故あるのか皆目分からなかった。
- 学校で習う理科の電気の実験は、乾電池を使った直流による実験が多くて、交流理論を教えてくれなかったのである。
- また小学校から慣れ親しんだモータも直流が多かったし、大好きなプラモデルに使うマブチモータも直流だった。
-
- しかし、家庭に帰れば、すぐ身近なところに交流電気がきていた。電気器具をコンセントに差し込むとき、何故、家庭に来る電気が交流でなければならないのかわからずホントに不思議だった。遊びのための乾電池がすぐなくなり、子供のお小遣いで乾電池は潤沢に買えなかった。家庭電気が直流電源だったらどんなに素晴らしいんだろうと当時思った記憶がある。高校の物理の教科書には、なるほど交流の説明が載っているが、良くわからなくて知識の詰め込みで終わってしまっていた。
-
- 大学に入って、工場を見学したり、研究室で実験をするようになって、初めて交流の御利益がわかり、交流電気には以下の特徴があることを身をもって知るようになった。
-
- 社会人になって三相交流電気のありがたみを体で知ることができた。
【交流送電の御利益】
■ 送電時に電圧を高めて送り、使用時に電圧を低くすることが簡単にできる。
→ 高圧送電をすることにより送電時の電力ロスを少なくすることができる。
■ 交流電動機(モータ)が幅広く利用されている。
→ 直流モータは力があるが回転が一定せずそれを制御する回路も高価で、
且つ整流ブラシの交換など面倒な面があった。
■ 特に3相交流電動機は大出力のモータが作りやすい。
→ 工場の動力といえばほとんど3相交流電動機だった。
■ 交流電気は変圧器で任意に電圧を上げたり下げたりしやすい。
■ 発電機をシンプルな交流発電機にし、電動機もシンプルな3相交流モータにする
ことにより電力設備が整えやすい。
■ 照明設備の蛍光灯は交流でないと点灯しない。蛍光灯管内は低圧で放電を必要とする。
点灯時、高電圧を作って放電を起こさせる。この始動点灯と点灯の安定化がトランス
1つでできてまう。交流電源の真骨頂を示す代表的な交流機器。
ただ、高校までの教科書には交流モータの説明はあったがが、実際どのような形で使われているかがピンとこなかった。
モータそのものは、それがどんなものであるかはわかるが、モータの区別を整然と区別できる人はそれほど多くないのではないかと思う。
前にも述べたが、発電機の歴史も、イタリアの天才化学者ヴォルタの影響からか、電気は直流でなければならないような風潮があったように感じる。化学実験などでは交流よりも直流の方が断然実験しやすいし、考え方として直流電流の方が理解しやすいかったのではないかと思う。ファラディーの電磁理論が完成して発電機ができても、それは直流発電機だった。電動モーターは整流ブラシを取り付けて直流にしていたし、エジソンは意地になって直流を主張した。
しかし、交流はそれにも増してメリットがあった。交流電気から直流を作るのはたいして難しい事ではなく、昔から簡単な電気素子で直流を作ることができた。直流から交流を作ることは難しい。難しいから、直流から交流を作るときは直流モータに交流発電機を接続して取り出していた。最近は電子素子の発達で、自由な周波数を作れるようになった。しかし、直流から交流を作る場合は回路の関係上矩形波(四角い波形)であることが多く、交流発電機のようなサイン波(正弦波)でないケースが多い。矩形波交流電源を使用した場合には、装置によっては電源部が加熱したり故障することがあるので注意が必要だ。
-
- 【交流の問題点】
- 交流発電とその送電は、直流に比べ比較にならないほどのメリットをもたらしていることは理解できた。しかし、交流送電でも問題が無いわけではない。交流の大きな問題点の一つは、電圧の周波数と電流の周波数のタイミング(位相)が一致しずらいことである。つまり電動機などを使用する際、電動機のほしがる電流が、電圧の位相とずれることである。電圧が144Vのピークにある時、モータに流れる電流はピークの70%程度であることがあり、電圧が下がったとき電流がピークになるという具合である。
-
- 電力は、電圧と電流の積で求まるから、
-
- 電動機器の使用電力(P) = 電圧(E) x 電流(I)
-
- で求まる。
- しかし、交流では電圧が絶えず変化するから、上の公式に変化する変数を加えてやる。
-
- 電動機器の使用電力(P) = 電圧(E) ・ cos(2πω) x 電流(I)・cos(2πω + α)
- 2πωは、交流周波数、αは位相遅れである。
-
- この積算が、時々刻々の電力消費となる。
- モータなどで100Vで10Aを消費していると言っても時間が一致していないので、
-
- 100V x 10A = 1000W
-
- で求められる消費電力は、見かけの電力(皮相電力)であり、実際は位相を考慮した実効電力を考えなければならない。
- なにせ、実効電力がホントの力を出すのだから。
- ・・・とは言っても、電力としては実際に100Vは印加されるし、10Aは流れるわけだから電線の太さや耐圧は相応のものを確保しなければならない。
-
-
- 【力率】
- この皮相電力と実効電力の割合を力率(りきりつ)と呼んでいる。力率の悪い電気機器は、供給側(発電所や変電所)に迷惑をかけるので、大きな事業所では、この力率改善のための設備(でっかなコンデンサを変電設備に配置し、電流が欲しいときこのコンデンサに蓄えた電荷で補償する)を設けている。
- カタログなどで電力仕様を述べるとき、1000VAと書かれてあり、Wになっていないことがある。これは、VAは皮相電力を表し、電源側にこれだけの負担をかけるという意味合いである。Wは実効電力を表すために用いる。従って、直流電源しか使わない電子機器の消費電力に300VAを記載するのは適切ではない。300VAと記載された機器機器の仕様を見ると、この機器には誘導モータでも使っているのかと勘ぐってしまう。
-
- 直流送電:交流電源は送電の電圧を変えるのに都合がよいことが理解ができたが、いったん高圧に変換してしまうと、交流で送るよりも直流で送った方が送電ロスが少ないことがわかっている。交流では、高圧で交番がかかるのだから忙しいことこの上ない。直流なら電圧と電流の位相がずれることもない。今の技術なら幹線は高圧直流にして、使用地域で交流に直すことができる。というわけで、電力会社では、直流送電の研究開発にかなりの力を入れている。静岡以西と東で周波数の変換も直流で送れば簡単だ。
-
-
- 【無効電力と有効電力】(2001.11.25)
- 機械屋にとっては、電力で使われる無効電力という言葉や、それを説明するのに使われている複素数の考え方がよくわからない、というメールをいただいた(No.261 - 無効電力についてご質問のIさん(2001.11.18)- )。
- 私自身も、交流機器(モータや水銀灯)がこうした効率の悪い電力消費をしていることを、社会人になるまで知らなかった。高速度カメラ用の照明装置の設計・設置に携わるようになって、初めて知ったのである。
- 高校時代の物理の授業で交流理論で複素数が登場したときには、何がなんだかわからずほんとうにとまどった。
- 現実にない虚数部というものが、なぜ現実世界に導入されなければならないのか、理解に苦しんだのである。
- しかし、今になって思うと、虚数という言葉に呪縛されすぎて、複素数の考え方をしっかり理解していなかったことに気づいた。
- (複素数の考え方は下記の【複素数の考え方】を参照のこと)
- 「無効電力」は、簡単に言ってしまえば、電気をせっせと発電所で作って供給しても、モータとか水銀灯で明かりをともす実際の仕事に使ったとき、電圧と電流のアンバランスな流れ方によって、有効な仕事となっていないことを表している。
-
- 無効電力は、電気機械が電気をもらって熱や仕事として実質的に消費したエネルギーのことではなく、見かけの電力と実際の機器が仕事をしているエネルギー(熱損失も含めて)の差を示すもので、効率を示す指標として使われることの多い単語である。
- 乾電池などの直流電源の場合、電圧と電流は使う抵抗に比例して一定の消費電力を与えるが、交流では電圧も電流も周期的に変化する。その変化のタイミング(位相)がすべて整っていれば、瞬間々々の電圧値と電流値は比例して変化するから、電力は直流の時と同じ考え方をすればよい。発熱電球や電熱器などは、交流で使っても素直な電力消費となって、電流と電圧の関係は単純な積の関係でことが足りる。
- しかし、コンデンサー(容量負荷)やコイル(誘導負荷)を使った装置では、交流を流そうとすると電圧に比例した電流が流れなくなり時間がずれた電流の流れとなってしまう。
- コンデンサを使った電気回路では、電圧が上がっていくと電気を蓄えようとしてコンデンサ内部に電気がイッパイになるまでため込むため、外部には仕事をしない。電圧が下がっていくと、今度は貯めておいた電気を外に出して仕事をするようになる。
- コンデンサは、電源の負荷変動を一定にする働きや不用意な電圧(ノイズ)を吸収する働きがあるので重宝する素子であるが、電圧と電流の関係を崩してしまう特性も持ち合わせている。これを電気用語で位相がずれると言っている。
- コイルも同じように電圧を与えると電気を通しにくくなり、電圧を取り去るとそれを引き留めるように逆起電力が起きる。
-
- この働き(誘導作用)のおかげで発電機で電気を作ったり、モータが回ったりするのであるが、電圧を与えても素直に電流が流れずに遅れて電流が流れるので話が複雑になっている。
-
- 通常、電力の計算をする場合、AC100V、50Hzにおいては1秒間に50回の割合で、-144Vから+144Vの交番電圧がかかり、100オームのフィラメントにこの電源が加わると、最高1.44アンペアの電流が同じ電圧周期で、また同じ比率の電流値で流れることになる。つまりこの場合の電力は、電圧と電流を掛けた値でよいことになる。一般的には交流電気は、ピーク値(144V)ではなく実効値(100V)であらわすので、消費電力も平均値、AC100V、1A(100オームのフィラメント抵抗時)を取って100Wと称している。
- しかし、交流モータなどの場合、144Vの電圧が加わった時にその電圧に比例した電流は流れないため、モータに流れた電圧の平均値と電流の平均値を掛け合わせて消費電力としても、それだけの仕事はしていない。
- つまり、電流と電圧の流れ方が比例せずにズレているのでそのまま掛け合わせたのでは実際の仕事をしている電力とはかけ離れた電力となってしまう。
- この見かけの電力(位相がズレを考慮しない電圧と電流を掛け合わせた電力)を皮相電力といい、本当に仕事をした電力を実効電力、仕事に回らなかった電力を無効電力と言っている。
 この三者の関係は以下の式で表される。
この三者の関係は以下の式で表される。-
-
- 皮相電力 = √{(有効電力)2 + (無効電力)2 }
-
- 力率 = cosθ = 有効電力 / 皮相電力
-
-
- 上の関係式は、上右図のベクトル図と一致している。
- すなわち、皮相電力は見かけ上の電力であり、実際の仕事はベクトル図の水平方向成分で表される有効電力であり、垂直成分が無効電力となる。
- 両者の開き(θ)が位相のズレとなり、このズレが大きいほど、発電所から電力をもらう割には仕事をしない電気機器となる。
- 白熱電球などではθ = 0で、Cosθ = 1、となり、誘導電動機(モータ)を使う電気機器ではCosθ = 0.75 〜 0.95となる。
-
- 上図右のベクトル図で、無効電力を複素数の虚数部に当て、有効電力を実数部に当てる複素関数にすると、三角関数のみで関係式を立てるよりも交流計算が便利になる。
-
-
-
- ■ 電気工学に複素数を導入したスタインメッツ
-
-
 複雑な交流理論(エジソンは、交流理論についていけなかった)に複素数を導入したのは、ドイツの電気工学者チャールズ・プロタス・スタインメッツ(Charles Proteus Steinmetz, 1865 - 1923)である。
複雑な交流理論(エジソンは、交流理論についていけなかった)に複素数を導入したのは、ドイツの電気工学者チャールズ・プロタス・スタインメッツ(Charles Proteus Steinmetz, 1865 - 1923)である。
- 彼は、複素数という数学的概念を導入することにより、時々刻々と変わる交流の電流と電圧の相互関係をスマートな数式にまとめ上げた。
-
- スタインメッツは、ドイツ領プロシアのブラスラウ(Breslau)で生まれ、ブラスラウ大学で学んだ。
- 社会主義に目覚め、学生社会運動に参加したため国を追われ、スイスを経由して、1889年、アメリカに移住した。
- 彼はそこで改名して今の名前になった。
- ニューヨーク州Yonkersにあるドイツ系電気会社(Rudolf Eickemeyer社)に働くうちに磁気ヒステリシスの研究で世に認められた。
- 1893年、Rudolf Eickemeyer社は、GE(General Electric)社に買収されたため、彼は顧問として迎え入れられ、ニューヨーク州シュネクタディ(Schenectady)にある研究所を舞台に電気機器の設計、水銀灯、避雷器、交流高圧送電機器など195にのぼる特許を取得した。
- 多数の論文も執筆し、交流電気技術の確立に決定的な役割を果たした。
- 彼の業績の中で、ヒステリシス現象の発見、電気の過度現象の理論的解析、複素数を導入した三相交流回路計算法の確立などが秀逸で電気工学に重要な業績を残した。
-
- 【私が、電気工学につまづいたのは、実にこの複素数概念であった。高校時代に物理学を勉強していて「電力」の分野でこの式が出てきた。
- 家庭に入り込む電気が何故100Vの交流であるのか理解できてない私に、なおそれ以上の理論が出てきたのである。
- これを理解するのが難しかった。
- 高校時代には、物理と平行して数学の授業で複素数というのを習っていたので、複素数の公式自体は理解もし、複雑な計算式も鵜呑みの状態でなんとか使いこなしていた。
- しかし、根本はわかっていなかった。
- 大学に入って、すべてのことが難しくなって来た時、キャンパスを歩きながら、なぜ電気工学が複素数で説明がつくのかいつも悩んでいた。
- しかし、それも徐々に忘れ去って行った。
- 私の専門の機械工学には、このような複雑な複素数の数学的概念が少なかったので、複素数を思い出さなくてもよくなったのである。】(2004.05.14記)(2007.08.16追記)
-
-
- 【複素数の考え方】
-
 複素数の考え方は、もともとは、二次元方程式の解が実数だけで解けないことから編み出された考え方である。
複素数の考え方は、もともとは、二次元方程式の解が実数だけで解けないことから編み出された考え方である。- 例えば、
-
- χ2 + 1 = 0
-
- という方程式を考えてみる。
- この方程式の解は、χ = +/- √(-1)となる。
- この√(-1)という値は現実の世界(実数の世界)にはない値である。
- この解は、おもしろい事実を我々に教えてくれた。
- つまり、この√(-1)という値を掛け合わせると、-1という実数に入り込むのである。
- √(-1)という値を、虚数を表す単位として簡単のために i と表す。
-
- ドイツ人の数学者ガウスは、この事実をもとにして、実数部だけの空間座標(X,Y,Z)とは別に、横軸に実数部、縦軸に√(-1) = i が支配する虚数部を割り当てる空間座標を考えた。
- これが複素空間(複素平面、ガウス座標)と呼ばれるものになる。
- これまでの実数部だけの空間は、フランスの数学者の名前を使用してデカルト座標(デカルト平面)と呼んでいる。
-
- 先に複素数の虚数部は、掛け合わせると実数部に戻ると言った。
- ガウスは、この虚数部の積の性質に注目して、複素関数の積というは複素平面を90°反時計方向に回転すると定義した。
- 実数 a に i をかけると ai となり、この値は虚数部の正の方向に移る。これは複素平面では 90°半時計方向に回転したことになる。
- この ai に、さらに i をかけると、ai 2 = -a となり最初のaの値の反対方向の実数部に移る( ai からではさらに 90°半時計方向に回転する)。
- ちなみに複素数の加減では、実数部は実数部、虚数部は虚数部での加減を行う。
-
- そこで本題の交流理論における電力の関係式に戻るわけであるが、電力は電圧と電流の積であることはすでに理解した。
- 交流素子の代表であるコンデンサやコイルは、交流電圧に対して電流を90°遅らせたり進ませたりする働きをもつため、電力を計算する上で複素平面を導入するのは格好の素材であった。
- 実数部は、現実の電力(有効電力)として表され、虚数部は発電所から電力を受けてはいるが実際の仕事には出てこない電力(無効電力)として表せるようになった。
- この複素平面の考え方を利用して、回路にコンデンサやコイルを入れると電力は複素平面上を回転し、その平面上で無効電力と有効電力、はては皮相電力、力率が一目瞭然にわかってしまうという御利益を受けることになったのである。
-
- ちなみに、電気工学で扱う複素関数の虚数部の記号は i ではなく j を使う。これは、 i が電気工学では電流を表す記号になっているため、混用を避けるためである。
-
- 複素数の考えを編み出したのは、ノルウェーの測量技師ウェッセル(1745-1818)と言われている。
- しかし彼の論文は、100年ほど忘れ去られ、もう一人の発見者ドイツ人数学者ガウスが有名になった。
- それが、ドイツ系アメリカ人GE社のエンジニア、スタインメッツによって工学的な見知から花開いたのである。
-
-
- 【整数、小数、分数、正数、負数、0、有理数、無理数、実数、虚数】
- 数学の世界は、数を扱う学問であるが、一日にして突然複素数が出来上がったわけではない。
- 最初、数といえば整数のみあった。一つ、二つという具合に数は分離した量であった。
- その数に連続性を見出しこれを統一したのはフランス人デカルトである。
- 彼は、連続量を長さという単位に全て置き換え数を連続する長さの量としたのである。
- この考えを延長して、量の2次元平面、3次元平面(グラフ)の概念が出来上がる。
- デカルト平面である。
- 彼の考えによって、数は無限の量と長さを持つに至る。
- 「0」の発見は、アラビア人とい言われているが、この発見も画期的なものであった。
- 一般的に、「無い」ものが存在してそれが重要な役割を果たすのであるから、「0」の考えがわかる人は血の巡りがいい人、と言えるだろう。
- それを考え出したアラビア人も非凡であったし、それを数学の記述の世界に組み入れて、普遍的な体系に築き上げた数学者も非凡である。
- 「0」の発見に続いて、負数の考え方の出現は、数学を記述言語として論理的なものにする上で大いに貢献した。
-
- 分数と小数はどのようにして生まれたか?
-
- 分数の世界の方が、小数の世界よりも大きいことはよくご存じであろう。
- 数学の歴史的を見ると、分数の方が早くから発達してきた。
- 小数は、10進法という考え方ができて概念化されるにいたり、工学分野では主流になっていった。
- (しかしながらコンピュータが普及する以前では、分数の方が計算処理しやすく誤差も少ないので、分数による計算手法が発達した。
- インチによる表記では、10進法による小数表記ではなく、分数表記[1インチ、1/2インチ、1/4インチ、1/8インチ]が一般である。)
-
- こうした数の世界で、演算処理が自由に行われるようになると、逆の処理も不自由なく行われなければならなくなる。
- 2 + 3 という足し算が自由に行われるようなってくると、その逆の演算、2 - 3 の演算も自由に行いたくなる。
- しかし、最初の数の世界には、負数という考えが無かった。
- そこで負数という考えを導入し、数の世界の仲間に入れた。
- 2 x 3 というかけ算も自由に行える。
- しかし、2÷3では整数の世界では解がない。
- そこで、再び分数という数を仲間に入れた。
-
- このようにして、数はどんどん仲間を増やし、最後に複素数が登場するのである。
- 複素数は、高次方程式の解を求める上でどうしても必要な数であったのである。
- かくして、複素数世界では、実数部と虚数部という二つの次元で数を表すようになり、乗除演算では複素平面を90°で回転するという考え方が成り立つようになった。
- (考えてみれば、実数部の世界の乗除演算で、-1 x -1 = 1 という処理もデカルト平面で考えると、180°回転するという考え方が成り立つ。)
-
- このホームページを立ち上げて電気をおさらいするにつれて、交流理論になぜ複素関数が導入されてきたのかがおぼろげながらわかってきた。
- 複素関数にしても、微分、積分にしてもプール代数にしても数学というのは概念の記号化であり、そうした数式はちょっと見、複雑に見えるがそれを使わないと(単なる加減乗除の記号だけでは)かえってとても複雑になるため、新しい考え方を導入して関係を一元化しているんだな、と思うようになった。
-
- 複素数を使った電力の関係式は、位相のずれた部分を虚数部にあてて、実際に仕事をしている有効な部分は実数部にあてて、有効電力も無効電力も一つの式に当てはめてしまうという画期的なものであることがわかる。
- 交流理論を扱う場合には、電圧と電流が同じ位相で流れないために、回路を組む場合電流と電圧がどのようなバランスで(位相のズレで)流れているのか知る必要がある。
- このとき、位相のズレを三角関数を使って関係式に書き表すと、とても複雑になってしまう。
- それを簡単にするために、複素関数の考え方を導入して一つの数式に当てはめているのである。
- だから、複素数は難しい、のではなくて、ことを簡単にするための手法と考える必要がある。
- 今は、コンピュータが発達したので、こうした複素数の考え方や制御工学で使われているラプラス変換などを用いずに、コンピュータの単純、高速処理機能を使って、初歩的な計算式をプログラム入れて高速で演算し、収れんさせて解を求める方法が多いように見受けられる。
- しかし、たとえコンピュータが高速になったとはいえ、数学的な素養があって、そうした関数をうまく組み合わせて計算ソフトウェアをプログラムすれば、稚拙な初等数学を使った数式よりははるかに時間短縮したソフトウェアが出きあがることは言うまでもない。
-
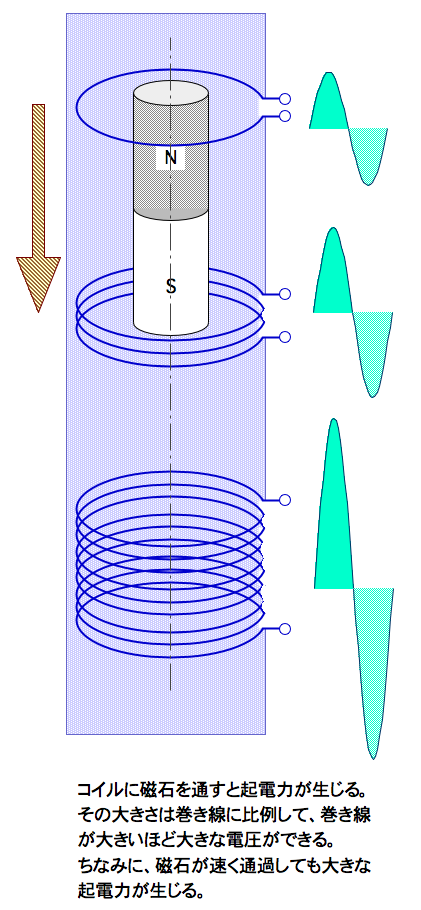
-
- 1-4-2. 変圧
-
- 交流電気の一番の特徴が変圧である。
- 電圧を自由に変えることができる。摩訶不思議だが事実である。
- 振動するものは往々にしてこういう現象が起きる。
-
- 例えば、光。単一の波長をある光学素子に入れると光を変えることができる。
- 移動体に音をぶつけるとその音の周波数が変わる(ドップラー効果)。
- 海洋の波を小さな湾に導き入れると波が高くなる(満潮干潮)、等々。
-
- この現象を説明するには、電気の持つ誘導理論を振りかざさねばならない。
- これはちと手厳しい。電気素子の一つにコイルと呼ばれるものがある。
- 電線をグルグル巻いたものである。
- このコイルが実は摩訶不思議な電気現象の立て役者なのである。
- このコイルに電気を流すと、流しはじめる時と流し終わる時にちょっと変な挙動を示す。
-
- コイルに電気を流そうとすると、コイルはチョット待ったと抵抗し、電気の流れを止めようとすると、それはないんじゃないかと引き止めようとする。
-
- まことに天の邪鬼(あまのじゃく)な素子である。
- おまけに直流(変化しない電圧もしくは電流)に対しては何の働きもしない。
- 交流成分にだけ監視の目を働かせ制限するような働きを持つ。
-
- しかし、この素子のおかげで多くの電気機器が作られたし、何よりも電力の供給というインフラ(生活基盤)を整備できるようになった。
- コイルが使用されている電気機器には、
- ベル、スピーカ、発電機、モータ、発信器、
- ドアロックやバルブを閉める電磁ソレノイド、
- ラジオ・テレビの受信回路電磁石、自動車の点火装置のイグニッションコイル、
- スライダック、電信柱から引き込まれる家庭電線の電圧を下げる柱上トランス
- などがある。
-
-
-
- 【トランス = 変圧器】
- 変圧器は、上に述べたコイルを使用している。右の図を見ていただきたい。小学校(私は確かに小学校で習った)や高校の教科書にでてくる図である。この図は、コイルの中に磁石を通すと、コイルに起電力が発生するというものである。巻き線が多いとたくさんの電気が発生する。自転車の前輪に取り付けられているランプの発電機は、実は、この磁石をタイヤを通じて一生懸命回している事になる。コイルの巻き数が多いと、磁石を勢いよく動かさないとコイルからの反撥で止まってしまう。発電所は、実は、この巨大なコイルをウンウンと回して電気を起こしているのである。この電機子は重い。手では絶対回らない。電機子を取り巻く磁界が強烈に強く、それを押しのけるようにして電機子が回り電気を作るわけだから。電機子を回すのに水蒸気の力を借りて羽根車(タービン)を回しそれに電機子を直結させて発電させる。水蒸気を作るお湯の沸かし方に、石炭があったり、重油があったり、原子力があったりする。水の落差でそのまま羽根車を回すのが水力だ。内燃機関(ディーゼルエンジン、タービンエンジン、ガソリンエンジン)で直接電機子を回すものもある。風で電機子を回すものもある。
-

-
- この磁石をコイルからの磁力線に変えて見たらどうだろう。それがその左の図である。
-
-
-
- 電気は、実は、電気が流れるとその周りに磁石と同じ磁力線を発することがわかっている。電気が流れる方向にネジを締める方向、つまり右回転(時計回り)に磁力線が分布する。電気が発生する磁力だから電磁力とも呼んでいる。性質は磁石と全く同じである。そうすると、上の図と左の図は同じ働きを示している。これが実は、変圧器(transformer)の原型である
- 図の左側の巻き線(一次側コイル)と右側(二次側コイル)の巻き線の比で、出力電圧が変わる。二倍の巻き線が二次側にあれば二倍の電圧出力になる。十倍になれば十倍になる。
-
【コイルの鉄心】
左の図は、概念的に示したものであるが、実際のものは、もっと緻密にコイルが巻いてあり、磁力線を効率よく二次側に伝えるために口型をした鉄心を使ってそれにコイルを巻き付け効率を上げている。鉄心には磁力線が通る道だから、ここではできるだけ材質による損失(鉄損)を避けたい。そのために磁力線が良く通る(透磁率の高い)珪素4%程度を含むケイ素鋼板の薄板にワニスを塗ってその間に紙等の絶縁層を施しこれを何枚も張り合わせて鉄心とする。
高価な鉄心は、鉄材自体が磁気方向に特性のそろったケイ素鋼板ができるようになって(冷間圧延によって圧延方向に良い磁気特性を持つ方向性ケイ素鋼板が製造されるようになって)、この薄板をグルグル巻いて重ね合わせた巻鉄心構造のトランスも使われている。
電力送電のあらゆる所に変圧器は使われるわけで、変圧の度に電力が損失するのは避けなければならない。これを鉄損と言うのだそうである。この鉄損は鉄心の中で電気エネルギーを消耗し発熱する。この発熱量は電気エネルギーのロスだけでなく、自らの発熱で変圧器を駄目にしてしまう。鉄心は当初純鉄が使われていた。これは発熱が大きかった。
- ■ ケイ素鋼板(Silicon Steel)
-
 1900年、イギリス人ハドフィールド(Sir. Robert Hadfield: 1858 - 1940)は、純鉄にケイ素(シリコン)を添加することにより固有抵抗が上昇し、鉄損が下がることを発見した。鉄の固有抵抗が低いと渦電流損失が大きくなるのである。
1900年、イギリス人ハドフィールド(Sir. Robert Hadfield: 1858 - 1940)は、純鉄にケイ素(シリコン)を添加することにより固有抵抗が上昇し、鉄損が下がることを発見した。鉄の固有抵抗が低いと渦電流損失が大きくなるのである。- 工業生産は、イギリスではなくアメリカで開始されケイ素鋼板(Silicon Steel)という名称で1903年に始められた。
- ケイ素鋼板は鉄の生産でも極めて生産の多い品種だそうで、全世界で年間約500万トン、日本で約100万トンが作られているそうである。
- 鉄損はあらゆる意味で排除しなければならず、ケイ素鋼板の発見以後、その改良が連綿と続いた。
- 基本的な改良方向は、板の結晶構造をなるべく一方向性に並べる工夫で熱処理や、レーザ処理などの手法を導入して熱心な研究が続けられた。
- 当初鉄心1キログラム当たり2.1Wの鉄損があったものが、1.2Wまで激減したと言われる。
- コイルと鉄心は絶対ショートさせてはならない。
- 特にコイルは電流が流れるので、絶縁被膜、絶縁紙で覆う。高圧になると熱などで絶縁が破壊しショートする。
- これは極めて危険だ。
- 外国製の高圧機器を輸入すると、必ずこの高圧トランスが危ない。
- 私は、このトラブルで何度も泣かされた。
-
- トランスは、通常重い。電力や電圧にもよるが、一般的に5kgぐらいから50kgまで。
- 電柱につけられているトランスはもっと重い。なにせ大事な電気を効率よく変換させたいからしっかりした鉄心に密にコイルを巻き付けるので重い。
- まあ、鉄の塊と思えばよい。
- コイルは、天の邪鬼(あまのじゃく)と言われていた。
- その気質は、相手に対して干渉する(相互誘導)働きと、自分にも電気を流さないとする干渉(自己誘導)の併せて二つある。
- 英語で誘導をインダクション(induction)と呼んでいるため、自己誘導(self induction)、相互誘導(mutual induction)とも呼んでいる。
-
- この干渉の度合いを示したものがインダクタンスと呼ばれるもので、H(ヘンリー)と呼ばれる単位で表される。
- この単位が大きいほど天の邪鬼の性質が強い。平たく言えばこれは抵抗の度合いである。
- この抵抗は直流では全く抵抗の値を示さず、周波数が高くなったり巻き線が多く線径が太くなると途端に癇癪を起こす(= インダクタンス H が高くなる)。
- 抵抗は通常、オーム(Ohm:Ω)(ドイツ人 George Simon Ohm: 1789 - 1854に由来)という値で示されるが、コイルの抵抗は、電流の移り変わる速さ(一般的に周波数 = Hz)で変わるので質が悪い。
- しかし、こんな複雑な性質をよく見抜いたものだと感心する。
- 【ヘンリー(Joseph Henry:1797 - 1878)】
 アメリカの電気物理学者。オルバニー(Albany)生まれ。
アメリカの電気物理学者。オルバニー(Albany)生まれ。- 貧しい家庭に育ち、苦学してオルバニー・アカデミーで工学を修める。
- 同校で1826年より数学、自然哲学を教える。
- 1929年から電磁石を発明したイギリスのスタージョンやフランスのノレの論文を読み大いに触発された。
- アンペールの理論を手がかりに電磁石の改良に着手し、空心コイルの代わりに鉄心を用いてコイルの巻き数と磁石の強さの関係を突きとめることに成功した。
- イギリスのファラディーと同時期に同じような研究と発見をした人で、電気の黎明期(1830年代)に科学基盤の整備されていない新大陸で電磁気の研究を行った。
-
- ヘンリーの大きな功績は、アイク(Philip Ten Eyck:1802-1892)とともに強力な電磁石を作ったことであり、電信技術に貢献した。
- 科学的には1830年の電磁誘導の発見が重要である。これはイギリスのファラディーとは独立の発見であり、自己誘導に関してはヘンリーの方が早かった(1831)。
- その意味で、ヘンリーは、電磁気学史上ファラディーと並ぶ重要な功績者であった。が、両者の研究条件や社会的条件は対照的で、ファラディーほど大きく脚光を浴びることはなかった。
- 当時アメリカには、ファラディーが利用したような研究所や研究組織はなかったのである。
-
- ヘンリーは、1832年、ニュージャージー・カレッジ(現プリンストン大学)で自然哲学教授となる。1846年には新設されたスミソニアン研究所の所長となりアメリカ科学振興のために力を尽くした。
- 現在の科学技術のレベルを見るとその差は歴然で逆転してしまっている。
- 19世紀にきら星の如く現れたイギリスの科学者も20世紀に台頭したアメリカの科学技術、特に、大学(プリンストン大学、マサチューセッツ工科大学、UCLA、カルフォルニア工科大学、シカゴ大学)や、サンディア、ローレンスリバモア、ロスアラモスなどの国立研究所の前に屈したような形になっている。
-
- 彼の功績に対し、1893年にシカゴ国際電気工学者会議では、電気単位の一つに「ヘンリー H 」を選ぶことに決めた。
- ヘンリーの単位がどういう計算式に載せられているかをちょっと紹介しておく。
- インダクタンスは交流の抵抗のようなものと述べたが、コイルが交流の中で示す抵抗を誘導性リアクタンス(XL)と称し、
-
- XL = 2π f L
- XL: 誘導性リアクタンス = インピーダンス(オーム)
- π: 円周率(3.1416)
- f: 電源周波数(Hz)
- L: コイルのリアクタンス(H:ヘンリー)
-
- で表す。
- Lは、巻き線が多いほど、巻き径が太いほど、またコイルに鉄心が入っていると大きな値を示す。
- 上の式からもわかるように、交流のコイルの抵抗(XL)は周波数が高いほど大きい事を表す。
- 電圧と電流、抵抗の関係式で最も基本的なものはオームの法則で、
-
- I = E / R
- I:電流(A アンペア)
- E:電圧(V ボルト)
- R:抵抗(オーム)
-
 で表す。オームの法則は、直流回路で成り立つ法則である。
で表す。オームの法則は、直流回路で成り立つ法則である。- 交流の場合は、今述べたようにコイルを使っていると交流の周波数によって流れる電流が変わる。
- このとき上にのべたリアクタンスが効いてくる。これをコイルでの関係に当てはめると、
-
- I = E / XL
- I:電流(A アンペア)
- E:電圧(V ボルト)
- XL:誘導性リアクタンス = インピーダンス(オーム)
-
- I = E / 2π f L
- I:電流(A アンペア)
- E:電圧(V ボルト)
- f:交流周波数(Hz ヘルツ)
- L:インダクタンス(H ヘンリー)
-
- となる。
-
- 交流では周波数が高くなると電流が流れなくなり、周波数が0だと分母が0になるから、コイルは抵抗の働きをなさず電流がドッと流れる。
- こうしたコイルの誘導性リアクタンス(XL)やコンデンサが交流に対して作る容量性リアクタンス(XC)と、本来の直流成分に対して持つ抵抗(R)を加味した総合の抵抗をインピーダンスと称している。
- インピーダンスは交流に対するマクロ的な(全体を概括した)値であり、ミクロ的には電圧や電流の変化で時々刻々絶えず変わっている。
- 前にも述べたが、コイルには、変圧器のように複数を近接して配置すると相互に影響を及ぼし合って、互いが互いを干渉し合う性格がある。
- これを相互誘導と呼んでいる。
- つまり電流が流れようとすると自分が流さないようにする性質(自己誘導)はもちろん、近接したコイルがそのコイルに干渉して流さないようにするのである。
- この値は、それぞれの自己誘導係数(自己インダクタンス(L1、L2)の積の平方根となることがわかっている。
- が、あくまでも理想で、最大値と言うことになっている。
-
- M = √(L1 x L2)
- M:相互インダクタンス
- L1:コイル1のインダクタンス
- L2:コイル2のインダクタンス
-
- ただ、現実には、この値にはならなくて半分くらいの値となる。
-
- M = κ x √(L1 x L2)
-
- この係数κが結合係数と呼ばれていて、鉄心を入れると1に近くなり、鉄心を入れないと0.5程度となる。

- 1-4-3. 三相と単相
-
- さて、交流が電力の送電上、また、動力(モータ)の確保の上で大事なものだと言うことがわかった。
- 電力の系譜がボルタの電池から始まって、直流発電機の発明と発展に移り、偶然の発見からモータの出現を見た。片や、電灯の発明と発展から送電という大命題に直面し、交流発電と送電が発展したこともわかった。交流発電から交流モータも発展し、動力と灯りを電気から得るという人類の知恵も授かった。
-
- 実は、電気にはこの動力と灯りの他にもう一つ、いや二つに対して非常に大きな働きをなした。
- それは、「通信」と「コンピュータ」である。
- この話題は別に改める。
- 電力を送るやり方に、単相交流と三相交流があるのをご存じだろうか。
- 現実に、電力会社では三相による電力を送っている。
-
- 【三相交流技術の確立】
- 何度も述べるが、発電、動力の方式には大きく分けて直流方式と、交流方式があり、上でも述べた通り、利権をめぐる激しい争いがあった。
- 交流方式の発電も米国エジソン研究所(後ウェスチングハウス)のテスラが考えた二相交流と、ドリヴォ・ドブロウォルスキー(ドイツ人AEG社アルゲマイネ社)の考えた三相交流があった。
-
- 二相交流は、はじめ、4本の導線を使って送電していた。この方式は、単相交流の周波数の位相を90°ずらした二組の交流電源を発電させて電動機に与える方式で、合計4本の電線を必要とした。
-
- テスラの方式には効率的にも難点があった。
- ドリヴォ・ドブロウォルスキーの三相交流はこれを見事に克服した。彼は、フェラリスの論文を読んで、まず回転子をかご型巻線にする工夫をした。次に位相の数を増やすことによって非同期電動機の固定子周辺の磁力分布を改善できると狙いをつけて二相よりも三相に的をしぼった。
- まず巻線を研究し、巻線の120°をなす三点からの分岐線を出すことで位相差が120°の三相交流を発生させることに成功した。次いでこの三相が回転磁界を生み出すことも確認して、これに「トレー・シュトローム(Drehstroms:回転電流)」と名づけた。
- この回転磁界を利用して、1889年には出力約100Wの最初の三相交流非同期電動機の制作に成功している。三相交流システムを確立するには、個々の電気機器の製作とともに送電問題にも目を向けざるをえなかった。これについてもドリヴォ・ドブロウォルスキーは1889年に三相変圧器を作り、翌1890年には三相四線式の交流結線方式を編み出した。

-
- このA.E.G.社(アルゲマイネ社)の電気技師ドリヴォ・ドブロウォルスキーが考え出した三相交流電力システムは、卓越したアイデアだった。発電機そのものの電力が、モータに入れればそのまま回転磁界を作って簡単に回すことができる。送電の電力線も少なくてすんだ。1891年、フランクフルトでの送電実験は、これらの発明をもとにして行われ、75kWの交流非同期電動機と150KVAの三相変圧器が使用された。発電機は、ドリヴォ・ドブロウォルスキーと協力していたスイスのエリキン社技師長ブラウンが作った。この送電実験は、送電電圧15,000Vで最小送電効率68.5%、最大75.2%という素晴らしいもので、これによって三相交流送電システムの方向性が決められた。
-
-
-
- ●三相交流電力のもう一つの御利益
-
- 電気を扱う技師たちはこの三相交流電源を単相交流と区別して「動力」と称している。工場の生産設備などで3相交流電源を使うというとまず、「大きなモータが使われているな」、とピンとくればかなり通になったと言ってよいだろう。3相交流のもう一つの特徴はこれを電力として取り出す場合消費電力に比して各線に流れる電流が58%ですむ。
-
- 例えば、20kWx3本(60kW)のヒータを使った加熱炉を考える。AC100Vの家庭用コンセントからこのヒータを使用すると、
-
- 60,000W÷100V = 600A
-
- 600Aの電流が必要であり、200Vの電源でも300Aの電流が必要である。しかし、これを3相交流200Vの電源を使用すると、
-
- 60,000W÷200V ÷√3 = 173A
-
- 173Aですむことになる。電流が少ないことは電線を小径化する特典がある。クルマのバッテリーにつながれているケーブルはかなり太いことにお気づきであろう、バッテリーの電圧は12Vなので、100W程度の電力でも10Aの電気が流れる。線が細いと加熱して線材が焼損してしまう。電力送電の基幹部では500KVの送電が行われているのも理解いただけるであろう。
-
-
-
-
-
- 1-4-4. 電気の基本 その1:電気の流れ
-
- 電気は、電圧の高いところから低いところへ流れる。抵抗の低い方へ流れる。
- これが基本。直流はそうだ。
- では交流はどうか。
- 答えは、同じだ。
-
 交流電源は、時々刻々電圧が変わるがその時に高い位置にある電位が低い方に流れている。
交流電源は、時々刻々電圧が変わるがその時に高い位置にある電位が低い方に流れている。- 電気の流れはとてつもなく速いので、1秒間に50回程度の交番など太平洋の大波のようにゆっくりしたものでしかない。1/50秒の間に電圧が高くなって0になって反対側に大きくなって0になる。
- 電子の流れはとても速いから、そのうねりに沿って低い方へ流れていく。満ち潮と引き潮のように。
-
- 行ったり来たりの電子の流れで、果たして仕事がちゃんとできるだろうか。
- 答えは、ちゃんとできる。
-
- まず、モータ。これは、発電機の反対だから、交流だろうと直流だろうと発電機と同じ構造のモータを使えばちゃんと回って仕事をする。潮の満ち引きと同じようにタイミングを取って電機子が回るから交流の方が都合がよい。
-
- 次に、ランプ。蛍光灯は交流でないと点灯しない。
- たしかに直流でも点灯はする(点灯時には始動のための高圧点灯電圧が必要)。
- が長続きしない。点灯と同時にどんどん電気が流れフィラメントが切れてしまう。
- 直流用の安定器を作らないとダメ。
- また、蛍光灯両極のフィラメントの一方のみが片ベリしてしまう。
- 屋外にある街路灯(ナトリウムランプ、水銀灯、HMIランプ)は放電灯と呼ばれる蛍光灯の仲間で、これらは交流でないとうまく点灯しない。
- 理由は、放電のために始動に高圧を用いるため交流方式にして高圧回路を作った方が作りやすいことと、蛍光灯と同じように安定器を直流用にしなければならないこと、それに電極の消耗が激しいためだ。
-
- 白熱電球は、ホントは直流点灯が望ましい。ホントは。加熱発光であるから直流点灯の方が発光が安定している。自動車のヘッドライトやランプは全てバッテリーからの直流点灯である。
-
- じゃあ、家庭用の白熱電灯も直流にしようか。
-
- これはできる、が、直流電源で100V、100Wを作るのは大変だ。
- ものすごく大きな直流電源を作らなければならない。お金がかかる、と言うわけで、白熱電球は交流をそのまま使用している。白熱電球を交流で使うデメリットは、フィラメントの発光が周波数により明るくなったり暗くなったりすることと、フィラメントが暖められたり冷やされたりで膨脹・収縮を繰り返すため寿命に問題が生じることである。
- しかし、これらは交流使用のメリットを考えれば小さな問題だ。
- フィラメントを太くすることによって熱容量を増し、50Hz程度では直ぐに冷えないようにして発光のチラツキも抑えてある。
- 学術用に使う校正用の標準光源はもちろん直流電源で、高価な直流電源回路を使ってフィラメントに電流を流している。
-
- 蛍光灯の方がよほどちらつく。
- 蛍光灯は、最近、インバータ付きというのが販売されている。
- inverterとは、英語で変換という意味である。
- 何を変換しているのか?これは、発光の繰り返しを商用電源周波数(50Hz、西日本は60Hz)そのまま使うのではなく、それよりも高い周波数をインバータで作って、人間がイヤだと感じるフリッカー(チラツキ)以上の周波数で発光させるというものだ。
- 我が家にもそのインバータ蛍光灯を二部屋入れている。
- 蛍光灯本体は割高だったが、結構明るい(と感じる、インバータが最適な電源を供給しているのかな?)。
- ラジオをその灯体に近づけてもノイズがでない。
- 居間にある古い蛍光灯はノイズが多い。
- 同じ居間に同じ蛍光灯が二つあるのだが、その一つはランプが古くなって黒ずんでいる。
- こちらの蛍光灯は激しくノイズを出している。
- 放電を繰り返しているわけだからノイズが出るのは当たり前。
- ノイズを出さないように蛍光灯内部にノイズ吸収フィルタがつけられている。
- 高価な器具ほどしっかりしている、一般的に。
-
- その他のものはどうだろう、交流と直流どっちが便利なのだろう。
- たとえばオーディオ。これは、交流電源をそのまま使用していない。
- 装置の中に交流電源を直流に直す電源部と呼ばれるものが入っている。
- テレビも、ラジオも、コンピュータも、最近のデジタルと呼ばれるものは間違いなく直流電源を使用する。
- 従って、それらの中には電源部が大なり小なり入っている。
- あるものは大きなトランスを抱え、あるものは基板の上に載るほどの小さなモジュールだ。
-
- もっと簡単なものになるとACプラグに黒い固まりとしてそこでDC電源を作って機器に送っている。ACアダプタというやつだ。
- これらは、いずれも使用する電力によって大きさが異なる。
-
- オーディオに使用する直流電源は、直流電源の極みだ。音の出力如何に関わらず一定の直流電圧を維持しなくてはならない。
- オーディオアンプは、安定した直流電源の設計が重要な要素だと言われている。
- 安定した電源を得るため、大きなトランスを使うからアンプは重いほど性能が良いと信じている人もいる。
- (私は必ずしもそうは思わない)。
- オーディオアンプの電源が非力で、大出力時に電力が足りないと電圧が落ちて音の波形が歪んでしまう。
- したがってどんな出力に対しても一定の電源を確保するため、電源部はしっかり作らなくてはならない。
- それも100Vという高い電圧ではなく、5Vとか12Vとかの低い電圧で安定した電力を作って供給している。
-
-
- 1-4-5. 電気の基本 その2:
-
- 電子の流れ
- 上の項では大きな電気の流れについて述べた。
- 今度は電子について述べる。
- 大きな川の流れを説明したかと思えば、今度は水の分子についてのべるようなものである。
-
- 電気と言っても幅広い学問である。
- 電気の基本は、言うまでもなく電子の流れである。
- 電子の作用でいろいろな働きをなす。
- 電子は地球上のありとあらゆる所にあり結構なスピードで動いている。
- あるものは相互に引きつけあい、あるものは反撥し、あるものは雪崩のように流れとなって移動する。
-
- 電気を広い見知からながめると、電気は負極(-)から正極(+)へ流れる電子の流れである。
- もしくは、真空や空気の絶縁された中でお互いににらみ合った(帯電した)状態である。
- 電子は絶えず引きつけられたり反撥しあったりして運動している。
- それが一定の量になると電気の流れになる。
- 導線を伝われば電流となり、空中を伝われば放電となる。
- 空中を一気に電気が流れると(電子なだれ)、それは雷と同じでまばゆい発光を伴ったアーク放電となる。
- すべての物質を構成している原子は電子を持っている。
- 原子を構成する電子は離れたり近づいたり、電子を共有したりしている。
- こうした電子の原子への関わりが様々な現象を引き出す。
-
- 電子が流れることによって発熱を促す。発熱が高じて光を出すようになる。
- 電離しやすい気体の中を電子が流れると放電を起こし発光を伴う。
- 磁界の中で電子が流れると力を受ける。
- 化学物質に電気を通すと化学変化を起こすことができる。
-
- また電子一つ一つは、以下でも述べるように外に対して力を及ぼしている。人間の体臭と同じように電子は電界と呼ばれるものを発散している。それはまたあたかもクモの巣のように空間を覆っている。
-
- 電子の流れや塊が大きいときそれらによって作られる電界は強くなる。また電子が激しく振動するとそれが外に対して及ぼす電界が強くなる。
-
- これらが電波と呼ばれる本質である。
-
- ミクロ的に見る電子は、電子粒とその電子の一群が作る電界と磁界の相互作用である。この電界と磁界の相互作用の理解が結構難しい。
- 現象的には、電波やモータなどにこの理屈が盛り込まれている。
-
- 電気と磁気の間の関係は、1820年にエルステッドによって電流の磁気作用が発見され、2年後の1822年にはアンペールにより定量的に表現された。
- 1830年には米国のヘンリーによって自己誘導作用、1831年にはイギリスのファラディーによって電磁誘導作用が次々と明らかになった。
- こうした電磁気学から電波への理論体系が出来上がっていく。
-
- これらのミクロ的な見知から電子を体系づけた人にスコットランド人マクスウェル(James Clerk Maxwell、1831-1879)がいる。
- 彼は、電子が波の働きを持ち、また粒子であることを理論的に導いた。これが無線通信の原理的なバックボーンとなっている。
- 電磁波現象はファラディーが明らかにしていたが、方程式として普遍的な定理まで押し上げたのは若き天才マクスウェルの業績だった。
- マクスウェルは1864年に電波の理論的な体系を予言し打ち出した。
- 電子の波は光と同じ速度で進むことを予言し、光も実は電磁波の一種であることを示した。
- この予言は、ヘルツらによって実証されていく。
-
- 従って、電気を電力のような大きな流れとしてみる場合には水の流れのような考え方(概念)を導入すればよい。
- そして、非常に高速な、かつ微小な範囲で電気を見るとき、電気は光のような存在として見ることができる。
- 光も波として振る舞うこともあれば粒子として振る舞うこともある。
-
- この相互作用の理解は私にとってはホントに難しい。(私が死ぬまでに理解できるかしら??
-
-
-
- 【電磁波】
-
- 電磁波と呼ばれる言葉が日常でよく使われるようになっている。
- 携帯電話、ラジオ、テレビなど無線通信が一般的になるにつれ、これを扱う際に好むと好まざるとに関わらずどうしても電磁波という言葉が出てしまう。
-
- 電磁波という言葉は何やら体によくないような響きがある言葉だが、実際は少し違う。
- 太陽の光だって電磁波の一種である。一概に体に有害だと考えるのは早計だろう。
- 電磁波は至る所にある。
- 雷が鳴れば四方八方に電磁波が広がる。
- 自然界にもたくさん電磁波が存在するし、ラジオやテレビ、無線、携帯電話などは電磁波を積極的に使っている。
-
- しかしこれらの電磁波はきわめて微弱である。
-
- 微弱ではあるが電波を受ける機器は周波数を感度よく検知しそれを質よく増幅して使っている。
- 電磁波は電場(電気が集まっているところ)と磁場(磁石のあるところ)の一方が動くとそれに影響されてそれぞれに歪みができる。
- その歪みを打ち消そうとして電場も磁界も変化が起こり振動となり波となる。
- 水面に小石を投げると水面に波が伝わるように、磁場や電場の世界も同じように歪んで拡がる。
- この時、電場と磁場は一定の関係がある。
-
- 電磁波が、その発生源を離れて、空間を伝わっていくためには、電場の変動が磁場を生んで、その磁場の変動がまた電場を生むと言う具合に、相互の助け合いが完全でなければならない。
- つまり、電場と磁場は互いに垂直で持ちつ持たれつで伝わっていく。
- 電磁波の速度は、電場、磁場の強さによらず一定で、真空では光速である。
-
-
-
- ■ マクスウェル(James Clerk Maxwell: 1831 -1879)の予言 (2001.03.05)
 1864年に英国人物理学者マクスウェルが予言した電磁波は、電界と磁界の絡み合った電磁界の乱れ(ゆらぎ)の横波(伝わる方向と直角の方向に振動する波)となって、エーテルで満たされた空間を高速で伝わるものであり、光もこの電磁界の波動の一種であるとした。
1864年に英国人物理学者マクスウェルが予言した電磁波は、電界と磁界の絡み合った電磁界の乱れ(ゆらぎ)の横波(伝わる方向と直角の方向に振動する波)となって、エーテルで満たされた空間を高速で伝わるものであり、光もこの電磁界の波動の一種であるとした。- (エーテルは後に存在が否定される。エーテルなしで電磁波は空間を光速で伝搬する。)
- マクスウェルの理論は難解であったため長い間理解されなかった。
- 当時、ヘルツの恩師であったヘルムホルツでさえもマクスウェルの理論を間違っていると思ったという。
- また当時の著名な物理学者のケルビン卿にいたっては1888年にヘルツが電波の存在を実証した後でさえも完全に信ずるまでには至っていなかったと言われている。
-
- 一方、マクスウェル理論の数少ない理解者の一人にアイルランド人物理学者フィッツジェラルド(George Francis FitzGerald: 1851 - 1901)がいた。
- 彼は、1879年に光の反射と屈折の問題がマクスウェルの電磁理論により説明できることを示した。
- マクスウェルは一様な媒質の中を伝わる波動しか扱わなかったため、屈折率の異なる媒質の境界にも適用できることを示したフィッツフェラルドの研究は、マクスウェルの理論の正しさを示す証拠となった。
- しかし電気的方法を使って光は作れるかとか、もし波が作れたとしてもそれがはたして光と同じ性質を持つかという疑問は依然として残ったままであった。
- 光のように波長が1,000分の1ミリにも満たない波、すなわち周波数で1014にも達する波を電気的に作るのは不可能かもしれないが周波数の低い波を作るのは易しい。となると、マクスウェルの理論を証明する波は、たぶん107 = 10MHzの桁くらいの周波数で作られるであろうと、1882年にフィッツジェラルドは予言したのである。
- この予言通りにヘルツは50MHzで電磁波を実証した。
- フィッツジェラルド自身は、とくに発明や発見をしたわけではないが、マクスウェル理論の正しさを証明し、電気的方法によって作れる波の波長を予言した。
- フィッツジェラルドは電波の歴史の中で陰に隠れた大きな貢献をした。
-
- マクスウェルの方程式を概説すると以下の4点に集約される。
-
- (1) 電界(電気力線)は電荷から放射状に広がる性質があること。
- (2) これに反して磁界(磁力線)はぐるりと輪をかいて元に戻る性質があること。
- (3) 電気が流れると、その通り道(それが導線であってもなくても)の周りに磁界ができること。
- (4) 磁界が変化すると、その周りに電界ができること。
-
- 1864年、マクスウェルが電磁理論を発表したときは、これほどスマートにまとめられてはいなかった。
- 今のような形になるには、ハビサイドやヘルツなどによる長い間の努力が必要であった。
- マクスウェル方程式の大事な部分は、(3)と(4)である。
- (3)は、たとえば電線に電流を流すとその近くにおいた磁石の針が振れるように、電線の周りに電流による磁界ができるというアンペアの法則として認められている。
- マクスウェルは、この法則を拡張して直流が流れると磁界が発生すると考えた。
- 変化する磁界ができればファラデーが発見した(4)の法則によりその周りに変化する電界ができる。
- こうして交互にできる電界と磁界は、波となって外側に広がっていく。
- これがマクスウェルの電磁理論の要約である。
-
- マウスウェルは、この電磁波がもつ波動としての性質をすべて備えているのは光であるから、光は電磁波の一種に違いないと考え、また光より長い波長の電磁波がこの世に存在するはずであると予言した。
- 20年以上も後になって、これを証明したのがヘルツである。
- - 「無線百話 - マルコーニから携帯電話まで」- 若井 登 監修、平成9年7月10日初版、無線百話出版委員会
-
-
- 電子は、原子を構成しているものなので、小さいといっても大きさもあれば質量もある。
- 電子は電気の力を持っている。電子1個には電荷という単位が割り当てられている。電荷は原子を形作る「力」である。そして電子は高速で移動する。また電子はそれ自体自分でスピン(回転)していることが明らかになっている。電荷を持ったものが回転をするのであるから運動量という「力」の他に磁石のような振る舞いをするようになる。「電子磁石」である。磁石は電子の配列が(原子の配列が)よく揃って電子磁石が効率よく同じ方向を向いて磁界を作っているものと見なすことができる。電子1個が磁界を持っているのであるから電子が動けば磁界も動くことになる。また電子は電荷を持っているから電子が動けば電荷が動くことになり電界ができる。
-
【電子とは?】
- 電子とは何か?
-
- だんだん難しくなっていく。
- この世の物質を構成しているもっとも根幹をなす要素の一つが電子である。物質の素は原子であることを中学時代に習った。その原子も実は原子核と電子で構成されていることがわかった。その原子核も陽子と中性子で構成されて、その数によって、水素、ヘリウム、リチウム・・、と元素ができていることがわかった。その陽子も・・、という具合にどんどん小さな素粒子の存在が明らかになった。しかし、電子だけは、どうもそれ以上は細かくなりそうもない素粒子なのである。電子は、我々の身の回りにあっていろいろな働きをし、かつどんな極微の世界でも自己を主張している存在である。
- 電子は、このように一つ一つと数えられる粒子であることが確かめられてきた。もちろん、粒子の性質とともに、波としての性質も併せ持つ。
-
- 電子は小さい、ホントに小さい。
-
- 電子の大きさはよくわかっていない。ぼんやりとした存在なんだそうである。原子モデルはいろいろな会社のロゴにもなったりして想像することができるが、原子の大きさは1億分の1センチメートルで原子核の大きさは数兆分の1センチメートルだそうである。この比は1/20,000〜1/30,000である。約80mmの野球ボールを原子核になぞえると電子は1,600メートル〜2,400メートルの遠い軌道を描いて取り巻いていることになる。だから原子は隙間だらけの構成で広い空間に原子核が点在していてその周りをせわしなく電子が取り巻き原子核との量子力学的なバランスを保っているのである。このように原子核は原子の大きさに比べると極端に小さなものであるが、重さとなると話は別で原子核自体が原子全体の重さを決定してしまうほどである。言い換えればそれほど電子は軽いのである。しかし電荷はしっかり持っている。それが電子なのである。
- この電子の粒が何億個と集まって、電気として外から見える働きになる。例えば、電球を灯すとか、モータを回すとか、ラジオを鳴らすとか。
-
- 我々が100Wの白熱電球をともすとき、AC100Vという電位の差(電圧)で1A(アンペア)という電流を流す。1Aというのはアンペールという学者にちなんでつけられた名前で単位時間に流れる電気の量を示す。学術的には1秒間に1C(クーロン)の電荷が流れる時を1Aと呼んでいる。電子1個の電荷は、 e = 1.602 x 10-19 C(クーロン)であり、1クーロンは電子が6.24 x 1018 個集まったものであるから、1Aは1秒間に6.24 x 1018 個の電子が流れる。しかし、実は電流の値は別の算定から割り出されたものであった。それは電流の「力」から計られた。電荷の単位であるクーロンも以下に述べるフランスのクーロンによって「力」から求められたものであった。電流の根本の定義は以下で決められた。
-
- ■電流の強さの単位
-
- 電流が流れるとその周りに磁界ができる。
- 逆に磁界の中の電流は磁界から力を受ける。
- 従って電流が正反対に流れている電線では互いに反発しあう力が働く。その斥力を測定して電流の強さの単位(アンペア)を決めた。
-
- 電流の強さ1:
- 真空中1mへだてて平行におかれた無限に小さい円形断面をもつ無限に長い2本の直線導体に電流が、長さ1m当たりに及ぼし合う力が、2x10-7(N)であるとき、その電流の強さを1Aときめる。
-
- この値の定義は電磁気を調べて行くときに大事な値となるが、一般的な生活においてはさほど重要性を持つものではない。
- 電流の流れの強さのもう一つの定義、
-
- 電流の強さ2:
- 1A(アンペア)の電流が流れているとき、導体の断面を1秒間に流れる電気の量を1クーロン(coul.、記号C)という。
-
- の方がわかりが良いかも知れない。
-
-
-
- 【物体相互の力の求め方】
- 電子の解明で宇宙がわかってきた。極小と極大の話であるがホントの話。質量を持ったものは相互に引きつけ合う力を持っていることに気づいたのは、イギリス人ニュートンであったが、この万有引力の力を測定し、2つの質量(m1、m2)をもつ物体が相互に引きつけ合う力を、
-
- F = G (m1・m2/r 2)
-
- と定義づけたのは、同じイギリス人キャベンディッシュ(Henry Cavendish、1731-1810)であった。
- この法則によると、質量(m1、m2)が大きければ大きいほど(例えば、地球や太陽のように)互いに引きつけ合う力が強く、その距離(r)が近ければ近いほどその力が強くなる。
- キャベンディッシュは、158kgと0.738kgの大小2つの鉛の玉とねじれはかりを使って互いに引き合う力を測定した。
- その結果、万有引力定数Gは、
-
- G = 6.67 x 10-11 Nm 2/kg 2
-
- となることを導いた。
- これに地球の質量を入れれば重力加速度が求まる。
- キャベンディッシュは、逆にこの定数と地球の半径及び重力加速度から地球の質量と密度を求めた。
- この方程式は、ニュートンの考えを宇宙にまで拡げる画期的な事だった。
- これが、実は、電子の力にも応用されるのだ。
-
-
- 【キャベンディッシュ Henry Cavendish (1731-1810)】

- キャベンディッシュは、イギリスの名家の家に生まれ、天才の名を欲しいままにしたが学位を取得しなかったり生涯独身を貫いたりと、常人とは違った生き方をした。
-
- 彼の名前をつけたキャベンデッシュ研究所は、ケンブリッジ大学の付属物理研究所であり、オックスフォード大学のクラレンドン研究所と並び称せられる有名な研究所である。
-
- 1874年、キャベンディッシュ一族の莫大な財産で作られたこの研究所は、初代所長がマクスウェルであり、その後、レーリー、J.J.トムソンらが続いた。
- 第一次大戦後は、ラザフォード、アストン、コッククロフト、ウォルトン、チャドウィック、G.P.トムソン、ディラック、ファウラーらの量子力学学者を排出している。
- 第二次世界大戦後は、ライル、ワトソン、クリック、モット、ジョセフソンらを輩出し、ノーベル賞受賞者は2012年まで29名を数えている。
-
- 高速度カメラ分野でも世界的な権威であるJohn E.Field教授が衝撃波の研究でユニークな研究を発表している。
-
-
-
- 【クーロン】(Charles Augustin de Coulomb、1736-1806)
 クーロンは、フランス人。
クーロンは、フランス人。- 最初、土木工学に携わり要塞、運河、港湾建設に従事した後、電気・磁気に関する力の研究に傾倒していく。
- 電気が力を及ぼし合っているという考え方と、実験によるクーロンの法則は、キャベンディッシュが導いた万有引力の法則と同じであった。
-
- F = κ(Q1・ Q2 / r 2)
- 彼は、この実験を行うのに「ねじれはかり」を使った。
- これはキャベンディッシュと同じ方式だが、キャベンディッシュのように158kgの鉛玉を使う必要はないためコンパクトなものだった。
- クーロンは、このねじりはかりを使って、
-
- 電気定数κ = 9 x 109 Nm2/C2
-
- を導き出した。
- Qは、電気量とした。
- Qは、キャペンディッシュでは物体の質量に相当するものであるが、電子は小さい上に動きが速いので力を及ぼす別の単位として電気量、クーロンが使われた。
- 1クーロンは、1アンペアの電流が流れている導線の任意の断面を通して1秒間に流れる電気量である。
- その後の研究で、電子は、
- 1個当たり、 e = 1.602 x 10-19 C(クーロン)の電荷量を持つことがわかり、
- 1クーロンは、電子が6.24 x 1018 個集まったものとなった。
-
- C.A.クーロンの電気素量の測定により、電気が物理的な力を持つことがわかった。これが集まって、電界というものができることは容易に理解できる。電子は力の及ぼす場を作り、この数がたくさん集まって力となる。これは、電子のような小さな粒子だけでなく地球や月、太陽が相互に及ぼし合っているのと同じ理屈だ。電子の大きさは、2.818 x 10-15 m (ただし、はっきりしたことはわかっていない)で、重さは、9.11 x 10-31kg である。これは、素粒子を扱う分野以外ではおそらく最も小さく、軽いものである。いたるところにあるものなのに決して見ることはできない。その存在さえも最近までわからなかった。その振る舞いにまだまだなぞがある。
- 現在でも、電子は決して見えない、と言うことで帰結している。何となくぼんやりした存在それが電子なんだそうである。このことはハイゼルベルグが唱え、現在に至っている。
-
-
- 【電子のスピン(回転)】電子は、原子の中では原子核の正の電荷ときっ抗して、原子核の周りをつかず離れずの位置にあって運動をしている。電子の運動は電子自体の自転(スピン)と原子核の周りを回る公転である。電子の自転であるスピンは、ある一定の回転(角運動量)で永久的に回っている。永久に回るというのはすごいなぁ。未来永劫回り続けるのが電子のスピンだ。電子のスピンは物理量として、
-
- 電子スピン S = h / 2 π
- h:プランクの定数、 h = 6.63 x 10-34 Js
-
- という運動量を持つ。
- マイナスの電荷eを持つ電子がこうした回転力を持つと、非常に小さい世界ではあるが、電荷が円運動をすることになり、円電流による磁力線が形成される。
- つまり、電子自体がもはや磁石ということが言えるのである。
-

-
- このスピンを行う電子が原子の中でたくさん集まって、ある方向を持つと金属内部で「磁化」と呼ばれる現象がおきる。
- 電子のスピンによって金属外部に及ぼす力を磁気と言い、これにより磁場ができる。
-
- 電場は、電子の電界である。磁場も電場も電子の働きで起きる力の場であるので、いともたやすく行き来ができる。
-
- 電場と磁場の違いや相互の及ぼす関係がいまいちすっきりとわからないかも知れないが、- 電子自体が外部に及ぼす力(電荷)や力の場(電位の場)を電場(電界)といい、- 金属や磁性体を介して外部に及ぼす力を磁場(磁界)
-
- と呼ぶようである。
-
- ただし、これは、このような言い方で言い切っている本が他になく私が納得した考えであるので、この説明は違うかも知れない。
- 間違っていれば訂正する。
- この両者はともに電子の振る舞いから発生していることは間違いのない所である。
-
- 電子が自転している(スピンしている)というのを気づくまでには相当の苦労があったということが、朝永振一郎博士の書いた『スピンはめぐる』1974年という本に書かれているそうである。
- 電子はいついかなる時でも気温が高くても低くても、気圧が高くても低くても、どんな場所でも一億年前も一億年後も、化学反応を起こしている間でも常に自転(スピン)しているのだという。
-
- 電子が自転しているという着想を最初にしたのは1925年頃、クローニッヒ(R. de L. Kronig)という人だったらしい。しかし、彼の考えは当時物理学学界で強い発言力を持っていたオーストリア生まれのスイスの物理学者ウォルフガング・パウリ(Wolfgang Pauli 1900 - 1958)によって全く無視されてしまう。
- その半年後、当時まだ大学院の学生であったガウシュミット(Samuel Abraham Goudsmit 1902 - 1978)とウーレンベック(George Eugene Uhlenbeck 1900 - 1988)の二人が電子のスピンに関する論文を発表した。
- さらに1928年、イギリスのディラック(Paul Adrien Maurice Dirac 1902 - 1984)は「相対論的量子力学」を発表する。
- この理論には「電子のスピン」が盛り込まれていた。
- ディラックは電子のスピンを予言したのである。
- この前後、電子のスピンが実験的に確かめられ、電子はスピンしていることが決定的となった。
- しかし、電子のスピンは始めから終わりまで「相対論的量子力学」によるものであるため、地球の自転やコマの自転とは本質的に異なるものであるらしい。
-
- しかし誰も電子のスピンを見たものはいない。電子すら見たものが無いのである。原子核の周りを一定の軌道上(原子核の大きさに比べて20,000倍から30,000倍という驚くほど遠くの距離で)で存在し離れたりついたり、ある時は別の原子と電子を共有したり、その電子は雲のような状態で存在している。
- そして電子1個はスピンという運動量を持っていて、スピンによって電子の持つ電荷が回転するために、その回転によって磁力線が発生して磁場を作っているというのである。
-
- 電子は内部構造がなくしかも極めて小さな点状であるらしい。こうした電子の動きが電磁波を発生することになる。
- アンテナの金属棒で電子が激しく行き来するとアンテナ棒の周りの電場が変化し磁場を道ずれにして相互作用で電磁波が光速で拡がっていく。
- マクスウェルの理論によれば、電界は放射状に広がる性質があり磁界は輪をかいて元に戻る性質があると説明し、電磁波は電界と磁界が90°方向を変え相互に相補い合いながら媒質のない真空中でも進んでいくのだと説明している
- (参考:マクスウェルの予言)。
-
-
- 1-5. 磁石と電気
-
- 難しい話が続く。
-
- 電気を機械的な力に変えるには、磁石の話を避けて通ることはできない。
- ここでまとめておきたいことは磁力についてである。
- 金属を引きつける磁石は一体どういう仕組みになっているのか。 磁石と電気コイルで起きる電磁石にはどういう関係があるのだろう。 電子が流れると電界ができるが、電界と磁石の作る磁界はどういう関係があるのだろう。
-
- ここらあたりはかなり難しくて、理解するのも説明するのも難しい。 現象的に説明すると、磁石は電気に対して少なからぬ影響を与える。地球自体も大きな磁石で、外部からやってくる素粒子や電子の流れ(例えば、太陽からの素粒子)に作用する。
-
- 磁石は電気によっても作られる。鉄にコイルを巻いて強い電気を流すと磁化される。材料によって、一度磁化されたらその磁力を保持する永久磁石ができる。また、電気が流れている間だけ磁力を保持する軟磁性材料があり、全く磁化されない材料もある。
- ・・・これはちょっと語弊がある。
-
- どんな物質でも程度の差こそあれ磁性を示すらしい。
-
- つまり、磁力というのは、電子自体のスピン(回転)により発生する運動量であり方向性を示すモーメントである。電子1個は小さなものだが、それがたくさん集まるとそれから発する磁気モーメントは強くなる。もっとも電荷が集まっているだけでは強い磁気モーメントは発生しない。バラバラにモーメントが発生するから相殺されてしまうのである。
-
|
|
|
- 磁気は、電荷の回転運動から発生する。
- つまり、原子構造に視点を置いて見ると、原子核の周りを電子が回る軌道運動、電子自体の自転運動(スピン)、そして原子核自体の自転運動に起因している。
|
|
|
|
- - 「金属なんでも小事典 - 元素の誕生からアモルファス金属の特性まで」 増本 健監修、ウォーク編著、ブルーバックス B-1188、
- 講談社 1997.9.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
-
- 集められた電線を流れる電気は、たくさんの電子の集まりであるから電気力線が規則正しく出ていて電場を形作る。この電場に物質を近づけると、物質の中でも原子の結晶が正しく並んでいるものは、電子の配列が規則正しくなって、バラバラだった電子個々のスピンが方向性を持つようになる。そのため、金属が強い磁力線を発するようになる。
-
- これが磁石である。
-
- 磁力を示す物体を磁性体と呼ぶ。物質すべては原子で成り立っている。原子は、原子核とその周りに電子が回っている。電子自体は高速で回るため、この回転力で電子の電荷がぐるぐる回り円電流の働きで磁力線ができる。これが磁気の正体だと言われている。こうしてみると、磁界も電界も元を辿ると電子の電気力によって発生している力であることが分かる。スピンによる電子自体が回転するスピンは2種類のスピンがある。この電子の配列が電場によって規則正しくなる金属がある。鉄や希土類金属がそれである。従って、鉄や希土類金属が磁石になりやすい金属となる。
- ■ 科学小冊子
- 「金属なんでも小事典 - 元素の誕生からアモルファス金属の特性まで」、
- 増本 健監修、ウォーク編著、ブルーバックス B-1188、講談社 1997.9.20
- を読んでいて面白い記述に巡り会った(1999.11)。
- 「磁性と金属」という項目の中で、磁気を帯びるというのは金属の特徴の一つと考えられがちであるが、吸い付くのは60種類ほどの金属の中で、鉄、コバルト、ニッケルの3種類だけだと明言されていた。
- この三種類の金属は4周期のVIIIb族の仲間で、電子配列が極めて似通っている。
- つまり、これらは、内側の電子殻に電子が埋まらないままその外側に電子殻をもっているので、完全にその総和が打ち消し合わなくなる。磁気が近づくと、打ち消し合わない磁気の向きがそろうので磁気を帯びるようになる。
-
-
-
-
- 1-5-1. 鉄・希土類金属
-
- 永久磁石は、永久に磁力を出す素材である。永久にエネルギーを出し続けるように考えがちであるが、これはちょっと違う。電子がスピンをして運動量が永久に保存されているように、金属内部でも電子が勝手ばらばらに運動量をもっていたものが方向性を持たされて運動量の方向が一定になったと考える方が正しい。方向を与えるためには外部から力(機械的な力でなく、磁気的な力)を加えてやらねばならず、その意味ではエネルギーが保存されたと言い換えられるかも知れない。
-
- サマリウムコバルト磁石が現れる以前は、強力磁石と言えば、アルニコ磁石であった。これとは別に、白金・コバルト磁石というものもあって、これはアルニコ磁石より強力だったが、非常に高価で工業材料などの実用化材料には向かなかった。
- アルニコ磁石は、鉄・ニッケル・コバルト・アルミニウムなどから成る合金で、巧妙な熱処理によって鉄とコバルトからなる強磁性の針とニッケルとアルミニウムから成る非磁性の針を束ねたような組織を作る。針の太さは0.1ミクロン以下。微細な磁性体の針は結晶の方向性が出るため永久磁石としての性質が多く出る。いったん針の長手方向に磁界を印加して針を一方向に磁化すると、磁界がゼロになっても、あるいは、少々の逆磁界が印加されても、最初にできたNSの方向は変わらない。針状粒子を用いた永久磁石は、長年、強力磁石の王座を占めてきたが、サマリウムコバルト磁石が出現してその座を明け渡した。
-
- サマリウムコバルト磁石は、、1960年代にカール・ストゥルナット(Karl Strnat、米国Wright-Patterson AirForce Base)たちにより開発が進んだ磁石である。高い保持力を得るためにサマリウム(Sm)が重要な働きをする。サマリウムは、元素の周期表57から71番の希土類に属する元素である。希土類元素は鉄族元素(鉄、コバルト、ニッケル)と同様、磁気を帯びやすい性質があるが性質がかなり異なる。
-
- 鉄族合金は磁気を発生する電子(原子の周り3dの準位にある電子)は、直接強い影響力を及ぼし合って互いに同じ方向を向こうとするため、電子の向きが非常に良くそろい大変大きな磁力を発生する。3d電子どうしの互いの連携がきわめて強いので、多少の熱攪乱にも負けずに高温まで同じ方向を向こうとする。つまり、鉄族合金は高いキュリー温度を持つ。
-
- 一方サマリウムコバルト磁石のような希土類元素からなる合金中では、鉄族合金のように原子の相互関係によって高い磁力を発生させるわけではなく元素個々が独立して磁力を発生しているため、希土類元素そのものはそれほど高い磁力も高いキュリー点も得られない。しかし、磁石の方向性が局所的に安定して存在するため、熱処理などをかけなくても強い磁力を発生する。こうして、大きい磁化と高いキュリー点を鉄族合金であるコバルトからもらい、大きい磁気異方性を希土類元素であるサマリウムから得て、双方の良いところを取り入れた永久磁石となっている。
-
- サマリウムコバルト磁石(サマリウムとコバルトの原子数の比が1:5)は、あっという間にそれまでのアルニコ磁石の最大磁気エネルギー積の記録を抜き去った。サマリウムコバルトはその後、構成比を2:17(Sm2Co17)にしたり、銅やジルコニウムの添加により、最大磁気エネルギー積30メガガウスエルステッドを突破した。アルニコ磁石の6倍以上の強さである。
-
- サマリウムコバルト磁石の発明は、エレクトロニクス機器の小型化、高性能化に大きい役割を果たした。サマリウムコバルト磁石がなければウォークマンは生まれなかっただろう。コンピュータのプリンターや磁気記録装置の高性能化もサマリウムコバルト磁石に負うところが大きい。需要が喚起されると資源問題がクローズアップされる。コバルトはアフリカのザイールなど産出する地域が限られていて、政情不安などで安定した供給が難しい側面がある。サマリウムも貴重な元素である。
-
- 【ウォークマンとサマリウム・コバルト磁石】(2000.05.20)
-
- ウオークマンはソニーが小型高性能製品戦略で市場に出して一世を風靡したカセットテープコーダである。今やファッションの一部と化しイギリスの辞書にも載ることになった。このウォークマンの成功の陰にも、サマリウム・コバルト磁石の恩恵があった。この磁石がなければウォークマンの駆動モータをあれほど小型にはできなかった。このサマリウム・コバルト磁石は、米国で軍事技術の一環として開発された。
-
- 1950年代から1960年代にかけて、アメリカは空軍を中心に、ミサイルや航空機に積み込むさまざまは装置の駆動用のモーターを小型化する研究を懸命に進めていた。そのなかで、1967年空軍研究所がサマリウム・コバルト(SmCo)合金の粉末磁石を発明した。やがて産業界に流れた技術情報が、いくつかの手を経て日本に渡り、ステレオカセットプレーヤーという、「軍事技術」とはおよそ無縁の「民生技術」の典型的な商品として実を結んだ。
- - 「日本の条件12 技術大国の素顔(1)〜強いのかメード・イン・ジャパン」
- 日本放送出版界、昭和58年10月10日 第1刷
-
- コバルトの代わりに他の鉄族が使えないか? サマリウムの代わりに他の希土類は使えないか?
- この回答を、1982年、日本の佐川眞人(住友特殊金属(株)→インターメタリックス社設立)とアメリカのジョン・クロートが解決した。
- ネオジウム・鉄・ホウ素磁石の開発である。
-
- ネオジウム・鉄・ホウ素磁石は(Nd2Fe14B)は、それぞれの構成比を2:14:1とした。この化合物の発見により、資源的な問題を解決しただけでなく、性能面でもサマリウムコバルト磁石の性能を一気に抜き去り最大磁気エネルギー積50メガガウスエルステッドが得られるようになった。
- 参考文献:『新しい磁石』一億人の化学、(社)日本化学会、大日本図書 1993.5.30初版、
- 逢坂哲爾(早稲田大学工学部)、山崎陽太郎(東京工業大学大学院総合理工学研究科)
-
-
-
-
- 1-5-2. 磁石の力
-
- この磁石の力は、1cm3の塊で10kgの鉄を吸い付け持ち上げることができる。この強い磁気力のおかげでハードディスク装置の磁気ヘッドを駆動するモータにこの磁石が使われている。ハードディスクは高速で読み書きをする必要があり、磁気ヘッドの高速アクセスのためにかつ電流を抑えて(発熱を抑えて)磁気ヘッドを駆動させるために高性能磁石が使われている。
-
- ウォークマンやヘッドフォン、デジタルビデオなどの製品は、こうした磁石の他に高性能のバッテリの恩恵を受けているが、発熱を抑えて小型・高性能な駆動を発揮するためにはこのような磁石の発明があったことを忘れてはならない。
-
- 佐川氏は、上記の本の中で、
- 「高性能磁石と言えども、磁石が蓄えているエネルギーは小さく、その値は先に出た1cm3の磁石を例に取ってみても、ガソリン一滴の燃焼により得られるエネルギーにも満たないそうである。たとえ、10kgの鉄を引きつけたとしてもそれを持ち上げるのは別の機械や人間で行わなければならないし、モータにしても、外部から電気エネルギーを受けて仕事をするわけである。」
-
- と記している。
- 永久磁石の重要な働きは、エネルギー変換である。電気エネルギーを機械エネルギーに変換するのにモーターを使い、音のエネルギーに変換するのがスピーカである。また、機械エネルギーを電気エネルギーに変換するのが発電機である。高性能な永久磁石は、これらの機器の軽薄短小化、高速化、省エネルギー化を実現した。
-
-
-
-
-
- 1-5-3. 磁性体
-
- 磁力を発する磁性体についてまとめてみたい。
-
- ・常磁性体:加えた磁界の方向に磁化されるがその強さが弱い物質(アルミニウム、スズ、空気など)
- ・強磁性体:加えた磁界の方向に磁化されるがその強さが強い物質(鉄、ニッケル、コバルト、特殊合金)
- ・反磁性体:加えた磁界と反対方向に強く磁化される物質(銅、アンチモン、水素、窒素など)
-
- ■ 磁性材料
-
- 磁芯材料(軟磁性材料):
- ごく弱い磁場でも簡単に磁化され、磁場を除けば元の状態に戻る。与えられた電気エネルギーに比例して磁力を発生する磁芯材料:磁気ヘッド、コイル鉄心、変圧器の鉄芯に使われる。
- 材質は、純鉄、ケイ素鋼板(silicon steel)などが代表的なものである。
- ケイ素鋼板とは、純鉄にケイ素を添加させたもので、これによって固有抵抗が上昇し、鉄損が下がる。
- これはイギリスの研究者によって発見され、1903年にアメリカで工業化された。ソフト・フェライトとも呼ばれている。
-
- 磁石材料(硬磁性材料):
- 磁場を加えても簡単には磁化されないが、いったん磁化されると磁場を取り去っても磁化された状態を保ち続けようとする材料。
- 永久磁石。鉄、W鋼(タングステン鋼)、Cr鋼(クロム鋼)、KS鋼、MK鋼、新KS鋼 ←アルニコ系磁石
- ニッケル、コバルト、ガドリニウムOP磁石(フェライト磁石)、バリウム・フェライト磁石、ストロンチウム・フェライト磁石 ←酸化物磁石
- サマリウム・コバルト磁石、ネオジウム・鉄・ホウ素磁石、希土類・鉄窒化物磁石 ←希土・コバルト系磁石
-
- 磁気記録材料(半硬磁性材料):
- できるだけ弱い記録磁場で磁化することでき(磁気書き込み)、記録磁場が除かれた後は記録磁場の強弱に比例した磁化状態を保ち続けることができる。必要に応じて消去でき再磁化できる材料。磁気テープやフロッピィディスクの磁性体材料に使用されている。酸化鉄(γ-Fe2O3)が有名。
-
-
-
- 【地球という磁石】
 地球は大きな磁石である。なぜ地球そのものが磁石となって磁力線を出しているのであろうか。
地球は大きな磁石である。なぜ地球そのものが磁石となって磁力線を出しているのであろうか。- 磁石になり得る物質は鉄とニッケルとコバルトの3種類である。
- 地球の内部は、中心より内核、外核、マントル、大陸地殻がある。
- 磁場を発生するのは、鉄とニッケルが4,000度〜5,000度の高温で溶けている外核と呼ばれる層が地球中心から1,390km〜3,470kmの間に存在して熱による対流と地球の自転(スピン)のためにこの二つの効果によって地球が磁石となっているのである。
- これは1940年代から発展してきたダイナモ説と呼ばれるものである。
- ダイナモ説によれば地球の外殻の液体の鉄-ニッケル合金の対流による発電作用で地球の双極子磁場が保たれるというものである。
-
-
-
-
-
- 1-5-4. 磁力
-
- 磁力は物理的な力となって磁性体に力を及ぼす。磁力の単位(磁気量)をドイツ人物理学者ウェーバの名前にちなんでWb(ウェーバー)と呼ぶ。
- すべての物体は、自ら磁力線をだして相互に力を及ぼしあっている。これを磁力という観点から考えたのが、ドイツ人ウェーバーやガウスらであった。
- 万有引力の理論からすべての物体は相互に力を及ぼし合うと考え、双方の力関係を導き出したのはイギリス人キャベンディッシュである。
- また、帯電した物体が電気的に相互に及ぼしあう関係を導き出したのがフランス人クーロンであった。
- 二つの磁極の間に働く力Fは、2つの磁極の磁気の量(単位:ウェーバー)m1、m2の積に比例し、磁極間の距離の二乗に反比例する。
-
- F = κm (m1・m2/r2)
-
- これを磁気に関するクーロンの法則と呼んでいる。κm は、比例定数で磁極のまわりの物質によって決まる値。ここで使われているm1、m2は、質量ではなく、磁気量である。これに磁気量のWb(ウェーバ)を与えている。
- キャベンディッシュは万有引力でmに質量をあて、クーロンは帯電した電荷をmと等価にした。そしてウェーバーは磁気量をmにした。いずれにしても2極間の物質量と距離の二乗で互いに働く力が決まるというのはすごいことだ。
- 磁気量の単位は、次のように定義されるが、一般的になじみが薄い。結論的には磁束密度(ガウス)でどのくらいの強磁石かどうかを感覚的にとらえた方が良いかもしれない。
- 一般に磁力を論ずるとき、磁気量の強さを用いることが多いので単位面積当たりの磁気量、磁束密度B(Wb/m2)であらわすことが多い。この磁束密度を1000倍にして、ガウス(G)と称することが多い。むかし、肩こりの貼附薬で磁石を使うものがあったが、その宣伝に800ガウスというような言い方をしていたので記憶されている方も多いと思う。また、SI単位系ではテスラを採用することに決めていて、
-
- 10,000ガウス = 1テスラ(T)
-
- と定義されている。
- 地球の地磁気は0.03ミリテスラ(0.3ガウス)の磁場持っている。また 、鉄を利用した電磁石では1,000ガウスの磁場が作れるという。ネオジウム系の磁石は、10,000ガウス( = 1テスラ)相当の磁束密度を持っている。
- また、超伝導の研究が進む中、100,000ガウス以上の磁場を作ることも可能になっているという。大きな磁場を定常的に発生させるにはたくさんの電流を流さなくてはならず、その設備と電力確保だけでも大変な装置となる。
-
- 日本では、パルス強磁場を発生する電磁石を利用した磁束濃縮法による350テスラの発生装置が東京大学物性研究所にある。また、非破壊的なパルス強磁場の大型施設は大阪大学にあり、そこで発生させている80テスラという値は現在世界最高と言われている。定常強磁場を発生させるハイブリットマグネットは東北大学金属材料研究所にあり、1984年に世界ではじめて31テスラを超える値を記録した。それを上回る40テスラ のハイブリットマグネットをつくば市にある科学技術庁金属材料技術研究所が建設中とのこと(http://www.from.co.jp/niroku/haiburittomg.htm、二六製作所ホームページより)。
-
- 磁場H(磁界の強さ)の単位としては同じ単位系ではエルステッドを使わなければならない。CGS単位系では、真空中でB=Hであるので、便宜的に1エルステッドの磁場を、その磁場中での磁束密度が1ガウスであるという意味でガウス磁場といっている。現在の国際標準単位系であるSI単位系では、磁束密度Bの単位はテスラ(T)であり、磁場Hはアンペア毎メートル(A/m)である。
-
- 磁場の強さの単位A/mは電流により発生する磁場を考えるときに便利であるが、物質に及ぼす磁場の影響を考えるときには、むしろ磁束密度の単位Tを使ったほうが便利なことが多い。磁石のNとSで挟まれた間の磁界では、このB(Wb/m2)を単位として、これを元に電気(電流I)と力Fの関係を公式化している。
- 磁力の単位:ウエーバ、ガウスとエルステッド
-
- CGS emuの磁束密度の単位: 10,000 G(ガウス) = 1 Wb/m2 = 1T(テスラ)
- CGS emuの磁界の強さの単位: 10エルステッド = 1 A/m
- (2007.09.13: 1,000G(ガウス) = 1 Wb/m2と記述していたのを、tamさんに指摘され直しました。tamさんご指摘ありがとうございました。)
-
-
- エルステッド(Hans Christian Oersted 1777-1851):
- デンマーク人物理・化学者。コペンハーゲン大学時代(1801年)、電気と磁気の研究に従事。
- 1820年7月強力な電池を手に入れることができ、その電池で磁針が電流によって偏向していることを発見。
- 彼の発見は、以下のものであった。
-
- 1. 電流が磁針に作用すること。
- 2. 電流の方向によって強度が異なること。
- 3. 極と電流の位置に対する簡単な法則を発見。
- 4. 電流と磁石は相互に作用を及ぼす。
-
- 彼の研究は、フランスのアラゴ(電流によって生じた磁気を発見)、アンペール(電流が磁針におよぼす作用を発見)らに影響を与えた。
-
- ガウス(Karl Friedrich Gauss 1777-1855):
 ドイツ人数学者・天文学者。
ドイツ人数学者・天文学者。- 彼が7才の小学生の頃、1から100までを加え合わせた合計の計算を見事な切り口で解いたのは有名。
- 彼の研究は、天文学、誤差論、正規分布(ガウス分布)、最小二乗法、五桁の対数表、複素関数論(ガウス平面)など多方面に及んでいる。
- 電気に関して実際に手を動かしたとう業績はなく、ウェーバらの優秀な人材と一緒に数学的な見知(ガウス分布、最小二乗法、複素数)から電磁気を体系づけたと言った方が当を得ている。
-
- ウェーバ(Wilhelm Eduard Weber 1804-1891):
 ドイツ人物理学者。
ドイツ人物理学者。- 1828年、ベルリン自然科学者会議においてアレキサンダー・フォン・フンボルトからガウスに紹介された。
- 1831年、ウェーバーはガウスの取り計らいによってゲッチンゲン大学の正教授になった。
- ガウスとともに磁気力の単位を構築した。
- ガウスの関心は、磁気の絶対単位(磁気の強さの長さ、時間、質量による表現)を求めることにあり、彼とウェーバーはゲッチンゲン磁気協会を創設して計測装置を開発し、全国の地磁気を示す地図を作った。
- また、電流の絶対単位の測定にも着手した。
- 1843年、ライプツィッヒ大学物理学教授になってからは、新しく開発したダイナモメータにより電流相互の力をアンペールよりも詳しく測定した。
- ライプチッヒ大学で発見した電気力学的根本法則「ウェーバーの法則」は、二つの電気量の及ぼし合う力は距離のみでなく、速度、加速度にも左右されるというものである。
- 1845年、ゲッチンゲン大学から復帰を求められ、1849年に同地に赴き再びガウスと科学上の共同研究を行った。1881年、パリに電気学者国際会議があったとき、ウェーバーの絶対単位が支持を受け、ボルト、アンペア、クーロン、ファラッドが電気量の単位として採用され、法定オームも決定した。
- ウェーバーの電磁気学はマクスウェルの場の理論に結局は駆逐されたが、電磁気学形成期おける測定装置の向上と、客観的な単位の設定に果たした役割は大きい。。
-
-
-
-
-
- 1-6. トランジスタって? (2001.03.12)(2015.07.30追記)
-
- 電気の世界で、電子部品の代名詞とも言えるトランジスタについて門外漢であった私がアプローチをしようとしている。 私は、小さいときから機械ものが大好きだった。ブルドーザやオートバイ、自動車、コンクリートミキサー車、飛行機・・・等、動くものを見ると心がワクワクして、ずっと見てても見飽きなかった。しかし、電気製品はあまり好きになれなかった。電気は頭の中で理解することが難しかったし、内部の仕組みに興味を覚えなかった。
- 私の育った昭和30年代から40年代(1950年〜1960年代)にかけては、電気製品が真空管からトランジスタに急速に移行していった時代である。そして昭和40年から昭和50年代(1960年〜1970年代)は集積回路からコンピュータへと移行していく時代でもあった。
-
- 我々の世代のあこがれの電気製品の一つに、オーディオがあった。学生時代は、オーディオのコンポを持つことがちょっとした夢だった。 そんなオーディオを手に入れて音に対するこだわりをもつようになっても、内部の仕組みまで理解するには至らなかった。ステレオアンプの中身を覗いてもラジオを分解しても、はたまた、コンピュータの基板を取り出しても、その基板は何がなんだかわからない線と部品が配列されていた。 基板の中に電子工学の集大成があった。 バックグランドのないものがこの基板を目の当たりにして見ても、電子回路の驚くべき進化の意味などこれっぽちもわかるわけはない。数十年前の電子回路と今の電子回路では発想が根本的に違うし、使われている素子も違う。
-
- こうした電子工学の流れを変えてきたのがシリコンチップなのである。トランジスタはもちろんその仲間であり主人公であった。
-
- 電気は、発電所の設置と発電機の開発、電動機(モータ)の開発、電灯の発達で大きな進歩を遂げてきたが、『トランジスタ』の発明とその技術革新は電気と我々の生活のあり方を根底から覆し、急速に進歩させた。コンピュータの歴史においてもトランジスタ技術の果たした役割は計り知れない。トランジスタが発達する前は真空管が用いられていた。真空管は、電気を電子として位置づける重要なコンポーネントであった。
-
- 真空管の登場は、電気を作る、動力として使う、明かりとして使うという電気の役割に加えて、「通信」の世界を牽引していった立て役者である。真空管は、電流を一方向に流す整流作用があったし、微小電圧で大電圧を制御する増幅機能もあり、また、電圧を数MHzで発振させて増幅させる機能も持っていた。真空管の発明により任意の電波が飛ばせるようになり、送られて来た電波から希望する音声信号や通信信号に置き換える検波もできるようになった。
-
- 真空管が使われた電気製品にラジオ、テレビがある。
- 真空管は、ガラスチューブの中に電極が組み込まれていて電子の流れを制御する素子である。トランジスタは、その真空管に置き換わるべく開発されたもので、三極真空管の固体素子とも言えるべきものである。トランジスタが開発された当初、その開発根底には絶えず真空管の存在があった。真空管の持つ欠点、すなわち、大きい、壊れやすい、電力を食う、信頼性が低い、という欠点を補うべくトランジスタは嘱望され成長を遂げた。それは東西の冷戦下の時期、米国の軍事秘密にも指定され、国家の存亡をかけてトランジスタ開発が取り組まれたと言っても過言ではない。
-

-
- そしてトランジスタに集積能力(IC = Integrated Circuit)があるとわかると、トランジスタは独自の路線を歩み始める。 コンピュータへの移行である。
-
- トランジスタ(Transistor)は、1947年米国のベル電話機研究所で開発された。開発の目的は、増幅素子である三極真空管の代わりになる固体素子化であった。トランジスタの開発が急ピッチで進んだ背景には、当時、電気増幅、整流、検波の主流素子であった真空管の欠点を置き換える特性をトランジスタがすべて持っていたことが挙げられる。トランジスタ自体も開発当初はそれほど信頼性があったわけではないが、真空管とはまったく違う動作原理を持っていて、トランジスタの潜在的性能が高く評価され、それにともなう技術革新にも助けられて驚異的な発達をみた。
-
- トランジスタの名前の由来は、抵抗が変化する素子 = トランス・レジスタ(trans resistor)から来ていると言われている。 シリコン半導体の発展、IC技術の発展、CPUの誕生はいずれも、1947年のトランジスタの発明にその源流を見ることができる。
-
- ICは、Integrated Circuitの略でトランジスタを集積化して複数のトランジスタを小さなチップの上に構成したものである。LSIはLarge Scale Integrationの略で1,000個程度のトランジスタを集積化した素子を呼ぶ。LSIの仲間にはICメモリーが含まれる。(集積回路の仲間にはこの他、100個程度のSSI = Small Scale Integration、100から1,000個程度のMSI = Medium Scale Integration、100,000個以上のVLSI = Very Large Scale Integrationがある。)
-
- 今は、ICもずっと進化し、コンピュータの心臓部のCPU(Central Processing Unit)もICの一つであるし、メモリチップ(ROM、RAM)もICのファミリーに入る。そして何よりも、電子装置の中に入っている基板を一つのICチップにまとめてしまうというPGA(Programmable Gate Array)が登場した。PGAにより、電子製品は驚くほどコンパクトになっていく。
-
-
-
 ■真空管
■真空管 -
- トランジスタを述べる前に真空管の話をしておこう。真空管と言ってもピンとこない人が多くなったのではないか?
-
- 真空管をよく理解できない人は、60Wの裸電球や、蛍光灯、テレビのブラウン管を想像していただいたらよい。これらは全て真空管の仲間である。
- 真空管の原型はエジソンらの白熱電球の発明からスタートする。灯りとしての真空管の働きが、電気の増幅や高周波発振機能に発展していった。真空管がトランジスタに切り替わっていったのはトランジスタの性能向上もさることながら真空管に以下の欠点があったからである。
-
- 【真空管の欠点】
-
- 1. ガラスでできていて壊れやすい。
- 2. 素子が大きい。
- 3. 素子が正常に働くまでに時間がかかる。
- 理由は、真空管で働く熱電子を作るためにフィラメントを暖めなければならないため。
- 4. フィラメントを使用しているため消費電力が大きい。
- 5. フィラメントを使用しているため比較的寿命が短い。
- 6. フィラメントを使用しているため故障が多い。
- 7. 固体素子と違って空間を電子が飛ぶので回路に高圧(100V 〜 5,000V)を使うことが多い。
-
- 半導体を使ったトランジスタは、上に述べた欠点をことごとくクリアできる潜在的な可能性を秘めていた。この着眼点が功を奏してトランジスタ技術は飛躍的な発展を見て、その派生素子である集積回路素子(IC)やマイクロコンピュータ(CPU)を産み、現在の電子産業、はては情報産業の大きな流れとなっていった。
-
- 【電子管 = electron tube】
- 現在では、真空管は電子管という名前で特殊な用途で生きながらえている。
- 真空管が電子管という名前に代わったのは、開発初期はチューブ内を真空にしていたものを、その後チューブ内に不活性ガスを封入したり、その他の気体を入れたりするケースが増えたため電子管と言う名前に取って代わるようになった。
- 電子管の総生産高のほとんどはテレビのブラウン管(CRT)であったが、2000年以後、液晶の品質が向上したためCRTディスプレーの需要が落ち込んで事業部を閉鎖する大手電気メーカが相次いでいる。
- 優れた特徴を持つトランジスタではあるが長所ばかりではない。トランジスタの欠点は熱である。熱によって容易に破壊を起こす。熱は半導体の中を流れる電流が内部抵抗によって発熱しておきる。それが定格以上になると組織が破壊する。トランジスタを扱う場合電流制御がいかに大事かの証左である。電子管は、トランジスタに比べ熱に対する許容範囲が大きい。大電流、高電圧、高周波数を扱う素子には現在も電子管を使うことが多い。例を挙げると電子レンジに使うマグネトロン(磁電管)は電子管であり、放送、レーダなど無線送信に使う1GHz以上の高周波数の送信管にもマイクロ波管と呼ばれる電子管が使われている。
-
- ●今も生き残っている電子管:
-
- ★ 電子顕微鏡に使われる電子ビーム管
- ★ 高電圧、高周波スイッチング電子管 = サイラトロン
- ★ 白熱電球(エジソンのランプ)
- ★ 電灯に使われる蛍光灯 = 熱陰極二極管
- ★ ランプ = ナトリウムランプ、クセノンランプ
- ★ レーザー = アルゴンレーザー、ヘリウムネオンレーザー、銅蒸気レーザ
- ★ 光を検出する光電管: フォトマルチプライアー、イメージインテンシファイア
- ★ 電子レンジに使われるマグネトロン
- ★ テレビ受像機(ブラウン管、CRT): ブラックマトリクス管、トリニトロン管
- ★ テレビ受像機 冷陰極管: プラズマディスプレー、
- ★ X線を発生するX線管(クーリッジ管)、とそれを検知するガイガーカウンタ
- ★ テレビカメラ撮像管: ビジコン、サチコン、カルニコン、
- イメージインテンシファイア、SIT管、ハーピコン
- ★ 送信器に使われる電子管: クライストロン、進行波管(6MHz、3kW、ピーク6MW)
-
-
- ●真空管の歴史:
-
- 電子管(真空管)は、無線技術の発達と同時進行する形で発展してきた。イタリアのマルコーニ(Guglielmo Marconi)が無線電信を発明した1896年当時、送信側には火花放電を用いて電波を発生させ、信号を受け取る受信側ではガラス管に金属粉を入れて飛来した電波によって橋絡することで信号を得ていた。この信号検出管(検波管)をコヒーラー(coherer:検波器)と呼んでいた。コヒーラは、いったん短絡した状態をリセットするにはハンマーによって元に戻す作業が必要だった。原理上、カミナリが発生しているところでは誤動作が相次ぐことは容易に想像できる。
-
 マルコーニ無線会社の顧問であるJ.A.フレミング(John Ambrose Fleming)が、1904年にそのコヒーラーに代わる二極真空管を発明した。二極真空管は、電子の流れが一方向で逆方向には流れない特性のものである。
マルコーニ無線会社の顧問であるJ.A.フレミング(John Ambrose Fleming)が、1904年にそのコヒーラーに代わる二極真空管を発明した。二極真空管は、電子の流れが一方向で逆方向には流れない特性のものである。-
- 1907年ド・フォレスト(Lee De Forest)が二極真空管に制御用の制御格子(グリダリアン = 肉焼き網)を入れた三極真空管を発明した。
-
- この三極真空管はパルス信号を作るのに好都合であったため通信技術を一気に高めた。真空管の登場は、1900年代初めの電子工学にあらたな風穴をあけた。無線通信を初め音響分野、映像分野、コンピュータ分野を大いに活性化させたのである。真空管の性能の真骨頂は、高周波制御と増幅機能である。
-
- 真空管の登場によって、ラジオが普及した。1950年代からはテレビの時代。同時期にコンピュータが実用化されていく。1960年がらからはトランジスタの時代となる。
-
- ●真空管の今:
- 仕事と趣味を兼ねてよく秋葉原へ行くが、秋葉原の小さなお店では未だに真空管を売っているお店がある。お客のほとんどはオーディオマニアと想定され、柔らかい音を求めて真空管に執着しこうした真空管を物色して手作りでアンプを製作していると言われている。私はその真空管で作ったアンプの柔らかみのある音がよく理解できない。しかしながら真空管の許容範囲の広い電流特性や周波数特性、ノイズに強い特性がなんとなくわかるから、真空管が生み出す電気信号もきっと歪みのない豊かな音が出るのだろうと思っている。
-
- 感心するのは、こうした真空管が今も製造されていて市場に出回っていることである。そして真空管を使ったアンプに関する技術雑誌が書店で売られている。このことからも真空管の根強い人気を見て取ることができる。こうした真空管は、世界のどこかで世界中の需要を賄える程度の生産設備を持って細々と作っているのだろうと想像している。
-
- 高校時代(1974年)に芥川賞受賞作家 柴田翔の「されど我らが日々」を読んだとき、その作品のおまけのような形で「ロクタル管」の短編小説が載っていた。作者が幼い日にあこがれた真空管の思い出をつづった作品で、古くなって忘れ去られていく真空管に郷愁を示した作品だったと記憶している。高校時代の私は電気の知識が全くなかったけれど、文化系の大学を出た作者「 柴田翔」にもこうした物理学的な側面の興味があるんだと複雑な気持ちになったことを覚えている。
-
- 私が物心ついたとき(昭和30年代後半、1960年代前半)、家にはミカン箱程度の大きさの真空管ラジオがあった。電源を入れてもすぐには音が出ず、しばらくして雑音に混じって音声帯域の狭められたラジオ放送が流れてきた。私はこのラジオに親しんだ記憶がない。私が6才の時に我が家に白黒テレビが入り、ラジオは居間の片隅に追いやられてしまったからである。
-
- テレビの衝撃は今でも忘れることができない。小さな箱が世界の扉となって次から次へと私の知らない世界に誘ってくれた。この真空管の白黒テレビ(たしか松下製だった。ナショナルというエンブレムがあった記憶がある)は電気を入れてもすぐには音も映像も出ず、2分ほど待たなければならなかった。我が家には厳しい掟(おきて)があってテレビを2時間以上つけてはならないというきまりがあった。2時間以上テレビをつけるとテレビが爆発するというのである。祖父が一番神経質になって時間の管理をしていた。高価なテレビが爆発したら二度とテレビを買ってもらえないという恐怖感がテレビをつけるたびに小学校低学年だった私の頭を支配した。自転車のタイヤのパンクを修理するのとはわけが違うから、家の誰もがこの難しいテレビの仕組みや回路、修理などできずに、畏怖の念でテレビとお付き合いしていた。テレビは我が家の居間でのヒーローであったし、安藤家の文化レベルを超えたカリスマでもあった。
-
- そんなテレビの側面パネルの排熱孔から内部をのぞき込むと、ガラスでできたランプのようなものが10個ほどあって赤く輝いていた。テレビの中からは電気回路独特のニス(絶縁塗料)の匂いが回路の発熱と一緒に鼻腔を刺激した。綿埃にまみれた回路のなかの、ボウ〜ッと光っている真空管を不思議な気持ちで見ていた記憶がある。
-
- そんなテレビも1960年代中頃からカラーテレビが出始め、1970年までにはソリッドステート(固体素子、いわゆるトランジスタ)を使用したテレビが台頭してきた。そして2000年からはブラウン管も液晶表示に代わった。2007年はテレビと言えば液晶になっている。ブラウン管は死語となった。
-
-
-
- ■トランジスタの発明
-
- トランジスタの発明は、ベル電話機研究所のショックレー(William B. Shockley)、バーディーン(John Bardeen)、ブラッテン(Walter H. Brattain)らによってなされた。トランジスタ発明に先だっては、以下の基礎的な物理学的基盤が必要であった。
-
- ・電気的にあいまいな振る舞いをする半導体(シリコン、ゲルマニウム、ガリウム、ヒ素)材料の
- 物性研究の下地があったこと、
- ・半導体材料の純度の高い製造技術に多くの知恵が集まっていたこと、
- ・ダイオード(Diode、半導体材料を使った固体整流素子、ショックレーが
- 当時先駆的な理論研究をしていた)の理論体系が整いつつあり、製造技術も向上していたこと
-
- ダイオードそのものは、金属を半導体に接触させると整流性があることが古くから知られていて、セレン整流器、亜酸化銅整流器が実用化され、無線電波を搬送波信号と音声信号に分離する検波素子として鉱石検波器に使われていた。
- 1930年代にはフレンケル(Ya. Frenkel:ソ連の科学者)、ウィルソン(A. H. Wilson)、ノルドハイム、1939年にはショットキー(Walter Schottky:ドイツ物理学者)、1940年にはモット(Nevil Mott)らによって半導体の整流理論が研究されていた。
- ショックレー(William B. Shockley)の偉大な点は、半導体(当時はゲルマニウム)結晶中にP型領域とN型領域を形成させるとこれを接合させた境界面に整流作用(一方通行の電子の流れ)が起きることを理論的に示したことである。さらに、この2極のダイオードの接合面にもう一つのP型(もしくはN型)領域を作って3極構造とした素子には電気増幅作用があることもつき止めた。P型領域(positive-charges)とは、電子的にプラスの電荷がたまりやすい(これを正孔 = ホール)領域をもつ半導体結晶のことであり、N型領域(Negative-charges)は、電子をためやすい半導体結晶のことである。 こうしたP型、N型の半導体結晶を作るのがトランジスタ製作の必要不可欠な技術だった。
-
- 【私とトランジスタ:余話】(2000.06.09)(2008.07.21追記) 私は、高校時代から今にいたるまでトランジスタの解説が載っている書物をたくさん読んできたけれど、どれもこれも同じような内容だった。たいていの本は、ゲルマニウムの原子が描かれてあり、その間に点在するようにインジウムやアンチモンの原子が置かれ、電子の手が多い、少ない、で電子を渡しやすい、受け取りやすい、という説明に終始していた。 私は、不幸なことにこうした解説書を読んでも十分な理解をトランジスタに示すことができなかった。高校時代は、そもそもトランジスタというのはどういう働きがあるのかもわからなかった。当時のラジオには、エンブレムに15石ラジオなどと書かれてあり「石」がトランジスタの意味を持っていて、その数が多いほど音質の良い高級ラジオということになっていた。だがその「石」がどういう働きをするのか皆目理解できなかった。中学1年の時より理科に興味を持ち友達とアマチュア無線をとるために無線の本を買って独学していたのにトランジスタはわからなかった。当時のアマチュア無線の解説本に出てくる送受信器の回路はすべて真空管回路であった。 大学4年の時、研究室でちょっとした電気ブームがあり、自作で電気回路を組むことが流行った。私の先輩の院生のI氏はとても起用に電気回路を組んだ。自分の自動車用としてトランジスタを使った点火プラグのイグナイタを製作したり、間欠ワイパーの回路を作って自分の車に搭載していた。当時我々の研究室で講師をしていらっしゃった太田安彦先生は電子回路(アナログ、デジタル回路)にとても精通していらして計測用アンプや、イオンプルーブ装置などあらゆる計測装置をとても器用に自作されていた。我々は先生のそうした息吹を吸い込みながら自分たちもあのように自由に電子回路を設計したいと思っていた。研究室には太田先生の作ったオーディオアンプ(たしか10Wクラス)が置いてあって良質なFM放送を我々に提供してくれた。こうした研究室の中でワイワイと話し合う電気の話題にいたく刺激されたものである。機械工学を専攻し電気に好奇心を示す者同士が集まって電気を語るようになって、トランジスタやそのほかの電気素子がいきいきと頭の中で踊るようになった。
-
- 自分も電子回路を作ってみようと思いたち研究室にあった「サイリスタ利用の電器工作」(石川碩哉著、昭和50年11月20日第1刷、日本放送出版協会)の中の白熱灯のコントローラのトピックを参考にして製作した。この装置には、白熱電球の明るさを調整する装置で心臓部にトランジスタの一種であるサイリスタ(SCR = Silicon Controlled Rectifier)を採用していた。サイリスタは商用電源の入力電圧を周波数分の任意の位置でON-OFFするスイッチ機能があり、この素子の働きによってランプに入る見かけ上の電圧が変化し最終的にランプの明るさを調整できるという装置である。サイリスタは、交流モータの制御やヒータの制御などの電力制御素子として産業機器に多用されている。この本はトランジスタを含めてSCRがどういう仕組みになっているかとか、事細かな説明が図とともに掲載されていてとても参考になった。何よりも自作できる手引き書であったために自分で装置を作ることで電気素子への造詣が深まった。
-
-
- ■ 半導体 シリコンの特性
- 現在半導体の主流になっているシリコンの電気的特性は、良導体(電気抵抗率:1.62 x 10-8 Ω・m)である銀、銅でもなく、絶縁体(電気抵抗率:1 x 1012 Ω・m)である磁器、天然ゴムでもない。それらの中間の電気抵抗(電気抵抗率:2.3 x 103 Ω・m)をもつものを総称して半導体と呼んでいる。
- 半導体物質は、極低温では絶縁物に近く無限大の抵抗率を示すが、温度上昇と共に急激に抵抗率が下がる。これは、金属の抵抗率が温度上昇によって大きくなるのと反対の性質で半導体の一つの特徴となっている。また、半導体は、不純物の添加や光を照射することにより抵抗率が大きく変化する。この性質を積極的に利用して電気を制御する素子が開発された。完全なるシリコンの結晶構造はダイヤモンド型構造のしっかりした共有結合をしているため電子的な結びつきが強く、絶対0度(摂氏-273度)では電子を放出しない(自由電子がない)。このため電気は流れず絶縁体となる。しかし常温での原子結合はゆるんでいて移動可能な自由電子が多数存在する。完全なシリコン単結晶の中にわずかに不純物(といってもシリコンにとっての不純物、ホウ素とかリン、アンチモンなどの純度の高い元素)を入れてやると電気を通しやすくなる。
- この発見がなされたのは1930年代の終わりのことで、ベル電話機研究所の無線研究グループの化学者ラッセル・オール(Russel S. Ohl)と冶金専門家ジャック・スカッフ(Jack Scaff)によってであった。ラッセル・オールは、1939年までにレーダの検波に使う半導体として何が最適かを調べるため100種類に及ぶ鉱石をテストし、その結果、レーダー波検波用の鉱物としてはシリコン・タングステンの組み合わせが最も優れているという結論を下した。シリコンはドイツのアイマー・アメンド化学社から購入したものがもっとも高純度で良好であったという。
- (詳細は、本ホームページ「1-6-1半導体って?」 及び 「1-6-2シリコンって何者?」 参照のこと)
-
- ■P型領域、N型領域の発見
- トランジスタには半導体が使われていることがわかった。半導体の材質としてシリコンが現在の中心となっているが、開発当初はゲルマニウムが中心であった。その理由は、本ホームページ「■ゲルマニウムVSシリコン どっちが優秀?」に詳しく述べる。
- これらの半導体を使って性質の違う2種類の半導体物質を作り、それを一つの素子の中で形成することでトランジスタが出来上がった。この2種類の半導体をP型半導体、N型半導体と呼ぶ。
- 1939年8月、第二次世界大戦の勃発直前、ベル電話機研究所のラッセル・オール(Russel S. Ohl)はシリコンの高純度化を同じ研究所の金属研究者であるジャック・スカッフ(Jack Scaff)に依頼した。彼は、融けたシリコンを使って部分的に高純度化する方法を採用する。これは、ゾーン・リファイニング(帯溶融精製)として知られる技術で戦後(1952年)になってベル電話機研究所のプファン(William G. Pfann)によって確立される手法である。
- 1940年のある日、ラッセル・オールは数ある試験鉱石の中の直径0.3mm、長さ25mmの細いシリコン棒におもしろい現象があることに気づいた。
-
- シリコン棒に光が当たると電気を起こしたのである。
-
- 彼がこれに気づいたのは、電気スタンドとシリコン棒の間に扇風機が回っていて、扇風機のゆっくりした動きに合わせて電気スタンドから照射される光がシリコン棒に遮られシリコン棒に接続した電流計が扇風機の動きに合わせて動き出したためである。シリコンに影ができると針は下がり、光が当たると針が大きく振れた。 「シリコンの光による起電効果」の発見であった。 さらによく調べていくと、シリコンは真ん中を境に左と右では電気的性質が異なっている事が判明した。 オールとスカッフは、二つの領域をそれぞれN型領域、P型領域と名付けた。 N型領域(Negative Charges)は電子が多く存在する領域で、P型領域(Positive Charges)は余分な正孔が多く存在するプラス領域であると彼らは考えたのである。
- この二つの半導体の性質がトランジスタの発展を促していくことになる。(pn接合 参照)
-
- 【ショックレー:William Bradford Shockley (1910 - 1989)】
- 米国の固体物理学者。1910年ロンドンに生まれた。父は鉱山技師、母が地質学者という科学者夫妻の一人息子である。両親が米国に移住しカルフォルニアのサンフランシスコの南50kmにあるパロアルトに住むようになる。彼はこの地で育ち、1932年カルフォルニア工科大学卒業。マサチューセッツ工科大学大学院で「固体の中の電子の挙動」で学位取得。1936年ベル電話機研究所に入所。ベル研究所では最初真空管の研究部門に配属されたが、研究総括責任者のマービン・ケリーの目に留まり固体素子の研究を促す。彼の薦めによって半導体部門に転属し「固体による増幅装置の研究」に没頭するようになる。後、同研究所半導体研究グループの主導者として、p-n接合の電子理論を展開。正孔の存在の実証など半導体のトランジスタ効果の発見とその物理的原理を解明し、p-n接合による接合トランジスタを発明した。この半導体の理論体系とトランジスタの発明により同僚のブラッデン、バーディーンとともに1956年ノーベル物理学賞を受賞した。ショックレーは1955年までベル電話機研究所に勤めた。名声は十分に得られたのだがベル電話機研究所からの報酬は彼の価値と功績を十分に評価したものではないと考え、他の環境でもっと良い収入を得たいと願い、自分のアイデアを活かせるようなトランジスターの研究・開発を専門にする新しい会社を持ちたいと思った。彼は若い頃にカルフォルニアに住んでいたので、1955年に故郷に帰ることを決め企業への出資者を探した。カルフォルニアに帰る途中、彼はイリノイ大学の旧友に会うためアルバナシャンペーンにしばらく逗留し、起業するためカルフォルニアの投資家に電話で交渉した。最終的にベックマン(Arnold O. Beckman)に財政的な援助をしてもらうことに成功し、パロアルトにショックレー・トランジスター会社を設立した。
-
- トランジスタ開発のための研究は、1945年、第二次世界大戦後から始まる。レーダーに使われた鉱石検波器の改良で培われた半導体材料や物性に関する知識をもとに、三極真空管に替わる半導体結晶による増幅器を作る目的でトランジスタの研究が始まった。 1947年12月、ベル電話機研究所のブラッデン、バーディーンらは、ゲルマニウム結晶表面にきわめて近接した2本の金属針をたてて電気を流したところ、この構造の電気素子に増幅機能があることを確かめた。しかし針の構造をしたトランジスタは構造上壊れやすく信頼性が乏しかった。1948年、これを見たショックレーは、トランジスタの増幅現象をpn接合理論に置き換えて完全な解析を行い、理論的な解析に基づいて「pn接合型トランジスタ」を考案した。これが後にバイポーラトランジスタとして主流になっていく。 ショックレーはさらに、1952年、別の原理による「電界効果型トランジスタ = Field Effect Transistor(FET)」を考案した。このトランジスタは、前述のバイポーラトランジスタと区別するためにユニポーラトランジスタと呼ばれている。電界効果トランジスタは、1960年代になってMOS FET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)として完成され集積回路では一般的なものになった。
-
- 【ベル電話機研究所とトランジスタ】
- ニュージャージー州マレーヒル、ニューヨーク市から車を跳ばせば2時間ほどで行ける郊外の町に、世界の通信とエレクトロニクス技術の総本山とも言うべきベル研究所がある。 AT&T(アメリカ電話会社)やWE(ウェスタン・エレクトリック社)からなるベルシステムグループのの研究部門として、1925年に設立されたが今では年間総研究費20億ドル(約800億円)、研究者や技術者など19,000人を有する世界最大の研究機関の一つである。
-
- ▼ベル電話機研究所:
- 1900年、ベル電話会社は、地域ごとに作った21の電話網を接続統合し、あわせてウェスタン・ユニオン電信会社も合併吸収して、アメリカ電信電話会社AT&Tに脱皮した。地域の電話網を縦横につないでアメリカ大陸全土にわたるネットワークを作りあげていく技術的背景には、信号の長距離電送を可能にした真空管の積極的利用があった。
- 1913年から1915年にかけては、ニューヨークとサンフランシスコの間に大陸横断電話回線が引かれた。三極真空管を使った七つの中継器を途中に設置し、減衰した信号電流を一定区間毎に増幅しながら大陸を横断させる仕組みであった。回線は1915年に完成し、その年、サンフランシスコで開催された博覧会の会場で大陸横断通話の実演が観客の前で行われた。人間が移動すれば5日かかる距離である。このプロジェクトは、一応の成功を見たがこの通信に使われていた真空管の限界を彼らは気づき始めていた。真空管は、タマ切れを起こすという致命的な欠陥があったのである。真空管の構造は、白熱電球と同じような構造をしているため、内部のフィラメントがいつかは焼け切れる運命にあった。通信事業では、ネットワークに膨大な数の真空管を使うため、いつかはそのどれかが切れる心配が常につきまとった。
- 信号の増幅問題(長距離通話)と並んで、電話回路の拡充を妨げるもう一つの障害があった。膨大な数の電話加入者の中から通話者同士だけをつなぎ合わせる交換業務がそれで、当初は交換手が電話線の端末同士をつなぎ合わせて通信接続を行っていた。これが交換台が開発されてパネルに端末を接続できるようになり、交換手が電話線の受け口同士にプラグのついた電線を差し込んで接続するようになっていくわけであるが、やがて、これが無数のリレースイッチに変わっていく。ところが、このリレースイッチには接点があり、それがスイッチ開閉の度に電気の火花を発して接点を腐食した。増幅装置としての真空管に寿命があるように、交換機の心臓部であるリレースイッチ群にも寿命があった。やがて登場するトランジスタは、増幅装置として使われると同時に機械的接点のない電子的スイッチとしても使われるようになったのである。こうした事情によって、ベル電話会社が真空管に代わる故障の心配のほとんどないトランジスタの登場を強く待ち望むようになったのも電話事業者としては当然のことであった。
-
- ▼トランジスタの発表:
- トランジスタ発明の発表は、当時それほどセンセーショナルに発表されたわけではない。「トランジスタ」という名前がはじめて公にされたのは、1948年6月30日、記者団に対する公開実験の場であったという。 NHK取材班(日本の条件12 技術大国の素顔 〜 強いのかメード・イン・ジャパン)がこの特集放送を制作するため取材を重ねていたときに、マイクロフィルムに収められた同年翌7月1日のニューヨークタイムズの紙面を探し出している。ようやく見つけた「トランジスタ」の記事は、週末のラジオ番組の内容を伝えるラジオ面の中にあって、小さな見出しの下にわずか200語ほどのささやかなものだったという。
-
- 「これまで真空管が使われてきた無線装置の分野に使うことのできる、トランジスタと呼ばれれる素子が昨日はじめてベル電話機研究所で公開された。・・・トランジスタは、一点3センチ程の長さの金属製の円筒のなかに収められており、真空管のように中を真空に保つ必要もなく、作動するまでに温める必要もない。金属基板にハンダ付けされた半導体の針の頭ほどのところに、二本の極細の針金が接触しているだけで、一方の針金から流れた電流が基板のところで増幅され、もう一方の針金によって取り出される。」
-
- 実は、トランジスタの発明は、この日の公開をさかのぼること半年あまり、1947年12月のことだった。ベル研では、電話の急速な普及に対するための電話システムのスイッチ、増幅器などの性能向上のための研究を積極的に進める中で、海のものとも山のものともつかない半導体の基礎研究にまで組織的に取り組むようになっていたのである。
-
- ▼軍需から開発されたトランジスタ:
- トランジスタ登場前夜の伏線として、ここにも「軍事」が見え隠れする。 第二次大戦中、アメリカ政府の軍事関連の研究開発契約の多くが企業や大学との間で結ばれていたが、その最大のものはマサチューセッツ工科大学におけるレーダーの研究だった。大学では物理学など基礎研究を中心に新しい理論がつぎつぎと生まれ、企業では新しい技術開発が兵器として日の目を見ていた。
- 特に軍の委託研究の成果は、そのままその企業の特許として認められるという特典が与えられ、研究開発に拍車がかかる大きな誘因になっていたのである。 「産軍複合体」「軍・産・学の共同研究体制」などと呼ばれる軍を中心とした科学技術の発展の枠組が、このときアメリカに根を下ろしたと言えるだろう。
- ベル研も例外ではなかった。第二次大戦中の艦載レーダーはほとんどすべてベル研で開発されたものだった。また、ベル研は戦後直ちに陸軍からナイキ防空システムの開発を委託され、敵機の追跡レーダー開発に力を注いだ。これが後のABM(Anti - Ballistic Missile、弾道弾迎撃ミサイル)の開発につながっていく。 こうした軍事関連の応用技術開発の陰で、真空管の代わりに半導体を使うことを目ざした基礎研究が1930年代の中ごろよりベル研で真剣に進められていた。
- この研究の中心人物がブラッテン(Walter H. Brattain)とショックレー(William B. Shockley)であり、これに大戦中海軍兵器研究所で潜水艦探知装置の研究をしていたバーディーン(John Bardeen)が加わる。この三人の不断の研究を通じて、半導体を使って電流が増幅されるという歴史的な発見が行われたのである。
-
- ▼トランジスタの品質向上:
- しかし、発明から公表までの半年間はあわただしかった。後続の研究グループが他にいることに感づいていたベル研は、三ヶ月かけて特許保護のために必要な理論づけの研究を行い、素早く手を打って特許を確保した。そして軍事機密の観点から国防当局の厳しい審査を受けなければならなかった。
- これだけ革新的な発明であるのにもかかわらず、世間の反応は今一つ盛り上がらなかった。先に紹介したニューヨークタイムズの冷ややかな反応がそのよい例である。 その最大の理由は、この時の「点接触型」と呼ばれるトランジスタが、振動などのメカニカルなショックに弱いうえ、材料になるゲルマニウムの品質が悪く性能もまだまだ不安定で工業化に適さないからであった。「歩留まり」が極端に低く、商業ベースで採算の取れる見込みがたたなかったのである。 しかも、当時は真空管全盛時代であり、RCA、GE、シルバニア、レイセオンなどの大手真空管メーカーは、コスト的にも技術的にも真空管の優位は当分崩れないと判断し、トランジスタに目を向ける代わりに、真空管への投資を一層強化するほどだったのである。
- ショックレー(William B. Shockley)は、ベル研と親会社のウェスタン・エレクトリック社(WE社)の至上命令を受けて「点接触型」で発明された増幅機能を一つの結晶体のなかにつくる「接合型」トランジスタの理論をまとめることに成功した。はるかに安定性を増した高性能なものに生まれ変わった新しいトランジスタが試作されたのは、最初の発明から3年半後、1951年6月のことだった。 このように二つの段階を経て、商品化の道が築かれたトランジスタに真っ先に飛びついたのは国防総省であった。 1952年にアメリカ国内で生産されたトランジスタは約90,000個、いずれもWE社製だが、このほとんど全部を国防総省が買い上げ、軍事利用の研究に回したのである。
-
- ▼トランジスタの特許公開:
- 「トランジスタ技術は、公開した方が得策」と判断したベル研は、技術公開を渋っていた国防総省を説得して、1952年4月にはじめて一般向けセミナーを開いた。優勢な真空管に代わるトランジスタ時代を一日も早く実現させるには、「仲間」を増やす必要があったのである。 司法省がベル研の親会社ATTを相手取って、3年前に起こした独占禁止法違反訴訟への配慮も働いた。しかも、独占的な技術を公開することによって、莫大な特許料収入や他企業とのクロスライセンス(相互に技術を提供しあう協定)による新技術も期待できる。
- セミナーには、内外の企業数十社の代表がつめかけ、すでに電話交換装置の一部にぼつぼつ使われるようになっていたトランジスタの技術や製法の説明が行われた。会場には、今日半導体メーカーの最右翼に上げられているTI社(テキサス・インスツルメンツ)の幹部で現会長のシェパード氏らの顔も見られた。 当時のTI社は、電気関係には手を染めたこともない石油掘削機器のメーカーだった。セミナーの参加者に対して、WE社は25,000ドル(¥9,000,000)で特許を公開することを明らかにしたが、これに飛びついたのは、アメリカ国内だけで25社、外国からも10社が特許を買う契約を結び、ベル研とWE社の工場で製造法が伝授されたのである。
-
- ▼ソニーの技術革新:
- 1952年の春、滞在先のニューヨークでベル研のトランジスタ・セミナーの話を聞きつけたひとりの日本人がいた。
- その人は、当時まだ、東京通信工業と呼ばれた現在のソニーの井深大(いぶか・まさる: 1908 - 1997)氏である。開発したばかりのテープレコーダの売り込みのためのアメリカに出張していた氏が、この情報を現地で入手して、とんだ土産物につながったのである。
- WE社はテープレコーダを独自で開発した東通工の潜在的な技術力を評価して、トランジスタ技術の提供に前向きになる。一方、日本の通産省は、ちっぽけな町工場のような会社に貴重な外貨を使わせることはできないと、けんもほろろという状態であった。
- 東通工は足かけ2年の折衝の末、1954年(昭和29年)2月、ようやく外貨の割り当てを受け、25,000ドル(¥9,000,000)の特許料を支払って、技術の提供を受けることができたのである。
- 「ラジオのトランジスタ製法は歩留まりが悪くて難しいからやめた方がいい」 短いながら先駆者としての経験から出るWE社の忠告を振り切って、ソニーはラジオ用トランジスタの開発に邁進する。「掌に乗るラジオを。」を合言葉に、スピーカーやプリント基板、音量つまみにいたるまで、部品の小型化を研究させながらトランジスタの歩留まり向上を急いだ。 苦労に苦労を重ねたあげく、1955年(昭和30年)7月、トランジスタラジオが誕生する。開発された技術を巧みに取り入れて改良を加え、一般大衆向けの製品に仕立て上げた。ついには生みの親の持つ技術をはるかにしのぐところまで技術を向上させてしまう。今日の日本企業の技術開発の進め方の典型的なパターンがそこにはあった。
- - 「日本の条件12 技術大国の素顔(1)〜強いのかメード・イン・ジャパン」
- 日本放送出版界、昭和58年10月10日 第1刷
-
-
- ■トランジスタへの世代交代
- 真空管は、トランジスタの発明により歴史的な産物として博物館に飾られるシロモノになりつつあるが、それでもまだ現役で活躍している真空管 = 電子管も多い。しかし一世を風靡した電子管の多くのものがトランジスタをはじめとする固体素子(Solid State element)に変わりつつある。
- 至近な例では、テレビ受像機のブラウン管が液晶ディスプレーに置き換わりつつある。学術的にはCRT( = Cathode Ray Tube:陰極線管)と呼ばれるタマネギのような形状をした真空管であるが、これは1897年ドイツのストラスブール大学のK.F.ブラウン( = K. Ferdinand Braun、1909年ノーベル賞受賞)が発明したのでこの名前がついた。テレビカメラの撮像素子は1990年まではビジコン、サチコン、カルニコン、プランビコンと呼ばれる撮像管が主流を占めていたが、1990年以降CCDに代表される固体撮像素子が台頭し主役の座を明け渡してしまった。また、照明設備でも電球が発光ダイオード(LED = Light Emitting Diode)に置き換わりつつある。
-
- ■トランジスタの恩恵
- 1947年のベル電話機研究所によるトランジスタの発明によって、8年後の1955年にはこのトランジスタを使ったラジオが日本の東京通信工業(後のSONY)によって開発される。同時期米国IBMでは、真空管を用いたコンピュータのスイッチング素子をトランジスタに置き換えたIBM608を開発する。そして1960年には、またまた日本のSONYがトランジスタを使って世界初のトランジスタテレビ受像機を開発する。そしてさらに、1982年には、シリコンの光反応の特性とトランジスタ技術を融合したCCDカメラ(Charged Coupled Device)が日本のSONYによって市販化される。CCD自体は電子メモリにでも使えればという発想で米国AT&Tベル電話機研究所のBoyle(ボイル)とSmith(スミス)によって考案されたものである。
- トランジスタの特徴は言うまでもなく小型、コンパクト、低消費電力、高耐久性である。このトランジスタ技術を製品としていち早く製品に投入したSONYは以後小型コンパクトな電気製品をつくるユニークな会社としてのイメージを大衆に植え付けることに成功した。
- 1970年代のIC技術の確立と高集積化によってICメモリ、コンピュータチップの高速化、高集積化が進んだ。 現在の情報技術(IT)のすごさの基盤は、シリコンという半導体の恩恵に負うところが大きいのである。
-
-
- ■トランジスタの機能
-
- トランジスタの機能は、
-
- ●増幅作用
- ●スイッチング作用
-
- である。増幅作用とは、オーディオのアンプに見られるような磁気テープやCDなどの微弱な信号を大きな音に変えるための信号を大きくする作用である。こうした電気信号を増幅する素子としてトランジスタは魅力ある特徴を備えていた。
- 下図にトランジスタの働きを示した図を示す。トランジスタは、大きく分けてNPN型トランジスタとPNPトランジスタの二つがある。ここではNPN型について述べる(PNPも原理的には変わらない)。NPNトランジスタはN型のシリコン結晶の真ん中に薄く(数ミクロンの厚さで)P型領域を形成したシリコン結晶である。この薄い反対の電気的性能をもつ領域を同じ結晶中に形成させれば電気的な増幅ができるというのがショックレーの考えたトランジスタ理論である。
- シリコン結晶がN型領域のみであるとするとこの結晶は単に抵抗体としてしか電気的に機能しない。しかし、その間に薄くP型領域を形成させたシリコン結晶ではN→P方向に電子が流れるようになる。そしてN→P→Nに沿って別の回路を作ってやると、N→P回路で流れる電子に引きずられるようにしてその何百倍もの電子が移動するようになり結果的に電気増幅がおきるようになる。トランジスタは電流増幅と言われる所以(ゆえん)である(電圧増幅ではない)。
-

-
-
- もう一つの機能であるスイッチング機能は「奇天烈エレキテル その2、電気についてのデジタルな話」に触れているが、情報をデジタルで伝えていくための必要不可欠な機能である。そのスイッチング素子としてトランジスタは高速、低消費電力、小型化(高集積化)、高耐久性という特徴を持っていため大きな発展を見ることになる。
-
-
-
- 1-6-1. 半導体って?
-
- 半導体(semiconductor)といえばシリコン。シリコンと言えば時代の寵児となった言葉である。シリコンアイランド、シリコンバレー。多くの先端技術の背景にシリコンの名前が使われる。シリコンが使われる前は、ゲルマニウムが時代の寵児だった。そのほかにセレンなどという金属も使われていた。そうした流れの中で、なぜ、今、シリコンなのであろうか? ゲルマニウムとシリコンの違いは何なのであろうか? その半導体の代名詞であるシリコン[silicon = ケイ素(Si)]は、地球上で2番目に多い元素だそうである。ケイ素単体で存在する事はまずなく、酸化物や化合物として地球上に至るところで見られる。半導体は、元素周期表で見ると、IVa族に入る仲間で、これらには炭素(C、元素番号6、原子量12.011)、ケイ素(Si、元素番号14、原子量28.086)、ゲルマニウム(Ge、元素番号32、原子量72.59)、スズ(Sn、元素番号50、原子量118.69)、鉛(Pb、元素番号82、原子量207.2)がある。 これらの元素を挟むような形で元素周期表の両隣には、リン(P、原子番号15)、ガリウム(Ga、原子番号31)、セレン(Se、原子番号34)、インジウム(In、原子番号49)、アンチモン(Sb、原子番号51)が控えている。
-
- ■ゲルマニウムVSシリコン どっちが優秀?
- 半導体研究が始められた初期、同じ半導体の仲間であるゲルマニウムの方が単体として作りやすかったので、ゲルマニウムを用いた半導体素子が作られた。トランジスタを発明したベル電話機研究所のブラッデン、バーディーン、ショックレーらも初期のトランジスタはゲルマニウムを使っていた。半導体と言えばゲルマニウムかもしくはシリコンが代名詞であったが、今日ではシリコンが非常によく使われるようになっている。 ゲルマニウムよりなぜシリコンの方がたくさん使われているか?
- 【埋蔵量】
- まず第一に、シリコンは地球上にたくさんあり安定供給が望めることが大きな理由としてあげられる。 赤外線レンズにはシリコンとゲルマニウムが使われているが、ゲルマニウムの方が材料がうんと高いと聞く。また、ゲルマニウムの原材料は特定の地域にしか産出せずに、戦略物資の一つになっていると聞く。
-
- 【結晶製造の容易さ】
- トランジスタが開発された当時(1950年頃)、ゲルマニウムの産出国はベルギーとアメリカだけであった。東西緊張が高まる中、米国はゲルマニウムを戦略物質として買い占めた。価格は金と同じであったという。また、ゲルマニウムは重い。シリコンの比重が2.33に比べゲルマニウムは5.35で2.3倍の重さがある。それに加え、ゲルマニウムは材質的に脆く加工に神経を使う材料と言われている。しかしながらゲルマニウムは融点が958度と低く、シリコンの融点の1412度に比べて低いため結晶が作りやすいのが大きな利点であった。 半導体製造の初期にゲルマニウムが選ばれた理由がここにある。ゲルマニウムを溶かすルツボもグラファイト(黒鉛)で良かった。 反対に、シリコンは化合性が強いためグラファイトを用いると炭化ケイ素ができてしまう。シリコン単結晶生成のルツボには、高純度石英が使われている。石英はシリコンよりも融点が高いからである。 半導体材料としてシリコンが使われだすのは、シリコンの精錬精度、単結晶生成技術が向上するようになってからである。 シリコンの結晶は、ひとたび作られるとゲルマニウムの結晶よりも安定して使いやすかった。
-
- 【安定した温度特性】
- シリコンが使われる第二の理由は、温度が高くなっても性能が安定していることである。ゲルマニウムは温度が50度前後になると性能がとたんに不安定になった。反面シリコンは150度の高温に耐えられた。軍用機器にトランジスタを多用する必要に迫られた米軍は、温度特性がよく耐久性にも耐えられるシリコントランジスタの開発を急がせ、1960年代にはシリコントランジスタが主流になっていく。
-
- 【高い集積化能力】
- シリコンが使われる第三の理由は、酸化被膜(酸化ケイ素)の形成である。シリコンは化合性が高くいともたやすく他の分子と結びつく。酸素とも強く結びつき、これが酸化ケイ素となる(石英は酸化ケイ素からできている)。この酸化ケイ素は良好な絶縁体である。この絶縁被膜の発見こそがシリコンを基板とした集積回路の立て役者であり、小さなチップに数百万個のトランジスタの配置を可能にした大きな特性であった。 ちなみに化合物半導体として高性能な素子として期待されているガリウム・ヒ素がシリコンのように主流デバイスになりにくいのは、シリコン酸化膜のように簡単で良質な絶縁被膜ができないためと言われている。
-
- 【ゲルマニウムトランジスタを作っているメーカ】
- 現在では、ゲルマニウムトランジスタはほとんど使われていない。しかしアメリカに一社ゲルマニウムトランジスタを製造しているメーカがあるという。このメーカーは、ボストン近郊のアンドーバー市にあるゲルマニウム・パワー・デバイス社である(この会社が2001年当時も仕事を継続しているかどうかは知らない)。ゲルマニウムの単結晶は、日本の住友金属鉱山とベルギーのホーボケンという会社から仕入れている。この会社はゲルマニウムの特性を生かした素子を作っている。ゲルマニウム・ダイオードは順方向の電圧低下が少なくて(約0.3V、ちなみにシリコンは約0.6V)、大電力の交流を直流に変換する整流素子としてはシリコンより優れている。電圧降下はそれだけ発熱を多く伴う。電圧降下の少ないゲルマニウム素子は、シリコンの半分の発熱となる。従って、ゲルマニウムを使用したパワートランジスタは、高速コンピュータを作っているコンピュータ会社に需要があるといわれている。
-
-
- ■半導体の特徴
- 半導体は、以下の特長を持っている。
-
- ● 常温で金属と絶縁物の中間の抵抗率(1 x 10-3 〜 1 x 1010Ω・cm)を示す。
- ● 極低温では絶縁物に近く無限大の抵抗を示すにもかかわらず、
- 温度上昇とともに急激に抵抗率が下がる。
- ● 半導体に不純物が混入したり、光をあてると抵抗率が大きく変化する。
-
- これは、良導体の金属が温度上昇とともに抵抗が上がるのと反対で、半導体の一つの特徴である。不純物の混入を理論的に分析し、シリコン結晶中にインジウム(In)もしくはアンチモン(Sb)を混入させることによって、特性のよくわかった半導体ができる。電気をよく通すかと思えばまったく通さなかったりと、なんとも気まぐれな電気特性をもった半導体も、ショックレーらの理論的な裏付けで精密に制御できるようになった。どころか、1秒間に100万回、いやそれ以上の10億回以上の応答で信号を作り出せるまでに半導体技術は進歩した。
-
- また最近急成長を遂げているデジタルカメラ、8mmビデオに使われている光センサーには、CCD(Charge Coupled Device)と呼ばれるシリコン半導体素子が使われている。CCDは、シリコンの光に反応する特性をうまく利用したものである。CCDの詳細説明は、以下のサイトを参照してほしい。
- AnfoWorld「高速度カメラ入門Q&A」 Q26. 固体撮像素子って何? AnfoWorld「光と光の記録」、撮像素子 - - -CCD(Charge Coupled Device)素子
-
-

-
- ■半導体物質
-
- 半導体の代表的なものに、単体のシリコン、ゲルマニウム、セレンがあり、金属酸化物では、酸化亜鉛、酸化鉛、酸化銅がある。また金属間化合物ではガリウムヒ素(ヒ化ガリウム)、ガリウムリン(リン化ガリウム)、インジウムアンチモン、硫化カドミウム、テルル化カドミウム、有機化合物のアントラセンなどがある。有毒な金属の名前が列挙されている。
-
- 元素の周期表で見てみると、これらの元素は、IVa族に属するものである。元素の周期表は原子量の順番に並べられているが、原子量の少ない順番に8個ずつを単位にわける「族」は属性がきわめて似通っている。たとえばVIIIa族の不活性元素(He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn)は、どの元素とも結びつきにくい単独で存在している元素である。また、VIa族のハロゲン元素(F、Cl、Br、I、At)は、電子一つを強烈にほしがるため活性度(強い酸化作用)の高い元素である。
-
- 難しい話になるが、元素の周期性がわかってからというもの、元素の属性を左右するのは原子量ではなく、原子が持ちうる電子の数が問題になることがわかった。原子を構成している電子は、原子核との間に量子力学的な関係があり、すべての電子が自由に振る舞えるわけではなく、太陽の周りを回っている惑星と同じように、ある決められた軌道に沿って電子が回っていると考えられている。原子核に一番近い軌道は、K殻と呼ばれるものでそこは電子が2つ入ると一杯になってしまう。水素は電子一つを抱え、K殻の軌道で回っている。ヘリウムは二つの電子をもっていて、K殻はその電子で満たされている。水素は、もう一つの電子をK殻に取り込むだけの力を持っており、これが他の元素と電子を共有する(共有結合、化合)力を持つことなる。ヘリウムは、逆にとても安定していて電子を共有しなくても満足できるから他の元素と結びつかない不活性元素となる。
-
- K殻が2つの電子で埋まると、その外にあるL殻には8つまでの電子が回ることになる。L殻に一つの電子をもったものがリチウムであり、L殻一杯に電子をもったものが原子番号10のネオンである。
-
- 半導体物質は、炭素族であるから、最外準位に4つ電子を受け入れる構造をした原子ということができる。つまり4つの電子をもらって共有結合する原子である。従って、電子的に4つの手をもっているのと同じであるから炭素や、シリコン、ゲルマニウムは原子が4つ近づいて結晶を作る立方格子状結晶を持つ。
-
- このような観点から見ると、純粋なシリコン結晶(半導体)は、原子結晶自体で電子の強力な結びつきがあるため電子を放出しずらく、結果的に電子を流しずらいものと言うことができる。
-
- 金属とはそもそも電子的にどんな特性があり、電気を流しやすいというのはどういう意味があるのであろうか?
- 増本氏が著した「金属なんでも小辞典」という本にヌケの良い解説があるので引用する。
-
- 【金属】 原子核から一番近い殻はK殻と呼ばれ、2個まで電子を取り入れることができる。そのすぐ外側のL殻には8個の電子、その外のM殻は18個まで電子を取り込む。つまり、原子核からn番目の殻が取り込める電子の数は、2 x n 2 で表すことができる。 それぞれの殻は、軌道上の電子がいっぱいになると電荷がつり合っていなくても、非常に安定する。周期表でいちばん右の0族のヘリウムやネオンなどがほかの物質と化合したりしないで安定なのは、それぞれK殻、L殻が電子でいっぱいになっているためである。 そして、安定しない原子も、できるだけ安定な状態になろうとする。そのためには最外殻に不足している電子が数個であれば取り込んだ方がいいし、最外殻にわずかしか電子がなければ放出したほうがいい。金属はすべて後者である。 つまり金属は、最外殻の電子が活発で離れやすい状態にある原子であるといえる。それはまた陽イオンになりやすいということである。
- - 「金属なんでも小事典 - 元素の誕生からアモルファス金属の特性まで」
- BlueBacks Y820 増本 健監修
-
- ものの本を読むと、金属は自由電子が云々という言葉がよく出てくる。自由電子とはとりもなおさず原子核を回っている電子の最外殻の電子が原子核との結びつきが弱く絶えず離れたりくっついたりを簡単に行えるものということができる。最外殻電子との結びつきが弱いから電圧(電気の勾配)が加えられればいともたやすく電子が流されるのである。
-
- では、半導体はどうかというと、ケイ素(シリコン)の場合、14個の電子を持っていて、K殻に2個、L殻に8個、M殻に4個持っている。あと4つ電子がM殻に入ると18個になってアルゴンと同じ電子数になり安定する。つまり、シリコンは4個の電子をほしがっている。ここでシリコンは、原子単体や結晶では自然界に存在しずらくたいてい酸素と結びついた酸化ケイ素(SiO2)の形になっている。石英などはこの分子でできあがっているが、この酸化ケイ素は原子の結びつきが強い共有結合であるため電子の自由な動きは制限される。ガラスが電気の絶縁体と言われるゆえんである。ケイ素の結晶も共有結合であるため電気の通りは良くない。
-
- そのシリコンの結晶の中にちょっと違った原子(電子をちょっと多く持ったアンチモン = Sb、5個の価電子。ちょっと少ないインジウム = In、3個の価電子)を打ち込んでやると、この不純物(純粋な半導体に対して電気を運ぶ物質 = 伝導物質のことを不純物という)の持つ電子が特異な働きをするようになる。アンチモンのような5個の価電子を打ち込んだものをN型半導体、インジウムのような3個の価電子を打ち込んだものをP型半導体という。N型伝導物質は自由電子を多く持つ物質でP型伝導物質は「正孔」を持つ物質ということになる。
-
-
-
- ■半導体の発見の歴史
-
- 歴史的に見ると、半導体の特徴を世の中に表したのは1873年 スミス (Willoughby Smith: 1828 - 1891、英国電信会社、Gutta Percha Company, London勤務) であると言われている。彼は、セレン(selenium)に光を当てると電気伝導が変化する光導電効果を発見した。セレンについでゲルマニウムに半導体の特徴があることが発見され、シリコンはその後になっている。シリコンに半導体の特徴があることがわかるのに時間がかかった理由は、融点が1410℃とゲルマニウムの融点の937.4℃に比べ高く、それに酸化物として強く結合し単体に分離するのに当時の技術では難しかったことがあげられる。工業的にシリコンを作るには電気炉内でコークスにより酸素を遊離して(還元して)取り出す。
-
- 半導体という言葉は、第一次世界大戦後ドイツの科学者ケーニッヒスバーガー(Johan Konigsberger)の研究室で使い出してから始まったとされている。ドイツ語でHalbleiterという言葉が英語でsemiconductorと呼ばれるようになり、日本語で半導体と訳された。当時、金属は温度が上がると電気抵抗が増すというのが通説であったが、ある物質では温度の上昇と共にまるで気体のように電気伝導度が増す現象が見られた。ケーニッヒスバーガーは、これは物体の中の電子に作用する活性エネルギーが伝導に寄与すると考えた。この活性化エネルギーで電子が伝導する物質を半導体(Halbleiter、Semiconductor)と呼んだ。
-
- こうした良導体と絶縁体の中間の振る舞いをする物質については、英国物理学者デービー(Humphry Davy)とファラディーによって観察されていた。デービーは、ガルバーニーが電池を発明した直後、多くの金属の伝導特性を研究し温度が上がると金属の電気伝導度が低下することを見つけていた。デービーの門下生のファラディー(Michael Faraday)は、デービーの測定を金属以外の多くの化合物に向け金属以外の物質(硫化銀、硫化銅など)は金属とは逆の法則、すなわち、高温で電気伝導度が高くなることを明らかにした。同年代1839年にA.E.ベックレルもある材料と電解質との界面に光を当てることにより電圧が発生する光起電力効果を発見した。
-
- また、結晶構造においても導体と絶縁体の中間の挙動があることがわかりだしてきた。ドイツの物理学者ブラウン(Ferdinand Braun)は1870年代、電気を良く伝えない天然に産する硫化物結晶について、電気伝導度が電流の流す向きによって変わることを発見した。結晶の整流効果である。これらの結晶は取り付けられた電極の大きさが違うほど整流作用が大きいことを見いだした。これゆえ初期のダイオードやトランジスタは点接触構造となっていた。ブラウンの発見はその後、いろいろな研究者が追試した。その結果、均質な結晶の中での電気伝導はオームの法則に従い、整流作用があるのは表面近くにある阻止層と呼ばれるものに関係があることがわかった。しかし、この発見が直ちに注目されたわけではなく、無線電信が発達する19世紀の末まで目立つ存在とはならななかった。
-
- イタリア人マルコーニ(Guglielmo Marconi)が無線通信時代の幕開けを告げると無線を送信するための発信・受信器の開発が急ピッチで進められた。信号を検波する装置には、最初コヒーラ(coherer:フランス語、検波器)が使われ、その後インドの科学者ボース(J.C.Bose)が方鉛鉱(PbS)の結晶を用いた整流器を発明した。その後、検波器は結晶構造のものから真空管時代へと入っていく。イギリス人科学者フレミング(John A. Fleming)は、結晶構造を使った装置に代わる整流器として二極真空管(ダイオード)を発明したのである。これを契機に真空管は大きな発展を見る。しかし真空管には大きな欠点があり、これを克服するために再び結晶構造の整流器の研究が高まることになる。
-
- ベル電話機研究所では、来るべき真空管に置き換えるべき素子としてどんな半導体何が使えるかの研究をおこなっていた。この研究を担当していたのがベル電話機研究所の無線研究グループの化学者ラッセル・オール(Russel S. Ohl)と冶金専門家ジャック・スカッフ(Jack Scaff)であった。彼らはレーダの検波に使う半導体として何が最適かを調べるため100種類に及ぶ鉱石をテストし、その結果レーダー波検波用の鉱物として、シリコン・タングステンの組み合わせが最も優れているという結論を下した。シリコンは、当時、ドイツのアイマー・アメンド化学社から購入したものがもっとも高純度で良好であったという。
-
- ■ pn接合 シリコン単結晶にある不純物を入れることにより、電子をためやすい性質を持つN型半導体と正電荷をためやすい性質を持つP型半導体ができることがわかった。これらの半導体に金属を点接触させることにより電気が一方向に流れるため、昔はこれを検波器や整流器として使っていた。1939年にN型、P型半導体を発見したラッセル・オールとジョン・スカッフが使ったシリコン結晶は偶然にもPN接合であった。
-
- ● 点接触型トランジスタ ベル電話機研究所のバーディーンとブラッテンの発明した点接触型トランジスタは、ゲルマニウム(N型)結晶の表面に細い二本の針をミクロン単位の間隔で接触させていた。この状態を長く維持することはとても困難だった。ベル電話会社の製造会社であるWE(ウェスタン・エレクトリック)社は、彼らの発明した点接触型トランジスタの量産に踏み切りこれをベル電話会社が電話回線に使用するがあまりに故障が多くて生産を中止せざるを得なくなった。真空管よりも信頼性が悪かったのである。
-
- ● 接合型トランジスタ ショックレーは、こうした問題を抱える点接触型トランジスタに代えてpn接合をもつトランジスタを提唱した。つまり一つの結晶中にNPNの構造を持つトランジスタを考えたのである。 接合トランジスタの特徴は以下に述べる通りである。
-
- 1. 一つの単一結晶である。
- 2. 単一結晶の中にN型、P型、N型と3つの領域がサンドイッチ状に隣接している。
- この構造は、貼り合わせのものではない。
- 3. 3つの領域の真ん中の領域(NPN型でPN型層)は非常に薄いミクロン単位の厚さである。
- 4. N型領域は、N型の伝導物質(ガリウム、ホウ素、インジウムなど)がドーピングされている部分であり、
- P型領域はP型の伝導物質(リン、アンチモンなど)が混入されたものである。
-
- このp型n型のシリコンを効率よく作る手法の確立によって、半導体技術が飛躍的に高められていった。 しかし、どうすれば単一結晶の中にNPNの三つの領域をつくり込むことができるのか。 どうしたらN型結晶の中に非常に薄いP型層をつくり込むことができるのか。 ショックレーが考案した接合型3層構造の結晶(トランジスタ)も当時の技術水準ではその方法が見つからなかった。
-
- まず最初に確立できた手法は半導体(ゲルマニウム)の高純度化、結晶成長手法である。 ベル電話機研究所のプファン(William G. Pfann)が、1954年にゾーン・リファイニング(帯溶融精製)という手法でそれを確立する。この手法でゲルマニウムの純度を100万分の1から1億分の1(99.999999%から99.99999999%)まで上げることができた。
-
- 半導体素子の製法についてはとても専門的で私自身も良くわからないため、ここでその解説を試みたとしても十分に内容が伝わらないだろう。この世界の技術革新が行われていく中で、特に大事だと思われることを以下に箇条書きにまとめてみたい。
-
- ▲ シリコン結晶の製造の確立 → 酸化物として存在しているシリコンをいかに純度よく取り出すか。
- 結晶シリコンを作る技術の確立。
- ▲ シリコンを薄板に作る技術、磨く技術、検査する技術
- → 結晶シリコンのインゴットから薄板(ウェハー)を切り出す技術。
- ウェハー鏡面研磨の技術、結晶欠陥を検査する技術。
- ▲ 不純物を混入(ドーピング = doping)させる技術
- → 不純物拡散法、イオン打ち込み法、エピタキシー法の確立。
- ▲ シリコン基板状に複雑なパターンのpn層を形成する技術 → マスク技術、パターン描画技術。
-
- これらの半導体製造に関わる周辺技術として、
-
- ・温度制御技術
- ・3次元精密微動制御装置
- ・精密切断加工機械
- ・写真製版技術
- ・顕微鏡光学装置
- ・電子顕微鏡装置
-
- などの高度な技術が要求されている。
-
- ■電気を流す
-
- シリコンの結晶自体には、電気を流す良好な特性はない。むしろ電気は流れない。完全なシリコン結晶は相互に電子をしっかりと保持しているため、電子を外に出さないし入ってくる余地もない。酸化ケイ素も電気的に安定した構造であり絶縁物となっている。しかし、シリコン結晶の中にわずかに電子結合の違う異原子を結晶構造内に組み入れてやると原子構造に欠陥ができて電気的に不安定な構造となり電子を出しやすい構造(N型)と電子を引き入れやすい構造(P型)ができるようになる。電気を流すというのは導体中に電気の勾配を作ってやることである。乾電池の電源であったり発電所からの電気であったり。こうした電気的勾配の中に半導体を接続すると電子を引き入れやすい構造では一方向に電気を流すことができるようになる。これがダイオードである。
-
1-6-2. シリコンって何者?
- 半導体の代名詞になったシリコン。
- シリコンの組成、シリコン結晶ができるまでについて述べてみたい。
- シリコンは、ケイ素とも呼ばれている。白っぽい石にたくさん含まれているのがケイ素。しかし単独では存在しないため、酸化ケイ素(SiO2)の組成で白石、珪石、火打ち石として見ることができる。私が子供の頃、道ばたで白石を見つけるとそれが宝物になった。白石は暗いところでぶつけると火花が出た。これが子供心に貴重な物に映った。酸化ケイ素がもっと順序よく結晶化すると水晶(石英)になる。山で水晶を見つけることが我々の子供の頃の宝探しであった。
-
- ケイ素は世界中の至る所にあると言う。花崗岩や玄武岩のなかにも多量にシリコンは含まれている。地殻の元素のうちで酸素についで二番目に多い元素だという。しかし同じ仲間の炭素と違って単体では存在せず酸素との酸化物、アルミニウム、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウム、鉄などと結びついて無数のケイ酸塩として、岩石、土壌、粘土などを形成している。
-
- ■ 半導体材料に使われるシリコンの原石
- このようにありふれたシリコン原石であるが、半導体材料に使う原石は日本から調達しない。シリコン原石、あるいは珪石と呼ばれるものは、酸化ケイ素(SiO2)の純度が95%以上あるものを言う(下写真左)。もちろんこうした原石は日本でも産出するが、半導体基板用としては100%輸入に頼っている。日本でも産出するシリコン原石を何故使わないかというと、その答えは世界一高い日本の電力料金にある。シリコン基板を作るためにはシリコン原石からシリコンだけを析出してシリコン結晶を作らなければならない。その析出に電気炉を用いるため、シリコン生産には莫大な電気を必要とするのである。これはアルミニウム精錬と一緒である。シリコン精錬を日本で行っていては採算が合わないため、砕石現場にてある程度の純度に上げて日本に持ち込むのである。日本に輸入されるシリコンはすべてシリコン結晶(単結晶ではなく金属多結晶)の形まで精錬して輸入される(下写真右)。
-
- こうして観点からシリコン原石を輸入する先はどこになるかというと、電力料金が安く、良質のシリコン鉱石が産出される国となり、カナダ、ブラジル、スウェーデン、フランスがその輸入国となっている。
-


-
- ■シリコン鉱山
- シリコン原石はどのような形で産出しているのであろうか?
- ここに、そのことについて触れたおもしろい本がある。
- NHKが1983年4月に放送したドキュメンタリー番組『日本の条件[技術大国の素顔]』シリーズの書籍「日本の条件12 技術大国の素顔(1)〜 強いのかメード・イン・ジャヤパン」1983年10月10日初版 日本放送協会発行 である。
-
- 彼らはフランスのラ・フェルトュ・アレイ鉱山を取材地に選んでいる。この鉱山はパリから南へ100キロ。フランス・オルリー空港から車で1時間半の所フォンテンブローの森の近くにある。ラ・フェルトュ・アレイ鉱山の操業は1952年。1983年当時の年間生産量が75,000トンで世界最大級のシリコン鉱山だそうだ。
- ここで産出するシリコン原石の9割がガラス、陶磁器の原料に回され、残りの一割が半導体の原料として輸出されるのだという。しかし、ここ数年、半導体としての用途は毎年3倍の勢いで急増していてその将来に大きな期待が寄せられていると記されてあった。もちろん得意先は日本。ここで採れた原石は貨車でアルプスのふもとにある工場に運ばれ、そこで金属シリコンに精錬されて、マルセイユの港から日本に輸出される。 「数年前、日本の商社の人間が、本社の人間に連れられて、突然シリコンを買いたいと、この山奥の鉱山を訪ねてきたときは、ビックリした」 と話すベルトルュス氏の言葉には実感があったとその本は記している。
-
- この鉱山の様子を一言で述べるとすれば、巨大な石切場という印象だそうだ。地上から1-2メートルの粘土層で覆われた地表の下はシリコン原石が鉱脈をなして連なっている。それが端から端まで300メールはあろうかと思われるほど山肌を削って大型ブルドーザとトラックが豆粒のように動いている。豊富な埋蔵量と97%を超えるという酸化ケイ素の純度がこの鉱山の自慢でもある。削岩はダイナマイトで行いブルドーザがトラックに積載していく。ここでとれるシリコン原石は、きらきらと光る砂が固まったようなものだそうだ。非常に脆く、親指で押しただけでさらさらと崩れていく。珪砂が水で浸食されて固まったものだというのが鉱山の所長の説明だった。
-
- 彼らは、ここで採れた鉱石が、洗練されて半導体に生まれ変わっているということは知識で知っていた。つまり、セミ・コンダクター(半導体)というこ・と・ば、は知っているもののその実物は知らなかったのである。そこで、取材班が東京から持って行ったシリコンの基板を彼らに見せたところ、「アンビリーバブル」(信じられない)ということばが、一様に返ってきた。 続いて、このシリコンの基板の上には、何十万もの回路が組み込まれ、いわば電子頭脳の働きをすると説明し、これは、あなたの時計のなかにも入っていると言った時の、みなの驚きの表情は忘れない、と取材の感想が述べられていた。
-
- NHKが放送した半導体産業に関するドキュメンタリー番組がある。 相田洋氏がディレクターをした『電子立国 日本の自叙伝』という番組である。 書籍は1991年に初版が出ているから放送は1990年だと思う。 このNHKスペシャルはとてもワクワクするものであった。 相田氏の映像を通したドキュメンタリー番組の取り組み方にとても敬服して、その番組を見ていた記憶がある。 この番組でもシリコン鉱山を取材している。取材の内容は以下の通り。
-
- 【採掘現場はフィヨルドの海岸】
- ノルウェーの首都オスロから4回飛行機を乗り継いで10時間。北緯70度30分、珪石の採掘現場は北極海に面した断崖の上にあった。露天掘り、推定埋蔵量7,000万トン。1日平均4,000トンずつ掘っても、50年間は楽に持つ量である。
-
- 地表に露出した鉱床を発破で粉砕し、パワーショベルですくい上げダンプが海岸にある砕石工場に運んでいく。ここで採れる珪石は、薄く青みがかっている。シリコンの含有率が46%、世界最高水準の石である。
- この珪石を砕石工場で野球ボール大の大きさにそろえて、8,000トン級の鉱石タンカーに積み込んでフィヨルドの島々を縫うように南西850kmに下り、ブレメンガー地方スペルンの町(人口1,500人)にある世界最大の金属シリコンメーカー、エルケム・ブレメンガー工場に運び入れる。ここでは、豊富な水源(年間雨量3,000mm、大小30もの湖、フィヨルドの高低差の多い地形)を利用して、工場の地底4カ所に水力発電所を設け、豊富な水が産み出す安い電力を利用して非常に安価なシリコンを精製している。この工場では、3基の電気炉が24時間稼働し、珪石を溶かし、コークスと生木のチップを混ぜて電気炉に投入し、炭素電極で電気を流して珪石を2,000度で溶かし酸素を奪って(還元して)、液体のシリコンを溶かし続けている。オレンジ色に輝く液体を取り出して冷やすと92%純度のシリコンができあがる。これをさらに化学処理して98%純度の粉末シリコンができあがり、輸出される。年間生産量50,000トン。約7割が日本向けである。
- - 『電子立国 日本の自叙伝(上)』 相田 洋(あいだ ゆたか)著、1991.8.20第1刷、日本放送出版協会
-
- ■ICに使うシリコンの精錬
- シリコンはありふれた物質であるが要求されている純度は99.999999999%と呼ぶ目もくらむ純度である。いわゆるイレブンナイン(9が11個)と言われるものである。この純度に加え、シリコンにはこの純度に加えシリコン原子が一つ一つ規則正しく並んだ単結晶の形になっていなければならない。きちんと並んだ結晶の中にリンやボロンという不純物を入れ込んで(ドーピングして)理想に近いP型、N型シリコンを作るのである。
-
- 鉱山で採掘され電気炉により精錬された金属ケイ素の純度は97-99%程度である。これを箱詰めして海路日本に送られる。国内では送られてきた金属ケイ素をまず塩化水素に反応させてトリクロロシラン(SiHCl4)という気体にする。この蒸留技術が後々のシリコンの純度に大きく影響を与えるそうである。これを水素と反応させて塩素と不純物を取り去って高純度シリコンを得る。しかし、この段階ではまだ原子がきちんと並んでいない多結晶シリコンと呼ばれるもので、この多結晶シリコンをさらにもう一度溶かして原子がきちんと並んだ単結晶シリコンを作る。
-
 こうしてできた単結晶シリコンはインゴットと呼ばれる10cm程度の棒状のものになる(右図参照)。この棒状(ダイコン状)のシリコンインゴットを薄い輪切りにしてその表面を磨き上げウェハーと呼ばれるシリコンの円板を作る。このようにして金属色の薄い丸円板ができあがる。このウェハーが集積回路(トランジスタ回路)を作る基板となるものである。この基板にN型、P型にするためのドーピング処理を行っていく。その上に2.5ミクロンという細い微細加工を施していく。現在のコンピュータの心臓部のCPUはサブミクロン、0.25ミクロン幅(Pentium III、Katmai)、0.18ミクロン幅(Pentium III Coppermine)になっている。空恐ろしい数字である。
こうしてできた単結晶シリコンはインゴットと呼ばれる10cm程度の棒状のものになる(右図参照)。この棒状(ダイコン状)のシリコンインゴットを薄い輪切りにしてその表面を磨き上げウェハーと呼ばれるシリコンの円板を作る。このようにして金属色の薄い丸円板ができあがる。このウェハーが集積回路(トランジスタ回路)を作る基板となるものである。この基板にN型、P型にするためのドーピング処理を行っていく。その上に2.5ミクロンという細い微細加工を施していく。現在のコンピュータの心臓部のCPUはサブミクロン、0.25ミクロン幅(Pentium III、Katmai)、0.18ミクロン幅(Pentium III Coppermine)になっている。空恐ろしい数字である。-
- このシリコン単結晶を作るメーカは、世界に数社しかなく、ドイツのワッカー・ケミカル社、米国のモンサント社、日本の信越半導体が大きなシェアを持っている。
-
1-7. ICからLSI、マイコンチップ (2015.07.17)
- ■ ICとは
- 現在の電子機械はすべてIC、LSI、マイコンによって作られている。
- これらはトランジスタがたくさん集まったもので集積回路(Integrated Circuit)と呼ばれた。
- これがさらに進んで、高集積回路(LSI)となり、頭脳を持つLSI、CPUが作られるようになった。
-

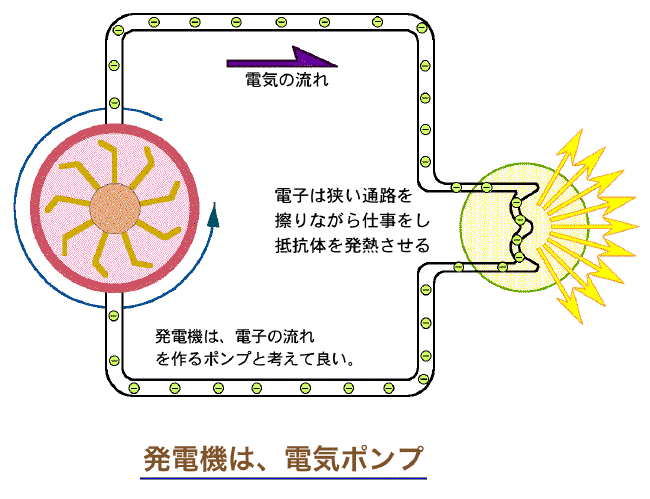

 【仕事をする電気】
【仕事をする電気】
 電気には、どのような作用があるのだろうか。
電気には、どのような作用があるのだろうか。
 サーミスタは温度によって抵抗が変化するので、この性質を利用して電流値を検出することで温度を測定することができる。
サーミスタは温度によって抵抗が変化するので、この性質を利用して電流値を検出することで温度を測定することができる。 さて、発熱の話。
さて、発熱の話。 電源コードは、おそらく0.1V程度の電位差(逆に言うと0.1オーム相当の抵抗)しかない。
電源コードは、おそらく0.1V程度の電位差(逆に言うと0.1オーム相当の抵抗)しかない。

 電熱作用から発生した電気製品に白熱電球がある。
電熱作用から発生した電気製品に白熱電球がある。
 この成功から実用化までにさらに改良が続けられた。
この成功から実用化までにさらに改良が続けられた。
 ガス灯の実用化は、1802年、イギリス(スコットランド)のマードック(William Murdock:1754-1839)が石炭ガスの発生装置を作り、これをボールトン・ワット商会(Boulton and Watt = 蒸気機関の改良を行ったJames Wattとその友人ボールトンの会社)のソホー工場(Soho Manufactory)の照明に使ったのが始まりとされている。
ガス灯の実用化は、1802年、イギリス(スコットランド)のマードック(William Murdock:1754-1839)が石炭ガスの発生装置を作り、これをボールトン・ワット商会(Boulton and Watt = 蒸気機関の改良を行ったJames Wattとその友人ボールトンの会社)のソホー工場(Soho Manufactory)の照明に使ったのが始まりとされている。
 ガス燃焼器の改良を経て、マードックの教え子であるクレッグ(Samuel Clegg: 1781 - 1861)が10年後の1812年に世界最初の都市ガス会社(the Gas Light and Coke Company = the Westminster Gas Light and Coke Comapnay)を設立した。
ガス燃焼器の改良を経て、マードックの教え子であるクレッグ(Samuel Clegg: 1781 - 1861)が10年後の1812年に世界最初の都市ガス会社(the Gas Light and Coke Company = the Westminster Gas Light and Coke Comapnay)を設立した。

 日本でのガス灯事業は、順調な広がりを見せ、商店の照明などにも普及を見たが、一般家庭にまで普及するには至らなかった。
日本でのガス灯事業は、順調な広がりを見せ、商店の照明などにも普及を見たが、一般家庭にまで普及するには至らなかった。



 もう一つ、加熱機器に電磁調理器(IH調理器、IHはInduction Heater)というのがある。
もう一つ、加熱機器に電磁調理器(IH調理器、IHはInduction Heater)というのがある。
 モータの原理の核心は、電気を通すと力を発生する
モータの原理の核心は、電気を通すと力を発生する ■ モータの大きさと種類
■ モータの大きさと種類 
 1820年、デンマークの化学者エルステッド(Hans Christian Oersted、1777-1851、磁界の強さの単位エルステッド[Oe]は彼の名前にちなむ)は、電流が磁場を作り出すことを発見する。
1820年、デンマークの化学者エルステッド(Hans Christian Oersted、1777-1851、磁界の強さの単位エルステッド[Oe]は彼の名前にちなむ)は、電流が磁場を作り出すことを発見する。
 実用的な最初の発電機は、1870年にベルギーの職人ツェノーブ・グラム(Zenobe Theophile Gramme、1826-1901)によって製作された。
実用的な最初の発電機は、1870年にベルギーの職人ツェノーブ・グラム(Zenobe Theophile Gramme、1826-1901)によって製作された。
 新幹線300系(のぞみ車両)には300kW出力のモータが1車両あたり4基、合計10車両(6車両は従車)に配備されている。
新幹線300系(のぞみ車両)には300kW出力のモータが1車両あたり4基、合計10車両(6車両は従車)に配備されている。
 機関車重量は、100.8tである。
機関車重量は、100.8tである。 その産業革命の立て役者となった蒸気機関の発明と改良が、イギリスの国力を一気に高めた。
その産業革命の立て役者となった蒸気機関の発明と改良が、イギリスの国力を一気に高めた。 トレビシック(Richard Trevithick: 1771 - 1833)は、無類の機械好きで、12、3才の頃よりワットの蒸気機関「水くみエンジン」の組み立ての手伝いをし、その才能が認められてワット・ボールトン商会で働くようになる。
トレビシック(Richard Trevithick: 1771 - 1833)は、無類の機械好きで、12、3才の頃よりワットの蒸気機関「水くみエンジン」の組み立ての手伝いをし、その才能が認められてワット・ボールトン商会で働くようになる。
 1830年に登場したロケット号(写真右)は、イギリスのリバプール&マンチェスター鉄道で走った最初の旅客営業鉄道機関車であった。
1830年に登場したロケット号(写真右)は、イギリスのリバプール&マンチェスター鉄道で走った最初の旅客営業鉄道機関車であった。
 イギリス産業革命の歴史を見てみると、色々な人間模様があったことを思い知らされる。
イギリス産業革命の歴史を見てみると、色々な人間模様があったことを思い知らされる。
 息子ロバート(Robert Stephenson: 1803 - 1859)は、父親の才能と意志を汲み、鉄道事業では鉄道架設、鉄橋建設、トンネル建設に優れた才能と業績を発揮した。
息子ロバート(Robert Stephenson: 1803 - 1859)は、父親の才能と意志を汲み、鉄道事業では鉄道架設、鉄橋建設、トンネル建設に優れた才能と業績を発揮した。
 ファラディは、1791年イギリスロンドン郊外に生まれた。
ファラディは、1791年イギリスロンドン郊外に生まれた。
 ここらあたりになると、若干イヤになってくる分野だ。
ここらあたりになると、若干イヤになってくる分野だ。
 電気は、酸とアルカリを反応させると電子が移動して電気が流れるようになる。
電気は、酸とアルカリを反応させると電子が移動して電気が流れるようになる。 実際のところ、ボルタの電池ができるようになって、電気工学、電気化学の大いなる発展を見た。
実際のところ、ボルタの電池ができるようになって、電気工学、電気化学の大いなる発展を見た。 動物が電気を作るという考えを示したのは、イタリアの解剖学者・生物学者ルイジ・ガルバニ(Luigi Galvani、1737-1798)であった。
動物が電気を作るという考えを示したのは、イタリアの解剖学者・生物学者ルイジ・ガルバニ(Luigi Galvani、1737-1798)であった。
 ダニエル電池の出現によって、グローブ電池やブンゼン電池が現れ、電信用に使われるようになった。
ダニエル電池の出現によって、グローブ電池やブンゼン電池が現れ、電信用に使われるようになった。 通信手段の『無線』の登場は、イタリア人でイギリスに渡ったマルコーニ(Guglielmo Marconi: 1874 - 1937)からスタートする。
通信手段の『無線』の登場は、イタリア人でイギリスに渡ったマルコーニ(Guglielmo Marconi: 1874 - 1937)からスタートする。
 1900年、マルコーニが無線通信会社を設立したときに有能な技術顧問を雇っている。
1900年、マルコーニが無線通信会社を設立したときに有能な技術顧問を雇っている。

 また、この画期的な大発明はマルコーニ社に利益をもたらすどころか、2年後、米国の発明家ド・フォレスト(Lee De Forest: 1873 - 1961)によって三極管が発明されたとき、真空管発明の先取権をめぐる長い訴訟の種となり、結局、高い開発品となってしまった。
また、この画期的な大発明はマルコーニ社に利益をもたらすどころか、2年後、米国の発明家ド・フォレスト(Lee De Forest: 1873 - 1961)によって三極管が発明されたとき、真空管発明の先取権をめぐる長い訴訟の種となり、結局、高い開発品となってしまった。




 ▼宇宙開発と水素燃料電池
▼宇宙開発と水素燃料電池 スタック(stack)とは積層されたという意味で、薄いフィルム状の化学変化膜(セル)が何百層も重ね合わさっている。
スタック(stack)とは積層されたという意味で、薄いフィルム状の化学変化膜(セル)が何百層も重ね合わさっている。 私が最初に記憶に留めた乾電池は、家庭にあった懐中電灯が主な活躍場所であった。
1960年代である。
鉄の薄板をメッキ処理した懐中電灯の筒の中に単一乾電池を直列に2本落とし込み、お尻の部分からバネのついた締めキャップを回して締めた。
私が最初に記憶に留めた乾電池は、家庭にあった懐中電灯が主な活躍場所であった。
1960年代である。
鉄の薄板をメッキ処理した懐中電灯の筒の中に単一乾電池を直列に2本落とし込み、お尻の部分からバネのついた締めキャップを回して締めた。
 単一、単二などの「単」は単層のからきた言葉であろう。
単一、単二などの「単」は単層のからきた言葉であろう。



 と言う図である。
と言う図である。


 名前からして高価そうな電池である。
名前からして高価そうな電池である。

 リチウム一次電池は、民生用としては日本で初めて実用化された電池である。
リチウム一次電池は、民生用としては日本で初めて実用化された電池である。

 ニッケルカドミウム電池の欠点の一つにメモリー効果がある。
ニッケルカドミウム電池の欠点の一つにメモリー効果がある。 カドニカライトは昭和40年(1965年)販売された。
カドニカライトは昭和40年(1965年)販売された。 ニッケル水素電池は、コンピュータの普及に伴って脚光を浴びた二次電池である。ノートパソコンタイプのバッテリや、自動車のハイブリッドカーで一躍その名を馳せた。
ニッケル水素電池は、コンピュータの普及に伴って脚光を浴びた二次電池である。ノートパソコンタイプのバッテリや、自動車のハイブリッドカーで一躍その名を馳せた。



 1891年、ドイツのフランクフルト・アム・マイマンで開催された国際電気技術博覧会で、ネッカー河から博覧会会場までの170km区間を三相交流発電機により、15kVで送電する実験に成功し、交流送電の実用化が見えてきた。この実験を行ったのは、ドイツA.E.G.社のドリヴォ・ドブロウォルスキー(Michael von Dolivo - Dobrowolski: 1862-1919)だった。
1891年、ドイツのフランクフルト・アム・マイマンで開催された国際電気技術博覧会で、ネッカー河から博覧会会場までの170km区間を三相交流発電機により、15kVで送電する実験に成功し、交流送電の実用化が見えてきた。この実験を行ったのは、ドイツA.E.G.社のドリヴォ・ドブロウォルスキー(Michael von Dolivo - Dobrowolski: 1862-1919)だった。 ニコラ・テスラは、1856年、ユーゴスラビア(現クロアチア共和国クライナ地方Smiljan)に生まれる。父親はセルビア教会の牧師で知識人であったという。テスラは、幼少より神童として数学の素養が高かった。
ニコラ・テスラは、1856年、ユーゴスラビア(現クロアチア共和国クライナ地方Smiljan)に生まれる。父親はセルビア教会の牧師で知識人であったという。テスラは、幼少より神童として数学の素養が高かった。 Westinghouse社は、George Westinghouse(ジョージ・ウェスチングハウス:1846 - 1914)が1886年に設立した米国の電機会社。
Westinghouse社は、George Westinghouse(ジョージ・ウェスチングハウス:1846 - 1914)が1886年に設立した米国の電機会社。



 この三者の関係は以下の式で表される。
この三者の関係は以下の式で表される。 複雑な交流理論(エジソンは、交流理論についていけなかった)に複素数を導入したのは、ドイツの電気工学者チャールズ・プロタス・スタインメッツ(Charles Proteus Steinmetz, 1865 - 1923)である。
複雑な交流理論(エジソンは、交流理論についていけなかった)に複素数を導入したのは、ドイツの電気工学者チャールズ・プロタス・スタインメッツ(Charles Proteus Steinmetz, 1865 - 1923)である。 複素数の考え方は、もともとは、二次元方程式の解が実数だけで解けないことから編み出された考え方である。
複素数の考え方は、もともとは、二次元方程式の解が実数だけで解けないことから編み出された考え方である。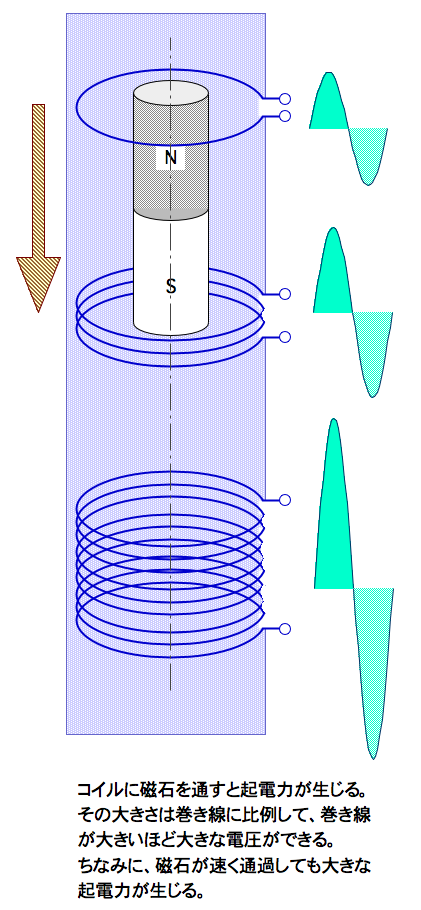

 1900年、イギリス人ハドフィールド(Sir. Robert Hadfield: 1858 - 1940)は、純鉄にケイ素(シリコン)を添加することにより固有抵抗が上昇し、鉄損が下がることを発見した。鉄の固有抵抗が低いと渦電流損失が大きくなるのである。
1900年、イギリス人ハドフィールド(Sir. Robert Hadfield: 1858 - 1940)は、純鉄にケイ素(シリコン)を添加することにより固有抵抗が上昇し、鉄損が下がることを発見した。鉄の固有抵抗が低いと渦電流損失が大きくなるのである。 アメリカの電気物理学者。オルバニー(Albany)生まれ。
アメリカの電気物理学者。オルバニー(Albany)生まれ。 で表す。オームの法則は、直流回路で成り立つ法則である。
で表す。オームの法則は、直流回路で成り立つ法則である。
 交流電源は、時々刻々電圧が変わるがその時に高い位置にある電位が低い方に流れている。
交流電源は、時々刻々電圧が変わるがその時に高い位置にある電位が低い方に流れている。 1864年に英国人物理学者マクスウェルが予言した電磁波は、電界と磁界の絡み合った電磁界の乱れ(ゆらぎ)の横波(伝わる方向と直角の方向に振動する波)となって、エーテルで満たされた空間を高速で伝わるものであり、光もこの電磁界の波動の一種であるとした。
1864年に英国人物理学者マクスウェルが予言した電磁波は、電界と磁界の絡み合った電磁界の乱れ(ゆらぎ)の横波(伝わる方向と直角の方向に振動する波)となって、エーテルで満たされた空間を高速で伝わるものであり、光もこの電磁界の波動の一種であるとした。
 クーロンは、フランス人。
クーロンは、フランス人。
 地球は大きな磁石である。なぜ地球そのものが磁石となって磁力線を出しているのであろうか。
地球は大きな磁石である。なぜ地球そのものが磁石となって磁力線を出しているのであろうか。 ドイツ人数学者・天文学者。
ドイツ人数学者・天文学者。 ドイツ人物理学者。
ドイツ人物理学者。

 マルコーニ無線会社の顧問であるJ.A.フレミング(John Ambrose Fleming)が、1904年にそのコヒーラーに代わる二極真空管を発明した。二極真空管は、電子の流れが一方向で逆方向には流れない特性のものである。
マルコーニ無線会社の顧問であるJ.A.フレミング(John Ambrose Fleming)が、1904年にそのコヒーラーに代わる二極真空管を発明した。二極真空管は、電子の流れが一方向で逆方向には流れない特性のものである。