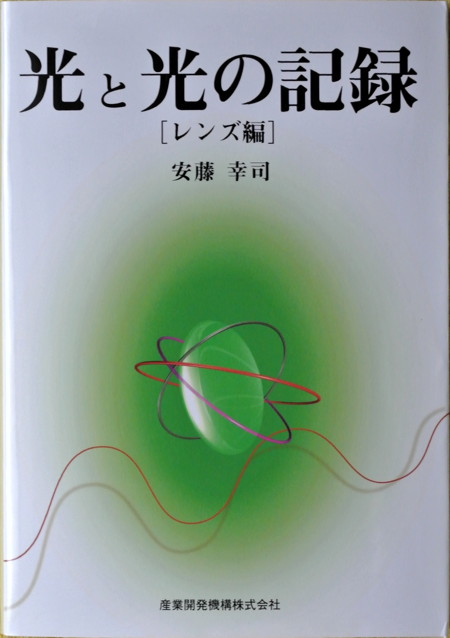 �ָ��ȸ��ε�Ͽ�Υ���ԡϡפ���Ǥ��ޤ��� ��2013.06.12��
�ָ��ȸ��ε�Ͽ�Υ���ԡϡפ���Ǥ��ޤ��� ��2013.06.12��
|
||||
- �������Ư����Lenses�ˡ���2004.08.06����2005.09.20�ˡ�2023.11.13�ɵ���
- �ڸ��ص�����濴��-�����
- ��ϸ�����������ΤǤ������ص���κǤ����Ū�����ʤȸ����ޤ���
- ���2�����ζ��־������˼������뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ������������ǤȤ��ư������ڤ�Ư����ô�äƤ��ޤ���
- �ʹ֤Ǹ����ȡִ�פ�Ʊ��Ư������äƤ����Ǥ���
- ���ص���Ƥߤ�ȡ�����濴�Ȥ��Ƥ��������ʤ�Τ����ޤäƴﳣ�������Ƥ��봶������ޤ����㤨�С��ߥ顼���ץꥺ�ࡢ�ե��륿�����ե����С������ʻҡ������ǻҤʤɤθ����ǻҡ������Ƹ����ŵ����Ѥ��ƽ�����Ԥ��Ż��ǻҤ�����ޤ���
- ���ص���ˤȤäƥ������Ǥ���
- ���Ư�����Τ뤳�Ȥˤ�ꡢ���ε�Ͽ���ɤΤ褦�˹Ԥ��뤫���Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

- ��
- �ڥ�ε�ǽ��
- ��ΰ��֤δ��ܤϡ�����뤳�ȤǤ���
- ���̥�ϼͽ�¦�˰����˸���ޤ������������¦�β��ۤΰ����������ͤ����褦�˼ͽ�¦�����ͤ���ޤ�����
- ������˽�����ʪ�Τΰ����������ͤ��줿�����դ����Ӱ����˽��ޤ�Τǡ������Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ���٤��ɤ���ϡ���������������ͤ��줿��������������ɤ�����뤳�Ȥ��Ǥ��뤿�ᡢ���������ʽ꤫�����Ф��Ƥ������ʬ�̤����̡��˽���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���줬��������ѤǤ���
- ��
 �ڥ�νи���
�ڥ�νи���
- ��ϡ�13�����˺���ޤ���
- ���������Τ���α���ѥᥬ�ͤȤ��ƥ����ꥢ��ȯ������ޤ�����
- �����������ꥢ�ξ����Իԥ٥˥��ʥ٥ͥ����ˤǤϥ��饹���ȡ�Venetian Glass�ˤ��ɤ��Ƥ��ơ�����ȯŸ�Ȥ��ƥᥬ�ͤ�ȯ������ޤ�����
- �ᥬ�ͤ�ȯŸ������ᥬ�͡���������˾����ؤ�ȯŸ����19�����ˤʤäƶ���ˤ�봶��������ȯ�������ȼ̿������ѤΥ����®��ȯŸ���ޤ���
- ��ϡ��ͤλ��Ϥ�����������Ū�Ǻ��줿�ᥬ�ͤ��顢��ŷ�Τ�˾����������ʤ�Τ���ᥬ�͡��������ʤɤ��礤�ʤ�ȯŸ�ޤ���
- �Ȥ����ˤ������δѻ��ˤϡ�˾����Ϥʤ��ƤϤʤ�ʤ��ﳣ�Ǥ�����
- �����������ˤ����ʸ��ݤ���������ޤ������ٶݤ�ȯ�����줿�Τ⸲�����Τ������Ǥ���
- ��
- �ڥ�����ȯ����
- 19�����ˤʤ�ȡ�������Ѥ�������������ȯ������ޤ���
- ������������ȥ���Ȥ߹�碌�������شﳣ����ˤ��礭�����ʤ����ޤ���
- ���줬������ȯ���Ǥ���
- ����餬ȯ��������������Ȥä��ɤ�ʪ�Τ���Ƥ����ơ������ʤ��ä����ʤ����ʪ������������饪�֥�������camera obscura�ˤȤ����礭������������Ƥ��ޤ�����������������Ǥβ�Ȥκ�Ȥ���������������ä��Ѥ��褦�ˤʤꡢ�����λ���ˤʤ�ޤ�����
- ����饪�֥��������礭�ʷ�ʪ�������̤ʥ��Ĥ��������ʰ�Ȣ�˽̾����ޤ�����
- ��
- ���Żҥ�����ȯŸ��
- 1940ǯ��ʹߡ��Żҹ��ؤ�ȯŸ�ˤ�äƥƥ�ӵ��Ѥ��礤��ȯŸ����̵�����Ѥ���ޤäƥƥ�ӥ�����������礭��������뤲�ޤ�����
- �����ȼ�äơ��������ŻҤǻ��Ƥ���Ͽ����ƥ�ӥ���Ѥȥӥǥ����Ѥ�ȯŸ�����ǥ����뵻�Ѥȥ���ԥ塼����ȯŸ�θ岡���ˤ�ꡢCCD�����γ�ȯ��Ф�IC����ˤ��ǥ�����������礤��ȯŸ���ޤ�����
- ��
- �ڻ����Ӥ����
- ���Ҥ٤��褦�ˡ���Ͽ���Τδ�¿�����������äƤ���¸�ߤ��礭������濴Ū����̤����Ƥ��ޤ�����
- ��������Τ⺣���礭�ʤ�Τ��ä��ΤǤ���
- ��
- ��
���������������Lenses��
 ��ϡ����˼����褦�ˤ�������ޤ���
��ϡ����˼����褦�ˤ�������ޤ���- �ɤ����Ƥ���ʤˤ�������ΤǤ��礦����
- �ع��ǽ���ʪ���ζ��ʽ��¿���ϡ����������ݤˡ�ξ¦���Ĥ���ξ�̤�Ʃ�����饹�������Ƥ�����Ȥ��Ƥ��������������ޤ���
- �����������¤Υ�ϡ�������¿�ͤǤ�����¿���ढ��ΤǤ���
- ��ξܤ����������ɤäƹԤ��Ȥ��ơ������Τ���Ƥ���ʼ̿��˥����ɽŪ�ʤ�Τ��ѼԤ�¦��Ω�äƳ��礷�ޤ���
- ����߷Ԥ�¦��Ω�ä������ϡ��ɡ��ԤäƤ����ޤ���
- ��
- ������ȥ�ޥ����
- ����̿���ȯ���ʹߡ��͡��ʥ���餬���졢������Ū�˱����Ƥ��������ʥ���߷פ���ƺ���Ƥ��ޤ�����
- ����Ϥʤ�Ȥʤ�����Ǥ��ޤ���
- �⤦��Ĥ����Ѥʵ���Ȥ��ơ���������դ����ޥ���Ȥ��ʤ��ޤ��ޤ��ʤΤ����Ȥ����Τ�����ޤ���
- �ʤ����Τ褦�ˤ�������Υ�ޥ���Ȥ�����ΤǤ��礦��
- ������ѥ�ϡ����⤽�⥫��黣�Ƥ�����Ȥ��ȤäƤ��ޤ�����
- �⤷���ϡ�������ͽ�����դ����Ƥ������ᡢ����ɬ�פΤʤ���ΤǤ�����
- ���줬���夬����ˤĤ�ơ�����ή�ˤʤäƤ���35mm�Ҥζ���ե���५��餬��ڤ��ޤ���
- 1950ǯ�ʹߡ��饤���������ʸ���ή�Υե���ॵ�����ˤΰ���ե���餬�Ȥ��䤹�����Ȥ����礤����ڤ�������������ȼ��θ����褦�ˤʤäơ������˹�碌���ȼ��Υޥ���Ȥ���ޤ�����
- �����ѤΥӥǥ�������Ѥ�C�ޥ���ȤΤ褦�ˡ��ۤ�Τ���äȤ������Ѥ���Ĥ��ǻȤ��Ϥ�Ť����ʤΥޥ���Ȥ����Ծ�˲������褦�ˤ��ư��̲�����Ĺ���ֻȤ��³���Ƥ����Τ⤢��ޤ���
- ��
- ��������ե�����Ѹ��
- ���μ̿��Υ�Τ���������ʤ��¤�������35mm����ե����θ�Ǥ���
- 35mm����ե����Ȥϡ�35mm�Ҥζ���ե����ʥѥȥ����ͥե����ˤ�Ȥä�����ե�å���������Single Lens Reflex Camera = SLR�ˤΤ��Ȥǡ���������̤��ƥե��������������Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���Υ����ϡ�������ĺ�����˥ȥ�����Υڥץꥺ�ब����Τ���ħ�ǡ��ڥץꥺ����̤��ƥ���������̤�������ľ�ܸ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ����ޤǤΥ����ϥ�����Ȥ��̤˥ե�����������ä��ΤǤ���
- �ڥץꥺ�����ä������Ϲ�饫������̾��Ǥ�����
- ����ե����ϥ���̤��ƥե�������ۤ�������Τ��ѻ��Ǥ�������γ�ǧ��ԥ�ȹ�碌��ڤǤ��ä����Ȥ��顢��Τ���ᤤ��ΤޤǼ�ͳ�˻��ƤǤ��������⡢�����ϰϤ����ƤǤ��������Υ�ΰۤʤ��������������ơ������⤽�줬�ưפ˸Ǥ���褦�˥�ޥ���Ȥ����줵��Ƥ��ޤ�����
- ����鰦���ȤˤȤä�̴�Τ褦�ʥ����ƥ���ä��ΤǤ���
- ���ߡ�2008ǯ�ˤǤϥե����μ��פ��㸺���ơ���������ե�����CCD ��CMOS ���λ����ǻҤ�Ȥä��ǥ����륫���˰ܹԤ��Ƥ��ޤ���
- �����˥å�����ޥ���ȡ�F�ޥ���ȡ˥��
- �屦�˼���������Τ��������ʤ˼�������ϥ˥�����¤���䤷�Ƥ���˥å������Nikkor�˥�ȸƤФ���ΤǤ���
- �˥�����ե�����˺��Ѥ��Ƥ����ޥ���Ȥ�F�ޥ���Ȥȸ��äƤ��ޤ���
- ��ޥ���Ȥ����줵��Ƥ���ȸ��äƤ⤽���Ʊ������������äǤ��äơ�����������㤨�Хޥ���Ȥ��ۤʤ�ޤ���
- ����Υ���ȼ��Υޥ���Ȥ���Ѥ��Ƥ��ޤ������ڥå����⥳�˥��ߥΥ륿�ʸ����ˡ��ˤ⤽�줾���ȼ��Υޥ���Ȥǥ���äƤ��ޤ���
- ���λ��¤ϡ���������ϥ����Τ��ᥤ��Ǥ��äơ������Ϥ��Υ��ޥ��ߤ����ʰ�̣�礤����������ޥ���Ȥ����줷�褦�Ȥ��������ʤ�ü����ʤ��ä����Ȥ��̣���Ƥ��ޤ���
- �Υ���ԥ塼������ϡ�USB���ʤˤ���IEEE1394�ˤ������٤Ƶ�������Τ���Υ��������ब�Ǥ������äơ��ޤ����ʤ����줵���Ƥ��줫����������ƶ���ޤ���
- ����Ǥ������äƤ������Ū�طʤƤߤޤ��ȡ������䤫�ޤ������֤����Υ桼�����������餺���ץ��̿��Ȥ䥢�ޥ��奢�����ޥ��á��˹����ʥ����Υ�������äƥ��ȤäƤ����Ȥ�������˵��Ť��ޤ���
- �˥����F�ޥ���Ȥϡ�1959ǯ�ˡ֥˥���F�פȸ�������ե�å�������餬��ȯ���줿���˺��Ѥ��줿��ޥ���Ȥǡ��ʸ�60ǯ��ߴ�����ݻ����Ƥ���¸�ߴ��Τ����ޥ���ȤǤ���
- ��������ե����Υ��
- 35mm����ե����ϡ�1950ǯ�˥ɥ��ĤΥĥ�������������Ҥ���ȯ�������å����ʱ��̿��ˤǼ¸����ޤ�����
 �����ξ����˸ѷ��������ڥץꥺ������֤�����������������о�ʪ������ե����ȥ�δ֤����֤���ȿ�ͥߥ顼��ķ�;夲�ơ��ڥץꥺ����̤��ƥ����ԡ�����ʪ�������������ե��������䥷��å���������ɤ������ޤ�����
�����ξ����˸ѷ��������ڥץꥺ������֤�����������������о�ʪ������ե����ȥ�δ֤����֤���ȿ�ͥߥ顼��ķ�;夲�ơ��ڥץꥺ����̤��ƥ����ԡ�����ʪ�������������ե��������䥷��å���������ɤ������ޤ�����- ����å�������ȿ�ͥߥ顼���ڥץꥺ��������ķ�;夬�ꡢ�����������ϥե�����̤�Ƴ����ե�������ץ졼��å����������ƥե������Ϫ������ޤ�����
- ����ե���餬�Ф����ϡ��ɥ��ĤΥ饤�ļҤ��饤���Ȥ�����ե����������35mm������ȯ��1913ǯ�ˤ��ư��Ƥ����Ӥ��Ƥ��ޤ�����
- �饤���ϥ��ͳ�˸���Ȥ����߷��ۤϤʤ�����ϸ���ǤǤ��Ƥ⤻������2�ܤ���3�����٤θ�������ѤǤ��ޤ���Ǥ�����
- ��ե�������������ϡ����Ƥθ�˹�碌����ե�������Ĵ�������ä��ΤǤ���
- ����ե����νи��ϡ�����ޤǤΥ����������Ѥ����ƥ����γ�ư�ϰϤ�ä��ۤɳ�ĥ�����ޤ�����
- ���Ǥε�Ͽ�̿��Ǥ���Ϥ�ȯ�����ޤ�����
- �Ȥϸ��äƤ⡢����ե���餬�Ф��Τ��������������Ǥ�������Ϥ�ȯ�������Τ�ī��ư��ʹߤˤʤ�ޤ���
- ����ե�����Ȥä��̿��ϡ���줫��Υꥢ��ʱ�������������������פ�Ǥ̳��ô���ޤ�����
- ���ݡ��ļ̿�����ƻ�̿��ˤ⡢����ե����ε�ư���Ϥ�����ʤ�ȯ������ޤ�����
- ����ե����ϡ��̿���Τ���٤��Ѥ��Ѥ�����Ȥ��������������˭�٤ˤ��ޤ�����
- ��ˤ�äơ��̿���ɽ�����Ȥ��ä��ΤǤ���
- 1970ǯ��Ⱦ�ˤϡ��ߥΥ륿���鼫ư�ե����������Ǥ������ե�����α7000�פ���ȯ���졢����ư�������볫���Ȥʤ�ޤ�����
- �ʤ�⼫ư������Ǥ���褦�ˤʤꡢ�ե���ബ���夲�⼫ư�ˤʤ�ޤ�����
- �ΰ���ե����ϡ�����ԥ塼���ο���β��äˤ�������Ϫ������ư�ˤʤꡢ�ޤ����������ɤ���Τ��Ǥ����Τǥ������֤�ʤ��ʤꡢ����å�������ȹ��ޤ˿��Ф�Ȥ������Τ�ΤȤʤ�ޤ�����
- ��
- ��������դΥ�������
- ����ե�å��������Υ�����ƥ��ȡ���Ȥ����Τϥ��1�ܤǤ��٤Ƥ�ޤ��ʤäƻ��Ƥ��뤳�Ȥ������ȶ����Ƥ���Ƥ��ޤ���
- ��˼���������ξ���3�ܤΥ�Ϥ��٤ƾ�����Υ�������ñ������ȸƤФ�Ƥ����Τǡ������ܤΥ��������Υ���Ѥ����륺�����ȸƤФ���ΤǤ���
- ���Ū�ˤϡ�ñ����������졢�����Ф�˽����������������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��������1�ܤΥ�Ǿ�����Υ���Ѥ�뤿�ᡢ����������Τ˶�Ť���������ꤷ�ʤ��Ƥ⡢������ư��������˾�����礭��������Τ�Ȥ館�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �Dz軣�ƤǤϡ������ॢ�åס���������������̤Ȥ���̥��Ū�ʻ��Ƥ��Ǥ��뤳�Ȥ��顢��������ɬ���Բķ�ʥ�Ǥ�����
- �������ϱDz軣�Ƥ��ᤫ��ȯŸ�����ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ���
- 35mm����ե����Υ���������ˤϡ�20ǯ�ۤɡ�1970ǯ���溢���餤��������ޤ���
- ��ͳ�ϡ���������ñ���������٤����̤��Ť����ȡ����뤤����������ʤ��ȡ�����߷פ����Ŀͤ��㤦�ˤϲ��ʤ������⤫�ä����Ȥ��夲���ޤ����������ʤ��顢����߷פ˥���ԥ塼�������Ѥ����褦�ˤʤäơ�ʣ����Ǧ�ѤΤ������߷פ�û���֤ǤǤ���褦�ˤʤꡢ�ޤ�������̥����¤�������ƥ����Ѥ���Ω��������˥ǥ����륫������ڤ�����äơ��������μ��פ���ޤꥺ�����ι���ǽ������֤�������ޤ��������ߤǤϡ��ǥ����륫���Τ��٤Ƥ˥�������ɸ����������Ƥ��ޤ���
- ������������������ڤ��Ƥ�ʤ�ñ������������ĤäƤ���Τϡ����������⺣�ʤ�����ǽ�Ϥ�ͥ��Ƥ��뤳�Ȥȡ����뤤�������Ǥ��뤿��¸�߲��ͤ���ʬ�ˤ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ����伫�ȡ�������¬��ʬ��˿Ȥ��֤��Ƥ��ޤ��ȡ�����������ñ������β��ä��֤�ȼ����Ƥ��ޤ�����¬ʬ��Ǥ�������ϰϤ����ˤ��Ѥ��ƥ�����Ƥ�ɬ�פ��ʤ��Τǡ����ä���Ȥ����ڤ줬�ɤ������뤤ñ����������뤳�Ȥ����ʤꤢ��ޤ���
- ����ե�����ѥ���礭����ħ�ϡ�������Ǥ����ȹ�����ͥ�졢��ιʤ��ե���������碌������˥����ñ�ˤǤ��뤳�Ȥ�����������ޤ��������η�̤Ǥ������ä��Τ���μ̿��˸�����褦�ʥ���ʤΤǤ����Ƕ�ϡ���ե�����������ʤ꤬��ư�����켫ư�ǹԤ����Τ����̤ˤʤ�ޤ�����
- ��������ե����Υ˥å�����F�ޥ����
- ��¬�ѥ����äƤ���Ȥ��������ʥ������ή�Ѥ��ޤ���
- ������ǺǤ�褯�Ȥ��Ƥ������˥����F�ޥ���ȥ��Nikkor��Ǥ���
- �ɤ����ơ����Υ��¿���Ȥ���褦�ˤʤä��ΤǤ��礦����
- ���ܤη�¬��������Τߤʤ餺�����Ƥη�¬�����������ɬ���ȸ��äƤ����ۤɥ˥å�������F�ޥ���Ȥ�Ĥ�����������ޤ���
- ����Υ�ޥ���Ȥ䥪���ѥ��ޥ���ȤǤϤ����ʤ��ΤǤ��礦����
- �¤ϡ����λ��¤����Ū�طʤˤϡ���¬����餬��ή��ή��Ǥ��ä����Ȥ��������ޤ���
- ������ʬ��ϡ��������̻�����ۤɤ��礭�ʥޡ����åȤǤϤʤ�����ˡ����Ҥ�������꤬���ʤ��ä��ΤǤ���
- �ü�ʥ����Ͽ������Ϥ���äƤ����ΤǤ���
- �������äơ���ϻ��Τΰ²������ꤷ�䤹������Ѥ����ΤǤ���
- ��¬������Ȥ���¬ʬ��Ǥϡ��˥���Υ������Ū�˿�Ʃ���Ƥ���������ή�Ѥ����ΤǤ���
- 1960ǯ�夫��1970ǯ�����ؤθ��漼�䡢����Ȥθ��浡�ؤˤϸ��浭Ͽ�ѤȤ��ƥ˥���F����餬����ޤ�����
- �˥���F�����ϡ��ܳ�Ū�ʰ���ե����Ǥ��ä���Ⱥ���Ƥ��ޤ�����
- ���ξ塢�ե��������������ư�����夲�⡼�����֤ʤɥ����ƥ��˭�٤Ǥ��ä����ᡢ������Ū�Ѥ˻Ȥ�ƻ�����ꡢ�����⤯�Ƥ⸦�浡�ؤǤ�·���뤳�Ȥ��Ǥ����ΤǤ���
- �����������·�����ʼ���ɥ��ĥ����ȤϤ����ʤ��ޤǤ�������ǡ����������ʥ��Ȥ����Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ����������ͳ�����¬����������饤���������Υ˥å�������Ȥ��褦�ˤʤꡢ��ȯ��������⤽��ˤʤ餦�褦�ˤ��ƻȤ��Ф��ޤ�����
- 1990ǯ�����®��ȯã��������Ǹ��λ����ǻҤˤ������ǥ����륫���νи��˻�äƤ⤳�η�����³�����ۤȤ�ɤη�¬������F�ޥ���ȥ�����夹�븽�ݤ�³���Ƥ��ޤ���
- ���μ̿��ϡ���¬�Ѥ�CCD�����Ǥ������Υ����ˤ��ޥ���Ȥϥ˥���Ҥ�F�ޥ���Ȥ���Ѥ��Ƥ��ޤ���

- ��¬����ѷ�CCD����� Redlake�� Megaplus EC11000��2006ǯ��
- ���� 4,008 x 2,672��12�ӥå�ǻ�١��Żҥ���å���CCD�ǻ�
- �����ǻҥ�����36mm x 24mm������®��4.6����/��
- ��ޥ���ȡ����˥å�����F�ޥ����
- ���� 4,008 x 2,672��12�ӥå�ǻ�١��Żҥ���å���CCD�ǻ�
- ������⡼�ȥ�� ����2023.11.13�ɵ���
- 2020ǯ�����ꡢ��¬�����Υ�����PC���ե����������ʤꡢ�����ߥ���⡼�ȤǹԤ����Τ��Ф���ޤ�����
- �ޥ���Ȥϥ���Υ�ޥ���ȵڤ�4/3����Ǥ���
- ���μ̿���IDT�Ҥ�XSM��®�٥����ǡ������˥�⡼�����ΤǤ��륿���ߥʥ�ü�Ҥ���°���Ƥ��ƥ�������³�������PC�ǥѥ������⡼�ȥե�����������⡼�ȹʤꡢ��⡼�ȥ����ߥ��Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���


��
����CCTV�ѡ�C�ޥ���ȡ˸�� ��2023.11.13�ɵ���
- CCTV�Ȥ����Τϡ�Closed Circuit Television�Ȥ�����̣��ά�ǡ������ѥƥ�ӤȤ�����̣�礤���������դǤ���
- �����Ѹ����Υ����ϡ�CCTV�Ȥ�����������¾�� ��ITV��Industrial TV�ˤȤ����������⤷�Ƥ��ޤ�����
- �����θ��դ��ˤϡ������ѥƥ�ӤȤ��̤Τ�ΤȤ������դ�������Ƥ��ޤ���
- �����ɤ��Ȥ��ۤɤι��ʼ����ᤵ��ʤ����ޥ���ӥ�����ѡ������٥�ʴƻ���ѡ��ؽѸ����ѤΥƥ�ӥ����Ȥ�����̣��������Ƥ��ޤ���
- ���̻����Ѥ˻Ȥ����Υޥ���Ȥϡ�"C"�ޥ���ȤȸƤФ�뵬�ʤΥ������Ū�Ǥ���
- 2000ǯ�����꤫��ǥ����륫��餬�²��˽в�ä����ȡִƻ륫���פȤ���������������Ū�ˤʤäƤ��ơ�CCTV�Ȥ�ITV�Ȥ����Ƥ����Ϥ���ʤ��ʤ�ޤ�����
- ��
- �����åޥ���ȥ��
- C�ޥ���ȥ�ʱ��̿��ˤϡ���Ȥ�Ȥ�16mm�ե����Dz��ѤΥ�����Ȥ��ƻȤ��Ƥ��ޤ�����
- 1940ǯ����äǤ���16mm�ե����Ȥ����Τϡ�����ѤαDz�ե�����35mm�ˤβ��Υ�˰��֤����Τǡ������ϤαDz衢��Ͽ�ѱDz衢�˥塼������Ѥ˻Ȥ��Ƥ����ե����Ǥ���
- 35mm�ե������ե���ॵ�������������к�Ū�ʥե����Ǥ�����
- 35mm�������ξ�Υե�����70mm�ҥ������Υե���ब����ޤ���
- ����ϡ��緿�Dz�˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- 16mm�ե���५���˻Ȥ��Ƥ�����ޥ���Ȥϡ�1��������¡�25.4mm�ˤ�1�����������32���Υԥå����ڤä��ͥ�����ä���Τǡ������C�ޥ���ȤȸƤ�Ǥ��ޤ�����
 1960ǯ�ʹߡ������ѤΥƥ�ӥ����餬��ȯ���줿�����ӥ�����ʤɤλ����ɤΥ������������16mm�ե���५���Υ�����������˶ᤫ�ä����Ȥ��餳�Υ���Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
1960ǯ�ʹߡ������ѤΥƥ�ӥ����餬��ȯ���줿�����ӥ�����ʤɤλ����ɤΥ������������16mm�ե���५���Υ�����������˶ᤫ�ä����Ȥ��餳�Υ���Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����- 35mm����ե�����ѤΥ�Ϥ�������Υ�������̤˥�ޥ���Ȥ��äƤ����Τ��Ф��������ѥƥ�ӥ�Υޥ���Ȥ�C�ޥ���Ȥ�����夤���Τ϶�̣����Ȥ����Ǥ���
- ���ޤ��ˡ�60ǯ�ʾ�����ε��ʤ����ߤޤǻȤ��Ƥ���Τ�ȤƤ⤪�������äǤ���
- �����Τ���ʬ��Ϥ���ۤɤΥޡ����åȤ�����櫓�ǤϤʤ����ü�ʱ���ʬ����ä��Τǥ�������ΤǤϤʤ���16mm�ե���५����ѤΥ��ή�Ѥ����Ȥ����Τ������ν�Τ褦�Ǥ���
- ����ʬ��ϡ�1980ǯ��������VTR��CD��DVD�ʤɤε�Ͽ���֤�ȯŸ���ɿ路�ƤϤ�����褦�˵���Ĺ����¿��¿�ͤʥ���餬���ʲ�����ޤ�����
- ����餬�����������Ƥ⡢����������ϥ�ޥ���Ȥ˼��夹�뤳�Ȥʤ�C�ޥ���ȥ����Ѥ������ᡢ���ߤ�ʤ�C�ޥ���ȤΥ���Ȥ��Ƥ���ΤǤ���
- ����C�ޥ���Ȥ⥫���ξ�������ȼ�äƼ㴳���Ѳ��������ޤ�����Ĥ�C�ޥ���Ȥθ����Ʊ���ˤ��ƥե�Хå���û������CS�ޥ���ȤȸƤФ���ΤǤ��ꡢ�⤦��Ĥϸ��⥵��������꾮�������ƥ�ȥ�å���ˡ�ǥͥ����ڤä�NF�ޥ���ȤǤ���
- ���٤Ƥ�����ư�˸������桢��˥�����ͥ�����ä�����ˤͤ�����Τϳ�Τ��äǤϤ���ޤ���
- �����ѤΥ�����ϡ������̤�35mm����ե����Υե�����̤��⤫�ʤ꾮�������ᡢ�����������������Ȥ뤳�Ȥ��Ǥ�����¤⾮��������ѥ��Ȥ˺�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �Ƕ�ϡ���������Υ�����CCTV���꤬����褦�ˤʤäƥ��²��ˤʤ�ޤ�����
- ��ư�ˤ���⡼�ȥե����������ʤ�Ĵ���������ൡǽ����Ĥ�Τ�¿����¤����Ƥ��ޤ���
- �ᥬ�ԥ����륫����ȯŸ�ϡ���ˤ��б���;���ʤ�����Ƥ��ޤ���
- �ᥬ�ԥ�����β��Ǥ������ޤ줿�����ǻҤ��������ʤ�ˤĤ�ƥ������Υ��û����Τ�ɬ�פˤʤꡢ4�ߥ��������٤β��Ǥ������Ф��뤿��˹�����٤Υ��ɬ�פˤʤäƤ��Ƥ��ޤ���
- ����ʬ��Υ�ϡ��ƻ륫����Ѥ����ʸ����Ѥʤɤη�¬ʬ��˻Ȥ��뤳�Ȥ�¿���Τ��ŻҲ����ʤߡ���ư�ե�����������ư�ʤ꤬�Ȥ߹��ޤ줿��Τ�¿���ʤäƤ��ޤ���
- ��
- ��
- ������������
- ��
- �������ϡ�8mm�ե���५���μ��ס�35mm�Dz襫���μ��פ������ʲ����������Ȥ��ޤ�����
- ��ȯ�����Τϱѹ��Cooke�Ҥǡ�Varo��ȸƤФ줿���������ƹ�Bell&Howell�ҤΥե���५���˼���դ����ޤ�����
- 1932ǯ�Τ��Ȥ��ä������Ǥ���
- 1932ǯ�Ȥ����С�������ƥ����Ѥ���Ω���Ƥ��ʤ�����Ǥ���
- �������ϡ��������Ȥ�¿�����ᡢ��ȯ����Υ������Ϥ����������Ť��ƥե쥢��¿������ä��ˤ���������ޤ���
- �������ϡ�����������Ѥ��뤿�������Υ���Ѥ��ޤ���
- ������Υ���Ѥ��ȡ���ä����ʤ��Ȥ˻����̾�ǤΥԥ�Ȥ���������꤬����ޤ���
- ������Υ���Ѥ��Ƥ��äƤ�ե����������Ѥ��ʤ�������������߷פ���äȤ����ڤ����Ǥǡ�����߷�����礭������ˤʤ�ޤ�����
- ������ˤ�ä��Ѥ�������Υ�˹�碌�ơ��������֤��䤨��������ݤĤ���Υ��ൡ�����߷פ���¤�������礭�������������ĥ���߷פ乭��¦�ʾ�����Υ��û���˥���߷פϺ����ˤ�����Ǥ���
- �Dz�ȳ��μ��פ������������ʤ��夲���Υǥ����륫������ڤDz�®��¥�����ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ���
- ���������߷פ�����ʿ��ͷ���ɬ�פ��ä����ᡢ�Żҷ�����ȯã�ǥ���߷פ�û���֤ǤǤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �Dz襫����ѤΥ������ϡ�1965ǯ���ե�Υ����˥塼�Ҥ����Ū�ʥ������굡���ˤ��10�ܤȤ�������������礭������߷�������Dz��ѥ������κDZ���Ȥʤ�ޤ�����
- �ʸ塢20�ܡ�40�ܤȤ�������������ȯ����Ƥ����ޤ���
- �ƥ�������ȳ��Ǥϥ������ϾQ�ǡ����뤯�ƥ���������礭�ʥ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �Ȥ�������ѤΥƥ�ӥ����˻Ȥ��륺�����ϥ������椬100�ܤ�Ķ�����Τ����ꡢ����Ͼ�����Υ��f8.9mm����f900mm�������������ݡ�����Ѥ˰��Ϥ�ȯ�����Ƥ��ޤ���
- ����������Ͻ��̤�23kg�⤢�ꡢ��˥���餬�Ĥ��Ƥ���Ȥ�������������ޤ���
- �Ƕ�����������˻Ȥ��Ƥ��륺��������ǽ���ɤ��ϡ��ϥ��ӥ����ƥ�Ӥǥ��ݡ�����Ѥ�줿���ʤ�褯����Ǥ���Ȼפ��ޤ���
- �λ��ư��֤�������δ��ɽ���ꥢ��ˤȤ館�뤳�Ȥ��Ǥ������ζ����Ǥο������ߤ�ۤȤ�ɸ����ʤ��ۤɿ�����������Ƥ��ޤ���
- ���Υ������ϥե�� �����˥塼�Ҥ���ƻ�ѥ�����ѥ������Ǥ���
-

- ��

- ��
- ���������ɥ�����ENG = Electric News Gathering���ѥ�������
- �����ѥ����ϸ���Ǥμ�ब������Ǥ��ꡢ�Ԥä��ʤ��μ�ब¿�����Ȥ��饺������������Ǥ���
- �ޤ�������������Τ�Τ���Ѥ���ط��塢3CCD��R,G,B��3�Ĥ�CCD�λ����ǻҤ��Ȥ��դ�����Τǥե��륿�ˤ��ñ��CCD����ٹ����˥���餬��ή�Ǥ���
- ���Υ����Ǥϡ�C�ޥ���ȥ�ϻȤ��ޤ���
- C�ޥ���ȥ�ϡ���Υޥ���Ȥ��黣���̤ޤ�17.526mm�����ʤ���3CCD�����Ǥ�������ʬ�뤿��Υ����������å��ߥ顼��3�Ĥλ����ǻҤ��������äƤ��뤿�ᡢC�ޥ���ȤΥե�Хå��ե���������=17.526mm�ˤǤϻ���ʬ����طϤ��Ȥ߹���ʤ��ΤǤ���
- ���äơ������դ��̡ʥե�ˤ��黣���ǻҤΰ��֤ޤǤΥե�Хå��ե���������Ĺ���������ơ����δ֤���������������å��ߥ顼���طϤμ�������θ���줿�������������ѡ�ENG =Electric News Gathering�˥�Ȥʤ�ޤ���
- �����ѥ����˻Ȥ��Ƥ��뻣���ǻҤϡ�8.8mm x 6.6mm��������2/3�����CCD���Ȥ��Ƥ��ơ�¾��CCD���������礭�������ǻҤǤ��ꡢ���Ѥ���˾��ޤǤ��ޤʤ��Ȥ����Ȥ������礭��ˤʤäƤ��ޤ���
- ��ޥ���ȤϥХ�ͥåȥޥ���ȼ��ˤʤäƤ��ƴ�ñ�˼�곰����褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ΥХ�ͥåȤϡ����ˡ����Х�ͥåȥޥ���ȡ�B4�ޥ���ȡˤȥӥ��������Х�ͥåȥޥ���Ȥ�2���ब����ޤ���
- �����ѤΥ����ϥ��ˡ���Ǯ���Ƕȳ��˼��������줿�Τǡ���餬�ȼ��˳�ȯ�����Х�ͥåȥޥ���ȤΥ����ή�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- ��
- ������Ƚ������ѥ��
- ��
- ��Ƚ�����ϡ�35mm�ե�����Ȥä��饤�����������������礭���������Υե�����Ȥ�����������ޤ���
- ���Ū�˸���ȡ������κǽ�Υ����פ��ܥå��������Ȥ��֥����˥����ȸƤФ줿��Ƚ�����Ǥ���
- ���μ�Υ����ϡ�6x7��6cmx7cm�Υ�����������ˡ�6x645��6x6��6x9�ȸƤФ��֥����ˡ��ե�����Ȥä������䡢4x5��4�����x5������Υ�����������ˡ�8x10�Υ����ȥե�����Ȥä���Τ�����Ū�Ǥ���
 ���̿�����Ƚ������ѤΥ�Ǥ���
���̿�����Ƚ������ѤΥ�Ǥ���- 4x5�����ϡ��ع������ؼ���´�ȼ��ǽ���̿���Ȥ���Į�Υ���鲰���Ȥ���Ȣ�η��������Ǥ���
- ����鲰�����ۤ���äƥԥ�ȹ�碌�������Ĥ�����ǥե�������ޤ���
- �ե���ब�礭���Τǡ����Υ����ǻȤ����ϥ�������������礭���Τ���ħ�Ǥ���
- �ץ����Ȥ����������ɤ��ƥ��줬�ɤ��Τ������Ǥ���
- �ޤ������Υ�ˤϥե��������Τ���Υ����Ф�����������ޤ���
- �ԥ��Ĵ���ϡ������ˤĤ��Ƥ����ʢ�����ǥ��Ф��ƥե����������֤���ޤ���
- ���Υ����ˤϥ����껣�Ƥȸ��äƥե�����̤ȥ�����Ф����ƻ��Ƥ��뵡ǽ������äƤ��ޤ���
- �⤤�ӥ�Ƥ���Ȥ����̾�Υ����Ǥ��ȱ�ᴶ���ǤƤ��ޤ��ӥ뤬�ݤ�Ƽ̤äƤ��ޤ��ޤ���
- �����껣�ƤǤϤ��Τ褦���Զ����ä����Ȥ��Ǥ���������ɽ���ˤ�뻣�Ƥ���ǽ�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����껣�Ƥξ��ˤϥ�������Ф��Ƹ����Фᤫ�����äƥե�����̤˼Ф�������뤳�Ȥ�����ޤ���
- ���Τ褦�ʻ��ƤǤ������֥���������������äƤ����ʤ��ȥ�Υ����ˤ�äƼ��������̤�ʤ��ä�����̤������ޤ���
- ��Ƚ������ϥե���ॵ�������2�ܤ��餤�礭�ʥ���������������äƤ��ޤ���
- �ޤ����������θ��������䤦��̣�ǥ��ʤ�ȼ������ޤǶѰ�˸����Ϥ��Τǥ����껣�ƤǤϥ��ʤäƻ��Ƥ���ޤ���
- ���Ū�˸���ȡ�������Ϥ��Υ����פ����ȯ���ޤ�������������बȯ�����줿�����Ǥ�����1800ǯ���Ⱦ�����ܤ��ȹ��ͻ�������������������ˤ���Ǥ���
- ���Υ���餫�顢�֥����ˡ������פ�Ĺ���ե����ˤʤꡢ�Dz�ե������åȤ˵ͤ��ؤ���35mm�ե����ˤʤꡢ1���ե�å��������פ����äƹԤ��ޤ�����
- ��Ƚ������ˤϥ����å�����¢����Ƥ��ơ�Ϫ���ϥ����å��ǹԤ��褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ��
- ��
- �������������
- ��
- ���˾����ʤ�Τ뤿�����ʪ��Ǥ���
- �������θ�������ᥬ�ͤǤ���
- ����Ψ�ζ�������ܤ����ˤ������Ƹ�������Τ˶�Ť���ȡ������ʤ�Τ�ڤ˸��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����Ť����ٹ礤�ϥ�ξ�����Υ�˰�¸����������Υ��û���ۤɶ�ʤꡢ�����礭�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ǽ�θ������ϡ�������Υ��û�����1�ĤǻȤ��Ƥ��ޤ�����
- �����ʥ��饹�̤Τ褦�ʤ�ΤǤ���
- ��ʪ����ܴ���2�Ĥ��Ȥ߹�碌�ˤʤä��Τϡ���μ������ޤ���줿����Ǥ���褦�ˤʤäƤ���Ǥ���
- �������ϡ�1590ǯ���������δ�����ͥ���Zacharias Janssen 1588 - 1628�ˤˤ��ȯ�����ǽ�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���θ塢1668ǯ������������ʪ�ؼԥ졼������եå���Antony van Leeuwenhoek ��1632-1723�ˤ������饹�̤��ᤤ�ƺ�ä���ᥬ�����٤δ�ñ�ʤ�Τ�����ơ��ַ�塢���ҡ��ҥɥ顢��ॷ�ʤ�������ʪ��ѻ�����������ǽ̤����ȿ��ؤ��ϻϼԤȤʤ�ޤ�����
- �Ȥ߹�碌��ˤ��ʣ�縲�������Ѥ���1665ǯ�˺�˦��ȯ���Ԥ����Τϡ������ꥹ��ʪ���ء�ŷʸ�ؼԤ�R���եå���Robert Hooke ��1635-1703�ˤǤ������ब������������ϼ������Ҥɤ����졼������եå��θ���������ǽ���ڤӤޤ���Ǥ�����
- ��������ˤϡ��̾�Υ��������褦�ʹʤ��ե�������Ĵ������������ޤ�����Ĵ��ϸ������˼���դ���줿�����θ���Ĵ��ǹԤ��ޤ���
- �ޤ����ԥ�ȹ�碌���������Τ�ư�������о�ʪ�Ȥε�Υ��Ĵ�᤹�������Ǥ���
- ��������ˤϥ�����������ޤ���
- ��ǽ���ɤ���ʪ������ʤ�����Ǥ���
- ���äơ���������ϡ���ܥ�С��Ȥ�����ž������åȤ�3��4�ܤ���ʪ������夷��ɬ�פ˱����ƥ�ܥ�С����ž���ƥ�������ȤߤˤʤäƤ��ޤ���
- ���绣�Ƥ�����������礹�뤿��˰Ť��ʤ꤬���ǡ��Ǥ���������뤯�Ʋ����٤��ɤ���������ޤ���
- ������������ޥ����
- �������Υޥ���Ȥ⥫�����Ʊ�ͥ���ˤ�äƥͥ����ߥ��������ۤʤ�ޤ���
- ���ε��ʤϡ��Ť���1866ǯ���ѹ��RMS���ʡ�Royal Microscopical Society��������ޤ���
- ���ε��ʤȤ����Τϡ����Τ褦�ʻ��ͤˤʤäƤ��ޤ���
- ��
- ��������RMS��Royal Microscopical Society�˵���
- �����������¡���20.32mm��0.8�������
- ���������ͥ��ԥå�����0.706mm��36��/������ˡ����γ���55���Whitworth = �����åȥ��������ͥ���
- ��������Ʊ�ǵ�Υ����45mm
- ��
 ���ε��ʤϸŤ���ΤǤ���140ǯ�����ε��ʤǤ���
���ε��ʤϸŤ���ΤǤ���140ǯ�����ε��ʤǤ���
- RMS���ʤϥ�����ͥ��Ǥ��ꡢ������ͥ����������åȥ���Ȥ������ߤΥ�������ʰ����ε��ʤ���Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ��
- �ѹ�ε������Ȥ���äȤ�������ä�������������դǤ��ä������åȥ���������Sir Joseph Whitworth��1803-1887�ˤ����ꤷ���ͥ����ʤ��������ɸ��Ȥʤꡢ���������͢�����줿������Ϥ��٤Ƥ��Υ����åȥ��������ͥ����Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �����åȥ������������ʲ������ͥ��ϡ��ͥ����γ��٤�55°�ǥͥ��η�������̡ʻ���ë���ݷ����ˤȤ������̼��ι⤵��ͥ����ι⤵��1/6�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �ޤ����ͥ��θƤӷ¤ϡ�1�������1/2�������1/4������Ȥ����褦��Ⱦʬ���Ĥ˳�꿶�äƤ��ޤ�����
- ���������ƹ�Ǥϡ����پ����������������꤫�餳�ε��ʤ��������餺���ƹ�ι�������ե��顼����William Sellers��1824-1905�ˤ��ȼ��Υ�������ʤ���ޤ���
- ���줬���ߥ���ꥫ��ɮƬ�Ȥ��ƺ��Ѥ���Ƥ����˥ե������ʤΥ�����ͥ��Ȥʤ�ޤ�����
- ��˥ե������ʤΥͥ��ϡ��ͥ����γ��٤�60°���ͥ������̼�꤬ʿ���ǡ��̼��ι⤵�ȥͥ����ι⤵���椬1/8�˲�����ޤ�����
- ���٤�60°�ˤ����Τ϶��٤����������ä�����Ǥ���
- �̼���ʿ��ˤ��ƥͥ������㤯�����Τϡ�����䤹�����������ä�����Ǥ���
- ���Υ�˥ե����ͥ��ϥ�ȥ�å��ͥ��ˤ�ƶ���Ϳ�����ͥ��γ���60°���̼���ͥ����ι⤵�ϡ���˥ե����ͥ���Ʊ���ˤʤäƤ��ޤ���
- ���������Ƥӷ¤�M3�ʸ���3mm�ˡ�M4�ʸ���4mm�ˡ��ͥ��ԥå�0.5mm��0.7mm�Ȥ������˥�ȥ�å��ˤʤäƤ��ޤ���
- �Τ��˥����åȥ��������ͥ���ȡ��ͥ�����Ω�äƤ���ʳ���55°�ˤΤ���̩�ʤͤ����ߤ��Ԥ��ޤ���
- ������ͳ���餫�ɤ����Ϥ狼��ޤ����������ǤϺ��⤳�ε��ʤ������Ƥ��ޤ���
- ��
- �������ܤθ������������ʪ��ޥ����
- �ä�����ޤ����������������äƤ������ܤΥ˥���⥪���ѥ��⤳��RMS���ʤˤϽ��äƤ��餺���ȼ��θ��¤ȥԥå�����ʪ����äƤ��ޤ���
- �ޤ���RMS���ʤǤϸ��¤������������뤤�����Ȥ��ˤɤ����Ƥ����������Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���ʤߤˡ��˥���ϸ���27mm���ͥ��ԥå�0.75mm��Ʊ�ǵ�Υ45mm�Ǥ��ꡢ�����ѥ��ϡ�����26mm���ͥ��ԥå�0.706mm��36��/������ˡ�Ʊ�ǵ�Υ45mm�ȤʤäƤ��ޤ���
- �˥���ȥ�å��ͥ��ǥ����ѥ���������ͥ���Ʊ�ǵ�Υ��Ʊ��45mm�ȤʤäƤ��ޤ���
- �������ܤθ������������ʪ��ޥ����
- �������ʤ�ñ�ʤ���äƤ����ƹ��Edmund�ʥ��ɥ��ɡˡ�NewPort�ʥ˥塼�ݡ��ȡˡ����ܤΥ��������θ�������ϡ�RMS���ʤȤʤäƤ��ޤ���
- ��������ȥ˥���䥪���ѥ����ʤΥޥ���Ȥ��Ȥ��ʤ��Τǡ��Ť�140ǯ�����ε��ʤǸ���������äƤ����Τȹͤ����ޤ���
- ���ʤȤ����ΤϤ�ä����ʤ�ΤǤϤ��뤱��ɡ����˽��פʤ�Τ��ȸ������Ȥ��狼��ޤ���
- ��
- ������������---���������Τ��ܺ٤ʻ��ˤĤ��Ƥϡ�������������פȲ�������
- ��
- ��
- ����˾������
- ������������---���������Τ��ܺ٤ʻ��ˤĤ��Ƥϡ�������������פȲ�������
- ˾����˻Ȥ����ϡ��Τ�Τ뤿��Υ�Ǥ���
- ˾�����ȯ��ư����ŷʸ�ؤǤ���
- ������������������α�����ȯ��������ȡ�ŷ�Τδ�¬��˾�����̵���ƤϤʤ�ʤ���ΤǤ�����
- ˾����ϡ���������ȯ�����٤�뤳��20ǯ��1609ǯ�˥����ꥢ�Υ���쥤�ˤ�äƺ��졢�ѹ�Υ˥塼�ȥ�Ͽ��������Ӥ���ȿ�Ͷ������פ�˾�����1668ǯ�˺��ޤ�����
- ˾�����ȯ����������쥪�ϡ��ᥬ�ͺ�꤬ȯã���Ƥ����������ͤκ�ä��ü�ʴ���˥ҥ�Ȥ�����˾������ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��λظ�����ؽ�Ū�ʰ�̣��ŷʸ�ؤǤ��ꡢ���ؤϼ��ʤǤ�����
- ���äơ�����쥪�ϸ��ؤ�õ��Ƥ��ޤ���
- ��
- ����˾����Υ���Ȥ߹�碌
- �������ϡ���ᥬ�ͤΤ褦�˰�Ĥ�ñ�̥�dz��礬�Ǥ����Τȡ���ʪ����ܴ���1�Ȥ��Ȥ߹�碌�ǹ���������Τ����ȯ���ޤ�������˾����ǤϤ��٤ƤΥ����פ���ʪ����ܴ����Ȥ߹�碌�������ޤ�����
- ˾����δ���Ū�ʹͤ����ϡ�������Υ��Ĺ�������ʪ��ˤȾ�����Υ��û������ܴ��ˤ�1�Ȥǹ������졢Ĺ��������Υ����ʪ���̵�±���֤����ʪ������������֤˷�Ф�����������������ܴ��ˤdz��礷�Ƹ��롢�Ȥ�����ΤǤ���
- ˾����ξ�硢�Τ�Τ��˴Ƹ������礭�����ٹ礤��˾����Ψ�ȸƤ�Ǥ��ơ����γ���ʪ�Τθ�������١����ʤ����Ѥγ���ɽ���Ƥ��ޤ���
- �����ʻ�Ѥ����äƤ���ʪ�Τ��礭�ʻ�ѤǸ��뤳�Ȥ��Ǥ���бΤ�Τ��礭�������뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���Τ����˾����Ǥ���ʪ��˾�����Υ��Ĺ����Τ�Ȥ����ܴ��ʥ����ԡ����ˤ˾�����Υ��û����Τ�ȤäƤ��ޤ���
- ξ�Ԥξ�����Υ����ǻ�Ѥ��椬�������Ψ�������ޤ���
- ˾����Ǥ���ʪ���Ĺ��������Υ�Υ��ȤäƤ��뤿�ᡢ��Ĺ��=���ˤˤ��������֤��ۤʤ뿧���������꤬�����ˤʤ�ޤ���
- �����������������γ�ȯ��˾�������ˤȤ�ʤ�ޤ�����
- �ޤ���������Υ��Ĺ����ϸ�����ʥ����/������Υ����Σ��ͤϸ�����εտ��ˤ��礭���ʤ꤬���ǡ����뤤��ˤ��뤿��ˤϸ��¤��礭�����Ƥ�������θ���ʤ���Фʤ�ޤ���
- ���Τ��ᡢ�Ѱ�ʸ��إ��饹����¤�ȡ����٤��ɤ�����̤θ��ᡢ�����ƿ��ä��Τ���Υ������Ȥ��Ȥ߹�碌��˾�����˵�����������ǤȤʤ�ޤ�����
- ��
- ����˾����μ�ή��-��ȿ�Ͷ�
- ���إ��饹���̤��������Ф������˾����ϡ����¤�̵�����礭�����뤳�Ȥ�����ǡ�1800ǯ��ν����˸���102cm�ζ���˾��������줿�Τ�Ǹ�ˡ�1900ǯ������äƤ����ȿ�Ͷ���Ȥä�˾������ڤ��ؤ�äƹԤ��ޤ�����
- ���ߤι���ǽŷ��˾����ϡ����¤�8��ȥ��8,000mm�ˤۤɤ�ȿ�Ͷ���ȤäƤ��ޤ���
- ŷʸ��ʬ��Ǥϡ�ȿ�Ͷ������פΥ����ή�Ǥ���Τˡ�������˾���Ǥ�ȿ�Ͷ������פΥ�Ϲ��ޤ�ޤ���
- ȿ�Ͷ������פ������²��Ƿڤ�������ѥ��ȤǤ���ˤ⤫����餺���Ť���Ĺ��˾�������ޤ�ޤ���
- ������ͳ�ϡ�ȿ�Ͷ������פΤ�Τϥ�ʤ꤬��ͳ�ˤ����ʤ����Ȥȡ���Υܥ�̣���������ȡ�����������ȤǤ���
- 1���ե����ǥ�ιʤ��ͳ���Ѥ����ʤ��ΤϺ���ޤ���
- ��Υܥ���ȿ�Ͷ������פǤϥԥ�Ȥι�ä����ʳ��Τ�Τ��ɡ��ʥåľ��˥ܥ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��������Υ�ϡ�ȿ�Ͷ����濴����̤��Ƥ����������̤äƥ�����Ƴ�����Τǥե��������ݥ���Ȱʳ��Ǥϥ���Υܥ����ȤʤäƤ��ޤ��ΤǤ���
- ŷ��˾����Ǥϡ�����Τ������Ǥ��괰���ʤ�̵�±�θ�������˽����Τ�����Ū�Ǥ��ꡢ�ܥ�̣�ϰ��̤μ̿��Τ褦�ˤ���ۤɽ��פǤϤʤ����¤��礭����Τ������뤿���ȿ�ͼ��Υ����������طϤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ---��˾����Τ��ܺ٤ʻ��ˤĤ��Ƥϡ���˾�������פȲ�������
- ����
- ��������¾
- ����¾������ü��ʬ��ǹ��٤�ȯŸ��뤲�ʲ����Ƥ��ޤ�������ȡ��Ҷ��̿��ѥ���̿������ѥ���ե��ȥ����ե����ѥ���Ȥ��Τƥե���५����ѥ�����ԡ���������ʡ��ѥ�ʤɤǤ���
- ��
- �����Ҷ��̿��ѥ��

- �Ҷ��̿��ѥ�ϡ�9.5������ҡ�240mm�ˤΥ�����ե�����Ȥ�������1,000��3,000m�����Ϸ�����̩�˻��Ƥ��뤿��ˡ����Ѥǥ�������������礭���Ķʼ����ζˤ�ƾ��ʤ�������ϤΥ��ɬ�פǤ���
- �ޤ�����®200km�����Ԥ���Ҷ�������ܤ��줿�����ˤϡ�1/500�ðʲ���û����Ϫ����ȼ����®�����å����Բķ�Ǥ���
- �ɥ��ĤΥĥ��������������Υ�����ɡ�Wild��Leica�ˡ������ꥹ�Υ����ꥢ�ॽ�ե�Υݥ��ӥꥨ���ƹ�Υܥ�����ࡢ�ե������㥤��ɼҤʤɤ�ͥ���ʹҶ������ڤӥ����¤���Ƥ��ޤ�����
- ��
- �����̿����ǥ����
- �̿����ǥ�ϡ������Ѥ��Dz�������Ū���߷פ��줿�Ĥߤ��ʤ������Ϥι⤤��Ǥ���
- ȾƳ�Τβ�ϩ�����������ѥ��ȯŸ���ȸ����ʤ��⤢��ޤ���
- ȾƳ�β�ϩ��¤�ʥ����ե����ˤǤϥ��֥ߥ��������������ɬ�פȤ��뤿�ᡢ���³��β����Ϥ���ä�����Ȥ�졢��������������Ǿ��ˤʤ�褦�˻糰�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����ʬ��Ǥϡ���θ³���ĩ���³���Ƥ���ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ���
- ����ּ̥��Ǥ��פ���ɽ�����Ȥ��Τƥե���५��顢�������ä˻Ȥ��Ƥ��륫����ϡ������ǽ/�����Ȥ����¤˰����Ф�����ΤǤ���
- �����⾮������ѥ��Ȥǰ²��˶��뤷�ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ���ץ饹���å���μ��פ����ߡ��ͽ������ˤ������̥����¤���Ω�����ޤ�����
- ����̥�ϡ�ʣ����ε��̥���ĤˤޤȤ�뤳�Ȥ��Ǥ�����Ū�ʤ�ΤǤ���
- �����Υ���̤δ��������ȳ��˵��ѳ���⤿�餷����Τȸ�����Ǥ��礦��
- �����������Ѥ��椯�椯���緿��˺��Ѥ��������ᤤ�ȹͤ����ޤ���
- �����Ҷ��̿��ѥ��
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
�����������ѡ�Light Collection��
- ��ΰ��֤�Ư���ϡ���ˤ�Ҥ٤��Ȥ��ꡢ�������ѤǤ���
- Ʃ��ʪ���˸�������Ȥ����������ζ���Ψ�ˤ�äƶʤ����ޤ���
- ���ޤ�ˡ§�ϡ��������ͥ��ͥ�ȥե�ͥǥ�������ܤ���Ĵ�٤ޤ�����
- ����ˡ§�˽��äơ����̤���ĥ�˸�����������̤˱褦�褦�˰����˽��ޤ�褦�ˤʤ�ޤ���
- ��ϲ��ޤ˼����褦�ˤ����Ĥ�Υץꥺ�ब���ޤä���Τȸ��ʤ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ʿ�Ԥʸ��ϳƥץꥺ������ͤ��ƶ��ޤ��������˽��ޤ�ޤ���
- �ʸ�̩�ˤϰ����˽��ޤ餺��˵�˽��ޤ롣���줬�����ȸƤФ���ΤȤʤäƤ��ޤ�����
- ��������߷�
- ����߷פϡ����إ��饹�ȶ����ʤ�Τˤ�äƤϱ��Τ���俿���ˤδ֤�������ɤΤ褦�˿ʤ�Ǥ����������פ��뤳�Ȥ����ܤȤʤäƤ��ޤ���
- ���������ʸ����ʹ⤵�����١���Ĺ�ˤ����ͤ����ư�ĤŤ�ðǰ�˷��������ͤ��������ɤη�ϩ���̤ä������ɤ��˷�Ф�뤫������ޤ���
- ���η��ϡ����ͥ��ˡ§��Ȥä��������פ��縶§�ǡ����������ʼ���������Ū�˹�θ���ʤ����ζ�Ψ�䡢��κ���������ݡ��ͥ�Ȥ���Ƥ����ޤ���
- �߷פϡ�������ͤ��������ˤ�äƷ�������ݤˤ��ޤ�Ǥ���ܥ��̤˼��ޤ�ޤǼ���֤��ʤ��夨�����������������Ԥ������Ǥ���
- ���αʤ�褦�ʻ��Ѵؿ��η�������߷ײ��λŻ����ä��ΤǤ���
- ��������ñ��ʻŻ���ԥ塼�����Ԥ��褦�ˤʤäƻ���ϰ��Ѥ��ޤ�����
- �ߥ����Ȥ��������Τ�ʤ�����ԥ塼���ϸ����߷פˤϤ��äƤĤ��Ǥ�����
- ����ԥ塼�����ǽ�˻Ȥ��Ф����Ȥ����ܲȥ���ꥫ�Ϸ����Ѥ�ˤ�ơʥߥ�����ˤ���ƻ���˥���ԥ塼����Ȥ��ޤ����������ܤξ�硢�ǽ�Υ���ԥ塼�����ä��Τ��ٻμ̿��ե����ǡ�������Ū�ϸ����߷פ��ä��ΤǤ���
- ����ۤɸ����߷פ�ñ������硢������ߥ���������ʤ�����Ϣ³���ä��ΤǤ���
- �������פˤĤ��Ƥϡ����ܤ����ƾҲ𤷤����Ȼפ��ޤ���
- �����ἴ������Paraxial Rays������������ Gauss Optics��
- ����̤������Ϥʤ������˽��ޤ뤫�ȸ����С�������̤ǤǤ��Ƥ��뤿��Ǥ���ʿ�Ը�«�ϵ��̤��濴���˽��ޤ���������äƤ��뤿��Ǥ���
- ʿ�Ը��������˽��ޤ����٤ϤɤΤ��餤���Ȥ����ȡ��������٤��������θ��κ��˰�¸���ޤ���
- ���̥�ϡ�����Ū�˸��Ƥ⤹�٤Ƥθ�������˽������ǽ����äƤ���櫓�ǤϤ���ޤ���
- �����褽��ʿ�Ը�«���濴���˸����äƽ��ޤ��ΤΡ������ɤ������˽��ޤ�Ȥ����櫓�ǤϤʤ��ΤǤ���
- ���̥��1�Ĥ�ʿ�Ը�������˽���뤳�Ȥϸ�����̵���ʤΤǤ���
- ���θ�����̵������������̼����ȸ��äƤ��ޤ���
- ���̶���Ʊ�͵��̤Ǻ��줿���̥�ϰʲ��˼����褦�ʽ�����������äƤ��ޤ���
- ���������ϡ����̶��Ǥϡ����͡�ȿ�ͤ�ˡ§����Ƴ����ޤ��������̥�Ǥϥ��ͥ롦�ǥ���Ȥ�ˡ§����Ƴ�����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- ���������̶�����������˽����Ȥϸ¤�ʤ�
- ��οޤ˼������褦�ˡ����ʤε��̶��ǤⲼ�ʤ˼�����ξ�̵��̥�Ǥ�ʿ�Ը��ϰ����˽��ޤäƤ��ޤ���
- ���̶��Ǥϡ������ҡ����åפ����̤Ǹ�����褦�ʲ����ȸƤФ�륫��������������Cardioid Line�ˤ˱�ä�����ȿ�͡�Caustic Surface�ˤ�����졢ʿ�Ը�«�������˽��ޤ뤳�ȤϤ���ޤ���
- ȿ�Ͷ��Ǥϵ��̶��Ǥʤ�����ʪ�̶�������ʿ�Ը�������˽����ǽ�Ϥ�ͥ��Ƥ��ޤ���
- �������������ϡ����ޤ����Ѥ����̥�Ǥ�Ʊ�����Ȥ������������˽��ޤ뤳�ȤϤ���ޤ���
- ��
- ���������˽���뤳�Ȥ�������θ³���
- �����ˤĤ��Ƥ���˽Ҥ٤�ȡ���ε��̼������θ���ʤ��Ȥ��Ƥ⡢�����ꥹ�ͤ�ʪ���ؼ��������ȯ��������������İʲ��ˤ��뤳�Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ��������ȸ��ε�Ͽ�إ��ʬ��ǽ�ٻ����ˡ�
- ������ͳ�ϡ������Ȥ������ˤ���ΤǤ���
- ��ˤϡ����¤ˤ��͡��ʼ����ޤ�Ǥ��ޤ���
- ��˽Ҥ٤��褦�ˡ����̤ǤǤ������̥�ǤϤ��٤Ƥθ��ϰ����˽��ޤ�ʤ����̼�������äƤ��ޤ���
- �����夲���������٤������Ƥ���ϰ����˽��ޤ�ޤ���
- �ޤ������ˤ���������Ĺ�����ꡢ��Ĺ�ˤ�äƶ���Ψ���Ѥ��Τ�ñ�����Ǥʤ��������ɤ������˽��ޤ�ޤ���
- �Фᤫ�����ͤ���ʿ�Ը�«�������������ˤϽ��ޤ�ޤ���
- ����߷Ԥ����Ϥ�������������Ǥ�������ޤ��ơ������������ͤ��줿����Ƥ������ɤ������˽���빩�פƤ��ޤ���
- ��
- ��������
- ����Ū�ʻ��Ȥ��ơ����٤�����ޤ�����1��ε��̥�����Ǥ�ʪ�Τ���θ�����ξ������������ޤǽ���뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- �ʤ��ʤ顢��ϥ�����ۤμ����Τʤ��Ȥ��������Ω�äƸ�����ư�δ���������ν����θ³����⤤�Ƥ��뤫��Ǥ���
- �ºݤΥ�ϡ����������ʸ�����ȼ�äƤ���ΤǼ����� = aberrations�ˤ�ȼ���ޤ���
- ������Ǥ���������������פ�����߷פ�̯̣�ȸ�����Ǥ��礦��
- ���������̶�����������˽����Ȥϸ¤�ʤ�
- �ºݤνꡢ���̥��Ȥä�ʿ�Ը�«�������˽��ޤ���ϡ�sinθ = θ�ȶ�������ἴ�����ΤߤʤΤǤ���
- �ʤ��ζἴ�����ˤ����ؤ������ء��������ΰ�ȸ����ޤ�����
- ����ʾ�����ͳ��١�θ�ˤ��Ф��Ƥ�̵�����Фơ����̼����������Ȥʤ�ޤ���
- ���äơ����μ�����Ȥ뤿��˥���ؤ����ꡢ���������ʥ���߷פ����ΤǤ���
- ��
- �����ص�Ū�ʸ�������
- �ʤ���sin�� = �Ȥȶ�������ἴ�����ΰ�Ǹ��ؤ�����Ω�äƤ��뤫�Ȥ����ȡ�¿���θ��������δط����Ǽ�«���뤿�ὸ����ͤ���ޥ���Ū�ʹͻ��塢���ؤǷ����ڤʤ���Ǥ���
- ���ζ�����ǡ����ΤǤ�����֤Ȥ��������ɤΤ褦�˿ʤ�Ǥ����Τ��Ȥ������Τ��������Ȥ��ΤǤ���
- ̵�±�θ�«�������˽��ޤ�Ȥ�����ξ������֤���ȯ������«��ʿ�Ԥ˿ʤ�Ȥ��������濴���̤���Ϥ��Τޤ���ľ���˿ʤ�Ȥ������������ѤǤ���褦�ˤʤ�ΤǤ���
- �ἴ�ΰ�Ǥ�¿���θ�������ξ��˼�«����Τǡ��ἴ�ʳ��θ��⤳���˽��ޤ�褦���������ä����ޤ���
- ���줬����������������Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ��
- �����ἴ�ˤ���������
- �ʲ��οޤ��ἴ�����ΰ�ˤ������η��������ޤǤ���
- ����ͭ̾�ʸ����Ǥ����ɥ��Ĥ�ŷ�Ϳ��ؼԥ�������ȯ�����ޤ�����
- �����ص�Ū�ʸ�������
- ��
- ��
- ������������
��1/a + 1/b = 1/f ��������Lens - 1�� a����ʪ�����ΰ��֤������濴�ޤǤε�Υ b��������濴����������ޤǤε�Υ f�����������Υ ��M = b/a = l / L ��������Lens - 2�� M����������Ψ
l���������礭��
L����ʪ�Τ��礭��
- ��
-
��
- ��
- ���μ��ϡ�������ʽ�Ǻǽ�˽ФƤ������Ū�ʼ��Ǥ���
- ���μ�����ϡ�
- ��
- ��������1�˥��ʿ�Ԥ����ä����ϡ���ξ�����Υ�˸����äƶ��ޤ��롣
- ��������2�˥����������Υ���̲ᤷ�Ƥ������ϡ������ʿ�Ԥ˿ʤࡣ
- ��������3�˥���濴��������Ϥ��Τޤ���ľ���˿ʤࡣ
- ��
- �Ȥ����ط����Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���μ��ϡ�������ʽ�Ǻǽ�˽ФƤ������Ū�ʼ��Ǥ���
- ���۸��Τ褦�����˱����Ϥ����Ϥۤ�ʿ�Ը��Ȥߤʤ��Ƥ褯�����θ����������Ⱦ�����Υ�˸������ޤ�褦�ˤʤ�ޤ���
- �ޤ�������ξ�����Υ��ʪ�Τ��֤��ȡ�ʪ�Τ���Ф����ʿ�Ԥ˿ʤ�褦�ˤʤ�ޤ���
- �������������������֤��ȡ�������ʿ�Ԥ˿ʤ�褦�ˤʤ�Τ�������������Υ�ˤϤ��Τ褦�����֤ǥ�ȸ������֤���Ƥ��ޤ���
- ��μ��Ϥޤ���ʪ�Τ���θ�������̤�Ȥ����줬�ἴ�ʥ�����˶ᤤ���١ˤ�����Ω�ĤΤǡ�����ʪ��¦�ε�Υ��a�ˤ���¦�ε�Υ��b�ˤϡ��������Υ��f�ˤ�ɽ����뤳�Ȥⶵ���Ƥ���ޤ���
- �Ȥ����ǡ��ἴ�����ΰ�ȤϤɤ����٤��ΤǤ��礦��
- ��
- sin��
- ������%��
- 100x�ʦ� - sin�ȡ�/��
-
��
- �ʥ饸�����
- ����degree��
- ��-��3/6
- ������%��
- 100x�ʦ�3/6 - sin�ȡ�/��
- 0.009999833
- 0.001666658
- 0.01
- 0.57295779
- 0.009999833
- 0.001666667
- 0.019998667
- 0.006666533
- 0.02
- 1.14591559
- 0.019998667
- 0.006666667
- 0.049979169
- 0.041661459
- 0.05
- 2.86478897
- 0.049979167
- 0.041666667
- 0.059964006
- 0.059989201
- 0.06
- 3.43774677
- 0.059964
- 0.06
- 0.069942847
- 0.081646661
- 0.07
- 4.01070456
- 0.069942833
- 0.081666667
- 0.079914694
- 0.106632539
- 0.08
- 4.58366236
- 0.079914667
- 0.106666667
- 0.089878549
- 0.134945336
- 0.09
- 5.15662015
- 0.0898785
- 0.135
- 0.099833417
- 0.166583353
- 0.10
- 5.72957795
- 0.099833333
- 0.166666667
- 0.198669331
- 0.665334602
- 0.20
- 11.4591559
- 0.198666667
- 0.666666667
- 0.295520207
- 1.493264446
- 0.30
- 17.1887338
- 0.2955
- 1.5
- 0.389418342
- 2.645414423
- 0.40
- 22.9183118
- 0.389333333
- 2.666666667
- 0.479425539
- 4.114892279
- 0.50
- 28.6478897
- 0.479166667
- 4.166666667
- 0.564642473
- 5.892921101
- 0.60
- 34.3774677
- 0.564
- 6
- 0.644217687
- 7.968901823
- 0.70
- 40.1070456
- 0.642833333
- 8.166666667
- 0.717356091
- 10.33048864
- 0.80
- 45.8366236
- 0.714666667
- 10.66666667
- 0.78332691
- 12.96367671
- 0.90
- 51.5662015
- 0.7785
- 13.5
- 0.841470985
- 15.85290152
- 1.00
- 57.2957795
- 0.833333333
- 16.66666667
- �ἴ�����ιͻ���-��sin�ȤȦȤθ���
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ��
- ��
- ���ɽ�ϡ�sin�Ȥ�Ȥ��֤��������Ȥ��ˤɤ�����θ������Ф뤫��ɽ�ˤ�����ΤǤ���
- θ�϶��Ѥ�ɽ���ޤ���
- ��ɽ�α�����ϡ�θ�����3���ޤ�Ÿ������θ - θ3/6 �Ȥ�������sinθ�Ȥθ����Ǥ���
- �������طʤǼ�������ϡ�������0.66%���٤Τ�ΤǤ���
- θ��0.20�饸�����11.45°�ˤ�Ķ����ȡ�������1%��ˤʤ����Ȥ��Ƥϵ����ʤ��ʤ�ޤ���
- θ��0.90�饸�����51.56°�ˤˤʤ�ȸ�����13%�Ȥʤ�ޤ���
- ����θ�ϡ����̥�ι⤵���Τǡ�2f��sinθ��ʿ�Ը�«�������¤Ȥʤꡢ����Ⱦ�����Υ����Ǹ�����ʹʤ�ˤ���ޤ�ޤ���
- θ��11.45°�θ������F2.52�Ȥʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ������椬F2.52���⾮���ʡ����뤤�˥�Ǥ϶ἴ�����ΰ�Ȥ��Ƥϰ����ʤ����Ȥ��狼��ޤ���
- ���äơ������ͤ�����뤤��˴ؤ��Ƥ��͡��ʼ����������������ɬ�������ФƤ��ޤ���
- ��μ������ȤǤ���������ΤΥܥ��ʥ�������ġˡ�����˲ä��ƿ��ˤ������Τ���礤������߷Ԥ��������Ƥ����ܼ��Ǥ���
- ��
- ��
- �������̥�ζ�ΨȾ�¤Ⱦ�����Υ�δط�
- ��
- ��δ���Ū�ʤ�Τϡ����̷�������Ǥ���
- ��ΤۤȤ�ɤϰ���ζ�ΨȾ�¤���äƤ��ޤ���
- ��ε��̤˱�äƸ��������ޤ��ư����˽��ޤ�褦�ˤʤꡢ������������Focus Point�ˤȤʤ������Υ��Focal Length�ˤ���ޤ�ޤ���
- �����������٤�����ޤ��������̥���̤ä����������˽��ޤ�Τ϶ἴ�ΰ�������äǤ���
- ���̥�Ǥϡ��ἴ�����ΰ�ǥ��ͥ��ˡ§���Ѥ��Ƶ��̥��Ⱦ�¡�r1��r2�ˤȾ�����Υf�˰ʲ��δط�����äƤ��ޤ���
- ��
�ڥ�θ��ߤ�̵��Ǥ���Ȥ��� ��1/f = ��n - 1�ˡ���1/r1 - 1/r2�� ��������Lens - 3�� - f�������̥�ι���������Υ
- n�������̥�ζ���Ψ
- r1�������̥��ʪ��¦�ζ�ΨȾ��
- ��������ξ�̥�Ǥ�r1>0��
- r2�������̥����¦�ζ�ΨȾ��
- ��������ξ�̥�Ǥ�r2<0��
- n�������̥�ζ���Ψ
�ڥ�θ��ߤ�t�Ǥ���Ȥ��� - ��1/f = ��n - 1�ˡ���1/r1 - 1/r2�� + ��n - 1��2��t /��n��r1��r2�� ��������Lens - 4����
- ����������ξ�̥�Ǥ�r2<0�ʤΤ���������Ȥʤ������Υ��Ĺ���ʤ롣��
- ��
- r1 = r2�ζ�Ψ��Ʊ���ǡ�n = 1.52�θ��إ��饹��Ȥä����̥�ϡ���ΨȾ�¤Ⱦ�����Υ�����褽Ʊ���ˤʤ뤳�Ȥ���μ�����狼��ޤ���
- ���¡��������ʥ���ε��̥�Υ��������Ƥߤ�ȡ�Ⱦ��r1 = r2 = 100mm��ξ�̥�ξ�����Υ�Ϥ����褽f = 100mm�ˤʤäƤ��ޤ���
- �ޤ��������ˤ�äƶ���Ψ���Ѥ��ΤǾ�����Υ���Ѥ��ޤ���
- ����Ψn = 2�κ���ˤ��ξ�̥�Ǥϡ���ΨȾ�¤�Ⱦʬ��������Υ�ˤʤꡢn = 1.5�κ���Ǥ϶�ΨȾ�¤�������Υ�ˤʤꡢ�����ζ���Ψ�˶�Ť��ˤĤ������Υ���ɤ�ɤӤƤ����ޤ���
- ����Ψn = 2�ϡ����ե������ȥ��������ɤ���֤��餤�Τ�Τǡ�n = 1.5���бѤ���إ��饹��BK7�ˤ�����˶ᤤ�ͤ���äƤ��ޤ���
- f�������̥�ι���������Υ
- ʿ�̥�Ǥϵ��̤�1�̤����ʤ���¾�̤�ʿ�̤Ǥ��뤿��r2 = ∞�Ȥʤꡢ1/r2 = 0�Ȥʤ�ޤ���
- ���Υ�Ǥϡ����̤�Ⱦ�¤��ܡʤĤޤ�ľ�¡ˤ����褽�ξ�����Υ�Ȥʤ�ޤ���
- ���̤�1�̤����ʿ�̥�ϵ�η¤�������Υ�Ȥʤꡢ2�̤ǹ��������ξ�̥�Ǥϵ�η¤�Ⱦʬ���Ĥޤ�Ⱦ�¤���ξ�����Υ�Ȥʤ�ޤ���
- ����Υܡ����ϤɤΤ��餤�ξ�����Υ����Ĥ��Ȥ����ȡ���μ�������إ��饹�Ǥۤܵ��ľ�¤��������뤳�Ȥ��狼�ꡢ��θ���tʬ����Ĺ���ʤ뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���n = 1.33�ˤǺ�ä����϶����Ϥ��夤�ΤǾ�����Ĺ���ʤ�ľ�¤�1.5�ܤۤ�Ĺ��������Υ�Ȥʤ�ޤ���
- ��

- ��οޤϡ�Ʃ���ʵ���ξ�����ɽ������ΤǤ���
- BK7�ȸƤФ�����Ū�ʸ��إ��饹���бѤϤܻۤ����褦�ʰ��֤˾���������ޤ�������Ͼ���Υ�줿��˾���������ޤ���
- �����������Ѥ��ƥܡ����Ƥߤ�������Ȥ˵��Ť��ޤ���
- �ܡ����ξ�����˵�˾�����ʪ�Τ��֤��ƥܡ������̤��Ƥ���ʪ�Τ��Ȥ���Ȥɤ��ʤ�Ǥ��礦��
- ������ʪ�Τ��礭��������ϥ��Ǥ���
- �礭�ʥܡ����϶�ΨR���礭���ΤǤ���ۤɤζ����Ϥ�����ޤ��������ʵ���Υܡ����Ϥ��ʤ�γ���뤳�Ȥ��Ǥ���Ϥ��Ǥ���
- �¤ϡ����줬�������λϤޤ���ä��ΤǤ���
- 1668ǯ������������ʪ�ؼԥ졼������եå���Antony van Leeuwenhoek ��1632-1723�ˤϡ����饹�̤��ᤤ�ƺ�ä��嵭�Υܡ����Ǹ��������ꡢ������ʪ�Τδѻ���Ԥä��ΤǤ���
- �Ǥ��������Ψ�����ä������ʥ��饹�ܡ������Τ�����θ���������ν��פʥݥ���Ȥ��ä��ΤǤ���
- ��äȤ⡢�ܡ����ϡ�����ʿ�Ը��ι⤵���⤤��ʬ�ǤϾ������֤��Ѥ�ꡢ����⤵������׳��ѤˤʤäƵ���������2��ȿ�ͤ��ƽФƹԤ��ޤ���
- ��ũ�ˤ�����ʤɤ���������ũ�α�ʹ⤤�����ˤǤ����븽�ݤȤʤ�ޤ���
- ����
- ��
- ����������Υ�Ȳ�ѡ�Focal Length, Angle Of View��
- ��ξ�����Υ�Ȳ�ѤˤĤ��Ƥϡ����ޤΤ褦�ʴط��Ȥʤ�ޤ���
 ����Ū�˾�����Υ��û����ۤɹ�����Ѥ�ʪ�Τ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
����Ū�˾�����Υ��û����ۤɹ�����Ѥ�ʪ�Τ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���- ������Υ��û����Ȥ����Τϡ������Ϥζ�����Τ��ȤǤ���
- �٤ζ�����Ȥ�����ޤ���
- ��¦����������������դˤ��ɤäƤ����ȡ�������Υ��û����϶��������ϤΤ���˸����������Ȥ��äƤ��ޤ���
- �դ˸����ȡ�������Υ��û����ϡ������ϰϤθ���뤳�Ȥ��Ǥ����ޤ���
- �̤δ��������ν������������Ƥߤޤ���
- ʪ��A����Ф����ϥ���̤��ƺǽ�Ū��A'�˽��ޤ�ޤ���
- ������ΰ�ڤθ����ϡ�����濴�ʼ����ˤ��̲ᤷ�ޤ���
- Ʊ�ͤˤ��ơ�ʪ��ɽ�̤�Ǥ�դ�������Ф����ϥ�ˤ�ä���ޤä��������夭�ޤ�����ʪ�ΤΤɤΰ��֤���Ф����⤽�ΰ�Ĥϥ���濴���̤�ޤ���
- ���οޤϡ�����濴���̤�����������ܤ��ƥ��������ط�������ΤǤ���
- ��̣���뤳�Ȥϡ�ʪ�Τȥ���濴��H�ˤǺ�뻰�ѷ��ʢ�ABH�ˤ����ȥ���濴��H'�ˤ���뻰�ѷ��ʢ�A'B'H'�ˤ��礭�����㤦������Ʊ���������ʤ��������ȤʤäƤ��뤳�ȤǤ���
- ���ʪ�Τ��������̾��ʤ⤷���ϳ���ˤ�����������äƤ���ȸ����ޤ���
- �������Ȥ����Τϡ����������뤫���Τ�ޤ���
- ��ϼ������餱�Ǥ��ΤDz����������Τ���������������ʤ���Фʤ�ʤ�����Ǥ���
- �Ǥ���������߷Ԥ���¤�Ԥ��������Ϥ���Ƥ���ΤǤ����顢�������������뤿��˥�������ǧ�����ƴְ㤤����ޤ���
- �������߷פβ�������¤�β����Ǥɤ����Ƥ�������ǤƤ��ޤ��Τǡ����������������������ٹ礤�ä����İ����Ƥ������Ȥ����Τ����Υ����Ȥ���Ū�Ǥ���
- ���֥�ϵ�§��������������Ĥ��٤�����Ǥϸ��꤬���뤾������������β�Ѥ˴ؤ��ƤϤ����Ǥ�����������������
- �ȸ��������ΤǤ���
- �ä�����äȲ�ƻ�ˤ���ޤ�������ʪ�Τ����ϥ����Ω���Ȥ������§����������Τǡ�ʪ�Τ��礭���ȥ�ε�Υ���狼���ʪ�Τ�Ȥ館����١��������Ѥ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ºݤΤȤ�����CCD�����ʤɤϻ����ǻҤ��礭���˸¤꤬����Τǡ������礭���������β�Ѥ������ޤ���
- �Ĥޤꡢ��β�Ѥϥ�ξ�����Υ�Ȼ����ǻҤ��礭���Ƿ����Ƥ��ޤ��ޤ���
- �����˥�β�Ѥδط������ޤ���
- ��Ѥϥ������������A'B'�ˤȥ���֤������֡�b�ˤǷ���졢����֤������֤ϥ������Υ�ˤ���ޤ뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
-
��2�� = 2��tan-1��A'B'/2��b�� ��������Lens - 5�� - ��������ѡ�Ⱦ�ѡ�
- A'B'���������̤��礭��
- b��������濴��H'�ˤ��黣���̤ޤǤε�Υ
- ������b = f����1 + M��
- M����������A'B'/AB��
- A'B'���������̤��礭��
��2�� = 2��tan-1��A'B'/2��f�� ��������Lens - 6�� ���弰�ϡ�ʪ�Τ�������20�ܰʾ��礭����b���¤�ʤ�������Υf�˶ᤤ���Τ�Ρ��� - �����̤��礭���ϡ������ǻҤο�ʿ�������Ǹ��ä��ꡢ�ĥ������Ǹ��ä��ꡢ�ġ������碌���г�����ɽ�����ꤷ�ޤ���
- �����Ǹ���ɸ���Ȥϡ��ͤλ�Ѥ˾Ȥ餷��碌��Ʊ���褦�ʲ�Ѥ���ä�����Ƥ�Ǥ��ޤ���
- �ͤλ�Ѥ�45°��55°�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��̩�˸����пͤϤ⤦�������������ξ�����140°�ˤ���äƤ��ޤ���������ϸ��ζ�����������Τʻ�ǧ���Ǥ���櫓�ǤϤ���ޤ���
- 50°������λ��Ϥȿ���ǧ��������ͥ�줿�����ʻ�ѤǤ���Ȥ���Ƥ��ޤ���
- �ͤλ�Ѥ�50°����ĥ������ɸ���Ǥ���Τǡ�2θ=50°���μ�������Ƥ��С������μ���Ȥ���˹礦ɸ������ޤ�ޤ���
- �㤨�С�2/3�����CCD�����ϡ�8.8mmx6.6mm���г���11mm�ˤλ����̤���äƤ��ޤ����顢A'B'=11���֤��ȡ�f=11.8�Ȥʤꡢf12mm�Υ��2/3�����CCD�Ǥ�ɸ���Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ��������ѡ�Ⱦ�ѡ�
- ɸ����f�ȥ���黣��������A'B'�δط��Ͼ�μ����������ơ�
-
��f = 1.072��A'B' ��������Lens - 7�� - �Ȥ����ط���Ƴ�����Τǡ������̤��礭���Ȥۤ�Ʊ�����ͤΥ������Υ��ɸ���Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �饤����������1���ե���顢24mmx36mm���г���43.3mm�˥�����Ǥ�f50mm��ɸ���Ǥ���ȸ�����ΤϤ�����ͳ������Ƥ��ޤ���
- �ʼºݤ�f43.3mm�ʤΤǤ�������¤��f50mm������䤹���Τ�f50mm��ɸ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- Ʊ�ͤˤ��ơ��֥����ˡ��Ǥ�4x5����������ȥե�����Ȥä���Ƚ�����Υ��f175mm���٤�ɸ���Ȥʤꡢ1/4�����CCD������3.6mmx2.7mm���г���4.5mm�ˤǤ�f4.8mm��ɸ���Ȥʤ�ޤ���
- �Ȥ����ط���Ƴ�����Τǡ������̤��礭���Ȥۤ�Ʊ�����ͤΥ������Υ��ɸ���Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���50°�Ȥ��ơ�����������Ѥ���ĥ�ѥ��������ѤΥ��˾���ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �饤����������ɸ����Nikkorf50mmF1.2��1/4�����CCD�˻Ȥ��Ȳ�Ѥ�5.2°�Ȥʤꡢ����Ͽʹ֤λ�Ф�1/10���٤Ȥʤ�Τ�˾���ˤʤäƤ��ޤ����Ȥ����Τ��Ȥ���狼��ޤ���
- ��
- �������Υ
- 2/3������ǻҤβ��8.8mmx6.6mm���г�11mm��
- 1/4������ǻҤβ�ѡ�3.69mmx2.77mm���г�4.61mm��
- �饤���������β�ѡ�24mmx36mm���г�43.3mm��
- 4x5�������Ƚ�����β��127mmx101.6mm���г�162.6mm��
- f6mm
- 85.02��
- 42.03��
- 149.0��
- 171.6��
- f12mm
- 49.24��
- 21.75��
- 122.0��
- 163.2��
- f25mm
- 24.82��
- 10.54��
- 81.79��
- 145.8��
- f50mm
- 12.56��
- 5.28��
- 46.83��
- 116.8��
- f100mm
- 6.30��
- 2.64��
- 24.43��
- 78.22��
- f200mm
- 3.15��
- 1.32��
- 12.36��
- 44.24��
- f400mm
- 1.58��
- 0.66��
- 6.20��
- 22.98��
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ���������Υ�Ȳ�ѡʳƼ參��黣���������ˤ���Ѥΰ㤤��
- �ԥ��ο��ͤϡ�ɸ���ȸƤФ�Ƥ����Ρ�
- ��
- ��
- ��
- ����������Ψ ��Magnification��
- ��
- ��ˤ�äƤǤ��������礭���ϡ���ξ�����Υ�ˤ�äƤ��Ѥ��ޤ�����ʪ�Τ��֤����֤ˤ�äƤ����褽���礭�����Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����ǡ�������Ψ�ˤĤ����������Ƥ����ޤ��礦��������Ψ�ϡ������礭����A'B'�ˤ�ʪ�Τ��礭����AB�ˤdz�ä��ͤ�����ޤ���
- ��
- ����������M = A'B'/AB�������������ҡ�
- ��
- ������ΨM�ϡ�����Ū��1�ʲ��Τ��Ȥ�¿����ʪ�Τ�̾������������̤˷�Ф��ޤ���M��1�ʾ�λ���ʪ�Τ�����������礭���ʤ���绣�ƤȤʤ�ޤ���
- �����ʤ�ΤƤ���Ȥ��ˤϡ�M���ͤ��礭���ʤ�褦�ʥ�����֤��Ѥ��ޤ���
- ��
- ��
- ��
- ��
- 1.���ˤ���ʪ��
- ��
- ʪ�Τ���ʪ���Ȥ������Ȥ����˱ˤ����硢ʪ�Τϥ���Ф������˱��֤���뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ٻλ��ʤɤϻ��ι⤵�����Ǥ�����2,700m�����ޤ���
- ����ζҤ�10km���٤Ǥ���
- �����20,000m����Υ�줿���¾줫��į���Ȥ���ȡ������ʪ�ΤޤǤϡ�a=20,000,000mm�Ȥʤ�ޤ���
- ���ΰ��֤�f50mm�Υ������Ȥä��Ȥ���ȡ��ٻλ��ϡ��������Υ��400,000�ܤ���֤ˤ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���ξ�硢���ϥ����������Υ��Ʊ���֤˷�Ф�ޤ���
- ���λ��λ�����Ψ�ϡ�b/a = 1/400,000�Ȥʤ�ޤ���
- 2,700,000mm�ᤤ���¤ߤ�6.75mm�����Ȥ��Ʒ������뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �������f100mm�Τ�Τ�Ȥ��Ȼ�����Ψ��Ⱦʬ�ˤʤ�Τǡ������礭����13.5mm�Ȥʤꡢf200mm�Υ�Ǥ�27mm���礭���ˤʤ�ޤ���
- ����ե�����f200mm�Υ��Ȥ��ȡ��ե������̤ˤ��äѤ����ٻλ���̤����Ȥ��Ǥ�������ʾ�ξ�����Υ��Ǥ��ٻλ���ĺ����ڤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��ʪ�ΤƤ������������Ψ�ǻ��Ƥγ���ɽ����������˾������ͤ�ʬ���Ȥʤ��������Τǡ���ѤǸ������Ȥ�����Ū�Ǥ���
- �㤨���ٻλ��ο����ĺ��ޤ�2,700m��10,000mΥ�줿�ٻε��ĤǸ����硢���λ���Ѥ�15.38°�Ȥʤ�ޤ���
- �ͤ�ɸ�����Ѥ�50°�Ǥ����顢��1/3���ٻλ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���ΰ��֤��ٻλ���餤�äѤ��˼̤����Ȥ���ȿ�ľ���15.38°�Υ��Ȥ����ɤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ����ե����Ǥ�f89mm�Υ��������������ޤ���
- �ȸ������ˡ����٤Ǹ��ä������狼�꤬�ɤ��ʤ�ޤ���
- �����Ǹ���������Ψ��˾����Ǹ�����Ψ�Ǥϡ���������������ۤʤ�ޤ���
- �����Ǥ������礭����ʪ�Τ��礭������ǻ�����Ψ����ޤ�Τ��Ф��ơ�˾����ǤϿͤ�����ʪ�Τλ�Ѥ�˾����ˤ�ä�������ʪ�Τλ�Ѥ���ǵ�ޤ�ޤ���
- ˾����ξܤ����������̤˽Ҥ٤뤳�ȤȤ��ơ���Ψ������˰㤤������Τ����դ�ɬ�פǤ���
- ����������Ψ��˾����Ȥϰ㤤�����γ�����Ψ��ؤ��Ƥ��ޤ���
- ������ʪ�Τ�ɤ줯�餤�ޤ��礭�����Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ��뤫�Ȥ�����������Ψ��������Ƥ���Τǡ�����������Ψ�ϥ��������Ψ�˶ᤤ�ͤ����ȸ����ޤ���
- �������ξܤ��������������������������Ȼפ��ޤ���
- ��
- 2.�����ܤǸ���
- ���Ȥä�ʪ�Τ�Ʊ���礭�����������硢ʪ�Τ�����¦������Υ��2�ܤΰ��֤��֤��С����¦������Υ��2�ܤΰ��֤������Ǥ��������礭����ʪ�Τ�Ʊ���ˤʤ�ޤ���
- a = 2f���֤��ơ���θ��� 1/a + 1/b = 1/f �����ƤϤ��С�a = b = 2f �Ȥʤꡢ������Ψ M = b/a = 1�Ȥʤ뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ʪ�Τ������¦������Υ��2�ܤ����Τ��ˤĤ�ơ����Ϥɤ�ɤ����ʤ���¦������Υ���֤˶�Ť��Ʒ������뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ��
- 3.�����礷�Ƹ���
- ʪ�Τ������¦������Υ����2�ܤޤǤΰ��֤ˤ���Ȥ������ϳ��礵��ޤ���
- ʪ�Τ�2f�λ�������ʪ�Τ�Ʊ���ˤʤꡢ2f����f�˶�Ť��ˤĤ�Ƥɤ�ɤ��礭���ʤ�ޤ���
- 10�ܤγ�������������ϡ�M = b/a = 10��b = 10a �ʤΤǡ���������������ƤϤ���a = 1.1f �ΰ��֤�ʪ�Τ��С�����10�ܤˤʤ�ޤ���Ʊ�ͤ�100�ܤγ���Ǥ�1.01f�ΰ��֤�ʪ�Τ��֤����ɤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- �¤�ʤ���¦�������֤�ʪ�Τ���äƤ��뤳�Ȥˤ�������礭���ʤ뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �������礵����ȼ���������Ǥ�����֤ϥ�ΤϤ뤫�������㤨��10�ܤλ�����Ψ�Ǥ�11f�ΰ��֡�100�ܤǤ�101f�ΰ��֤ˤǤ����礭�������Ǥ��ޤ���
- ������������Ϥ����������Ť����Ȥʤ�ޤ���
- �ޤ����礵�줿���ϥ�μ����ˤ��ƶ��ǥ��㡼�פ�����˾��٤��⤢��ޤ���
- ���礷�Ƹ���ˤϳ����Ѥˤ��ä�����������ܤ��줿���ɬ�פǤ���
- ��
- 4.�������Ǥ��ʤ�����
- ʪ�Τ�����¦�������֤��֤��ȡ�ʪ�Τ���Ф����ϥ���̤ä�ʿ�Ը��Ȥʤ�ޤ���
- �Ĥޤꤳ�ΰ��֤Ǥ����ϤǤ��ʤ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ϤǤ��ޤ���ʪ�Τ���Ф�����ʿ�Ը��ˤʤ뤿�ᡢʪ�Τ�������˻Ȥ��褦�ʸ����ˤ���ȸ�������Ф����ϱޤdzȤ��餺���Ϥ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ���θ��������Ѥ��������������θ�������ƥ���߷פ����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ��
- 5.��������Virtual Images�ˤΤǤ������
- ���ˤϼ�����Real Images�ˤȵ�����Virtual Images�ˤ���Ĥ�����ޤ���
- �����Ȥ����Τϡ����ΤǤ�����֤�����֤��������Ǥ��Ƥ��뤳�ȤǤ狼�ꡢʪ�Τ���θ������ΰ��֤˽��ޤ뤳�Ȥ��̣���ޤ���
- CCD���������ե�����������Ǥ�����֤˻����̤��֤�������Ͽ���ޤ���
- �����ȸ����Τϡ��������⤽�ΰ��֤���������褦�˸����뤱��ɤ⡢�ºݤˤ��ΰ��֤�����Ƥ����ϸ����ʤ���Τ�����ޤ���
- �������ϵ�����ŵ��Ū�ʤ�ΤǤ���
- ���α��ˤ������ϡ����ΰ��֤��餢����������ФƤ���褦�˸����ޤ����ºݤ��̤ν�ˤ���ʪ�����θ�����ȿ�ͤ�����������褦�˸����Ƥ�������Ǥ���
- ��Ǥϡ�ʪ�Τ���¦������Υ���֤����¦�ˤ���Ȥ������ϵ����Ȥʤ�������֤��Ȥ�����ޤ���
- ���ΰ��֤ǤλȤ����ϡ���ᥬ�ͤ�롼�ڤʤɤΤ褦�ʳ�����Ȥ��ƻȤ��ޤ���
- ���ΰ��֤ǤǤ�������ϡ�ʪ�Τ�����¦�������֤ζ���֤����֤��ۤ��礭�ʳ���Ψ�������ޤ���
- ��˶�Ť���������礭�������ޤ���
- ����Ψ���礭�����ƤǤ����礭�ʳ������ϡ��ˤǤ��Ƥ��ޤ����ᡢ����Ǥ��ε�����ˤϸ��Ť餯�ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �ͤ��ܤǤϰ���Ū��250mm���դ�������äƤ���Τ����ָ��䤹������ˡ�b=-250mm���֤��ȡ��������ꡢ1/a - 1/250 = 1/f��M = b/a = 1 + 250/f �Ȥʤꡢf=250mm�Υ��2�ܤγ���Ψ������졢f=50mm�Ǥ�6�ܤγ���Ψ�Ȥʤ�ޤ���
- f=250mm����Ѥ����Ȥ���ʪ�Τΰ��֤�125mm�ΰ��֤��֤����ɹ��ʵ���������졢f=50mm�Υ�Ǥ�41.7mm�ΰ��֤�ʪ�Τ��֤��С�250mm�ΰ��֤˵������Ǥ�6�ܤ���Ψ��ʪ�Τ���礷�Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �롼�ڤ������ϡ����Υ�ξ�����Υ��û���ۤɳ���Ψ���⤤���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��
- ���Τ褦�ˤ��Ƹ���ȡ��������Υ��˵��ʪ�Τ��֤����͡��ʤ��⤷�������ݤ������뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �äˡ���ǽҤ٤�4.��5.�ϳ��绣�Ƥ˺ݤ��Ƶ��Ťʥҥ�Ȥ�Ϳ���Ƥ���Ƥ��ޤ���
- 4.�ξ�硢�������֤�ʪ�Τ��֤������ϤǤ��ޤ���̵�±�˼ͽФ���������ǺƤӷ���������ȡ�������ξ�����Υ�Ȥ��������֤�����ξ�����Υ����ˤ�äƳ��绣�Ƥ��Ԥ��ޤ���
- ���μ�ˡ�ϥ����������åץ�ˤ����绣�ƤΤ�����Ǥ��ꡢ�������ˤ��̵�±���طϤΤ�����Ǥ⤢��ޤ���
- ���μ�ˡ�ˤ����绣�Ƥ϶�̣������Τǹ�����ƾҲ𤷤褦�Ȼפ��ޤ���
- ��
- ��
- �����ԥ��Ĵ���ʥե���������Focusing��
 �ԥ�ȤȤ������դϤɤ������ܸ�Τ褦�Ǥ���
�ԥ�ȤȤ������դϤɤ������ܸ�Τ褦�Ǥ���
- �츻�ϥ�������ξ�����brandpunt�ˤȤ������դΤ褦�ǡ����줬�¤äƥԥ�ȤȤ������դ��Ǥ����褦�Ǥ���
- �Ѹ�Ǥϥե������å��ȸ����ޤ���
- ���ܸ�Ǥϥԥ�ȹ�碌�Ȥ������դ�����Ū�ǡ��ե�������Ĵ���Ȥ������դϵ��ѼԤδ֤Ǥ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���Τ褦�ˤ��Ƹ���ȡ��������Υ��˵��ʪ�Τ��֤����͡��ʤ��⤷�������ݤ������뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���Ȥ����˰������ˤ˻Ȥ��꤬�ԥ��Ĵ���ǤϤʤ��Ǥ��礦����
- �Ƕ�ϥ����ȥե��������ˤ�뼫ư�����ڤ��ƥե�������Ĵ����Ԥ�ɬ�פ��ʤ���Τ������Ƥ��ޤ���
- �Ǥ����顢�ե����������¸�ߤ��餢�ޤ굤�ˤ��ʤ��ʤäƤ��뷹���ˤ���ޤ���
- ���������ԥ��Ĵ���ȤϤɤ�������ΤǤ��뤫�����Ƥ������Ȥ����ڤǤ���
- C�ޥ���ȥ��˥å�����F�ޥ���ȸ�ˤϥ�������ž�����ƥԥ�Ȥ��碌����Ȥߤ�����ޤ���
- ������ʬ��ե���������ȸƤ�Ǥ��ޤ��������Υե����������ʤ��������տ�������ȡ������������˰�ư���Ʒ���Ф�������ù�����ꤷ�Ƥ���Τ��狼��ޤ���
- ���ܻ��Ƥ�����ϥ�η���Ф����礭����̵�±��∞�ˤǺ�û�ˤʤ�ޤ���
- ���Ф��Ȥ����Τϡ�����������������ˡ��о�ʪ�����ˡ˰�ư���뤳�Ȥ��̣���Ƥ��ޤ���
- ���οޤǸ����ȡ�b�פΰ��֤��Ѥ��ơ�����ΤޤǤε�Υ��a�פȾ�����Υ��f�פδط�������������ΤǤ���
- �����ΰ��֤���ޤäƤ�������Τΰ��֤��ޤäƤ�����ˤϡ���b�פ��ư������Lens -1������������ɬ�פ�����ΤǤ���
- ��
- �����ԥ�Ȥ����ʤ�
- ��Υե����������ƥԥ��Ĵ����ԤäƤ�ԥ�Ȥ����ʤ����ϡ�¿���ξ������Τ���ζ�ˤ��äơ�a�פ�û���ʤꤹ���Ƥ��ơ�ɬ��Ū�ˡ�b�פ�Ĺ�����ʤ���Фʤ�ʤ����ִط��ȤʤäƤ�����Ǥ���
- ���ξ�硢�����ι�¤���b�פ�ʬĹ������Ф����Ȥ��Ǥ��ʤ��ΤǤ���
- ��b�פ϶������߷塢Ĺ������Ф����ȤߤˤʤäƤ��ޤ���
- �ޤ���������Ψ���Ѥ��Ȳ������դμ�����¿���ʤ�Τǡ�����ϥȡ�����ΥХ��ˤ�ߤʤ����Ŭ�ʺ�û��Υ�Υ����Ф��̤���Ƥ��ޤ���
- ����Ū�ˡ�û��������Υ�ʹ��ѥ�ˤ�������û���Ƶ�Υ��û����������Υ��Ĺ������˾���ˤ���û��Υ��Ĺ���ʤ�ޤ���
- ˾���Ƕ��Υ�Ƥ��褦�Ȥ���ȡ���b�פʤ��ư�����ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǶ��Υ�Ǥλ��Ƥ����ꤷ����ˤϤʤäƤ��ޤ���
- �ޥ�����ϡ����绣�Ƥ�����Ȥ�����ʤΤǡ���η���Ф��̤��礭����������̷���Ф����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���ñ�Τ�����M=1/2�γ��绣�Ƥ��Ǥ��ޤ���
- ���λ�����Ψ�Ǥϡ�f105mm�Υ�ξ�硢����濴���黣���̤ޤ�150mm�ⷫ��Ф����Ȥˤʤ�ޤ���
- ��
- ��������ʡ��ե�������
- ˾���ϡ�����Τ��Ť��ƥե������������礭�ʥ�����Τ�����˰�ư������Τ����Ѥʤ���ˡ��Ƕ�Τ�Τ������˥���ڥ�����ȸƤФ�뾮������������Ȥ�����ơ����Υ�����夵���ƥԥ�Ȥ��碌���Τ��ФƤ��Ƥ��ޤ���
- ���Υե��������Τ������֥���ʡ��ե��������פȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ��
- ������Ƚ��Υե�������Ĵ��
- ����ե����Υ�ϡ���ư���δ�������ե�����������������ޤޥե�����������ñ�˹Ԥ���褦�˥�ζ����˥ե�����������Ĥ��Ƥ��ޤ���
- �������ܲȤǤ���4x5����������פΥܥå��������Υ�ϥץ졼�Ȥ˼���դ����Ƥ��ơ���ζ������Τ˥ե�������Ĵ����ǽ���Ĥ��Ƥ��ޤ���
- �������ꥫ���¦�˼�ʢ�ȥ�����굡�����Ĥ��Ƥ��ơ����ε����ˤ�äƥ��Ф��ƥե�������Ĵ����ԤäƤ��ޤ���
- �����Υԥ�Ȥϡ��ե���ॷ���Ȥ������������ꥬ�饹�ǤǤ����ե��������ץ졼�Ȥ�����ۤ������äơ��ե��������̤˥롼�ڤ����ƤƼ�ʢ�����ǥ�����夵���ʤ���ԥ��Ĵ����ԤäƤ��ޤ�����
- ��ꥬ�饹�Υե��������̾�ˤǤ������Ͼ岼�������դ����Ǥ��뤿�ᡢ�������֤����ݡ�����������ư���Ȥ�ȿ�Ф�ư����ΤǴ���ʤ��ȼ谷�ˤ�����ΤǤ���
- ��
- �����������Υԥ��Ĵ��
- �������Υ�ϡ���������ܴ��ʤ⤷���ϥ���������ˤ����ΤˤʤäƤ����Τ�¿��������Τϥ����ü�������˶ᤤ���֤ˤ����ʤ���Хԥ�Ȥ��礤�ޤ���
- ����ϡ���������Ĥ�������餴�ȥ�����ư������������Τ������ư�����ƥԥ�Ȥ��碌�뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ�弰�Ǹ����ȥ�ξ�����Υ��f�פȥ����ޤǤε�Υ��b�פ���ޤäƤ���Τǡ�ɬ��Ū�ˡ�a�פ����ꤵ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��
- �ʾ��ޤȤ��ȡ������Υ����˽Ҥ٤��ἴ�����ΰ�Ǿ�μ����������뤿��˥���ư�����Ʒ��������Ƥ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ��a�פ��ͤ������礭������Τ�̵�±�ˤ��������b�פϸ¤�ʤ��������Υ��f�פ˶�Ť����Ȥ���μ���������Ǥ��ޤ���
- �����ơ���a�פ���ξ�����Υ��f�פ˶�ˤʤ�����Ϥɤ�ɤ�ˤʤäơ�b�פ�Ĺ���ʤ�Τǡ���ʤ귫��Ф��ʤ��ƤϤʤ�ʤ��ʤ�ޤ���
- ���Ф����ʤȤ��Ƥϡ�C�ޥ���ȥ�����ե�����Ǥ�����ܼ̥�ȸƤФ�����䡢��ʢ�ʥ٥������ˤ��ȥ�δ֤�����Ʒ���Ф��ޤ���
- ��b�פ��礭���ʤ�������礭���ʤ�Τdz��绣�Ƥ���ǽ�ˤʤ�ޤ���
- �ɤΤ��餤���礷������ɽ���Τϡ�a�פȡ�b�פ����ɽ���졢b/a����������Τ��Ф�����Ψ�Ȥʤꡢ�������Ψ�ȸƤ�Ǥ��ޤ���
���������� - �����ԥ�Ȥ����ʤ�
-
��M = b/a �����������ҡ� - M:��������Ψ
- a����ʪ�����ΰ��֤������濴�ޤǤε�Υ
- b��������濴����������ޤǤε�Υ
- a����ʪ�����ΰ��֤������濴�ޤǤε�Υ
- M:��������Ψ
- ��μ��������ˤ�뻣����Ψ�δط����Ǥ��ʤ��δط����ϲ��٤��о줷�Ƥ��ޤ��ˡ�
- ����Τ��ˤ���Ȥ��ϡ�a�פ��礭������b�פ��¤�ʤ���f�פ˶�Ť��ޤ���
- ���λ�����a�פ��礭���Τ�M�Ͼ������ͤˤʤ�ޤ���
- ��a�פȡ�b�פ�Ʊ���ͤλ������ΤȤ��ϡ�a = b = 2f �Ȥʤꡢ���Ѥ��Ƥ���������Υ��2�ܤΰ��֤�����ΤȻ����̤�������Τ�Ʊ���礭�������������̤���Ƥ���ޤ���
- f100mm�Υ�����ܻ��Ƥ���ˤϡ�����濴�ϻ����̤���200mmΥ�줿�Ȥ������ޤ���ʪ�Τޤ�200mmΥ�줿��ˤ���ɬ�פ�����ޤ���
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
�����ʤ�κ��ѡ�Diaphram��
- �����ʤ�Ƚ����ܥ���Diaphragm, Image Blur�� ��2005.04.18���ˡ�2005.07.24�ɵ���
- �����ι��������ʤ顢���ʤä����������Υ��줬�ɤ��ʤ뤳�Ȥ�����Ƥ���Ǥ��礦��
- ����������������Ȥ��Ƥ������Ȥ��졼������������طϤ˷Ȥ�äƤ������ϡ���������礭����äƹʤ�ʳ������ˤ������������줬�ɤ��ʤ뤳�Ȥ�����Ƥ��ޤ���
- �������졼��⤽�Τ褦���⤭�ޤ�����
- �����ꥹ�ΰΤ��ؼԤ������Ȥ�ʢ�ˡ��̿������Υ�ʤɤϹʤä������ԥ�Ȥ���������礦�Ȥ����и���褯���ޤ���
- �̿��Ȥ�ͭ̾��������ϡ�4x5���������ؼ���´�ȼ��Ǽ̿������Ȥ������ۤ���äƻ��Ƥ���Ȣ�������ˤ�Ȥ��ݤˡ���ιʤ��F32�κǾ��ʤ��Ȥä�Ĺ����Ϫ����Ԥ����Ƥ����դȤ��Ƥ��ޤ�����
- ��ιʤ��Ȥ���硢�����ǻȤ����ȹʤ����ξ�ԤϤɤ��餬�������ΤǤ��礦��
- ��������߷Ԥˤ��ȡ��¤���ϼ������礭���Τǥ��ʤäƲ��ޤˤ��ܥ����ФƤ⡢�����Ǥμ��������������뤳�Ȥ�¿���Ȼ�Ŧ���Ƥ��ޤ���
- ����ۤɤ˰²��ʥ�ϼ������礭���ΤǤ��礦��
- �ޤ����������ϥԥ�Ȥι礦�ϰϤ������Τǡ���̳����٤��ᤫ������ƥԥ�Ȥι礦�Ȥ���������Ǥ���������㡼�פˤ����������ޤ���
- �Ǥ����鸲�����Υ�ˤϡ�����Τ˹ʤ굡����⤦���Ƥ��ޤ���
- �졼���ӡ���ν�����Ʊ�������ޤ���
- �졼����ñ�����Ǥ����鿧�����Ϻǽ餫��������ƹͤ��褯���ޤ���ʿ�ԥӡ���Ǥ����饳�������Ķʼ����ʤɼФᤫ����������ˤ�������̵�뤷���ɤ����ᡢȯ����Ĺ�Ǥ�ʬ��ǽ��¿ʬ�˰ռ����ޤ���
- ������Ф����̿����Ƥϲ�Ѥ���ä����������Ļ���ä��ꡢ�������٤���̳����٤��ۤ����Τǥ��ʤ���ळ�Ȥ�;���ʤ�����ޤ���
- 35mm����ե����Υ�ϡ�F5.6�����ɤΥ����ǽ��ȯ���Ǥ���褦���߷פ���Ƥ��ޤ���
- �������������ʤ���ñ�ʥ�Ǥϡ������椬F2.52�������뤤��Ǥϵ��̼������礭�ʤ����Ҥ٤ޤ�����
- ¿���μ̿���Ϥ���ǤϻȤ�ʪ�ˤʤ�ʤ�����ˡ����뤤��Ǥ���̼������ޤ��ƶἴ�����ΰ�θ�����1/a + 1/b = 1/f�ˤ����Ǥ���褦�˥���߷פƤ��ޤ���
- ����ե�����ѤΥ�ϡ�F5.6���٤ˤ����Ƥ��٤Ƥμ������ɹ��˼������߷פˤʤäƤ����ʹ���Ƥ��ޤ���
- �̿�����߷פ���ˤ�Ҥ�Ȥ��Ƹ��ޤ��ȡ��̿����ȯ�����������Ĥ��礭����8����� x 10����� = 203.2mm x 254mm�Ȼ��ƥ��ꥢ���礭���ä����ᡢ���������������礭�����ʤ���Фʤ餺�����ġ������������ˤ錄�ä��濴����Ʊ���٤β�����ᤵ��Ƥ��ޤ�����
- �̿���ϡ������������Ǥ��������� �䥳�����������Ѷʤ��äˤҤɤ����졢��������뤿��ˤϥ�θ��¤������ơ����ʤä����ǻȤ��������̤�����ޤ�����
- ����������̣�ǡ��緿�������̿��Ȥϲ桹���ޥ��奢�����ޥ����ɬ�װʾ�˹ʤ���Ф��ƿ��м��ˤʤꡢ�ʤ��������ƤƤ���褦�˸��������ޤ���
- ��Ƚ�����Υ����ޥ�ϥԥ�ȹ�碌�ѤΥ롼�ڤ�Ȥäƴ����̡ʥե��������ץ졼�ȡˤζ����ˤ錄��ԥ���̤���ǰ�˥����å����ƻ��Ƥ�ԤäƤ��ޤ���
- �����������������ȹʤ�
- ��ιʤ���Ѥϡ���̳����١ʥԥ�Ȥι礦�ϰϡˤ��礭������Ȥ��������ȡ������μ��դޤǸ����㲼���ޤ���Ȥ������̤�����ޤ���
- 4����� x 5�������10cm x 12cm�ˤȤ����礭�ʴ����ե�����Ȥ���硢���Ƥ��줿�ͥ��ե���फ������˳���Ƥ��դ���Τˤ���ۤɤ������Ψ���ᤷ�ʤ��Τǥ��ʤ����Ǥ���β����Ѥ��礭�ʱƶ���Ϳ��������������̳����٤���ä������ɤ��Ȥ�����ͳ�����ʤ���ʤäƤ��ޤ���
- �ޤ�����Ƚ������ξ�硢�礭�ʥե�����̤�Ȥä��ꥢ���껣�Ƥˤ�äƼ�������Ȥ�ʤ���Фʤ餺�����������������礭�����ʤ���Фʤ�ʤ��ط����ʤ��ʤäƥ��������������礭����äƤ��ޤ���
- �ǥ����륫���ϡ������ǻҤ������������Ǥ�5um���٤Ⱦ���������ˡ������ߤ˹ʤ���ळ�ȤϤǤ��ޤ���
��
- �����ƺ���ߡʤ���褦�������Allowable Image Blur��
- ��ˤ�뽸����������Ȥ��ˡ��ɤ��ޤǤ����Ȥ��Ƶ����뤫�Ȥ������꤬�ФƤ��ޤ���
- �������Ȥ��Ƶ������ϰϤΤ�Τ���ƺ���ߡ�Allowable Image Blur�ˤȸ����ޤ���
- ���ƺ���ߤ������ۣ��ǡ�������ס�����߷Ԥˤ�äƤޤ��ޤ��Ǥ���褦�˸��������ޤ���
- ����ե�������߷״��ε��ƺ���ߤ���Ƚ������Τ���Ǥϰ�äƤ��ޤ������Υǥ����륫����ѥ�ǤϤ��ο��ͤ���ľ����Ƥ���褦�˸��������ޤ���
- ���⤽����¿���μ�����ȼ�äƤ��ơ����٤Ƥ���Ƥ��ޤ��뤳�Ȥ�����Ǥ���
- ������Ω�Ƥ�Ф����餿�����ǡ��������ޤ����߷פǤϡ��������դǸ����С��Ŷ����ʤ���ԤäƤ���ΤǤ���
- �����ޥ�ϡ������˾Ƥ��դ���줿�����ơ�������ɤ��������ϰ�����ȸ��äƤ��ޤ�����
- ���δ�����������ȡ���Ϻǽ������λž夬��ʤ����߷ס���¤��ȿ�Ǥ��Ƥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ���ƺ���ߤϡ����äơ����Ʋ����λž夬�꤫���������ܥ���и�Ū��Ƴ���Ф���35mm����ե����Υ饤���������ե����Ǥϡ�0.033mm��33um�ˡ�16mm�Dz襫���Ǥ�0.025mm��25um�ˡ���Ƚ�����Ǥ�0.5mm��50um�ˤȤ���Ƥ��ޤ�����
- ���Υܥ��θ����̤ϡ����Ƥ�����˰����˰�����Ф��ư����β����ƥ��㡼�פ˸������ϰϤǷ��Ƥ����ΤǤ���
- �㤨�С�35mm�饤���������Υե���फ�饭��ӥͥ������ΰ����˰�����Ф���硢����ӥͥ�������4 3/4�����x6 1/2������ˤ��礭����120mmx165mm�ǡ��ե���ॵ������24mmx36mm�ʤΤǰ������Ф���Ψ����4.6�ܤˤʤ�ޤ���
- �ͤδ�Ϥ��褽0.1mm��ʬ��ǽ������ޤ����顢����ӥͥ������˰�����Ф����̿��ϡ�0.1/4.6 = 0.022mm���٤ޤǤ����Ȥ���ǧ������ޤ���
- ���Τ褦����ͳ�����ε��ƺ���ߤ������ƥ���߷��ΰ����ǤȤʤ�ޤ���
- �ޤ������ƺ���ߤϡ���̳����١ʥե��������ι礦�ϰϡˤ����ݤ�����Ȥ�ʤäƤ��ޤ���
- CCD�����ʤɤθ��λ����ǻҤǤϡ����ƺ���ߤȤ�������Ϥ���ΤǤ��礦����
- CCD������߷ס���¤�Ԥϡ�����Υ����ϡ�����Ǥ��������������Υ��åפ���ɬ�פ����ꡢ�ޤ����������Ϥξ��ʤ����������åפ��ꤿ���Ȥ�����⤢�ꡢ����˱����륵�֥ߥ��������Υ��ƥåѵ��ѤǾ����ʲ��Ǥ�CCD��¤����ǽ�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����ʻ����ǻҤϡ��������ä�ƻ륫����ѡ����֤��Ȥ߹��ॻ�����פ��顢1/2�����→1/3�����→1/4�����→1/7������������Ȥ������ˤɤ�ɤ����ʤäƤ��������ˤ���ޤ���
- �����ȼ������ǥ�������9umx9um����4ummx4um���٤ޤǾ������ʤä���Ƥ��ޤ���
- ���ä�CCD�˻Ȥ���̿���κ���ߤ�1���Ǥ�Ǽ�����ǽ������н�ʬ�Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ��
- �ڥ��ޡ��ȥե��� ������β��ۡ���2020.01.09�ɵ���
- ���ޡ��ȥե���Υ����β���ˤ϶ä�����ޤ���
- iPhone�Ǥϡ�5.7 mm x 4.3 mm��1/2.5���ˤ����̾ȼͷ�CMOS���Ȥ��Ƥ��ޤ���
 �����ǻҤ��礭�������1200�����ǡ�12M�ˤμ����������֤���Ƥ��ޤ���
�����ǻҤ��礭�������1200�����ǡ�12M�ˤμ����������֤���Ƥ��ޤ���- iPhone�λ��ͤˤ�CMOS�����ǻҤξܤ����ǡ��������Ҥ���Ƥ��餺��12M�ԥ�����Ȥ���ɽ������Ƥ��ޤ���
- ���iPhone 6s�ǻ��Ƥ��������ξ����ȡ�
- ��3024���� x ��4032����
- ��������= 12,192,768���ǡ�12.2M���ǡ�
- �ȤʤäƤ��ޤ���
- ���ξ���1���Ǥ��礭���Ф���ȡ�
- 5.7mm / 4032���� = 1.414 um /����
- �Ȥʤ�ޤ���
- 1.414�ޥ�������ȥ�Υԥå��Dz��Ǥ����ꤵ��Ƥ��ޤ���
- ����1���Ǥ��ε��ƺ���ߤˤ��褦�Ȥ���ȡ������ͤϤȤƤ⾮������35mm�ե����ʥ饤�����������ѥ�ε��ƺ���ߤǤ���33 um����23�ܤ⾮�����ͤȤʤ�ޤ���
- �嵭�κ���ߤ��������������ϡ��ʲ��ι���ˤϡ�350��/mm���ᤵ��ޤ���
- ���̤μ̿����ƤǤ���ʥ�Ϻ��ޤǤ��ܤˤ����ä����Ȥ�����ޤ���
- �Ŀ���Ĺ�����ֿ��ޤ���0.4um�ζҤ�����Τǡ������������Ǥ��礭�ʥܥ��̤��θ���ʤ��ƤϤʤ�ޤ���
- 1���Ǥ˼��ޤ��������ǽ����ĥ�����ޡ��ȥե�������夵��Ƥ��뤫�ϵ���λĤ��Ǥ���
- ��ˤ����̤�ʤ�ʪ������Ĥ���ޤ���
- ����ϸ�������������ݤǡ����Υܥ��Ȥʤ��ΤǤ���
- �ʱ����ȡˡ����ȸ��ε�Ͽ - ���� ���ʬ��ǽ���ȡ���
- �ܥ��̤ϡ�������Ĺ��λ�ˤȥ�θ������F�ʥ�С��ˤ��ѡ� = 2.4λF�ˤǷ�ޤꡢ�����̰ʲ��ξ��������Ȥ��ƤϽ����Ǥ��ʤ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ܥ��ζ��ϡ�����ޤ˼������褦�ʻ��ʤ�ζ���ʬ�ۤȤʤ�ޤ���
- �Ф���Ĺλ = 555nm��������F = 2.2�Υ�ϡ�2.9um�����ޤˤ��ܥ��̤Ȥʤꤽ��ʲ������ˤϤʤ�ޤ���
- ������ͳ���顢���ظ������Ǥϸ�����Ĺ�ʲ���ʬ��ǽ����������ʼºݤˤ���Ĺ��0.7�����١ˡ�������Ψ��1000�ܤ��³��Ȥ���Ƥ��ޤ���
- �ޤ��̤���Ȥ��ơ�ȾƳ���ǻҤ�������դǤϻ��Ѥ��������糰����λ = 157nm��F2�졼���ˤ��Ѥ�����̩������θ�����F = 0.667��=��N.A.0.75�ˤ��Ѥ��ơ�0.25um�Υ��ݥåȷ¤��äƤ��ޤ���
- CD��DVD��Blu-ray Disc�Ǥϡ��ǥ����������ĥԥåȤ������뤿��ˡ�CD�Ǥ�λ = 780nm���ֳ��졼����N.A.0.45�ʳ����洹��F=1.1�ˤν������Ȥä�1.5um�Υ��ݥåȤ��ꡢDVD�Ǥ�λ = 650nm�Υ졼����N.A.0.6��F=0.83�ˤΥ��0.96um�Υ��ݥåȤ��ꡢBD�Ǥ�λ = 405nm�Υ졼����N.A.0.85��F=0.59�ˤΥ��0.47um�Υ��ݥåȤ��äƤ��ޤ�������Disc-CD/DVD/Blu-ray�ΤޤȤ���������
- �äޡ��ȥե���Υ�������ᤷ�ޤ��ȡ�iPhone6s�Υ��f = 4.2mm��������F2.2�ǡ���ˤ�Ҥ٤��褦�˰����˽��ޤ륹�ݥåȷ¤�����Ū��2.9 um�Ȥʤ�2����ʬ���礭���Ȥʤ�ޤ���
- ������������Ͽ��������θ�����ե��������Τ��ä������濴�������Ǥ��ꡢ�ʤ����IJ����������Ϥ���˰���������������Ȥʤ�ޤ���
- ���ޥۤΥ��φ6mm���٤��礭����5�����٤Υ������Ȥǹ�������Ƥ��ޤ���
- ����ʤ˾�������ǡ��ɤΤ褦�ˤ����餳������ι���������������Τ��ȤƤ��ԻĤǤ���
- �ޤ������ʤ�Ȳ��ޤΤ���˥ܥ��̤������Τǡ����ޥۤΥ����Υ�ϤۤȤ�ɳ����ΤޤޤǤ���
- ���̤Υ����Τ褦�˥�ιʤ굡�����ʤ��ΤǤ������ƤϤ��٤ƥ���������ʤ����F2.2�ǹԤ��Ƥ��ޤ���
- ���̤ϡ�Ϫ�����֤ȥ����δ��٤���Ĥ�Ĵ�����Ƥ��ޤ���
- �ʰ���Ū�ˤϡ���ʤꡢϪ�����֡������ǻҴ��١�ND�ե��륿�Ǹ���Ĵ���Ԥ��ޤ�����
- ������ˤ��Ƥ⡢�����ǻҤ�1���ǤΥ������ϥ�β����Ϥ�Ϥ뤫�˱ۤ����ΰ�Τ�ΤǤ��ꡢ����ˤ�ؤ�餺�����ʲ��������Ƥ���Τϡ�ñ������Ȼ����ǻҤ���ǽ�˲ä��Ʋ������夵���륰��ե��å�����ν������ˤ�ƹ�̯�˺��Ѥ��Ƥ����Ƚ�Ǥ��ƺ����٤��ʤ��Ȼפ��ޤ���
- �ȤϤ��äƤ�iPhone�β����ϤȤƤ����Ǥ����ΤǤ��ꥳ��ѥ��ȥǥ������ο�魯��ۤɤδ��١�������Ȥ�����������Ƥ���ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ���
- ��������������ȤȤ����¬�Ѥβ����ġ���Ȥ��ƤϿ��Ťˤ������������ƻȤäƤ���ɬ�פ�����ȹͤ��ޤ���
- ���μ̿��ϡ���������㡼�Ȥ�Ȥä�iPhone6s�ǻ��Ƥ��������Ǥ���
- �ʥ��ꥸ�ʥ�������̾�ɽ�����Ƥ��ޤ����ޤ������Ŀ��Υ���åɤϲ������եȤǽŤ�碌�Ƥ��ꡢ���졼�����Υҥ��ȥ����ϲ����������եȤǺ�äƤ��ޤ�����
- �פ���¾�������Ĥߤ����ʤ��ä��Ƥ��ޤ���
- f4.2mm�Υ�ϡ�Ĺ�������λ���Ѥ�68.3°�Ǥꡢ35mm�ե륵������f=26.5mm���������빭�ѥ�Ǥ���
- ���μ̿��νž����줿���ĥ���åɤ��黣�Ƥ��줿�о�ʪ�Υ��㡼�Ȥ�ȤۤȤ���Ĥߤ��ʤ����Ȥ��狼��ޤ���
- �ʻ��Ƥϼ�����ǹԤä����ᥫ���˼㴳���ݤ줬�ФƤ��ޤ������ä��ꤷ�����Ƥˤϥ��ޥۤä����ݻ��Ǥ���ե��������ɬ�פǤ���ȴ����ޤ�����


- �ޤ�����β����ϥ��㡼�Ȥϥ�������㡼�ȡ����ͷ����ˤ�ǻ�٥ץ��ե����������Τǡ����ǻ�٤�4�ԥ����롢2�ԥ�����ñ�̡�1.414 um x 2 = 2.8 um�ˤDz������Ƥ���Τ��狼��ޤ�����ʬ����ľ�����̤Ǥ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���f=4.2mm��F2.2��θ³��Ȥ��������ͤǤ���
- ��
- �ڥ��ޡ��ȥե��� ���λ����ǻҡۡ���2020.01.09�ɵ���
- ���οޤϡ����ˡ���2018ǯ9��˳�ȯ�����ޡ��ȥե����Ѥ�1/2��48M���ǡ�8000���� x 6000���ǡˤλ����ǻҤǤ���
- 1����0.8um�Ȥ����������Ǥ����ʸ����ֿ�����Ĺ��0.8um�Ǥ�����
- ���ˡ��ˤ��ȡ������ǻҤ�0.8umx0.8um��1����ʬ��2 x2 ���ǽ����1�֥��å��Ȥ���1�֥��å����RGB�Υե��륿�����碌�Ƥޤ���
- ���줫������줿�������顢���������ˤ�ä�1�֥��å���ʬ�ƹ��4�ܤ�8000��6000���ǡ�4800�����ǡˤβ����ˤ��Ƥ��ޤ���
- IM586CMOS���λ����ǻҤϡ�Xiaomi��ASUS�˺��Ѥ���Ƥ��뤽���Ǥ���
 ��
��
- ���ޥۤΥ�ϡ�1����ñ�̤�ʬ��Ǥ�����������ꤳ�ळ�Ȥ�����Ū���Բ�ǽ�ʤΤǡ�2��2 =4����ʬ��ʤ�Ȥ�����Ȥ��Ƽ����ߡ���������������4�ܤβ������äƤ��뤳�ȤʤΤ������ޤ�����
- 1.6um x 1.6um��4����ʬ�Ǥ�����ǽ�������Τ����ȹͤ��Ƥ��ޤ���
- ���äơ����Υǡ���������������Ƥ��줤�ʲ����������Ǥ���Τ�������Ǥ��ޤ���
- ��
- ����������Ϥο���Ūɽ������2006.01.07�ɵ���
- ��ǻȤ��Ƥ��������ɽ���ϡ���ñ����������ȡ������̤�1mm�ζҤ˲��Ф�����γʻҤ��֤��Ȥ��Ǥ��뤫�Ȥ�������ɽ�����ơ�20 lp/mm��lines pair /mm�ˤȤ���ɽ����ˡ��Ȥ�ޤ���
 ���ޤˤ��γ�ǰ���ޤ���
���ޤˤ��γ�ǰ���ޤ���- 20 lp/mm�Ȥ���ɽ���ϡ�1mm������20�Ф�����γʻҤ�����̤˷�Ф��뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ�����ΤǤ���
- ���θ������ϡ���䴶���ե����Ǥ���ǽ��ɽ���Ȥ��ˤ褯�Ȥ�����ɽ���Ǥ���
- CCD�����ξ�硢1���Ǥ�4um�Ǥ��ä��Ȥ���ȡ�8um�����1�ФγʻҤ����������ǽ����äƤ���Τǡ�������������ϡ�125 lp/mm��ɬ�פǤ���
- �����ͤϡ�Nikkor����濴��������Ǥʤ�Ȥ��Ф��륰�졼�ɤǤ���²��ʥ�Ǥ϶ˤ�Ƹ������ͤǤ���
- �ºݤθ��λ����ǻҤˤϡ��ǻҤ����̤˥����ѥ��ե��륿�ȸƤָ��إ��饹���Ϥ��դ����Ƥ��Ʋ��Ǥȴ��Ĥ�����ȿ��ι⤤����ϥ��åȤ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����ѥ��ե��륿������ʤ��ȡ��ͥ������μ����ͤΤ褦�ʼ��ȿ��ι⤤ʪ�ΤǤϻ����̤Ǵ��Ĥ����ƥ⥢��ʤ�ȯ�������Ƥ��ޤ��ΤǤ���
- ������뤿���2���ǰ���ξ��������ʤ��褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ���δ������餹��ȡ�1����4um�λ����ǻҤǤ�63 lp/mm�β����Ϥ���ĥ�ǽ�ʬ�Ȥʤ�ޤ���
- ������������������Ȥ��äơ������ǻҤβ������٤β����Ϥ���ĥ�ǻ����ǻ����٤β����٤���¸�Ǥ�������������뤫�Ȥ����Ȥ����ǤϤʤ���Ʊ�����٤���ǽ�Τ�Τ�����Ȥ߹�蘆�����������٤�Ⱦʬ������Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���λ��¤ϡ��ƹ��ʪ�����ؼԤǼ̿���¬����ʹҶ�¬�̥����ˤγ�ȯ�˽�������Amrom H. Katz��1915-1997�ˤ�1948ǯ�˽�ɽ�����Τ��ǽ�ǡ����θ夤�������ʸ���Ԥ��¸���ԤäƼ¸�����Ƴ���Ф��Ƥ��ޤ���
- Katz��ˡ§�ˤ��С�100 lp/mm����ǽ����ĥ��100 lp/mm����ǽ����ĥե�����Ȥ��ȡ���������ϤϤ���Ⱦʬ��50 lp/mm�ˤʤꡢ�ե���ब300lp/mm���٤ι�����٤�ͭ�����ΤǤ���С���������٤ϰ������ǤǤ����˼����Ȥ������Ȥ���äƤ��ޤ���
- ��������ǻҥ����ȥ�����ƤϤ��ȡ�4um�β��Ǥ���Ļ����ǻҤ�63 lp/mm�Υ��Ȥ��ȡ�Ⱦʬ�β����ϡ�31 lp/mm���٤ˤʤäƤ��ޤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ���äơ�������٤ϸ����ǻҤβ��ǰʾ�β����٤�˾�ޤ�ޤ���
- ����ե�����Ѥ�Nikkor��ϡ�24mmx36mm�Υ��������������ݤ��뤿���φ44mm���礭�ʥ���������������äƤ��ޤ���
- ���Υ��1/4��������������ǻҡ��г���φ4.5mm�ˤ˻Ȥ��Ȥ���ȡ���������������1/10�����ȤäƤ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ������¬�δ������������Ϥ���硢����϶ˤ�ƽ��פʰ�̣������ޤ���
- ���������վ��Ѥδ����ʱDz軣���Ѥδ����ˤ���Ѥ���硢�����ǽ������Ϥ����Ƿ���Τ������Ȥϸ����ޤ���
- ��ư�֤���ǽ��ǹ�®�٤Ƿ���褦�ʤ�ΤǤ���
- �վ��Ѥδ��������ɹ��ʥ����ǽ��Ҥ٤��硢�������������Ϥ��ɹ��ʲ����٤���������ϰϤ�ǻ�٤��Ϥäơ��㤤����ȥ饹�ȤǤ���ɹ��ʲ����Ϥ����ꡢ���顼�Х���ɤ��ƥܥ�̣���ɤ����Ȥ����ޤ���
- �����̤˴ؤ��ơ��ե�����CCD����ɽ�������λ����ǻҤǤϵ�Ͽ�λ������礭�ʰ㤤������ޤ���
- ���λ����ǻҤϡ����ǤȤ�����ǰ�������ˤ��ä����ϥ⥶�������˹�������ޤ���
- ����ե����϶��γ�Ҥ�����������ߤ��Ƥ��ơ����Ǥ���������褦�ʥ���������ˤιͤ�������ޤ���
- �⥢���Фޤ��Ĥޤꡢ�����̤ˤ�����ξ�Ԥΰ㤤�����Υܥ�̣�ΰ㤤�ȤʤäƸ���ޤ���
- ����������Υ�����ɤ��������٤ˤ�㤤���Фޤ���
- ���λ����ǻҤϡ��٤�������Ⱦ����ʾ����Ѳ������ե�������Ǥ�Ϣ³���Ѳ����ޤ���
- ���äƻ����ǻҤǤϥܥ�̣�ϳ��ʾ��˸��졢�Ǿ�����ߤ⥻�륵�����Ȥʤ�ޤ���
- �������Ƥߤ�ȡ����λ����ǻҤǤϥ�λ��ĥܥ�̣��ɤΤ褦�˽Ф������礭�ʥơ��ޤȤʤ�ޤ������ɤ�����������뤫�ϻ����ǻҤβ��ǥ������˷�ޤäƤ��ޤ���
- �����������ɾ���ȥ�����ɾ���ϡ��ǽ�Ū�ˤϰ�����Ф��줿������վԤ��ܤǸ���Ƚ�Ǥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ������ϡ����������ʵ�Υ�ˤ���ʪ�Τ����̤��ƻ����̤������Ф��ޤ����顢�������ֶ�˵�Ǥθ��ν��ޤ��礬�ȤƤⵤ�ˤʤ�ޤ���
- ����������������Ĺǯ�ηи��ˤ�äƾ�˽Ҥ٤����̼����������������Ȥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
����
- ��
- �����������ޤ��������
- ��Ǽ�������ˤ�뽸����«�ޤϡ����ʿ�Ԥ����ͤ��������ɤΤ褦�ʵ��פǾ������̲᤹��Τ���ɽ������ΤǤ���
- ��Υ�ξ�硢����濴���ȼ��������̤���ʹ⤵���ֹ��0��1��2��10�ˤϺǤ���֤˽��ޤꡢ7�ΰ��֤ǺǤ���ʿ�Ը������ޤ�褦���߷פ���Ƥ��ޤ���
- ���ξ����ΰ��֤ϡ�0.125mm�δ֤Ǥ��ꡢ����Υ�줿���֤Ǿ������֤Τϡ���7�פι⤵��������Ǹ�����F2.0�θ������Ǥ������˾�������Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���Υ�ϡ������ξ�̥�ǤϤʤ����ʤ������ǡ�ξ�̥�ȱ�����Ȥ߹�碌��Ž���碌��ˤ���������줿������Ǥ���
- ��οޤǼ�����Ƥ���Ž���碌��ˤ�������Υܥ����Ͼ����ΰ��֤ˤ�ä��Ѥ�ꡢ��d�פΰ��֤����֤��ä���Ȥ��������Ȥʤ�ޤ���
- ��οޤǸ���¤ꡢ���ʤä�����ʿ�Ը��������˽��ޤ��ٹ礤���⤯���ʤ���ͤ�F2�������뤤��Ǥ��礭��������ä��Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �ԥ�Ȥ��礦�ȸ����Τϡ���d�פΰ��֤����ǤϤʤ��������줿�ϰϤΥܥ�������äƤ�����ɤ����ȤˤʤäƤ��ޤ���
- ��οޤǤϡ���c�ס���e�פޤǤ�������ܥ��Ȥ���ʤ�С��������ƺ���ߤȸƤ֤��Ȥˤ��Ƥ��ޤ���
- ���γ���Ψ�ʤɥ�λ�����Ū�ˤ�äƵ��ƺ���ߤ��ͤ��Ѥ�äƤ���Τ���˽Ҥ٤��̤�Ǥ���
- �ܥ��ʺ���ߡˤ������̰��֤�������ϤäƵ�������ͤ�Ȥ�ȸ������Ȥϡ��������ܥ��ξ������֤��ϰϤǤ�ԥ�Ȥ���äƤ���Ȥ���Ƚ�Ǥˤ�ʤ�ޤ���
- �����������١�Depth of Focus�ˤȸ����ޤ���
- �����ȿ�Фˡ���Ϻǽ�˽Ҥ٤��褦��ʪ�Τΰ��֤ˤ�ä����ΤǤ�����֤����夷�ޤ���
- ����Τ�����˰�ư���Ƥ��������������äƤ���Хԥ�Ȥ���äƤ���Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ����ΤΥե��������ι礦���֤�������̳����١ʤҤ��㤫������ɡ�Depth of Field��ʪ�ΤΥԥ�Ȥι礦�ϰϡˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ��
 ���οޤϡ�Ž���碌���Ȥä����̼��������δ���Ū�ʹͤ������Ƥ��ޤ���
���οޤϡ�Ž���碌���Ȥä����̼��������δ���Ū�ʹͤ������Ƥ��ޤ���
- �̥�Ǥϡ��⤤���֤�����������϶ἴ������������˽��ޤ�ޤ���
- ����ǤϹ⤤�������϶ἴ���������˶ᤤ���֤���������Ф��褦�˶��ޤ��ޤ���
- �̥�ȱ���Ǥϼ����������оΤˤʤ�Τǡ�ξ�Ԥ��Ȥ߹�碌��Ž���碌����Ѥ����ξ�Ԥ˸����ʵ��̼������껦������ɹ����������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �̥�ȱ���ˤɤ줯�餤�ξ�����Υ�Τ�Τ�Ȥ����ϸ��������ˤ�äƹԤ��ޤ���������Ū�ˤ��̥�ξ�����Υ����Ĺ��������Υ����ı����Ȥä�������Ԥ��ޤ���
- .
- ���οޤβ��˼�������c�ˤ���ɽŪ�����������ǡ�������70%�⤵���֤�������Ѷ����ˤʤäƤ��ޤ���
- �����ͤ��˾��������뤫������߷Ԥ��Ӥθ�����ˤʤ�ޤ���
- ��a�ˤζ������̥�˸�����ŵ��Ū�ʤ�Τ���������Undear Correct�ˤζ����Ǥ���
- ��b�ˤϵդ˲���������Over Correct�ˤǤ���
- ��d�ˤ�����������2�ʤΥ����֤���äƤ��ޤ���
- ����¥���߷פ����硢��c�ˤ������ˤ�����Ѷ������Ф�ĥ�ꤹ����ΤǤ��Τ褦���������������Ѥ���ޤ���
- ��
- �����ʤ���Ѥ�������������ʤ����
- �����ǻ��Ƥ���ݤˡ������ʤ��ȤäƤ����ιʤ�Ϥʤ������ˤ���ΤǤ��礦��
- ��γ��ˤ��äƤ��ɤ��ΤǤϤʤ���������ʤ��Ȥ�ͤ��Ƥߤ��ꤷ�ޤ���
- ������ʪ���λ��ͽ�ˡ����Ⱦʬ�˳��Ƥ��ޤä�Ⱦ����Υ����������ȷ�֤����������Ȥ������꤬����ޤ�����
- �����Ϥ����������ǡ��ɤ�ʷ����ˤ������̤ǤǤ�����ʬ������Х�Ȥ��Ƥ�äѤ˵�ǽ���ޤ���
- ���ʪ�Τ�Ǥ�դΰ����������;��������줿��������ƺƤӰ����˽�����ΤǤ����顢��η������ɤ��������ͤ����̤����̤Ǿ����˸������ޤ�������Ǥ���ΤǤ���
- ʪ�Τ������ͤ��줿���ϡ���η����˴ؤ�餺����̤ζ�Ψ�˽��äƸ�������˽���ޤ���
- ������̤ϥ���̤γ������Ѥ˰�¸���ޤ���
- ���������ʤ�η����ˤ�äƤϥܥ��η����ʤ�����˺�������Ƥ��ޤ��ΤǤǤ�������߷��˶ᤤ�ʤ꤬���ޤ�ޤ���
- ���ѷ��ιʤ�ϻ��ѷ��Υܥ������ˤʤꡢ�濴������ʤ�������̤ϼ���������ʤ�˹ʤ�Ǥϥɡ��ʥåľ��Υܥ��ˤʤ�ޤ���
- ���ơ��������¤��뤿��˥�˸��Υ��ȥåѡ��ʹʤ�ˤ�����Ƥߤ뤳�Ȥˤ��ޤ���
- ���ľ���ˡ��߷������ȥåѡ��ͳѷ��Υ��ȥåѡ����ѷ��Υ��ȥåѡ��ʱ߷��Υ��ȥåѡ��ɤΤ褦�ʷ������줿�Ȥ��Ƥ⤽��Ϥ���ǵ�ǽ���ޤ���
- ���Υ��ȥåѤ�����˥�����ä��Ƥ��ä���ɤ��ʤ�Ǥ��礦�������餯���ȥåѤγ���Ǹ����פ��ƻ��������ΤˤʤäƤ��ޤ��Ǥ��礦��
- ����Ϥ��礦�ɡ��ɥ��θ��꤫�������������������Τ˻��Ƥ��ơ��ܤ�Ǥ����������˶�Ť��ʤ�������ͻҤ������ʤ��Τ˻��Ƥ��ޤ���
- ��ʤ�ϤǤ��������˶�Ť������֤��Ƥ����ʤ��ȡ��ʤ�γ���������礱������ʥ���� = Vignetting�ˤ������ޤ���
- �ʤ�ΰ��֤ϡ����٤Ƹ�������֤��֤��ʤ�������Υ���줬�����뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ��
- ��
- �����ƥ쥻��ȥ�å���Telecentric������
 �ʤ�ΰ��֤��������֤����֤�����Τ��ƥ쥻��ȥ�å����طϤδ��ܤǤ���
�ʤ�ΰ��֤��������֤����֤�����Τ��ƥ쥻��ȥ�å����طϤδ��ܤǤ���
- ���ޤ��ƥ쥻��ȥ�å����طϤγ�ǰ�ޤǤ���
- ����Ū�ʹʤ�ϥ�ζ�˵�����֤��졢�ʤ�θ��¤��Ѳ������뤳�Ȥˤ��Ʃ�᤹����̤�Ĵ�����Ƥ��ޤ���
- ��
- ��ʤ��������Υ���֤��֤������¤������ޤ���
- ��������ȡ�¿���θ��Ϲʤ�Ǽפ��ʪ�Τ�����ʿ�Ԥ����äƾ�����Υ���̤���������ʤ��ȴ��������������뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���θ������֤Ǥ�ʪ�Τ����ʿ�Ը��������������˴ؤ��Τǡ�ʪ�Τΰ��֤����夷�Ƥ�������Ψ���Ѳ����ޤ���
- ʪ�Τε�Υ�˰�¸������Ʊ�����Ψ�ǻ��Ƥ��Ǥ��������ϡ�������¬�Ǥ�ͭ���ʤ�ΤǤ��뤿��˥ޥ���ӥ����䡢��ǽ��Ƶ������������ʤɤθ��طϤˤ������֤��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- .
- �ƥ쥻��ȥ�å����طϤξܺ٤ϡ�������ƾҲ𤷤����Ȼפ��ޤ���
- ���οޤ���¦�˹ʤ�����֤���ʪ��¦�ƥ쥻��ȥ�å����֤Ǥ����������¦������Υ�����֤�����¦�ƥ쥻��ȥ�å����֡�ξ������������ξ¦�ƥ쥻��ȥ�å����֤�����ޤ���
- ���θ��طϤϤȤƤ�̥��Ū�ʤ�ΤǤ����������Ĥ������դ��ʤ���Фʤ�ʤ���������ޤ���
- ����ϡ�
- ��
- ����1.�����طϤ��Ť���
- ����2.���ʤ�Ĵ�ᵡ����̵����Τ�¿����
- ����2.�������θ��¤Ƿ�ޤäƤ��ޤ���
- ����3.���ʤ���礭����Ŭ�������Фʤ��Ȳ��ޤˤ�������ܤ��롣
- ����5.�����Ƶ�Υ�ʺ�ư��Υ�ˤ������Ƥ����Τ�¿����
- ��
- �Ȥ��������Ǥ���
- ���طϤ��Ť��Τϡ��ƥ쥻��ȥ�å����طϤν�̿�Ǥ���
- �������֤����֤����ʤ���礭�����礭�������顢ʪ�Τ��������ͤ������ʿ�Ը������ǤϤʤ��ʤ�ޤ���
- �ʤ���¤��礭��������̾�Υ�ʤ�Τ褦�˥ԥ�Ȥι礦�ϰϤȹ��ʤ��Ȥ������ФƤ��ޤ���
- ������������Ψ���Ѥ�ä���ޤ���
- ���ΤΥƥ쥻��ȥ�å����طϤιʤ�ϤɤΤ��餤�ˤʤäƤ���ΤǤ��礦����
- ����1.�����طϤ��Ť���
- �������ʤ��Ȥ�¿���Υ��������ˤϥƥ쥻��ȥ�å�������뤵��ɽ�����ʤ���Ƥ��ޤ���
- ���ޤ������˸��줺�ˤǤ�������ʤ�ξ��������¤����֤Ȥ���ȡ�F8����F20������θ����椬�ƥ쥻��ȥ�å����طϤ������ʤȤ����Ǥ���
- ������礭�ʤ�Τˤ�������硢����礭���ʤ�ɬ��Ū�˾�����Υ��Ĺ�����Ȥ����Ȥˤʤ�ޤ�����Ť���ˤʤ�ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å����طϤι�¤�塢�ʤ���¤ϸ��ꤵ�줿��Τ�¿���褦�Ǥ���
- ��ˤϹʤ굡�����Ĥ��Ƥ��Ƹ�������Ѥ������Τ⤢��褦�Ǥ��������ߤ����뤤������ˤ������̳����٤������ʤꡢ�ƥ쥻��ȥꥷ�ƥ� = telecentricity�μ����ϰϤ������ʤ�Τǥ������θ�����ǻ��Ѥ������ƻ���Ϫ�л��֤��Ѥ���ʤ�������פ���ɬ�פ�����Ȼפ��ޤ���
- ��®�٥����Τ褦�ˡ�1/100,000�á�=10us�����٤�Ϫ�Ф��ڤ뻣�ƤǤϰŤ���λ��ѤϿɤ���Τ�����ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å����طϤǤϡ�ʪ�Τ������ͤ������Τ���ʿ�Ը��������������˴�Ϳ����Τǥ���礭�������ʤ������Ρʻ����ϰϤΡ��礭���Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- �Ǥ����黣�Ƥ������ϰϤ����θ��¤��ä����ɬ��ɬ�פˤʤ�ޤ���
- �ޤ����ޤ�ߤƤ�狼��褦�˥�ξ������֤˹ʤ���ޤ����顢ʪ�Τ�ɬ��̵�±�ǤϤʤ���˶ᤤ���֤��֤��ʤ���Фʤ�ޤ���
- ʪ�Τ��ˤ���Ф���ۤɡ����Ϲʤ�ζ�˵�˴�äƤ��ޤ���
- �����ʤ�ΰ��֡�-������Ʒ���ͽ�Ʒ ��Entrance Pupil��Exit Pupil��
- ���������д����˾������ܤ����Ƥ���������ȡ����֤ˤ�ä��ܤλ������Τ��������餺���դ��Ť��ʤäƤ��뤳�Ȥ�����ޤ���
- ����ϥ�θ��¤���ФƤ�������ͤ�Ʒ��꾮������Ʒ���äѤ��˸�������ʤ�����Ǥ���
- �������ȥ������Ȥ߹�碌�����ƤǤ⡢���̤μ��դ��ݤ������ƿ����椷�������������ʤ����Ȥ�����ޤ���������ϸ���������θ��������λ����̼������˽�ʬ�˹Ԥ��Ϥ�ʤ�����Ǥ���
- �����������ݤϡ�������= Vignetting�ˤȤ������ݤǥ�θ��¤α郎������������⤷�Ƥ��뤿��˵����ޤ���
- ��ʤ�ϡ���θ��¤����¤��Ƥ����Τǹʤ�ˤ�äƥ�θ��¤��Ѥ��ޤ���
- ���¤Τߤ������礭���ϡ�����̲ᤷ���������ޤ��뤿��˼ºݤιʤ���礭���Ȥϰ�äƸ����ޤ���
- Ʒ���ܴ����˶�Ť��ʤ��Ƚ�ʬ�ʻ������ݤǤ��ʤ��Τϡ��ܴ�����Ф����«�¤�Ʒ�η¤��⾮��������Ǥ���
- ���뤤�д����Ʒ�η¤˽�ʬ�˸�������褦�˸��¤��礭�ʸ��طϤ���Ѥ��Ƥ���ΤǤ���
- �����ۤɡ����طϤ���ФƤ�����ϥ�ʤ�ǹʤ��ƽФƤ��뤱��ɡ��ºݤιʤ�ȥ���̤��Ƹ�����ʤ���礭�����㤦�ȸ����ޤ�����
- �ºݤιʤ���礭�����ʤ��Aperture Stop�ˤȸ���������̤��Ƹ�����ʤ�����ʤ��Field Stop�ˤȸ��äƤ��ޤ���
- ξ�Ԥδط��ˤϲ��˼����褦�ʴط�������ޤ���
- ��
- ��
- ��οޤ˼������褦�ˡ��̾�Υ������ʣ���Υ������Ȥ��鹽������Ƥ��ƹʤ�ϥ����ˤ���ޤ���
- ��οޤǹ���������A��B����ʤ�Ǥ���
- ʪ�Τ������ͤ�������ϡ�����A��B�ιʤ�ˤ��������¤�����������櫓�Ǥ����������ˡ����ιʤ�����ˤ�����L1�ζ��ޤ�����ޤ���
- ʪ��PQ����Ф����ϥ�Ƕ��ޤ����AB�����¤������L2��˸�������L2��Ǻ��ٶ��ޤ������P'Q'�������Ӥޤ���
- ���λ�������¦�Ǥ�A'B'�ˤ�������ʤ꤬����褦�˸������ͽ�¦�Ǥ�A''B''�˹ʤ꤬����褦�˸����ޤ���
- ʪ��¦�����������ȳ����ʤ�AB�Ϥ�������A'B'�ˤ���褦�˸�����Τǡ�A'B'������Ʒ��Entrance Pupil�ˤȸƤӡ��ͽ�¦��A''B''��ͽ�Ʒ��Exit Pupil�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ����Ʒ�ȼͽ�Ʒ���礭������֤ϥ�ˤ�äƤޤ��ޤ��Ǥ����ͤ��Τꤿ���Ȥ��ˤϥ��������䤤��碌�뤷������ޤ���
- ��ñ���Τꤿ���ΤǤ���С�������뤤��ˤ������ƥ��Ʃ�ᤷ�Ƥ������Ʒ���礭�����ܻ뤹�뤫�����Ʒ���¤��礭����ǥ�����ǻ��äƲ�������Ʒ�¤�¬�뤳�Ȥ��ͤ����ޤ���
- ���͡��ͽ�Ʒ�Ƥ�����˻Ȥ����ƥ�����ϡ��Ǥ���з�¬�ѤΥƥ쥻��ȥ�å�����ޥ��������������Ǥ���
- ��οޤ˼������褦�ˡ��̾�Υ������ʣ���Υ������Ȥ��鹽������Ƥ��ƹʤ�ϥ����ˤ���ޤ���
- ���Ʒ�ϡ��������ºݤθ����̤Ⱦ����ΰ��ִط��˱ƶ����Ƥ���Τǥ桼���������������ä����Ƥ褦�Ȥ���ݤˤ���������ǤȤʤ�ޤ���
- ������뤵�ϡ������ʤ���礭�������ǤϷ���줺������Ʒ���礭����φent�ˤȾ�����Υ��f�ˤ��桢�⤷���ϼͽ�Ʒ���礭����φexit�ˤȼͽ�Ʒ�ΰ��֤�������ޤǤε�Υ��f-χ�ˤ���ǵ�ޤ�ޤ���
-
F = f /��ent= ��f - �֡�/��exit ��������Lens - 8�� - F :���ʵա˸�����
- ��ent��������Ʒ���礭��
- f�����������Υ
- ��exit :���ͽ�Ʒ���礭��
- �֡�������Ʒ�ΰ��֤ȼͽ�Ʒ�ΰ��֤κ�
- ��ent��������Ʒ���礭��
- F :���ʵա˸�����
- ����Ʒ���ºݤιʤ��Ʊ���Ǥ���С���ιʤ�ʸ�����ˤϡ���θ��¤Ⱦ�����Υ�����Ʊ���ˤʤ�ޤ���
- �ޤ�������Ʒ�ȼͽ�Ʒ��Ʊ���Ǥ���С�χ=0 �Ȥʤ�Ʊ���ͤˤʤ�ΤǤɤ��餫���ͤ�Ȥ��и����椬��ޤ�ޤ���
- ��
- �����ʤ�ΰ��֤ˤ�������Ĥ�
- ������ϡ������Ƥ�ʣ����Υ������Ȥ��鹽������Ƥ���Τǡ�Ϫ���̤�Ĵ�᤹���ʤ��ʣ����Υ������Ȥ���������֤���Ƥ���Τ����̤Ǥ���
- ñ��ξ��ˤϹʤ�ΰ��֤ˤ�ä������Ĥߡ��ͳѤ�ʪ��î���ˤʤä���崬�����ˤʤä��ꤷ�ޤ���
- �ʤ꤬ʪ��¦�ˤ���Ȥ��뷿�ˤʤꡢ�ʤ꤬��¦�ˤ���Ȼ崬�����ˤʤ�ޤ���ʣ���Υ������Ȥǹ�������륫����ϡ�������ͳ�������ο���������֤���ξ�Ԥ��Ĥߤ�뤹��褦�����֤ȤʤäƤ��ޤ���
- �����Ĥߤ�����ޥ�����������ѥ�϶ˤ�Ƹ��ʤ˹ʤ�ΰ��֤�����߷ס���¤����Ƥ��ޤ���

- .
- �ʤ�ˤ�äƤɤ����������Ĥ�ݤ������뤫�Ȥ����ȡ������ϡ�����̤������η����˱����ơ�3������㤷�ơ�����Ψ���Ѥ�뤳�Ȥ˵������Ƥ��ޤ���
- ����濴��������Ψ�ȼ��դǤ�����Ψ���Ѥ�뤿��ˡ���Ψ���Ѳ��������ĤߤȤ��Ƹ���뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���äơ��濴������������˻��ޤ�����Ψ��Ʊ���Ǥ���ʤ顢�ĤߤΤʤ�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ������������Ψ���濴������Ψ����礭�����ϡ��崬�������Ķʼ����Ȥʤꡢ����������Ψ���������ʤ��î�����Ķʼ����Ȥʤ�ޤ���
- ���μ����ϡ��ʤ�ΰ��֤ˤ�äƸ�����ΤǤ��ꡢ��ιʤ���礭���ˤ�äƽ���Ǥ��ޤ���
- ¾�Υ��������ιʤ���礭���ˤ�äƲ��������Τ��Ф����Ķʼ����Ϲʤ���礭���˰�¸���ޤ���
- �ʤ�ΰ��֤ˤ�äƺ�������ޤ���
- �Ķʼ������ٹ礤�ϡ�
- �Ķʡ�%�� = 100 x ��y' - Y'�� / Y' ��������Lens - 9��
- y' �� �Ķʤ������ΰ���
- Y' :�����ۤ����ΰ���
- �Ǽ�����ޤ���
- �����Τ��Ȥʤ������濴�����������������Ķʤ��ٹ礤���礭���ʤ�ޤ���
- �ޤ����ѥ�ۤ�����Ķʤ�����˾���ۤ������Ķʤ��礭���ʤ�ޤ���
- �̾�ϡ�1-2%�ޤǤ�����ǵ��ƤǤ����ͤǤ���������ʾ���������ĤߤȤ���ǧ������ޤ���
- �桹���̾�ȤäƤ���ɸ���ǤϤ��褽0.1%��0.3%���٤��Ķʼ�������äƤ��ޤ���
- ��
- �����ü�ʸ�����Ȥä����ƤǤιʤ�θ���
- ��ιʤ�ϡ�����Ȭ���˳Ȥ��ä�ʪ�Τ���������������������Ȥ��ˡ����̤�Ĵ�᤹�뵡ǽ������ޤ���
- �����ü�ʤ�Ρ��㤨��ʿ�Ը�«������Ȥ������Ƥξ��˥�ιʤ��Ư���ΤǤ��礦����
- �����ϥΡ��Ǥ���
 �ʤ��ʪ�Τΰ����������ͤ��줿���������̤����¤��뤿��Τ�ΤǤ����顢ʪ�Τ���ȯ������������������θ������Ф��ƤϹʤ�θ��̤ϴ��ԤǤ���������줬����������������Фʤ��ʤ�ޤ���
�ʤ��ʪ�Τΰ����������ͤ��줿���������̤����¤��뤿��Τ�ΤǤ����顢ʪ�Τ���ȯ������������������θ������Ф��ƤϹʤ�θ��̤ϴ��ԤǤ���������줬����������������Фʤ��ʤ�ޤ���- ������������ϡ�������ʪ�Τ��ظ夫��Ȥ餷�����ΥХå��饤�ȸ����ˤ����Ƹ��졢�������������ξ��˸����ˤ����ޤ���
- ������Ƥ䥷��ɥ�����ջ��Ƥ�ŵ��Ū����Ǥ���
- ���������Ƥ�˾�����Ȥä����ƤǤ⸲������˾����˹ʤ������뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- �����������ƤǤϥ����˸��̤�Ĵ�᤹��ND�ʥ��̥ǥ���Neutral Density�˥ե��륿��������ޤ���
- ���οޤ����ä����տ������Ƥߤ�ȡ����ΰ��֡ʻ����̡ˤˤ��������������뤳�Ȥ˵��Ť��ޤ���
- ��Ĥϡ�ʪ�Τˤ��ʪ�����Ǥ��ꡢ�⤦��Ĥ�ʪ�Τ��ظ�ˤ�������ˤ�����Ǥ���
- ���ʪ�����ΤߤǤʤ��������⻣���̤���Ƥ���Ƥ���ΤǤ���
- ����������̤�ʪ�����Υե����������礦���֤��֤���Ƥ��ޤ����顢�������ϥե��������Υܥ������֤ˤʤäƤ��ޤ���
- �������ʤɤθ����ǤϤ������������ΰ��֤�ʪ�Τΰ��֤���̩�˷����Ƹ�Ψ�Τ褤�����뤿�ᡢ���Ҥ٤���������ʪ�����ιͤ����ϤȤƤ�����ʤ�Τȸ����ޤ���
- �ޤ�������ɥ�����դ䥷�����ˡ�ˤ����Ƥ⤳�ιͤ���������ǡ����������θ������ʤ��Ȼ����̤ǽ�ʬ�ʻ�������ʤ��ʤ�ޤ���
- �������θ����ˤĤ��ƤϹ�����ƾҲ𤷤����Ȼפ��ޤ���
- ��
- ��
- ����������Υ�ȸ��¡�Focal Length and Optical Diameter��
- ��
- ��ϡ�ʿ�Ը�«������˽���ޤ���
- �����˽��ޤ�Ȥ���������ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �����ϵ��̥�ζ�Ψ���������ۤɡ����ʤ��������ۤɶ����Ϥ������Τǥ���濴��������ޤǤε�Υ�ʾ�����Υ�ˤ�û���ʤ�ޤ���
- ������Υ�ϥ�ˤȤä��������ǽ���ǤǤ���
- �ޤ�������������θ��¤���פ����ǤǤ���
- ���¤��礭���ۤɤ�������θ������ޤ�ޤ���
- ��������Ʊ�����¤ʤ�о�����Υ��û���ʶ����Ϥι⤤�˥��������������θ����ǽ�Ϥ�����ޤ���
- ��θ��¡�D�ˤȥ�ξ�����Υ��f�ˤ����������Aperture Ratio�ˤȸ����ޤ���
- ������ϡ�1:1.4�Ȥ����褦��1���ƤȤ��������������¤��Ф��ƾ�����Υ���ɤ����Ĺ������ɽ���ޤ���
- ������ǤϿ��ͤ�üŪ��ɽ���ʤ��ΤǸ�����εտ����ä�F�ʥ�С���F�͡ˤ�ɽ���ޤ���
- ��ϡ�������Ȥ����������ͤȰ��˻ȤäƤ��ޤ�������̩�ˤϸ������1���Ƥ�ɽ�������ͤȤ϶��̤���ޤ���
- ���ͤϵո�����ȸ����Ƥ��ޤ�����ɡ�������ˤ��Ѥ�ꤢ��ޤ���
- ��
- ����

- ��
- �������ϡ�̵�±�θ����������˽��ޤ���θ�����ʣ��͡ˤ����������Τǡ����Υ���Ƥʤɤǥ��Ȥ������ͤ��Ѥ��ޤ���
- �����ͭ���ƥʥ�С��ȸ��äơ������������̵�±�ǤΣƥʥ�С��ȶ��̤��Ƥ��ޤ���
- ͭ���ƥʥ�С��ˤĤ��Ƥϰʲ����أƥʥ�С���ͭ���ƥʥ�С����Ǿܤ�������Ƥ��ޤ���
- �������ϡ�̵�±�θ����������˽��ޤ���θ�����ʣ��͡ˤ����������Τǡ����Υ���Ƥʤɤǥ��Ȥ������ͤ��Ѥ��ޤ���
- Ʊ��F�ʥ�С��Υ�ϡ�ʪ�Τ������ͤ���������������Ω�γѤ�Ʊ���ˤʤ�Τǡ����뤵�δ��������Ʊ����ǽ�Υ�Ȥ������Ȥ��Ǥ��ޤ���
- F�ʥ�С��ϡ��ɤΤ��餤���ͤޤǤ��뤫�ȸ����ȡ�����Ū�ˤ����뤤���F1.2����F32�ޤǤǤ���
- ��ˤ��ü�ʥ��F0.95�Ȥ������뤤��⤢��ޤ�������Ƚ�����Ǥ�F128�ޤǹʤ뤳�ȤΤǤ���������ޤ���
- ������뤵�θ³��ϡ�F0.5�Ǥ���
- F0.5�Ȥ����ͤϡ���μ������狼�뤳�ȤǤ�������θ��¤�������Υ��2�ܤ��礭������Ĥ�ΤǤ���
- f50mm�Υ�Ǥ���и��¤�100mm�Ǥ��뤳�Ȥ��ޤ���
- ���¤�100mm�Ȥ������Ȥϡ�Ⱦ��50mm�Τ�äȤ�⤤���֤������ͤ������ϥ�ε��̤˱�äƶ��ޤ��Ƶ��̥��ɽ�̾�ο�����˽��ޤ��Ǥ���
- ����¤ϡ����ΤΥ�ξ��ʤ굡����Diaphragm�ˤ���¢����Ƥ���Τǡ��ʤ���ѹ����뤳�Ȥˤ����¤��Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ʤ굡���ΤĤ�����Ǥϡ�������γ�����ͤ�ɽ�����Ȥ�¿����√2���������ǿ��Ͳ�����Ƥ��ޤ���
- ���äƥ�ιʤ�ϡ��Ǿ��ͤ�F0.5�ǡ������ͤ���√2���������Ǥ���
- 0.7��1.0��1.4��2.0��2.8��4.0��5.6��8��11��16������
- �Ȥ����ͤ���Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ������֤ιʤ��ɽ�����ϡ�F2.0 1/2���Ȥ�f2.0 1/3�Ȥ����褦��ʬ���ͤǸ���ɽ���Ƥޤ���
- �Ƕ�Ͼ���ñ��ɽ����Ȥä�F3.2�Ȥ����褦�ʸ������⤷�ޤ������������ޥ˥奢��ʼ�ư�ˤ����ꤹ��Ȥ��Ϲʤ��ͤʤ���Ԥ��Τǡ�F2.0��F2.8����֤�ʬ����F2.0 1/2 �Ȥ�����������ľ��Ū�Ǥ狼��䤹���������Ƥ��ޤ���
��
| ��F = f / D ��������Lens - 10�� | |||||
| F������ո������F�ʥ�С���F�͡� | |||||
| f�����������Υ | |||||
| D��������� | |||||
- ��ιʤ�ϡ�����������褦�ʿ��߷���������Ū�Ǥ���
- �ʤ�ϤɤΤ褦�ʷ��Ǥ������ȵ�ǽ�Ϥ����ΤΡ��ܥ�̣�����餫�������˽Ф�ΤϿ��ߤǤ���
- �²��ʥ�Ǥ�2�繽���ιʤ��Ĥ�Ȥä��ʤ굡���Ǥ��ä��ꡢ3�繽���Ǥ��ä��ꤷ�ޤ���������ʤ�Τˤʤ�ȿͤδ�����̤Τ褦�˿��ߤ˶ᤤ�ʤ�ˤ��Ƥ��ޤ���
- 35mm����ե�����Ǥ�5���6�繽���ιʤ굡����¿������Ƚ�����˻Ȥ�������å��Ǥ�13��ι����Τ�Τ�����ޤ���
- ���̹ʤ������ϡ����⤷�������Ȥ˴�������¿����ʹ���ޤ���
- ���۸��ʤɤζ���������������ˡ����ʤäƹԤ������̹ʤ�Υե쥢�����졢��������ιʤ�ǤϹʤ�ο��������������ιʤ�ǤϤ����ܤθ���ʤ����ܤ��ˤ�����ޤ���
- ��������Υե쥢��Ф��������ˡ������ιʤ걩�����Թ礬�褤�Τ����ʼ̿��Ȥ�5���7��ιʤ걩���Τ�����Ȥ��ޤ���
- ���������̿��Ȥϡ��Ǥ�������߷��Υܥ�̣��ۤ�����Τ�13��ιʤ걩���Τ�����Ȥ��ޤ���
- �ʤ걩����¿������Թ礬�������ȸ����Ȥ����Ǥ�ʤ�����¤��ʣ���ˤʤ�Τǹʤ����Ǥ����ȹʤ�������Ĥ��礬����ޤ���
- ����ǤϤ��줤�ʥܥ�̣���Ǥʤ��Ф���Ǥʤ����Τ�Ϫ�Ф������ޤ���
- ��
- ����F�ͤ�ͳ��
- �Ȥ����ǡ���ʤ��F�͡�F.stop��F-number�ˤȤϰ��Τɤ�ʰ�̣������ΤǤ��礦����
- ��ʤ�ϡ�Iris�Ȥ�LensDiaphragm�ȸƤФ�Ƥ���Τˡ�����¾��F�ͤȤ����Ƥ�̾������Τ��ޤ���
- �¤ϡ�����Υ�ˤϺ��Τ褦�ʥ�ʤ꤬�Ĥ��Ƥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- �����ǡ����Ƥκݤ˸��̤�Ĵ�᤹�뤿��˥�����˸���Ĵ�᤹��ݷ�Ĥ��Ѱդ��Ƹ��̤�Ĵ�ᤷ�Ƥ����ΤǤ���
- ���κݤ˥�ξ�����Υ���Ф��Ʋ�ʬ��1�δݷ꤫�������f-number�ȾΤ��ơ�f/2.0�ʤ������Υ��Ⱦʬ�θ��¤δݷ���̣����f/4.0�ʤ�1/4�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ������«�ϴݷ���礭����Ϫ���̤���������İ��Ǥ��뤿��������Ǥ�����
- �㤨�С�������˲����ǻ��Ƥ����ݤˡ�3��������f=75mm�ˤ�f/4.0�ιʤ��Ĥ�Ĥ��Ƥ����Τ������������ƾ����Ť��ʤä��Τǡ�f/2.8�ιʤ��Ĥ��Ѥ��롢�Ȥ������˻ȤäƤ��ޤ�����
- ���줬�����Фơ������¢�����褦�ˤʤꡢ���̹ʤ�ˤ�äƼ�ͳ�˹ʤ���Ѥ�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ʤ������¢����ݤˡ��ʤ���ͤ��Τʤ���θ������Ǥ��Τޤ����Ѥ��줿�Ȥ����櫓�Ǥ���
- ��
- ����F���ȥåפȳ�����N.A.��Numerical Aperture��
- ������ѥ�ϡ�������Ȥ�������ʤ�ʤɤȤ����Ƥ����ǥ�����뤵�����ɽ���Ƥ��ޤ�����ñ�̥�串�����ʤɤ�N.A.�ʥ��̡������ˤȤ����������Ƥ��ޤ���
- N.A.�ʳ������ˤȤϸ��¤���Ͳ������Ƥ����Ǽ��Τ褦���������Ƥ��ޤ���
-
��N.A. = n��sinθ ��������Lens - 11�� - n�������ζ���Ψ�ʥ������Τδ֤ˤ�������
- ����������Ψ�������Ǥ���� n = 1.000�����n = 1.333
- θ����������ͤ���������ͳ��١�0 <θ <90°��
- ����������Ψ�������Ǥ���� n = 1.000�����n = 1.333
��F = 1/��2��N.A.�� ��������Lens - 12�� ���F�ͤ�N.A.�δط��� ���ȸ��ε�Ͽ�֥��ʬ��ǽ���� - n�������ζ���Ψ�ʥ������Τδ֤ˤ�������
- N.A.�ʳ������ˤȤ����ͤ����ϡ������ǽ�Ϥ�ɽ���Ȥ������Ǥϥ�ʤ��F�ʥ�С��Ȱ��Τ�Τǡ��Ȥ�������Թ�夳���2�Ĥθ������Ƥ��ޤ�����
- ����Ū�ˤϡ�N.A.�Ȥ���ɽ�����Ϥ���ˤ��äơ����������ڤ���ˤĤ�ƣƥʥ�С���Ȥ��褦�ˤʤ�ޤ�����
- N.A.����������Ū�dzؽ�Ū�Ǥ���

- N.A.�������sinθ���ͤ��Τ�ΤǤ����顢�ɤΤ��餤�γ��٤Ǹ���뤳�Ȥ��Ǥ��뤫�����ܤ���ñ�̤Ǥ���
- N.A.�ϡ�������������ǤϤʤ������ե����С���θ�����ã����ǽ�Ϥ�ɽ�����ͤȤ��Ƥ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ե����Фϡ��ե����С���������ȿ�ͤˤ�äƸ����ʤ�Τǡ����٤ζ�����θ���礭�ʡ˸�����ȿ�ͤ��˥ե����С�����ϳ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- �ե����С�����ȿ�ͤ����ϰϤǸ���ե����С��������Ƥ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- �ե����С��Ǥ���ȿ�ͤ������١�θ�ˤ� N.A.�γ�ǰ��ή�Ѥ��ƥե����С�����ǽ��ɽ�����ͤȤ��ƻȤäƤ��ޤ���
- �졼�����ʤɤ�ե����С���Ƴ�������졼���ν������N.A.�ȥե����С���N.A.����פ����Ƥ����и�Ψ�ɤ��졼������ե����С���Ƴ�����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ƥʥ�С��ϡ�������˻Ȥ����Ѹ�ǡ�Ϫ���������Τˤޤ��Ȥ��Թ礬�褫�ä��Τ�¿�Ѥ���Ƥ��ޤ�����
- ����������ե����С��ʤɤǤϡ����طϤߤ˹ʤ�Ȥ����ͤ��������ʤ��Τǣƥʥ�С������夷�ʤ��ä��ȹͤ��ޤ���
- ��
- ����N.A.�������-�����ץ�ʡ��ȡ�aplanat��
- �������θ���Ƥ��ʤ���Ǥϡ����̼����Τ���˾�����Υ�ϰ����˽��ޤ餺�������˽����ˤϺ��ޤΤ褦���̤����̤ˤʤäƥ��Τɤΰ��֤���Ǥ������Υ��ΰ��֤ˤ��ʤ��ƤϤʤ�ޤ���
- �����������������ȡ����å���ȯ���������ؾ��ˤ�����������ȸ����ޤ���
- ���ιͤ�����������ȡ�������Ϥϸ����ι⤵��D/2�ˤȾ�����Υ�ʣ�ˤ���ǵ��뤳�Ȥ��Ǥ��������椬sinθ����������ΤǤ��������N.A.�ˤ���������ΤǤ���
- �ƥʥ�С��ϡ�f/D����������Τ�sinθ�ǤϤʤ���tanθ����������ΤǤϤʤ��������Ȼפ������Ǥ���
- ��������f/D����¦���̤����̾��ˤʤäƤ���Ȥ������Ȥ�����С�sinθ���������뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ����������������ץ�ʡ��ȡ�aplanat�ˤȸ����ޤ���
- ���ץ�ʡ��ȥ��aplanatic lens�ˤϡ��̥�ȱ�����Ȥ߹�碌�뤳�Ȥˤ��ã�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���ץ�ʡ��Ȥ��������ˤĤ��Ƥϡ���μ����ΤȤ����ǿ���褦�Ȼפ��ޤ���
- N.A.�ϡ���������狼��褦����n�ʾ���ͤ������ޤ���
- �ƥʥ�С���N.A.���������1/��2�����˰ʲ��ο��ͤϼ�����ޤ���
- ���äơ��̾�δĶ��ʶ�����n=1.00�ˤǥ������Ȥ���硢0.5�ʲ��Σƥʥ�С��ϼ�����ʤ����Ȥ��狼��ޤ���
- ��
- ����F�ͤθ���ãǽ��
- ���⤷�����ͻ��ޤ���
- ��Ȥ����Τϡ�ʪ�Τθ��Τɤ�����ʲ�ʬ��1�ˤθ�����¦����ã����ΤǤ��礦��
- ���Ȥ��С����������θ���
- ���������θ��϶��֤�Ȭ�������ͤ��ޤ���
- ���������ͤ��줿���Τɤ��������Ǥ�����������������ˤĤʤ���ΤǤ��礦����
- ����������٤�ʪ�Τδ������٤ǹͤ��Ƥߤ����Ȼפ��ޤ���
- ��������Ҥ٤�ȡ�������뤵F2�Ǥ�ʪ�Τ����뤵��1/100���������뤵�ˤʤ�ޤ���
- �������äȤ����뤤��Ǥ���F0.5�Ǥϡ�ʪ�Τ�1/6.7�����뤵��������������ޤ���
- ��������Ҥ٤�ȡ�������뤵F2�Ǥ�ʪ�Τ����뤵��1/100���������뤵�ˤʤ�ޤ���
- .
- ��

- ��
- ��ޤˡ���ˤ�äƤǤ����������뤵���ϼ��ޤ��ޤ���
- ����B����ä�ʪ�Τ���Ф����ϡ���ʸ�����F�ˤ��̤��Ƥ����̤θ��ʸ�«�ˤ������̤�ã���ޤ���
- ����B��ʪ�Τϡ����٤˴�������ȡ�
- ��
- ��������������EB = B����/�ҡ������������ҡ�
- ����������������������EB����ʪ�δ�������
- ����������������������B����ʪ�ε���
- �����������������������С�����Ψ
- ����������������������R����ȿ�ͷ���
- ��
- �Ȥ����ط������ꡢ����̤�����«�����������̾��٤ϡ�
- ��
- ��������������EC = B����Q/4Fe2����������Lens - 13��
- ����������������������EC�������̾���
- ����������������������B����ʪ�ε���
- �����������������������С�����Ψ
- ����������������������Q��������������0.828��
- ������������������������e�������ͭ���ʤ�
- ����������������������������= ͭ��F�ʥ�С���̵�±���ιʤ�ǤϤʤ���Ψ���θ�����ʤ��
- ��
- �Ǽ�����ޤ���
- ���̾��٤ϡ���ιʤ�ˤ�ä��Ѥ��ʤ��ͤ�����ȿ���㤷�ޤ���
- ʪ���̤ξ���EB�����̤ξ���EC����٤�ȡ�
- ��
- ��������������EC / EB = R��Q/4Fe2����������Lens - 14��
- ��
- �ȤʤꡢR=0.18�ʳ�������Ρˡ�Q=0.828�ʷ��������ˤȤ���ȡ�
- ��
- ��������������EC / EB = 1/26.8Fe2����������Lens - 15��
- ��
- �Ȥ����ط�����Ƴ���Ф���ޤ���
- ���μ���ꡢFe=1.0�λ���ʪ�Τ����뤵��1/27�����뤵�����˼̤���뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���������������äȤ����뤤��Ǥ���F=0.5�λ����������뤵��ʪ�Τ�1/6.7�ˤʤ뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���Τ褦�ˤ��Ƹ���ȡ�F2.0�ǤϤ��褽1/100�θ������˽��ޤ뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- Fe�ϡ�ʪ�Τ��ˤ��ä������������ʤ��ʤ��M<<1/20�˻��ϥ�ιʤꤽ�Τ�Τˤʤ�ޤ���
- ��������ʪ�Τ����Υ�ˤʤäƤ����ʪ��¦�θ�«��������ͤ�����٤����˼ͽФ����«�γ��٤˺��ۤ��ǤƤ��뤿�����̾��٤��Ѥ��ޤ���
- ��˹�ޤ줿��ʤ�Ϥ����ޤǤ�������ʿ�Ը��Ǥ��뤳�Ȥ�����˹�ޤ�Ƥ���Τǡ����¤ˤ�������Ψ���θ����ͭ��F�ʥ�С����������ʤ�Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ͭ��F�ʥ�С��ˤĤ��Ƥϸ�ι��������ä��Ƥ���ޤ���
- ��
- �����ʤ�θ���Ĵ�ᵡǽ
- ��ʤ�ˤϡ����̤�Ĵ�᤹�뵡ǽ�ȥԥ�Ȥι礦�ϰϤ�Ĵ�����뵡ǽ������ޤ���
- �����ޥ�ϡ��ԥ�Ȥ��礦�ϰϤĤ�ٿ������դ�ʧ���ʤ����ʤ����Ƥ���褦�˸��������ޤ���
- ��Τ褦�˹�®�ٻ��Ƥ˽������Ƥ����Τϡ�Ϫ�л��֤�û������ˤ��Ĥ���̤��ꤺ����ϤۤȤ�ɤξ�糫���ǻȤ��Τǡ��ʤ�θ����פˤϤϤ��ޤ��¤���ޤ���
- ��

- .
- ��
- �ʤ�ˤ��ե��������ι礦�ϰϤ��äϰʲ��ǽҤ٤�Ȥ��ơ��ʤ�ˤϾ�ޤ˼������褦�˥��Ʃ�᤹����̤�Ĵ�����뵡ǽ������ޤ���
- ���١����塼�֤��������Τ�ʤ�Ф�����Τ褦��Ư������äƤ��ޤ���
- ���θ�����礭������ʤ�Ф����������������ڤäơʥ���å����ڤ���ˡ����������̤˸����ͥ륮���ʸ��̡ˤ�Ϳ���ޤ���
- ����T�ȹʤ���礭���������̤���ޤ�ޤ���
- ��
- ����F�ʥ�С���T�ʥ�С�
- �ʤ�ˤ��ե��������ι礦�ϰϤ��äϰʲ��ǽҤ٤�Ȥ��ơ��ʤ�ˤϾ�ޤ˼������褦�˥��Ʃ�᤹����̤�Ĵ�����뵡ǽ������ޤ���
- ���Ǥ������ʤ���ͤ�T�ʥ�С��Ȥ������դ�ʹ�����ȤϾ��ʤ��ʤ�ޤ��������ʤ���ͤˤϡ�F�ʥ�С���T�ʥ�С���2���ब����ޤ���
- F�ʥ�С��ϡ���ǽҤ٤Ƥ����褦�˥������Υ�ȸ��¤����ɽ����Τǡ�T�ʥ�С���F�ʥ�С���Ʃ��Ψ���̣������ΤǤ���
- ����ɽ���ϡ��Dz��ѤΥ������ʤɤˤ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- F�ʥ�С���T�ʥ�С��δط��ϼ��Τ褦�ˤʤ�ޤ���
-
��T = F/√τ ��������Lens - 16�� - T����T�ʥ�С�
- F����F�ʥ�С�
- τ������������Ʃ��Ψ��0.00��1.00��
- F����F�ʥ�С�
- T����T�ʥ�С�
- �Ӥϡ����Ʃ��Ψ��ɽ�����������䥳���ƥ����ٹ礤�ˤ�ä��Ѥ�äƤ��ޤ���
- �������ʤɤǤ�Ʃ��Ψ��80%���٤ʤΤǡ�τ = 0.8 �Ȥ����F/2.0�Υ�ϡ�
- ��������T = 2.0/��0.8 = 2.24
- 2.24�Ȥ����ͤˤʤ�ޤ���
- F�ʥ�С��ϡ��ԥ�Ȥι礦�ϰϡ���̳����١ˤ����ݤ����ڤʤ�Τǡ�T�ʥ�С��ϼºݤλ��Ƥ�Ϫ���̤���������ڤ��ͤȤʤ�ޤ���
- Ϫ�зפ�Ȥä�Ŭ�ڤ�Ϫ����ԤäƤ����ΤΥ������Ǥ�T�ʥ�С������ڤ����ǤǤ�������TTL��Through The Lens��¬���Υ���餬���������ߤǤϥ���餬Ŭ��Ϫ����ԤäƤ����ΤǤ��ޤ��̣��ʤ��ʤ��ʤä���Ƥ��ޤ���
- ��
- �������뤤���Fast Lens, High Speed Lens�ˤ�ͳ��
- �Ѹ�Ǹ�����ξ��������뤤���Fast Lens�Ȥ�High Speed Lens�ȸ����ޤ���
- ���ܸ��ľ�������®�������®��Ȥʤ�ޤ���
- ���������ʤ�Ȥʤ��ԥ����ʤ����դǤ���
- ���뤤��ȸ��ä������褯����Ǥ��ޤ���
- ���θƤ����ˤʤä��طʤˤϡ��̿����ƤȤ�����Τ������������֤Τ����ä���ΤȤ�����ǰ��������Ƥ��ޤ���
- �̿������Ǥ��������ϡ����Ƥ�30ʬ�Ȥ�1���֤�Ϫ���������������ä��ΤǤ���
- ���줬�ڥåĥС���ʤɤθ��Ӥˤ�����뤤��������褦�ˤʤꡢ���Ƥ�10ʬ��1����20ʬ��1��û�̤��졢1��2ʬ��Ϫ���ǺѤ�褦�ˤʤ�ޤ�����
- ������������®��Ϫ�����Ǥ����Ȥ������Ȥǡ�Fast Lens��High Speed Lens�Ȥ����Ƥ������ʤ��줿�ΤǤ���
- Fast Lens�⤽��̾���Ǥ�������ϡ�������F3.6���٤Τ�ΤǤ�������F2.8���Ǥ���F2���Ǥ���F1.4��F1.0�Ȥ������ˤɤ�ɤ����뤯�ʤꡢ���Τ��Ӥ�����ǰ������뤤���Fast Lens�ȸƤӤޤ�����
- �����ֿ����ʡפȤ����촶�˶ᤤ��Τ�����ޤ���
- ��
- ����F�ʥ�С���ͭ��F�ʥ�С�
- ��ǽҤ٤�������ϡ�ʪ�Τ�̵�±�ˤ������������ۤ�ʿ�Ԥʸ��ξ�������Ω�Ĵط����Ǥ���
- �ºݤλ��ƤǤ�ʪ�Τϥ�˶ᤤ���֤ˤ��ꡢ���ˤ�äƤϤ��ʤ���Ψ��夲�����Ƥ뤳�Ȥ�����ޤ���
- ��Ψ���⤤����F�ʥ�С���̵�±��ʪ�λ��Ƥξ��Ȱۤʤ�ޤ���
- ̵�±�Ǥ�F�ʥ�С����Ф��ơ���Ψ����������F�ʥ�С���ͭ��F�ʥ�С��ȸ����ޤ���
- ξ�Ԥˤϰʲ��δط�������ޤ���
- ��
Feff =��1 + M x 1/�ס�F��������Lens - 17�� - Feff����ͭ��F�ʥ�С�����Ψ�����͡��ͽ�Ʒ���θ����F�ʥ�С���
- M����������Ψ
- �� :��Ʒ���� = �ͽ�Ʒ/����Ʒ = ��exit / ��ent��
- F :�������� �ʥ�˹������Ƥ���F�ʥ�С���
- M����������Ψ
- ��
- ��μ��ϡ���ιʤ��F�ˤ����ꤹ��ȡ��ºݤιʤ�ϻ�����Ψ�ʤ�����/�ͽ�Ʒ�η����ˤ��������졢������Ψ1�ܤǤλ��ƤǤϡ�F2.8�����ꤷ���ͤ��ºݤˤ�F5.6�������ˤʤ뤳�Ȥ�ɽ���Ƥ��ޤ���
- ���Τ��Ȥϲ����̣���Ƥ��뤫�Ȥ����ȡ����Ȥ���1��ȥ�Υ�줿���֤�30cm�Τ�ΤƤ��Ƥ��ơ�Ʊ��������Ϫ�����ǻ��Ƶ�Υ��ɤ�ɤ��Ť��Ƥ���30cm��ʪ�Τΰ�������绣�Ƥ��褦�Ȥ���ȸ��̤���ʤ��ʤäƤ��ޤ����Ȥ��Ƥ���Ƥ��ޤ���
- ���������Ǯ�ŵ�Τ褦�ʤ�ΤǤ���Ǯ�ŵ����ΤƤ���ˤϽ�ʬ�ʸ��̤���äƤ��Ƥ⡢���礷�Ƥ����ȸ������ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ������Ψ���ܤˤʤ�и��̤�4��������������Ψ��3�ܤˤʤ��9�ܤθ��̤�ɬ�פȤʤ�ޤ���
- Feff����ͭ��F�ʥ�С�����Ψ�����͡��ͽ�Ʒ���θ����F�ʥ�С���
- ���⤽��ƥʥ�С��ϡ��������������̵�±�ˤ���Ȥ��Υ�θ��¤������ְ��֡����ξ��Ͼ������֤���Ǥ���������ɽ����ΤǤ��ꡢʪ�Τ�ͭ�°��֤ˤ���Ȥ������ΤǤ�����֤Ͼ����ǤϤʤ����������֤ˤǤ��ޤ���
- ���ΤǤ�����֣�ϡ�
- ��
- ��������������b = f����1 + M�ˡ������������ҡˡ�
- ��
- ��ɽ����ޤ���
- ���Τ��Ȥ���μºݤΣƥʥ�С��ϡ�
- ��
- ����������������eff = b / �ġ���������Lens - 18��
- ��������������������eff����ͭ���ƥʥ�С�
- ������������������b�������ΤǤ������
- �������������������ġ��������
- ��������������b = f����1 + M�ˡ������������ҡˡ�
- ��ɽ�����ΤǤ�����μ��ϡ�
- ��
- ����������������eff = f����1 + M�� / ��
- ���������������� =���ơ�1 + M�ˡ���������Lens - 19��
- ��
- ��ɽ�����Ȥ��Ǥ���Τǡ�ͭ���ƥʥ�С��ϡ�̵�±�������ǤΣƥʥ�С��˻�����Ψ���̣������ΤǤ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ��
- ��
- ��
- �����ʤ�ȼ��ո���
 ��Ƚ�����Υ�Ǥϡ����ʤ����ǻ��Ƥ��뤳�Ȥ����ˤˤ���ޤ���
��Ƚ�����Υ�Ǥϡ����ʤ����ǻ��Ƥ��뤳�Ȥ����ˤˤ���ޤ���
- ���Τ���ˡ��緿��Ǥϥ�ʤ꤬F128�ޤǹ�ޤ줿��ΤޤǤ���ޤ���
- F128�ޤǹʤ������顢�դ˲��ޤˤ�ä������ܥ��Ƥ��ޤ��ΤǤϤʤ����ȿ��ۤ���ۤɤιʤ�Ǥ���
- ��Ƚ������ѤΥ�ǤϤʤ����Τ褦���礭�ʹʤ��ͤ��Ĥ��Ƥ��뤫�Ȥ����ȡ���Ƚ�����ʤ�ǤϤΥ����껣�Ƥ�ݤ�ɬ�פ�����Ǥ���
- ��Ƚ�����Υ��������Υ��ꥢ�ϡ�4"x5"��100mmx125mm�ˤǡ��饤����������36mm x 24mm�ˤ���Ϥ뤫���礭��φ208mm����ݤ��Ƥ��ޤ���
- �����������ȡ���̣���뤳�Ȥˡ��ʤ�ˤ�äƥ��������������礭�����ۤʤäƤ��ޤ���
- Nikkor W180mm F5.6��Ȥ�����Ƚ�����Υ�λ��ͤǤϡ�f5.6�λ���φ208mm�Ǥ��륤����������뤬��f22�˹ʤ��φ253mm�Ȥʤ뤳�Ȥ���Ƥ��ޤ���
- �ʤ�ˤ�äƥե�������С����륤�������������礭�����Ѥ��ΤǤ���
- ������������������ե���ॵ�������⤫�ʤ��礭�ʥ���������������ݤ��Ƥ���Τϡ���Ƚ�����Ǥϥ����껣�ƤȤ�����ˡ��¿�Ѥ��Ƥ��뤿��ʤΤǤ���
- �����껣�ƤȤ����Τϡ��ե�����̤ȥ�����θ������ƻ��Ƥ����ΤǤ��������Τ褦�ʻ��Ƽ�ˡ�Ǥϡ��������濴�������Ǥʤ���������褯�Ȥ��ޤ���
- �ʤ��ե�����̤�������Ф��ƼФ���ݤ��Τ��ȸ����С��㤨�С����إӥ�Ƥ���ݤ��Ͼ夫�饫�������˸������Ȥ���ȡ��ӥ�����̡��Ͼ夫���ľ��Ω�äƤ���ˤȥ���餬�ӥ��ͤ餦�������Ф�Ȥʤ�ޤ���
- ���ξ�硢���������˿�ľ�˥��åȤ���Ƥ���ե�����̤��ӥ�����̤�ʿ�Ԥˤʤ�ʤ�����˱�ẹ���Ǥ��ޤ���
- ���ˤ��������Ψ�Ѳ��ˤ�äƹ��إӥ�ι⤤��ǤϾ������̤ꡢ�Ͼ��ն�Ǥ��礭���̤äƤ��ޤ��ޤ���
- ���������ǥե���ᤵ�줿�ӥ�β��������տޤȤ��ƿ��Ϥ褯�ʤ����ˡ����������ޤ����뤿��˥ӥ�����̤ȥե�����̤�ʿ�Ԥˤ���С���Ψ���Ѳ��ˤ�������Ĥߤ��ޤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����������������eff = f����1 + M�� / ��

- ��������-��������������������F16
- ������ǤϼФᤫ������������̤���������Ǥ϶����ˤ�륱���Τ�����̤��Ѥ�롣�ʤ�η������礱�롣
- ���ʤ�ȼФ������Ǥ�������ȸ��̤��Ѥ��ʤ����ʤ�η������ݻ�����Ƥ��롣
- ��������-��������������������F16
- ���Τ褦�ʥ����껣�Ƥ����ˤˤ����ʤ���Ƚ�����Υ�Ǥϡ�����濴���Τߤʤ餺�������ޤǻȤäƻ��Ƥ��Ԥ��ޤ���
- ����ˤȤäƿ����̤������̤��������������˷����ƹԤ��ȡ�����̤ϡ��ǽ顢�ʤ���سԤ��ϥå���ȸ��Ƽ��Ƥ����Τ������˷礱�ƹԤ��Ǹ�ˤϡ������ʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �����˷礱�Ƥ������٤Ǥ��������Ͻ�ʬ�ʸ��̤����̤��Ϥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �Ȥ�������ιʤ��ʤ�ȡ���ʤ극���Ƥ��äƤ�ʤ�η�������뤳�Ȥʤ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���¤��礭���Ȥ��Ȥ⤿�䤹�������Ƥ��ޤ��Τˡʤ��������ˤ�뿩�ȸ����ޤ��ˡ����ʤ�ȿ��γ�礬���ʤ��ʤ�ΤǤ���
- ����ϡ����֤��Х��ʤ�ȥ����������������ˤ錄��Ѱ�˸������Ϥ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���줬���¤ϡ���Ƚ�����Υ�ʤ꤬�礭���ͤޤǹ�ޤ�Ƥ�����ͳ�ΰ�ĤʤΤǤ���
- �ޤ���������Ѥǻ��Ƥ�Ԥ��ȡ������μ��������濴������٤Ƽ����αƶ��Dz����������ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �ʤ��ʤ�ȡ����̼�����Ϥ����������� �������������ʤ���������Τǡ��緿�����λ��ƤǤϲ�������Τ���ˤ�ʤ��ʤ���ळ�Ȥ����ڤʤΤǤ���

- ����Ƚ��������ɽŪ�ʻ��Ƽ�ˡ�ʥ����껣�Ƥΰ��ˡ���饤�����ơ�
- ��
- ��Cos4��§��
- �ʤ�Ȥ���
 ���ط�����ޤ�����ˤ��ܼ�Ū�������Ȥ��Ƽ������Ǥθ����㲼�����ꡢ���줬��������4��˽��ä��㲼���ޤ������������4��§�ȸ��äƤ��ޤ���
���ط�����ޤ�����ˤ��ܼ�Ū�������Ȥ��Ƽ������Ǥθ����㲼�����ꡢ���줬��������4��˽��ä��㲼���ޤ������������4��§�ȸ��äƤ��ޤ��� - ���������ϤɤΥ�ˤ���äƤ����ΤǤ���
- ����ɽ���Ȱʲ��μ���ɽ����ޤ���
-
��E = Eω��cos4θ ��������Lens - 20�� - E�������̤Ǥγ���θ�˰�¸��������
- Eω���������濴����θ=0�ˤξ���
- θ��������������̹⤵���֤Τʤ�����
- Eω���������濴����θ=0�ˤξ���
- E�������̤Ǥγ���θ�˰�¸��������
-
- �Ĥޤꡢ��ϤɤΥ�Ǥ��濴�����������뤯���դ˹Ԥ��˽��äƽ������㲼����32.77��ΰ��֤Ǥϸ��̤�Ⱦʬ�ˤʤäƤ��ޤ���90��Ǥϸ����ޤä����Ϥ��ʤ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ѥ�ʤɤϹ����ϰϤθ���ޤ��Τǡ����������������㲼��ɬ�������ޤ���
- �����������¤Υ����ι��ѥ�ϡ���Υ���դˤ���褦�ʸ������������㲼��̵���褦�˴����ޤ���
- �ɤ����ƤǤ��礦����
- �����ʤɤΤ褦��180°�μ̳Ѥ��äƤ��Ƥ⽽ʬ�˼̤äƤ��ޤ���
- ���ѥ�Ǥ��������㲼�������ˤĤ��Ƥϡ������������к����ͤ����Ƥ��ޤ�����Ĥϡ�������������٤ζ��������Υ�˥�����������֤��ơ��������θ������γ��������礭�����Ƥ��ޤ���
- �ޤ��������������������Ť��Ƽ������ˤ����ƽ��������뤯�ʤ�ND�ե��륿����¢��������ˡ������ޤ���
- �⤦��Ĥˤϡ������Ķʤ����ư��̤��������ˡ������ޤ���
- �Ĥޤꡢ��ϤɤΥ�Ǥ��濴�����������뤯���դ˹Ԥ��˽��äƽ������㲼����32.77��ΰ��֤Ǥϸ��̤�Ⱦʬ�ˤʤäƤ��ޤ���90��Ǥϸ����ޤä����Ϥ��ʤ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��������˹��ߤ�ǻ��ʬ�������ND�ե��륿����¤�Ǥ��ʤ��ä��Τϡ��ɥ���Zeiss�Ҥ�Hypergon���ѥ�ʲ��130°�ˤ˸���줿�褦�ˡ�������̤˲��۾������֤����֤��ƥ���ɤ��̤��ƶ��������ꡢ���֤��������θ��̤�����ˡ���Τ��Ƥ��ޤ�����
- ���Ϥ��Τ褦�ʥ�Ϥ���ޤ���������ˤ��蹭�ѥ�ξ��ˤϼ������������٤��㲼���뤳�Ȥ���줺��ǻ�پ�����濴�Ȥ���������¬�Ǥϡ����ѥ�����ڤ�ǻ�٥��ν����ͽ�ḡƤ���Ƥ������Ȥ�ɬ�פˤʤ�ޤ���
- ��ιʤ�ˤ����ո����㲼�β����ϡ�����߷�ζ������ˤ���������Ƥ�������Ǥ��ꡢ���ʤäƶ����������������ˤϤ���cos4��§������Ƥ��ޤ���
- ��
- �����������١ʤ��礦�Ƥ�ɡ�Depth of Focus�ˡ���̳����� �ʤҤ��㤫������ɡ�Depth of Field��������2009.07.10�ɵ���
- ��ιʤ��ʤ����ȥԥ�Ȥι礦�ϰϤ��Ȥ���ޤ���
- ���Τ˸����ȡ����֥��㡼�פʥԥ�Ȥ������������������ܥ����ơ��ܥ��Ƥ���ƤǤ���ԥ�Ȥ��ϰϤ�Ȥ��褦���Ȥ����Τ��ʤ�ˤ��ե��������ϰϤ�Ĵ���Ǥ���
- ���Ƥ����ܥ��̤����ƺ���ߡʤ���褦�������allowable image blur���ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ��ˤ�äƷ����������������Υܥ����ϰϡʵ��ƺ���ߡˤ����äƤ���Хԥ�Ȥ���ä��Ȥߤʤ���ʾ������١ˡ������ʪ��¦�ˤޤdz�ĥ����ʪ�ΤΥե��������ϰϤ����ꤹ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����̳����١ˡ�
- ��̳����٤η����ϰʲ����������ޤ���
- ����ʣ���ʷ����ȤʤäƤ��ޤ���
- ��
��DP1 = L x (H + f) / (H +L) ��������Lens - 21�� ��DP2 = L x (H - f) / (H - L)
��H = f 2 / (�� x F)
- DP1 ������̳����١�-�������ʻ����̤���ե��������ι礦�ᤤ��Υ��
- DP2 ������̳����١�-�������ʻ����̤���ե��������ι礦��Υ��
- L �������Ƶ�Υ����ʪ�Τ��黣���̤ޤǤε�Υ��
- H �����������Υ���ʥ��̵�����Υ�˥��åȤ������Υե��������ι礦��Υ��
- f �����������Υ
- �� :�����ƺ���ߡ�0.01mm��0.05mm��
- F ������ʤ�
- DP2 ������̳����١�-�������ʻ����̤���ե��������ι礦��Υ��
- 2009.07.10��S����ꡢL����Ŭ�ڤ������λ�Ŧ������������ޤ�����S���꤬�Ȥ��������ޤ�����
- ��
- ��̳����٤ϡ���λ��Ƶ�Υ��L�ˤ����ꤷ���Ȥ���������Τɤ��ϰϤޤǥԥ�Ȥ���ä��Ȥ��Ƶ��ƤǤ��뤫�Ȥ����������������ȱ�����ɽ����ޤ���
- �����ϡ���ξ�����Υ��f�ˤȻ��Ƶ�Υ��L�ˡ�����˲������Υ��H�ˤ�ȤäƵ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- DP1 ������̳����١�-�������ʻ����̤���ե��������ι礦�ᤤ��Υ��
- ��
- ��
- �����������Υ�ʤ����礦�Ƥ�ꡢHyper-focal distance��
- �������Υ�Ȥϡ����̵�����∞�ˤ˥��åȤ������ˡ��ɤε�Υ����̵����ޤǥԥ�Ȥ��礦��������ΤǤ���
- �������Υ�ȥ�ιʤꡢ����˵��ƺ���ߤ�ɤ����٤�������뤫�Ƿ�ޤ���ͤǤ���
- �������狼��褦�ˡ��������Υ�ϥ������Υ�����������㤷����ʤ��ȿ���㤹��ΤǾ�����Υ��û���ۤɶ�������ԥ�Ȥ��礤�ޤ���
- ��ʤ��ʤ����ۤɶᤤ���֤���ԥ�Ȥ��礦�褦�ˤʤ�ޤ���
- �㤨�С����ƺ���� δ = 0.033mm �Ȥ���
- f = 50mm�Υ������Ȥä����β������Υ�ϡ�
- F/1.2��63m�ʥ�ȥ�ˡ�
- F/5.6��13m�ʥ�ȥ�ˡ�
- F/22��3.4m�ʥ�ȥ��
- �Ȥʤ�ޤ���
- f = 20mm�Υ�Ǥϡ�
- F/2.8��4.3m�ʥ�ȥ��
- F/5.6��2.1m�ʥ�ȥ��
- F/22��0.55m�ʥ�ȥ��
- �Ȥʤ�ޤ���
- ������Υ��û����Ǥϥԥ�Ȥι礦�ϰϤ������ʤ뤿��ˡ�Ķ���ѥ�Ǥϥե�����������⤦�����Ƥ��ޤ���
- �����̳����٤δط������顢�����������Τۤ������Ƶ�Υ����ε�Υ��Ĺ���ʤ�ޤ���
- ���Τ��Ȥϡ���̳����٤������ʤ�ˤĤ�ԥ�Ȥϱ�Υ�ޤǹ礦�褦�ˤʤ��ΤΡ��ᤤ���Ϥ���ۤɿ������ʤ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��

- ��
- ��
- ��οޤϡ���̳����٤η���������Ƿ��������դˤ�����ΤǤ���
- ���ξ��ϡ��������f50mm�Ȥ������ƺ���ߤ�25um�Ȥ��Ʒ����ޤ�����
- ���Ƶ�Υ��L�ˤ�300mm��500mm��1000mm��1500mm�Ȥ��ơ���ιʤ��F/1.4����F/22�ޤ��Ѥ��뤳�Ȥˤ��ե��������ι礦�ϰϤ��ɤΤ褦���Ѥ�뤫��ɽ���Ƥ��ޤ���
- �����ʼ������ο��ͤ���IJ�¦�Υ���աˤ��������������ο��ͤ���ľ�¦�Υ���աˤ��ԥ�Ȥι礦�ϰϤ����ʤ����Ȥ��狼��ޤ���
- �ޤ����ʤ������ۤ����ԥ�Ȥι礦�ϰϤ������뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �����������Ƶ�Υ���ᤤ�Ȥ���ۤɿ����ޤǥԥ�Ȥ����ʤ����Ȥ��Υ���դ���狼��ޤ���
- ��
- ��
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
|
|
||||
���������ֺ���
- �����ԥ�ۡ�����Pinhole lens������2005.05.10��
- ��θ��¤������Ƥ��äơ������ʷ�ǥ���ꡢ���η꤫������̤��ȿ˷�̿����ʥԥ�ۡ��륫���ˤ��Ǥ�������ޤ���
- ���ع������ʤλ��֤ˡ��ܡ�����Ȣ���ꡢ�����˷������Ƴ�����θ�����������̤˳Ȼ����Ž�äƥԥ�ۡ��륫�����ꡢ�����������Ǥ��Ƥ���Τ��и�������Ȼפ��ޤ���
- �ԥ�ۡ��륫�������ϡ�ʪ�ΤȤϾ岼�����դΤ�ΤǤ�����
- �˷�ϰ츫��������ۤμ������Ѥ�����褦�˸����ޤ���
- �˷��ɤ�ɤ������Ƥ����������¦����¦�ΰ��֤�1��1�Ƿ�Ф졢����Τ������ͤ����1��θ����˷���̤��ư�������Ƥ���뤫��Ǥ���
- 1��1���б�����Ȥ����Τϡ�����Τ��ɤΰ��֤ˤ��äƤ���Ƥ�������������˸�����Ȥ������ȤǤ���
- �츫���ۤ˶ᤤ�褦�˸�����˷�̿����Ǥ��������꤬���Ĥ���ޤ���
- ����������ܤϡ���������ʤ���ʪ�Τ����ϰ��а���б�������;ʬ�ʸ����������ǽ�ʬ�ʲ���������ʤ����ȤǤ���
- ����������ܤϡ��˷������������äƤ����������Ǽ��Ѥ��Ѥ����ޤ���
- ���Ǹ�ˡ��˷��������ȸ��β��ޤΤ���˸���������������ܤ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��ɡ��˷�̿��������꤬���ꤹ���Ƽ��Ѥˤ��Ѥ����ʤ����Ȥ��狼��ޤ���
- ����餬ȯ����������ޤǤϡ�����饪�֥������Ȥ������ʤ��ϼ̤���������֡ʾ����ˤ��Ȥ��Ƥ��ơ�16�����ޤǤϥ������Ƥ��ʤ��ä��Τǡ���Τʤ��ԥ�ۡ��뤬�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �������ԥ�ۡ��륫���ϤȤƤ�Ť�������γ����о�ʪ��Ť�������������٤ξ������Ǹ����뤯�餤�ˤ��褦�Ȥ���ȡ��ԥ�ۡ���ι���φ20mm���٤ˤʤä������Ǥ���
- ����Ǥ������ܤ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- ����Ǥ���褦�ˤʤäơ������ԥ�ۡ���������ळ�Ȥˤ�äƤ����������뤯�Ʋ��������Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ԥ�ۡ���Ǥϲ���������ưŤ��Ȥ������Ȥ�褯ʪ��äƤ��륨�ԥ����ɤǤ���
- ��
- ��
- ���������������طϡ�Perfect Optical Instrument�ˡ���2005.06.05��
- ���Ѥʵ��䤬�來�夬��ޤ���
- ʪ�Τ���������1��1�˼���������طϤϤ���ΤǤ��礦����
- �ԥ�ۡ������������ۤ��Ȼפä��ΤǤ��������ۤ˶�Ť��뤿��˥ԥ�ۡ���η��¤�ʤ����������Ƥ����ȡ������Ȥ������ˤ�äƲ��ޤ���������Ѥ��Ѥ����ʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �����������طϤ�ͤ��������Τϡ��ѹ�ͤ�ʪ���ؼԤǤ��륯�顼�����ޥ����������Clerk Maxwell�ˤȡ��ƹ�ͥ�ͥ٥륰��R.K. Luneberg�ˤǤ���
- ��ͥ٥륰���ƹ�ͤȽޤ������ܺ٤Ϥ狼��ޤ���
- ��ϡ�1944ǯ�ƹ�֥饦����ؤˤ����Ȥ��˥�ͥ٥륰�Υ�Ȥ���ͭ̾�ˤʤ����������ɽ���ޤ�����
- ��ͥ٥륰�Ͽ��ؼԤǤ��ꡢ�ޥ����������ʪ���ؼԤǤ���
- ��ͥ٥륰�οͤȤʤ�ϻ伫�Ȥޤ��褯�狼�äƤ��ޤ���
- ��ͥ٥륰�Υ��ͭ̾�Ǥ�������ͥ٥륰���οͤλ������ʤ��ʤ����Ĥ���ʤ�����Ǥ���
- ξ�Ԥ������������������طϤϡ����ؼԤδ֤ǤϤ��ޤ깥��Ǹ��椵��Ƥ��ʤ��褦�Ǥ���
- �Ȥ����Τϡ��ޥ���������ξ����������������طϤȤ����Τϡ����褽���¤Υ���餫��Υ�줿���طϤǤ��ꡢ��ͥ٥륰�ξ����������إ�Ȥ������⡢����ƥʤˤ�����Ȥ�����"���"�Ȥ��Ƽ��Ѳ�����Ƥ���ʵդ˸����ȥ���ƥʤ��餤�ˤ������Ѳ��Ǥ��ʤ������٤Τ�Τ�����Ǥ���
- ξ�ԤȤ��ż��Ȥ�ʬ��ǤϤȤƤ�ͭ̾�ʤΤǤ��������ؤ�ʬ��ǤϤ���ۤɽ��Ѥ���Ƥ��봶��������ޤ���
- ���θ��طϤȤ����ΤϤɤ�ʤ�ΤǤ��礦��
- ���Ȥ��Ƥ��륫����ѤΥ�ȤϹͤ��������ۤʤäƤ��ޤ��������ͤΤ���˽Ĥ��Ƥ��������Ȼפ��ޤ���
- ��
- ��
- �ޥ���������δ����������طϤ��ޤ˼����ޤ���
- ���θ��طϤ���ħ�ϡ��֥�פȤ������Τ��ʤ����طϤǤ���
- ���֤��Τ�Τ���Ȥ�����褦����ʪ�Ǥ���
- ���θ��طϤϡ�ʪ��¦��P�ˤ���¦��Q�ˤ�1:1�Ǵ����˷�Ф�Ƥ��ޤ���
- ��̣���뤳�Ȥϡ�ʪ�Τ���Ф����������������褦�ˤ�����¦�˼�«���Ƥ��뤳�ȤǤ���
- ���θ����ε��פϸ���ľ�������ǤϤ������ʤ����ȤǤ����ޥ���������ϡ����֤���̩�١ʶ���Ψ�ˤ��������Ѳ������Ǥ���ʤ�С�ʪ�Τ������Ф��줿���Ͻ����˶ʤ����ư����˼�«����Ⱦ����ޤ�����
- ���줬ͭ̾�ʡ֥ޥ����������Fish Eye�ʵ����ܡ˥�פǤ���
- ���٤�����ޤ������ޥ���������ε����ܥ�ϡ���Ȥ��Ƥ�ͭ��Ū���֤�����ޤ���
- �����������֤������ʤ�С��Ȥ�������Ǥ���
- ��οޤƤ���ȡ��Ų٤��ų����������δط��˻��Ƥ���Τ˵��Ť�����ޤ���
- �ޥ��������뤬���¤Ȥ���Υ�줿�����������طϤ���Ƥ����Τ��Ф�����ͥ٥륰�Ͼ������Ѥ˶ᤤ���طϤ���Ƥ��ޤ�����
- ��ͥ٥륰�Υ�ϵ���Ƥޤ���
- ���Υ����ħ�ϡ�����Υ���濴�ζ���Ψ�����ֹ⤯��¦�˹Ԥ��ˤĤ�������㤯�ʤäƤ��뤳�ȤǤ���
- ��������ζ���Ψ������ǤϤʤ�Ⱦ���������Ѳ������ͥ٥륰�Υ��Ȥ��ȡ����ϥ�ε��̤˱�äƽ��ޤ�褦�ˤʤ�ޤ���
- �������äƤ��Υ�Ǥ�����ʿ�̾�ˤϷ������ޤ���
- ���Υ�ϸ���ʬ��Ǥϼ��Ѥ������ż��ȹ��ؤΥ���ƥʤ˱��Ѥ����ͥ٥륰����ƥʤȤ��Ƽ��Ѳ�����Ƥ��ޤ���
- ��ͥ٥륰��ǵ��̾�������Ǥ���Ȥ����Τϡ��ʤˤ����������Ϣ�ۤ����ޤ���
- �������ˡ�������̾�˷�Ф���Ȥ����ΤϤ�������������������ޤ���
- ���̼�����ͤ��ʤ����ɤ������������������Ѷʤʤɤμ�����㸺���ޤ���
- ���̷��������λ����ǻҤ��Ǥ������Ѷ���Ψ����ĵ��̥���Ǥ���и��ؤ⿷���������������뤫���Τ�ޤ���
- ��
- ��
- �������ȥ��Mirrors and Lenses��
 ���ȥ�ǤϤɤΤ褦�ʰ㤤������ΤǤ��礦����
���ȥ�ǤϤɤΤ褦�ʰ㤤������ΤǤ��礦����- ξ�Ԥ��礭�ʰ㤤�ϡ�����������ȿ�ͤ������Ф���Τ��Ф�����ϸ����ζ��ޤ������äƤ��뤳�ȤǤ���
- ���ܿͤϡ����ȥ�ζ��̤ϤϤä���ȤǤ��ʤ��ä��褦�ǡ��ߥ顼�ˤ϶��Ȥ������դ�Ϳ���ޤ���������ˤϤ����Ȥ������������ƤƤ��ޤ���
- ���ȤäƤ���˾����串�������Ф��ơֶ��פλ������ƤƤ��ޤ���
- �ᥬ�ͤʤɤϥ���Τ�ΤǤ���Τˡ�����ȸ��äƤ��ޤ���
- ���ܿͤο��ˤϡ�������Τ�Τ��ֶ��פǤ��ä��˰㤤����ޤ���
- ���ϡ��������λ��夫�餽��¸�ߤ��Τ��Ƥ��ޤ���������ϼ�Į�λ���ˤ�äƤ��������ԤǤ��ꡢ�����Ȥ������դ�Ϳ�����ʤ��ä��褦�Ǥ���
- �������Ѥ����ɤ��Ȥ����褦�ʴ������������ޤ���
- �ܤˤ��Ƥ��Ρؤ�� = ����٤ϡ����θ츻���Ϥä���ȤϤ������ܤλ��Ϥ������뤿��Τ�������→�ܤΤ�������→�ܡʤ����ˤ���→��ͤȤʤä��Ȥ����⤬�����Ϥ���äƤ��ޤ���
- ���Ȥۤɤ��褦�����ܿͤˤȤäƶ��ȥ�ϻ����褦�ʤ�Τ��ä��ΤǤ��礦��
- ��ȶ��ǻפ��Ф�������Ū�ʥ��ԥ����ɤϡ����ؤ����Աѹ��ʪ���ؼԥ˥塼�ȥ�Τ��ȤǤ���
- �˥塼�ȥ�ϡ�������ޤˤ�äƿ���������Ĥ��Ȥ���Ѥ����������֤٤ƶ��Ǻ�����Ȥ��ޤ�����
- ���Ͽ�����������ޤ���
- ���Ǻ�ä�˾�����˥塼�ȥ�˾����ȸ����ޤ���
- ����������ˤϥ˥塼�ȥ���Ѥ����褦�������ˤϤ��������������֤ϥ��Ȥä������Τ�Τ�����������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Ͽ����������Ǥʤ���ΤΡ������ϰϤ�ʪ�Τ����������Ȥ�����������뤤���طϤ��뤳�Ȥ����������������ä��ΤǤ���
- �Ĥޤ�̿���Ȥ��ƤϤ����������Ը����ʤ�ΤǤ��������äơ����ߤǤ϶���Ȥä��������طϤϡ�ŷ��˾����䡢ʬ������������طϤΥ������������Ѥ���Ƥ���˲�ʤ��ʤ�ޤ�����
- �����ϡ��������ʿ�Ը�«���ᥤ��θ��طϤǤ���
- �������Ѥ�ȼ�鷺�˸������Ū���Ӥˤϡ����̶�����ʪ�̶������Ǥ�Ȥ��Ƥ��ơ�ʬ����Ǥ������ˤϵ��̶����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �����������֤ϡ�ʿ�Ԥ˶ᤤ��«�ΰ�ǻȤ��Ƥ��ޤ���
- ���������֤˻Ȥ�����̶��ϡ���Ǥ��礭�ʾ㳲�Ȥʤ뿧���������Ǥ�������²���Ԥ��ݤˤ���غ��������䤹�������ʿ�Ը����Ȥ������ν����⤢�äơ�����������ħ���褫�������ʬ��Ǥ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���̶��η��������ϡ����ޥ����פΥ��Ʊ���Ǥ���
- ξ�̡ʱ��˥�ϡ����̤�2�̤Ȥ��ƹ������뤳�Ȥ��Ǥ���Τ��Ф���ȿ�ͼ��ζ��Ǥ�1�̤Ǥι����Ȥʤ�ޤ���
- ���̶��η��������ϡ����äư��̤Ǥ�ȿ�ͤˤ������Ȥʤ뤿��˵��̤ζ�Ψ�ʣҡˤ��Ѥ��ưʲ��Τ褦��ɽ����ޤ���
- ���ޤ�ȼ����Ǥϡ���� ���� ���̥�ζ�ΨȾ�¤Ⱦ�����Υ�δط��� �ι�Ǥ�Ҥ٤��褦�ˡ������ζ���Ψ��n�ˤȶ����̤ζ�ΨȾ�¡�r�ˤǸ���������Ω������ΨȾ�¤Ⱦ����϶ᤤ���֤ˤ���ޤ���
- Ʊ����ΨȾ��2�̡�r1=r2�ˤǤǤ��������̡ʱ��˥�Ǥ϶�ΨȾ�¤�Ⱦʬ�˶���Ψ���̣�������֤��������֤Ȥʤ�ޤ���
- ���μ��ϡ����Ʊ�͡��ἴ������Ω�ļ��Ǥ���������Υ���������Ф��Ƥϼ������ФƤ��ޤ���
-
��1/a + 1/b = 1/f = 2/R��������Lens - 22�� - a ����ʪ�Τ�����ޤǤε�Υ
- b �������������ޤǤε�Υ
- f �������ξ�����Υ
- R�������ζ�ΨȾ��
- a���⡢�������ϡ�
- �������������ˤ���Ȥ������� + ��
- �������θ����ˤ���Ȥ������ - ��
- b �������������ޤǤε�Υ
���̶��η�������- �������̶���Convex Mirror��
- a ����ʪ�Τ�����ޤǤε�Υ
- ���̶��϶���ɽ�̤��̷����̤ˤʤäƤ����Τǡ�ƻϩ�Υ����֥ߥ顼��֤Υե�������ߥ顼���롼��ߥ顼�˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���̤ζ���깭�����������Τǡ�����������������Ȥ��˻Ȥ��ޤ���
- �������ʤ��顢�̷����̶��α�����Ū�϶��������Ҥ٤��褦�ʻȤ����ʳ��������Ȥ����Ϥ���Ƥ��ޤ���
- �����οޤ����狼��褦�ˡ����̶��Ǥϵ��̤ζ�ΨR��Ⱦʬ�������Ȥʤ���������˾������Ǥ��ޤ���
- ���ξ����ϼºݤˤ�������ǤϤʤ�������������褦�˸����Ȥ���Τǵ�������virtual focal point�ˤȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- ���̶�������ʿ�Ը�«�ϵ���������Ȥ���褦��ȿ�ͤ��ޤ���
- ���̶������ʪ�����Ϥ��Ĥ�����Ǥ��ꡢ�����ΤǤ�����֤�ʪ�Τ��ˤ�����ϵ�������˶�ˤǤ������̶��˶�ʤ�˽��äƶ��ζ�ˤǤ��ޤ���
- �庸�˺ܤ����̿��ϡ����ͱء������̹��ˤ������ɩ��Բ��ͱػ�Ź�����ˤ�����̥ܡ���Ǥ���
- ���ξ��ˤϡ�Ʊ�����̥ܡ��뤬����¤�Ǥ��ޤ���
- ���ε��̥ܡ��������˼̤äƤ���Τ���ǡ�����������Ƥ��ޤ���
- ���̥ܡ���˱Ǥ��Ф����������϶�ü���Ѷʤ��Ƥ���Τ��褯�狼��ޤ���
- ���̥ܡ���˶�Ť��ж�Ť��ۤ������礭���ʤ�ޤ���
- ������������ˤ�Τ����äƤ���褦�Ǥ���
- �庸�˺ܤ����̿��ϡ����ͱء������̹��ˤ������ɩ��Բ��ͱػ�Ź�����ˤ�����̥ܡ���Ǥ���
- ��
- �������̶���Concave Mirror��
- ���̶������̶�����٤�Ȳʳ�Ū���Ѳ��ͤ��⤯��¿���̤����Ѥ���Ƥ��ޤ���
- �ʤ������̶��������Ѳ��ͤ��⤤���Ȥ����ȡ����Υ���դˤ⼨���Ƥ���褦�˱��̶��Ǥ�ʪ�Τ��֤������֤ˤ�ä����ν�������������ˤ��Ѥ�뤫��Ǥ���
- ���̶��Ǥϡ�ʪ�Τ�ɤΰ��֤��֤��Ƥ����Ϥ��٤Ƶ����Ȥʤä��礭���Ѳ��Ϥ���ޤ���
- ���̶��Ǥϡ�ʪ�Τ����̤��������ޤǤ��֤��줿��Τϳ������ʵ����ˤ��ꡢ�������֤Ǥ�ʿ�Ը��Ȥ���ȿ�ͤ��졢���֤��줿ʪ�ΤϾ������դ˼��������������Ȥ���3�ͤ��Ѳ��ޤ���
- ���̶������̶��⡢Ʊ�����ؼ���Ȥä�ʪ�Τ����ΰ��֤��������Τˤ�ؤ�餺�����̶����������ΤǤ�����֤�¿�ͤǤ���Τϡ��¾������������ˤ��뤿��Ǥ���
- ���Τ���ˡ������褿���������˽��ޤä��ꡢ��������Ф�����ʿ�Ը��ˤʤä��ꡢ�����δ֤��֤���ʪ�Τ����礵���ΤǤ���
- ���̶��ϡ�ʬ������Υ������Ȥ��ƻȤ��Ƥ��ޤ���
- ŷ��˾����μ���Ȥ��Ƥ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �������θ����Ǹ������ˤ�Ȥ��ޤ���
- �ޤ���ȿ�ͥ����פδ��ķפθ������ʤˤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��
- �������̶��ξ�����Υ��ȸ��£�
- ��Ǥϡ�������Υf�ȸ��£Ĥ�ɽ��������ʹʤ�ˤ�����ʰ�̣����äƤ��ޤ���
- ���̶��Ǥ������ϥ��Ʊ�ͤ��������ޤ���
- ���̶��ˤ����Ƥ�����������������¤ζ�����Ȥ�������θ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���������¤��礭���ʤ�ȼ������θ��ϵ��̼����ˤ�������ΰ��������Ȥʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ���뤤���طϤǤϱ����ʪ�θ�������˽���뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����������������ͤ�������ʿ�Ը��ȤϤʤ�ޤ���
- ����Ū�ˡ�����Ȥä�ȿ�ͼ����طϤǤϥ��Ȥä������θ��طϤ���Ť��ʤꡢ������F4���٤��ǹ�Ǥ���ȸ���졢���̼������θ�����F10���٤��ɤ��ˤ��Ȥ����Τȸ����Ƥ��ޤ���
- �ʤ�ȿ�ͼ����طϤ϶�������٤����뤤���طϤ����ʤ����Ȥ����ȡ�ȿ�ͷ��Ͽ����������������崰�����ޤ��뤳�Ȥ��Ǥ��Ƥ⡢���̼����䥳���������������ʤɤ����ޤ���꤭��ޤ���
- ���äơ���«�����ޤ�Ҥ�����ʤ�̵�±��ʿ�Ը�«��ꡢ�դ�ʿ�Ը�«��Ȥ����طϤ��ò��������طϰʳ��λȤ�ƻ���ʤ�����Ǥ���
- ���Τۤ���ȿ�Ͷ��϶��ޥ����פΥ�������Ĺ�μ�����ۼ����ʤ�����糰�ΰ��UV�ˤ����ֳ��ΰ��IR�ˤޤ��ɹ���ȿ����������äƤ��ޤ���
- ������ħ�椨��ʬ����θ��طϤ�ŷ�δ�¬���֤Ǥϡ����̶��Ϻ��Ǥ�ʤ��ƤϤʤ�ʤ��������ʤȤ��ƽ��פʰ��֤����Ƥ��ޤ���
- ��
- ��������̶���Aspheric Mirrors�ˡ�-����ʪ�̶����ʱ��̶����ж��̶�
- ���̤�Ⱦ��R�ε��̤ǤǤ��Ƥ��ʤ���Τ�����̶��ȸ����ޤ���
- ��ɽŪ�ʤ�Τ���ʪ�̶���parabolic mirror�ˡ��ʱ��̶���ellipsoidal mirror�ˡ��ж��̶���hyperboloidal mirror�ˤ�����ޤ���
- ��ʪ�̶��ϡ��̷�������ʪ�̤ǤǤ��Ƥ����Τǡ�ʿ�Ը�������˽�������Τ��ɹ��������������碌�Ƥ��ޤ���
- ��ʪ�̶��ˤϵ��̼������ʤ�����ʿ�Ը��������ɤ������˽���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��������ʿ�Ը�«�ϸ�����ʿ�ԤȤ�����郎���ꡢ�������鳰�줿�����˴ؤ��Ƥϵ��̶�����Ҥɤ������ܥ��������ޤ���
- ��ʪ�̶��ϡ��̾�ϵ��̶��ˤ��Ƥ����̤μ�����������Ȥ���������Τ����̤Ǥ���
- �֤Υإåɥ��פ˻Ȥ�ȿ�Ͷ��ʤɤ϶ⷿ����⡼�����¤�ˤ�äƺ���Ƥ��ޤ���
- �ʱ��̶����ʱ߶����ǤǤ������Ǥ���
- �ʱߤˤ�2���ξ���������Τǡ�1���ξ�������Ф��������ʱ��̤�ȿ�ͤ��Ƥ⤦��Ĥξ����˽������ޤ���
- �Ĥޤꡢ��ʪ�̶���̵�±��ʿ�Ը����Τ�Ŭ�������Ǥ���Τ��Ф����ʱ��̶���ͭ�µ�Υ�������ͤ��줿�����Τ�Ŭ������Τȸ������Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ʱ��̶��ϡ��졼�����嵯����Ȥ��θ������֤Ȥ��ƻȤ��ޤ�����
- ���θ������֤Ǥϡ��嵯���ʥ����Υ�ե�å�����塼�֡ˤ�����ξ������֤��ơ�¾���ξ����˥졼����ȯ��������åɡʥ��饹��YAG����ӡ����ʤɡˤ����֤��Ƥ��μ�����ʱ��̶���ʤ���嵯����ͭ���˥��åɤ˽���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �ж��̶��ϡ��ж���������ȿ�Ͷ��ǽ�����«��ʿ�Ը�«�ǤϤ���ޤ��ˤ���ξ����˽����Τ˻Ȥ��ޤ���
- ���ζ��ϡ�������«���ȿ�ͤ������̤ΰ��֤˽�����������˻Ȥ�졢ŷ�δ�¬�Ѥ�ȿ��˾����˱��Ѥ���Ƥ��ޤ���

- ��
- ��
 ��
��
- ��
- ���̶���ʪ�ΰ��֤����ΰ��֤δط��ޡʾ�ˡ������̶���ʪ�ΰ��֤����ΰ��֤δط��ޡʲ��ˡ�
- .
- ��
�����̥�ȱ����Convex Lenses and Concave Lenses������2005.06.12�ˡ�2005.7.30�ɵ���
- ��ˤϡ��礭��ʬ����ʿ�Ը�«���«������ץ饹�ζ����Ϥ���ä��̥�ȡ��ޥ��ʥ��ζ����Ϥ���ä����������ब����ޤ���
- �ɤ�ʤˤ�������Υ������Ȥ��Ȥ߹�碌�Ƥ�ͤޤ�Ȥ��������ζ��ޤ�����̥�ˤʤ뤫����ζ��ޤ���ı���ˤʤ뤫�ɤ��餫�Ǥ���
- �Ϥ��ޤ���Ω���ݤĤʤ��ʿ�ĥ��饹��ܸ�ʤ����ӡ˷����ץꥺ��ˤʤ뤫�Τ����줫�Ȥʤ�ޤ���
- ��η����礭��ʬ����Ȱʲ��Τ褦�ʷ�����ʬ�����ޤ���
- ��
- ��

- ��
- ��
- ξ�̥�ϡ�ʿ�̥����Ĺ�碌����Τǡ����ޤ�ʿ�̥��궯���ʤ�ޤ���
- ����ϡ��̥�ȶ����Ϥ�ȿ�Фˤʤ�����������ޤ���
- �̥���ˤ������Ƹ�����оݤ��ܤ䤱�Ƹ����뤳�Ȥ�¿��������Ǥ��оݤ��ܤ䤱�������������ޤ���
- ξ�̥�ϡ�ʿ�̥����Ĺ�碌����Τǡ����ޤ�ʿ�̥��궯���ʤ�ޤ���
- ��˥�������meniscus�ˤȤ�����̣�ϻ�����Ȥ�����̣�ǡ����̤��̷���ȿ���̤������ˤʤäƤ����Ǥ���
- ξ�Ԥζ��ޤ��ٹ礤�����ΤȤ����̷��������ˤʤä���������������褦�ˤʤ�ޤ���
- �������Ѹ�Ǥϡ�ɽ��ĥ�Ϥˤ�äƥ��饹�ɤ������줿���Τ�ɽ�̤���������ͽФ����ꤹ�븽�ݤ��˥������ȸ����ޤ���
- ��˥�������Ǥϡ�ξ�Ԥζ�Ψ�ΰ㤤���̷��ˤʤä�������ˤʤä��ꤷ�ޤ���
- ���������θ��ߤ�����������٤Ƹ�����Τ��̷���˥������ȸ�����������Τ������˥�������ȸ����ޤ���
- ���̤ˡ��桹�������ߤ�������Ȥ����о�ޤΰ��ֺ���ξ�̥�Ǥ���
- ��ᥬ�ͤ⤿���Ƥ����Υ����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ����ϡ���˥����������פ��Ȥ�졢����ѤȤ��Ƥ��̷���˥���������Ѥ���졢����Ѥˤϱ�����˥���������Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����ϡ���夬�岼�������礭��ư���Τǡ�ξ�̥��Ȥ��ȴ�夬������ˤ���Ȥ����Թ��ɤ��ԥ�Ȥ��礦��ΤΡ���夬ư���ƥ�μ��������̤���ʪ����ˤϡ��������ä����������������˸���Ƥ��ޤ���ǽ���ޤ���
- ��˥�������ϡ��Фᤫ����������äƤ����Ū���䤫�˸����«���Ƥ����Τǡ��Фᤫ�������������ǤϽ��פ�Ư��������ޤ���
- ���ϡ�Ʒ���礭����7�ߥ����٤Ǥ��뤿��ᥬ�ͤ��礭����60mm���١ˤ���پ������ΰ������ȤäƤ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ����Ʒ�����������Ȥ��顢��˥�������λ�����������������ˤʤ�ʤ����餤�˽���졢���ġ����α�ư���Ф��Ƥ��Ψ�褯��������Ƥ����Τǡ��ᥬ�ͥ�Ȥ��ƥ�˥������������Ū�ˤʤ�ޤ�����

- 1803ǯ�˱ѹ�β��ؼ������饹�ȥ��William Hyde Wollaston��1766-1828����������Ѵ������̥�˥��������饪�֥����������Ѥ��ޤ�����
- ����ˤ�ꡢ�̥��Ȥä�����饪�֥����������������夷�ޤ�����
- ��˥�������ϡ�������ʿ�Ը�«������˽����ǽ�Ϥ����ϤǤ���
- �̥���Ϥ뤫���礭�ʵ��̼���������ޤ���
- �������äơ������饹�ȥ���饪�֥������˻Ȥä��̥�˥�������ϡ�������˹ʤ���֤��ưŤ���Ȥ����̼�����������Ƥ��ޤ�����
- ���Τ��Ȥ�ꡢ��˥�������ϡ���Ѥι��������ݤ�ɬ�פʥ�Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �̿���Ǥ��礭�ʻ����̡ʥե�����̡������ǻ��̡ˤ˲�������ɬ�פ����˥���������褯�Ȥ�졢�������������뤿��ˤ����Υ�����ŤͤƼ̿��������Ƥ��ޤ���
- ����ñ��μ����Kind of Lenses������2005.08.02���ˡ�2005.08.13�ɵ���
- ��ϵ��̥��¾�ˤɤΤ褦�ʥ������ΤǤ��礦��
- �褯�Τ��Ƥ�����ʲ��˼����ޤ���
- 1.�����̥��Spherical lens��
- ���ɽ�̤����̷�������ǡ���äȤ����Ū�ǸŤ����餢���Ǥ���
- ���������Ū��ñ�ʤΤǤۤȤ�ɤΥ�����̥�Ǻ���ޤ���
- ��˼������̥���������˥�������Ϥ��٤Ƶ��̥��°���ޤ���
- 2.������̥��Aspherical lens��
- 1.�ε��̥��°���ʤ���ǡ��Ȥβ�������̥�Ǥϱ��ξ�Ѥδ���������ޤ���
- ����̤Υ��ƥ���ˤ���ʪ�̡��ж��̡��ʱ��̤ʤɤ�ޤޤ�ޤ���
- ��ϥ��饹���ᤷ�ƺ��ط��塢���̻ž夲�����ܤǤ�����
- �����������̥�ǤϤ�������Υ���Ȥ߹�碌�ʤ��ȼ�������꤭��ޤ���
- ��μ����������ȡ���������������ʤ˸��餹���Ȥ��Ǥ��뤳�Ȥ��Τ����Τ��Ƥ��ޤ�����
- �������ʤ��顢���Ȥ���ʤ�Ȥ⤫�����̻��������̥�������뤳�Ȥϻ���ζȤǡ��ץ饹���å���������ޤ�����̥���̻����ϼ¸����ޤ���Ǥ�����
- �ץ饹���å���ϡ�ͽ����̩�ʶⷿ���äƤ����Ƥ�����Ϥ����ץ饹���å���ή�����ߡ�����������뤳�Ȥ�ʣ���ʷ����Υ���̻����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ץ饹���å���ˤ������̥���о�ǡ���������ü�˾��ʤ�������������²��ˤǤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 1995ǯ7��˥ե��̿��ե���फ��ȯ�䤵�줿����դ��Ȥ��Τƥ����ּ̥��Ǥ��פϡ������ȳ��ˤȤäƾ�Ū�ʽ�����Ǥ�����
- 800�����٤��ʧ�äơ��ե���ब���ä�Ȣ���Υ���������������Ƥ�����ä���̿�������˻��äƹԤäơ������ȥץ��ȤƤ�餦�Ȥ�����ΤǤ���
- �Ȥ��Τƥ����ϡ����������β�������ä��Τǡ����ؤ�������Ƥ��äȤ����֤˥ե���५���μ������ʤˤʤ�ޤ�����
- ���Υ����˻Ȥ�줿�Τ���1��Υץ饹���å�����̥��f=32mm�ˤǤ�����
- ���ä�1��Υ�Ǥ�������β����������ΤǤ���
- ���Υ����ħ�ϡ����ץ饹���å��ˤ����̻�����ޤꡢ����̤ˤ��Ƽ������ޤ�������˹ʤ��F/10�ˤ��Ƽ������μ������ޤ����������Υ������1m����̵�±��∞�ˤޤǥե����������礦�褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- 1��Υץ饹���å���������⤵�뤳�Ȥʤ��顢�ե����δ��ٸ��夬F/10�Ȥ�����
 ������߷פ��ǽ�Ȥ�������ˡ��ե�����̤�ʿ�̤ǤϤʤ��Ѷʤ����뤳�Ȥˤ������������μ����������뤳�Ȥ��������ޤ�����
������߷פ��ǽ�Ȥ�������ˡ��ե�����̤�ʿ�̤ǤϤʤ��Ѷʤ����뤳�Ȥˤ������������μ����������뤳�Ȥ��������ޤ����� - 1��Υ�Ǥ⤢�����ޤDz�������夹��Τ����Ȥ�����ɮ���٤������Ȼפ��ޤ���
- ��
- 3.�������ɥꥫ����Cylindrical lens���������
- ������Υ�ζ�Ψ���������Τߤ��ߤ���줿�����ޥܥ������ʱ����Ǥϱ��ȥ������ˤΥ�Ǥ���
- �٤���������դä�����������ɤ���ˤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ޤ����졼�����Ⱦ��ˤ�����طϤˤ⥷���ɥꥫ�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �Dz��Ѥλ��ƥ�ڤӱǼ̥�ˤϡ������ɥꥫ�����Ȥ߹�������ʥ�ե��å����anamorphic lens�ˡ��ڤӥ��ͥ������Cinema scope lens�ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ͤδ�����ˤ⥷���ɥꥫ�������Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���������ºݤδ���Ǥϥ�˥�������˥����ɥꥫ������Ƥ뤿�ᡢ�������������ˤϰʲ�����������ȥ����������Ȥ��ޤ���
- ��
- 4.���ȥ���������Toroidal lens���ߴĥ��
- .
- ������ʥ����ɥꥫ���ˤ�Ĺ���������Ѷʤ�������Ǥ���
- �ȥ�������Ȥϱߴľ��ΤȤ�����̣�Ǥ���
- �ȥ�������Ȥ���̾���ǰ���Ū�ʤ�Τϡ��Ż����ʤΥȥ�������ȥ�䡢��ư�֤μ�ư��®���˻Ȥ��Ф����ȥ�������ȥ�ߥå�����CVT = Continuous Variable Transimission�ˤʤɤ�����ޤ���
- �����Ϥ������ɡ��ʥåĤη������餳�θƤ�̾���Ĥ����Ƥ��ޤ���
- �ȥ���������ɡ��ʥåķ����Ȥ����ʤ��⤢��ޤ����ɡ��ʥĤΰ���ʬ���ڤ�Ф����褦�ʷ����Ƥ��ޤ���
- ����Ѥδ����ϡ��ȥ���������ŵ���Ǥ���
- �ȥ��������ζ�Ψ���������̤�̵�����ʿ�̡ˤˤ�����Τ�������ʥ����ɥꥫ���ˤˤʤ�ޤ���
- ��
- 5.���ե�ͥ���Fresnel Lens�ˡ���2006.02.15�ɵ��ˡ�2007.05.21�ɵ���
- ������������Dz�����ѥ��OHP����ƥ����Ģ���Ͽޤ���礷�Ƹ��뤿��ηȹ��ѤΥץ饹���å��ץ졼�Ⱦ��Υ���ե�ͥ��Ǥ���
- �̾���̥�Ȱ�äƥ�˸��ߤ��ʤ���ʿ�Ĥ˶ᤤ���Ƥ���ˤ⤫����餺�������Ѥ���ĥ�Ǥ���
- ���Υե�ͥ���������Ѥ˻Ȥ����Ȥ���ȼ������礭������Τǡ���˸������Ū�˻Ȥ��ޤ���
- �ե�ͥ��ϡ�1822ǯ���ե��ʪ���ؼ��ե�ͥ��Augustin Jean Fresnel��1788-1827�����������������ѤȤ��ƹͤ��Ф��ޤ�����
- ���ȯ������Ū�ϡ���η��̲��Ǥ�����
- ���桢�������饤�ȡ��Dz�����Ѥ˻Ȥ�������ϡ���������θ������̤���Ƥ��ʤ���Фʤ�ʤ��Τǡ�����礭���ʤ�ޤ���
- ��������Ƚ��̤��ȤƤ�Ť��ʤ�Τǡ����̲��οޤ��ե�ͥ����Թ��ɤ���ΤǤ�����
- �ޤ��������ѤΥ롼�ڡ�Ϸ����Ѥν����ѤȤ��Ƥ�ե�ͥ��ϰ²��ǻ������Ӥ������Ǥ��뤿�ᡢ�ץ饹���å�����ʿ�ĤΤ�Τ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����¾�������ե�������Υե�����ɥ�Ȥ��ƥڥץꥺ��β���ʿ�ĤΥե�ͥ���Ž���դ����Ƥ��ޤ���
- ��Ǽ�����ɤ��Τ��礭����ͳ�Ǥ���
- ������ѥ�Ȥ��ƥե�ͥ��ϻȤ��ޤ���
- ������ͳ�ϡ��������Ϣ³�ǤϤʤ����ʳ�Ū�ʥ�ʥץꥺ��ˤǤ��뤿�ᡢ�������μ�������ü�˰������Ѥ��Ѥ��ʤ�����Ǥ���
- �������ʤ��顢7.�ǽҤ٤�������ץ졼�ȡ�DOE = Diffractive Optical Element���γ�ȯ�ˤ�ꡢ�ե�ͥ������Ǥ�����������뤳�Ȥ��¾ڤ���ޤ�����
- ���ƺ���߰�������ܥ������ޤ�褦�˥ե�ͥ�����̷�����٤������Ƥ����ɤ��Ȥ������ȤΤ褦�Ǥ���
- ʿ�ĥե�ͥ��κ���ϡ���������PMMA = Polymethylmethacrylate, �ݥ�����������졼��) �ǡ��ⷿ��Ȥä���������뤳�Ȥ�¿��10mm�Ѥ���500mm�����٤��礭���Τ�Τ����Τ���Ƥ��ޤ���
- ��
- ��������Υ��ץϥ���
- �ե��ʪ���ؼԥե�ͥ뤬�������Ѥ�������Ȥ��ƥե�ͥ���ȯ������ư���ϡ������̲����Ƹ�Ψ�褤�������֤��ꤿ���ä�����Ǥ���
- ���ȳ�̿���1820ǯ�����ϡ��緿�ξ������η�¤���ʤ߳�ϩ�ΰ������Ԥ��ȤƤ�����ˤʤäƤ�������ǡ��ޤ��Ϥ�����������꤬�����Ƥ��ޤ�����
- ����˻Ȥ��Ƥ���ե�ͥ����ɤΤ褦�ʷ��Ƥ���Τ����桹�ˤϤ��ޤ������ߤ��ʤ��ΤǤ褯�狼��ʤ��Ȼפ��ޤ���
- ����˻Ȥ�����ץϥ����ϡ��������濴���֤������̥��饹ĥ��������Ȥ��������Τ�ΤǤ���
- ���Υ��ץϥ����dz���50km���٤ޤǸ�����ã�����ޤ���
- ����ޤ���ã�����뤿��ˤϡ����������Ψ�褯ʿ�Ը��ˤ���ɬ�פ�����ޤ���
- ����˻Ȥ�������ϻפä��ۤ��礭�ʥ��פ�ȤäƤ��餺�������ƥ��ŵ塢�����Υ���ס�HMI���פ�¿���褦�ǡ����Ϥ�250W��1,000W����Τ褦�Ǥ���
- ���椬�Ǥ�������θ����ˤϡ��ߤλ餬�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ���줬�顼�ɡ��ڤλ�ˤˤʤꡢ��������������ˤˤʤꡢ�ŵ�����������ؤ�äƤ����ޤ�����
- �����νФʤ���ٸ����Ϲ�����꤬�Ф�ۤɤۤ����ä��˰㤤����ޤ���
- �����ΤǤ�����ϥե�ͥ����ޤ餻�������ݽ������Ѥ�����Ǥ���
- �ŵ��������꤬�Ǥ��������ϥ��������פ��Ȥ�졢���ߤ���Ǿ������ؤ����������������ؤˤ�ä��ŵ�����������äƤ��ޤ�����

- ����θ����ϡ�������ã��Υ������ʤΤǡ������̤�����١ʥ���ǥ� = �����������Ф����ñ��Ω�γ�������θ�«�ˤζ�����Τ������ޤ���
- ���Ϥ��礭���������������ǤϤʤ��̤�ȼ�ä������Ȥʤ�Τǡ����ߤ˽��Ϥι⤤��Τ�Ȥ��ΤǤϤʤ������Ϥ��㤯�Ƥ���٤ι⤤���ס��������ˤ����Ф�Ƥ��ޤ���
- �����������Ф������������������ʿ�Ը����Ѥ���Τ��ե�ͥ������ܤǤ���
- ʿ���٤��ɤ���������ʤ��ȡ����ϱޤ��Ϥ���û����Υ��ȯ�����Ƥ��ޤ��Τǥե�ͥ��θ���ù�������϶ˤ�ƹ⤤���٤��ᤵ��ޤ���
- ����Υ�ϡ��礭������ǽ��ä�6�����ʬ����Ƥ��ơ�1���������礭����6�������־�������ΤˤʤäƤ��ޤ���
- ���ܤǤϡ�1���������ϸ��ʺ�����ո�ĸ�ҡˡ�����̨�ʹ��θ��ˤ�ޤ�6�ս�ˤ����ʤ������Ǥ���
- 1����Υ�ϡ�������Υf=920mm��������1,840mm����ι⤵2,590mm�ȷ����Ƥ��ޤ���
- ��ϡ�2�̡�3�̡�4�̡��⤷����8�̤ǤǤ��Ƥ��ơ���������β����ž���Ƴ�����ʿ�����˥������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ¿�̤Υե�ͥ���ʤ��줿���ץϥ������濴�˸������֤���ޤ���
- ���٤Ƥ�����ˤ錄�äƥ�ξ�����Υ����¤�2�ܤδط������ꡢ������Υ��2�ܤ���¤ˤʤäƤ��ޤ���
- �Ĥޤꡢ�����ϥե�ͥ��ξ�����Υ�����֤���Ƥ��ơ���������Ф�����ʿ�Ը������ͤ������ȤߤˤʤäƤ��ޤ���
- 1����Υ���礭����2,590mm�Ȥ��ʤ��礭�����������Υ920mm��2.8�ܡ�F�ʥ�С���ɽ����F/0.36�Ȥʤ�ޤ���
- �����ͤ��顢�ե�ͥ��Ϥ��ʤ����뤤���طϤǤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ����Υ��ץϥ����Υ���濴���ϡ��ե�ͥ�����ħ�Ǥ���Ʊ���߾��������̥�����Ƥ��ޤ���
- ��ι⤤���֤��㤤���֤Ǥϡ�Ĺ���ץꥺ���Ĺ�������˴ˤ䤫�˥����֤�Ĥ�����¤�ȤʤäƤ��ơ����줬���ʤˤ⳻�ͤΤ褦����������Ƥ��ޤ���
- �������������ǥꥢ�ˤ�����褦�ʥ��饹��������ʤ��줿�饤�ȥϥ����ˤ�äơ����Ū�����ʾ������Ϥθ��줤�����ä�ʿ�Ը��ˤ�����γ��˱ޤ�����Ǥ���褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ���Τ褦�ʷ��̲���ޤä��ե�ͥ��饤�ȥϥ����Ǥ⡢1����ν��̤ϥ���������Ǥ�5�ȥ�ˤ�ʤ�ȸ����ޤ���
- ���νŤ������饹�Υ��פ���ž������γ��˶��������ꤲ�����ޤ���
- ���ζ����ϡ�1����������100������ǥ�θ��٤����뤽���Ǥ���
- ����Υե�ͥ���ȤȤƤ�ͥ���Ƿݽ������������ޤ���
- ���ޤΥե�ͥ��ϡ��ƹ�ե�����ˤ��륻��ȥ������������St. Augustine������Τ�ΤǤ���
- �Ÿ��ʴ���������ޤ���
- ����������Ϥ��٤Ƽ���ʤΤ��Ȼפ��ޤ���
- ����������椬���ܤ�6�������ʤ����פ�ͤ���ȡ�������ǿ������٤θ��ز�Ҥ�����Υ���äƤ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
- ���ܤ������¿���ϥե����͢�����Ƥ����褦�Ǥ���
- �ե�Υ����������ϡ��졼�ҡ������ꥹ�Υ�����֥饶�����Ҥʤɤ���͢�����ơ�1919ǯ����켡�������ェ��˰ʹߤϡ������Ϥ졢���ߤǤ����ܸ������Ȥ����ܤ���������¤�����ƥʥ���˰��������Ƥ��뤽���Ǥ�����
 ����
����
- �ƹ�ե�����ˤ��륻��ȥ������������St. Augustine�����档
- �ۤȤ�ɤ��٤Ƥ����إ��饹�ǤǤ��Ƥ��롣
- ����
- ����
- ��
������
- ���Ų���������Ԥ����������7ǯ��1874ǯ���ߡˡ�
- ���������ϰ���������Ǥ���������ʿ�������Ϣ�緳��ɸŪ�ˤ��ä��˲�����ޤ�����
- ��塢�����緿��ˤʤ�ޤ�����
- �����ˤϥե�ͥ�����������Ƥ��ơ��濴���֤��줿��������ʿ�Ը��ˤ��Ʊ�������ꤲ�����Ƥ��ޤ���
- �ե�ͥ������Τϡ�20�äǰ��ž���Ƥ��ޤ���
- ���ξ�̤ˤ���Τǡ�10�ü����dz���˸����ʿ�˥�����Ƥ��ޤ���
- 2006.02.14�˸�����������θ������Ǥ����������Υ���פ�HMI ���פȻפ��ޤ���
- ��������ι⤵��22.5m�������ϳ�ȴ��54m�ˤ���ޤ���
- ����θ��٤ϡ�56.0������ǥ顣��ã��Υ�ϡ�19.5��Τ����36km�ˡ�
- �ڲ��ò���ıDz�ִ�Ӥ��ᤷ�ߤ���з�פ�����Ȥʤä�ͭ̾������Ǥ���
- �ƹ�ե�����ˤ��륻��ȥ������������St. Augustine�����档
- ��˽Ҥ٤��絬�Ϥ�����Υե�ͥ��ȤޤǤϹԤ��ʤ��Ƥ⡢�������Ū�Ȥ����ե�ͥ��ϼ�ư�֤Υإåɥ��ס��ơ�����פʤɿȶ�˸��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����Υ��פ����������Ψ�褯���Ȥ����뤿��˥�����̤ˤ��������ʥ��åƥ����ܤ���Ƥ��ޤ���
- �����Υ�ϥ⡼��ɤˤ�����������ǤǤ��Ƥ��ޤ���
- 6.���������GRIN lens = Gradient Index lens������Ψʬ�ۥ��
- ���إ��饹�ϡ����̤˶Ѱ�ζ���Ψ����äƤ��ޤ��������Υ�ϸ��οʹ����������̤��Ф��ƶ���Ψ���������Ѳ������Ǥ���
- ���ե����С��Υ������Υ��饹���������θ����ǤǤ��Ƥ��ޤ���
- ������ϡ�����Ū�ˡ�φ1.0��φ2.0mm��2��5mm���٤α�����Υ��饹��BSG=�ɡ��פ��줿�﷾�����饹�ˤǤǤ��Ƥ��ơ����饹�����ζ���Ψ���濴����������˹Ԥ��˽��ä���ʪ��Ū���Ѳ����Ƥ����ΤǤ���
- ������Υ��饹��ϡ�ξü�����ظ��ᤵ��Ƥ��ޤ���
- ξü��ʿ�̤Ǥ��äƤ⥬�饹�����ζ���Ψ���Ѳ��ˤ�꽸�����Ѥ�����ޤ���
- ������Ǥϡ�ʿ�Ԥʸ��������������ä��Ȥ���ȿ��¦��ü�̤ǽ�������褦�ˤǤ��Ƥ��ޤ���
- ���Υ��ü�̤ǽ�������Ư�����Ĥ��Ȥ��顢�����ǽ��ɽ�����ͤΰ�ĤȤ�����Ĺ�Υԥå���ɽ����0.25P�ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- 0.25P�Ȥ����Τ�1/4��Ĺ���̣���Ƥ��ơ����ü�̤˸�����«���뤳�Ȥ��̣���Ƥ��ޤ���
- ̵�±�θ��ξ������ͽ�¦��ü�̤�곰�ˤǤ���0.23P�Υ�ȸ��äƤ��ޤ���
- ������ˤϾ�����Υ�Ȥ����ͤ����Ϥ���ޤ���ʿ�Ը����ɤΰ��֤ǽ������뤫������ˤʤ��Ǥ���
- ������ϡ��ե����С��Υ��ץ����Ū�Ȥ��ƻȤ��ޤ���
- 7.��������ץ졼�ȡ�Fresnel Zone Plate lens = FZP�����ޥ�ˡ���2005.08.17��
- ���β����Ѥ�Ȥä���Ǥ���
- �̾�βĻ����ǤΥ�Ȥ��Ƥ��⡢ñ�������������Ĺ��û��X���ΰ�ǻȤ��ޤ���
- �Ļ���ΰ�Ǥϥԥ�ۡ����������Ȥ��Ƥΰ��֤Ť���������ǡ��ԥ�ۡ���������뤤���ɤ��̾�Υ����٤ưŤ��Ƽ������Ф䤹�����եȥե��������β����ˤʤ�ޤ���
- ñ��Ĺ�ǻȤ��ΤǤ���Ф����������⤷�����Ȥ���������ΤǤϤʤ����Ȼפ��ޤ���
- ʬ��ʬ�Ϥ˻Ȥ�����ʻҤϺ٤���ľ����Υ������������̤Ǥ�����������ץ졼�ȤϤ���κ٤���Ʊ���߾��Υ������ߤǤ���
- �濴��������դ˹Ԥ��ۤɥѥ�����δֳ֤�û���ʤꡢ���δֳ֤ϻ��Ѥ�����Ĺ�ȥѥ�����ο����Ѥ�ʿ���������㤷�Ʒ����ޤ���
- X���ǻȤ��륾����ץ졼�ȤΤ���κ٤����ʥԥå��δֳ֡ˤϡ��롼������Ȥä����������٥��ۤ�����Τǡ�ȾƳ����¤���ѡʥե��ȥ����ե����ˤ��Ѥ����ʥΥ�٥�Υ��������ǤǤ��Ƥ��ޤ���
- X���ѤΥ�����ץ졼�Ȥ�Ư���ϡ����礦�ɥʥΥ�٥�ǤΥե�ͥ��ȸ����ޤ��礦��
- ����ϡ�X���Τ褦������ľ�����������������äƤߤ���̾�θ��إ�Ǥϼ�«�Ǥ��ʤ���������������Ū�����Ѥ��졢X�������ν�����Ȼ���Ū�˻Ȥ��ޤ���
- �����ǻҤϡ���¤������꤫�餢�ޤ��礭�ʤ�Τ��Ǥ�����φ1mm����φ5mm���٤��礭���˸¤��뤿�ᡢ�����礭���Ǥ�X���ӡ���μ谷�Ȥʤ�ޤ���
- ���ꥳ����Ĥξ�˥���ζ�°���2.5um�θ����ˤ��ơ������Ʊ���ߤΥѥ���������Ȥ��ƺ���ޤ���
- �ѥ�����ζҤˤ�äƲ��³�����ޤ�Τǡ��٤������ۤ���Ĺʬ��ǽ���ɤ��ʤ�ޤ���
- X���Τ褦����Ĺ��û�����ϡ�����nm��٥�Υѥ�������������������ץ졼�Ȥ�X�������Υ������Ƥ��ޤ���
- �����������ǻҡ�DOE = Diffractive Optical Element��
- 2000ǯ9�����Υ̿�����Ѥ����ط��������ǻҤ��Ѥ���˾������EF400mmF4DO IS USM��EF��EOS�������AutoFocus��DO��Diffractive Optics��IS��Image Stabilizer��USM��UltraSonic Motor��ά������77���ߡ���ȯɽ��Ԥ��ޤ�����
- �������ǻҤϡ������ǽҤ٤Ƥ��륾����ץ졼�Ȥȹ�¤���ˤ�ƻ��Ƥ��ơ�����̤�Ʊ���߾�����٤ʥ�������������뤳�Ȥ��Ѷ�Ū�˲��ޤ����������������2�������碌�뤳�Ȥˤ������ع�¤�ˡ����פʲ��ޤ���������Ψ�褯������ã�Ǥ���Ȥ�����ΤǤ���
- �������ǻҡ�DOE�ˤϡ���Ĺ�ˤ�뿧������������ȵդˤʤ�Ȥ������������ꡢ���ط��������ǻҤȽ���ζ�������Ȥ߹�碌��ȡ��ˤ���ɹ��ʿ�������������ǽ�Ȥʤ�ޤ���
- ������������ǽ�ϡ�����ή�ˤʤäƤ�����ʬ���η��аʾ�θ��̤�������ȸ����Ƥ��ơ������ġ����ޥԥå��ʴֳ֡ˤ��Ѥ��뤳�Ȥ�����̥��Ʊ�ͤμ����������Ǥ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����������ħ���顢˾�������ط��������ǻҤ��Ȥ߹��ळ�Ȥˤ�ꡢ����Υ������ʤ˥���ѥ��Ȥǹ���ǽ�ʥ����ǽ�ˤʤ�ޤ�����
- ����Υ�ϡ��������ǻҤ�̿���˱��Ѥ��褦�Ȥ����ץ��������Ȥ�1995ǯ��Ω���夲��2000ǯ�˻���ʤ��������ޤ�����
- 5ǯ�κз���פ����Τϡ������߷פ⤵�뤳�Ȥʤ���ߥ�����ñ�̤ǤΥ��졼�ƥ��ù���ɬ�פʶⷿ�߷פ䡢��������ù����������ä��˰㤤����ޤ���
- ����Υ�ȯ�����������ǻҤϡ�ľ�¤�100mm���礭����������濴����7-8mm��Ʊ���߾�Υԥå���10�ߥ��������٤ι⤵����ä�������������ޤ졢�������˹Ԥ��˽����ԥå����٤����ʤ�100�ߥ��������٤ˤʤäƤ��ޤ���
- ����ˤ��Ƥ⡢�����ݤ�̿�������Ǥ��Ȥ߹�����Ȥ����ΤϤ��������ۤ��Ȼפ��ޤ���
- DOE�ϡ����塢˾����¾�˴���ǥ����ץ졼��HMD = Head Mounted Display�ˡ��վ��ץ����������������������ѥ�ʤɤ˱��Ѥ����Ԥ���Ƥ��ޤ���
��
������������������
 ���ǡ�Ʊ�����¤�Ʊ��������Υ�ʤΤˡ���������Υ������Ȥǹ�������Ƥ����Τ�����ޤ���
���ǡ�Ʊ�����¤�Ʊ��������Υ�ʤΤˡ���������Υ������Ȥǹ�������Ƥ����Τ�����ޤ���
- ����������ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �������¿���ϱ������ι�������Ǽ����ơ�������ˤ�������Υ������Ȥ����äƤ��ޤ���
- �ʤ������Τ褦�ʸ����������ΤǤ��礦����
- ��������ˤⲿ�٤�Ҥ٤ޤ���������������θ����ǽ���Ʋ�����ɤ��������뤿��ˡ��ἴ�����ΰ����������ἴ�ΰ賰�Ǥ����������ꡢʿ��������������Ϥä��ɹ��˷��������뤿��˥����������ɬ�פ��顢��������Υ������Ȥ�ȤäƤ���ΤǤ���
- �����褽�η����Ȥ��ơ���������Υ������Ȥǹ�������Ƥ����ϡ�����ǹ���ǽ�Ǥ���
- �Ƕ�Υ������̥����¤���ɼ��θ��إ��饹�γ�ȯ�ˤ�äơ�����˽���ʤ������Υ������Ȥ���ǽ���ɤ���Τ��Ǥ��Ƥ��ޤ���
- ��ε��̼������뤿��ˤϡ�ξ�̥��ξ������Ȥ߹�碌������Ū�Ǥ��뤳�Ȥ����ˤ�Ҥ٤ޤ�����
- �Ķʼ����������������뤿��ˤϡ��ʤ�ΰ��֤�Ǹ�������������оΤʥ��������ͭ���Ǥ���
- ��������Ȥ뤿��ˤ϶��ޤ�ʬ���ΰۤʤä�����Ѥ����������ޤ���
- ���Τ褦�ˤ��ơ���˾������Ū�Υ����夲�뤿��ˤ��������ʥ������Ȥ�ȤäƼ�����������Ƥ��ޤ���
- ������ϡ����ѥ��ɸ����˾���ˤ�äƤ��������Υ�������Ǥ������äƤ��ޤ���
- �����ϡ���ã���Ԥ߽Ф���������ˤ�������뤤��䥭����ɤ�����߷ס���¤���Ƥ��ޤ���
- ������Ǥ���������Ǥ��졢ʪ�Τΰ��֤����ΤǤ�����ִط���Ʊ���褦�˹ͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ������Ǥϡ���θ����濴H�ϥ��������ˤ���ޤ���
- ������Ǥ����濴�Ϥ������ޤ���
- ��������������Ǥϥ���濴��2����Ǥ��ޤ���
- ���ʤ��ʪ�Τ���Υ���濴����������H�ˤȡ���¦����Υ���濴�����������H'�ˤ���Ĥ�����ޤ���
- ��Ĥμ����ϡ�ʪ�Τȥ�ΰ��ִط��ˤĤ��Ƥ������������濴�Ȥ��ƹͤ������ȥ�δط����������������濴�Ȥ��ƹͤ��ޤ���
- H��H'�֤ϼ����ֵ�Υ�ȸƤФ���Τǥ����������줿��Υ�ˡ����ε�Υ���̣���Ƽºݤΰ��ִط�����ޤ���
- ��
- ��
- ��
- ��������Υ��Ȥä����η����δط��ʥ������δ��áˡ���2005.07.10�ˡ�2009.05.18�ɵ���
- ��
- �����̥��2��ξ��ʹ���������Υ���Ѳ��ˡ�
- ��
- ����Υ��Ȥä������ɤΤ褦�ˤǤ��뤫�ͤ��Ƹ��ޤ��礦��
- �ͤ�����ɤ����Ȥʤ�Τϥ�η��������Ǥ���
- ���θ�����Ȥä�1���ܤΥ�Ǥɤΰ��֤������Ǥ�����������2���ܤΥ���ɤΤ褦�ˤȤ館�ơ��ɤ��˺Ƥ������֤��ˤ�ä��ɤäƹԤ��ΤǤ���
- �ºݤΥ���߷פǤϤ�ä���ƻ�˸������פˤ�ä������ɤ������ޤ������桹�Τ褦������ȤǤʤ����ϡ�������������ɤ�����������ǽ�ʬ���Ȼפ��ޤ���
- ��
- ��
- ����Ū�ˡ�ʣ���Υ���Ȥ߹�碌�ˤ�����������Υ�ϡ��ʲ��μ���ɽ����ޤ���
- ����
- ��������1/f = 1/f1 + 1/f2 -�� /��f1��f2�ˡ�����������Lens - 23��
- ���������������弰�ϡ���������ƥ�ֵ�Υ��û��������Ω��
- ����������������f���������������Υ
- ����������������f1�������1�ξ�����Υ
- ����������������f2�������2�ξ�����Υ
- �����������������ġ�����ֵ�Υ
- ��
- ��
- f1 = f2 = 100mm ���̥��Ĥ�̵��Ǥ�����֤�����Ѥ���ȡ�����������Υ��Ⱦʬ�ˤʤ�f=50mm�Ȥʤ�ޤ���
- ��ֵ�Υ�ʦġˤ��������礭�����ƥ��Υ���Ƥ����ȡ����⤷�������Ȥ˹���������Υ��Ĺ���ʤäƹԤ��ޤ���
- ��=0�λ��Ϥ��褽Ⱦʬ�ξ�����Υ�Ǥ���Τˡ��� = f �λ��ϡ�Ʊ��������Υ�Ȥʤ�ޤ���
- �������ϡ����Τ褦��2��ʤ⤷���ϡ������ʤɤ��θ����2���ˤΥ���֤��Ѳ������뤳�Ȥˤ�������Υ���Ѥ����ΤǤ���
- ��

- ����������������������������������2009.05.18��M.T.�����국�ҥߥ���Ŧ��������������ޤ�����
- ��
- ����������������������������������2009.05.18��M.T.�����국�ҥߥ���Ŧ��������������ޤ�����
- �����̥�ȱ���ξ�硧������2008.06.22�ɵ���
- �̥�ȱ�����Ȥ߹�碌�Ǥϡ��̥���̥�Ǻ�������������Υ�Ȥ�ȿ���������Ѳ����ޤ���
- Ʊ��������Υ���̥�ȱ���Ǥϡ��ޤ�������Ť�碌�����֤λ��ϡ���=0 �ʤΤǹ���������Υ�ϡ�Ȥʤꥬ�饹��ʿ��ʿ�ġʤ������Ѷʤ��Ƥޤ��ˤȤʤ�ޤ���
- ���ξ��֤���Ĥ�������礭�����Ƥ����ȡ�����������Υ�Ͻ�����û���ʤꡢ
- �� = f1 �ǡ�����������Υ�ϡ�ñ���Ĥ�Ʊ��������Υ f1 �Ȥʤ�ޤ���
- ���Υ���Ȥ߹�碌�Ǥι���������Υ�ϦĤΰ�ư�ˤ�ä���ľ���Ѳ������������Ȥʤ�ޤ������ξ�硢�Ĥΰ�ư���礭���ʤ�˽��äƾ�����Υ��û���ʤꡢ��ǽҤ٤��̥�� + �̥�ξ��ΦĤΰ�ư��ȼ�äƹ���������Υ��Ĺ���ʤ�Τ�ȿ�Фˤʤ�ޤ���
- �ºݤΥ������ϡ��⤦����ʣ���ʥ�������ȤʤäƤ��ơ��㤨�С��Ĥ��Ѥ��ƾ�����Υ���Ѳ������Ƥ�������Ф����֤��Ѳ����ʤ��褦�ʹ�¤�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ξ��֤���Ĥ�������礭�����Ƥ����ȡ�����������Υ�Ͻ�����û���ʤꡢ
- ��

�����ºݤΥ�ε�ǽ�����������2005.3.20�ˡ�2009.07.02�ɵ���
- ���ޤǽҤ٤Ƥ������Ȥͤˤ��ơ��ºݤΥ�����ϤɤΤ褦�ˤʤäƤ���Τ���Ĵ�٤Ƥߤޤ��礦��
- ��ɽŪ�ʥ�����˼����ޤ���
- ���Υ�ϡ��ޥ˥奢��ե��������Υ˥å������Ǥ���
- �ǥ��������ե���餬��ή�ˤʤäƤ��븽�ߡ�2008ǯ�ˤˤ��äƤϡ����Υ��Ť������°�����Τ����Τ�ޤ���
- �ǿ��Υ�ϡ��ե��������Τ���μ�ư��⡢�ʤ��Ĵ�᤹��ʤ��⤢��ޤ���
- ���٤ƥ���餫����ŵ�����ˤ�äƥ���餬�ե������������ʤ��Ĵ�ᤷ�Ƥ��ޤ��ޤ���
- �����Ǥϥ�ε�ǽ��Ҳ𤹤뤿��ˡ��������ɥå����ʥ����˵��������ޤ���
- �桼����ɬ�פȤ����ε�ǽ�ϡ������˼���դ���ޥ�������ʱ��ˡ����̤�Ĵ�᤹��ʤꡢ�ե�������Ĵ������ե���������������ե��륿���ʤɤ����夹��ե��륿���ʤɤ˽����Ȼפ��ޤ���




������������ե��륿�����դ���ͥ����ڤäƤ��롣 �����˼���դ����ޥ���ȡ����ȳ��Ǥϡ��˥����F�ޥ���Ȥ�C�ޥ���Ȥ�����Ū�� 

�ե����������������������ƥԥ��Ĵ����Ԥ������Ƶ�Υ�����ͤ����ˡ��ʤ�ˤ��ԥ�Ȥι礦�ϰϤ����˼�����롣���Ƶ�Υ�ο��ͤϡ���ȥ�ɽ���ȥե�����ɽ����2����Ǽ�����Ƥ��롣 �ʤ���������������ƥ�ιʤ��Ĵ�᤹�롣�ʤ���ͤϡ������ͤ����2���ܿ���1.4��2��2��2.8��4��5.6��8�������ˤǿ�������ޤ�Ƥ��롣 ��������ϡ���οޤΤ褦�ˤʤäƤ��롣��Ͼ�����ΥF����äƤ��뤬��������Υ�������ξ�����Υ��F�ˤȸ���������Υ��F'�ˤ�2�Ĥ��롣������Υ�ϡ���μ�������ΰ��֤ǵ���졢�����������ξ�����Υ�Τ��������H��H'��2�Ĥ��롣�����ϡ���ˤ�ä��Ѥ�ꡢ���ΰ��֤ϥ��������䤤��碌�ʤ�������Τʰ��֤Ϥ狼��ʤ��� - ��
- ������������Focal Length��
- ��Τ�äȤ����Ū����ǽ�ΰ�ĤǤ���
- ��ϡ������λ��ʤ��������ȸ���˾������֤���äƤ��ޤ���
- �����ξ�����Υ���F�ˤ�ɽ��������������Υ���F'�ˤ�ɽ���ޤ���
- ������Υ��Ĺ���ȶ����Ϥ��夯������Υ��û���ȶ����Ϥ������ʤ�ޤ���
- ���绣�Ƥ乭���ϰϤƤ���ˤϾ�����Υ��û�����Ȥ�����Τ�Τ�����Ĥ��ƻ��Ƥ���ˤϾ�����Υ��Ĺ�����Ȥ��ޤ���
- �ʹ֤�ɸ��Ū�ʻ�ѡ�50°�ˤ��Ѥ˻��ä����ɸ���ȸ���������������ѤС������ѥ��������Ѥ��Ĥ�Τ�˾���ȸ��äƤ��ޤ����ʡ�������Υ�Ȳ�����ȡ�
- ��
- ��������
- ������ѥ�ϡ��������ޤ��뤿���ʣ���Υ���Ȥ߹�碌�ƥ���äƤ��ޤ���
- ��ξ�����Υ�����ݤˡ���θ���Ū�濴������Ȥʤ�ޤ���
- ���Υ���濴���֤������ȸƤФ���Τǡ�H�Ǽ�����ޤ���
- �̾��ˤ���Ĥμ�����H��H'�ˤ����ꤳ�μ����ε�Υ������ֵ�Υ�ȸ����ޤ���
- �̾���������Ψ���оΤʵ��̥�Ǥϥ�μ�����H��H'�ˤϥ���濴�ˤ��ꡢξ�Ԥ�Ʊ��Ǥ���
- ������ʣ���Υ������Ȥǹ���������Ǥϼ������ۤʤ�Τ����̤ǡ���̩�ʸ��ؼ����������Ȥ��ˡ������ֵ�Υ��HH'�ˤ��θ���ޤ��������ֵ�Υ���θ�������ؼ��ϰʲ��μ���ɽ����ޤ���
- ��
- D = f��2 + M + 1/M ��+ HH'������������Lens - 24��
- ����D�������Ƶ�Υ��=������Τ��黣���̤ޤǤε�Υ
- ����f�����������Υ
- ����M������������
- ����������M=b/a����b��a�ϡ�Lens - 1�ˤ������
- ����HH'���������ֵ�Υ
- ����f�����������Υ
- a = f��1 + 1 /M �ˡ�����������Lens - 25��
- ��
- b = f��1 + M�� ������ ��������Lens - 26��
- ��
- ����M:��������Ψ
- ����a����ʪ�����ΰ��֤�������H�ޤǤε�Υ
- ����b���������H'����������ޤǤε�Υ
- ����a����ʪ�����ΰ��֤�������H�ޤǤε�Υ
- ���� ��2009.07.02��Len-24�ε��Ҥ˸��꤬����ޤ�����
- 2009.06.27��S���ꤴ��Ŧ�������������ޤ�����S����ɤ��⤢�꤬�Ȥ��������ޤ�������
- ��μ��ϡ������ֵ�Υ��HH'�ˤ��θ�����줿���Ƶ�Υ��D�ˤȥ������Υ��f�ˡ�������Ψ��M�ˤ�ɽ������ΤǤ���
- ���μ��ϡ����绣�Ƥ�Ԥ��Ȥ��λ��Ƶ�Υ��������ͭ���Ǥ���
- �ޤ���������H��H'�ˤ��Ȥ�����ΤޤǤε�Υ��a�ˤȷ������֤ޤǤε�Υ��b�ˤ��μ��Ǵ�ñ�˵��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ������Ψ������������M<<1/100�ˡ�b���ʤ���������֤ϸ¤�ʤ�������Υf�˶�Ť���a��ʪ�ΤޤǤε�Υ�ϡ�������Υf�˻�����Ψ�εտ���1/M�ˤ�ݤ����ͤˤʤ�ޤ���
- ���绣�ƤʤɤΤ褦��M���ͤ�1�����礭���ʤ�ȡ�ʪ�Τΰ���a�ϸ¤�ʤ�������Υf�˶�Ť����������֤���ΨM�����㤷�ƾ�����Υf���ܿ��DZʤ�ޤ���
- M=1�ǡ�a=b=2f���Ĥޤ���Ѥ����ξ�����Υ��2�ܤΰ��֤�ʪ�Τ�������֤��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��
- ����������ȹʤ��Aperture Ratio, Diaphragm��
- ���褯�����f50mmF2.0�Ȥ����褦��ɸ���˽вޤ���
- ����ե��٥åȤΡ�F�פ���Ĥ�ФƤ��ޤ���
- ��˾ܤ������ʤ顢����ɸ���κǽ餬��ξ�����Υ��ɽ��������ɸ����������뤵��ɽ����ΤǤ��뤳�Ȥ��ΤäƤ��ޤ���
- ������Υ��ɽ��f50mm�Ȥ���ɸ���ϡ�������Υ��focal length�ˤ�50mm�Ǥ���Ȥ�����̣�Ǥ��ꡢ����Ϥ褯����Ǥ��ޤ���
- �������ʤ�ΰ�̣��F�Ȥ����ΤϤɤ�������̣����ĤΤǤ��礦����
- �Ѹ�Ǥϡ��ʤ��Diaphragm�Ȥ������դ�����Τˡ�������F.stop�Ȥ�F number �Ȥ������դ����ƤƤ��ޤ���
- ���θ��դ�������ͳ�褷�Ƥ��뤫�ϡ���F�ͤ�ͳ����ΤȤ����ǽҤ٤ޤ�����F�ͤϡ��������Υf���Ф������¤���Ǽ�������ͤǤ���
- ��
- ������ޥ����
- ��ޥ���Ȥϡ������˼���դ��뤿��θ���ǡ��ȤƤ���פʰ�̣����äƤ��ޤ���
- ͭ̾�ʥ�ޥ���ȤȤ��Ƥϡ�������CCD������CMOS�����ˤ˻Ȥ��Ƥ���C�ޥ���ȤǤ��ꡢ35mm����ե����˻Ȥ��Ƥ���˥���F�ޥ���ȡ������ɤ�ENG�����˻Ȥ��Ƥ��륽�ˡ�ENG�ޥ���Ȥʤɤ�����ޤ���
- ��ޥ���Ȥ����Ū�ʰ�̣�ˤĤ��Ƥϡ�����Τ��������פǽҤ٤ޤ�����
- ��������߷�
- ����߷פϡ��桹�桼����ľ�ܤ˴ؤ�뤳�ȤϤ���ޤ���
- �桹�ϡ�����礤�Υ��Ȥ����ɤ��Τǥ���߷פʤɹͤ��ʤ��Ƥ�褤�ΤǤ���
- �����������Ȥ��桼���Ǥ��äƤ⡢�ɤΤ褦�˥���߷פ����Τ��Ȥ������פ��ΤäƤ������Ȥϡ���ȴؤ�äƤ�����Ƿ褷��̵��̣�ʤ��ȤǤϤʤ��Ȼפ��ޤ���
- ��ϷݽѤβ��Ǥ���Ȥ���Ƥ��ޤ���
- �������ˤ��줤���ᤫ�줿�����������ǽŪ�Ǥ���
- ������������ǽŪ�ʥ�⡢�����߷פ˺ݤ��Ƥ��߷�������ޤ�ˤ�¿���������ȳ�Ʈ���ʤ����Ŭ�ʥ���߷פ��ʤ���Ƥ��ޤ���
- ����߷פǤ��߷ԤΤҤ�����ƻ�ʸ���������ɬ���Բķ�Ǥ�����
- ����ԥ塼���Τʤ��ä�����������������䤵�줿���֤�������ʤ���ΤǤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ʲ��ˡ��ܳ�Ū�ʼ̿���γ�ȯ�аޤȼ̿�����߷פˤĤ��ƾҲ𤷤ޤ���
- ��
- �ڥڥåĥС����Petzval�ˤȼ̿����
- �̿�����߷פδ��ܤϡ����ߤˤʤäƤ�19�����ΥڥåĥС����Jozeph Miksa Petzval : 1807.01.06 - 1891.09.17�������Х����͡ˤλ��夫���Ѥ�äƤ��餺���������ס�ray tracking�ˤȤ�������ˡ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �������פϡ��ɥ��Ŀͤ��ե饦��ۡ��ե�����Joseph von Fraunhofer : 1787-1826�����ͰƤ�����Τȸ����Ƥ��ޤ���
- �̿���ξܤ������ϡ����ܤ����ƽҤ٤�Ȥ��ơ������Ǥϡ��ܳ�Ū�ʼ̿���������Ȥ��ƤΥڥåĥС���β̤��������ȡ��ڥåĥС���ʸ�μ̿�����פ�Ҥ٤ޤ���
- �����ơ��ʤˤ���̿�������߷פ��ˤ��Ǧ�ѤΤ����ȤǤ��뤳�Ȥ�Ҳ𤷤����Ȼפ��ޤ���
- �ڥåĥС���ϥϥ���ޤ�ο��ؼԤǡ��������ȥꥢ�Υ���������ؤǿ��ض����ο������ƥ�ץ饹�ο��������ʥ�ץ饹�Ѵ��ˤ椷�Ƥ��ޤ�����
- �����ڥåĥС���ο������̿����
- ����߷�ˡ�ϡ���θ���μ�ή�ǤϤʤ��ä��褦�Ǥ������Ҥ礦��ʤ��Ȥǥ���߷פ˴ؤ�뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- 1839ǯ�βƤΤ��ȤǤ���
- �ե�Υѥ�ʳإ����ǥߡ������Υ��饴����������μ̿��Ѥ�ȯɽ���Ƥ��顢��ǽ���ɤ��̿����ɬ�פˤʤ�ޤ�����
- ���饴�ȸ�ή�Τ��ä�����������ض����Υ��åƥ����ϥ������Anrease von Ettingshausen�� �ϡ��̿��Ѥ�ȯɽ��ʹ���Ƽ̿����ɬ�������˴���������塢Ʊ����ؤο��ؼԤǤ���ڥåĥС�����߷פ���ꤷ�ޤ�����
- ��ϡ�����������1840ǯ���߷פ���ꤷ����������θ������������ˡ��ͤ������ơ��ݡ��ȥ졼���ѿ��ä������¤���ޤ�����
- 1840ǯ�ϡ��������ζἴ������������ȯɽ���줿ǯ�Ǥ�����������߷פ����Ū�ʼ���������Ǥ��������ǥ��μ�������1856ǯ�ˤ��Ф�16ǯ�����λ��Ǥ�����
- ����Ф������Ū�������դ��Ϥޤ���ʬ�ǤϤʤ��ä�����Ǥ���
 �ڥåĥС���ϡ�����ο���Ūǽ�Ϥǰ쵤�˹���ǽ�����夲�Ƥ��ޤä����Ȥˤʤ�ޤ���
�ڥåĥС���ϡ�����ο���Ūǽ�Ϥǰ쵤�˹���ǽ�����夲�Ƥ��ޤä����Ȥˤʤ�ޤ���- ���Υ�ϡ������Ȥ��Ƥ�����˥����������١������椬F3.4��16�ܤ����뤯�������Ϥ���ʤ�ͥ�줿����ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��˥�������Ȥϡ��ᥬ�ͥ�Τ褦��ξ�̤�Ʊ�������ζ��̤Ǥ�����Τǡ�ξ�̤ǤϤʤ��������̤Ǥ⤦���������̹����Ȥʤ����ΤȤ����̤���ǽ����ĥ�Ǥ���
- �ڥåĥС����ϡ�4��Υ�ǹ������졢������Υf=149mm�ǡ�������F/3.4��φ90mm�Υ���������������äƤ��ޤ�����
- 35mm����ե����Υ���������������4�ܡ�2/3�����CCD�����λ������ꥢ���8�ܤ��礭�ʥ�Ǥ���
- ���Υ���߷פˤ����äƤϡ�������ǽ�Ϥ����ǤƤ����������ȥꥢ��ˤʼ���ľ��⤬����Ф��졢�������˶��Ϥ����Ȥ����ä��ĤäƤ��ޤ���
- ���Υ�ˤ�äơ����衢30ʬ�ʾ��Ϫ���ˤ����äƤ������Ƥ�1ʬȾ��û�̤Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����������Фơ��ڥåĥС���Υ�ϥ������ȥꥢ�θ��ز�ҡ�Peter Friedrich Voigktl��der��ˤ��ե����ȥ������ҡˤμ�ˤ�ä�1841ǯ�����ʲ����졢�����ƥѥ�����������˽�Ÿ����������������Ƥ��ޤ���
- ���μ̿�����о�ϡ����������L.J.M. Daguerre��1787-1851�����������������ȯ�����̿��δ��ä��Ǥ���2ǯ��Τ��ȤǤ���
- �ե����ȥ������ҤΥ�����ϡ��ĥ�������饤�ĤΥ�������Ǥ���ޤǤδ֡�ͥ���ʥ�Ȥ��Ʒ��פ��ޤ���
- �����ڥåĥС�������μ̿����
- �̿���ȯ�����줿�������Ĥޤꡢ�ڥåĥС��뤬���뤤�ڤ���ɤ���������ޤǤϤ��������̿���ʤɤʤ����������ʤ�Ȥ����������٤Τ�Τ��ä����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������뤬�Ѥ�����ϡ����ʲ�Ȥ������Ȥ��ȤäƤ�������饪�֥�������ѤΤ�Τǡ����Υ���������ѹ��ʪ���ؼ������饹�ȥ��William Hyde Wollaston��1766-1828������ä���ΤǤ���
- �̿�����������ޤǤΥ���饪�֥������ϡ��ܤǸ����ʪ�����ʤ�ž�̤���Ǥ��ä��ΤDz�Ѥ�40-50�٤Υ�������Ƥ��ޤ�����
- ���Τ褦����Ū���鹭����ñ��Ǥ����˥���������о줷���ΤǤ���
- �����饹�ȥ�ϡ������ᥬ�ͥ�μ����椷�Ƥ��ơ�������ư�����Ƥ�ʴ�夬��ž���Ƥ���ɼ������������������ʤ�����������������Ū�˽���ƹ��ѤС������˥�������θ����ԤäƤ��ޤ�����
- ���Υ�˥�������ϡ�������Ȥ��Ƥ��ɼ��ʤ�ΤǤ�����
- �����ǡ���ϱ���ѥ�˥���������֤��˻Ȥ�������1812ǯ�˹ͤ��Ф������60°��ñ�̼̿������ޤ�����
- ���Υ�ϴ���ѤΤ�Τǡ������դ��˻ȤäƤ��뤿��ˡ���ιʤ���ܤ�Ʒ��Ʊ�����֤��礭���˥��åȤ���Ƥ��ޤ�����
- ����饪�֥����������ʤ�̤���ꡢ����ԥĤǤʤ���ˤϤ��Υ���ä��礭������ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ���������̿������ब�Ǥ��ơ��̿������Ѥ˻Ȥ���Ȥ��Ƥϼ������μ������礭���Τǡ������쥪�Ͼ�����Υf=340mm�Ǹ���φ81mm��������̤˹ʤ�����줿������F14�Υ���Хꥨ���Chevaliers' lens�ˤ��ˤ��Ĥ館�ޤ�����
- ����Хꥨ��Chevalier�ˤϥե�θ��ص��ѼԤǤ���
- ���Υ�ϡ��ե��ȥ��饹�ȥ��饦�饹��Ž���碌�ƿ��ä���ޤä���˥�������Ǥ�����
- ����Хꥨ�κ�ä���Ǥ�Ť��ä��Τǡ��ڥåĥС��뤬�о줷���Ȥ����櫓�Ǥ���
- �ڥåĥС���Υ�⡢������������������Ǥ������̼�����������������������ʬ�ˤȤ�Ƴ������ɹ��ʲ����������Ϥ�����ΤΡ��������������Ѷʤ��Ӥ��������20°���٤������Ѥ��Ѥ��ޤ���Ǥ�����
- ���Τ���ˡ����ȯ��������ϲ�Ѥζ��������Ѥ˻Ȥ�졢��ʪ�����ѤΥݡ��ȥ졼�ȥ�Ȥ���ͭ̾�ˤʤäƤ����ޤ���
- �����̿���ΰ��֤Ť�
- ˾����串������1600ǯ����ȯ������Ƥ��ޤ����顢�̿���ϡ�240ǯ��ФƼ̿������������Ǥ�����ˤ�����ɽ����ƤǤ��Ƥ����ʹ��Ǥ���
- ˾����串������ʬ��ǤϿ��ä��ε��Ѥ�ʤ���ǽ�Τ褤����Ǥ��Ƥ��ޤ�����
- ����Ǥ�ɥ��ĤΥե饦��ۡ��ե����������٤ι⤤���饹�����Ф���1810ǯ���˻�äƤ⡢���뤤��ϤǤ��ʤ��ä��褦�Ǥ���
- �ʼ��Τ褤���إ��饹���Ǥ���褦�ˤʤä��Τϡ��ڥåĥС��뤬����ä�30ǯ�ۤɸ�Τ��ȤǤ���
- �����٤��ʼ��ΰ��ꤷ�����إ��饹�������褦�ˤʤä��Τϡ��ɥ��ĤΥ��å٤ȥ���åȤλ���ˤʤäƤ���ǡ�1889ǯ�Τ��ȤǤ���
- ����ǯ������åȼҤˤ�äƥХꥦ�९�饦�饹����ȯ����ơ������Ѷʤ���������������Ǥ��륢�ʥ������ޡ��ȥ�������褦�ˤʤ�ޤ�����
- 1900ǯ��ۤ�����켡����������̤��ƥ���ء��̿����ؤϵ�®�˿�Ÿ���Ƥ����ޤ�����
- ���������桢�ƹ��Kodak�Ҥϴ����६�饹��ȯ�������줬��������¥�����ึư�ϤˤʤäƤ����ޤ�����
- �̿���ȯ����ȯŸ�Ȥ���ݡ��Ȥ������뤯���ڤ���ɤ��ڥåĥС����ϡ�����Ū��ͭ̾�ˤʤ�ޤ������༫�ȤϤ��β��äˤ������餺�������ۤ����Τ���¤��Ҥ�Voigktl��der�ҡʥե����ȥ������ˤ��ä��ȸ����ޤ���
- ���β�Ҥϡ��ɥ��ĤΥĥ��������饤�ļҤʤɤ�ͥ���ʥ������ȯ����ޤ�ͥ���ʥ����ȥ���������Ƥ��ޤ�����
- �ڥåĥС���κǸ���Ϥ����ä��ȸ����ޤ���
- ��ϡ����Τۤ���˾����䥪�ڥ饰�饹���߷ס���¤�ˤ�Ȥ��ޤ�����
- �ڥåĥС�����粼���ˡ�ʪ���ؤ�ͭ̾�ʥܥ�ĥޥ��Ludwig Boltzmann�ˤ����ޤ�
- �ڸ������ס�
- �������פϡ�����Τ�Ǥ�դΥݥ���Ȥ�������ӡ����Υݥ���Ȥ�������ܤθ���������Ф��ƥ�����ͤ����ޤ���
- ����̤����ͤ��������ͥ��ˡ§��Ŭ�Ѥ������ʹԤ��Ƥ���������ϩ���༡�ɤ������ơ��Ǹ�Υ���̤���Ф������������̤Τɤΰ��֤�����夯����ðǰ�˷����Ƥ����ޤ���
- �Ǹ�η���̤ϡ����̤�Ӥ���ɸ�κ����鲣������Δy��Δz�ˤ�����졢�����������ȸ�����֤���ļ�����Δχ�ˤ������ޤ���
- ���θ������פϡ����ͥ��ˡ§����ܤȤ��Ƥ��ޤ����顢���Ѵؿ���������Ȥʤ�����٤�7�夬ɬ�פȤʤ�ޤ���
- 7��η��ϥ���ԥ塼���ǹԤ���24�ӥåȿ��ͤˤʤ�ޤ���
- 8�ӥåȽ����Υѥ�����Ǥ�3���ʬ����ɬ�פ�����Τǡ����ȥ쥹�ʤ�����Ԥ��ˤ�32�ӥå�CPU���ۤ�����Ǥ���
- 32�ӥå�CPU�ϡ��ѥ�����Ǥ�1990ǯ��Ǽ¸����줿��ǽ��Pentium4��32�ӥå�CPU�Ǥ���
- 1960ǯ���ޤǤϡ�����ԥ塼������ڤ��Ƥ��餺�������ε��Ѽ�ã�ϻ��פ�7����п�ɽ���п�ɽ�Ϥ������ȳ�껻�줾�������Ȱ��������Ѵ������Ǥ���ΤǷ����֤���ְ㤤�����ʤ��ä��ˤ��Ѥ��ơ���Ͱ��Ȥ�1����˷���̤�ȹ礷���������ɻߤ��ʤ���������פ�ԤäƤ��ޤ�����
- �̾���4�礫��6�����٤��ꡢ���1�Ĥ��Ф��Ƥ�ξ�̡�2�̡ˤ���Τǡ����8�̤���12�̤η���ɬ�פˤʤ�ޤ���
- ���θ������פ���䤵�����ϡ����������ͤ�1��������5ʬ����10ʬ�����ꡢ12�̤����Ǥ�1�ܤ����פ���Τ�2�������٤����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �������פϡ�1�ܤǤϤʤ�ξ��������줺������Τ���50�����٤θ�����Ф��������פ����뤿�ᡢ50�ܤθ������פǼ����ξ������İ�����ˤ�100���֤η���ɬ�פˤʤ�ޤ���
- 1��8���֤�ϫƯ�Ȥ���12.5������2���֤�ϫƯ��ɬ�פȤ��ޤ�����
- ���ϡ�����ǽ���ä��櫓�ǤϤ���ޤ���
- 2���֤η��ˤ�äơ���μ����Τ����褽�η������İ��Ǥ����˲�ޤ���
- ���η���̤��ˡ���ζ�ΨȾ�¤��Ѥ����ꡢ�������Ȥδֳ֤������Ѥ����ꤷ�Ƽ����β����η������ɤ��ʤ��顢��Ŭ�ʼ�«������������ɴ��Ȥʤ������֤��ޤ���
- ��κ�Ŭ������뤿�ᡢ100��η���Ԥä��Ȥ���200���֡�4ǯ��κз�����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���̤ϡ������륰�롼�פ��Ĥ��˼�ʬ�����ƺ�Ȥ�ʤ�뤿��ˡ�4ǯ�Ϥ�����ʤ��ˤ��Ƥ�1ǯ���٤��߷״��֤����������Ǥ��ä����Ȥ����������ޤ���
- ����ԥ塼������˾����Ƥ����߷�ʬ��ΰ�Ĥ�����߷פǤ��ä����Ȥ����Τ��Ȥ��齽ʬ������Ǥ���Ȼפ��ޤ���
- �ڥ���ԥ塼���ˤ��������ס�
- �����Ǻǽ�˥���ԥ塼������ȯ���줿�Τ��ƹ�ǡ��ߥ��������ƻ���˻Ȥ��ޤ�����
- ���ܤǥ���ԥ塼���������줿ư���ϡ������߷פˤ���ޤ�����
- 1956ǯ3��ٻμ̿��ե����β���ʸ���� ��1914-1998�ˤμ�ˤ�� 1700�ܤο����ɤ��Ѥ�����FUJIC�פȤ�������ԥ塼������ȯ���졢����߷פ˻Ȥ��ޤ�����
- �����������ԥ塼����Ƴ����˾�ޤ�Ƥ��������ξڵ���ȸ����ޤ���
- �����ϡ�1939ǯ����������ؤ�´�ȸ塢�ٻμ̿��ե��������Ҥ�����߷פ�ô��������ǡ�10ǯ���1949ǯ�˥���ԥ塼���ˤ������ˡ�γ�ȯ����ꤷ��20���ߤ�ͽ����7ǯ���1956ǯ3��˴����������Ǥ���
- ���줬���ܤι��ˤ���Υ���ԥ塼���Ǥ�����
- ���Υ���ԥ塼���ϡ������å����ȿ�30KHz��2��ˡ3���ɥ쥹��3�ӥåȡˡ�255WORD�����4080�ӥåȡˤ�Ķ���ȿ���ٱ����ˤ�뵭�����֤���ä���Τ��ä������ǡ��ø��黻�� 0.1ms = 1/10,000�á�����黻��1.6ms =1/625�� �ǹԤ��ޤ�����
- ������ǽ�ϡ��ͤˤ�����2,000�ܤ���ǽ���ä������Ǥ���
- �Ĥޤꡢ�߷��֤�1/2,000��û�̤��줿���ˤʤꡢ1ǯ�η���Ⱦ�������û�̤��줿���Ȥˤʤ�ޤ���
- ���Υ���ԥ塼���ϡ���ȯ����Ƥ���2ǯȾ�δ֤��ٻμ̿��ե����ξ��ĸ�����Ǽ��⡢�ҳ��Υ���߷פ˳������������Ǥ���
- ���ߤΥ���߷��ѤΥ���ԥ塼���ϡ�1�ô֤�800�̤�η���ۤɤ���ǽ���夬�äƤ��뤽���Ǥ���
- �ͼ�˴�äƤ�������μ¤�250,000�ܤι�®�黻�ˤʤ�ޤ���
- ����ԥ塼���Τ������ǥ���߷פϤ��®����Ŭ���������������褦�ˤʤ�ޤ�����
- �������Ȥ�¿����������ȯŸ�⡢�ץ饹���å���ˤ������̥���߷פ⥳��ԥ塼���ٱ�ʤ����Ƥ������ʤ��ä����ȤǤ��礦��
- ����
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
|
|
||||
����������Aberrations������2005.09.20��
- ��ϡ��Ŷ��Τ��ޤ�Τȸ����Ƥ��ޤ���
- ���������Ŷ��Ȥ����ɤ�桹�ˤ��Ф餷�����������Ƥ������ܡפǤ���櫓�Ǥ����顢�Ŷ��μ������㤦�Τ������Τ��Ȥǡ�����ޤ�¿���Υ���߷Ԥ������������ᤷ��̤Υ����夲�Ƥ��ޤ�����
- ��ˤϤ��������ʼ���������ޤ���
- ��Ĥμ�������������Ȥ����¾�μ������礭���ǤƤ��Ƥ��ޤ���������Ω�Ƥ�Ф�����Ω�����Ȥ�����ȿ�������ʤ���äƤ��ޤ���
- ��ˤϡ��ʲ��˼����褦���礭��ʬ����ñ���Ǥμ����ȿ���������Ĥ�����ޤ���
- ����ˡ�ñ���Ǥμ����ˤ�5�Ĥμ��������ꡢ�������ˤ�2�Ĥμ������Τ��Ƥ��ޤ���
- ñ������5�Ĥμ����Τ��Ȥ�����3���ο�����Ȥä�����Ū��ɽ�����ɥ��Ŀͤ�ŷʸ�ؼԡ����ؼ������ǥ��L. Seidel�� 1821-1896���ˤ��ʤ�ǥ����ǥ��5�����ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ��
- ��
- ��
| �������̼�����-������Ǥξ��������ʤ���
��������������-���������Ǥξ��������ʤ��� ������������-���������������Τ褦����������� �����Ķʼ�����-�������Ĥߡ� ���������Ѷʡ�-�������̾���������ޤ�ʤ��� |
||||||||
| ��
�� �� �� |
����ñ���Ǥμ���
|
�� | ||||||
|
����
|
||||||||
| �������������-����Ĺ�ˤ�����Ψ�ΰ㤤�Ǹ����Ǥξ��������ʤ���
������Ψ��������-�����ˤ�ä�������Ψ���ۤʤ롣 |
||||||||
|
����¿���μ����ʿ�������
|
||||||||
���������� ��Chromatic Aberration��
- �������ϡ����������ǵ��̼����Ȥʤ��ǰ����礭�ʼ����Ǥ���
- ¾�μ����ϸ����μ��դ˸����Τ��Ф����������ȵ��̼�������Ĥϼ�����濴���ˤǤ⸽��ޤ���
- ���äơ����μ����Ϻ���Ū�ʼ����Ȥ�����ޤ���
- �������ϸ�����Ĺ�˰�¸���Ƥ��뤿�ᡢ��������Ѥ�ȼ���¤괰���ˤϽ���Ǥ��ʤ���ΤǤ���
- ���˹��������䡢����ʬ��������ץꥺ�ࡢ�������饹������˿���ʤɤ��̤��Ƹ���ʪ�Τμ��դ����֤��Ĥˤˤ���Ǹ����뤳�Ȥ�и�����Ƥ���Ȼפ��ޤ���������ϸ�����Ĺ�ˤ�ä�����Ǥζ���Ψ���Ѥ�äơ����Τ���˸�ϩ���Ѥ�뤳�Ȥ˵������Ƥ��ޤ���
- ������ͳ�ˤ�ꡢ�����ѤΥ�Ǥϡ����������Ĺ�ˤ�äƾ���������뼴�������Axial Chromatic Aberration�ˤ����졢�������Ǥ���Ĺ�ˤ�ä������礭�����ۤʤ���Ψ��������Lateral Chromatic Aberration��Chromatic Difference of Magnification�ˤ�����ޤ���
- ������Υ��Ĺ��˾���䡢����Ψ�ι⤤��������ǤϿ������ϸ�����ɽ��ޤ���
- ������������Τϡ��̥�ȱ�����Ȥ߹�碌����������ϤǶ��ޤ��Ǥ��ä��������ͭ���ǡ�����˲ä�����ʬ�����إ��饹��Ȥ��Τ�ͭ���Ǥ���
- ���Ū�˸��ޤ��ȡ�����������������ϥ���Ǥ������Ū�ᤤ��������ǧ�����졢2����Υ���̥�ȱ���ˤ�Ž���碌��Ȥ������ä���ˤ�ä�ã���������ޤ�����
- �Ļ����Ĺ�����2��Ĺ���äƿ������������ä�������ޡ��ȥ�ȸ�����3��Ĺ�ˤ�뿧����������ݥ����ޡ��ȥ�ȸ����ޤ���
- ���ä��������ϡ��ɥ��ĤΥ����롦�ĥ������ҤΥ��å٤�����Ū��Ƴ���Ф��ơ����ݥ����ޡ��Ȥϸ�������Ȥ������ʲ����ޤ�����
- ��

- ��
- ��

- ��
- ��α��Υ���աʡֿ�������ȿ������������ٹ礤�סˤˡ���������������Ȥ��ʤ���Ǥ���Ĺ�ˤ�뼴��������ٹ礤��ɽ���ޤ�����
- ñ��Ǥϡ�d����������֤Ȥ��������Ŀ��������ֿ����˸����äƤۤܰ�ľ���˼������ФƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ��ʰ켡�����ˡ�
- �������ޡ��ȥ�Ǥϡ�F����C���μ���Ǥξ������פƤ��ޤ���
- ����������������ǤϾ����������ư���������ȤʤäƤ��ޤ���
- ��̣�����Τϡ��Ŀ�����糰�ˤ�������Ĺ�Ǥϡ��ֿ������ֳ�������������˿��ӤƤ��뤳�ȤǤ���
- �糰���������Τϡ����إ��饹������⤵�뤳�Ȥʤ��顢�糰��θ����ʿ������Τ���Ǥ���
- �糰�����Τ��Ϥ������������Τϻ���ζȤǤ���
- ��
- �����������λ�ɸ��-�����åٿ�
- ���ݥ����ޡ��Ȥϥ������ޡ��Ȥ�2��Ĺ�ˤ�뿧���������˲ä������3������Ĺ��ȤäƼ������ä���ΤǤ���
- ���ݥ����ޡ��Ȥμ��������ϡ�d���ξ������֤ͤ��ͤȤĤ���Υ�줺�˴��ź�äƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���ݥ����ޡ��Ȥο���������������3�������ˤʤäƤ��ޤ���
- ɽ�Ǥϡ�C����F��������˻糰����3���Ǿ����ΰ��פ�����ޤ����������Ū�ˤ�ä�3���ܤ���Ĺ��Ǥ�դ˷��Ƥ���褦�Ǥ���
- �������������ϡ����å٤�Ƴ�����ʲ��Υ��åٿ����礭���߷����ǤȤʤ�ޤ���
- ��
- ����������d = ��n d -1��/��n F - n c�ˡ���������Lens - 27��
- ����������������d ����d���ˤ�������إ��饹��ʬ���͡ʥ��åٿ���
- ��������������n d���������ˤ��������Ψ
- ��������������n F���������ˤ��������Ψ
- ��������������n c���������ˤ��������Ψ
- d��F��C���������ϥإꥦ��ȯ���˴ޤޤ��589.3nm�ε�����F���Ͽ���ȯ���˴ޤޤ��486.1nm�ε�����C���Ͽ���ȯ���˴ޤޤ��656.3nm�ε��������ʤߤˡ�D���ʥ���ե��٥å���ʸ���Σġˤϡ��ʥȥ��ȯ����ʣ��������������Ǥ���589.3nm�����åٿ��ϡ�����ʥȥ��ε�����D�����Ȥ��Ƥ���������˵��ʣ���ε��������ä����٤������Ŭ�ڤǤʤ����ᡢ�إꥦ��ε����Ǥ���d�����Ȥ���褦�ˤʤä���
- ���Υ��åٿ����Ѥ��ƿ��ä�����߷פ�Ԥ��ޤ���
- ���åٿ��Ȥ����Τϡ����إ��饹����Ĺ���Ф������Ψ���Ѳ����ٹ礤�������ڥ��ȥ����Ĺ��ȤäƵ�ᡢ��Ĺ�֤η����Ȥ��Ƶ���ΤǤ���
- �Ļ���ΰ����Ĺ���Ф���Ʊ������Ψ���ä����饹�ʥץꥺ����̤Τʤ����饹�ˤǤ���С����åٿ��������礭���ͤȤʤ�ޤ���
- ���åٿ��ι⤤���饹����ʬ�����饹�ȸ����ޤ���
- ��ʬ����ͭ̾�ʸ��غ����˷��Ф�����ޤ���
- ����߷פϡ����٤Ƥ��Υ��åٿ������ܤȤʤäƤ���Τǡ����ݥ����ޡ��ȥ�Ǥ�d����F����C�����������Ĺ�Ǥ���d���Ȥ�F���Ȥ����Τϡ��ɥ��Ŀ��ե饦�ۡ��ե�����Joseph von Fraunhofer�� 1787-1826�������ۤΥ��ڥ��ȥ뵱����ȯ�������Ȥ��ˡ���������Ĺ�̤˽��֤˿��ä���ΤǤ���
- �����߷פǤϡ����å٤�������Ĺ�ǥ��åٿ�����������Τǽ��פʰ�̣����Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���
- �������������ϡ��ʥȥꥦ���ȯ������Ǥ�dz��ȯ�������Ū��ñ�˼��Ф����Ȥ��Ǥ�����Ĺ�Ǥ��ä����ᡢ���إ��饹��¬�ꤹ��ݤ������Ǥ�����
- ����������d = ��n d -1��/��n F - n c�ˡ���������Lens - 27��
- �����������������硢���Ȥ����d����F����C���Ǥμ���ΰ��פ褦�����ꤹ��ȡ��ֿ������Ŀ��������ʤ�Υ��Ƥ��ޤ����ᡢ��Ū�ˤ�äƤϻ糰���˼���ΰ��פ����ƲĻ�����̤ˤ錄�ä��ɹ��ʼ�«�Ƥ���褦�Ǥ���
- ���å٤ϡ�1868ǯ�����ݥ����ޡ��Ȥθ���������Ƴ���Ф��Ƥ��ޤ��������ºݤΥ��ݥ����ޡ��Ȥθ��������Ǥ���ޤ�20ǯ�����äƤ��ޤ���
- 3��Ĺ�Ǥο��ä����Ǥ�����غ������Ǥ��ʤ��ä�����Ǥ���
- ���ݥ����ޡ��ȥ�����ʲ��Ǥ���褦�ˤʤä��Τϡ���ʬ�����غ����Ǥ���եò����륷����ʷ��С˷뾽������Ǥ���褦�ˤʤäƤ���Ǥ���
- ���������Ф�ŷ������ˤ��������������Ȥ��Ǥ�����ŷ���Τ�ΤϾ������ΤǸ������Ǥ������ݥ����ޡ��ȥ�����ʲ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- ���äơ����ݥ����ޡ��ȤȤ����������ϼ�˸���������Ф��ƻȤ��Ƥ��ޤ�����
- ���줬�������礭�ʥեò�ʪ��LiF��CaF�ˤ��Ǥ���褦�ˤʤäơ��̿���ˤ�Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �������������������
- ���������������뼰�ϡ���Υ��åٿ���Ȥäưʲ��Τ褦��ɽ���ޤ���
- ��
- ������1/��f1����1�� + 1/��f2����2�� = 0����������Lens - 28��
- ������������f1 �� f2�������ä���Ԥ�2��Υ�ξ�����Υ
- ��������������1 ����2�������ä���Ԥ�2��Υ�Υ��åٿ�
- ��
- ������1/��f1����1�� + 1/��f2����2�� = 0����������Lens - 28��
- ���ξ��˹礦�������Υ�ȸ��إ��饹�����٤п��ä��������夬��ޤ���
- ������Ʊ�����إ��饹��ν1 = ν2�ˤ�Ȥäơ�f1 = - f2 �Ȥ���ȡ���ξ����������ΤΡ�����Ǥ�ñ�ʤ륬�饹�ĤˤʤäƤ��ޤäơ���Ȥ��Ƥ��ѤϤʤ��ޤ���
- ���äơ�ξ�Ԥξ�����Υ�ϰۤʤä���Τ����ꤷ�����ξ�����Υ��ʬ���ΰۤʤä����إ��饹��Ȥ��Ȥ�����ˡ�ˤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ�ޤ���˾���������Υf����ޤ������ξ�����Υ�ϡ�
- ��
- ������1/f1 + 1/f2 = 1/f����������Lens - 29��
- ��
- �ǵ����ޤ���
- ������Υf�����ˤϡ����̤꤫��f1 �� f2���Ȥ߹�碌���ͤ����ޤ���
- �������Ȥ߹�碌���Ф��ơ���˽Ҥ٤�ʬ�����θ������������������Ȥäƺ�Ŭ�ʥ��饹�����Ƴ���Ф��ޤ���
- �ޤ��������Ȥ߹�碌�Ǻ�Ŭ�ͤ���ޤäƤ⡢�����Ȥ߹�碌����ˤϡ������Ѷʤ���������Τ����뤿�ᡢ�ʲ��μ����ڥåĥС�����¡�Petzval sum�ˤ��������ʤ���Фʤ�ޤ���
- ��
- ������1/��n1��f1�� + 1/��n2��f2�� = 0����������Lens - 30��
- ����������n1 �� n2�������ä���Ԥ�2��Υ�ζ���Ψ
- ��
- ���Τ褦�ˤ��ơ�����ƹԤäƺ�Ŭ�ʿ��ä�����Ȥ߹�碌����ޤ�ޤ���
- ���������������������Ȥ߹�碌�ϡ��ʲ��η����˼���ޤ���
- ������1/f1 + 1/f2 = 1/f����������Lens - 29��
- �����̥������Ψ���⤯��ʬ�����㤤���饹�ʥХꥦ�९�饦�饹��
- �������������Ψ���㤯��ʬ�����⤤���饹�ʥե��ȥ��饹��
- ���ξ��Ǻ�Ŭ�ʿ��ä������Ƥ����ޤ���
- ����åȤ�ͥ���ʸ��إ��饹�����1886ǯ�ˤޤǤϡ��̥�����ǻȤ���������Ψ���⤯��ʬ�����㤤�ʥ��åٿ��ι⤤�˸��إ��饹������ޤ���Ǥ�����
- ����åȤ���ȯ�����Хꥦ���ޤ���ť��饦�饹��SK���饹�ˤˤ�äơ����ä������ǽ�����夷�ޤ�����
- �ޤ��������������1943ǯ�ˤκ��桢�ƹ�Kodak�Ҥ�����˿��������إ��饹��ȯ���ޤ���
- ���Υ��饹�ϡ������Ǥ�ޤ����ΤǶ���Ψ�����⤯��ʬ�����㤤���إ��饹�Ǥ�����
- ���θ��إ��饹�δ����ǡ���ǽ�Τ���ɤ����إ���Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ����������إ��饹���㡼�����ȡ�
- �������ˤϡ�������Ǹ���뼴�忧�����ȸ������鳰�줿���֤ˤǤ�����Ψ������������ޤ���
- ��Ψ�������ȸ����Τϡ��������鳰�줿�����μ�������ɽ��뿧�ˤ�륺��Ǥ���
- ��Ĺ�ˤ�ä������礭�����Ѥ��ΤǤ��Τ褦�˸ƤФ�Ƥ��ޤ���
- ���μ����ϡ���Фᤫ��������ˤ�ä��������Τǡ�������������������Ʊ���褦�ˡ�����оΤ����֤������ꡢ�ʤ������������֤��뤳�Ȥˤ������ޤ���
- ��
- �������̼��� ��Spherical Aberration������2005.09.24�ɵ���
- ���̼����ϡ����ޤǤ˲��٤�Ҳ𤷤Ƥ��ޤ��������ἴ�������ʤ�Ƚ����ܥ����������ޤ����������F���ȥåפ�N.A.��
- ���������¤�ǥ�Τ�äȤ⺬��Ū�ʼ����ȸ������ΤǤ���
- ������̤ǤǤ��Ƥ���¤��ܼ�Ū�˻��äƤ�������Ǥ���
- ���̼���������Τϡ��̥�ȱ�����Ȥ߹�碌�ǹԤ�������濴����⤤���֤Ǥθ������㤤���֤����˶ʤ��ޤ���
- ���Υ���Ȥ߹�碌�ϡ�����������Ȥ��ˤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���äơ��������ȵ��̼����Ϥ��Υ���Ȥ߹�碌�Ǻ�Ŭ�ˤʤ�褦�ʸ��غ���ȵ��̷����ǵ����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���̼���������������ץ�ʡ��ȡ�Aplanat�ˤȸ����ޤ���
- ���ץ�ʡ��ȥ�Ǥϥ�����ͤ���ʿ�Ը��Ϥɤι⤵����Ǥ������˽������ޤ���
- ���ץ�ʡ��Ȥϡ�Ʊ���˥��������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���̼����������λ����ϡ��������ʤ�Ƚ����ܥ��٤Ȥ��Ƥ���������
- ��
- �������ץ�ʡ��ȡ�aplanat��
- ���̼����ϡ���μ������������ͤ���������濴���θ����Ȥ�Ʊ���������֤˽������ʤ����Ȥˤ�ä������ޤ���
- �������ˡ�����������濴���Ǥϥ������ޤ��ƾ������Ϥ��ޤǤε�Υ���㤦�櫓�Ǥ����顢���Τ褦�ʸ��ݤ�������Τ�����Ǥ��뤳�ȤǤ���
- �Ǥ���ʤ�С���������֤��濴�ˤ��ƥ����¦���̤���̾��ˤ��Ƥ��С���ι⤤���֤���Ǥ��˾����������֤˸������ޤ�褦�ˤʤ�Ϥ��Ǥ���
- ���Τ褦�˹ͤ������å٤ϡ�ͭ̾�ʥ��å٤����������ޤ���
- ���å٤���������������������ץ�ʡ��ȤǤ��ꡢ���̼������������줿��Ȥ������ˤʤ�ޤ���
- ��
- �������å٤���������Sine Condition��
- .
- ��������ؤΥ��å٤���1866ǯ�˥ĥ������Ҥ˵��Ѹ���Ȥ��ƾ��ۤ��줿�Ȥ��������������ǽ�����Ƴ�����������㸺��郎�������Ǥ���
- ���ξ������������Ȥˤ�ꡢ�����ǽ�����ʤ˸��夷�ޤ�����
- ���ξ��ϼ�ˡ���Ƿ�����������������˽��ޤ�ʤ����̼���������Ӽ������˹Ԥ��˽���������������ή��륳����������Τ��礤����Ω���ޤ�����
- ���å٤ϡ��ĥ������Ҥ˾��ۤ���Ƥޤ�������������������¤�����β��פ˼�꤫����ޤ�����
- ��������¤����ϡ��ޥ����������٤������ȻĤäƤ��ơ����줾��ο��ͤ����̤����ʤ���夲�Ƥ��ޤ�����
- ���Τ褦�������Τ�ȤǤϡ������ʼ��ΥХ�ĥ����Фޤ���
- �Ф�Ĥ������������Ĵ�������Ȥ��륷����Τˤ��ƽв٤���Τ�����Ĺ�λŻ��Ǥ�����
- ���������������ϥ��Ʊ�Τθߴ������ʤ������ФǻȤ�ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- ���å٤ϡ����Τ褦����¤�����ƥ��ľ���������ˡ�ΥХ�ĥ�����������ε����ͤ��ߤ��Ƹߴ����Τ������ʤ���¤���륷���ƥ����夲�ޤ�����
- ��¤������ľ������ϡ����˥����ǽ�θ���˼�꤫����ޤ���
- ���λ���ͭ̾�ʥ��å٤�������郎���߽Ф���ޤ�����
- ��ʪ��ϡ�����ޤǷи�Ū�ˡ�����������븫���߳ѡʸ�˳����� =N.A.�ȸƤФ���͡ˤ��礭��������ʬ��ǽ���褯�ɤ������뤳�Ȥ�ǧ����Ƥ��ޤ�����
 ���å٤ϡ����顢N.A.����������ޤ��뤳�Ȥˤ�ä�������λ����Ĥ��⤦�Ȥ��ơ�N.A.�������ơ����Τ����˵��̼�����ʬ�˶�̣��������߷פ��ޤ�����
���å٤ϡ����顢N.A.����������ޤ��뤳�Ȥˤ�ä�������λ����Ĥ��⤦�Ȥ��ơ�N.A.�������ơ����Τ����˵��̼�����ʬ�˶�̣��������߷פ��ޤ�����- �����������Υ�ϲ����Ϥ��㤯�����褫�鿦��Ĺ�餬�Ȥ߾夲�Ƥ�������ǽ�ǵڤӤޤ���Ǥ�����
- �����Ǻ��٤ϡ�N.A.��夲�ơ����뤤��ˤ��ơ˵��̼�����������������ä��Ȥ��������٤ϡ������濴�Ǥβ����Ϥ����Ǥ����ΤΡ��濴���龯���Ǥ⳰�줿�������Ǥ������ܥ��Ƥ��ޤ��ޤ�����
- ���å٤ϡ������μ��Ԥ��Ȥ˥�����뤵��N.A.�ˤȵ��̼����δط���������������å٤��������Ȥ��ƴ�ñ�ʴط�����Ƴ���Ф��ޤ�����
- ���θ�����Ƴ��������������ϡ��ˤ���ɹ�����ǽ��ȯ�����ĥ������θ�������̾������Ƥ����ޤ�����
- ���Υ��ԥ����ɤϡ���̣�������Ƥ�ޤ�Ǥ��ޤ���
- ��Ĥϡ����å٤Ȥ����ɤ��Ĥθ������Ԥ߽Ф��ޤ�2��3�μ��Ԥ�ФƤ��뤳�ȡ�
- �����ơ�����������˸��¤�ͥ���ʸ��������Ǥ��Ƥ������ȡ�
- ���������и�Ū�˽Ф��줿ͥ���ʤ�ΤˤϷѾ��������ȡ�
- ȿ�Фˡ�����Ū�˹��ۤ��줿��Τ����������ġ�ï�Ǥ��ñ�˺���ˤ��ȡ��Ǥ���
- ��
- ���å٤��������ϰʲ��μ���ɽ����ޤ���
- ��
- ������sin u / sin u' = m����������Lens - 31��
- ����������u ����ʪ�Τ�����Ф�����
- �������������������ͤ�������θ������Ф������
- ����������u'������������ؼ�«����ͽи���
- �����������������������������
- ����������m���������������
- ��
 ������ͤ�����γ��٤ȥ����ͽФ��������ָ��γ��٤������ͤ�������ˤ��롢�Ȥ����Τ����å٤��������Ǥ������μ���u��90��λ���¨��ʪ�Τ�̵�±�ˤ��äơ�sin u = 0�λ���
������ͤ�����γ��٤ȥ����ͽФ��������ָ��γ��٤������ͤ�������ˤ��롢�Ȥ����Τ����å٤��������Ǥ������μ���u��90��λ���¨��ʪ�Τ�̵�±�ˤ��äơ�sin u = 0�λ���
- ��
- ������h' / sin u' = b����������Lens - 32��
- ����������h'��������ʿ�Ը����������⤵
- ����������b����= f ����¦�������Υ��
- ��
- ��ɽ����ޤ������μ��ϡ������ؤ���ȡ�
- ��
- ������sin u' = h' / f ����������Lens - 33��
- ��
- �Ȥʤꡢ�ˤ�Ƥ狼����ɤ����Ȥʤ�ޤ���
- ̵�±�������ʪ�θ��������˽��ޤ�ˤϡ����δط��������Ƥ��ʤ��ƤϤʤ�ʤ��Ȥ������Ǥ����顢����ʿ�Ը��ϡ������¦���̤�����ޤ��ƾ������֡�f�ˤ˽������뤳�Ȥ�����Ȥʤ�ޤ���
- ���ξ���������������̼����ΤȤ줿��Ǥ��ꥢ�ץ�ʡ��ȥ�Ȥʤ�ޤ���
- �������Ƹ���ȡ����̼����ΤȤ줿��Ȥ����Τϡ�ʪ��¦����¦��Ȥ�˼��̤��Ѷʤ��Ƥ��뤳�Ȥˤʤꡢξ�Ԥ��Ѷʤ������̤������ɤ���ˤʤ뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ���å٤�����������������̼����ΤȤ줿��ϡ��Фᤫ�����ͤ���������̤��Ѷʤ��Ƥ��뤿�ᡢ�������٤Υ������ޤDz������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����������ѥ�ˤ����Ƥϡ����٤ƤΥ��ޤץ�ʡ��Ȥǽ���뤳�ȤϤǤ��ʤ��褦�Ǥ���
- ��
- ��
- ����ñ��ε��̼���
- ���å٤��������ϰʲ��μ���ɽ����ޤ���
- ñ����̥�ˤǤε��̼����κ��Ƥߤޤ��礦��
- Ʊ��������Υ����ä��̥�Ǥ⡢�����Ϥ����������ꤹ�뤳�Ȥ��Ǥ������줾��ξ��ε��̼����Ͽ�ʬ�Ȱ㤤������ޤ���
- ��
- ��

- ��
- ��οޤǤϡ�Ʊ��������Υ�Ƿ����ΰۤʤ��˥��������ʿ�̥��ξ�̥�ˤĤ��ơ����줾���θ������Ѥ��Ƽ������ٹ礤���ɤΤ褦�ˤʤ뤫�δط���ɽ���Ƥ��ޤ���
- ���οޤ�ȡ���˥�������ϵ��̼������礭���ơ�ξ�̥��̵��ʵ��̼������������Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- �ޤ���Ʊ�����ȤäƤ��θ����ˤ�äƤϼ����κ��ۤ�ǧ���졢ʪ�Τ������ˤ���¦�˶��ޤζ����̤�������������̼������ޤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��οޤǤϡ�������ʿ�Ը������ͤ��ޤ�����ʪ�θ���̵�±�ˤʤ�ޤ���
- ���ä�ʿ�Ը������ͤ���¦�˶�Ψ���礭���̤�������������̼��������ʤ��ʤꡢξ�̥�Ǥϡ�ξ�Ԥζ�ΨȾ�¡�1/r1��1/r2�ˤ��椬1:1.5�Ȥʤ��������̼�����Ǥ⾮�������뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ��
- ��
- ����

- ��
- ��
- ��˼�������A�ˤȡ�B�ˤǤϡ��ɤ��餬�������ɤ��Ǥ��礦����
- �����ϡ�A�ˤǡ�ʿ�̥�ξ�硢ʿ��¦�����ͤ��Ƥ������������������˽�������ͽ�¦�ˤ�ʿ�̤�����ޤ���
- �����ơ���Ψ����ä�¦��ʿ�Ը��ˤ��Ƥ������������ɤ��ʤ�ޤ���
- ��A�ˤΥ쥤�����Ȥϡ���������Ф�����ʿ�Ը��ˤ��뤿���ʿ�̤�����¦�˸����Ƥ���Τ�ʿ�Ը������٤��夬��ޤ���
- ʿ�Ը���������Τ˺��٤ϵո������̥�����֤���ȡ������˽��ޤ�䤹���ʤ�ޤ���
- ��������B�ˤ�����Ǥϡ���A�ˤȤϵ�����Ǥ��뤿��ո��̤Ȥʤäƻפ��褦�ʸ��̤������ޤ���
- ��˼�������A�ˤȡ�B�ˤǤϡ��ɤ��餬�������ɤ��Ǥ��礦����
 ��ɤνꡢ���ζ��ޤ϶��ޤ����ͳѤ���������о������ۤɵ��̼��������ʤ��ʤ�ޤ����顢�����ǰƬ������ƥ���طϤ��Ȥߤޤ���
��ɤνꡢ���ζ��ޤ϶��ޤ����ͳѤ���������о������ۤɵ��̼��������ʤ��ʤ�ޤ����顢�����ǰƬ������ƥ���طϤ��Ȥߤޤ���- ��ĤΥ�Ƕ������ޤ������Ȥ���ȵ��̼����������ʤ�ޤ���
- ��������Ǥϡ����������������ޤ��뤿��ˡ����˼������褦��ʣ���Υ���Ȥ߹�碌�ƽ����˸���ʤ��Ƥ��������̼������ޤ��빩�פ��ʤ���Ƥ��ޤ����ʱ��ޡ���
- ���̼����ϡ�ñ���ǵ�˸���ʤ��褦�Ȥ���Ȥ��˵����䤹���Τǡ�ʣ���Υ��Ȥäƽ����˶ʤ��Ƥ����ȸ����Τ�������ʤǤ���
- ʣ���Υ��Ȥ��ȡ����ɽ�̤�ȿ�ͤ�Ʃ��Ψ�������ʤä���ե쥢��¿�������Ȥʤ뿴�ۤ�����ޤ�����������̣���Ƥ���̼����β�����������ɹ��ˤʤ�褦�Ǥ���
- ������ƥ��ϡ��������������˰���Ū�ˤʤ�ʥ�����ƥ����Ѥϡ�1936ǯ��Carl Zeiss��Alexander Smakula��Τ�ȯ�������ˡ�������ƥ����Ѥγ�Ω�ʹߡ�ʣ����Υ�ˤ��������������������Ǥ�褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- ����
- ������������ ��Oblique Astigmatism��
 ����2005.09.25�ɵ���
����2005.09.25�ɵ���
- ����
- �ɤ�ǻ��Τ��Ȥ�����������˽��ޤ�ʤ���Фʤ�ʤ�ʪ�Τ�Ǥ�դΰ�������������������˽��ޤ�ʤ�����������ޤ���
- �����������鸫��ȡ����̼��������������ȸ��������Ǥ����������Ѹ�Ǥϸ�������Υ�줿���֤Ǥμ��������������ȸ��äƤ��ޤ���
- �Ѹ�Ǥϡ�Oblique Astigmatism �Ȥ���ɽ���ˤʤäƤ��ơ��Фᤫ�����ͤ�������Ф�������Ǥ��뤳�Ȥ�üŪ��ɽ������Ƥ��ޤ���
- ���äơ��������� �ϸ�������Υ�줿�Ȥ����Ǹ����˸���ޤ���
- �������� �ϡ��ͤ��ܤ����ˤ褯���Ƥ��ޤ���
- ���Ź�ǥᥬ�ͤ�����ˡ����;��˲��ܤ������Ф����㡼�ȡʥ���������� : Siemens' star �ˤ�Ȥäơ��ɤ��������ܥ��뤫�Ȥ��������ٹ礤�����ޤ���
- �������� �Ϥޤ��ˤ��Υܥ����Ƥ��ޤ���
- �������� �ϡ������濴����Υ��Ƥ��������˥ܥ�����������;��Υ��������Sagittal���̤ȡ��������濴�Ȥ����������Υ��ǥ����ʥ��Meridional���̤Ƕ��̤���Ƥ��ޤ���
- ��������Ȥ���ɽ���ȸ�����ꥸ���ʥ�Ȥ���ɽ���ȸ�����ξ�Ԥ������դǤ���
- ���θ��դϡ�Ω�����̤��ڤ�Ȥ��˻Ȥ�ɽ���Τ褦�ǡ����Τ��˶����ݤ˿��Τ�Ĥ��ڤ����̤��������̤ȸƤ�Ǥ��ޤ�����
- ���ΰ�̣�ϡ��������ˤ�����Ƥ���褦�Ǥ���
- ���������ͤ�褦�������Ǥ����̤Ȥ������ȤǤ���̾�����Ĥ����ΤǤ��礦��
- �ޤ������ǥ����ʥ�Ȥ���̾���������������������Ȥ����Τ������������Ǥ���
- ���ǥ����ʥ�ϡ���̾��������tangential�ˤȤ�ƤФ�Ҹ����Ȥ�������Ƥ��ޤ���
- �����Ǥ�������̤Ǥμ�«���ϡ���������濴�Ǥ����ƺ�����ι��ܤǽҤ٤��褦�ʸ��ν��ޤ�����¿���ξ�硢�ܥ��ϱ߷����Ǥ���������礦�˽��äƤ��Υܥ��̤��������ʤ�ޤ���
- ��������������줿���֤˷��������硢����ʣ���ʷ����Ǹ�����«���ޤ���
- ������ʤͤ��ˤ���褦�ʷ��ǽ������ޤ���
- ��������ʣ���ʽ������ͻҤϵ��̶��Ǥϸ����˸��졢�������˻Ȥ����̶��Ǥν�������˵�Ǥ����ˤ褯ǧ����ޤ���
- ���̶��Ǥϡ������μ����Ǽ�«���ϲ�Ĺ�Ȥʤꡢ���줬DZ�ʤҤ͡ˤ���褦�ʷ��ǽ�Ĺ�˲�ž���ƿʤߡ���������Υ���˽��äƺƤ�ȯ�����Ƥ����ޤ���
- ��Ĺ�����Ƚ�Ĺ�ˤʤä�������֤��Ŷ���������Ȥʤ�ޤ���
- �������� �ϡ��ޤ��ˤ��Τ褦�ʾ��������֤ΤǤ���
- ����ޤϡ��Фᤫ��������ä����μ�«�����ͻҤ��Ƥ��ޤ���
- ������μ�«�ȤϤ��ʤ��ä���Τˤʤ뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- �������� �������Ϸ빽��ä����ǡ�����߷פ���ˤ���Ǥ����ˤʤä��������Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ޤǤϡ����ʤäƤ����μ���������ʤ����ǻȤäƤ��ޤ�����
- �����������������Ȥ줿������ʥ������ޡ�����Anastigmat�ˤȸ����ޤ�
- ���ʥ������ޡ��Ȥ������Ѷʤμ������������ޤ���
- ���������ϡ����������ޥƥ�������Astigmatism�ˤȸ������������� �ΤȤ줿�ʤ���˲ä������Ѷʤ��������줿�˥�����ʥ������ޡ�����Anastigmat�ˤȸ����ޤ���
- ξ�Ԥθ��դϡ��ȤƤ��ƺ�Ʊ���Ƥ��ޤ������Ǥ�����������ɳ�Ȱʲ��Τ褦�ˤʤ�ޤ���
- �ǽ�ˡ�stigma�פȤ������դ����äơ�����Ͼ������Ȥ�����̣�Ǥ�����
- ����stigma�ˡ�a�פȤ���������Ƭ�줬�Ĥ��ơ��������ʤ����Ĥޤ�������ɽ����astigma�פȤʤ��������� �Ȥ������դ����Ƥ��ޤ�����
- ����ˤ�������ꤹ����դȤ��ơ�an�פ���Ƭ��Ȥ��ƻȤäơ�����������̵���פȤ����������ˤ��ޤ�����
- ��an-a-stigma�פȤ������դϤ��Τ褦�ʷаޤ�����Ƥ��ޤ���
- �������� �������������ȯ�����Τϡ�1890ǯ�Τ��Ȥǡ��ɥ��Ĥ�Carl Zeiss�ҤΥ�ɥ����Ρ�Dr. Paul Rudolph��1858��1935�ˤμ�ˤ�äƴ������ޤ�����
- ���Υ�ϡ�Protar�Ȥ�������̾�����Ф���ޤ�����
- �����������������ä����Ǥ��������դ������������ä����Ǥ���
- �ͤ��ܤΡ����פ��������� ������Τ˰��֤狼�꤬�ɤ����ȸ����Фʤ�Ȥʤ����Ƥ�館��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
- ��
- ����
- ���������� ��Coma�ˡ���2005.09.24�ɵ���
 �������ϡ�ŷ�Τ�������comet�ˤΤ褦��������������ˤʤ뤳�Ȥ�����ޤ���
�������ϡ�ŷ�Τ�������comet�ˤΤ褦��������������ˤʤ뤳�Ȥ�����ޤ���
- ���ޤϡ������μ������Ǥ���������ǡ��Фᤫ�����ͤ������������˽��ޤ餺�˳�¦��ή���褦�˼�«���븽�ݤǤ���
- ��ñ�˸����С��������Ȥϸ���������������̼����Τ��ȤǤ���
- ����������������̼����ˤϡ���˽Ҥ٤����������⤢��ޤ���
- �������� �ϡ��Фᤫ�������«�θ�����ź�äƤǤ�����Ԥ������μ����Ǥ���Τ��Ф����������ϡ������̤˳Ȥ�������ˤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ�������Ǥϡ��Фᤫ����������Ͼ����̤˾������Ӥޤ���
- �������������̤ΰ����ǤϤʤ�����ƾ�������Ǥ��ޤ��ΤǤ���
- ����ϡ�����������мФᤫ�����ͤ�����ϡ�������٤ˤ�ä�����Ψ���ۤʤäƤ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���Τ�������˽��ޤäƤۤ������������դ˹Ԥ��˽�������Ψ�Ѳ������ޤ����顢���դ˹Ԥ��˽��������ܥ����礭���ʤꡢ��������������ʥ��ޡˤΤ褦�����ˤʤ�ΤǤ���
- �������ϡ��Ǥ���ʤ�С��Фᤫ�����ͤ����«�κ������Ψ�����ͳ����̤ˤ錄�ä�Ʊ����Ψ�ˤ��Ƥ��С������Ǥ���Ϥ��Ǥ���
- ����ˤϡ����å١�Abbe������������������Sine Condition�������ƤϤޤ�ޤ���
- ���ξ��������Ƥ���Ȥ��ϡ��������餢�ޤ�Υ��Ƥ��ʤ��Ȥ����ޤǥ�������������ޤ���
- ���δط����ϡ�����ԥ塼���ʤɤʤ�����ˡ���ñ�ʼ��Ǽ���������Ǥ���Τ������Ȥ��Ƥ������ˤ��꤬���������ä��褦�Ǥ���
- ���̼����ȥ�������Ʊ���˽���뤳�Ȥ�Aplanatism�ʥ��ץ�ʥƥ�����ˤȸ�����Aplanatism�θ��طϤ����ץ�ʡ��ȡ�Aplanat���ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ����
- �������Τ�������ϡ��㤨�о�����������ʤdz������꤬���Ȥ��ƻ��Ƥ�����硢�����������Ǥϲ������濴�������;�������������褦�ʲ����ȤʤäƸ���ޤ���
- �ޤ������������ǤϤʤ����������٤��礭�����ä������Ǥ���ʤ���سԤ��ܥ���Ȥ������ݤ�����ޤ���
- ���Υܥ��������������濴�������Ф��Ƴ�¦���ҥܥ����Ƥ���Ȥ����褦�ʾ��˥��ޤ�����Ƥ���ȸ����ޤ���
- �������ϡ��ʤ�ˤ�ä����Ū��ñ�˽���Ǥ���ɸ���˺��Ѥ���Ƥ��륬��������Ǥϡ������ʤ꤫��1��2�ʤ˹ʤ�ȤۤȤ�ɳ�ǧ�Ǥ��ʤ����餤�˲�������ޤ���
- �̿�����ʤ�뤵��������ͳ�ΰ�Ĥ����������������μ������Ǥμ����ʤΤǤ���
- �����ϡ��濴���β����ȼ������β����Ǥϲ�����礭�������������β������ʤ����Τ�����߷פ��ӤΤդ뤤�ɤ����Ȥʤ�ޤ���
- ��
- ��
- �����Ķʼ��� ��Distortion������2005.09.18��
- ��
- �ͳѤ���Τ��ͳѤ��̤餺���ѷ����Ƥ��ޤ����ݤ�����ޤ���
- �Ķʼ����ϡ���ιʤ�ΰ��֤˵������Ƹ���ޤ���
- ���δط��ˤĤ��Ƥϡ��� �ʤ�ΰ��֤ˤ�������Ĥ� �ι�ǿ���ޤ�����
- �Ķʼ����ϡ���θ��¤������Υ�˰�¸�����ʤ�ΰ��֤ˤ�äƵ�����Τǡ����μ���������ˤϥ������Ȥ��оȤ����֤������濴�˹ʤ�����֤���褦�ˤ��ޤ���
- �Ķʼ����Ϲ��ѥ�˸���䤹����ΤǤ����������Τ褦������Ψ���Ѳ��ˤ������ΰ��̤Ȥϰۤʤ�ޤ���
- �ޤ����Ķʼ����ϸ����Ȥʤ�����ω��3������㤹�뤳�Ȥ��狼�äƤ��ơ����Ѥˤʤ�Фʤ�ۤɤ��η����������Ǥޤ���
- �������濴���Ǥϼ������������Τǹ��ѥ�Ǥ��Ѥξ������ϰϤǻȤ��ΤǤ���Ф��αƶ���̵�뤹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �Ķʼ����ϡ����������Τ��¬���褦�Ȥ������̵��Ǥ��ʤ������Ȥʤ�ޤ���
- �Ķʼ����ϡ��̿����ǤȤ�IC����ե��ȥ����ե����Υ������ǿ�����˹�θ���������Ǥ���
- �̿���Ǥ���ܻ��Ƥ���Ū�ˤ����ޥ�����Ǥ��Ķʼ����ξ��ʤ��߷פˤʤäƤ��ޤ���
- ����������ϡ��Ķʼ������Ǥʤ�������Υ��ɸ����������ˤ�����������Ƥ��ޤ���
- ����������ˤϡ��㤨�С��Ҷ�¬���ѤΥ�Ǥ�Ķ���ѥ��Ȥäơ��������Ķʼ������ü���ޤ����������Ƥ��ޤ���
- ��
 �����Ҷ��̿���¬���ѡˤΥ�������Ķʼ���
�����Ҷ��̿���¬���ѡˤΥ�������Ķʼ���
- �Ҷ��̿��ϡ��廡�Ȥ��Ƥη�����Ū�����ȯ���ޤ�����
- �ǽ�ιҶ�����餬�Ǥ����Τϥɥ��Ĥȸ���졢��켡�������郎�Ϥޤä�1914ǯ�˥ɥ��ıDz�Υѥ����˥����������������������ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���θ塢���Υ����ΰ��Ϥ��ܤ�Ĥ���Ϣ�緳�䥽�ӥ��ȤʤɤǤϡ�̩���ˡ��������絬�Ϥ�ͽ����夷���廡�����γ�ȯ���ʤ���ޤ�����
- ���Ե��˥�����ܤ��ơ��Ͼ�⤯�����Ϸ������ʪ��̿��ˤ�������ˡ�ϡ����Ե���ȯ������Ƥ���Τ��Ȥˤʤ�ޤ����顢��켡�������������ˡ������������������������̤���1970ǯ����꺢�ޤ�Ϣ�ʤ�³���ޤ���
- ��������α���̿��Ⳬȯ����ޤ�����
- �ĥ������⤴¿ʬ�ˤ�줺�����������Ǥ�ͥ���ʥ�����ޤ���
- �Ҷ��̿��ϡ��̿������Ͽޤ���ط��塢�������Ĥߤ����뤵���������ޤ���
- �ޤ����������ԤǤǤ��������������Υ��ꥢ����̩�˼̿��Ȥ��Ƶ�Ͽ�������Τǡ����Ѥ��ĤߤΤʤ��������Ϥι⤤��������ޤ���
- ������˱���������ʲ��˼����Ҷ�������ѥ�Ǥ���
- ���������Ҷ�¬�̥����Υ���߷פǤϡ�ŷ�ͥ�ǥ����ʡ��Υ٥�ƥ��Ludwig Bertele�ˤ��ȤƤ�ͭ̾�Ǥ���
- ��ϡ�Carl Zeiss�ǥХ��������Biogon�ˡ����ʡ���Zonnar�ˤʤɤΥ���߷פ�������1945ǯ�ˡ��������θ��ص�����WILD�˰ܤäƹҶ�������� Aviogon���߷פ��ޤ���
- ���Υ�ϡ�1968ǯ���߷פ��줿�����ѡ����ӥ������Super Aviogon�ˤǤ���
- ��ϡ����Υ���߷פ������ޤǤˡ�1948ǯ�˲��94°�Υ��ӥ�������߷פ�����ǯ��1949ǯ�ˤϲ��63°�Υ��ӥ������롢1963ǯ�ˤϥ��顼/�ֳ������ƤΥ�˥С����롦���ӥ�������߷פ��Ƥ��ޤ���
- �����ѡ������ӥ�����ϡ�������Υ3 1/2�������f88.9mm�ˡ������椬F/5.6�ǡ����120°����ǽ����äƤ��ޤ���
- ���Υ��9�������9�������228.6mmx228.6mm�ˤΥե������Ϸ�����ޤ���
- ����3,000m�ε�Υ�������10km�������Ϸ���̿��ˤ��������ˤʤ�ޤ���
- ���Υ���Ķʼ����ϡ�±0.030mm��30um�ˤȸ����Ƥ��ޤ���
- ¾�Υ�����Ȥ��С��⤦������Ѥ������Ҷ���ʥ��ӥ�����ˤǤ�10um���٤��Ķʼ����ˤʤ뤽���Ǥ���
- 30um���Ķʼ����Ȥ����Τϡ�228.6mm�Υե������̤˼̤��Ͼ�ξ���30um�Ȱ�äƤ��ʤ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���θ�����0.013%�Ǥ���
- 120°�ι�����ѤǤ������Ķʼ�����0.013%����Ȥ����ΤϤȤƤ�����ʤ��ͤǤ���
- ���ѥ�ǵ��Ť��Τϡ���������4��§�ˤ������������θ����㲼�Ǥ���
- 120°����IJ�ѤǤϼ��ո��̤�������ߤ������ʤ�ΤǤ���
- �������¤�Ǥϡ�������ȸ����ξ¦���������������Υ�˥���������Ȥ߹��ޤ�Ƥ���Τǡ��������θ����㲼�����äƤ���褦�˸��������ޤ���
- ���Υ�쥤�����Ȥ�Ȥ��ȥ�������4��§�˽���ʤ��������θ��̤�Ԥ����Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ������������Ǥ���̤�ʬ�ˤޤ��ʤ���ޤ���������Ƥ���ȤϹͤ����ޤ���
- Super Aviogon���ɤΤ褦�ʼ��ո��̤���ä������Ǥ���Τ���ˤϤ褯�狼��ޤ������ո��̤��䤦�������饹�Ϥ�������������Ǥ��ä��Ȥ��������⤢��ޤ�����
- ���Υ�β����Ϥϡ�ʿ�Ѥ�40lp/mm���٤��뤽���Ǥ���
- ��Ѥ�ˤ90°���٤Υ�Ǥ�60-80lp/mm����ǽ���Ф���Ȥ����ޤ���40lp/mm�β����ϤȤ����ȡ�228.6mm�Υե�������̤���Ƥ���18,300�ܤ�������������ˤʤꡢ�ե������12.5um���٤�ʬ��ǽ������ޤ���
- ������ǽ�ϡ�10km���Ͼ��0.5m���٤ޤǼ��̤Ǥ���ǽ�ϤȤʤ�ޤ���
- ���������ե���५������ǽ�ϡ����ߤǤΥǥ����륫���Ǥ������֤������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���ߤ�CCD��˥������ϡ�4,000���Ǥ����٤Ǥ���
- 18,300�ܤȤ����ȥ�˥�����9��ʬ�ʥե����β����Ϥ��ܤ�CCD���������ǡˤ��������ޤ���
- �����������������ĤߤΤʤ���ϡ�ʪ��¦����¦���Ф��ƥ����ȥꥫ����оη��ˤʷ����ˤʤäƤ��ޤ���
- �ޤ������ѥ�Ǥ��뤿��˥�γ�¦���礭�ʱ�����˥�����������֤���Ƥ���Τ���ħ�Ǥ���
- �礭���ϡ�������̸��¤����Ǥ�φ120mm�ۤɤ��ꡢ������ޤ�������֥�ʥ������ˤ�250x250x200Hmm�ۤɤˤʤ�ޤ���
- ���Τ褦�ʥ���߷פ���ΤϤ�������غ��������ꡢ����ṩ����������ƥ�����������դ��ˤ������ʵ��Ѥ��פ����ΤȻפ��ޤ���
- ��������WILD�Ҥϡ�1921ǯ¬�̸������֥���Ȥ��ƽ�ȯ��������������̤��ƹҶ�¬���ѤΥ������ܳ�Ū�˺��褦�ˤʤ�ޤ�����
- 1987ǯ�ˤϡ��ɥ��Ĥ�Leitz�Ҥȹ�ʻ��Wild Leitz���롼�פ��ꡢLeitz�Υ֥��ɤǹҶ�¬�̥����ƥ�뤷�Ƥ��ޤ���
- ����
- ����
- ���������Ѷ� ��Curvature of Field��

- ����
- �����Ѷʤϡ�����ʿ�̾�˷����������Ѷʤ���������Υ���˽��äƸ��������ˤ������ݤ����˸��ݤǤ���
- �ͤ��Ƥߤ�С������̤���������˿�ľ��Ω�Ƥ�ȡ�����濴��������濴�η����̤ޤǤε�Υ�ȼ������ޤǤε�Υ�Ǥϼ������ؤε�Υ��Ĺ���ʤ�ޤ���
- ���äơ����μ�������������Ƥ��ʤ���Ǥϼ����������̤��濴���������֤������������Ф���������ޤ���
- �̾�ե�����CCD�����ǻҤ�ʿ�̤ǤǤ��Ƥ��Ƹ������Ф��ƿ�ľ�����֤���Ƥ���Τǡ������Ѷʤ��������ʤ���Ƥ��ʤ����Ȥä������Ф���ȡ��濴������Υ���˽��äƥԥ�Ȥ��ܤ��������Ǥ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- �����Ѷʤϡ��������� �ȶˤ�ƶᤤ�ط��μ����Ǥ���
- �Ȥ��Τƥ����Ǥϡ��²��ʥץ饹���å����1�礷���ȤäƤ��ʤ�����������Ѷʼ�������Ǥ������Ǥ������ե�����̤��Ѷʤ��ݻ������뤳�Ȥˤ���������Ƥ��ޤ���
-
- �����ڥåĥС����¡�Petzval sum��������2005.09.25��
- �����Ѷʤ��ٹ礤��üŪ��ɽ����ñ�ʴط���������ޤ���
- �ڥåĥС����ϡ��̿������Ǥ����������Ū�ʥڥåĥС�������ޤ�����
- �����ब����Ū�˼�����Ƥ����������ǵ��ط������ʲ��˼����ڥåĥС����¡ʥڥåĥС���ξ�P�ˤǤ�����
- ���δط����ϡ�ʿ�̤�ʪ�Τ���ˤ�ä������֤Ȥ��ˡ��ʲ��ξ�郎���Ǥ��������ʿ�̾��Ÿ�������Ȥ�����Τǡ�������ρ�ˤ��Ф��Ȥ��ϡ�1/ρ�����̤��Ѷʶ�Ψ�Ȥʤ�Ȥ�����ΤǤ���
- ��
- ������- ����1/ni x fi�� = 1/�ѡ���������Lens - 34��
- ������������ni��fi��������ξ�����Υ�Ȥ��ζ���Ψ
- �������������ѡ��������Ѷʶ�Ψ���� = ���1/�� = 0�ˤλ�������ʿ�̤Ȥʤ롣
- ��
- ���η��ϡ�����߷פ���Ȥ��ϡ�������������ξ�����Υ�ȶ���Ψ��Ĵ�٤�ɬ���¹Ԥ���뤽���Ǥ���
- ���ߤϥ�������Ǥ��ñ�ˤǤ�������Ǥ���
- ���μ��ϡ��㤨�С�BK7�ʶ���Ψn = 1.58680�ˤθ��إ��饹1������ǤǤ���������Υf=50mm�Υ��Ȥä���硢�����Ѷʤ� -79.34��= �ѡˤȤʤꡢ�����̤��Ф���Ⱦ��79.34mm�ζ�Ψ�Ǹ����������ݤ��褦�����Ȥʤ�ޤ���
- 8.8mmx6.6mm��CCD�����̤ξ�硢�⤵������6.6/2 = 3.3mm�ΰ��֤Ǥϡ�68.54um���������Ǥ��ޤ����饤���������λ����ǻ��̡�36mmx24mm�ˤǤϡ�0.8922mm��892.2um�ˤȤʤꡢ���ʤ����������Ǥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ����Ψ����Ĺ�ˤ�äƤ��Ѥ��ޤ����顢���ˤ�ä������Ѷʤ��Ѳ����ޤ���
- ��
- ��
- �ڥ����ǥ� ��Philipp Ludwig von Seidel��1821-1896�ˡ�
- 1821ǯ�ɥ��Ĥ����ޤ�ޤ���
- ���ܤ�ǯ��Ǥ����ȹ��ͻ������ˤ�����ޤ���
- ����ľ����ϡ��ضɤ˶Ф����ƤλŻ����Թ�dzع���ž���Ȥ��ޤ�����
- 18�ͤdzع���´�Ȥ����塢��������ؤ����餺�˿��ؤβ������դ�ۤ����ؤ��ٶ���Ϥ�ޤ���
- ���ΤȤ��β������դ����������θ��ǿ��ؤ��ٶ����Ƥ���ͥ���ʥ���ʥ��������ؿʳإ������ι����ع��ˤζ��դǤ��ä����ᡢ��ο������ܤä������֤����뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- 1840ǯ��19�ͤλ��˥٥�����ؤ����ؤ��ޤ���
- �����δ����Ȥ�����غ߳����¾����ؤؤ�α�ؤ�ǧ����Ƥ����Τǡ���⤽����ˤʤ�äƥ����˥ҥ��٥륰��ؤ˳ؤӡ�����κǹ���ؼԡ��䥳�֡�Carl Gustab Jacob Jacobi�ˡ��٥å����Friedrich Wilhelm Bessel�ˡ��ե��ġ��Υ��ޥ��Franz Ernst Neumann�ˤ�μ�ۤɤ�������ޤ�����
- ���θ塢�ߥ��إ���ؤذܤ���ι��������ޤ�����
- .
- ��ι�ϡ�ŷ��˾˾����˻Ȥ���ߥ顼�ο���Ū�ͻ��ˤĤ��ƤǤ��ꡢ6�����ˤϡ����ؤȤϴط��Τʤ�Ϣ��ʬ���μ�«��ȯ���˴ؤ��������ʸ��夲�ƥߥ��إ���ؤιֻդο������ޤ�����
- �ʸ塢�ߥ��إ���ؤˤ�ŷʸ�ؤȿ��ؤ˸��Ӥ�Ĥ�����
- �����ǥ�θ��Ӥϡ����ء��ä˥�μ������ˤ����Ʒ�Ф����פ�Ĥ������ȤǤ���
- ��μ������ϡ����ؤߤ˱��Ѥ���ñ�����Ǹ����5�Ĥμ������Ĥμ��ǽ�ɽ�����������������߷פκݤΰ�Ĥλ�ɸ����夲�����ȤǤ�����
- ����߷פ���Ӥ��ιͻ��ˤϡ��������Υ��ͥ�ʤ⤷���ϥե�Υǥ���ȡˤ�ȯ���������ޤ�ˡ§�ˤ�äƻ��Ѵؿ���¿�Ѥ���ޤ���
- ʣ���Υ���Ȥ߹�碌�������߷פǤϡ�sinθ = θ�ȶ�������ἴ�ΰ�ʥ������ΰ�ˤ���ή�Ǥ�����
- �����ڤ�����Ǥ���
- �������������ΰ�Ǥιͻ������ΤǤ�����֤�����Ǥ����ΤΡ����μ������Ĥ���ˤϲ��Υҥ�Ȥ����뤳�Ȥ��ʤ����������礭�����ޤ�����
- �����ǥ�ϡ�����/�ͽи����� sinθ = θ + θ3/6 �ޤ�Ÿ�����Ƹ����μ����ۤ��ޤ�����
- 3���ι�ˤ�äƿ��������줿���ؼ��ϡ����̤��������μ���������Ū�ˤ��줤���������졢5�Ĥη����Ȥʤäƿ��������줿��5�Ĥη����ϡ��Ȥ��ʤ�������ǽҤ٤Ƥ���5�Ĥμ����Ȥʤ�ޤ�����
- �����ǥ�ϡ����������3����ޤǼ��夲�������ǤޤȤ�夲�ޤ����������ο������5�Ĥμ���������������ǡ�����¨�¤������뤫�Ȥ����Ȥ���������ΤǤϤ���ޤ���
- �����ޤǤ���������1�Ĥμ��ǽ�ɽ����Ȥ�����ΤǤ��äơ�������������������ؤμ�����Ƥ����ͭ�Ѥʥġ���Ȥ��ư��֤Ť���������Τ�ΤǤ���
- �����ǥ�μ��Ǥϡ�3����ޤǤ�����θ���Ƥ��ʤ��Τǡ��̿���Τ褦�˹��Ѥ����뤤��ʾ�����Υ��û�����¤��礭�ʥ�ˤǤϸ������ʤ�̵��Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ���
- ��̩�ʸ����߷פǤϸ�������ˡ�ˤ��ʤ���ΤϤ���ޤ���
- �����ǥ�ϡ���ʬ�γ�������̤�Ʊ����ؤ�ŷʸ�ؼԤǸ��شﳣ��¤��Ҥ���äƤ��륷�奿����ϥ����Karl August von Steinheil: 1801-1870��©�Ҥ�Adolph:1832-1893�ˤ��������ץ�ʡ��ȡ�Aplanat�ˤȤ����оη����ѥ��1866ǯ�˺��ޤ�����
- ���Υ�ϡ�������ǽ���褯���ʸ塢���Υ�����͡���ȯŸ��������ޤ�ޤ�����
- ���Υ�ϡ�1840ǯ���ڥåĥС������߷פ����ݡ��ȥ졼�ȥ��������ʤ�����μ̿���η��Ǥ�����
- �����ǯ�Ϸ褷�ƹ�ʡ�Ȥϸ����ޤ���Ǥ�����
- ��������������ض����ȥ����ǥߡ�����������˼��������������ʤ��ʤä���δǸ�ϡ��ब�����ȿȤ��̤���²�����ʤ��ä������Ʊ���ȿȤ��̤����Ф�������ݤ�1889ǯ�ޤǴǤޤ�����
- ���˴���ʤ�Ǹ��7ǯ�֤ϡ�����������Ԥ�̤˴�ͤδǸ�ˤ���ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ޤ����ؽ�Ū�˸��Ӥ�¿���ä������ǥ�Ǥ�������Ʊ���Ʊǯ��ο��ؼԥ�ޥ��Georg Friedrich Bernhard Riemann��1826-1866�ˤ��Ԥ߽Ф��������ؤ��ƻ�ʤ�ΤȤ����������̤���ǧ��ޤ���Ǥ�����
- ��
- ��
- ���������������줿���
- �ʲ��˵����̾���ϡ��ɤΤ褦�ʼ���������ܤ�����Ǥ��뤫���Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���Ū�˸��Ƥߤ�ȥ������ޡ��ȡʿ��ä���ˤ��ǽ�μ��������Υ�ǡ��Ǹ�˥��ʥ������ޡ��Ȥ�����夤���ȸ����ޤ���
- ���ä���ϡ��̿�����Ǥ���������˾�����串������ǻȤ��Ƥ��ޤ�����
- ���ʥ������ޡ��ȥ�νи���1890ǯ�Ǥ���
- �������뤬�̿���ˡ���Ԥ߽Ф��Ƥ���50ǯ���ޤ꤬�ФäƤ��ޤ���
- ��
- ���������������ޡ��ȡ�Achromat�˥����
- ����������������������Ĺ�ο������������������
- ������������������1757ǯ�ѹ�θ��شﳣ�ȼԥɥ���ɡ�John Dollond��1706-1761�ˤˤ�ä�ȯ�����õ��������
- �������������������ɥ���ɤϡ�����ʪ�����ä�����˸��ؤ�����ȤȤʤꡢ1761ǯ�ļ��ᥬ�;���Ǥ̿���줿��
- �������������������ɥ���ɤ�̼̻����ॹ�ǥ��ϻʬ�����ܴ��θ��ص��Ѽԡˡ�
- �����������ݥ����ޡ��ȡ�Apochromat�˥����
- ����������������������Ĺ�ο������������������
- ������������������1868ǯ�����å٤�ȯ����1886ǯ����������Ȥ��ƾ��ʲ���
- �����������ץ�ʡ��ȡ�Aplanat�˥����
- ���������������������̼����ȥ������������������
- ������������������1866ǯ���ɥ��ĤΥ��奿����ϥ��뤬̿̾��
- �����������ʥ������ޡ��ȡ�Anastigmat�˥����
- ���������������������������������Ѷʤ������������
- ������������������1890ǯ���ɥ��ĥĥ������ҤΥ�ɥ�ա�Dr. Paul Rudolph��1858��1935�ˤ�̿̾��
- ������������������Protar��Ȥ�������̾�����䡣
- ��
- �ʾ�Τ褦�˼̿���ϡ����ä������Ϥޤäơ����������������ѶʤޤǤ��������ʤä����ʥ������ޡ��ȥ������夬��ޤ�����
- ����ǡ������Υ���ɤΤ褦�ʷаޤ�Фƿʲ����Ƥ����Τ���Ҥ٤Ƥߤ����Ȼפ��ޤ���
- ��
- ������- ����1/ni x fi�� = 1/�ѡ���������Lens - 34��
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
�����̿����Photographic Lenses��
- �����̿����ȯ����� ����2005.07.27���� ��2006.09.11�ɵ���
- �̿����ȯã�˴ؤ�������Ϥ��ޤꤿ������ޤ���
- �������ۤ�ȯã�����ˤ⤫����餺�����ȯã���Ƥ����������̤οͤ���������Ƥ��ʤ��Τ���ͤ����˿���������ޤ���
- �����˼̿����ȯã��ή����֤äƤߤ����Ȼפ��ޤ���

- �����˴ؤ���ϡ��礭��ʬ����4�Ĥ���褦�Ǥ���
- ��Ĥϥᥬ�͡��ᥬ�ͤμ��פ��Τ���⤯��ͥ�����Υ����ꥢ�Dzֳ����ޤ�����
- ����ܤ�ŷ��˾������ᥬ����¤��ȯã���������ꥢ���������Ǻ�����礤��ȯŸ���ޤ���
- �������ŷ��˾�������������Dz�������Ƥ��ޤ�����
- ���ؤ˽�������ؼԤ�ͭ̾��ŷʸ�ؼԤ�̾��Ϣ�ͤƤ����Τ�����Ǥ��ޤ���
- 3���ܤϸ�������
- ŷ��˾����Ȥ�ȿ�Фξ������������ܤ��������ޤ�����
- �������ϡ��������ʤ���ŷ��˾����ۤɤˤ�ͥ����ƬǾ�����뤷�ʤ��ä��褦�ǡ�Į���ο��ͤ����ꤷ�Ƥ����Ȥ�����������ޤ���
- ���衢�������ϥ����ꥹ�ȥ��������ե���ɥ��Ĥʤɤǿ��ͤˤ��и�Ū�˺��Ф���Ƥ��ޤ�����
- ���θ������������˰���֥졼���������ޤ���
- 1886ǯ�ɥ��ĤΥ����롦�ĥ������ҤΥ���ȡ����å٤ˤ������������դ��ȿ��������إ��饹��Ƴ��������������ȯ���Ǥ���
- ���å٤ϡ�����Ū���դ�����äƼ�������������˸��礦���٤ι⤤���إ��饹����Ф��ƥ��ݥ����ޡ��Ȥθ���������夲�ޤ�����
- �������Ϥ��λ���ˤ��ƿ�������������ä��ȸ����ޤ���
- .
- 4���ܤΥ���̿���Ǥ���
- �̿���η���ˤĤ��Ƥ��줫���ä����Ȼפ��ޤ���
- �̿���ϡ��̿�����ˡ���Ԥ߽Ф���Ƶ�®�˹��ޤäƤ����ޤ���
- ����������ŷ��˾���������פ�����ޤ�����
- �ʹ֤δ��Ʊ��Ư���Ƶ�Ͽ�˻Ĥ��Ƥ������ΤǤ�����ɾȽ�ˤʤ�ʤ��Ϥ��Ϥ���ޤ���
- ��������Ĭή�ˤ�����Ƽ̿���ϲ��ɤ˲��ɤ�Ťͤ�ȯŸ���ޤ�����
- �̿��Ѥϡ�1839ǯ�˥ե��ȯ�����졢����ɾȽ�Ϥ�������Τ��ä��褦�Ǥ���
- �ե�����ܤˤ�ä�ȯɽ�����������顢������Ͽ����¸�Ǥ���ﳣ���Ǥ����Ȥ������ϥ衼���å�����Τ��Ƥ��ơ���ɽ���줿������ˤϥѥ�θ��شﳣ����ŹƬ�˥����쥪�����פδﳣ���¤ӡ�������㤤����ͤ���������䤿�ʤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �������̿���̿��ۤ����Τ��������ˤǤ��ޤ�����
- �̿��ۤϡ���˾�����뤳�Ȥ���ʾ���Ǥ��ꡢ�̿��äƤ�餦�����10�ե��������ν������ͤ�2��ʬ�����ߤ����ܱߤǤ�6�������٤��ˤǤ�����
- ����ʼ̿��ϡ���̱�������˰�������Ѥǻ����ΤǤ��ä��˰㤤����ޤ���
- �̿��ۤ�3�����ƤˤʤäƤ��ơ�3�������������ˤʤäƤ��ޤ�����
- �����ˤϾ��뤬���Ĥ館�Ƥ��äơ����۸���������˼������ƿ�ʪ��Ȥ餷�Ф��ޤ�����
- �������������ʤ�̵������Ǥ�������ŷ�����ɤ����줿�����̿����Ƥ����Ǥ��ä����ȤǤ��礦��
- �̿��äƤ�餦�ͤ����ϡ��ޤ֤������۸��ˤ��餵��ơ������Ĥ�Ϫ����Ԥ�1ʬ��δ֤��äȤ��Ƥ��ʤ��ƤϤʤ�ޤ���Ǥ�����
- �̿��Ѥϡ����ܤˤ�ۤɤʤ����äƤ����ޤ���
- �ե��ȯɽ���줿2ǯ���1841ǯ6��1���������ͤθ��Ѿ��͡������Ƿ��ʤ����ΤȤ��Τ��礦�ˤ��������ͤ��̤��ơ������쥪�����פΥ����ȴ����������������������ʰ켰��͢�������ͼ������ƶ��Ƥ��ޤ�����
- �ʼºݤϤ⤦������Ȥ�����⤢��ޤ��������ܤμ̿���ǰ�����������ˤʤäƤ��ޤ��Τǡ�1841ǯ6��1���Ȥ��Ƥ����ޤ�����
- �ʸ塢�������ˡ�����Ĵ����ζ�ϡ���ƣͦ���������ʤ������λֻ�ã�������˼̿��˼�����ޤ�����
- ��������Ϻ�Ρ�dz������פˤϡ���ƣͦ���̿����ʤ�����ˤ��ФƤ��ޤ���
- ��ƣͦ�ϴ����ʴ�ʤ��������ˤ��ɤ�ʴ�����뤯���ơ�Ĺ���֥��������˺¤äƤ����ȸ����ޤ���
- ���줬����ͭ̾�ʶ�ƣͦ�ξ����̿��Ǥ��ä��ΤǤ��礦��
- ����ζ�ϤϿ�����ι������ä��褦�ǡ����̿��������ǥݡ������äƤ��ޤ���
- ���������ܿͤˤϡ��̿����Ф��ƺ���ȴ�������ޤ路����ΤȤ����ռ����ä��褦�ǡ��ߤ�ʤ��ߤ�ʴ��Ǽ̿��������˺¤ä��褦�ǤϤʤä��ߤ����Ǥ���
- ��
 ����������ġ������ꥢ��
����������ġ������ꥢ��
- �����˻Ȥ������ǽ�˷��ˤʤä��Τϡ�1589ǯ�������ꥢ�ͤΥݥ륿��Giovanni Battista della Porta�ˤǤ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��ϥ��Ȥä�����饪�֥������ ��camera obscura�� ��ͰƤ����ͤȤ���̾���Τ��Ƥ��ޤ���
- ����饪�֥������ιͤ��ϰ������餢�ꡢ���ꥹ�ȥƥ쥹��Aristoteles��BC384-BC322�ˤλ��������֤ιͤ����Ǥ��Ƥ��ޤ�����
- ������θ��ϥ����ꥢ�ˤ���ޤ�����
- ���饹����¤�ڤӴ�����ȯã�������ǹԤ��Ƥ��ޤ������顢����饪�֥�������ѤΥ�⥤���ꥢ�Ǻ���ޤ�����
- �������֤ˤϡ��̥���Ȥ�졢���������Ť�����������ŷ��˿����˸����ƥ������դ����Ƥ��ޤ�����
- ��������ˤ�ʿ�����ơ��֥뤬������Ƥ��ơ���ξ�ˤ϶����Ф�45°�ˤ�����Ƴ��������ʤ���������ߡ��ż���Ω�Ƥξ����ˤ����줿�ơ��֥�������Ф��ޤ�����
- ������ˤ����ʤ꤬������Ƥ��Ʋ�����夬�ޤ��Ƥ��ޤ�����
- .
- �����Ȥ������դ�������ؤ������֥������ϰŤ��Ȥ�����ƥ��Ǥ���
- ������˥ߥ顼���֤����Τϡ���Ƿ�Ф�������������岼ȿž����ΤǶ��ˤ�äƶ��������Ǥ��������Ȥ�����ΤȻפ��ޤ���
- �ޤ��������Υ���饪�֥������ϸ���ʪ�Ȥ�������Ω�äƤ����Τǡ������ʧ�äƤ��ξ������������̤��Ƴ������ʤ�ݤˡ����������360°�����ʤ뤳�Ȥ��Ǥ��ƿ͵������ä��ȸ����ޤ���
- ����饪�֥������ϡ�����ʪ���Ԥ�¾�˲�Ȥ�ƻ��Ȥ��Ƥ�Ȥ��Ƥ��ơ��ǽ�Ͼ������餤���礭�ʤ�Τ��ä���Τ�����ɤ��ʤ�ˤĤ�Ƥ������Ⱦ������ʤ���Ӥ�������Ȣ�ˤʤ�ޤ�����
- ����Υ����θ���������饪�֥��������ä��ΤǤ���
- ��
- ��
 ����θ��塧�����ꥹ��
����θ��塧�����ꥹ��
- ��
- ����饪�֥�������ѤΥ�ϡ�1804ǯ�˱ѹ�β��ؼ������饹�ȥ��William Hyde Wollaston��1766-1828��������ޤǤ��̥���夨�ƥ�˥�������ˤ������Ȥǡ����ʤθ���ޤ�����
- ��˥�������Ȥ����Τϡ�����˻Ȥ��Ƥ��뻰����Υ�ǡ�ξ�̤�Ʊ���������Ѷʤ�����Τ��Ȥ�����ޤ���
- ����Ѥδ�����ո����ˡ��Ĥޤꡢ���̤�����¦�ˤ��Ƽ���դ��ƥ���饪�֥�������ѥ�Ȥ��ޤ����ʱ��Ǿ��ʡˡ�
- ��˥�������ϡ�ξ�̥������ϰϤ�ʿó���������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �����饹�ȥ��ñ�̥�ϡ�60°�β�Ѥ���äƤ��ޤ�����
- �ब��ä����Υ�ϡ�Periscope��ʥڥꥹ�����ס���˾���ˤȸƤФ�ޤ�����
- �����饹�ȥ�ϡ�������̾�ʲ��ؼԤǡ��������ࡢ�ѥʥ������ȯ���ԤȤ����Τ�졢�ץ���ʡ����ˤ���ϣ��ˡ���Ω�����ͤȤ���ͭ̾�ˤʤ�ޤ�����
- ����Ԥ߽Ф�����ˡ�ˤ�ä���ϣ���ƺ��줿�ץ���ʴ�������Ͻ����ʼ������Ȥʤꡢ���ؤθ���ˤ��ä�������ǰ���Ǥ����ȸ����ޤ���
- ��ϡ��ѹ�ͤβ��ؼԥޥ����롦�ե���ǥ���1�������β��ؼԤǤ��ꡢ�ե���ǥ��λվ��Ǥ��벦Ω�����Υϥ�ե���ǥ��ӡ����ȶ�Ʊ����⤷�Ƥ��ޤ���
- �����饹�ȥ�ϡ�����θ���ơ��ޤ��Ԥ����Ǹ������֤�ɬ�פȤʤꡢ���������ѤΥ���ä��ꡢ����饪�֥��������¤���ƥ����륷������Camera Lucida�ˤ�ȯ�������ꡢ�����饹�ȥ�ץꥺ����ä��ꤷ�ޤ�����
- �����饹�ȥ�����ˡ��̥�ȱ�����Ȥ߹�碌���������ȵ��̼��������뿧�ä�������ѹ����ɥ�Υɥ���ɡ�Dollond�ˤˤ�äƺ���Ƥ��ޤ��������̥�˻Ȥ�줿���饦�饹�ȱ���˻Ȥ�줿�ե��ȥ��饹���ʼ��ȶѼ�����˳�����������饹�ȥ�Υ�˥�������������Ϥ뤫����ǽ���褫�ä��ȸ����ޤ���
- �����饹�ȥ�Υ�˥�������ñ�̥�ϡ��Ƕ�ޤǡ�110�����Τ褦�ʾ������ʥ������Υե�����Ȥä��²��ʥ���ѥ��ȥե���५���˺��Ѥ���Ƥ��������Ǥ���
- ��
- ��
- �����̿��λϤޤꡢ�ե��
- ��
- ���إ��饹���ʼ��ϡ�1790ǯ���������Υ��ʥ��P.L. Guinand���ˤ�äƸ��夷���ʸ��ɼ��ʤ�Τ������褦�ˤʤ�ޤ���
- ����ޤǤθ��إ��饹�ϱѹ�äȤ�ʤ�Ǥ��������Ǥ���������Ǥ��ʼ��ϸؤ줿��ΤǤϤʤ��ä������Ǥ���
- ���ʥ�ϡ����饹���ϲ�������¤��뤳�Ȥ�ͤ��Ф��Ѽ��ʸ��إ��饹���뤳�Ȥ��������ޤ�����
- ���������Τ������ǿ��ä������ǽ���ɤ���Τ��Ǥ����ܽ褬Ω����1839ǯ���ե�Υ������뤬�̿���ˡ��ͰƤ����Ȥ��ˡ����ƥ�Ȥ���Ʊ��Υ����Хꥨ��Chevalier������饪�֥���������¤�ȼԡˤˤ�äƿ��ä��������ޤ����ʱ��夫��2���ܡˡ�
- ���Υ�ϡ��ե��ȥ��饹�ȥ��饦�饹��Ȥä�2���Ž���碌��ǡ�������Υf=380mm������φ81mm�Ǥ��ꡢ������̤���68mmΥ�줿���֤�ľ��27mm�ιʤ����������F/14�Τ�ΤǤ�����
- ���ߤμ̿������٤ƿ�ʬ���礭����ΤǤ���
- ����Υ����6 1/2 x 8 1/2 ������μ̿����Ĥ���������ΤǤ����顢���������������礭����ȸ������Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����̿��dz��μ̿������Ȥ�Ȣ���̿���θ��������Υ����쥪�����פΥ������ä��ΤǤ���
- ��
- ��
- ��������Ū��ˡ��Ƴ�����ɥ��ġ�
- ��
- ������������Ǥ�ޤ����̿�����������Ȥ��ƤϽ�ʬ�ʤ�ΤǤϤʤ�����������F/14�ȰŤ����̿������ޤδ��٤��㤤�Τ��Ĥ��äơ����Ƥˤ�����Τ�ȤǤ�30ʬ�ʾ��Ϫ����ɬ�פȤ��ޤ�����
- ���ξ�狼��ե����δ��٤Ф���ȡ�ISO 0.004�� = 1/3,000�ˤȤʤ�ޤ���
- �������뤬ȯ�������̿��ϡ��������äơ�ȯ�����줿���������Τ�ư���ʤ����ʤƤ��뤳�Ȥ�¿�����������ˤ�î�����Ķʼ������ĤäƤ��������ʪ�λ��Ƥˤ���Ŭ���Ǥ�����
- ���Υ�Ϥ�äѤ����ʼ̿��˻Ȥ�줿���ᡢLandscape Objective�����ʥ�ˤȸƤФ�Ƥ��ޤ�����
- �����Хꥨ�θ��2ǯ�塢1841ǯ�˥ڥåĥС������о줷�ޤ���
- �ڥåĥС����ϡ������Ȥ��Ƥϲ��Ū������¡�F/3.4�ˤΥ�ʾ�����Υf=149mm�ˤ��߷פ��ޤ����ʱ������ܡˡ�
- �������ʤ��顢����߷��ۤȤ�ʢ�ˡ������θ��إ��饹�Ȥ����Х��ʥ�θ��ӤϤ����ΤΥ��饦�饹�ȥե��ȥ��饹��2���ष���ʤ�������2�Ĥθ��إ��饹��Ȥä������ǤϥڥåĥС��뼫�Ȥ�Ƴ�����ڥåĥС���ξ����������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- ���äơ����Υ�ϲ���������Τߤ���Ԥǡ��������β����Ǥϸ�����������ǧ���줿���ᡢ��Ѥ�����������ޤ���Ǥ�����
- �����������Ȥ���ڥåĥС���Υ�ϡ��ݡ��ȥ졼�ȥ�Ȥ��ƻȤ��ޤ�����
- ��
- ��
- �������ѥ�������ꥹ�ȥɥ���
- ��
- �ڥåĥС������Ǥ��Ƥ���24ǯ���Фä�1865ǯ������ɥ�Υ�����ᥤ���John Henry Dallmeyer��1830-1883�����ޤ�ϥɥ��ĥ������ȥե��ꥢ =Westphalia��1851ǯ��21�ͤλ��˥���ɥ�˰�̱��Ross����Ω���θ����߷ԡˤϡ�3��Υ��Ž���碌�ư�ĤΥ�Ȥ���ñ�̡ʥȥ�ץ륢�����ޥ��å���ˤ����ۤ��������ѹ��ѥ��Wide Angle Landscape Objective�ˤ��߷ס���¤���ޤ�����
- ���Υ�Ϲ��ѤdzΤ����ڤ줬�ɤ���ΤǤ�������ñ�̤Τ���˱������Ķʤ���������Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- ������������ˡ�Ȥ��Ƥϡ��ʤ���濴�ˤ�����ξ¦�˥����Ķʼ���������������ʤ���������ᥤ��ϡ��ȥ�ץ륢�����ޥ��å����ȯ������ǯ��1866ǯ���Ķʤ������������ȯ����Rapid Rectilnear�ʥ�ԥåɥ쥯����˥��ˤȤ�������̾�����Ф��ޤ����ʱ��Dz��ʡˡ�
- Ʊ��ǯ��1866ǯ�ϡ��ɥ��ĥߥ��إ�ˤ���Steinheil�Ҥ�Aplanat�ʥ��ץ�ʡ��ȡˤȤ���̾����Ʊ�ͤΥ���äƤ��ޤ���
- �Ķʼ������������������γ�ǰ�ϡ�1841ǯ���ѹ��åȥ��ɤμ̿��ȥȡ��ޥ����ǥӥåɥ����Thmas Davidson��1798-1878���ե�Υ������뤬�̿�ˡ���������䤹�����ޥ�������¤�����Ԥä��͡ˤ��ͤ������Ƥ��ޤ�����
- �����Υ�ϡ������椬F/8�Υ�˥��������ο��ä����Ȥäƹʤ���֤��оΤ����֤��Ƥ��ޤ�����
- ���Τ��Ȥˤ�ꡢ�ڥåĥС������ϰŤ���ΤΡ����̼������褯��졢���������⤢�ޤ���Ω�������оι�¤�Τ�����Ķʼ������褯�������졢ľ����ľ���Ȥ��ƻ��ƤǤ��ޤ�����
- �Ķʤ��ʤ����Ȥ��顢��Υ��Rectilinear��ľ���ˤ�̾�դ����ޤ�����
- ��
 �ߥ��إ�Υ��奿����ϥ����Hugo Adolph Steinheil��1832-1893�ˤ⡢�ѹ��åȥ��ɤΥ�����ᥤ���Ʊ��ǯ1866ǯ��Ʊ��ȯ�ۤΥ����ޤ���
�ߥ��إ�Υ��奿����ϥ����Hugo Adolph Steinheil��1832-1893�ˤ⡢�ѹ��åȥ��ɤΥ�����ᥤ���Ʊ��ǯ1866ǯ��Ʊ��ȯ�ۤΥ����ޤ���
- ���奿����ϥ���Υ��Aplanat�ʥ��ץ�ʡ��ȡˤȸƤФ�ޤ�����
- Ʊ������2�Ĥ�ȯ���Ԥ����줿�ΤǤɤ��餬��˺��줿�Τ�����������ˤʤ�ޤ����������奿����ϥ���������������ȯ��������ǧ����ޤ�����
- ���奿����ϥ���ϡ�1881ǯ�������Ȥ��ƤϤ⤦����ʾ��������꤭��ʤ��ȸ���줿Antiplanet�ʥ�����ץ�ͥåȡ˥��ȯ���ޤ���
- ���Υ����������������ޤ����ɹ���ʿ���������뤳�Ȥ��Ǥ����ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����ʾ�ˡ����Υ�ϼ���������Ū�˽�ʬ�˹�θ����ơ�����ʾ������θ��إ��饹�ʥ����ʥ��饹�����Υ��饹�ˤ�ȤäƤϽ���Ǥ��ʤ���ޤ���Ƥ��ޤ�����
- ����ʥ���߷פ��б����뤿��ˡ����������إ��饹��˾�ޤ����夬��ä���Ƥ��ޤ�����
- ��
- ��
- �������إ��饹��¤�γ�Ω���ɥ��ġ�
- ��
- ���إ��饹����¤�γ�Ω��Ω��Ԥϡ��ɥ���Jena�ʥ����ʡˤΥ����롦�ĥ������Ҥε���Ĺ����ȡ����å���Ρ�Ernst Abbe��1840-1905�ˤȥɥ���Witten�ʥ����åƥ�ˤΥ��åȡ�������å���� ��Otto Schott��1851-1935�� ��3�ͤ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- 1877ǯ�Τ��ȤǤ���
- ���إ��饹��������ޤȤ�夲��ξ�Ԥζ��Ӥϡ����ص�����¤�����̿�Ǥ��ä��ȸ�����Ǥ��礦��
- 1877ǯ�����åȡ�������åȤϾ����ʥ��饹��¤������ƥ��å���Τ�Ϣ�Ȥ�Ȥ�ʤ��顢���饹�ˤǤ����ΤϤ��٤�����ĥܤ������20-60��������٤Υ��饹�ˤ������å���ΤΤ�Ȥ�����ޤ�����
- ���å٤Ϥ����ץꥺ����ᤤ�ơ�ʬ���פ�Ȥä���̩��¬�ꤷ����Ū��������̩��Ĵ�پ夲����¿���θ��إ��饹�����Ƥ����դȤ��ƤޤȤ�夲�ޤ�����
- ����դ϶���Ψ��ʬ����ѥ����ˤ���2��������դǤǤ��Ƥ��ơ���ɴ����˵ڤָ��إ��饹����ĤΥѥ�������ؤ��äơ������߷פκݤ�ɬ�פʸ��إ��饹�����������ˤ狼��褦�ˤ��ޤ����������إ��饹���㡼�����ȡˡ�
- ���å٤ϡ����إ��饹���������ͤȤ��ơ����饹�ζ���Ψ�Ϥ��������Ĺ���Τ��ϤäƤɤ����٤ζ���Ψ�κ������뤫������Ǽ�����ʬ���ͤ����ܤ����ΤǤ���
- ���å٤�ʬ���͡ʥ��åٿ��ˤȤϡ�
- ��
- ��������d = ��n d -1��/��n F - n c�ˡ������������С�
- ��������������d ����d���ˤ�������إ��饹��ʬ���͡ʥ��åٿ���
- ������������n d���������ˤ��������Ψ
- ������������n F���������ˤ��������Ψ
- ������������n c���������ˤ��������Ψ
- ������������d��F��C���������ϥإꥦ��ȯ���˴ޤޤ��589.3nm�ε�����F���Ͽ���ȯ���˴ޤޤ��486.1nm�ε�����
- ����������������������C���Ͽ���ȯ���˴ޤޤ��656.3nm�ε��������ʤߤˡ�D���ʥ���ե��٥å���ʸ���Σġˤϡ�
- �����������������������ʥȥ��ȯ����ʣ��������������Ǥ���589.3nm��
- ��
- ��ɽ�������ͤǤ���
- ���ðǰ�˥��饹�ζ���Ψ��Ĵ�٤ơ�����Ψ�ˤɤΤ褦�ʷ���������Τ���ͻ����ޤ��� ��
- ��������d = ��n d -1��/��n F - n c�ˡ������������С�
- ���������إ��饹���ä���ǡ��ä˥Хꥦ�९�饦�饹��SK���饹������Ψ���������ʬ�����㤤=���åٿ����⤤�ˤγ�ȯ�ϡ������߷פ˼�ͳ�٤�Ϳ��������ޤ��Բ�ǽ�Ȥ���Ƥ������������������Ȥ�¿��ʤ����̤����ޤ�����
- �����θ��إ��饹�ϡ������롦�ĥ������Ҥȥ���åȤ����������Ƥ����饹������ϥ����ʤˤ��ʤ�ǥ����ʥ��饹�ȸƤФ�ޤ�����
- �����ʥ��饹��Ȥäƺǽ�˼̿�������줿�Τϡ�1887ǯ���ѹ����ɥ�ˤ��ä�Ross�Ҥ���Ф��줿Concentric��ʾ�����Υ3�������f=75mm�ˤǤ���
- ���Υ�ϡ�Ʊ���ߡפȤ���̾���Τ��Ȥ����ʤ���֤��濴�Ȥ������̤ȸ�̤��оΤ����֤��졢���̤��̤�ʿ�̡�ʿ���������Ž���碌�Ǥ��٤�Ʊ�������ȶ�Ψ�ˤʤäƤ��ޤ�����
- �����������Υ�θ������F/16�ȰŤ�������ʾ����뤯����ȵ��̼����������ǤƤ��ޤ��Ȥ�ʪ�ˤʤ�ʤ��ä������Ǥ���
- F/16�Ȥ������뤵�ˤ������Ȥ��������� ���ɹ����������졢���̤�ۤ�ʿó��60°�β�Ѥ����Τ�������ǥ��С��Ǥ��������Ǥ���
- ���Υ��F/45�ޤǹʤ��80°�β�Ѥޤ��ɹ��ʲ��������ݤǤ�������ˡ�����ʪ�ʤɤλ��Ƥ˰��Ϥ�ȯ�����������Ǥ���
- ����ɥ�ˤ���Ross�Ҥ�Concentric��ϡ��ʤ���֤�ǥ�ι����ȶ�Ψ���ޤä����оΤǤ��ä��Τǡ����ʤ�ʤ��ȵ��̼�������ʬ�˼�꤭��ʤ�����������ޤ�����
- ���η�������������Τ��ɥ��ĥĥ������Ҥǥ��å���Τν���Ƥ�����ɥ�ա�Paul Rudolph�ˤǤ�����
- ��ɥ�դϥ���߷�ˡ�����̤����ɹ��ʥ��ʥ������ޡ��Ȥ����뤿�����ۤ�����ǽ��ȯ������Protar�ʥץ������˥��1890ǯ�����˽Ф��ޤ���
- ���Ҥθ��إ�ʥ����ʥ�ˤ�ȤäƼ��Ҥ��߷פ��������������Ф����ΤǤ���
- Protar��ϡ�Ross�Ҥ�Concentric��ȹ�����Ʊ���Ǥ������ʤ������̤���̤���礭������Ƥ��ơ���̤ˤϿ��������إ��饹�ʥХꥦ�९�饦�饹�ˤ�Ȥä������ο��ä�������֤���Ƥ��ޤ�����
- ���̤ε켰���ä���ˤ�äƼ������Ѥ����������̤ο������ä����ȯ�����Ѥ��������ξ�Ԥμ������껦���Ѥǵ��̼������������� ��Ʊ�����������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ��ɥ�դϡ����θ�����Ū�ʼ̿�������߷פ��̿���δ��ä��ۤ��夲���ĥ��������̾������ư�Τ�Τˤ��ޤ�����
- ��
- ��
- �ڥĥ������ȥ��å٤ȥ���åȡ�
- ������ص���θ����Ȥ�ʤä��ĥ������ȥ��å٤ȥ���åȤϡ��ɤΤ褦�ʴط��Ǥ��ä��ΤǤ��礦��
- 3�ԤΤɤοͤ�礤�Ƥ⸽��θ��ؤ�ȯŸ���٤�Ƥ����˰㤤����ޤ���
- �ʲ��ˡ�3�ͤοͤȤʤꡢ��ߤδط���Ҥ٤뤳�Ȥˤ��ޤ���
- ��
- �������롦�ĥ�������Carl Friedrich Zeiss��1816-1888��
 �����롦�ĥ������ϡ��ɥ��ĥ磻�ޡ�������ޤ�ޤ�����
�����롦�ĥ������ϡ��ɥ��ĥ磻�ޡ�������ޤ�ޤ�����- ��Ƥϴ�ͤǤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����ޡ����������´�ȸ塢���ص������¤���뤪Ź�ʻվ��ϥե�ɥ�åҡ�����ʡ��ˤ������ͤȤ���Ư������������ء�The University of Jena�ˤǸ��ء�ʪ���ؤιֵ�������ޤ�����
- 1846ǯ���ब30�ͤλ�����Ω���ơ������ʸ��ص������Ź���ʤ˳��Ȥ�����ñ�ʸ���������ص���ʤɤ���¤�����١��ȻϤ�ޤ�����
- ��������ؤ��������ڤʤ����ͤǤ�����
- �����������Ϥ�Τϡ���ʪ�ؤζ����Ǥ��륷��饤�ǥ�δ�����ä�����ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��������β�ҤϤޤä���̵̾�ǡ��ĥ�������̾�����������Τ���褦�ˤʤä��Τϡ�1847ǯ���ब31�ͤλ������꤫��Ǥ��ꡢ�����ͤ��ۤä�������Ǥ�����
- ����ǯ�ˤϸ��������������¤����Ź�Ȥʤäơ���˶���Ѥ�ñ�̤θ�������¤��Ϥ�ޤ�����
- ���θ������ϡ�����ǯ23���å���줿�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��ϼ���ʣ����Ȥä���������¤�˾��Ф��ơ����줬ɾȽ�Ȥʤ�ޤ�����
- ���褬�ɤ��ä��ΤǤ���
- 1861ǯ���ब45�ͤλ��ˤϥɥ��ĤǺǹ�α����Ȥ����ʳشﵡ�Υ�����ɥ�������ޤ��ޤ�����
- ���κ��ˤ���ι�˼�ˤ�20̾�ν��Ȱ���ޤ��ʤ��ޤǤ��礭���ʤäƤ��ޤ�����
- 1866ǯ�ޤǤˡ����1000��θ���������¤�����䤷�ޤ�����
- �����������ض��������Ƥ��ʤ��ä��Τǡ���������¤����ǽ����夵���Ƥ����Τϥȥ饤����ɥ��顼�ʻ�Ժ����ˤ�����ˡ���ʤ��������˴Ť뤳�Ȥʤ��䤨�ʤ���ؤ����������褷�Ƥ�������ˤϡ����ؤ�����Ū���դ��ΤǤ��뵻�ѻ�Ƴ�Ԥ�ɬ�פʤ��Ȥ��˴����Ƥ��ޤ�����
- ���������ޤꡢ��ϥ�������ؤǿ��ؤ�ʪ���ؤǶ�����ȤäƤ���26�ͼ㤤ͭǽ�ʳؼԡ�����ȡ����å٤��Τ�礦���Ȥˤʤ�ޤ���
- �����Υ��å٤϶�Ф���̵�����عֻդǤ�����
- �ļ���ؤΥ�������ؤˤϽ�����ʪ���¸����̵�������å٤�����ư��������ʤ��¸����˼��ä��ʤ��顢������ʪ���¸����Ƥ����ȸ����ޤ���
- �¸������ľ������ˡ���ʬ�μ�ǤϤɤ����Ƥ�Ǥ��ʤ���ϳ�����ष���ʤ��������ʤ�Į�Ǥ��Ӥ��ɤ���̩�����ȼԤ������롦�ĥ������ҤǤ��ä��Τǡ����줬��Ȥ���ͤϸ�ή��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���Υ�����β�ҤǤ⡢��˽Ҥ٤��褦�ʸ�����������ǽ���ɤ���Τ��Ǥ�����Ǻ��Ǥ�������Ǥ⤢�ä��Τǡ��������ɤ�����Ԥȶ��ϼԤˤʤäƹԤ��ޤ�����
- ������ϡ����å٤ȶ�Ʊ��1869ǯ�˸������θ������֤�ȯ���ޤ���
- 1872ǯ��������ϥ���ȡ����å٤���β�Ҥ˾�������ơ���Ʊ�Ǹ��ص������ǽ������ܻؤ��Ƶ��ѳ�ȯ��ԤäƤ����ޤ�����
- ���å٤ϡ����ؤ˴ؤ��������Ƚ�Ǥȿ��ؤ���������äƤ��ơ����ȯ���������̼���������������������sine condition�ˤ��Ѥ������ۤΥ��꤬�ĥ������ҤǻϤޤ�ޤ�����
- 1884ǯ������ϡ����åȡ�������åȤ����饹���ص��Ѥ����뤳�ȤȤʤꡢ����åȤ��ɼ����饹�������Ȥ��뤳�Ȥˤ�ä������ǹ���θ��ص�����Ǥ���褦�ˤʤꡢ�ĥ�������̾�����ͭ̾�ˤ��Ƥ����ޤ�����
- �����롦�ĥ��������Ȥϡ��ĥ��������Ĥ��ۤ�������72�ͤ�ŷ�����������ޤ���
- .
- ��ΰջ֤�����Ѥ��ǡ��ĥ���������Ĥ˻�Ω�ƾ夲ϫƯ�������������ұ��Ĥ��ɤ��ڤä��Τϡ������24�ͼ㤯����λ��17ǯĹ�����������å���ΤǤ�����
- .
- 20���������ä������������郎�����1945ǯ�ޤǤ�Ⱦ�����ϡ������롦�ĥ������Ҥ������κ���ü��Ԥ����ص����ҤǤ�����
- ��������������������ˤ�����ɥ�������ˤ�äơ�����������줿�����ʤ��Ϥϥ����롦�ĥ������Ҥ�ʬ�Ǥ����Ȥ������֤˸�����ޤ�����
- ������������塢�ɥ��Ĥ�����ʬ�Ǥˤ�äơ��ɥ��������ˤ��ä������ʤϥ�Ϣ�������������֤���뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��������Ϣ�緳�ϡ������ǹ�Ѥ���ĥ����롦�ĥ������θ��ص��Ѥ���Ϣ�ˤ錄�뤳�Ȥ졢��Ϣ������ƥ����ʤ����ꡢ���ѼԤ�¿����Ⱦ�ж���Ū�˥���ȥ��åȥ���Ȥ˰�ư�������⤦��ĤΥ����롦�ĥ������ҤȤ��Ƹ��ص��������������Ѥ����ޤ�����
- ��������Ϣ���ϥ����ʤˤ��ä����췲���ܼ����Ĥä����ѼԤ⥽Ϣ������ޤ�����
- ����ˤ�äƥ����롦�ĥ�������������ʬ��������¦�ϥ���ȥ��åȥ���ȶ�٤Υ����С����åإ�˿���Ҥ���Ω���졢��¦�ϥ����ʤ�Ⱦ��Ⱦ̱�Ρֿ�̱���ҥ����롦�ĥ������������ʡפ��֤���뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- �����롦�ĥ������ϡ������ɥ��������������뤳�Ȥˤʤä��ΤǤ���
- ����ξ���ʬ���줿�����롦�ĥ������Ҥϡ��ɤ��餬�ĥ�������̾�䥳�å�������ɸ�θ�������Ĥ���ˡ��Ʈ��˵ڤ�Ĺǯ�ˤ錄����Ĥ�³�����ޤ�����
- 1989ǯ���ɥ��������ˤϡ��ƤӰ�Ĥˤʤ�ޤ�����
- ���Ļ����δ�ȤȤ��ơ������롦�ĥ������Ҥ�ĥ�������������ҡ�Zeiss-Ikon�ˡ�����åȡ����饹�� (Schott Glas)�ʤɤ�����ޤ���
- ��
- ��
- ������ȡ����å١�Ernst Abbe��1840-1905��
 ���å٤ϡ����ӹ�����˻����Ϥ������������ޤ�ޤ���
���å٤ϡ����ӹ�����˻����Ϥ������������ޤ�ޤ���- ���ض�ˤ�äƥ�������ؤ�ʪ���ؤȿ��ؤ�ؤӡ����θ奲�å�����ؤ�Ǯ�ϳؤˤ�äƳذ���ʸ��������ޤ�����
- 1863ǯ��23�ͤ�ǯ�˥�������ؤ˹ֻդο�������ʪ���ؤȿ��ؤθ��������ޤ���
- 1870ǯ�ˤϥ�������ؤ�ʪ���ؤȿ��ؤζ����ʤ��������������ˤˤʤꡢ1878ǯ��38�ͤλ��ˤϥ�����ŷʸ��ȵ��������Ĺ��Ǥ̿����Ƥ��ޤ���
- ŷʸ��ȤϤ������ļ�Į�����ʤ�ŷʸ��ϼ��Ǥʤ�Τǡ���²�ν��ྮ���ʲȤ�ŷʸ��ˤĤ��Ƥ����ΤǤ���������Ƥ������٤Ǥ�����
- ŷʸ�λ��ߤϤ������ʤ�ΤǤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���δ֡�1866ǯ�ˤϥĥ������Ҥ��鵻�ѽ�Ĺ�ξ��ۤ���������ؤθ������Ƭ���Ƥ����褦�ˤʤ�ޤ���
- �ĥ������Ҥε��ѽ�Ĺ�ȸ��äƤ⽾�Ȱ�5̾�ξ����ʲ�ҤΤ��ȤǤ���
- ���ظ�����������Ū�������Ϥ���ꤵ�줿�����Υ��å٤ϡ�26�ͤ�̵�����عֻդǤ�����
- ��餷�������Ϥ����ä���
- ����������������ˤϸ��ؤˤ�äƺ��ʤ������Ȥ��������������ͭ̾�ˤʤäƳ��ܤ�Ĺ��Ω�������Ȥ�����˾�ϴ����Ǥ�����
- ���ξڵ�ˡ���γ��䤬���֤�ǧ�����褦�ˤʤä�1878ǯ���٥����ͭ̾��ʪ���ؼԥإ��ۥ�Ĥ���βȤ�ˬ�͡�������ԤǤ���ɥ������μ��ԥ٥���˽Фơ��٥�����ؤ�ʪ���ض��������̶����ο��˽��������Ф������Ǥ���
- ��ϡ������������ο����Ǥꥤ���ʤǤΥ����롦�ĥ������Ȥθ������ζ�Ʊ�����ƻ�����Ӥޤ�����
- ���Ϥε�ƻ�ԤΤ褦�Ǥ�����
- �ब��������ؤǤ��ޤ��ɤ��Զ�������Ƥ��ʤ��ä��Τϻ��¤Τ褦�ǡ���������������ˤʤ뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ����ϰ�Ĥˤ���νм����褯�ʤ��ץ��쥿�ꥢ���ȽпȤǤ��ä������礤�˱ƶ����Ƥ��ޤ�����
- ���å٤ϡ���������ؤ��������Ǥ��륫���롦���ͥ��ǧ���졢���̼��Ǥˤ�餦�Ȥ���������Ĥ���Ǥ��ޤ���������������ؤ���ǧ�����ޤǤˤϻ��ʤ��ä��ΤǤ���
- �ޤ�����β�²���Թ��������ޤ���
- 1874ǯ��������β�²�Τ��٤Ƥ����ե��ˤ����äƤ��ޤ��ޤ���
- ��²��ߤ�����ˤϼ�ʬ��ˤʤ뤳�ȤϤ������к�Ū�ʽ�����ɬ�פǤ�����
- ���ξ�������ǡ����å٤ϥĥ������˼���Ф��Ƥ��ޤ���
- �ĥ������������Ƥϡ���β�Ҥζ�Ʊ�бļԤȤʤ뤳�ȤǤ��ꡢ���θ��֤�Ȥ��������夲�����פΤ���1/3�å٤��������Ȥ�����ΤǤ�����
- ���ϡ�1876ǯ�ˤ��η�����路�ޤ���
- 1868ǯ�����å٤ϸ������ˤ����륢�ݥ����ޥ��å����ͰƤ��ޤ���
- �����������θ������⤳�����夲����إ��饹���ʤ��ä�����ˡ�����åȤ���ä������ʥ��饹���Ǥ�������ޤǤ�20ǯ�֡�1886ǯ�ޤ��Ԥ��ͤФʤ�ޤ���Ǥ�����
- �ޤ������å٤ϡ�1869ǯ�˸������˻Ȥ�������ˡ��ͰƤ������θ������֤�����ޤ���
- 1872ǯ�ˤϡ����ͭ̾�ˤ��������˴ؤ�����������Sine Condition�ˤ���ؤ���Ψ�³�����������ޤ���
- ��ǯ�θ�ˤϡ�����������Ǥ����줿�ĥ�������17����θ���������������ޤ�����
- ��������γ�ȯ�ˤ����äơ��ब���������غ��������������åٿ���Abbe Value���ϡ������߷פ����ڤ��߷��ͤȤʤ�ޤ�����
- ���åٿ��Ȥϡ�3��ʬ����Ĺ��C����D����F���ˤζ���Ψ��Ȥä���ʬ���ͤǡ����ο��ͤ�٤��������إ��饹����¤���ʼ������ˤ�äơ����ص�����߷��̤����ǽ���Ф�褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ޤ����å٤ϡ���̩����ʬ��Ǥ��פ�Ĥ���¬��ʪ�ȴ��ʪ��Ʊ��μ�������֤��Ƶ���Ū�������������Ǥ���������������륢�å٤θ������Ԥ߽Ф����������Ѥ���¬Ĺ���ȯ���ޤ�����
- ¬Ĺ��ϡ��ĥ������ҤǸ��ص������¤����ݤˡ����٤��ɤ���α�ޤ�Τ褤���ʤ���Τ��Բķ�ʤ�ΤǤ�����
- ���å٤��������ѤǤ�¿����פ�Ĥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- 1882ǯ�������ʥ��饹�ⴰ�����������ݥ����ޥ��å����Ǥ��Ƥ��ʤ��������ɥ��Ĥΰ�سؼԥ��åۡ�Heinrich Hermann Robert Koch��1843-1910�ˤ��ĥ������θ�������ȤäƷ�˶ݤ�ȯ�����ޤ���
- ���������Υ��åۤϡ��٥�������������ν���Ǥ�����
- ���å٤ϡ����åۤ������ϸ�������Ҳ𤷡����뤵�������˸��夵���뤿��β��ɤ�ܤ������������դ��������γ��ѤɥХ��������ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ĥ������Ҥϡ���Τߤʤ餺���֤��Τ�Τޤǿ���ƶ���Ϥ����֤���夵���Ƥ������Ȥ��Ǥ��륨�ԥ����ɤǤ���
- ���ʤߤˡ��ٶݤϥե�Υѥ��ġ��뤬1862ǯ��ȯ�����Ƥ��ޤ���
- 20ǯ��κз���Ƥ褦�䤯���������������Υ��ݥ����ޡ��ȸ��������å٤ϰտ�Ū���õ������ޤ���Ǥ�����
- �������ĥ������ˤϡ�Ʊ��Υ饤�Х�Ǥ��륨��ȡ��饤�ļҡ�Ernst Leitz, Wetzlar��1850ǯ��Ω�ˤ����ޤ�����
- ���ݥ����ޡ��ȸ��������Ǥ����Ȥ������褤�輫ʬ�����β�ҡʥ饤�ġˤ⽪��꤫�Ȼפä��ȸ����ޤ���
- ���������å٤��������õ��������ʤ��ä����Ȥˤ�ꡢ�����åĥ顼�ˤ��륨��ȡ��饤�ļҤ⥢�ݥ����ޡ��ȸ�������¤���Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 1888ǯ�����å٤Τ褭����ԡ������롦�ĥ�������˴���ʤ�ޤ���
- ���å٤�58�ͤλ��Ǥ���
- ���å٤ϥĥ�������˴���ʤä�1ǯ�塢���β�Ҥ��ʪ���������Τ�Τˤ��뤿�ᥫ���롦�ĥ��������Ĥ���ޤ���
- ���Ĥ���ݤˡ��������©�ҥ����ǥ�åҡ��ĥ�������������κ����³����ȯ��������������å٤Ȥϰ㤦�����Dz�ҤĤ��褦�Ȥ��Ƥ����Τǡ����å٤����դ�Ԥ����ƺ�����Ω��Ʊ�դ������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���κ��ĤΤ������Ȥ����ϥ��åټ���κ�������Τߤʤ餺���ĥ������Ҥ�ȯ������¿�����õ���̵���Ǹ����������ȤǤ���
- ���κ��Ĥϡ�����δ�Ȥ��������Ƥ���ϫƯ�Ԥ�Ư���䤹�������Ĥ��Υ����ǥ����������Ǥ��ޤ�����
- ������ɽŪ�ʤ�Τϡ�1��8����ϫƯ�Ǥ��ꡢͭ��ˤ������ٲˤ䡢ϫƯ�ҳ����µ��ˤ���ݸ���Ŭ�ѤʤɤǤ�����
- ���å٤��㤬���¿����Ȥ��ư���16���֤�ϫƯ�ǿȤ�ʴ�ˤ��ƥ��å٤��Ƥ������طʤȡ�Ʊ������Ʊ���ϰ��ů�ؼԡ��кѳؼԡ���̿�ȤǤ��륫���롦�ޥ륯����Karl Heinrich Marx��1818-1883�ˤ������������Ʈ���Ω���夬�ä��Ҳ��طʤ�ͤ���ȡ��ץ��쥿�ꥢ���ȽпȤΥ��å٤��������ζ˰��ʤޤǤμҲ�ϫƯ�Ķ���ޥ륯���Ȥ��̤������Dz��פ������Ū�ʲ�ҷбĤ��Ǥ�Ω�Ƥ����Ȥϵ����ˤȤɤ�Ƥ����٤������Ȼפ��ޤ���
- ���å٤���ǯ�ϡ����ص��ѤβʳؼԤȸ��������ҤĤ���бļԤȤ������礤��ǻ���ʤ�ޤ���
- �бļԤȤ��Ƥ��������ꤹ��ͥ�줿���ѥ����ƥ�������줿��ͭ�ʺ�ǽ��ȯ�����ޤ�����
- ��
- ��
- �����åȡ�������åȡ�Friedrich Otto Schott: 1851-1935��
 �ɥ��ĥ����åƥ��Witten�ˤ��ĥ��饹��¤��Ĥ�Ȥ����ޤ�ޤ�����
�ɥ��ĥ����åƥ��Witten�ˤ��ĥ��饹��¤��Ĥ�Ȥ����ޤ�ޤ�����- ��Ƥ����饹�����ȹ������Ĺ��̳���ۤɤǤ��ä����顢������Ū͵ʡ�ʲȤǰ���ޤ�����
- �Ĥ�����ꥬ�饹�����������Ĺ�������饹����¤���������ޤǤˤʤ�ޤ�����
- ��ϡ����إ��饹���Ĥȸ����Ƥ��ޤ���
- ����åȤϡ������إ���ؤDz��ع��ؤ�ؤ���塢1875ǯ����������ؤ��륬�饹��¤���η�٤˴ؤ�����ʸ����ι��������ޤ�����
- 1876ǯ���ब26�ͤ�ǯ�˥��ڥ���˥襦�ǤȾ��Ф��������빩���Ω�Ƥޤ���
- ���å���ΤȤϡ�ǯ��11��Υ��Ƥ��ޤ���
- �����롦�ĥ������Ȥ�35��Υ��Ƥ��ޤ���
- ����åȤ���������ؤ����ä����������å���Τ�Ʊ��ؤΰ��������ο��ˤ��ꡢ�����롦�ĥ������β�Ҥε��Ѹ���Ȥ��Ƥ�������Ƥ��ޤ�����
- ����åȤϡ����åٶ����θ����������������٤��ɤ����إ��饹��ɬ������ʬ��ǧ�����Ƥ����Ȼפ��ޤ���
- ����åȤȥ��åٶ����Ȥϸ��إ��饹�˴ؤ���ո��������֤�Ȥ��ä��褦�ǡ�1877ǯ������إ��饹�δ��ø��椬ξ�Ԥδ֤ǻϤ���Ƥ��ޤ���
- 1879ǯ������åȤϿ��������إ��饹�����θ����ʹ������ˡ�������������ޤ�����������إ��饹�å���Τθ�������ޤ�����
- ¬��η�̡����Υ��饹�ϥ��å٤�˾��Ǥ�����������Ĥ�ΤǤϤʤ��ä�������åȤλŻ��֤���礤�˴��ä�������ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ʸ塢���å٤ȥ���åȤϸ��إ��饹�˴ؤ���Ĺ���Τ��Ȥ��³���뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- 3ǯ�ε��ѽ��̤��ƿ��������إ��饹����Ф��ʳ��ˤޤǤ����Ĥ���1882ǯ������åȤϸ��椹������ʤ˰ܤ��ޤ�����
- �����Ƥ���ʤ뿷�������إ��饹�λ��¸���³�����ޤ�����
- ���λ��¸��ϡ�����åȤȥĥ������Ҥˤ����إ��饹��������Ω�Ȥ������Ǥ�����ޤ�����
- �����������θ���ˤ�����¿�ۤλ�⤬ɬ�פǤ��ä����ᡢ�ĥ������ȥ��å٤������Ϥ����Ǥϸ�����³���뤳�Ȥ��Բ�ǽ�ˤʤ�ޤ�����
- �����ǡ����ϥץ�������ν���������������λ��ǿ�������������Ԥ����������Ȥ����ޤ�����
- 1884ǯ�ˤϡ��ޥ���ġ�Mainz�ˤ˿��������إ��饹��ȯ���뤿���Schott & Genossen���饹���Ƚ����Ω���ޤ�����
- ���β�Ҥϥ����롦�ĥ������ҤȤζ�Ʊ�л�ι���Ǥ�����
- 1886ǯ�ˤϡ���ʬ�����إ��饹��ȯ����44����Υ��饹��ꥹ�ȥ��åפ���������Ͽ���������ޤ������������إ��饹���㡼�������ȡˡ�
- ����������Ͽ�ϡ�������ηϤȤ��礭���ۤʤäƤ��ޤ�����
- ����θ��إ��饹����Ť����Ƕ��̤���Ƥ����Τ��Ф����������ʥꥹ�Ȥˤϡ�����Ψ��3�ܤΥ��ڥ��ȥ�����ʬ���͡������ͤޤǵ��ܤ���Ƥ��ޤ�����
- ������̩�ʸ���������Ф��륷��åȤθ��إ��饹�δ����ˤ�äơ����å٤�20ǯ�ʾ��ۤ��Ƥ������ݥ����ޡ��Ȥθ��������¸����ޤ�����
- ����åȤϤ���ˡ�1887ǯ����1893ǯ�ˤ錄�äƥۥ������Ǥˤ����إ��饹��ȯ���������ʥ��饹���ʼ�����ư�Τ�ΤȤ��ޤ�����
- 1891ǯ���ब40�ͤ�ǯ�ˤϡ����å���Τμ�ݤ˻�Ʊ���Ƽ�ʬ�λ��äƤ�������åȴ�Ȥ˴ؤ���������٤ƥ����롦�ĥ��������Ĥ˰ܤ��ޤ�����
- �ʸ夳�κ��Ĥϡ��ĥ��������롼�פȥ���åȥ��롼�פ�2����DZ��Ĥ���뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- ��
- ��
- �����̿���δ��äγ�Ω�ȸ��إ��饹��¤�γ�Ω���ɥ��Ĥȥ����ꥹ������2005.10.02�ɵ���
- �����ʥ��饹�������إ��������Ϳ�����ƶ���¿��ʤ�Τ�����ޤ���
- �����ʥ��饹���Ǥ���ޤǤθ��ص���ϡ������ꥹ���Τ�Τ�����Ū����ǽ���褯���ɥ��Ĥ����ʤˤ�2ή�Υ�åƥ뤬Ž���Ƥ��ޤ�����
- �����ʥ��饹���Ǥ��Ƥ���Ȥ�����Ρ����ص�������٤��쵤�ˤ�����ޤ�����
- �����ʥ��饹���ä�Carl Zeiss�Ҥϡ������Ǻ���Ȥ˸��������̿�����д����˾���������¬�굡��ʤɤ˼�̤����ʤ���Ф��ƹԤ��ޤ�����
- �����ʥ��饹�ϡ��ĥ������ҤΤߤʤ餺�����ꥹ��ե������θ��ص���������ⶥ�ä��㤤����졢���θ��إ��饹�ˤ�ä���ǽ���ɤ����ص��郎����ƹԤ��ޤ�����
- ���Τ褦�ˤ��ơ����ص������ˤ��֤äƸ��ޤ��ȡ������ꥹ������Ū�˸��ص�����ꡢ���إ��饹�ϥɥ��ĤΥ����ʤdz�Ω���줿��������ޤ���
- 1800ǯ��ϡ����ȳ�̿��̤����������ꥹ���������ȤǤϷ���ȴ�������Ѥ���äƤ��ޤ�����
- �����ꥹ�ϥإ����⡼���졼�����祻�ա������åȥ��������ʤɷ�Ф���������ε��ѼԤ����졢��������ü�ι��������������Ф��Ƥ��ޤ�����
- �ͥ��ʤɤε������Ǥε��ʲ��ˤ⤤�����ꤷ�Ƥ��ޤ�����
- ��ʤɤθ������ʤ⼫�������ꥹ���Τ�Τ������ʼ����褯���̿��������⥤���ꥹ���Τ�Τ��ɼ��Ȥ���Ƥ��ޤ�����
- �ɥ�������������ή�ʤȤߤʤ���Ƥ��ޤ�����
- ���δ������鸫���������Ǥ��ʤ����ȤǤ���
- .
- ���������ػ��Ȥ���ή�ι�Ǥ��ä��ɥ��Ĥ�������ȡ����å٤ȥ��åȡ�������åȤˤ�äƸ��ؤι�ȸ�����褦�ˤʤä����פ���ޤ���
- ���Τ�äȤ��礭�ʤ�Τ������ʥ��饹�γ�ȯ�Ǥ�����
- ���å٤ϡ�����åȤȶ��Ϥ��ƺ��ޤǤ�̵���ä����������إ��饹��ȯ��������θ��إ��饹��ï���Ф��Ƥ�ʬ���֤�̵�������ȤäƤ�餦�褦�ˤ��ޤ�����
- ��
-
- ��
- �������إ��饹���㡼�ȡ�����2005.10.14�ɵ���
- ��
- ���ޤϡ����إ��饹�Υ��㡼�ȤǤ���
- �����˥��åٿ���ʬ���ˤ��ꡢ�ļ��˶���Ψ��Ϳ���Ƹ��إ��饹����������㡼�Ȥ�ɽ������ΤǤ���
- ���إ��饹�ϡ����ߡ��ɥ��Ĥ�Schott�Ҥ�Ϥᡢ���ܤ�OHARA��HOYA���˥���ʤɤθ��إ��饹������餤�������ʸ��إ��饹���ФƤ��ơ��Ƽ��ȼ��ˤ����������㡼�Ȥ��ä����ۤ��Ƥ��ޤ���
- ���Υ��㡼�Ȥ�ǽ�˺�ä��Τϡ������ʥ��饹��ͭ̾�ˤʤä�����åȼҤǤ���
- ��
- ��
- ��
- ���إ��饹���㡼��
- ��
- �ޤ���������ǽ줿ʸ���ϡ���ޤ��ʥ��饹��ʬ���ɽ����Τǡ���ʸ��������إ��饹�Τ����褽���������������Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���åٿ���55�ʾ�Τ�Τϡ����饦��ʥɥ��ĸ��Krone = �����ˤǡ�K�פ�Ϳ�����Ƥ��ޤ���
- νd�ʥ��åٿ��ˤ�45�ʲ��Τ�Τϡ��ե��ȡ�Flinte = ���ƽơ��Ѹ��flint�ϲ����Ф��ˤȸƤФ��F�פ�Ϳ�����ޤ���
- �ˤȣƤ����ˤĤ����Ƥ����L�פȡ�S�פϡ��ڤ���Leicht�ˤȽŤ���Schwer�ˤȸ�����̣�����ꡢSF�����ܸ�Ǥϡ��ťե��Ȥȸ��äƤ��ޤ���
- �ťե��Ȥϡ�����Ψ��⤯ʬ����⤤�ʥ��åٿ����㤤�ˤΤǸ��뤫��˽Ť����饹�����ǡ��Ť��ϱ������줿���饹�Τ��Ȥ�ե��ȥ��饹�ȸƤ�Ǥ��ޤ�����
- ���Τۤ���Ba��La�Ȥ��������Ĥ��Ƥ���Τϡ��Хꥦ�ࡢ����ά�ǡ����饹�ˤ�������������ʬ���ޤޤ�Ƥ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����������Υ��饹�Ǥ���
- ���å٤ȥ���åȤ���˼��������إ��饹�Υ��㡼�Ȥ���Ф��ơ����إ��饹�����������ܤ��İ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �����ʥ��饹�����ϡ���Υ���դ����������ΰ�Ǽ��������饹��������ޤ���Ǥ�����
- ���Υ��饹�ϡ��礭��ʬ���ƥե��ȥ��饹�ȥ��饦�饹�ȸƤФ�Ƥ����ΤǤ���
- ξ�Ԥ��Ȥ߹�碌�ǿ��ä��������ޤ�����
- 1700ǯ���溢�ˤ����θ��إ��饹�����줿�褦�Ǥ��������饹���Ѽ��Ǥʤ�̮���⤢�ä�������Τ������إ����Ф��Τ��ȤƤ����ä������Ǥ���
- 1600ǯ�λϤ�˥���쥪����ä�ŷ��˾����ϡ����饹��Ʃ���٤����ޤޤʤ餺̮����¿��������ʥ��ȤäƱ���������Ƥ����ΤǤ���
- �ե��ȥ��饹�ȥ��饦�饹���ʼ��褯�����褦�ˤʤä��Τϡ�1790ǯ�Υ������ͥ��ʥ�ˤ����إ��饹��¤ˡ�γ�Ω����Ǥ���
- ���å٤ȥ���åȤϡ�����θ��إ��饹�˥Хꥦ���ź�ä��뤳�Ȥˤ�äơ�����Ψ���ݤ��ʤ���ʬ�����㤯�ޤ��륬�饹����Ф��ޤ�����
- ���줬�ޤ������ԥǰϤޤ줿�ΰ�Υ��饹�Ǥ���
- ����դξ����ˤ���忧���ΰ�ϡ���ʿ�������˺��줿���إ��饹�Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- �����ʥ��饹����50ǯ�ۤɷФä�1940ǯ��ˡ��ƹ�Υ⡼�졼��George W. Morey���亮��ȥ����ͥ������浡���ϵ�ʪ���ظ����ˤϡ�La2O3�ʤɤδ����ี�ǻ���ʪ������ΥХꥦ���BaO�ˤ�����Ψ�����ʬ��������Ư�������뤳�Ȥ��ͤ��ߤᡢKodak��꾦�ʲ�����ޤ�����
- ���Ѳ��ޤǤˤϤ��������ʺ����ä��褦�ǡ�����ޤ�����饹�Ϸ�ǯ�Ѳ��ˤ�äƲ������忧����ʤɿ��������饹��¿��������������Ƥ��������Ǥ���
- ������������褹�뤿�ᡢ��ĤˤϽ����Ǵ�ڥ�ĥܤ�ȤäƤ�����ˡ���������ĥܤ�Ȥ��褦�ˤʤä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����������������Τ������äǤ���
- ���ߤǤϡ�����˥��åٿ��ι⤤���إ��饹����ȯ���졢���Ф˶ᤤ�㤤ʬ������ĥե��Dz���ʪ�۾�ʬ�����饹���Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �����Υ��饹�ϡ�˾���ʤɤ˰��Ϥ�ȯ�����Ƥ��ޤ���
- ���饹���㡼�ȿޤƤ���ȡ����إ��饹�ϡ���������Τ褦��ʬ�ۿޤξ�˾�ä���褦�˿��������饹���Ǥ��Ƥ�������������ޤ���
- �̤θ�����ȡ�ʬ�����ޤ��ʤ���ʥ��åٿ���⤯�ݻ����ʤ���˶���Ψ�ι⤤���饹���ä��褿��ˤȤ�Ȥ�ʤ�����ޤ���
- �ޤ���������ǽ줿ʸ���ϡ���ޤ��ʥ��饹��ʬ���ɽ����Τǡ���ʸ��������إ��饹�Τ����褽���������������Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����BK7
- �桹������äȤ�褯�����äˤʤ�BK7�Ȥ������إ��饹�ϡ����åٿ���64.17������Ψ��1.5168�Τ�Τǡ����إ��饹����ǤϤ��ޤ����Ψ���⤯�ʤ�ʬ�����㤤����Τ�ΤǤ���
- ���Υ��饹�ϡ�B ��= �ﺽ�ˤ���K�ʥ��饦��ˤȤ�����̣���﷾���饦�� ��Borosilicate Crown�� ���̣���Ƥ��ޤ���
- ���å٤ȥ���åȤ�1884ǯ�˥����ʥ��饹�����������Ȥ�������Υ��饹�Τʤ��˿��������饦�饹��BK�ˤ����äƤ��ޤ�����
- ����Ψ��Ʊ���ˤ���ʬ�����㤯�����ʥ��åٿ����⤤�˥��饦�饹�Ǥ�����
- BK7�ϡ��ѵ�����ͥ�쥭�����Ĥ��ˤ���ʬ���⾯�ʤ��Τǡ��ץꥺ��κ�����¿���Ȥ��ޤ�����
- ����ե����Υڥץꥺ����д������ᥬ�͡��롼�ڤʤɤˤ�������Ȥ��Ƥ��ޤ������إ��饹����Ǥ�äȤ�¿���ϲ�Ƥ����ΤǤ���
- �������غ���
- ���ͤޤǤˡ����إ��饹��¾�˲桹���褯�ΤäƤ�����غ����Ǥ����������ɤ䥵�ե��������бѡ��ѥ���å��������С��������ʤɤ��ɤΰ��֤ˤ��뤫��ޤ˺ܤ��Ƥ����ޤ�����
- ��������ɤϡ�����Ψ��¾�θ��غ�������٤Ƥ�ȴ���ƹ⤤���Ȥ��狼��ޤ���
- ���ե�����ϡ��빽����Ψ���⤯����������ݤʤΤǸ��إ��饹�Ȥ��ƤϤ��ޤ����Ѥ��줺���ɹ��ʵ���Ū�����䡢��Ǯ�����������륫��ʤɤ����忩�������ܤ��ơ�����Ū�ʻٻ����ⲹ���ⰵ�Ķ��δ�¬������Ѥ���ޤ���
- �бѤϡ�BK7�˶ᤤ����Ψ��ʬ�����äƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �бѤϻ糰�������ֳ��ޤ�����������Ʃ�ᤷ����Ǯ�����Ѿ����ˤ�ͥ��Ƥ��뤳�Ȥ���졼���������ʤȤ��Ƥ褯�Ȥ��ޤ���
- �ѥ���å�������Ǯ�����ɤ��бѤ��²��ʤΤǡ��ⲹ��ǻ��Ѥ�����إ��饹�˻Ȥ��ޤ���
- �������ϺǶ����ܤ���ӤƤ�����غ����Ǥ���
- �����ȥ�����κ����ˤ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����ϥ��饹�Τ褦�ʵ����˲������ʤ���Ǵ�꤬����ڤ��ΤǶ�ǯ���إ��饹�Ȥ��Ƥ����Ѳ��ͤ���ޤäƤ��ޤ���
- �ޤ����ⷿ���äƥ⡼�����ˡ�ˤ�äƥ����������Ǥ���Τ�����̥�����̤ˤ�����²��ˤǤ��ޤ���
- ����������ħ��ɾ�����졢����������ʬ���ȶ���Ψ����ä����餬����Ƥ��ޤ���
- ����ϡ����ܤ��٤�����������������äƤ��ޤ����������ϲ��٤ȼ��٤ˤ�ä����Ѥȶ���Ψ�����إ��饹�����礭���Ѳ����뤳�ȤǤ���
- ��̩�ʸ��ص���˱��Ѥ���ˤ����դ�ɬ�פǤ�����
- ��
- �������إ��饹����ħ��-�����饹�äơ�����2006.04.21�ˡ�2009.05.24�ɵ���
- ���饹�Ȥ���ʪ���ϡ��ɤ�������������äƤ���ΤǤ��礦����
- ���饹�Ͽ尻��Ʊ�����ȸ����Ƥ�ԥ�Ȥ��ʤ��Ȼפ��ޤ���
- ���饹�ϡָ����Ρʤ��褦�����ˡפȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- �Ĥޤꡢ�尻�����˸ǤޤäƤ�����֡��Ȥ����櫓�Ǥ���
- �Ȥ������Ȥϡ����饹�Ͼ�蘆�������б��ΤȤʤ�ޤ���
- �Ť����饹����ɽ�̤��礭�����ͤäƤ���Τ뤳�Ȥ�����ޤ���
- Ĺ�����ַв�ǥ��饹���Ĥ�Ǥ��ޤä��ΤǤ���
- �Ĥޤꡢ���饹�Ϸ뾽��¤����äƤ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ���������бѤ���֤ˤϷ뾽��¤����ä���Τ⤢��ޤ��������������ɤ⥵�ե�������뾽�Ǥ���
- ������������Ū�˥��饹�ϸ����ΤDz��٤�夲��ȿ尻�Τ褦�˽��餫���ʤ�ޤ���
- �ޤ������饹�ϡ��Ļ����ʰ������ֳ���ˤ�Ʃ���Ǥ��ꡢǮ�ˤ�äƺٹ����ưפˤǤ��ޤ���
- ���饹�˶�°ź��ʪ������뤳�Ȥˤ��ȯ�����饹���뤳�Ȥ�Ǥ��ޤ���
- ���������ˤ�äƹ����ʤ�Ϥᡢ�����ص������ʤ�¿�Ѥ���Ƥ��ޤ�����
- ��
- ������ħ��
- ���饹�ϸ����ΤǤ��롣
- �뾽����¤�ǤϤʤ���
- Ǯ���̤��䤹����
- �ŵ����̤��ˤ�����
- ���Ϥ����椹������̡ʵ����˲��ˤ��䤹����
- ������°�ȥ��饹��
- ��°�ȥ��饹���������礭���ۤʤ�ޤ���
- ��°�ϡ�����Ū�˶�°���Ƥ��ơ�Ʃ���ǤϤ���ޤ���
- Ʃ���ʶ�°�Ϥ���ޤ���
- ��°���ŵ����ɤ��̤��ޤ��������饹���ŵ����̤��ޤ���
- ��°�ϡ��뾽��¤��ʣ������ʬ��ʬ�Ƿ뾽��¤����Ĥ�Τθġ��η뾽γ�������ޤäƤǤ�����Τ��ۤȤ�ɤǤ���
- ���������ΤΤ�Τ⤢��ޤ���
- ��
- ����̵������ȥ��饹��
- ̵���������ɽŪ�ʤ�Τϡ�ƫ��Ǥ���
- ƫ��ȥ��饹�ˤϡ����˲���䤹�����ŵ����̤��ʤ��Ȥ�����ħ�����ꡢǮ���Ф��Ƥ�ƫ��϶������饹�Ͽ尻�ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �ޤ���ƫ��ϰ��̤˸����̤��ʤ���Ʃ���ΤǤ��ꡢ���饹��Ʃ���Ǥ���
- ��
- ��������ȥ��饹
- ����ȥ��饹�ΰ㤤�ϡ���������̤��ˤ��������饹�Ͼ�˼夯�˲����䤹�����ȤǤ���
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
|
|
||||
- ��
- ������ɽŪ�ʼ̿����-�����������ȥ�ץ�åȡ��ƥå�����Gauss��Triplet��Tessar������2005.08.26�ˡ�2018.09.12�ɵ���
- �̿��ѤΥ�Ϥ���ޤǤˤ��������ʥ����פΤ�Τ��������ޤ��������̿����ȯ�θ�ή�ɤäƤߤ�ȡ����θ����ϸ��إ��饹�����ꤷ�ƶ��뤵���褦�ˤʤä�1900ǯ����˹Ԥ��夭�ޤ���
- ���λ����˴���Ū�ʼ̿���θ��إ쥤�����Ȥ����������褦�˻פ��ޤ���
- ���줬�����������פΥ�Ǥ��ꡢ�ȥ�ץ�åȥ����פǤ��ꡢ�ƥå��������פǤ���
- ����3�ĤΥ����פ��餵��˻�ʬ���줷��¿���οʲ������̿�������ޤ줿�ȹͤ��ޤ���
- ���������̿���δ��äȤʤä����ĤΥ�ˤĤ��ƴ�ñ�˾Ҳ𤷤����Ȼפ��ޤ���
- ��
- ���������������ס�Gauss��1888ǯ
- ��
- ���Υ�ϡ�����¤�ɸ������̾��ˤʤäƤ��������ǡ��������Ȥ��ʤ��Ǥ��褽�����оΤΥ쥤�����ȤˤʤäƤ��ޤ���
- ����ʿ��ؼԤ�̾�����դ���줿��Ǥ�������������Johann Carl Friedlich Gauss�� 1777 - 1855�ˤ��ºݤ��߷פ����櫓�ǤϤ���ޤ���
- �������뤬�̿���ȯ��������������������60�ͤ��Ƥ��ơ��̿���ˤϿ����ؤ�äƤ��ޤ���
- ���ŷʸ�ؤ�ơ��ޤˤ��Ƥ��ޤ������顢��μ㤤����˾����˿����ؿ�������ޤ�����
- 1817ǯ��40�ͤ��ब��������˾�������ʪ��ϡ�2��Υ�˥�������Ǥ�����
- ����ϡ�����ޤ�˾����μ�ή�Ǥ��ä��̥�ȱ����Ž���碌��ե饦��ۡ��ե������Ȥ������ۤʤä���ǰ�Ǥ�����
- �ե饦��ۡ��ե�����Joseph von Fraunhofer�� 1787-1826���ϲ��ʻҤ�ͤ��Ф����ͤȤ���ͭ̾�ǡ��������ͤȤ��Ƥ�����ͭ̾�ʿͤǤ���
- ��������ν����˾���������ޤ�����
- �������ξ�������ʪ��ϡ����̼����ȿ��������褯���פ���Ȥ�����ħ��spheroachromat�ˤ���äƤ��ޤ���������������¤�����ä���
- �����顢��Υ�ϰ��٤�˾����Ȥ��ƻȤ��뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����
- 70ǯ���1888ǯ�������ʥ��饹����ڤ⤢�äơ��ƹ��ŷʸ�ؼԥ��顼����Alvan G. Clark�ˤϡ�����������Ƥ�����ʪ�����Ѥ��ƹʤ���ξ¦��2�����֤���Ȥ����������פ��Ĥ����õ����ä��ƹ�Υܥ�������Bauch&Lomb��1853ǯ��Ω�ˤ������䤷�ޤ�����
- ������������߷פǤϿ����������ʤ�ĤäƤ������ᡢ�ɥ��ĤΥ����롦�ĥ������ҤΥ���߷ԥ�ɥ����Ρ�Paul Rudolph�� 1858 - 1935�ˤϡ���˥��������1�Ф�Ž���碌������֤����������顼����4�繽��������6�繽�����夨������������ޤ�����
- ���줬1895ǯ��ȯ�䤵�줿�ץ�ʡ���Planar��f=60mm��F3.5�ˤȤ�����Ǥ���
- ����ˡ��ץ�ʡ��Ǥϡ���쥤�����Ȥ��оΤˤ��뤳�Ȥ˸Ǽ����������F3.5�γ����ǤϤ��ʤ�Υ��������ФƤ��ޤ��������������뤿��ˤ�2��3�ʤ�ʤ�ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- ����������褷���Τ����ѹ��T.T&Hobson�ҤΥ��Horace William Lee�� 1889 - 1976�ˤǤ�����
- ��ϡ������о�������������ġ��ˤ����Ƹ��̤ζ���Ψ���ä����إ��饹�����ơ��������������˽���ޤ�����
- ���Υ��F/2�����뤵�Ȳ��50°����礹���ǡ���Opic�סʥ��ԥå��ˤȤ�������̾�����䤵��ޤ�����
- �����˥����������פΰ���δ�����˻��ޤ�����
- �ʸ塢�����������פϴ�¿���ѷ���ФƸ���Ǥ�ɸ������ɽŪ�ʥ�쥤�����ȤȤʤäƤ��ޤ���
- ��
- ��
- ������������߷פǤϿ����������ʤ�ĤäƤ������ᡢ�ɥ��ĤΥ����롦�ĥ������ҤΥ���߷ԥ�ɥ����Ρ�Paul Rudolph�� 1858 - 1935�ˤϡ���˥��������1�Ф�Ž���碌������֤����������顼����4�繽��������6�繽�����夨������������ޤ�����
- ��
- ��
- ��
- �����ȥ�ץ�åȥ����ס�Triplet��1893ǯ
- �ѹå��ҡ�Thomas Cooke & Sons�ˤθ��ص��Ѽ��ơ��顼��Dennis H. Taylor��1862-1943�����߷פ�����3�ĤΥ������Ȥ��鹽��������Ǥ���
- �ơ��顼��������ƥ�����ȯ���ԤȤ��Ƥ�ͭ̾�Ǥ���
- �ĥ������ҤΥ�ɥ����Τ��ץ������ȸƤФ�륢�ʥ������ޡ��ȥ��ȯ���Ƥ���Ʊ��������1893ǯ�ˡ����˥���ץ�ʥ�쥤�����ȹ����ˤ�äƥ��ʥ������ޡ��Ȥ�ã�������ˡ���ơ��顼�ˤ�äƹͤ������졢�ȥ�ץ�åȥ��̿̾����ޤ�����
- �ȥ�ץ�åȥ�ϡ��̱��̤λ����ñ���Υ�������֤��뤳�Ȥǡ�2�Ĥο������ȥ����ǥ��5��������ͳ�˥���ȥ�����Ǥ���Ȥ����礭����ħ����äƤ��ޤ�����
- �̱��̤Υ���ץ�ʹ����ˤ���ϡ���������֤��줿���������������Τ˰�Ͳ���⤳�ʤ����Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ���������⤳�ʤ��ˤϡ�3�Ĥθ��إ������Ȥ˿����������θ��إ��饹��ɬ�פǤ�����
- ���θ��إ��饹�˥����ʥ��饹���������ޤ�����
- ���å���ϡ������Ȥˡ����å��Τ���Thomas Cooke & Sons�ҤǤϺ���ޤ���Ǥ�����
- �Ȥ����Τϡ�Thomas Cooke & Sons�ҤǤ�ŷʸ�ط��λŻ��Ǽ���դǡ��̿���Υӥ��ͥ��ˤϤޤä�����̣������ʤ��ä�����Ǥ���
- �����ǡ����å������¤����ѹ�Leicester�ˤ���Taylor, Taylor & Hobson�ҡ�TT&H�ҡˤ˾����Ϥ����Ȥˤ����ʸ塢Cooke��ϡ��Dz���������ä˥ϥꥦ�åɤ�̾��������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- �����ƥå��������ס�Tessar��1902ǯ
- �ƥå�����ϡ�1902ǯ�ɥ���Carl��Zeiss�Ҥ�Paul Rudolph��Τˤ�ä��߷פ���ޤ�����
- ��ɥ����Ρ�Paul Rudolph ��1858-1935�ˤϡ����å٤ν���Ȥ��ƥ�������ؤ�´�ȸ�ĥ������Ҥ����Ҥ��ޤ�����
- ��ɥ�դν���Ǥ��ä�����ȡ�������ǥ륹��֡�Ernst Wandersleb��1879-1963 �ˤ�ޤ���������ؤ�´�ȸ�ĥ����������ꡢ��̤μ̿�������߷פ��Ƥ����ޤ�����
- �ƥå�����ͳ��ϡ����ꥷ����Tetra��4�ĤΡˤȤ������դ�����Ƥ��ơ�4�繽���Υ��Ȥä��ΤǤ���̾�����Ĥ����ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ƥå�����ϡ������ꥹCooke�Ҥdz�ȯ���줿3�繽���Υȥ�ץ�åȥ��¿ʬ�˰ռ����Ƥ��ޤ���
- �ƥå�����ϡ��ȥ�ץ�åȥ�θ�̤����ޥ��å���ʿ��ä���� = achromatic doublet�ˤǹ���������ΤǤ�����
- �ʸ塢�ƥå�����ʬ�व��륫�������������Ǥ��ޤ�����
- �ĥ������Υ饤�Х롢�饤�ļҤΥ饤���ʥ饤�ļҤΥ���顢Leitz Camera��ά�Ρˤ˻Ȥ��Ƥ���ͭ̾�ʥ���ޡ���ϡ��ĥ������Υƥå������õ����ڤ�Ƥ���ޥå������٥졼����Ρ�Max Berek��1886-1949�ˤˤ�ä��߷פ���ޤ�����
- �ƥå�����ϡ������롦�ĥ��������õ�����ʧ�äơ��ƹ�Υܥ���&����ҡ������ꥹ�Υ��å��ҡ������ꥢ��F�����ꥹ�����ҡ��ե��E�����饦���Ҥʤɤ��������ޤ�����
- 35mm�ե�����Ȥä������ϡ��ĥ������ҤΡ֥��å����פ��饤�ļҤΡ��饤���פ�����ͭ̾���ä��褦�Ǥ���
- �Ȥ����Τ⡢�饤�ļҤϤ��⤽��̿�������¿���ä��褦�ǡ��饤�ļҤΥ���顢�饤����1913ǯ�˵��ѼԤǤ��ä������������Х�ʥå���Oskar Barnack��1879-1936���ˤ�ä����߽Ф���ޤ���
- ������ή�Ǥ��ä��̿����Ĥ�Ȥä�����餬�ɤ��ˤ�Ť�����ñ�˻������ӤǤ��륫�����ꤿ���ȹͤ��Ƥ����Х�ʥå������Dz��Ѥ�35mm�ե��������ڤäơ�������Ǽ��ƻ��Ƥ����Τ��Ϥޤ�Ȥ���Ƥ��ޤ���
- �ʥХ�ʥå���ξ���Ȥ�����ҡʤҤȤҤ��ˤ�Ĺ����ե�����Ĺ���ȷ���36�绣��θ����Ȥʤ�ޤ�������
- �饤���ϡ����������ͥ���Ǥ�����������鼫�Τ������ɤ��Ǥ��Ƥ��ơ��㤨�С��ե�������Ĵ���Τ���Υ�ե���������������ե���ബ���夲�����������Υۡ���ǥ��ʼ�������ˡ��ե�������ץ졼��å���������ϴ���ʤɥ饤�Х����ٷ���ȴ���Ƥ����褦�Ǥ���
- �饤�������夵�줿��ϡ�1925ǯ�Τۤ�ν���δ֤ϡ��饤�ġ����ʥ������ޥåȡ�Leitz Anastigmat��f50mmF3.5��3��5�繽���ˤȥ���ޥå�����Elmax��f50mmF3.5��3��5�繽���ˤ��Ȥ�졢1926ǯ����ޥå������٥졼����Τˤ�륨��ޡ���Elmar�˥��f50mm��3��4��ˤˤʤ�ޤ�����
- ����ޡ���ϥ����������ʤ��Ʋ�����ɤ��ä��Τ�������Ψ���夬�ꡢ�饤�����������礤�˹������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����;�̤Ǥ������Υǥ����륫���ο����ȼ�äơ��ǥ����륫���������Ĥ���ƥե���५���ǥΥ��ϥ������Ѥ�������ե�������ȡ��Żҵ��Ѥ����դȤ���AV���ť���ζ��褬�㲽���Ƥ��ޤ���
- AV���ť���ϡ����طϡʥ�ˤΥ֥��ɥ�������ʤ��Τǡ��ĥ����������Ѥ����ꡢ�饤�ĤΥ����Ѥ�������֥��ɥ������������Ϥ�ʧ�äƤ��ޤ���
- �����Υ��������ͭ̾�Ǥ��뤫�ξں��ȸ����ޤ��礦��
- ��
- �ڥɥ��Ŀ��ؤε� - ��������Johann Carl Friedrich Gauss��1777-1855�ۡ���2005.07.27����
- �ɥ��Ĥ�������������ϡ�ŷ�ͤ�̾��ۤ����ޤޤˤ������ؼԤȤ��Ƥΰ��֤Ť��������ˤ���ޤ���
- Ʊ����ˡ��ե�Υե�ͥ��Augustin Jean Fresnel��1788-1827�ˤ����ޤ���
- �������ξ��ع����塢1+2+3+������+98+99+100�ι���¤Ȥ��ñ�ʿ������֤����������ԥ����ɤ䡢�����ζ��դ����⤦��˶����뤳�Ȥϲ����̵���ȸ��路��ۤɤ���Ϥ���������Ū��ǽ�����֤��Ƥ��ޤ�����
- ¿����ͥ���ʿ��ؼԤ������Ǥ���褦�ˡ����ŷʸ�ؤ�����Ȥ���1807ǯ��30�ͤ�ǯ�˥��å���ŷʸ��Ĺ�ȤʤäƸ塢40ǯ�֤��ο��ˤȤɤޤ�ޤ�����
- �������Ͽ��ؼԤȤ��Ƥΰ��֤Ť�������ȿ�̡��������Ȥˤ���ʪ���ؤؤι���¿��ʤ�Τ�����ޤ�����
- ������ñ�̤Ǥ��륬�����䡢ʣ��ʿ�̤γ�ǰ�������줿������ʿ�̡��Ǿ����ˡ��ȯ�����������˸���������ʬ��������ʬ��=������ʬ�ۡˤ�����ʤ�����������Τ���¿������ޤ���
- ���ؤ�ʬ��Ǥ⥬�������פ�Ĥ��Ƥ��ޤ���
- ��μ����Ȥ����ͤ�����ǽ�˻Ȥä��Τ��������Ǥ��ꡢ�������Ѥ��ƥ�����ʶἴ�����ˤ�Ƴ���ޤ�����
- ������Ȥϡ�1/a + 1/b = 1/f �Ȥ��������ߤο�����ñ�ʸ����Ǥ���
- ���θ���������Ω�ĸ��ؤ��ΰ��ἴ�������������ΰ�ȸ��äƤ��ޤ���
- ��μ����ιͤ��������������ʸ�ϡ�1840ǯ��ȯɽ�Ǥ���Τ������ǯ�θ���Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ��θ���ơ��ޤϡ����ؤ�ŷʸ�ؤ���ʤ�ΤǤ��ꡢ���ؤ�ŷ��˾����δط�����ͻ����оݤȤ����褦�˸��������ޤ���
- ����߷פ�ԤäƤ��ơ���˼̿����ɸ��Ȥʤ륬���������פΥ�ϥ��������߷פ������ȯü�ȤʤäƤ��ޤ���
- �����������ߤΥ����������פΥ���Τ�Τ��������ۤ������Ȥ����Ȥ����ǤϤʤ���ͭ̾�ʳؼԤ�̾����˥å��͡���Τ褦�ˤ��ƻȤä��Ȥ�������̤�������ޤ���
- ��
- ��
- ��
- ��
- ���������Υ������-���Dz襫���˻Ȥ���ĥ��������
- ��μ̿��Υ�ϡ��Dz襫���(�ɥ���������ե�å��� = ARIIflex) �˻Ȥ��Ƥ����Ǥ���
- ���¤�φ80��Ĺ����76mm����ޤ������ä���ȽŤ���720��˥��饹�β��Τ褦�ʥ�Ǥ���
- ���Υ�ϡ��ɥ��ĤΥ����롦�ĥ������Ҥ��߷������������Υf85mm��T2.1����ǽ�����Planar�ʥץ�ʡ��ˤȸƤФ���Ǥ���
- �ץ�ʡ��ϡ�1895ǯ�ʺ�����110ǯ�����ˡˡ������롦�ĥ������ҤΥ���߷ԥ�ɥ����Τ��߷פ������������Υ�ǡ��������Ū�ʥ�Ȥ���̾�����Τ��Ϥꡢ���������Ӥ��ޤ�����
- ���Τ��ᡢ���Ǥ⤳�Υ֥��ɤ��ĤäƤ��ޤ���
- ��ιʤ꤬F�ʥ�С��Ǥʤ���T�ʥ�С��ˤʤäƤ��뤳�Ȥ˱Dz軣�Ƥ����̤����Τ��᤹�륷�ӥ��������Ǥ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ��ޥ���Ȥϡ�����ե�å��������Υޥ���Ȥǡ����ƥ�쥹���ΥĥФθ����ե���������˽ФƤ��ơ��ԥ��ɤˤ�äƥ����Υ����ɥԥ�˹�碌���������������¦����������Ƥ����ž����ۥ����ƥ�����夷�ޤ���
- ��ʤ��T�ʥ�С��ˤ���ΰ�����ˤ��ꡢ���μ��˥ե�������Ĵ��������֤���Ƥ��ޤ���
- �ʤ�θ��2�Ĥο���ϻ��Ƶ�Υ�Ǥ��ꡢ�ե����ȿ������֤ǥ�ȥ�ɽ������Ǥ���
- �����������餱�Ǥ狼��褦�ˡ��ե��������ϥ������ۤ�1��ž���Ȥ��Ǥ������Ƶ�Υ0.9m����̵�����∞�ˤޤǤΥե�������Ĵ������ǽ�Ǥ���
- 0.9m�Ȥ����Ȥ��ʤ���Υ�λ��Ƥǡ����ε�Υ�ޤǼ������äƤ���Τ����ȴ������ޤ���
- ����ǥ�����뤵��T2.1��
- ����Ť��櫓�Ǥ���
- �ե����Ȥȥ�ȥ�ɽ���δ֤ˤ��륮���λ����Τ褦�ʤ�Τϡ��ե���������γ��ߤ�Ǥ�������������ޤ�Ƥ��ƥ��ӥ��ʥե�������Ĵ���˱�������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �ե����������ե�����ϽŤ������ڤ���������˾������֤ǥե�����������ԥ��äȤȤޤ봶���Ǥ���
- ���Υե�����ϺΥ����ȥե�������35mm����ե�����Ǥ�̣�廊�ޤ���
- �����ȥե���������Ǥϥ⡼���ǥ��Ф����ᡢ��ư�Ǥ�����ͤ��Ƥ��ޤ���
- ����������ư����ư��ư�������Ȥ���Ȥޤ��Ȥ������Ǥ���
- �鷺��1/3�β�ž�ѤǶ��Υ����̵�±�ޤǹ�碌�褦�Ȥ��ơ����ξ��ž�⥹�ࡼ���Ǥʤ�����̯�ʥԥ�ȹ�碌�˻Ͷ�Ȭ�줷�Ƥ��ޤ��ޤ���
- �Dz襫���ǻȤ����Ǥϡ��ɥ��Ĥ�Zeiss�Υ��¾�������ꥹ�Υ��å���Cooke�ˤΥ��ͭ̾�Ǥ���
- ���å��Ȥ����Τϡ�Thomas Cooke & Son�ҤΤ��Ȥǡ��ѹ�ͥǥ˥����ơ��顼���ȥ�ץ�åȷ��Υ��ȯ���������Ȥ�ͭ̾�ʲ�ҤǤ���
- ���å��֥��ɤΥ�ϡ��ºݤˤϤ��β�Ҥ���¤���줺��Taylor, Taylor & Hobson�ҡ�TT&H�ҡˤ���¤�����䤵��Ƥ��ޤ�����
- ���β�Ҥϡ��Dz�ȳ��ǤϤȤƤ�ͭ̾�ʥ������ǡ��Dz襫�����ƹ�Bell & Howell��Michell�˸����˥���äƤ��ޤ�����
- ���ߤϡ�Cooke Optics Ltd.��Leicester�ˤȤʤäƱDz��ѡ���Ƚ�ѤΥ����¤�����䤷�Ƥ��ޤ���
- ������Ф��ƱDz襫����ͦ�Ǥ���ɥ���ARRI�ҡ�Arnold & Richter�ˤϡ�����Υ����Ѥ����Ȥ����櫓�Ǥ���
- ����ɸ������2020.01.11����
- ���Ʋ�Ѥ��ʹ֤λ�Ѥ�Ʊ��50�����٤��ļ̿����ɸ���ȸ����ޤ���
- ��
 �����ϡ����˼����褦���������������ȤʤäƤ��ƹʤ����оݷ��ȤʤäƤ��ޤ���
�����ϡ����˼����褦���������������ȤʤäƤ��ƹʤ����оݷ��ȤʤäƤ��ޤ��� - ���Υ���ץ���1962ǯ����¤���줿��ΤǤ���
- �����Ĥߤ���äȤ⾯�ʤ���������ľ�ˤȤ������²����䤹����Ȥʤ�ޤ���
- 1962ǯ���������뤤���ɬ�����ϡ�®��Ϫ�л��֤�����Ȥ�����ͳ���⡢�ե�������������뤯�������Ȥ�����ˤ��ޤ���
- �����ΰ���ե����ϡ���������ͤ������ȿ�ͥߥ顼��ķ�;夲�ƥե���������Ǹ��Ƥ��ޤ�����
- ���¤ξ�������ϰŤ��ƥե����������碌���餤���꤬����ޤ�����
- 1960ǯ���ɸ���ϡ�F2.0��F2.8���٤Ǥ���桼���������ˤ��F1.4�Ȥʤ�F1.2�����뤤������ޤ�����
- ͼ������֤λ��Ƥ˰��Ϥ�ȯ�������Τϸ����ޤǤ⤢��ޤ���
- �����������뤤���ɸ���˸����ǡ����ѥ��˾���Ǥ����뤤��Ϥ��ޤ긫�����ޤ���
- ��������Τ����Ѥǥ����Ȥ�⤯�ʤ긽��Ū�ǤϤʤ��褦�Ǥ���
- �ǥ����륫������ˤʤäƻ����ǻҤδ��٤��夬���Żҥե���������ˤʤ�ȡ����Ȥ��������¤Υ��ȯ���뤳�ȤȤ�ʤ��ʤäƤ��ޤ�����
- ����¥�ϼ������ޤ��뤿��ˤ�������Υ������Ȥ�Ȥ������Τ���˥��ȿ�ͤ�¿���ʤä�F4��F5.6�ǻ��Ѥ�����Ǥ�����¥�ˤ��ʤ�����������ɤ����Ȥ�����ޤ���
- �������ѥ��
- ���Υ�ϡ� f = 13mm�ξ�����Υ����ĥ饤���������ʥե륵�����ˤ�Ķ���ѥ�Ǥ���
 ���Ʋ�Ѥ��г���������118�٤���ޤ���
���Ʋ�Ѥ��г���������118�٤���ޤ���- ���β�Ѥϡ�����餫��3��ȥ�Υ�줿�о�ʪ��8.3��ȥ� x 5.5��ȥ���ϰϤ��ڤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���̤�180�١�Ⱦ����ˤϤ��������Ȥ����ۤɤε���Ƥ��ޤ���
- ���ϰϤ������ͤ����������˶ʤ��Ƥ��������̤�Ƴ���Ƥ��ޤ���
- ���Υ�ϡ�����ե�����ѤΥ�Ǥ��뤿�ᡢȿ�ͥߥ顼��ե�����̤ȥ������δ֤����֤���ط��塢����濴���֡�������� H'�ˤ���Τʤ����֤ˤ���ޤ���
- �ޤ��������������F�ˤϡ������ˤ���ޤ���
- ��������ˤĤ��Ƥ���֤Ӥ�Τ褦�ʥĥФϥ�ա��ɤǡ����������˴ط����ʤ����������������ä���ȿ�ͤˤ�äƲ����Υ���ȥ饹�Ȥ��㲼����Τ��ɻߤ���ΤȤभ�Ф��ˤʤä�����ݸ����Ū������ޤ���
- 1976ǯ�˳�ȯ���줿���Υ�ϡ�������ɤ���������Ū��̾��������ơ������ޤ�40ǯ����¤����³���Ƥ��ޤ���
- ����˾����
- ˾���ϡ���Ѥ�10�����ٰʲ��ȶ�����ǡ��ˤ�������Τ�����Ƴ��绣�Ƥ���Τ˻Ȥ��ޤ���
- ����¤��礭���Τˤ⤫����餺������Υ��Ĺ���ΤǸ����椬�������ʤ�ޤ���
- F2.8��˾���Ǥ����뤤��Ȥʤ�ޤ���
- ˾���Ǥ�F4����F5.6������Ū�ǡ�F8�ȸ�����⤢��ޤ���

- ��ޤ�˾���������ޤ���
- ���3���롼�פǹ������졢�����椬����ȤʤäƤ��뤿���ȥ�ץ�åȷ��Ȥʤ�ޤ���
- ������α����������˰�ư���뤳�Ȥˤ��������֤��Ѥ�ꡢ�ե���������ǽ������ޤ���
- �̾�Υ�ϥ�����Τ�����˰�ư�����ƥե���������Ԥ��ޤ���
- ������˾�����礭���ƥ�����Τ������ư�����Τ����ѤʤΤǡ�������������α�������������夵���ƥե�������������ˡ���Ȥ��ޤ�����
- �����ʡ��ե������������ȸ����ޤ���
- ���̤ˤϡ��۾�ʬ����ED���Extra-low Distortion Lens�ˤ�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �۾�ʬ����ϡ����Ф���ɽ����뿧�����ζˤ���㤤���إ��饹�ǡ����������˾���ˤϤʤ��ƤϤʤ�ʤ���ΤǤ�����
- �Τϡ����������۾�ʬ�����饹�Ϸ��ФΤ褦��ŷ���Ǥ�������Ǥ������ѹ���ʤ�ΤǤ�����
- ���줬���Ǻ����褦�ˤʤ�Ȱ²��ˤʤꡢ���ꤷ�䤹���ʤ�ޤ�����
- ���η�̡��쵤��˾������ǽ���夬�ꡢ���ġ����ʤ��ޤ�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ED��β��äϡ��д����˾������������ˤ�ڤ�Ǥ��ޤ���˾���ϡ�ŷ�λ��Ƥ�¾�˥��ݡ���ʬ���¿���Ȥ�졢�����ԥå������Ť����ǯ�����äƿ����������ȯ������褿��������ޤ��������ԥå����Ťϡ�����������ˤȤäƼ��ҤΥ֥��ɤ�ؼ������礭��������Ǥ���褦�Ǥ���
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
|
|
||||
-
- ��
- ������β����ϡ�Resolving Power������2005.10.01�ˡ�2006.04.10�ɵ���
- ��
- ����ޤǥ�η�����Ȥߡ��ʤ�κ��Ѥʤɤ������Ҥ٤Ƥ��ޤ��������ǽ�Ū�˥����ǽɾ���ϤɤΤ褦�˹Ԥ��Ƥ���ΤǤ��礦����
- �����Ϻǽ�Ū�ˤϿʹ֤�Ƚ�Ǥˤ���ͤ���Τǡ��ݽѤȤ�����������ϡ���εҴ�Ū�ʿ���ɽ��������ΤǤ�����
- �����ϡ��ͤˤ�ä�ø�����̤����ߤǤ��ä��ꡢ���������ߤǤ��ä��ꡢ���å���Ȳ����ζ����ޤǥԥ�Ȥ��魯���⾯���ܤ��������������Ǥ��ä���Ȥޤ��ޤ��Ǥ���
- ����������¬�Ȥ����������������ȡ��ͳѤ���ΤϻͳѤ������ϤǤ���������㡼�פˡ����ϸ��¤ο�����¤ˡ��Ȥ����Τ����ޤ��������Τ��������ȹͤ��ޤ���
- ���ä� ��ϡ�ʪ�Τΰ��������ΰ����Ȥ��ƥ��㡼�פ˷�Ф��뤳�Ȥ�����Ū������ǽ�Ȥʤ�ޤ���
- ʪ�Τ���Ф����������˽��ޤ�ʤ�����ɹ��ʥ�Ȥϸ����ޤ���
- �ɹ��ʥ���Ҵ�Ū�ʿ���ɽ���Ȥ��Ƥϡ���β����Ϥ����Ѥ���Ƥ��ޤ�����
- �����ǽ�ϡ�������ǽ�����٤ƤȤ����櫓�ǤϤ���ޤ���
- �������ʤ��顢�Ҵ�Ū�ʿ���ɽ���Ȥ��ƤϤ��줬��äȤ�üŪ�˸���ɽ������;����ǽɽ���Ǥ��뤿��˺��Ѥ���Ƥ���ΤǤ���
- ��
- ��β����Ϥϡ��ɤ�����٤������Ҥ����Ȥ��Ƽ��̤Ǥ��뤫�Ȥ�����Τǡ����ͤ�ñ�̤Ȥ�����/mm��lp/mm�ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- lp�ϡ�lines pair��ά�Ǥ��������1mm������Τɤ�����κ٤�������Υڥ��������������뤫�������ͤǡ����ͤ��礭���ۤɺ٤������������Ф��뤳�Ȥ��Ǥ���ǽ���ɤ��ȸ����ޤ���
- �����Ϥϡ�������������Ϥο���Ūɽ���٤ι�Ǥ��ޤ�����
- �ºݤˤɤΤ褦����ˡ�ǥ�β����Ϥ�¬�ꤵ���Τ��Ȥ����ȡ�����㡼�ȤȸƤФ���������ޤ줿���㡼�Ȥ�ȤäƸ����������̤��������ꡢ�ɤ����٤κ٤���������/mm�ˤޤ����Ȥ��Ʒ��Ǥ��뤫��Ĵ�٤ޤ���
- ������ݤˡ��ɤ����٤ޤǸ����뤫��Ƚ�Ǥ������Ԥ�ǽ�ϤǷ����Ƥ��ޤ��ΤϤ褯����ޤ���
- �ޤ�������濴���ȼ������Ǥ���ǽ�ϰ�äƤ���Ǥ��礦��������ΤϤä��ꤷ���ʻҼʤ�ø���ʤǤϷ������ٹ礤���Ѥ�ä���ޤ���
- ��
- ��
- ����ǻ�٤ˤ��쥹�ݥ����ȿ��ˤ��쥹�ݥ�

- ���˼����褦�ʰ���ֳ֤Υ��ȥ饤�֡ʳʻҾ��ˤΥ��㡼�Ȥ�Ȥäơ�����̤��������ä��Ȥ����ɤΤ褦��������Ф��Ǥ��礦����
- ����Ū�ˡ������Ϥ�ɾ�������硢���٥쥹�ݥˤ����ˡ�ȡ����֥쥹�ݥˤ����Ĥ�ɾ��ˡ������ޤ���
- ���٥쥹�ݥ�ˡ�ϡ����㡼�ȡʼ� = ���ȥ饤�֡ˤ�ǻ�٤��Ѳ������ơ�ǻ��ǻ�٤�������ǻ�٤��Ѳ������ơ������ɤΤ褦���ɽ����뤫����ˡ�Ǥ��ꡢ���֥쥹�ݥ�ˡ�ϡ����ȥ饤�֤μ��ȿ���⤯���Ƥ��äơ����˺٤��ʼʳʻҤ�Ȥäơˤɤ��ޤ��ɽ����뤫����ˡ�Ǥ���
- ����Ū�ˡ����٤��夯�ʤ��Ϣ��ơʥ���ȥ饹�Ȥμ夤����Τˤʤ�ˤĤ�ơˡ����Υ쥹�ݥ������ʤ�ޤ���
- �ޤ������ȿ����⤯�ʤ�����Ϥ�����ɽ��Ǥ����˶��٥쥹�ݥⰭ���ʤäƹԤ��ޤ���
- ���������쥹�ݥ�ɾ������ݤ˻Ȥ����㡼�Ȥϡ���ȹ��Υ���ȥ饹�Ȥ�1:1000���⤷����1:30�Τ�Τǡ����ȿ��ϡ��ʻҴֳ֤�√2���⤷����2^1/3��2^1/4���������ǹ�����Τˤ��Ƥ��ޤ���
- ����ȥ饹�Ȥ�1:1000�Ȥ����Τϡ�����ʬ�����뤵�ȹ�����ʬ�����뤵���椬�����������Ȥ������ȤǤ���
- �Ĥޤ굱���椬�����������Ȥ������ȤǤ���
- ���̤�CCD�����ϡ�8�ӥå�ǻ�٤Dz��������Ƥ���Τ�ǻ���ϰϤ�1:256�Ȥʤ�ޤ���
- ���ΰ�̣�Ǥ�1:1000�Υ��㡼�Ȥϡ�10�ӥåȡ�1,024��Ĵ�ˤ�ǻ����Ĵ����Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���
- �����������㡼�Ȥϰ����ˤ�äƺ���ޤ����������ϰ��̤�CCD�������⿼����Ĵ��������ΤǤ���
- Ʃ�᷿�Υ��㡼�ȤǤϡ����إ��饹�˥���ߤʤɤ���夹�뤳�Ȥˤ�äƤ�����������ȥ饹�Ȥ���Ĥ�Τ�����Ƥ��ޤ���
- ���Υ��㡼�Ȥ�Ȥäƥ���礭��������Ƥ���������̤����������Ƥ��ޤ�������Ǥ��뤫�ɤ�����Ĵ�٤ޤ���
- ���ϡ����ˤ�äƤϸ�������Ȥä�Ĵ�٤뤳�Ȥ⤢��ޤ���
- �����濴���ȼ������Υ쥹�ݥ�
- ��ϡ��濴���ȼ������Ǥ����������Ϥ��ۤʤ�Τǡ������Ĵ�٤뤿�����㡼�Ȥ��濴���ȼ������˲����ϥ��㡼�Ȥ����֤��ޤ���
- ���̤ˡ�����濴���ϲ����Ϥ��⤯���������˹Ԥ��ۤɲ����Ϥ�����뤿�ᡢ�濴���Υ��㡼�ȤϺ٤������������Τ�ΤϹӤ��߷פ���Τ����̤Ǥ���
- �ɼ��ʥ�Ǥϡ�����濴����100��/mm���٤β����Ϥ����ꡢ��������60��/mm���٤���ޤ���
- 4x5������ե������Ѥ�����Ƚ������Ǥϡ�������������뤬�礭���Τ��礭�����̥��ꥢ���٤Ƥˤ錄�ä��ɹ��ʲ����Ϥ����櫓�ˤϤ����ޤ���
- ¿���ξ�硢��ιʤ��ʤ�Ȥ����Τϡ��濴�����Ϥ���Ȥ��Ƽ��ռ����������������Ū�˲����Ϥ�ʿ�Ѳ����뤳�Ȥ�ͤ餤�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �������뤳�Ȥˤ�ꡢ4�������5�������101.6mm��127mm�ˤ����̥��ꥢ��50��/mm���٤β����Ϥǥ��С����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- 50��/mm�ϡ������̾��10umñ�̤��������������ǽ�ϤǤ����顢���Υ��Ȥä�CCD���λ����ǻҤǤ��ä���ȤȤ館��ˤ�5umñ�̤β��Ǥ����ɬ�פ�����ޤ������֢��ե����Υ쥹�ݥ����λ����ǻҤΥ쥹�ݥ����ȡ���
- 5umñ�̤θ��λ����ǻҤϾ������������Τ�ΤǤ������뤵��Ƥ��餺��4x5������������μ̿����Ĥ��ؤ����λ����ǻҤ�������ˤʤ��Τǡ������ǽ�ϸ��λ����ǻҤ���٤ƽ�ʬ���뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���Υ����ǽ��ʬ�˰����Ф����λ����ǻҤ�����Ȥ���С����β��ǿ��ϡ�20,000x25,400���ǤȤʤ�ޤ���
- ���ʤߤˡ�35mm�饤����������24mmx36mm�˥ե�����ѥ�ξ�硢ʿ�Ѳ����Ϥ�70��/mm�Ȥ���ȡ�6,720 x 10,080���������ˤʤ�ޤ���
- ���ߤι��ǥ��������ե����β��Ǥ���4,000x3,000���ǤˤʤäƤ���Τǡ������ǽ���鸫��Ȥ������٤β��Ǥ�ɬ�פˤ��Ƥ��Ľ�ʬ����ǽ�Ǥ���ȸ�����Ǥ��礦��
- ����ʾ�β��Ǥ�餬���Ĥȥ����ǽ�����뤿��˥����ǽ���ɤ���Τ�Ȥ���������������ȤäƵ���Ū�˲������ɬ�פ��ФƤ��ޤ���
- ����������������ȥ饸���������Υ쥹�ݥ�
- ��β����Ϥϡ��������� �αƶ��ˤ�äƲ�����Ǥ�դ��������������ʥ饸�����������������������ˤȱ������ʥ���������������ǥ����ʥ������ˤDz����Ϥ��Ѥ�äƤ��ޤ���
- ���äơ�������Ǥ�դ����������ʥ������������ȥ��ǥ����ʥ������ˤβ����٤�����ɬ�פ�����ޤ���
- �����濴���Ǥ��������� �αƶ��ϳ�̵�Ǥ����������������ˤ����ۤɸ����ˤ��αƶ�������Ƥ��ޤ���
- ������ͳ���顢���ɾ����������ϥ��㡼�ȤǤϡ����˼����褦�ˡ����;��˥ƥ��ȥ��㡼�Ȥ����֤����������������ȥ��ǥ����ʥ������Ǥβ����Ϥ�����å�����褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ���������ϥ��㡼��
- ��ǽҤ٤��褦�ˡ��������̤ˤ錄�äƲ����Ϥ�����å����뤿��ˤ��������ʥƥ��ȥ��㡼�Ȥ���ȯ����Ƥ��ޤ�����
- JIS���ʤǤ�����ǽ��������㡼�Ȥε��꤬���ꡢ���ѤΥ��㡼�Ȥ���¤���䤷�Ƥ������⤢��ޤ���
- ���㡼�Ȥϡ�����Ū�ˤ���˽Ҥ٤��ʻҾ��Τ�ΤȥɥåȾ��ʤ⤷���ϥɡ��ʥåľ��ˤΤ�Ρ�����˵Ƥβ֤Ӥ�����Τ�Τ��褯�Τ��Ƥ��ޤ���
- �����������㡼�Ȥ��礭���ΰۤʤä���Τ��¤٤ơ����������̤ˤ�äƤɤ��ޤǺƸ��Ǥ��뤫�����ޤ���
- ���������ͤϡ�¿���ϡ�lp/mm�ϡʥ饤��ڥ�/�ߥꡢ�ߥ겿�ܡˤȤ�����������ɽ�����ޤ�����
- ��



JIS�����ϥ��㡼�ȡ������Ϥκ٤�����㴳���餷��ľ�����֤�����Ρ����ͤϡ��ʻҶҥڥ��δֳ֡�3.5�ϡ�������Ф�3.5mm�δֳ֤��� JIS���ʤβ����ϥ��㡼�ȡ�2^1/3���������Ǻ���롣�������Ȳ��������Ȥ߹�碌���Ƥ��롣 �ɥåȥ��㡼�ȡ��Ķʤ��ٹ礤������å��� 

ǻ�٤ȿ����������å����륫�顼���㡼�� ��Ⱦ�߷����Υ������åȥ��㡼�ȡ���ư�ɤ��եȤǻȤ����㡼�ȡ�����Ĥߤ��¬�� 

�������������Siemens' Star�˥������åȡ����;��˳Ȥ���ƾ��Υ������åȡ������ݥ���ȤΥ����å������������Υ����å������Ѥ���롣 - ��Υ��㡼�ȤΤ����������Ϥ�����å�����ΤϺǾ��ʺ��˼�����û�����γʻ�����Ȥ��ޤ���
- �ʻ����Υԥå��ϡ��ĤȲ��β��Ȥ��ι����ǤǤ������äƤ��ޤ���
- ���Υ��㡼�Ȥ�������ФζҤ�3.5mm���Ȥ��ơ��������Ψ1/50�˽̾����ƥ����˻��Ƥ����Ȥ���ȡ����γʻҤϻ����̤ǡ�
- ��Υ��㡼�ȤΤ����������Ϥ�����å�����ΤϺǾ��ʺ��˼�����û�����γʻ�����Ȥ��ޤ���
- ��
- ������������3.5/50 = 0.07mm��14.29��/mm��
- ��
- �Ȥʤ�ޤ���
- �ɥåȾ��Υ��㡼�ȡʾ屦�ޡˤϡ�����ĤߤΥ����å��˻Ȥ��ޤ���
- ���Υ��㡼�Ȥϡ������ϤȤ������������Ĥߤ���Ĵ�٤���㡼�ȤǤ����������å��濴��������ϥ��եȥ������Ǽ�ưŪ�����ꤹ����ˤϡ����β��οޤ˼������褦�ʻ�Ⱦ�߷����Υ������åȥޡ������Ȥ��ޤ���
- ����ޤ��������ˤ�����㡼�Ȥϡ�ǻ�٤俧�뤿��Τ�ΤǤ������Υ��㡼�ȤǤϥ��졼��18�ʳ���85���3.5%�ˤ�ʬ���졢���顼�ϡ��֡��С��ġ������ޥ������������λ������ǹ�������Ƥ��ޤ���
- ���Υ��㡼�ȤǤϡ���Ȥ���������ޤ����餬������ǻ�٤俧�����Ͽ���Ƥ��뤫�Υ����å���Ԥ��ޤ���
- ��ޤβ��˼�������Τϡ�������������ȸƤФ���Τ����;��η����Ƥ��ޤ���
- ���ͷ����Υ��㡼�Ȥ��������� ������å�����Τ��Թ礬�ɤ����ɤ������˥ԥ�Ȥ��ФƤ��ʤ������Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ɥåȾ��Υ��㡼�ȡʾ屦�ޡˤϡ�����ĤߤΥ����å��˻Ȥ��ޤ���
- �������ʥ����ȥǥ������Analog vs. Digital��������2006.05.23�ɵ��ˡ�2020.01.02�ɵ���
- �������Ф����ϡ����ʥ����ξ�����ã���ǤǤ���
- ���ʥ������ǤǤ�����ɾ������ˤϡ���ǽҤ٤��褦�ʥ��㡼�Ȥ���Ū�˱����ƻȤ�ʬ����ɬ�פ�����ޤ���
- ������Ͽ����CCD��CMOS�˸��λ����ǻҤϡ�������ֲ��ǡפȤ���1ñ�̤�ʬ�����ǥ�Ȥϰۤʤꡢ�ǥ��������Ǥȸ������Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���λ����ǻҤ��Ǥ�������λ����ɤ�Ȥä��ƥ�ӥ��������ե����ϡ����ǤȤ�����ǰ���ʤ��Τǥ��ʥ������ǤǤ�����
- ���ʥ����Υ��Ȥäơ����ʥ����λ����ɥƥ�Ӥ䥢�ʥ����ζ���ե���ശ����˵�Ͽ�����Ȥ߹�碌�ϡ����ʥ��� + ���ʥ����Ȥʤ�ޤ���
- ���ߤϡ����ʥ����Υ�ȥǥ�����λ����ǻҤ��Ȥ߹�蘆�ä����ʥ��� + �ǥ����뤬��ή�ȤʤäƤ��ޤ���
- ���ʥ���+���ʥ����ε�Ͽ���饢�ʥ���+�ǥ�����ε�Ͽ���Ѥ�뤳�Ȥˤ�ꡢ��������ǽ��ɤΤ褦��ɾ���������ɤ��ΤǤ��礦����
- ��
- �����ǥ�����
- �ǥ����뿮��ɾ���ˤϥ��ʥ��������ɾ���Ȥϰ�ä�ɾ��ˡ������ޤ���
- �ǥ�����ϡ����ʥ����Ȱ�ä���ǽ�³������ΤǤ����Ĥޤ�ǥ����뵡��ˤ�������ã�ϡ��ǥ����륵��ץ���줿��ǽ�ʾ�ˤϾ������ã���뤳�ȤϤǤ��ʤ��ΤǤ���
- CCD�����ξ�硢�����β��ǰʾ�β����Ϥ������ޤ��⤦�����ܤ��������ȡ����Ǥ�Ⱦʬ���������Ϥ�����ޤ���
- ����ϡ��ƹ�βʳؼԥ���Υ�ȥʥ������������餫�ˤ������ȤǤ���
- ����������¬������������餫����狼�äƤ���Ȥ��ϡ������η���������䤷�ƥ��֥ԥ�����ޤǤν����뤳�Ȥ�����ޤ���
- ���Ȥ��С��߷����������餫����狼�äƤ���Ȥ��������濴���֤�߷���������ſ����֤�����ƥ��֥ԥ�����ޤǷ��ǵ��뤳�Ȥ�����ޤ���
- ����ϡ������λ��äƤ���ǡ������ܼ�Ū�ʤ�ΤǤϤʤ��Τǡ����ι�Ǥ������Ͼʤ��Ƥ��ޤ���
- �������ʥ���
- ���ʥ����ξ�硢�ǥ�����Ȱ�äƺ٤���������ڤ뤳�ȤϤ��ޤ���
- �٤����Ȥ����ޤǤ���ʤ�˾������ã���ޤ���
- �����䲻���ʤɤκ٤�����ʬ�ϡ��ͤθ��Ǥ�����;�����������ޤ���
- �٤����Ȥ����ޤ�;����Ĥ������ʥ�����Ͽ������ե����Ǥ��ꥪ���ǥ����Υ쥳�����פǤ���ȸ����ޤ���
- �����ǥ����Υ���פǤϡ����ߤǤ⿿���ɤ��Ѥ�����Τ�����Ƥ��ޤ���
- ���Ȭ���Ҥˤ��륪���ǥ������ƥ��ͼҤȤ��������ʲ�Ҥϡ������ɤ�Ȥä������ǥ�������פ��äƤ����ҤǤ��������Υ���פϹ⤤ɾ������ä˥����ꥢ�ǡ����Ƥ��ޤ���
- �����ɥ���פϿ�����ľ����������ǽ�Ǥ���
- �ȥ�����Ͽ����ɤ�������ǽ������ΤǤ�����NFB��Negative Feed Back = �鵢�ԡˤˤ�����������ܤȤʤäƤ��뤿������Ӱ���Ϥä���ľ���������Ǥ��ޤ���
- �ȥ��������פǤϡ�������ˤ�äƹⲻ�����㲻���˥����饤�����Ѥ���������ä��ʤ���Фʤ�ޤ���
- ���俿���ɤϥ�˥���ƥ���ͥ��Ƥ��ơ������ʲ������礭�ʲ��ޤ���ľ���������ޤ���
- ��������¤˺�������Τ˿����ɥ���פۤ�ͥ����Τ�¾�ˤʤ��ΤǤ���
- ����������ͳ��������Υ����ǥ��������Ȥ䲻�ڥۡ���Ǥϡ����ߤǤ�ʤ������ɥ���פˤ�벻�����֤����졢�����ƻȤ��Ƥ��ޤ���
- ���쥭�������Υ���פ������ɻ��ѤΤ�Τ�¿���ΤϤ�������Ǽ���Ǥ��ޤ���
- ��äȤ⡢������������֤����İ�����ڤǤ����iPod�ǽ�ʬ�Ǥ��礦�����̲ۻҤΤ褦�˲��ڤ���ĥ��ΤǤ���й���DZ��Ѥ����Ѥʿ����ɥ���פ�Ȥ�ɬ�פ������ʤ��Ǥ��礦��
- ���פ⡢�ǥ�����ʿ徽ȯ���Ҥˤ�륫����Ȳ�ϩ��¢�λ��סˤ���ή�Ǥ����桢���ʥ����ʥƥ��=����Ҥȥҥ�����ޥ���Ȥä����סˤ⤷�ä���Ⱥ��դ��Ƥ��ޤ���
- �ä˥������ι�鵡�ˤ��Τʤ���Υ��ʥ������פ��⤤�͵���Ƥ�Ǥ��ޤ���
- 30���ߡ�50���ߡ�100���ߤȤ��ä����ʥ��������פ���ʪ�Ȥ��ƹ��������ã���������㤤�㤤����ˤޤǹ����äƤ���褦�˸��������ޤ���
- 1����10�äⶸ�������פȡ�10����1�ä�������ʤ�5,000�ߤΥǥ�������סʹ�饢�ʥ������פ�100�ܤ����١ˤǡ��ɤ��������٤νФʤ�����ʻ��פ�����ΤǤ��礦��
- �Ƕ�Ǥϡ������δ֤�1�äȶ���ʤ����Ȼ��פ�2���ߤ��餤�ǹ����Ǥ��ޤ���
- �ʳ�Ū�������������ʿͤο��ˤ����٤������������ʥ������פ���᤹�������Ȼפ��ޤ���
- ���ܤ������ץ���ϡ�1970ǯ���Ⱦ���硹Ū�˥ǥ�������פ��ڤ��ؤ��Ƥ��ޤä��ΤǤ�����̤�����������ʥ������פμ��פ����뤳�Ȥȡ��������ξ����ʻ��ץ�����ι��֥��ɥ���������ߤ⺬�����͵���ؤäƤ��뤿��֥��ɥ������Ƥ��᤹��Ū����ƤӤ����������פ���Ϥ�ޤ�����
- ��¬��ʬ��鸫��Х��ʥ������פ����褹�뵡��Ϥ���ޤ���
- �ʥ⡼�����˥��ݡ��Ĥη������ƥ�ʤɤǤϡ��ۤȤ�ɤΥ������ǥǥ�������פ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �������������ԻΤϺ��Ǥ⥢�ʥ����μ괬�������סʥ������Υ��ᥬ��SpeedMaster�ϡ����ݥ��ײ�Ǻ��Ѥ��줿�������Ի��Ѥλ��סˤ�ȤäƤ��뤽���Ǥ���
- �Хåƥ��Ȥ鷺������ץ�Ǵ��Ȥ����Τ����Ѥ���Ƥ�����ͳ�������Ǥ���
- 1����10���٤�Ƥ����Τʷ��ϱ������η������ƥबô�äƤ���뤿�ᡢ����ѤȤ��ƿͤ�¦�ˤ��ƥ������Ȥ���Ȥ����ͤ��Τ褦�Ǥ���
- ������ˤ��衢�䤿���ϥ��ʥ����ȥǥ������ξ�Ԥ�������ʬ�����Ƥ���ɬ�פ�����ޤ���
- �ʲ�����꤯�ɤ����⤷��ޤ������ʥ�����Ͽ�ȥǥ����뵭Ͽ�ΰ㤤�ˤĤ��ƿ���Ƥ������Ȥˤ��ޤ���
- ��
 �����ǥ�����Ȥ���2006.05.28�ɵ���
�����ǥ�����Ȥ���2006.05.28�ɵ���
- �ǥ�����Ȥ�����ǰ���������Ƥ����ޤ��礦��
- �ǥ�����Ȥϲ��Ǥ��礦����
- �ǥ�����ȸ������դ��ФƤ����طʤˤϡ��ǥ�����Ǥʤ���������ǥ�����������ˤʤä����Ȥ����ռ���̿��¥����̣�礤��������Ƥ��ޤ�����
- �ǥ�������и줬���ʥ����Ǥ���
- �ǥ���������Ǹ����ȡֿ��Ͳ��פǤ���
- ��ä��ͤ��ͤ�Ƥ����ȡ�0�פȡ�1�פ�����ष���ʤ�����ɽ���������Ȥ������Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ʸ��¤�����Ǥϡ���0�פȡ�1�פ���Ĥ����ο���ɽ���ǤϤȤƤ�����Ǥ��ʤ��Τǡ�����ˡ�ο���ɽ�����ƥǥ�����ȸ��äƤ��ޤ�����
- ���Ρ�0�פȡ�1�פο���ɽ������ؤǤ����ˡ�ȸ��äƤ��ޤ���
- ���Ͳ��������Ǥϡ��������ˡ�����������ʴ������Ƥο�����������ۤ��Ƥ��ޤ����ʤ��ʤ饳��ԥ塼���˻Ȥ��Ƥ��뻻�Ѽ�ˡ�����ˡ�Ǥ��ꡢ����ԥ塼�������ǹԤ��Ƥ������ �����Ƥ���2��ˡ�Ǥ��뤫��Ǥ���
- ���äơ��ǥ�����������ȤɤäƤ��������ˡ�ο��͵��ҤȤʤ�ޤ���
- ��0�פȡ�1�פ�����������������⤤�����������������ۤ���褦�ˤʤä��Τ϶�̣����Ȥ����Ǥ���
- �ѥ�����ʤ��䡢������̣��IC���Ѥ�Ȥä��ǥ�����ץ����å����ˤΤ������ǡ��ǥ�������������ߤ�ߤ빭���äƹԤ��ޤ�����
- ��
- �������ˡ��Binary Notation��
- ���ˡ�ˤĤ��Ƥ����餤�ޤ���
- ���ˡ�Ȥ����Τ���Ĥο��������ο�Ūɽ���������Ǥ���
- 2�Ĥο�����������ʤ��ΤǤ���
- ����ˡ��10�Ĥο������äƤ��ơ�9�Ȥ����ͤ˰���ͤ��ä��ȷ夬�夬�ä�10�Ȥʤꡢ0��9�ζ��̤�ε���ǿ���ɽ���Ʋø������ԤäƤ��ޤ���
- ���ع��ǽ������Ѥ�������10��ˡ�ˤ��ø������¾�ʤ�ޤ���
- �����������ˡ�ϡ���0�פȡ�1�פ���Ĥο������ʤ�����ˡ���1�פˤ⤦��IJä��Ƥ��2�פȤ�������Ǥ������夬����夬�äơ�10�פȤʤ�ޤ���
- ���ˡ�Ǥϴ�ñ�˷夬�夬�äƤ����ޤ���
- ���ͤ�2�̤ꤷ�����ʤ��Τ������ȸ����������Ǥ���
- ���äơ���1001�פȤ���4������ˡ�ο���ɽ���ϡ�����ˡ��ľ���Ȱ��Ρ�9�פȤʤ�ޤ���
- ��1111�פ�15���������ޤ���
- ���ˡ�Ǥϡ����줾��η�Ǥ�ɽ������1�פȡ�0�פ����ʤ��Τǡ�����ԥ塼���Υ����å��Ǥϡ����줾��η����ή��ή����ή���ʤ����Ṳ̋���äƤ��롢���äƤ��ʤ��Ȥ��������å��Ρ�ON�ס���OFF�פ����������ƾ������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ѥ�����ε�Ͽ���ΤǤ���CD�ʥ���ѥ��ȥǥ������ˤǤϡ��ǥ������ε�Ͽ�̡ʥԥå�pit = ����ξ�������ˤ˥졼���������Ƥơ��ԥå��̤Ǥθ���ȿ�ͤ�̵ͭ�ǡ�0�פȡ�1�פ�ɽ�����Ƥ��ޤ���
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡ʼ�����Ͽ���ΡˤǤϡ���Ͽ�̤μ����Τξ��֡���N�פȡ�S�פζ����ˤ�äƥǡ�����Ͽ���Ƥ��ޤ���
- ���Τ褦�ˡ����ˡ�ϡ֤���פȡ֤ʤ��פ���Ĥ�ɽ����ˡ�Ǥ���ȸ��äƤ�褤�Ȼפ��ޤ���
- �֤���פȡ֤ʤ��פΤ狼����ɤ���ñ�ʻ��Ѥ�������ԥ塼����ȯã����������ۤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Τ褦�˥���ԥ塼���ϡ��ŵ������å��ʡ�ON�פȡ�OFF�סˤΤ����ޤ�ǤǤ��Ƥ���Ȥ��äƤ����ǤϤʤ����ŵ����̤�����ߤ�ꡢ���뤤�Ϥ�����ݻ����Ʊ黻��¹Ԥ������η�̤ο��ͤ�2��ˡ�Ȥ��Ƶ���������ɽ�����˲Ƥ��ޤ���
- ����ԥ塼���Ǥ����ˡ�Ǿ���ʿ��͡ˤ����Ϥ��뤳�Ȥ�ӥåȡ�bit�ˤ�Ω�Ƥ�ȸ��äƤ��ޤ���
- ���Ȥ��С���1001�פȤ������ͤ�4�Ĥη�ΥӥåȤ�Ω�ƤƤ���櫓�Ǥ��ꡢ�������֥����ߥʥ����å��ˤ��̤�4��ΥӥåȤȤδ֤Dzø������ԤäƤ��ޤ���
- ����4��ΥӥåȤǤα黻������4�ӥåȽ����ȸ��äƤ��ޤ����ʾ���ȡ���
- 4�ӥåȡ�24 = 16�ˤǤϡ�16�̤�ο���ɽ�����Ǥ���Τǡ�����ˡ��10�̤�ο��ͤ�4�ӥåȤ����Ƥ����ˡ�ˤ��������ʤ���Ƥ��ޤ�����
- 3�ӥåȤ���8�̤�ˤ����ʤ�ʤ��Τǡ�����ˡ�ο��ͤ������Ƥ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ʹ֤����䤹��10�ʿ��Ȥζ��֤ˤ��äơ�2��ˡ��4�ӥåȤ��Ĥ�ñ�̤Ȥ��ư�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���θ塢����ե��٥åȤ�ʸ���䵭���+ - & %�ˤʤɤ����ƤϤ��ɬ�פ��Ǥ����Τǡ�4�ӥåȤ��ܤ�8�ӥåȡ�256�̤�ˤ����Ϥδ��ܷ���Ȥʤꡢ1�Х��ȡ�byte�ˤȸƤФ��褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ˡ�������������������ƤϤ��ɬ�פ���2�Х��ȡ� = 16�ӥåȡ�65,000�̤�˽�������ή�ˤʤäƤ����ޤ�����
- ��
������10��ˡɽ���ʾ��ʡˤ�2��ˡɽ���ʲ��ʡ�
- 2��ˡ�������֤Ǥ���ǽ�Υޥ�����ϡ�4�ӥåȤ���Ϥޤ�ޤ�����
- 1970ǯ���Ⱦ�Υޥ����åȤǤϡ�8�ӥå�CPU����ȯ���졢NEC9801�������ͭ̾�ˤʤä��ѥ�����Ǥ�16�ӥå��б��ˤʤꡢ���ߤ�32�ӥåȤ���64�ӥåȤη������Ĥ˻�äƤ��ޤ���
- 64�ӥåȤϽ��ʿ���ľ����200����2,000,000����19��ˤο������������ޤ���
- ��������ʿ�����1�ĤΥ����ߥ����å��DZ黻�����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �Τϡ����٤ˤ��Τ褦�ʷ�Ǥη����Ǥ��ʤ��ä��Τǡ����٤��ᤵ�����Ǥϡ����ʬ���ƽ������Ƥ��ޤ�����
- �ӥåȤξ��ʤ��ѥ�����ǤϽ����˻��֤�������櫓�Ǥ���
- 64�ӥåȤα黻���̾��CPU�Υ����å��Ǥ���500MHz�ǹԤ��Ȥ���ȡ�����ˡ��19��ñ�̤η���1�ô֤�5�����֤��ƹԤ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����ο��ͤϡ��桹����������ˤϵڤӤ⤷�ʤ����������Ǥ���
- �������ʤ��顢�ǥ���������������ä��ꤹ����ˤϤ������٤α黻��ɬ�פˤʤäƤ��ޤ���
- ��
- �䤿����2��ˡ��ʪ����ͤ��뤳�Ȥ����ǡ��դ˥���ԥ塼����10��ˡ�Ƿ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���äơ��ͤ��ƥ���Ȥä�10��ˡ�˽��ä����ͤ����Ϥ���ȡ��������ޤ����2��ˡ���Ѵ����ƥ���ԥ塼�������ν����˲ޤ���
- ����ԥ塼�������ǽ������줿��̤�ͤ�Ƚ�Ǥ���ݤˤϡ�2��ˡ�ǽ������줿�ǡ��������10��ˡ��ľ���ƥ�˥��ʤɤ�ɽ�����Ƥ��ޤ���
- �Ƕ�Ǥϡ����ͤ�����ɽ�������Ť餤�Τǡ�ɽ�䥰��դ�ľ����ɽ�����Ƥ��ޤ���
- ���ʥ���ɽ���ˤ��Ƥ���櫓�Ǥ���
- ��
- ���������ǥ�����γ�̿�ϡ��ȥ������ȯ����ȯŸ��ȴ���ˤ��Ƹ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ȥ������ȯ���ˤ�äơ���®�黻��������ǽ�ʥǥ������ϩ��ȯŸ���ޤ�����
- �ʥȥ���������ˤϿ����ɤǥǥ������ϩ�����졢�ŵ��ˤ��������Ǥ������ˤϡ������ꥹ�ο��ؼԥ��㡼�륺���Х٥å���Charles Babbage��1729-1871�ˤ����֤ˤ�������ȯ�Ƥ��Ƥ��ޤ�����
- �ȥ������ȯŸ�ˤĤ���褦�ˤ��ƥǥ����뵡�郎���⤷���ΤǤ���
- �ȥ������ȯŸ�ϡ����Ѳ�ϩ���ѡ���äȸ����ȡ����ꥳ��ȾƳ�Ρʥȥ��������ϥ���ޥ˥���ȾƳ�Τ���ή�ˤ�Ȥä����ѵ��Ѥ����ä����餳���ʤ����ޤ�����
- ����ȯŸ�ε�ˤ�CPU�ι⽸�Ѳ���IC����ι⽸�Ѳ��Ǥ���
- ����ޥ˥����Ȥä�ȾƳ�ΤǤϡ����Τ褦�ʽ��Ѳ�ϩ��ȯŸ���Բ�ǽ�Ǥ�����
- ���ꥳ����������ѡ������ƥ��ꥳ��λ�����ˤ��ץ졼�ʡ����Ѥ��ʤ���к��ν��Ѳ�ϩ�����ޤ�Ƥ��ޤ���Ǥ�����
- �ȥ�����ν��Ѳ��ȤȤ��IC��Integrated Circuit�ˤ�1960ǯ��ȯ�����졢�ǥ������ǻҡ�IC�ǻҡ�TTL�ǥ������ϩ�ˤ��ƹ�ƥ��������ĥ���ļҤ���ȯ�䤵��ޤ�����
- TTL�ǥ�����IC�ե��ߥ�ǻҤ�ȯ���ˤ��ǥ������ϩ���礤����ڤ��ޤ���
- ���ʤߤ�IC�ȥ������Ȥä�����ԥ塼���ϡ�1964ǯ�˳�ȯ���줿�ƹ�IBM�Ҥˤ��IBM/360���ǽ�Ǥ���
- �ǥ��������֤Τ�äȤ�ȶ�ʤ�Τϡ��ǥ�������פǤ���
- ����ϥޥ�����θ��ĤǤ���
- �ѥ�����ϥǥ����뤽�Τ�ΤǤ���
- ���ߤϡ�CD ��DVD�������ǥ����������ޤǥǥ�����λ���ˤʤ�ޤ�����
- �ƥ��������ǥ����벽���ʤ�Ǥ��ޤ���
- 1990ǯ��Ⱦ�ޤǤϥƥ�Ӳ�������������Τϥ��ʥ����Ǥ�����
- �����ϤȤƤ⤿������ξ����ꡢ�����ǥ��������������Τϵ���Ū��̵�����ä��ΤǤ���
- NHK����ȯ�����ϥ��ӥ����ϡ���ȯ�������ʥ�������������Ƥ��ޤ�����
- ����Ǥ������Ӱ褬��ʤ��Τ�MUSE�ȸƤФ�륢�ʥ������̤ˤ����������äƤ��ޤ�����
- ������ˡ�Ǥϥ��ݡ��Ĥʤɤ�ư����®�������Ͻ������ɤ��Ĥ��������β����������ۤ���ƥ��֤ä������ˤʤ�ޤ�����
- ���ߤǤϥϥ��ӥ�����ǥ�����ˤʤ�����Υ��֤��ʤ��ʤäƤ��ޤ���
- �ǥ���������ζä��٤�ȯŸ�Ȥ����ۤ��ʤ��Ǥ��礦��
- ���ߤΤ���Ӥ䤫�ʥǥ�����������ϡ������äƤ����ȡ�0�פȡ�1�פ��ŵ�����˹Ԥ��夭�ޤ���
- ����ɸ�ܲ��ʥǥ��������ˤδ�������
- �ǥ����벽��Ԥ���������ˤʤ�Τ������Υǡ����̤�ɤΤ��餤�٤������ڤ�ˤ��ơ���0�פȡ�1�פξ�����Ѵ����뤫�Ȥ������ȤǤ���
- ���Ȥ��С���������ʥ����ǥ����ˤξ�硢1�ô֤ˤɤ�����٤�������ɸ�ܲ�����и�������¤ʥǥ����벻�ˤʤ뤫�Ȥ������꤬����ޤ���
- �����ǥ���CD�Ǥ�1�ô֤�44,100����ץ��44.1KHz�ˤ�ɸ�ܲ���ԤäƤ��ޤ���
- ���äơ����Υ���ץ��ɸ�ܲ��ˤǤϤ���ʾ�μ��ȿ��ʹⲻ���ˤϴޤޤ�Ƥ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- �ͤμ���20kHz��ʹ�����ʤ��Ȥ��������Ω�ä����ʤǤ���
- �ޤ���CD�Ǥϡ����ο�����16�ӥåȤȵ��ꤷ�Ƥ��ޤ���
- CD�˵�Ͽ���줿�ߥ塼���å��β��ζ�����1:65,000�Υ����ʥߥå������Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���
- ����ʾ�β����˴ؤ��Ƥϸ�§�Ȥ��ƺ����Ǥ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- �ǥ��٥�Ǥ����Ȥ���16�ӥåȤβ�����96dB�����������ʹ֤β�İ����120dB�˾�����ʤ���Ȥʤ�ޤ���
- ���������ȥ�ϡ�120dB���٤ޤDz����Ф뤽���Ǥ��Τǡ��Ť��ʲ�������粻�ޤǤ�Ʊ�����Ǽ�Ͽ����CD��Ǽ��뤳�Ȥ�̵���Ȥʤ�ޤ���
- ��
- �ǥ���������Ǥϡ�������ɸ�ܲ�����Τ˲��ǡ�pixel = �ԥ�����ˤȤ����ͤ�����Ƴ�����ޤ�����
- CCD �����ι�¤�ϡ�������ǥ�����ˤ����dzʹ����ǻҤǤ��������֡�T�ˤȶ��֡�X��Y��D�ˤ��Ф���ɸ�ܲ����ǥ�����δ��ܳ�ǰ�Ǥ���
- �����������̡ʥ��ʥ����̡�→����ԥ塼�������ʥǥ������̡�→�ʹ֤�ǧ���ʥ��ʥ����̡�
- ��
- �����������ϡ����ˤ��Ƥ����̤��������ˤ��Ƥ⡢��0�פȡ�1�פξ���ǤǤ��Ƥ���櫓�ǤϤ���ޤ���
- �̤�̵����ˤ��ꡢ�̤��Ѳ��ϳ�餫�Ǥ���
- ���������������ˤ����̤ʥ����̤ȸ����ޤ����������̤��Ѳ���ԥ塼����������Ȥ�����ȤΥ��ʥ����̤�ǥ������̤��Ѵ����ƽ�����Ԥ������η�̤���Ϥ���ݤ˺Ƥӥ��ʥ����̤��᤹�Ȥ���������Фޤ���
- �����Ѵ���AD�Ѵ���Analog to Digital Transfer�ˡ�DA�Ѵ���Digital to Analog Transfer�ˤȸ��äƤ��ޤ���
- ���������ò�����ƥ�������⥳��ԥ塼���ι���ǽ���Ⱦ������ˤ�äƤɤ�ɤ�ǥ����벽����Ƥ��ޤ���
- �ͤ�ǧ�������ʥ����ߡ��������ˤ����Τ����٤ƥ��ʥ����ʤ��������̻��ϳؤǤ��������Ӥ��ͤ���ˤǤ���Τˤʤ����ǥ������Ѵ��ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǤ��礦��
- ����ϡ��ǥ����벽������������������Ǥ���
- �ʤ������ʤΤ��������Τ��ȤˤĤ��ƽҤ٤뤳�Ȥˤ��ޤ���
- ����

- ��
- �����ʤ���0�פȡ�1�פε�Ͽ�����ꤷ�Ƥ���Τ�����-���ǥ����뵭Ͽ�ȥ��ʥ�����Ͽ
- ���ʥ��������̤ȥǥ���������̤ˤĤ��ƽҤ٤ޤ���
- ���ʥ����̤Ȥ����Τϥǥ������̤��и�Ȥ��ƤǤ������դǤ���
- ���äơ�����ԥ塼��������̤�ǥ������̤ȸ�������������̡ʼ������ˤ���Ϣ�ʤ�³���������ʤ��̡ˤʥ����̤ȸ����ޤ���
- ���������ˤĤ��Ƹ����ȡ��ͤˤ�륹���å��䳨�衢�ե�����Ȥä����������� VHS�ơ��פˤ��ӥǥ������ʤɤϥ��ʥ��������ȸ��äƺ����٤��ʤ��Ǥ��礦��
- ���ʥ����̤���ħ�ϡ�������ǻø��Ϣ³Ū���Ѳ��̤Ȥ��Ƶ�Ͽ���Ƥ��뤳�ȤǤ���
- �����ԡ������硢�������ȴ���Ʊ��ʤ�Τ����뤳�Ȥ������ݴɤ���֤ˤ�����ʼ�����ǯ�Ѳ����Ƥ��ޤ��ޤ���
- �����å��ϡ�ɮ�����ɮ����ǻø�����ʤɤˤ�äƵ�Ͽ�����Τǡ��ͤ������¤��ĤȤ���Ʊ����ΤϤǤ��ޤ���
- �ե��������ϡ����γ�Ҥ����ζ�����ȿ�����ƹ�����Ȥ��Ƹ����������夵����ΤǤ��ꡢ���ʥ�����Ͽ�θ����ʤ�ΤǤ���
- ���Υե�������ⴰ����Ʊ��������Τ��������Ѥ���ե�������¤���ݴɡ��������θ����������ʤ�����ɼ���ʣ�����������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- VHS�ơ��פˤ�������Ͽ�⡢�ơ����̤˵�Ͽ���줿�����̤��إåɤˤ�äƽ����夲���ŵ�������Ѵ����Ƥ��ޤ���
- �ơ��פ������������ơ��פμ�������¸ǽ�ϡ������إåɤ���ǽ�ˤ�äƺ����������ʼ����礭���Ѥ�äƤ��ޤ���
- �ǥ���������ϡ������������ʥ��������ʱ�˸��ꤷ�Ƥ��ޤ������٥��ԡ����Ƥ⸵�ξ����»�ʤ����Ȥ��ʤ��ȸ�����ˡ�Τ褦��ǽ�Ϥ��äƤ��ޤ���
- ��
- �ǥ������������ɽŪ�ʤ�Τϡ��ǥ����륹����ʡ��Ǽ�����������ǡ��������ꡢ����˥ǥ����륫���β����ǡ������ӥǥ�����餫��α���������ܡ��ɤ�𤷤ƥ���ԥ塼������³���Ƽ���������ʤɤ�����ޤ���
- üŪ�˸����С�����ԥ塼������¸���줿�ǡ�����ʸ���ڡ������ˤϤ��٤ƥǥ�����ǡ����Ǥ���
- �ʤ��ʤ�С�����ԥ塼���ϡ���0�פȡ�1�פ�������ʤ��ʰ����ʤ�������������Ǥ���
- ��
- �ϥꥦ�åɤǺ����Dz�ϡ�����Ū�ˤ�35mm�ʤ⤷����70mm�ҤΡ˱Dz�ե����ʥ��ʥ����ˤǻ��Ƥ��Ԥ��ޤ���������������β������������̽����ʤɤϤ��٤ƥǥ�����������ʤ���Ƥ��ޤ���
- �������ƤǤ������ä����ʤ����ԥǥ��������¸�����A/D�Ѵ��ˡ��۵���˥졼���ץ�ǺƤӥե����˾Ƥ��դ����ԡ�����ơ�D/A�Ѵ��ˡ��Ǽ̵��Ǿ�Ǥ���Ƥ��ޤ���
- SFX�ȸƤФ�른����αDz�ʥ����ɡ����֡�����������������������������ߥ͡���������饷�å��ѡ����������ˤʤɤϸ����˵ڤФ����ƹ�ԥ������Ҥ��꤬���륢�˥�ʥե�����ǥ����˥⡢Mr.����ǥ��֥롢�������ˤʤɤϥǥ�����Dz��ŵ���Ǥ���
- ��������1994ǯ�ˤ˺��줿�Dz�֥ե��쥹�ȡ�����ססʥȥࡦ�ϥ���顢���С��ȡ����ᥭ�����ġ������ǥߡ���6������ޡˤϡ������ʥɥ�ޤ�ή�����ˡ�����á��Ȼפ�����������¿�����������ޤ����ʥ˥����������Τ˲����ԥ�ݥ�Υ�����ξ�����Ǥ��줿����Υ�����ʤɡˡ�
- �����Ϥ��٤ƥǥ�����Ǻ��줿��ΤǤ���
- �֥��ݥ�13�פȤ����Dz�ˤ����������ȻפäƤ��ޤ��褦�ʥǥ���������Ǻ��줿�����åȤ��Ǥ��夲������䱧���ư�Υ�����¿������Ф���Ƥ��ޤ�����
- ���Τ褦�ˡ��ǥ�����Dz�ϤĤ��Ĥ��ȿ������������ڤ곫���ƹԤ��ޤ�����
- ��
- �ǥ���������ϡ����ԡ����Ƥ�ʤ�������Ѳ����ʤ����������ʤ��ˤΤ��Ȥ����ȡ��ǥ���������ξ���0�פȡ�1�פ���Ĥ���������ʤ�����Ǥ���
- ����ˡ����Ρ�0�פȡ�1�פξ�����ŵ�Ū�˵�Ͽ�����硢��0�פξ���0V��0.8V�ޤǤ��Ű�����1�פξ���2.7V��5V�Ȥ������ˤʤäƤ��ơ������Ͽ����ݤ˾����Ű�����ư�����äƤ⤷�ä���ȡ�0�פȡ�1�פξ���������뤳�Ȥ��Ǥ��뤿��Ǥ������ʥ�������ξ�硢�㤨�Хӥǥ�����ϡ� 0.3V��1.0V�֤��Ű������뤵����ȤʤäƤ��ơ�0.7V�δ֤˹�������ޤǤξ��������ʤ���Фʤ�ޤ���
- 0.1V���ŵ�Ū�ʥΥ��������äƤ�������������Ѥ�äƤ��ޤ��ޤ���
- ����ǥ����뵭Ͽ�Ǥϡ�0.1V���٤���ư�Ǥ����˱ƶ���Ϳ���뤳�Ȥ������ʤ��ΤǤ���
- �ǥ�������¸�ο���ĺ�������ˤ���ޤ���
- �����ʤ��ǥ�����ʤΤ���
- �ǥ����������ȯã������ͳ�ΰ����礭�ʤ�Τϡ����٤�����ޤ�������ԥ塼����ȯã�Ǥ���
- ��äȹ��������ȥǥ������ŻҲ�ϩ��ȯã�Ǥ���
- �դ˸����С�����ԥ塼����ȯã̵���ˤϥǥ����������ȯŸ�Ϥ������ޤ���Ǥ�����
- �������Υ���ԥ塼���ϡ�������٤Ƴ��ʤ�ǽ�Ϥ����ꡢ������Ͽ����ˤ��������ˤ����Ѥʻ��֤������äƤ��ޤ�����
- �������äơ��ƹ��NASA�ʹҶ�����ɡˤȤ����ܤ��礭�ʸ����Τ褦�ʹ���ǽ�Υ���ԥ塼�����ͭ���뵡�ذʳ��Ǥϥǥ�������������Ȥϻ��¾��Բ�ǽ�Ǥ�����
- 12ǯ����1994ǯ�����ˤΥѥ������ͤ��Ƹ��ޤ��礦��
- �����ϡ������ͥåȤ�������夲�������ǡ��������ۿ��Ǥ���WWW�ͥåȥ�����ե� = Netscape Navigator�����ȤǤ���⥶���������ߥ�˥�����������Ρ֥⥸�顦�С������0.9�פ�ȯ�䤵�줿�����Ǥ���
- HTML�����HyperText Marking up Language�ˤ�WWW��World Wide Web�ˤ�1989ǯ�˥ƥ��ࡦ�С��ʡ�������ˤ�äƳ�ȯ���졢���θ���ǵ��Ҥ��줿ʸ�ϤϤɤ�ʥѥ�����Ǥ�������̤������������š����������ĤǤ�¨�¤��ɤ߽Ф���Ȥ�����ΤǤ�����
- �������̿����ʤϡ����Ѥβ����Τ�����ߤ��̤Ȥ��ơ����ò����ˤ��RS232C��ž��®�٤�9600bbs��9,600�ӥå�/�áˤ���ή�Ǥ�����
- �ѥ�����ˤϸ���ή�ˤʤäƤ���USB2.0��Universal Serial Bus�ˤ⡢IEEE1394��The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. = �ƹ��ŵ����Ż�ɸ�ಽ���Τ����Ѥ���1394���ܤε��ʡˤ⡢�ޤ��ƥ������ͥåȤʤɤȤ�����®�̿������ե������ʤɤ�Ĥ��Ƥ��ޤ���
- Com�ݡ��ȡ�RS232C�ˤȥץ�ݡ��ȡʥ���ȥ��˥����ˡ��⤷����SCSI�ʥ��������ˤȸƤФ�륤���ե���������ή���ä��ΤǤ���
- ������ǡ�Ĺ��Υž�����Ǥ���Τϥ��ꥢ��ž���Ǥ���RS232C�Ǥ�����
- �����̿����ʤϡ��ƹ��Żҹ��Ȳ��EIA = Electronic Industries Association��1997ǯ���Electronic Industries Alliance�ˤ�1969ǯ�˷���Τǡ��ƥ쥿���פ˻Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ���ε��ʤϥ���ץ�ʵ��ʤǡ����ò�����Ȥä����������̿��Ǥ����Τǰ����Ӹ�����Ӥޤ�����
- CPU��1993ǯ�˳�ȯ���줿Pentium��66MHz�ˤ��Ȥ��Ƥ��ơ�DRAM16MB��HDD400MB����������Ū�Ǥ�����
- �����Υѥ�����β��̤ϡ�640x480���ǡ�RGB��8�ӥåȤβ���ɽ������ή�ȤʤäƤ��ޤ�����
- ���ȤʤäƤϤӤä��ꤹ�뤳�Ȥˡ�����ɽ���ϡ�����ɽ���Ȥ������ʸ��ɽ���Ǥ�����
- ������ʸ��ɽ����ʸ���Υ����ɡ�2�Х��ȡˤ����ɽ�������ͥ졼�������äơ������ͥ졼������ʸ����ȯ��������1ʸ��24�ӥå�x24�ӥåȤDz��̤�ɽ�������Ƥ��ޤ�����
- ���ä��礭������ꤵ��Ƥ����Τǡ�ʸ�����礭����Ⱦ�ѡ��ܳѡ�4�ܳ����٤������ݡ��ȤǤ��Ƥ��ޤ���Ǥ�����
- VGA��˥��ǥ�ݡ��Ȥ�Ȥ���ʸ����20ʸ��x26ʸ���ȸ��ꤵ��Ƥ����Τ�400���ͤḶ���ѻ����٤Ǥ�����
- ��������餫��ʸ���Ȳ�����դ����˻Ȥä�ɽ���Ǥ����ѡ����ʥ륳��ԥ塼���ϡ��ޥå���ȥå����Macintosh�����åץ�ҡˤ�������ޤ���Ǥ�����
- ��餫��ʸ����ͳ���礭�����������Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤä��Τϡ�Windows98����Ǥ���
- ����Ǥ��餫��ʸ���ʥݥ��ȥ�����ץȡˤ�ɽ������ˤϤ��ʤ����ǽ�Υѥ�����ɬ�פǤ�����
- ���λ��¤���狼��褦�ˡ�10ǯ�ۤ�����1990ǯ�ˤΥѥ������640x480���ǤΥǥ����������1�ô֤�60�����٥�ե�å��夷�����褹�뤳�Ȥϲ���ɽ���ܡ��ɤ���ǽ��CPU����ǽ�������ƥ������̤�������ⶲ����������Ǥ��ä��ΤǤ���
- ������ɽ���Ϥ����ƥΥ��ޤǤ�����
- �Ǥ����顢�����Υѥ�����Ϸ���줿���ǿ��ˤ��ɥå�ʸ���ˤ���̿����濴�ǡ������ܤˤ��ä������ݥ��ȥ�����ץ��б���ʸ�������ɽ���ˤ��ۡ���ڡ����Ϻ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- �ݥ��ȥ�����ץȤȤ����Τϡ��ƹ�Adobe�Ҥ�Ĺǯ��ȯ���Ƥ�������ɽ���θ���ǡ�ʸ���������ɽ�����դǤ�����
- �ӥåȤǤϤʤ������Ǥ���ʸ���������������Ƥ����ΤǤɤ���礭��ʸ���Ǥ⥹�������¿������г�餫��ɽ���뤳�Ȥ���ǽ���ä��ΤǤ���
- ��������1990ǯ�����Υѥ�����Ǥϥݥ��ȥ�����ץȤ��������ǽ�Ϥ��ϼ��1���̤���夲��Τ˶����������֤�ɬ�פ��ä��ΤǤ���
- ������RS232C�ˤ��ǡ���ž���Ǥ�1�ô֤˺���9600�ӥåȤΥǡ����������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- �̾�ǡ�����������ˤϥ��顼�����ʤɤ����äơ��߷�®�٤��Τޤޤǥǡ�����ž���Ǥ��뤳�ȤϤۤȤ�ɤ���ޤ���
- �������ͥå��̿��ˤ��Ƥ��®�٤�1/10��1/20���٤����������Ǥ���
- �������Ƥߤ�ȡ�RS232C�̿��Ǥ�1�ô֤ˤ�������960�ӥåȡ�120�Х��ȡˤξ�������ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- VGA�⡼�ɤβ���ɽ������̤٤ƥӥåȥޥåפǽ������褦�Ȥ���ȡ�640����x480����x3��x8�ӥå� = 7,372,800�ӥåȤȤʤꡢRS232C���̿������Ǥ��β���������Ȥʤ��2�������٤����äƤ��ޤ��ޤ���
- �����̤��������ˡ�ϡ�1984ǯ�˥���ԥ奵���֡�CompuServe�˼Ҥ�GIF�Ȥ��������ե�����������Ƥ��ơ�������ɤ�������褦��JPEG�ե����뤬�Ǥ�������ޤ�
- 1994ǯ�����ϡ�JPEG������ѥ������ǻȤ���褦�ˤʤäƤ��ޤ������ʲ����ΰ��̤ϡ�FAX��������Ū�dz�ȯ���줿�褦�Ǥ�����
- ����JPEG�������äƤ��Ƥ�1��Υǥ����륫�顼����������Τ�10ʬ���٤����äƤ��ޤ��ޤ���
- ����ƥ�ӡʥ��ʥ��������ˤǤϡ�Ʊ���β�����1�ô֤�30������륷���ƥ��Ȥä����Τ˴��������Ƥ��ޤ�����
- �������ʥ��������ϥǥ������������٤�2��20���ܤ��®�����뤳�Ȥ��Ǥ����ΤǤ���
- �º����ꡢ2000ǯ�ޤǤϥӥǥ�����ˤ�������Ͽ������������®���������Ǥ��ä��Τǡ�CCD�����ǻ��Ƥ��������VHS�ơ��פ�8mm�ӥǥ��ơ��פ�Ȥäƥ��ʥ�����Ͽ��ԤäƤ��ޤ�����
- VHS�ơ��פ����ष�����ä�DVD��HDD�ˤ�������̥ǥ����뵭Ͽ����ڤ��Ƥ����Τϡ���Ͽ���Τ��¤��ʤꡢMPEG���̵��Ѥ��ʤߡ�CPU����ǽ�����夷��2004ǯ�����꤫��Ǥ���
- ���δ֡������ͥåȤι�®����ޤ�졢�ǥ����벽�����̲����ˤޤǵڤӤޤ�����
- �������ƥǡ���ž�������꤬��褵���褦�ˤʤ�ȡ������ǥ����������ͥ�����������������åפ���뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ǥ���������β��äϰʲ��ǽҤ٤ޤ���
- �������դ��ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥϡ��ǥ�����Ϥ��٤Ƥˤ�������ǽ�ǤϤʤ����ȤǤ���
- �ǥ����벽�κǤ�����ʤ��Ȥϥ��ʥ����ǡ�����ɬ�פˤ��ƽ�ʬ�ʥǥ�����ǡ����˿��Ͳ����뤳�ȤǤ���
- �Ƥ�����ץ�ǥǥ����벽���줿�ǡ����ϻ��Ȥ����������Ω���ʤ����Ȥ�����ޤ���
- ���ǥ����뵭Ͽ - �����δ���Ū�ʹͤ���
- ��������¸�ߤ��륢�ʥ����̤�ǥ����벽����ͤ�����Ҥ٤ޤ���
- �ǥ����벽�ΰ��֤κ��ܤϡ��̻Ҳ��Ǥ���
- ����ϡ����ʥ����̤�ɤ������ʬ�����ơ�0�פȡ�1�פ�ʬ���뤫�Ȥ����ͤ����Ǥ���
- �̻Ҳ��ϥ���ץ��ɸ�ܲ��ˤȤ�����Ƥ��ޤ���
- ������ɸ�ܲ��ˤϰʲ��Υѥ���������ޤ���
- ��
- ������1.�����֤��̻Ҳ������ٹ礤��-�����ǡ�512x512���ǡ�720x480���ǡ�1280x1024���ǡ��ʤɡˤ�ʬ���롣
- ������2.��ǻ�٤��̻Ҳ������ٹ礤��-��8�ӥåȡ�256��Ĵ�ˡ�10�ӥåȡ�1024��Ĵ�ˡ�16�ӥåȡ�65,000��Ĵ��ǻ�٤ʤɤ�ʬ�̤��롣
- ������3.�����֤��̻Ҳ������ٹ礤��-������ץ���ȿ��ʻ���®�١����ޡ��áˤ�Ȥäƻ��֤���ڤ�ˤ��롣
- ������4.�������¿�Ų������ٹ礤��-��ʣ���ǡ���������������롣
- ����Ϣ³�̤��ʬ�������Ͳ�����
- Ϣ³�̤��ʬ�������ˡ�ϡ����ؤ���ʬ����ʬ�ιͤ�����������Ƥ��ޤ���
- ������������줿�Τ���ʬ����ʬ��ˡ�ΰ�������μ�ˡ�Ǥ����ʬ����ˡ�Ǥ�����
- ��ʬ����ˡ����ǡ��ä�ͭ�¤��̻Ҳ���ˡ����Ѥ��ơ�Ϣ³�̤���ڤ�ˤ��ƥ⥶��������ˤ��ޤ�����
- ̵�¿������Ƥ�����Ƥ��줤��Ϣ³�ؿ��Ȥ����ο��ؤǽ�����ʬˡ�ޤǤ�ԥ塼���˵��ޤ���Ǥ�����
- ���ĥ��Ĥ����̻Ҳ��Ǥ���ɤ��פȸ��ڤ������ˤ����ߤ�����ޤ���
- �Ĥޤꡢ���Τ��Ȥϥǥ���������Ͽ��Ť˥���ץ�ʤ���С�ɬ�פˤ��Ƴ�Ľ�ʬ�ʾ���������ΤˤϤʤ�ʤ����Ȥ����Ƥ��ޤ���
- �������ƽ���夬�ä��ǥ���������ʸ��ڤ꤬�����ȥ��ĥ��IJ����ˤʤ�ˤϡ��ɤ�������ԡ����Ƥ⥢�ʥ�����Ͽ�ʥơ��ץ쥳����������̿��ˤΤ褦���������뤳�Ȥ�����ޤ���
- ��äȤ⡢�����ե����ޥåȤ���Τ����Ĥ��ϰ��̤ˤ��ǥ�������¸���˸��Υǥ�����������������������Ƥ��ޤ��ޤ���
 ����
����
- ���ߤ�ǥ����벽����ݤ���������
- ���Ǥ�Ӥ����̻Ҳ���ְ㤨��ˤȽ�ʬ�ʾ����Ͽ�Ǥ��ʤ���
- ���οޤ�360dpi��dot per inch�ˤDz����ˤ�����Τǡ�����50dpi�ǹԤä���Ρ�
- ���ߤ�ǥ����벽����ݤ���������
- ��
- ��
- �����ǥ������Ĺ�ꡢû��
- ����ޤǤ�Ĺ���ȥǥ�����ˤĤ��ƽҤ٤Ƥ��ޤ��������ǥ�����ιͤ��϶ˤ�Ƹ��ڤ���ɤ��ͤ����Ǥ��ꡢ���ν�����ñĴ�ʺ�ȤǤ���ȸ����ޤ���
- ����ԥ塼���Ǥʤ���ФȤƤ�Ԥ��ʤ���ȤǤ���
- Ŭ�ڤ��̻Ҳ��Τ�Ȥǥǥ����벽���줿�ǡ������ʼ����������ʤ������٥��ԡ����Ƥ��ʼ���Ʊ���ˤʤ�ޤ���
- �Ǹ�˥ǥ������Ĺ�ꡢû���ޤȤ�Ƥ����ޤ���
- ��
- �����
- �������ԡ��ˤ���ʼ�������̵����
- �����ǡ����̿��������Ǥ��롣
- �����Խ����ù����ưפǤ��롣
- �����ߴ��ե����ޥåȤˤ��ǡ����ζ��̲�����ǽ��
- ��
- ��û���
- �����̻Ҳ��ʥǥ��������ˤˤ�äƤ��ʼ����������롣
- �����ǡ����̤�¿����
- �����ե����Υ쥹�ݥ����λ����ǻҤΥ쥹�ݥ�����2006.07.07�ɵ���
- ����̤��ƤǤ�������Ͽ������ˡ��ե�����Ȥ����ȸ��λ����ǻҡ�CCD��CMOS�ˤǤ��������Ѥ��ޤ���
- ξ�Ԥ��礭�ʰ㤤�ϡ��ե���ब���ʥ�����Ͽ�Ǥ���Τ��Ф������λ����ǻҤϥǥ����뵭Ͽ�Ǥ��뤳�ȤǤ���
- ���λ����ǻҤǤϡ������̤˲��ǤȸƤФ�뾮���ʸ����ߤ�������������Ƥ��ơ������Dz��������ڤ��ޤ���
- �����ʲ��ǡˤǾ����ڤ���Ȥ������Ȥϡ������ڤ�ˤʤ뤳�ȤǤ��ꡢ�ǥ����륵��ץ��ɸ�ܲ����̻Ҳ��ˤ���뤳�Ȥ��̣���ޤ������λ����ǻҤǤϡ����ǿ��ʾ�ξ�������뤳�Ȥϴ���Ū�ˤ��Բ�ǽ�Ǥ���
- �ʤ�����������Τη������狼�äƤ����硢�㤨�б߷��Τ�Τ�̤���硢ʣ���β��Ǥ���߷��η������濴���֤֥ԥ�����ñ�̤ޤǷ��ˤ�äƵ��뤳�Ȥϲ�ǽ�Ǥ�����
- 2/3�����CCD��8.8mm x 6.6mm�ˤǡ�800x600���Ǥ���Ļ����ǻҼ��Τβ����Ϥϡ�
- ��
- ������800����/8.8mm x 1/2 ����/���ǡ� x 1/2 �ʥʥ������ȸ³��� = 22.7��/mm
- ��
- �Ȥʤ�ޤ���
- ȿ�̡�����ե����Τ褦�ʥ��ʥ�����Ͽ�ϲ��ǤȤ�����ǰ���ʤ������γ�Ҥ��礭���������Ϥη����װ��Ȥʤ�ޤ���
- �ޤ������ʥ��������ϡ��ǥ���������Τ褦���̻Ҳ��ˤ�äƤ�������ϰʾ�ˤʤ�Ⱦ��������˾ä��뤳�ȤϤ���ޤ���
- ���ʥ�����Ͽ�Ǥϡ��٤���������Ф���������̵���ʤ뤳�ȤϤʤ�������̵���ʤäƤ������Ǹ�ޤǤ������˾������äƤ��ޤ���
- ����ե���༫�Τϡ�����ե����Ǥ��褽200��/mm���٤β����٤����ꡢ���顼�ե�����100��/mm���٤ξ������äƤ��ޤ���
- ���ʥ�����Ͽ���Τϡ����̤�CCD �����ǻҤ�100�ܰʾ�ξ�����������ΤǤ���
- ��
- ��
- �����ʥ������ȼ��ȿ��ιͤ�������2006.05.22�ɵ���
- �Ƕ�θ��ؽ��CCD�����δ�Ϣ���Ҥ��ɤ�Ǥ���ȡ������Ϥι��ܤ˥ʥ����������ޤȤ������դ��ФƤ��ޤ���
- ����ϡ���ŵŪ�ʸ���ʬ��ǤϻȤ��ʤ��ä����դǤ���
- �ǥ�������������о줷�Ƥ������դǤ���
- �ʥ����������ޤȤϤɤΤ褦�ʤ�ΤʤΤǤ��礦����
- ����ˡ��ʥ������ȤȤ����ΤϤɤ�ʿ�ʪ�ʤΤǤ��礦����
- �ʥ������ȡʥϥ���ʥ������ȡ�Harry Nyquist��1889.2.7 - 1976.4.4�ˤϡ����������ǥ��Nilsby���ޤ��ʪ���ؼԤǡ���ư���������θ�����Τ��Ƥ��ޤ���
- ���18�ͤλ����ƹ���ϤäƵ�����̤������Ρ�����������ؤ��ŵ����ؤ�ؤӡ���������ءʥ���������ء�Yale University�ˤ���ι��������ޤ�����
- ���´�ȸ塢28�ͤ�ǯ��1917ǯ����1934ǯ�ޤǤ�17ǯ�֡�AT&T������American Telephone and Telegraph Compnay�ˤ˶Фᡢ�ſ������Ȳ����̿��θ���˽������Ƥ��ޤ���
- ���θ塢1934ǯ����1954ǯ�ޤǥ٥����õ������˰ܤ��̿����Ѥθ���˽������ޤ�����
- �����Υ٥븦��꤫��ϡ��������Τ��Ȥ�ͭ̾�ʸ����ã���ڽФ���Ƥ��ޤ���
- �ȥ�������ä�����å��졼��1947ǯ�ˤ䡢CCD�ǻ���ͰƤ���W.S.�ܥ����G.E���ߥ���1970ǯ�ˡ��졼���θ�����Τ��륿����Charles H. Townes��1915���ˡ�����ԥ塼�����������ʴ����Ƥ���UNIX���ۤ������ȥ�ץ���ȥǥ˥�����å���1968ǯ�ˤ�٥����õ������θ�����Ǥ�����
- ��Υ饤�ե���Ǥ����®�٥����⡢���Υ٥����õ������ǻ�����夲�ޤ�����
- ���λ��塢�����������狼�������������ˤ����ƤΥ���ꥫ�ϡ����ƹ��ɤ˼���Ȥߡ��ȥ�����γ�ȯ��졼���γ�ȯ�⥤���ͥåȡ��̿�ʬ��ˤ��ȯ�ʸ��椬�ʤ�ǡ��٥����õ��������ä�ͥ�줿�������̤�Ф��Ƥ����ޤ�����
- ��
- 1927ǯ��AT&T�������̿����Ѥθ���Ƥ����ʥ������Ȥϡ����ʥ��������ǥ����륵��ץ����ݤˡ������Ƹ�����Τ˼��Ф��������ʥ���������ȿ���2�ܤ�ɬ�פǤ��뤳�Ȥ��ͤ��ߤ��ȯɽ���ޤ�����
- ���줬��ˡ��ʥ������� - ����Υ�Υ���ץ��������ɸ�ܲ����� = Sampling Theorem�ˤȸƤФ��褦�ˤʤꡢ�ǥ����뿮����������������ڤʤ�ΤȤʤ�ޤ�����
- ����Υ��Claude Elwood Shannon, 1916.04 - 2001.02���ƹ�ߥ��������ޤ�ˤϡ����������˴ؤ���ͭ̾�ʿ��ؼԤǥ���ԥ塼�����Ѥδ��ä��ۤ��夲���ͤǤ���
- ��ο���Ū��ˤ�äƥʥ������Ȥ�ȯ���ο���Ū�դ����ʤ���ޤ�����
- ɸ�ܲ������Ȥϡ��פ���ˡ���������Ȥ��������桢���٥ǡ����ʤɤΥ��ʥ��������ǥ����뿮��Ȥ��Ƽ�����ݤˡ��ۤ������ʥ��������2�ܰʾ�Υ���ץ����ä��ǥ����뿮�������ɬ�פǤ��롢�Ȥ��������Ǥ�������������ʤ����ٴ�����10Hz�γΤ��餷�����٥ǡ������ߤ����Ȥ��������ǥ����륵��ץ�����硢����0.05�ä˰���20Hz�ˤǥǡ�������ʤ������Τʲ��ٷ�¬���Ǥ��ʤ����Ȥ��̣���ޤ���
- �ޤ����㤨�С�100Hz�ǿ�ư���Ƥ���ʪ�Τ��¬����ˤϺ���200Hz�ǥ���ץ�Ǥ���¬��Ϥ�ɬ�פǤ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- 2�ܤΥ���ץ������Фʤ�Ȥ��ǡ������ɤ��롢�Ȥ����Τ�ɸ�ܲ������Ǥ���
- ��
- �����ǰ�Ĥλ�ߤ��Ԥ��ޤ���
- CC�Ĥ���ɽ�����ǥ����뻣���ǻҤϡ������̤����פ��ܤΤ褦�˶��ڤ��Ƥ��ơ����ǤȤ���ñ�̤ǥ�ˤ�륢�ʥ�������ɸ�ܲ�����ޤ���
- ���λ����ǻҤǤϡ����Ǥ���������δ���ñ�̤ȤʤäƤ���ʾ�κ٤�������ϴ���Ū�ˤ��ɤ߽Ф����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���Ǥ�ʥ������ȤΥ���ץ�����������ƤϤ�ޤ��ȡ����ξ���ϡ������β��Ǥ�Ⱦʬ������Ͽ�Ǥ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- 1,000mm x 1,000mm���о�ʪ��1,000���� x 1,000���ǤǤȤ館��ȡ������1mm�����ǤϤʤ���2mm������500 x 500����ץ�ˤε�Ͽ�Ȥʤ�ޤ���
- ���ޤ˼������ǥ����륫���Ǽ̤��������ϥ��㡼�Ȥβ����ϡ����������褯ɽ���Ƥ��ޤ���
- ��ȹ��β�����4�ԥ������2�ԥ�����x2�˰ʾ�ʤ��Ƚ�ʬ�ˤ��ξ���������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- 2�ԥ����뤬�ǥ���������κǾ�����ñ�̤ˤʤ뤳�Ȥ�褯ʪ��äƤ��ޤ���
- �����ϡ�CCD�����Τ褦�˱������ܤ�ʬ���뤳�ȤϤʤ������ʥ����θ������Ǥȸ����ޤ���
- ���ե����С��Τ褦�����ݤDZ����������ã�����Τ⡢ɸ�ܲ�����Ȥ��ƺ����٤��ʤ��Ǥ��礦��
- ��������Ψ��Fill Factor�ˤȲ�����
- �����Ǥ���äȤ������䤬�來�夬��ޤ���
- ��Ȥ�ľ�ܴط�����ޤ����ǥ����륵��ץ�������ε���Ǥ���CCD�����˻Ȥ��Ƥ�����λ����ǻҤ�1����ʬ�����٤Ƽ������ǤϤʤ�������ʬ�����������Ȥ��ƻȤäƤ��ޤ���
- ������������Ǥ����Ѥ��������Ψ��Fill Factor�ˤȸƤӤޤ���
- �Żҥ���å���ǽ�����륤���饤��CCD�����ʸ��ߤΤۤȤ�ɤ�CCD�����Υ����סˤϡ��ǻ�����ž����ϩ���������ʤ���Фʤ�ʤ��ط��塢����Ψ��20%���٤Ǥ���
- ��ŵŪ��CCD�����Ǥ���ե졼��ȥ�ե����Ǥϡ�������ž������Ǿ�ǹԤ��Τdz���Ψ��100%�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���̤�CCD�ǻҤξ�硢�����������ߤ�����Ǥǥ��ʥ�������Τɤ��ޤǤ���¤˺Ƹ��Ǥ���ΤǤ��礦����
- ������������ޤ��ȡ����ȿ�Ū�ˤϳ���Ψ���㤤�����������٤������̤�Ƹ��Ǥ���ȿ�̡����������־���Ϸ���Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��
- ��

- ��
- ��

- �� ��
- ��
- ��
- ������
- �ǥ�������������ˤϡ����ʥ�����Ͽ�Ǥ�����ˤʤ�ʤ��ä��嵭�Τ��Ȥ����դ��Ʋ����Ƥ���ʤ��ƤϤʤ�ޤ���
- �ǥ��������ϡ�����θ³����Ϥä��ꤷ�Ƥ��ơ��³��ʾ�ʥ���ץ���ȿ���Ⱦʬ�ʾ�ˤξ���Ϥ���������ʤ����פ�����Ƥ���ΤǤ���
- ����ץ���ȿ�����⤤���ȿ��������ȡ��ְ������줿�������ʾ�����Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���줬ͩ��ʥ����ꥢ���ˤǤ���⥢��ˤʤ�ޤ���
- ����Ū�ˤϥ����ꥢ�������졢����Ū�ˤϥ��ȥ��ܸ��̲����ˤʤ�ޤ���
- ��®�Dz�ž���Ƥ���ʪ�Τ���ä���Ȳ�ž���Ƹ�������ղ�ž���Ƹ�������ߤޤäƸ�����Τϡ��ºݤ�ʪ�Τβ�ž����ٲ�������ץ���㤯�ƴְ�������Ƥ��ޤ�����Ǥ���
- �Dz��ƥ�ӥ��ޡ������Ǽ֤����ϼ֤μ��ؤ��ղ�ž���Ƹ�����ΤϤ��θ��ݤǤ���
- ���䥢�ʥ�����������ե����ʶ�����������ˤǤϡ��ǥ����륵��ץ��Ǻ�ޤ���뤳�Ȥ�����ޤ��顢�ʲ��˽Ҥ٤�MTF��Modulated Transfer Function�˶����ˤ������Ϥ�ɾ��ˡ�����Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���ιͤ����Ͼ�����ã�ؿ��Ȥ������ؼ�ˡ������Ƥ��ޤ���
 ��
��
- ��
- ����MTF������Modulation Transfer Function Curve�ˡ���2006.02.12��
- ������
- MTF�����ˤ��ɾ��ˡ�Ǥϡ���� �� ����ǻ�٤ˤ��쥹�ݥ����ȿ��ˤ��쥹�ݥ� �פǽҤ٤��ʻҼʤΥ��㡼�Ȥ��������������ζ��٥쥹�ݥ��鱦�Τ褦���������������ޤ���
- ���ζ����ϡ������˲����Ϥμ��ȿ���ʬ��Ȥꡢ�ļ��˥���ȥ饹�ȤΥ쥹�ݥʶ��٥쥹�ݥˤ��äƤ��ޤ���
- ����դϡ������α��˹Ԥ��ۤɺ٤���������ʬ��ɽ�����������ȿ����⤯�ʤ�ޤ���
- �ļ��Υ���ȥ饹�ȤȤϡ��������ʲ����Ǥ�ǻ�پ���ˤä�����ã�����ٹ礤����1.0�Ȥ����ͤ�100%����ã�ʴ�������ã�ˤǤ��ꡢ0.5�Ȥ����Τ�Ⱦʬ�˸��ꤷ��������ã�Ȥʤ�ޤ���
- ����Ū�˲�����ʬ�μ��ȿ����⤯�ʤ�ȡ���Ͽ����Ϥ���˽�ʬ�ˤĤ��ƹԤ��ʤ��ʤꡢ�Ǹ�Ϥޤä���ȿ�����ʤ��ʤ�ޤ���
- ���ȿ����㤤��ʬ�Ǥϥ���ȥ饹�ȥ쥹�ݥ����������ʾ�����������ã����ˡ����ȿ����⤯�ʤ�ˤĤ�ƥ쥹�ݥ������ʤꡢ�Ĥ��ˤ�ȿ�����ʤ��ʤ�ޤ���
- �ʾ�����ã����ʤ��ʤ롣��
- ���μ��ȿ��ȥ쥹�ݥδط������֤�MTF��Moduration Transfer Function�˶����ȸ��äƤ��ޤ���
- �����Ѹ�Ȥ���OTF��Optical Transfer Function�ˤȤ����������⤢��ޤ���
- ����MTF�����ˤ�äƥ������ǽ�Ϥ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���ޤ˼����������ϡ����������ħ����MTF�����Ǥ���
- ��
- ��1�ˤ����ۤ�MTF�����Ǥ����⤤���ȿ����Ϥäƹ⤤����ȥ饹�Ȥ��Ƥ��ޤ��������������ʸ��ʤ���ǽ���ɤ���Ǥ���
- ��2�ˤϡ��������٤μ��ȿ��ޤǹ⤤����ȥ饹�Ȥ���Ĥ�ΤΡ��٤������̤ˤʤ�ȥ���ȥ饹�Ȥ���ü���㲼���ޤ���
- ��3�ˤϡ��㤤���ȿ��ǥ���ȥ饹�Ȥ��㲼�����ΤΡ��⤤���ȿ��ޤǤʤ�Ȥ�����ȥ饹�Ȥ�ݻ����Ƥ��ޤ���
- ��4�ˤ�¨�¤˥���ȥ饹�Ȥ�����Ƥ��ޤ���ΤǤ����ԥ�ȥܥ��μ̿��������ˤ���������������̤ǤϤ��Τ褦�ʲ����������ޤ�����
- ���οޤǶ�̣����Ȥ����ϡ���2�ˤȡ�3�ˤζ�������IJ��������̤Ǥ���
- ��2�ˤϥ���ȥ饹�Ȥι⤤���̤ǡ�3�ˤϥ���ȥ饹�Ȥ��㤤���̤Ȥʤ�ޤ���
- ��������Ƚ�Ǥ���ȡ��⤤���ȿ��ޤǥ���ȥ饹�Ȥ���ġ�3�ˤ������̿����̤Ȥ��Ƥ��ɤ��褦�˸��������ޤ������ºݤϡ�2�ˤΤۤ������줤�˸����ޤ���
- ��3�ˤϥ��եȥե��������Υ�Ȥʤ�ޤ���
- ���Τ褦�ˡ��̿������Ū�ˤ��ä����̤���ƥ���߷פ��ʤ���ޤ���
- ���ɾ���������ݽѴվ��ѤȤ��ƻȤ����ɾ���Ϥ����ۣ��Ǥ���
- ������ˤ��äơ�MTF�����Ͽ���Ū��ɾ�����Ǥ�������ʤ���ˡ�Ǥ���
- �����ǥ������������������-���⥢��
- ���λ����ǻҡ�CCD��CMOS�ˤ��Ȥ߹�碌����λ��ѤǤϡ����λ����ǻҤβ��Ǥ�ǽ�Ϥ˹�碌���������ɬ�פȤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ���λ����ǻҤβ����ϰʾ����ǽ����ä����ɬ�פˤʤ�ޤ���
- ��ϥ��ʥ��������λ����ǻҤϥǥ�����Ǥ��뤳�Ȥ�Ƭ������Ƥ����٤��Ǥ���
- �ǥ������ǻҤǤϥ����ꥢ�����ݡ�ͩ��ݡˤ�����ޤ���
- ���λ����ǻҤǤϡ��㤨��12um�Ѥβ��ǤǤ��ä��Ȥ���ȡ��ǻҤβ����Ϥ�
- ��
- ����1/��2x12E-3�ˡ�mm/lp =��41.67��lp/mm����������Lens - 35��
- ��
- ��
- ���³��Ȥʤ�ޤ���
- ����ʾ�κ٤��������Ф��Ƥ�������������ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- �٤��������ϡ��������ʤ��ɤ��������˼������褦�ʥ⥢������ȤʤäƸ���ޤ���
 ���οޤϡ����λ����ǻҤ��Τ�Τβ����ǤϤ���ޤ������褽���Τ褦�ʥ⥢������Ȥʤ�ޤ���
���οޤϡ����λ����ǻҤ��Τ�Τβ����ǤϤ���ޤ������褽���Τ褦�ʥ⥢������Ȥʤ�ޤ���- ���ꥸ�ʥ�����ʺ���ˤ��濴���κ٤�����ʬ�ϡ��⤤���ȿ���ʬ����äƤ��뤿�ᡢ�����ǻҤβ��Ǥȴ��Ĥ����������ְ���������㤤���ȿ���ʬ�Ȥ��Ƹ���Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��
- ���������ꥢ��
- ����1/��2x12E-3�ˡ�mm/lp =��41.67��lp/mm����������Lens - 35��
- �ǥ������ǻҤǤϡ���ʬ�λ��äƤ��륵��ץ���ȿ��ʲ��ǡ˰ʾ�κ٤�����������ȸ������Ȥϰ�ä�����������뤳�Ȥˤʤ�ΤǤ���
- �ǥ����륵��ץ���ؤǤϡ����Τ褦�ʸ��ݤ��ꥢ����ͩ��ˤȸƤ�Ǥ��ޤ����������ؤǤϤ����⥢��ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �ǥ��������Ǥϡ��ǥ����륵��ץ�ʾ�θ�����������ȡ����θ��ݤȤϰۤʤä�����ץ���ʤ����Ȥ�����̿������ޤ���
- �ǥ����빩�ؤǤϥ���ץ���ȿ�����٤������ȿ��˴ؤ��Ƥ����Ϥ��ʤ�����Ƥ�����Ƥ��ޤ���
- ���줬�������ѥ��ե��륿��Low Pass Filter�ˤȤ���High Frequency Cut Filter�ȸƤФ����ȿ������ˡ�Ǥ���
- ����ץ���ؤǤϥ���������ꥢ���ե��륿��Anti Alias Filter�ˤȤ����Τ��Ƥ��ޤ���
- ��
- ��������Ū�����ѥ��ե��륿
- CCD �ǻҤˤĤ��Ƥ⡢���Τ褦�ʼ���Ƥ��äƤ����Τ�����ޤ���
- CCD�����ǻҤ˻Ȥ�������ѥ��ե��륿�ʲ��ǥԥå�����٤�����������줵���ʤ��ե��륿�ˤϡ��徽��ʣ�����������Ѥ�����Τǡ����ظ��ᤷ�������бѥ��饹�����ǻҤ����̤����֤��ޤ���
- �������뤳�Ȥˤ�äơ��٤����������ǥ��åȤ���Ʋ��ǰʾ���礭�ʾ���Τߤ������ǻҤ���ƤǤ���褦�ˤʤ�ޤ���
- �����ѥ��ե��륿���������������ǻҤǤϡ��ߤ����β����Ϥ�Ⱦʬ�ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- Ⱦʬ�ˤʤäƤ⤪�����ʲ����ʥ⥢�졢������ˤ���������ɤ��Ȥ���Ƚ�ǤǤ���
- ���ξ�硢���㤨��12umx12um�β��Ǥ���IJ����ǻҤβ����Ϥϡ�41.67��/mm��Ⱦʬ��20.8��/mm�Ȥʤ�ޤ���
- �ǥ�����ǡ����ϡ����Τ褦�ʴ�������ɸ�ܲ��ʾ�Υǡ��������뤳�Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ��
- ��
- ����ʣ������ϡ�ʣ������Ȥ߹�碌�ˤ������ϡ���Ȼ����ǻҤ���������ϡ���2005.12.08�ˡ�2006.04.16�ɵ���
- ��
- �ºݤνꡢ�����β����Ϥϥ�ȵ�Ͽ���Ρʸ��λ����ǻҡ��ե����ˤ��Ȥ߹�碌�Ƿ�ޤ�ޤ���
- ���ñ�ΤǤ��Ф餷�������Ϥ���äƤ��Ƥ⻣���ǻҤβ����Ϥ����äƤ���в��ˤ�ʤ�ޤ���
- �ޤ������ʣ���Ȥ߹�碌�Ƹ��طϤ��ä����ˤ⡢��������Ϥϸ���ޤ��������ϡ�����طϤȵ�Ͽ�ǻҤ�����ɾ���Ƿ�ޤ�ޤ���
- ���ξ塢�ե����ʥ��ʥ�����Ͽ�ˤȸ��λ����ǻҡʥǥ����뵭Ͽ�ˤǤϹͤ����������Ѥ��ޤ���
-
- �������ʥ�����Ͽ���Τξ��
- .
- ���ʥ�����Ͽ�Υե�����Ȥä���������Ϥϡ�������������Ϥο���Ūɽ���ˤǿ���ޤ�����
- ���ʥ����ǻҤ�ʣ���Ȥ߹�蘆�ä��ϤǤ���������Ϥϡ��ʲ��ζ������ɽ����ޤ���
- ��
- ������1/R = 1/R1+ 1/R2 + ��---�� + 1/Rn����������Lens - 36��
- R1��R2��Rn���������Ϥ˴ط�������ط����Ǹġ��β����ϡ���/mm��
- ��
- ���δط����Ϸи����Ǥ���
- ���طϤ��Ȥ߹�碌��������������Ϥ�Ƥ����Ȥ��˻��ͤˤ��٤����Ǥ���
- ���δط����ϡ����ñ�Τȥե������Ȥ߹�碌���ե���५���ξ�硢��β����ϡ�80��/mm�ˤȥե����β����ϡ�150��/mm�ˤǤ����礷��52��/mm���٤ˤʤ롢�Ȥ������˵��ޤ���
- ���δط����ϡ��ƹ��ʪ�����ؼԤǼ̿���¬����ʹҶ�¬�̥����ˤγ�ȯ�˽�������Amrom H. Katz��1915-1997�ˤ�1948ǯ�˽�ɽ�����Τ��ǽ�ǡ����θ夤�������ʸ���Ԥ��¸���ԤäƼ¸�����Ƴ���Ф��Ƥ��ޤ���
- Katz��ˡ§�ˤ��С�100 lp/mm����ǽ����ĥ��100 lp/mm����ǽ����ĥե�����Ȥ��ȡ���������ϤϤ���Ⱦʬ��50 lp/mm�ˤʤꡢ�ե���ब300lp/mm���٤ι�����٤�ͭ�����ΤǤ���С���������٤ϰ������ǤǤ����˼����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���δط����Ϸи����Ǥ���
- ��
- ��
- �����ǥ����뵭Ͽ���Τξ������2020.01.02�ɵ���
- �ǥ����뵭Ͽ��Ԥ����λ����ǻҡ�CCD����顢CMOS �����ˤǤϡ������ǻҤβ��Ǥ������Ϥη���Ū�����ǤȤʤ�ޤ���
- ��˵��ط��������ˡ����λ����ǻҤβ��ǥ�������S�ˤǴ���Ū�ʲ����Ϥ���ޤäƤ��ޤ��ޤ���
- 1���Ǥ��礭����um��
- �����ǻҤ����в����ϡ���/mm��
- 40x40
- 12.6
- 25x25
- 20
- 12x12
- 41.6
- 9x9
- 55.6
- 6x6
- 83.4
- 4x4
- 125
- ������R ��/mm = 1/��2xS�ˡ���������Lens - 37��
- ������������S�������λ����ǻҤ�1������������礭����mm��
- ����
- ������������S�������λ����ǻҤ�1������������礭����mm��
- 1990ǯ���ᡢ1���Ǥ�40 um x 40 um ��CMOS ���λ����ǻҤ�Ȥä���®�٥���餬ȯ�䤵��ޤ�����
- ���Υ����ϡ�4,500���ޡ��äλ��Ƥ��Ǥ����ᡢ���ʤ�®����®�ٸ��ݤ�¨�¤˻��Ƥ��ƺ������Ǥ���褦�ˤʤꡢ������������ڤ곫���ƹԤ��ޤ�����
- �����������Υ����ϲ��Ǥ�256����x256���Ǥ��Ƥ���ΤǤ�����
- �����ɽ�Ǹ���ȡ�12.6��/mm�β����ϤȤʤ�ޤ���
- �������٤��ǻҤ�ޤ��ʤ���ϡ����ʤ�²��ʤ�ΤǤ⽽ʬ�ʤΤǡ����Υ�����Ȥ��¤��Ť�����ɬ�פϤ���ޤ���Ǥ�����
- ��������40um��������256���ǣ�256���Ǥ���ޤ������饤�����������10.24x10.24mm���礭����1�������1���ˤ��緿��C �ޥ���ȥ����Nikkor���F-�ޥ���ȡˤ�Ȥ�ɬ�פ����ꡢ1/2�������1/2�������٤Υ�Ǥϲ����������˥���줬�ФƤ��ޤ��ޤ�����
- ���ߤ�CCD �ǻҤϡ���¬�ѤǤ�12 um x 12 um ��������¿���褦�Ǥ���
- ���Υ������Ǥϡ�41.6mm/�ܤβ����Ϥ���Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ����顢����ܰʾ��83��/mm�β����Ϥ���Ĥ�Τ�ɬ�פǤ���
- �ʤ������٤β����Ϥ���ĥ��ɬ�פǤ��뤫�ȸ����ȡ����λ����ǻҤ�Ʊ�������Ϥ���ĥ��Ȥ�����������ϤǸ��λ����ǻҤλ��IJ�������ǽ���ݻ��Ǥ��ʤ�����Ǥ���
- ��������Ϥϡ���ǽҤ٤�Katz�μ����θ����ȡ�
- ��
- ��������1/41.6 ��/mm�� + ��1/83 ��/mm��=��1/27.4 ��/mm����������Lens - 38��
- ��
- �μ���ꡢ27.4mm/�ܤȤʤꤽ���Ǥ��������ʥ����Υ�ȥǥ�����θ����ǻҤǤϤ��μ��Ϥ��Τޤ����ƤϤޤ�ޤ���
- Katz�μ��ϥ��ʥ������Τ���������Ϥ�и�Ū�˼�������ΤǤ��ꡢ�����ǻҡʥǥ�����ˤ���ߤ�����ˤϡ��Ϥä���Ȥ����̻Ҳ����������뤿��˥�β����Ϥ������ǻҤ���ǽ�ʾ�Ǥ���и¤�ʤ������ǻҤβ����٤˶�Ť��ȹͤ����뤫��Ǥ���
 �⤷�����λ����ǻҤ˥⥢����ɤ�����˥����ѥ��ե��륿����������Ƥ���Ȥ���ȡ�12 um x 12 um���������ǻҼ��Τβ����Ϥϥ����ѥ��ե��륿�ˤ�ä�20.8��/mm�����ˤʤ�Τǡ�����ܤ�41.6��/mm����ǽ����ä���Τǽ�ʬ�Ǥ���ȹͤ��ޤ���
�⤷�����λ����ǻҤ˥⥢����ɤ�����˥����ѥ��ե��륿����������Ƥ���Ȥ���ȡ�12 um x 12 um���������ǻҼ��Τβ����Ϥϥ����ѥ��ե��륿�ˤ�ä�20.8��/mm�����ˤʤ�Τǡ�����ܤ�41.6��/mm����ǽ����ä���Τǽ�ʬ�Ǥ���ȹͤ��ޤ���
- ���������ǥ������ǻҤβ����Ϥϡ�20.8��/mm�ʾ�β��������������դ��ʤ��Τǡ����٥쥹�ݥϡ������ͤ�100%�����0%�ޤǵ�˸������ޤ���
- ���䥢�ʥ����ǻҡʥ�ˤϡ��ˤ䤫�˥쥹�ݥ��Ѳ����ޤ���
- ���δ������鸫��ȡ����ʥ����ǻҡʥ�ˤβ����Ϥϡ��ǥ������ǻҤλ��ġʥ����ѥ��ե��륿���θ�����˲����Ϥ�������80%�ʾ�ζ��٥쥹�ݥ���äƤ��뤳�Ȥ�˾�ޤ�ޤ���
- ���ʥ����ǻҤξ�硢���٥쥹�ݥ�10%���٤Τ鷺���˲����٤��ݤä����֤Ǥ�����Ϥ�����ȸ��ʤ����Ȥ�����Τǡ�ξ�Ԥβ����٤δ����ˤϽ�ʬ�ʹ�θ��ɬ�פǤ���
- 12 um x 12 um�β��Ǥ���ĸ��λ����ǻҤ�41.6��/mm�β����Ϥ���������β����Ϥǽ�ʬ�ʥ쥹�ݥ���ĥ��2�ܤ�83��/mm���٤β����٤���ä���Τ�˾�ޤ�ޤ���
- �㤨�С�12 um x 12 um���ǥ�������1280x1024���Ǥ��ǻҤλ����ǻҤϡ��ǻҤ��礭����15.36x12.29mm���г���19.7mm�ˤȤʤꡢC �ޥ���ȥ�ǤϤ���С��Ǥ��ޤ���
- �˥å������ǤϤ����ϰϤС��Ǥ��ޤ����������μ������ˤ����Ƥ�83��/mm�β����Ϥ��ݤĤΤϲ������ʤ�ޤ���
- 12um����������٤��ʸ��λ����ǻҤǤϡ������ǽ�������Ϥ��礭����������ȸ��äƤ⺹���٤��ʤ��Ǥ��礦��
- ���λ����ǻҤβ��ǥ���������β����Ϥ��������˺٤�������ˡ������ǽ�����������褦�ˤʤ�ޤ���
- �äˡ�4um��������CCD �ǻҤǤϡ����250��/mm�ʾ�β����٤��ᤵ���Τǡ��������������Τ϶�����������Ǥ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- �ޤ���4um���Ǥ��ǻҤ˥�ξ����褦�Ȥ���Ȳ��ޤȤ������꤬�����ơ�������θ���������Ѥ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ��ιʤ꤬F/4�ʾ�ˤʤ�Ȳ��ޤˤ��4um�Υܥ��Ȥʤ뤿��ˡ���Ϥ���ʲ������뤤������ǻȤ�ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ���δ����ʥ�β����Ϥδ����ˤ���Ҥ٤�ȡ����̤θ��λ����ǻҤǤ�1����4um���³��ǤϤʤ��������ȹͤ��ޤ���
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
- ������ǽ�̥�μ���
- ������ᥬ�͡�magnifying glass, loupe������2006.02.22�ˡ�2006.08.02�ɵ���
- ��ΰ��ִ���Ū�ʴ��Ǥ�����ᥬ�ͤˤĤ��ƴ���Ū�ʤ��Ȥ��餤���Ƥ����ޤ��礦��
- ��ᥬ�ͤθ������Τ뤳�Ȥˤ�äơ�����̿��������������Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��ᥬ�ͤϡ������ʤ�Τ���礷�Ƹ��뤿����̥�Ǥ���
- �롼�ڤȤ�Ƥ�Ǥ��ޤ���
- ��ǯ��꤬�����äˤʤ�����ŷ����ʤƤ礦�ˤǤ���Ϸ����Ǥ���
- �����ϡ�����Ū�ˤ���ᥬ�ͤǤ���
- Ϸ�ͤξ�硢���Ǥ϶�Τ�Τ������ޤ��顢��Τ�ˤ����Ƹ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��������ȡ���Τ��������ʤäƤ��ޤ��Τǡ���ᥬ�ͤ�ڤ��Ϸ�ͤ��ܤι礦���֤�������äƤ���ɬ�פ��ФƤ��ޤ���
- ����ˡ������Τ���������硢�礭�����ˤ���ɬ�פ�����ޤ���
- �ĤޤꡢϷ�ͤξ�硢������ʪ�Τ�Ŭ�ڤʵ�Υ�Ǥ����⽽ʬ���礭�������뤿���ƻ�����ᥬ�͡�ŷ�����Ϸ����ˤ�ɬ�פʤΤǤ���
- �㤤�ҡʶ��ԡˤ��Ȥ��Τ�Τä���ȸ��뤿��ζ���Ȥϼۤʤ�ޤ���
- ��ᥬ�ͤδ���Ū����ǽ�ϡ�������ʪ�Τ��̥�ξ�����Υ��˵���֤��ơ����礵�줿�ص����٤��äƤ��ε�����ͤ�����Ȥ�����ΤǤ���
- �����ϡ��̥�ξ�����Υ�ζ���֤��Ф����ۤɳ��礹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������������ΰ��֤ˤǤ��Ƥ��ޤ������礭�����礷�Ƥ������ΰ��֤ˤǤ��Ƥ��ޤ����껦����Ƴ��礬���ԤǤ��ʤ��ä��ꡢ�̥����ǽ�ˤ�äƤϳ��������ܤ��Ƥ��ޤ������礭�ʳ���ϴ��ԤǤ��ޤ���
- ���̤οͤ��ܤϡ�250mm���դ�ʪ�Τ����ָ��䤹�����֤Ȥʤ뤿��ˡ���ᥬ�ͤ���Ĥȼ������ܤ���ᥬ�ͤ˶�Ť��ơ�25cm�ν�˵������Ǥ���褦��Ĵ�ᤷ�Ƥ��ޤ���
- ��̤Ȥ��ơ��ʲ��˼����褦�����֤Ȥʤ�ޤ���
- ��

- ��
- ��οޤǤϡ�����Τ���ᥬ�ͤξ������ֶ�˵�ʤ����ޤǤ��˵�ˤ��֤���ޤ���
- �������֤�����֤�����硢�����ϤǤ��ޤ���
- �������֤��������¦�ˤ��֤��ȵ����Ͼ�������Τˤʤ�ޤ���
- �ͤ���ᥬ�ͤ���������Τ������Ȥ��������Ȱ��ָ��䤹����Υ�ǡ��ʤ����ĺǤ��礭�ʳ�������褦�Ȥ��ƥ�����夵��������Τ�������ֶ�˵���֤��褦�ˤʤ�ޤ���
- ��
- ��������ε�Υ
- �ºݤˡ��̥�����ƾ�����ʪ�Τ������Ȥ����ͤϰ��ָ��䤹����Υ�˵������Ǥ���褦�˥�ΰ��֤�Ĵ�����Ƥ��ޤ���
- ���줬¿���ξ�硢����ε�Υ��the least distance of distinct vision, 250mm���ȸ����Ƥ����Υ�Ǥ���
- ���������ºݤνꤽ�ε�Υ�Ͽͤˤ�äƤޤ��ޤ��ǡ����οͤ�100mm�ΤȤ����Ǥ�Τ뤫���Τ�ޤ������οͤ�400mm�ε�Υ�Ǹ��뤫���Τ�ޤ���
- ���ΰ�̣�Ǥϡ���ᥬ�ͤ���Ψ�ϰ���Ū�ʤ�Τǡ��ͤˤ�ä��Ѥ��ȸ�����Ǥ��礦��
- ��
- ������ᥬ�ͤ���Ψ
- ��ᥬ�ͤ���Ψ�Ǥϡ��ͤϳ�������250mm�ΰ��֤��鸫��Ȥ����������Ω�äưʲ�����Ψ�θ�����Ƴ���Ƥ��ޤ���
- ��
- ����������M = 250/ f + 1����������Lens - 39��
- ����������������M����������������������
- ����������������250��������ε�Υ��the least distance of distinct vision�ˡ�mm��
- �����������������桧����ᥬ�ͤξ�����Υ��mm��
- ����������M = 250/ f + 1����������Lens - 39��
- �����⤦��Ĥ���Ψ��ɽ����
- ��ᥬ�ͤΤ⤦��Ĥ���Ψ�θ����Ȥ��ơ�a → f�ȶ�������ơ�����b ��250mm������ε�Υ�ˤ������֤Ȳ��ꤷ�ơ���ΨM=b/a��a→f��b→250�˶�������ơ�
- ��
- ����������M = 250/f ����������Lens - 40��
- ��
- �Ȥ��Ƥ����Τ⤢��ޤ���
- a��f�˶�Ť��С�b��250mm����ɤ�ɤ��̵�±�˰ܤäƤ��ޤ��Τǡ����μ��Ͼ���̵��������ޤ���
- f��5mm�Τ褦�ʾ�����Υ��û����ΤǤ���С�b��250mm���礭���ͤȤʤ�����Τ��������ȸ����ޤ�������ᥬ�ͤξ�����Υ��Ĺ����ΤǤϤ��μ������ƤϤޤ�ʤ��ʤ�ޤ���
- ��
- ������Ѥˤ����Ψ
- ����������M = 250/f ����������Lens - 40��
- �̤θ����ơ���Ѥ��礭������Ӥ��Ƥߤޤ��礦��
- ����ʪ��L����礷��L'�Ȥ����Ȥ��Τ��줾��λ�ѡ�ω��ω’�ˤˤĤ��Ƥ���ӤǤ���
- ����250mm�ΰ��֤�L���Ȥ��λ�� tan ω=��L/2*250�ˤȡ���ᥬ�͡ʣ�ˤ�b�ΰ��֤˳��礷���Ȥ��λ�� tan ω’=��M*L/2*b�ˤˤ����ơ�����������ȡ�
- tan ω’/tan ω = ��M*L/2*b��/��L/2*250��= M*250/b������������Lens-41��
- M = b/a��ꡢ
- tan ω’/tan ω = 250/a����������Lens-42��
- �Ȥʤꡢ��ᥬ�ͤ������֤�ʪ�Τΰ��֡�a�ˤ���Ψ���Ѥ�뤳�Ȥ��Ƥ���Ƥ��ޤ���
- a���̾���ᥬ�ͤξ�����Υ�ʣ�ˤ˶ᤤ���֤��֤����Τǡ�a→f�Ȥ������˽Ҥ٤���Ψ�θ��� M=250/f ���������ʤ�ޤ���
- �����������ξ��ϡ�a→��Ȥ��Ƥ�b�������ͤ�a�����礭�����Ȥ�ɬ�פǤ���
- ���äơ����μ��ϱ��֤ˤǤ���̵�±����ˤĤ������ƤϤޤ���Ψ�����Ȥʤ�ޤ���
- ��
- ����������Υ��Ĺ����ᥬ��
- .
- �ä���������ޤ�����Ϸ�ͤδ����f300mm����f500mm�Τ�Τ�ȤäƤ��ޤ���
- ���Υ����Ψ���㤤�Τ���ᥬ�ͤȤϸ����ΤǤ�����ɡ����������礭�������ޤ���
- ��ʹ���ɤ�Ȥ����礭�ʥ�⤳�Τ褦�ʾ�����Υ��Ĺ�����ȤäƤ��ޤ���
- ���Υ��Ȥäƾ�����ʸ�������ˡ�M=250/f�θ��������ƤϤ��Ⱦ�������Ψ�ͤˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �㤨�С�f=300mm�Υ�Ǥϡ�M=250/300=5/6=0.83�Ȥʤ����Ǹ����꾮�����ͤˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ���ξ��ˤϡ���ᥬ�ͤ�ʪ������250mm������ε�Υ�ˤǸ���Ȥ��������Ω�äơ�a�������Υ�ζ�˵���֤��Ȥ�������ˤ��M=250/f + 1�θ��������ƤϤ�ޤ���
- ���ξ�硢M=250/300 + 1 = 1.833�Ȥʤꡢa�Ͼ�����Υ300mm�ζ�Ȥ�����꤫�ʤ���¦�˶�Ť���136.4mm�ΰ��֤�ʪ�Τ���ä���뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ޤ���1/a + 1/b = 1/f �μ�����b = -250mm�����ƤϤ�ƣ� = 300mm����a�����ȡ�a = 136.4mm�Ȥʤ�M = 1.833����Ψ�Ȥʤ�ޤ���
- ��ʹ���ɤ���ᥬ�ͤϡ���Ψ����Ȥ��������ˤ����Τ���Υ��Υ���Ƹ��䤹�����뤿��˻Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ��
- �����μ�����狼�뤳�Ȥϡ���ξ�����Υf��û����Τۤ�����Ψ���礭���ʤꡢ��������Τ���礷�Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ������ȤǤ���
- ������Ψ�����ˤϡ�1/a + 1/b = 1/f �Ȥ���������Ȥäơ�b = -250mm �����������ǥ�κ�¦�ˤǤ���Τ��鵭��Ȥʤ�ˤ�����Ȥ���a → f�˶�Ť���Ȥ������ǵ��Ƥ��ޤ���
- ��ᥬ�ͤξ�硢f = 125mm��50mm���٤������٤���Ψ��M=2��5�ˤȤʤꡢ������פ�����ᥬ�ͤǤϡ� f =25��10mm���٤Τ�Τ��Ȥ���10�ܤ���25�ܤ���Ψ�Ȥʤ�ޤ���
- 10�����٤���ᥬ�ͤǤ� ��ʪ�Τ�50um���٤ޤǿͤδ�Ǹ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����μ�����狼�뤳�Ȥϡ���ξ�����Υf��û����Τۤ�����Ψ���礭���ʤꡢ��������Τ���礷�Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ������ȤǤ���
- ���������������������ޤ��ʼ����Τ褦�Ǥ���
- �ͤδ㼫�Τ⸷̩�ʼ�������ޤ���1�����٤θ�����̵�뤷�ƺ����٤�̵���Τ����Τ�ޤ���
- ����ܤ����Ǥ�̵�±�ʱˤ˥ԥ�Ȥ��礤�ޤ���
- �Ĥޤ�̵�±���طϤ��Ȥ�ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ��������ȡ���ᥬ�ͤ���Ψ�ϡ�M=250/f�ǤϤʤ���M=1+250/f�Τ褦�ʵ������ޤ���
- ��
- ������ᥬ�ͤ���Ψ��-���ޤȤ�

- ������ʤ��Ȥ�Ҥ٤ޤ�����������Ū����ᥬ�ͤ���Ψ�ϡ�M = 250/f �Ȥ��Ƥ���ʸ����¿���������ޤ���
- ���οͤʤ顢̵�±��������Ф��Ƥ�����ʤ������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����餳�μ�������ʤ��ΤǤ��礦��
- ��Τ褦�˶��٤ζ��ȱ�뤬�����äƤ���ȡ�25cm���餤�����ֳڤ�����������ΤǾ�˼�������Ψ���������褦�Ǥ���
- �롼�ڤ串�������ܴ�����Ψ��x5�Ȥ�x10�ˤ⡢��ñ�ʸ�����̵�±�Ǥε����ˤ�뻻�С� M = 250/f�ˤǵ����Ƥ���褦�Ǥ���
- ��μ긵�ˤϡ�x10��10�ܡˤΥ롼�ڤ�����ޤ�
- �ʱ��̿���3�ĤΥ롼�ڤο�����Ⱥ��Υ롼�ڤ�10�ܤǤ��ˡ�
- ���Υ롼�ڤ�Ȥäƺ٤��ʤ�Τ��������ϡ��Τ��˽������ޤ���
- ����1mm�Τ�Τ�10mm�Τ�Τ˸����Ƥ��뤫�Ȥ����ȡ��ɤ��⤽�Τ褦�˳��礵��ƤϤ��餺����������3mm���٤��礭���ˤ��������ޤ���
- ���ط��ǤϳΤ��ˤ���������Ψ�ˤʤäƤ��ޤ���������ܤδ��ФȤ��Ƥϻؼ����줿��Ψ�ۤɤˤ�ǧ���Ǥ��ޤ���
- ��ᥬ�ͤ�����ʤ��Ȥϡ�������ʪ�Τ�ڤ˸��뤳�ȤǤ���
- �㤨�п�ʹ���ɤ�Ȥ�����������ʤɤ�ѻ�����Ȥ������פʤɤ���̩���ʤ�Ĵ����Ȥ˻Ȥ��ݤ˽�������ġ���Ǥ���
- ���ξ������ڤˤʤ���ǽ�ϡ���Ψ�������Ȥʤ�ޤ���
- ��Ψ���⤤�롼�ڤϡ�������Υ��û��������Ȥʤ뤿����¤��礭�ʤ�Τ��뤳�Ȥ�����ǡ����η�̡���������ʤ�ʸ�����Τ�ʪ�Τ����Τ�Ȥ館��Τˤ��ϫ���Ƥ��ޤ��ޤ���
- �礭�ʻ���������ϤȤƤ�Ȥ��䤹����ΤǤ���
- ��λ��äƤ���롼�ڡʱ��̿���3����ˤΤ����ǰ��ֱ��Τ�Τ�����Ū����ᥬ�ͤȤ�Ф���Τǡ����Ū�㤤��Ψ��¿���λ����Τ˻Ȥ��ޤ���
- ������Υ롼�ڤϡ�x10�γ���Ψ����������ѤǤ���
- ����¤��������Τǹ�������뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ���ֺ��Υ롼�ڤϡ����С��֡ˤ�դ��ޤˤ����褦�ʤ�Τǡ����Фα��̤������̤ˤʤ�ޤ���
- ���äƴ��ξ�ˤ��Υ롼�ڤ��������֤��д��ξ���֤��줿����ˤ����Τ����礷�Ƹ����ޤ���
- ��Ψ��x10�ܤǤ��Фα�ޤ��ɹ��ʻ������äƤ��ޤ���
- �����������ȸ���Τ����ʤ��������Ǥ���
- ��
- �����ᥬ�͡�a pair of glasses�ˡ� ��2006.07.09�ɵ���
- �ᥬ�ͤϡ���롢��롢���ʤɤξ㳲����ä��ͤδ�����Ϥ�ڤ������������Ǥ���
- ���Ū�ˤߤơ����إ��饹��ȯã�����طʤ��縵�˥ᥬ�ͤμ��פ����ä����Ȥϵ����Τʤ����¤Ǥ���
- ���ߤ�40����ʾ�οͤ�Ⱦʬ�ϥᥬ�ͤΤ����äˤʤäƤ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
- 60�Ͱʾ�ϤۤȤ�ɤǤ��礦����20�Ͱʾ�Ǥ�3��ʾ夬�����Ȥ�ᥬ�ͤʤɤǶ����Ƥ���Ȼפ��ޤ���
- �������Ƹ���ȡ����ܿͤ�4�����ᥬ�͡ʵڤӥ����ȥ�ˤ��Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- 4000�����åȤ���ͭ���ס������3ǯ��5ǯ���㤤��������פϤ��ʤ�Υޡ����åȤȸ�����Ǥ��礦��
- �伫�Ȥ�ǯ��Ťͤ�ˤĤ�ƥᥬ�ͤΤ����äˤʤä���ޤ�����
- ���ع��ޤǤϻ�λ��ϤϤ����֤��ɤ������ǻ���1.5��Ĵ�Ҥ��ɤ��Ȥ��ˤ�2.0�������Ƥ��ޤ�����
- �ļ˰���ǻ��ǰ�ä���������Τ�Τ����褬���ʤ��ä�����Ȼפ��ޤ���
- ��ؤˤʤ�ȡ����˸����ä��ܤ��ɤळ�Ȥ䡢��Τ���Ȥ�¿���ʤä������⤢�ꡢ���Ϥ��ɤ�ɤ�����Ƥ��äơ��3ǯ�κ��ˤϻ��Ϥ�0.8���٤ޤ�����Ƥ��ޤ��ޤ�����
- ���ä����Ȥ˱��λ��Ϥ�0.8�ʤΤ˺��λ��Ϥ���ü�˰����ʤ�0.1�ˤʤäƤ��ޤ��ޤ�����
- ����˲ä�����λ������ȷ3�Ĥˤ�4�Ĥˤ⸫����Ȥ������äƤ��ޤ��ޤ�����
- ���θ塢ǯ��Ťͤ�45���������꤫�顢��Τ�Τ�Τ��ɤ��ʤꡢ���Ǥϱ��ξ�ѤΥᥬ�ͤ����ؤ��Ƥ����������餯�ʤ�Ȥ������֤ˤʤäƤ��ޤ�����
- �㤤����ˡ���Ϸ�οͤ�����ۤ������δ���ꡢ��ʪ�ʤɤ�ˤ��������ɤ�Ǥ���Τ⤷�������������Ƥ�����ʬ�������ޤ��ˤ���ǯ�ˤʤäơ�Ϸ���οͤ����ε��������狼��褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ͤδ��°���ϡ����ȸ��ε�Ͽ��-���ҥȤ��ܡ�http://www.anfoworld.com/Lights.html#humanseye���Ȥ��Ʋ�������
- ��
- ��
- ��

- ��
- ��
- �ᥬ�ͤˤ����Ϥζ����ϡ�����Ĵ���������������� ����Ĥ��ᥤ��Ǥ���
- �Ĥޤꡢ��롢��롢���ζ������ᥬ�ͤμ��Ư���ȸ����ޤ���
- �ᥬ�ͤ��礭������٤ƴ�����̤��礭����7mm���٤Ǥ���Τǡ��ᥬ�ͤμͽ�Ʒ�Ͼ������ʤ�F �ʥ�С��ʸ�����ˤ��礭�ʥ�Ȥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ºݤˡ��ͤϥᥬ�ͤΰ������̤��Ƥ�����������뤷�ʤ��Τǡ���λ��äƤ�����̼����䥳������̵�뤷�Ƥ⤵�����礭�ʻپ�Ϥʤ������������礭�ʱƶ���Ϳ���ޤ���
- ���äơ��ᥬ���ѤΥ�ϡ���夬��ž�ʲ����ˤ��Ƥ���������������ʤ��褦�ʹ�θ��Ф褤���Ȥ��狼��ޤ���
- �Ĥޤ������Ѷʤ��������� ���ᥬ�ͥ�������ι�θ���٤������Ȥʤ�ޤ���
- ����ϼ̿������٤�������礭��������Ǥ���
- ��
- .
- �ᥬ�ͤ�1��Υ��饹��Ǻ���ޤ���
- �̿���ǤϤ��Τ褦�ʷ����ϤǤ��ޤ���
- �ᥬ�ͤϴ�夬ư���ƹ����ϰϤС�����ط��塢����礭����ľ��60mm���٤ǥ�˥����������Ƥ��ޤ���
- ����ѤΥ�ϱ��̤������������ѤǤ����̤Ȥʤ�ޤ���
- ����ˡ��������뤬����ȥȡ���å��̡ʥȥ��������ˤ��ä��ޤ���
- ��ǯ���α��ξ�ѥ�Ǥϡ����äƤϥᥬ�ͤ���Ⱦʬ�Ȳ�Ⱦʬ����Ĥ�ʬ�����ơ�����Ѥȱ���ѤΥ���Ȥ߹�蘆�ä��Х�ե��������Ǥ�����
- ����ϡ��ᥬ�ͤο������ʿ�˥��ʬ���붭�ܤ����äƤ����Ǥ���
- ���Υ�ϸ��Ƥ��줬��������ˡ��Ƕ�Ǥ϶��ܤ�̵�����ƽ������Ѳ�����������߿ʶ����ϥ�ˤ���ή�ˤʤäƤ��ޤ���
- ʣ���ʥ�����ϡ��ץ饹���å����������Ѥ����夷������˿�¿�������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���β��äˤ�äơ���Τ褦��ʣ���ʴ�ʺ����λ��Ϥ��ۤʤꡢ��뤬���äơ����ȱ����碌���ä���ˤ����Ǥ������뤳�Ȥ���ǽ�ˤʤ�ޤ�����
- .
- �ᥬ�ͤϡ����������濴���Ȥ��Ƶ��̾��������Ӥޤ���
- ���̤��Ѷʤ��Ƥ��Ƥ��Ƥ⡢�������̤ΰ����������Ѥ��Ƥ��ʤ��Τ�����Ϥ���ޤ���
- ��夬�������ƹ����ϰϤ뤿��ˤϡ����ϵդ˲����濴�˱�ä��Ѷʤ��Ƥ��������Թ礬�ɤ��ΤǤ���
- �����ξ�礽�����̤�ʿ�̤ˤʤäƤ��ʤ���Фʤ�ʤ��Τǡ��ᥬ�ͤ���Ȥ��ƻȤ����濴���˥ե����������碌�Ƥ���������ܤ䤱�Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��äȤ⡢����ѤΥᥬ�ͥ�ϱ���ʤΤǼ����η������ѤϤʤ�������Ȥ��Ƥϻ��ѤǤ��ޤ���
- �ᥬ�ͥ�Ǥϡ���οޤ˼������褦�ˡ����β����濴R���濴�Ȥ������̤����̡�FPS�ˤ��뤳�Ȥ����ۤǤ���
- �ʶ���ѥ�Ǥϡ����������̤���ޤ�����
- ���̾������ۤ����뤹�뤫���ᥬ�ͥ���߷�ν��פʥݥ���ȤȤʤ�ޤ���
- ���ꤷ�����̾������̤������С���夬��ž���ƹ�������Ƥ�����˳ڤ�����������뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ��������ե�����ѥ��Single Lens Reflex Camera Lenses�ˡ�����2006.07.16���ˡ�2006.09.20�ɵ���
- ����ե�å��������ϡ����ޤ˼����褦��35mm�ҤΥե�����Ȥä��饤���������ʥ����������24mmx36mm�ˤΥ����ǡ�������ĺ�������֤����ڥץꥺ��ȥ����ߥ顼��𤷤ƥ�������������ľ�ܻ�ǧ�Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ�����
- ���ε����ˤ�äơ��ե����˼̤����ι��ޤ�ե�����������ñ�ˤ��ĥ��ԡ��ǥ��˹Ԥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Υ����Ϸ������������ɤ�����⼫ͳ�˻Ȥ��뤳�Ȥ���1950ǯ����2000ǯ�ޤǤ�50ǯ�֡��̿��������ǤϤ�äȤ�ʤ�������Ȥ��Ƥ����ϰ̤���ݤ�����ޤ�����
- �ǥ����륫���Ȥʤä����ߤǤ����ե�å��������Ͻ�ʬ�ˤ���ǽ�Ϥ�ȯ�����Ƥ��ޤ���
- �̿������ϡ�����ե����������Ȥ����Ȥ����Ǥ�ʤ�������ե���餬��������ˤϡ�Ʊ���饤���������Υ�ե�����������Υ���餬����ޤ��������֥����ˡ��ե�����Ȥä���㼰�Υ����⤢��ޤ�����
- ͭ̾�ʥ饤���ϡ�����ե����ǤϤʤ���ե���������������Ǥ�����
- �ޤ����饤���������Υ���餬�Ǥ�������ˤϡ������Ⱦ��Υե�����Ȥä���Ƚ���ܥå�������餬��ή�Ǥ�����
- ���ߤϡ�135�����פ�35mm�ҥե���ശ������夨��CCD��CMOS �ʤɤθ��λ����ǻҤ��Ȥ߹������Τ���ή�ˤʤäƤ��Ƥ��ޤ���
- ��
- ��

- ��������ե�������ħ
- ����ե�����ѥ�ʥե�����ѡˤ���ħ��ʲ��˼����ޤ���
- ��
- ������(1)�������ѤΥ��ľ�ܻȤäơʥ�ե�å����ե�����������̤��ơˡ�����Τβ�Ѥ�ԥ��Ĵ����Ԥ���
- ������(2)��24mm x 36mm�Υ��������������礹���Ǥ��롣
- ������(3)����ȥե����δ֤˥ե���������Ѥ�ķ�;夲���ߥ顼�����뤿��ˡ�
- ���������� �ե�Хå��ʥ�μ����̤���ե�����̤ޤǤε�Υ�ˤ�47mm����
- �����������ʥ˥���F �ޥ���ȤΥե�Хå���46.5mm�˳��ݤ��Ƥ��롣
- ����������������f20mm�ʤɤι��ѥ�Ǥ�ե�Хå���47mm���٤�Ĺ����Υ�����ݤ���롣
- ������(4)�������æ���Х�ͥåȥޥ���ȤǤ��뤿�����ưס�
- ������(5)���ץ����饢�ޤޤ�¿���Υ桼���������Τǥ����ȥѥե����ޥκǤ��ɤ���Ȥʤä���
- ������(6)���������Υ��f18mm����f400mm�ޤǽ������ढ�롣
- ������(7)���������μ��פȵ��Ѥν��Ѥʤɤǹ����ǰ²��ʥ��������лϤ�Ƥ��롣
- ��
- ���Υ����ˤϥץ����饢�ޥ��奢�ޤ��������ˡ����˱��������ᡢ��������μ���Υ�䥹�ȥ��ܤʤɤΥ�����������������ޤ�����
- ��
- ��
- �����ǥ��������ե����
- ��
- ����Kodak DCS
- ������(1)�������ѤΥ��ľ�ܻȤäơʥ�ե�å����ե�����������̤��ơˡ�����Τβ�Ѥ�ԥ��Ĵ����Ԥ���
- .
 2000ǯ��ꡢ��Ͽ���Τ�ե���फ����λ����ǻҤ��夨���ǥ����륫��餬����Ū�ˤʤä���ޤ�����
2000ǯ��ꡢ��Ͽ���Τ�ե���फ����λ����ǻҤ��夨���ǥ����륫��餬����Ū�ˤʤä���ޤ�����- �ץ��ե��å���ʥ��ѥǥ����륫���λϤޤ�ϡ�1991ǯ���ƹ�Kodak�Ҥ���ȯ����DCS100��Digital Camera System�ˤ��ǽ���ȵ������Ƥ��ޤ��ʿ��������ȡˡ�
- ������Kodak�Ҥ�¾�Ҥ������ȼ����緿CCD�ǻҤ��äƤ����Τǡ������ǻҡ�1.3�ᥬ�ԥ�����ˤ��¸��Nikon����ե�����Nikon F3�ˤ��Ȥ߹�������䤷�ޤ�����
- CCD�ǻҤϡ�1024���ǣ�1280���ǡ��ǻҥ�����16.4mm��20.5mm�ˤǡ��Żҥ���å���ǽ������ʤ���Τ��ä��Τǡ������Υե�������ץ졼��å���Ϫ�Ф�ԤäƤ��ޤ�����
- ���λ��˻Ȥ��Ƥ��������ǻҥ������ϡ��饤����������꾮�����ä�����ˡ�������Υf28mm�Υ��ɸ���ȤʤäƤ��ޤ�����
- ������������ʻ����̤��礭���ˤ�ɸ���ξ�����Υ���Ѥ����ͳ��ʲ��οޤ˼����ޤ�����
- f28mm�ξ�����Υ����ĥ�ϡ��饤���������ǤϹ��ѥ�����������ޤ���
 �饤���������ι��ѥ�ˤ����뤤����ʤ���������F2.8���٤��Ǥ����뤤��Τǡ�ɸ����f50mmF1.4����٤�4�ܤ�Ť���ΤǤ�����
�饤���������ι��ѥ�ˤ����뤤����ʤ���������F2.8���٤��Ǥ����뤤��Τǡ�ɸ����f50mmF1.4����٤�4�ܤ�Ť���ΤǤ�����- �ޤ������Υ����ϡ�SCSI�Υ����ե������ǡ����������Хå��Υѥ���ץ饤���ȥǡ������ʺ��ޤ��Ÿ��ڤӥ�����ˤ���³����Ƥ��ơ����Ƥ��������ǡ�������¸���뤳�Ȥ��Ǥ����������¸���������ǡ�����ѥ���������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- kodak�Ҥ�DCD����٤�뤳��11ǯ���2002ǯ9��ˡ�����Υ�饤���������ʥե륵�����ˤΥǥ����륫��顡����Υ�EOS-1Ds��ȯɽ����ޤ�����
- ���Υ����ˤϡ�24mmx36mm�Ȥ����礭��CMOS�����ǻҤ��Ȥ�졢4,064x2,704���ǡ�2004ǯ�����Ǥ�4,492���ǣ�3,328���ǡˤ���äƤ��ޤ�����
- �����ǻҤ�饤���������ˤ��뤳�Ȥˤ�ꡢ��������������ե���ॵ������Ʊ���ˤʤ뤿�ᡢ����Υե���५����Ʊ�������Ǻ��ʤ�����Ǥ�����åȤ��ФƤ��ޤ���
- ����ϥץ������ޥ�ˤȤäƤϤȤƤ�̥��Ū����ǽ�Ǥ�����
- ��

- �����ե���५���ο���
- 2006ǯ2��˥���å��ʥ˥塼��������ޤ�����
- �˥��ե�������ե����Ծ줫��ű�ह�뤳�Ȥ�ɽ�������ΤǤ���
- �ե���५����2����Ĥ��Ƥ��٤���������ߤ���Ȥ�����ΤǤ���
- ����Ʊ�������ƥ��˥����ߥΥ륿��ե������Ȥ���ű�ह��ȯɽ��Ԥ��ޤ�����
- �ʥ��˥����ߥΥ륿�Ϥ��λ�������ˡ�����Ѥ��ޤ�����
- �ե���५���Ϥɤ�ɤ�Ծ��̵�����Ƥ��ޤ���
- �桹��������¬��������Τϡ��²���ͥ���ʰ���ե������̵���ʤäƤ��ޤ����ȤǤ���
- ������ǯ���ޥ˥奢��ե��������Υ����¤����ߤ���ơ�Ai Nikkor f105mmF1.8s��Ai Nikkor f35mmF2s��Ai Nikkor f85mmF1.4S�ʤɡˡ������ȥե��������ѤΥ�������եȤ��Ƥ�����֤ˤʤäƤ��ޤ���
- �����ȥե��������ѤΥ�ϡ���ư�ˤ��ե���������碌�����Ť餤�ΤǤ���
- ��Τ褦�˴�¸�ΰ²�����ǽ���ɤ����ȤäƤ��⤷�������طϤ����ΤˤȤäơ����ξ���Ͽɤ���ΤǤ���
- 2006ǯ8��Υǥ����륫���ȳ��ϡ����˥����ߥΥ륿�Υǥ����륫������������������ˡ���α������Υǥ��������ե����ǹ�����������Υ�˼����ǥ�����2�̤������Ȥ����˥塼��������ޤ�����
- 3�̤ϥ˥���ǡ���ǯ�ޤǤϥ���Υ�ȥ˥����8��Υ���������äƤ����ȳ��Ͽޤ��礭���ɤ��ؤ����ޤ�����
- ��ϥ��ˡ���α������Υǥ����륫����褯�Τ�ޤ���
- ���ˡ��Υ֥��ɥХ�塼�ȶ��Ǥ�����롼�ȤǥߥΥ륿α������θ�Ѥ�쵤�˲����夲���褦�ʵ������Ƥ��ޤ���
- ���Υ�ϥߥΥ륿�Υ���Ȼפ��ޤ���
- ��
- ��
- �Ƕ�Υǥ��������ե����Υ�Ƥߤ�ȡ���������������饤���������ʥե륵�����ˤ�꾮��������ˡ����ѥ��Ȥˤ������ѤΥ����������Ϥ���Ƥ��ޤ���
- �����Υ�ϤۤȤ�ɤ���������f18mm��f200mm�ˤǤ����ޤ������Υ��F3.5���٤ȰŤ����桹�η�¬ʬ��Ǥ�����Ⱦü����ʪ�Ǥ���
- ����饺�����γ�ȯ�ϡ����������ѤΥǥ�����λ��Ѥ����Ū�Ȥ��Ƥ��ơ�1�ܤΥ�ǻ����ϰϤ�ͳ���Ѥ����륺�����μ��פ�ȿ�Ǥ�����Τ��������ޤ���
- �伫�ȥ������ˤ��ɤ��פ��Ф����ʤ���������������¬�Ѥ˻Ȥ����Ȥˤ���餤��Ф��ޤ���
- �����ǽ���ɤ�ɤ���夷�Ƥ���Ȥ������¤�ǧ��ʤ��櫓�ǤϤ���ޤ����������������ơ�
- �Ƕ�Υǥ��������ե����Υ�Ƥߤ�ȡ���������������饤���������ʥե륵�����ˤ�꾮��������ˡ����ѥ��Ȥˤ������ѤΥ����������Ϥ���Ƥ��ޤ���
- ������Ť���
- ��ñ���������٤��ڤ�̣�������Ⱝ����
- ���������Ĥߤ�������ˤ�ä�ʣ�����Ѳ����롢
- ����¬�ѤǤ����֤ǻȤ����Ȥ�¿�������������Ѳ��ͤϰ�����Ū���⤯�ʤ���
- �ʤɤ���ͳ�ǡ����ʤ�ñ����������Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ��
- �����ե륵���������ǻ�
 ����ե����Ȥ����С��ɥ��ĤΥ饤�ļҤ����Ѥ���24mmx36mm�Υ�����������ʥ饤���������ˤ����ڤʵ��ʤǤ�����
����ե����Ȥ����С��ɥ��ĤΥ饤�ļҤ����Ѥ���24mmx36mm�Υ�����������ʥ饤���������ˤ����ڤʵ��ʤǤ�����- ���Υե���ॵ�����Ǥ��٤ƤΥե���ॢ������������줵�����ޤ�����
- �饤���������ϡ��ɥ��ĥ饤�ļҤ��������ӥե���५���ʥ饤���ˤ��ä��Ȥ���1913ǯ�ˡ���餬���Ѥ����ե���ॵ�����Ǥ�����
- �Dz��ѥե�����35mm�ե����ҡˤ���Ѥ��Ƴ�ȯ�ԡ������������Х�ʥå���ξ���Ȥ���Ĺ�����ڤäƥ����˵ͤ���ߤޤ�����
- �Dz�Υ������������18mmx24mm���ä��Τǡ�24mm��ĶҤȤ���Ʊ����Ψ�ˤʤ�褦�˲�����36mm�Ȥ��ޤ�����
- ���줬�饤���������ȸƤФ���ΤǤ���
- �Х�ʥå��ΰ�ҡʤҤȤҤ��ˤ�Ĺ�����ڤ�줿�ե�����36��λ��Ƥ��Ǥ��ޤ�����
- �饤���������Υ����ϡ���ե�������������������������ˤʤꡢ���ޥ��奢����ץ��˻��ޤǤ����äƻȤ������ޤ�����
- ��
- ��������λ����ǻ�
- ����ե���餬�ե���फ��ǥ�����˰ܹԤ��Ƥ��ä��Ȥ��������ǻҤ��礭���˥饤������������ä���ΤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ����ʤ��礭��CCD�ǻҤ��뵻�Ѥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- ������1991ǯ�ˤϡ������å�����ȯ����1024���ǣ�1280���ǡ��ǻҥ�����16.4mm��20.5mm�ˤ��ǹ�Τ�ΤǤ�����
- ����Ǥ⤽��������˹���ǡ�������Kodak DCS�ˤβ��ʤ�150���ߤۤɤ��Ƥ��ޤ�����
- ���Υ����ϲ���������������������ˡ�ɸ���ѤΥ��f28mm�Ȥʤꡢ�饤���������ǤϹ��ѥ�����������ΤǤ���
- ���Τ褦�ʥ�ϡ����뤯���ڤ���ɤ���Τ����ʤ����������˶�ϫ�������Ȥ�Ф��Ƥ��ޤ���
- .
- 2006ǯ���ߤΥ˥���Υǥ��������ե����ϡ�5����ȯ�䤵��Ƥ��ޤ����������������Ϥ��٤�23.6mmx15.8mm��0.2��0.3mm���٤ΥХ�ĥ��Ϥ���ˤˤʤäƤ��ޤ���
- �����Υǥ����륫���ϥ饤���������ʥե륵�����ˤλ����ǻҤ���äƤ��ޤ���
- ���Ϥ����APS�������ȸƤ�Ǥ���褦�Ǥ�����APS�������Ϥ���äȰ㤤�ޤ���
- APS�������ϡ��ե���ॵ������1�Ĥ�1995ǯ�˵��ʲ�����ޤ�����
- Advanced Photo System��ά�Ǥ���
- �ե���ब�����ˤʤä��Τǥե����Ҥ�35mm����24mm�Ҥ˾��������ƥ�����ޤ�����ƥ�ξ������������ޤ�����
- ���������ǥ����벽�αƶ��⤢�äƤ��ޤ���ڤ��ޤ���Ǥ�����
- �������������16.7mmx30.7mm�ȤʤäƤ��ơ��˥���Υǥ����뻣���ǻҤ���٤��礭������Υ��Ƥ��ޤ���
- ��
- ��������Υ��CMOS�ǻ�
- �ե륵���������ǻҤϡ��饤����������Ʊ�����������������ä���Τ�24mmx36mm���礭���Ǥ���
- �ȤƤ��礭�ʻ����ǻҤǤ���
- �ե륵��������Ѥ����ǥ��������դϡ�����Τ�¤ꥭ��Υ��EOS-1D��������ޤ����2006ǯ���ߤϡ�Canon EOS-5D�ˡ�
- ��¬�����Ǥϡ�Redlake�Ҥ�Megaplus�� 24mm x 36mm �ե륵������CCD�����ǻҤ�Ȥä��Ż���ѡ��Żҥ���å���¢��12�ӥå�110�����ǤΥ���餬����ޤ���
- �Ż���Ѥ�110�����Ǥ�CCD������ʹ���������ǤȤƤĤ�ʤ��������Ϥ����������10W��20W�ˡ��Хåƥ��ư�ΰ���ե����ˤ�������Ѥ���ʤ������ǻҤǤ���
- ���äơ�����Υ�Ͼ������Ϥξ��ʤ�CMOS�Υե륵�����λ����ǻҤ���Ѥ����Τ��Ȼפ��ޤ���
- ���ʤߤ˥���Υ�Υǥ����륫���Ϥ��٤�CMOS�����Ǥ���
- .
- �ե륵�����λ����ǻҤϡ�����鸫����ɤΤ褦�ʥ��åȤ�����ΤǤ��礦����
- �ե���५���ǻ��ƤƤ����ץ������ޥ�ˤȤäơ��ե륵�����Υǥ����륫���ϡ�
- ����餬��ͭ���Ƥ���������³���Ȥ���
- ������饢��⥫����Ȳ�Ѥδط��⽾���Ʊ���ʤΤǤȤƤ�Ȥ��䤹����
- ���ե���फ��ǥ�����˰ܹԤ���ݤ˰��´������ʤ������ࡼ���˰ܹԤǤ���
- �Ȼפ��ޤ���
- �ʤ����������ѥ�Ǥϥե����ȸ��λ����ǻҤǤϼ��ո��̤��㲼������ˤʤ�ޤ�����
- �ե륵�������λ����ǻҤǤ�f50mm��ɸ���Ǥ���Τ��Ф���������������ξ������ǥ����륫���Ǥ�f28mm��ɸ���ѤȤʤꡢ�ܥ�̣���Ѥ�äƤ��ƻ��Ƥ��줿�����δ��Ф��ۤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ����˲ä����ǥ����륫���ǤϹ��ѥ�������ˤʤ������Ѹ��̤����ä����Ƥ����ʤ�ޤ���
- ��
 ����
����
- �������ѻ���Ǥλ���
- ���Υ����Ȥ����������ɤޤ�Ƥ������ϡ�����ä˼̿����ȯ����ˤϹ��Ѥ���ˤǤ��ä����Ȥ����줿�Ȼפ��ޤ���
- ���ѥ�ϸ����Τ��������뤤��������������Ǥ���
- �̿�����餫��ǥ����륫���ذܹԤ�����ˡ����������Ƭ��Ǻ�ޤ������Ѳ���Ȥ��ưʲ��ι��ܤ����ä��Ȼפ��ޤ���
- ��
- �����������ǻҤ��礭����-�������ǻҤ�ɤΤ��餤���礭���ˤ��뤫
- �����������礭���ǻҤ�Ȥ����������礭���ǻҤϹ���Ǥ��롣
- �����������������-���������Ϥ�Ǥ�������ޤ�������
- �������������ӻ��ѤǤϥХåƥ�μ�̿��̿��
- �����������礭�������ǻҤǤϾ������Ϥ��礭���ʤ롣
- ���������뤤��������-�����٤�夲�뤿��˼������ϤǤ������
- ��������������Ψ���礭����Τ�Ȥ�������
- �����������Żҥ���å���¤�ϼ������ʳ���Ψ�ˤ��������ʤ롣
- �����������ե�������ץ졼��å��Ȥζ��Ѥ��Żҥ���å���
- �����������������ʤ���
- ������ȯǮ��-��Ĺ����Ϫ�����硢ȯǮ���Ф�����θ��
- �������������ʤ���Фʤ�ʤ���
- �������������ʾ塢�Ż���������Ϻ��ѤǤ��ʤ���
- ����������Ĺ���֡�1/2�ðʾ��Ϫ���Ǥϡ�Ǯ�������ǻҤ�
- ����������������߲�����㲼���롣
- �������ե�Хå��γ�����-������դǤ��뤿�ᡢ
- ���������ߥ顼��ķ�;夲�륹�ڡ�������ݤ��ʤ���Фʤ�ʤ���
- �����������ե�Хå��ε�Υ��45mm��50mm�Ȥ��ơ�
- ���������������ߥ顼��ķ�;夲�륹�ڡ�������ݤ��ʤ����
- �����������ʤ�ʤ���
- �������������ѥ���߷פ����ʤ롣
- �����������������θ����㲼���ʱ����ȡ�
- ���������������������ؼФᤫ�����äƤ�������ˤ����ơ��ե����
- �����������Ǥ����꤬���ʤ����������ǥ������ǻҤǤϸ����ˤ���
- �������������롣
- ����������������ͳ�ϡ����λ����ǻҤ���¤��Ф��������Ф��Ƹ�
- ����������Ψ�褯�ե��ȥ��������ɤ����ͤǤ��ʤ����Ȥ�ͳ�褹�롣
- �������������Ȥ��ơ���������������礭�����������γ��٤�
- �����������ˤ䤫�ʡ˥�����ѤΥǥ����륫����ʼ��ո�
- �����������̤�夲����ˤ��Ѥ��롣
- ��
- �������Ƹ���ȡ��ǥ����륫���ǤϹ��ѥ��ȯ���礭������ˤʤäƤ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ��������ϡ���¬�ѥ����ˤ����Ƥ�Ȥ��Ƥ�����λ����ǻҤ�����������ˡ������ϰϤǤλ��Ƥ�Ԥ����Ȥ���Ⱦ�����Υ��û�����Ȥ虜���������ɬ��Ū�˼��ո��̤��㲼������ˤʤ�ޤ���
- ���ո����㲼������ϡ�����Τˤ�COS4��§�����äƥե���५���Ǥ�Ʊ������������Ƥ��ޤ�����
- �����ǥ������ǻҤα��ܹ�¤
- �����������ǻҤ��礭����-�������ǻҤ�ɤΤ��餤���礭���ˤ��뤫
- �ǥ����륫���ǤϤ�����������˲ä��ơ������ǻҼ��Τ˼��ո��̤�������ˤ�����¤Ū���������äƤ��ޤ���
- �����ǻҤǤϡ����Ǥ�30%���٤������������ʤ�����꤬�ŻҲ�ϩ�ǰϤޤ�Ƥ��뤿��Фᤫ��������������������̤���ã���ʤ����꤬����ΤǤ���
- �������������Ȥ��ƽIJ���˰㤤��������ʲ����ޡˡ���ʿ�����μ������ȿ�ľ�����μ������Ǥϸ����㲼���ٹ礤���Ѥ�äƤ��ޤ���
- ��
 ����
����
- ��
 ��
��
- ��οޤϡ���¬��CCD�����ǻҤι�¤���Ƥ��ޤ���
- CCD�����ǻҡʥ����饤�ˤϡ������ǻҾ��ž���������֤���Ƥ��Ƽ����ʤ���Ƥ��ޤ��ʾ���ˡ�
- ��������1���Ǥ�Ⱦʬ���٤ǽ�Ĺ�ˤʤäƤ��ޤ���
- ž�����ȼ���ϡ��������ʥե��ȥ��������ɡˤ��⤯�ʤäƤ��ơ����������㤤���֤����֤���ޤ���
- ����1���Ǥ��屦�ޤΤ褦�˲��ǿ�ʬ�����Ӥä�����¤٤��ޤ���
- �������Ƹ���ȡ������ǻҤξ岼�����ϡ�ž�����ʼ���ˤ˼��⤵��뤳�Ȥʤ�����������ΤǾ岼�����μ������Ǥ�����Ϥ��䤹���ʤ�ޤ�������ʿ�����Ǥ�ž���������⤷�Ƽ������˹Ԥ��˽���������֥��å����Ƥ��ޤ��ޤ���
- �ޥ�����������֤����Ȥ��Ƥ�Фᤫ���������ե��ȥ������������˽��������뤳�ȤϺ���ˤʤ�ޤ��ʱ��ޡˡ�
- ���Τ褦����ͳ�ǡ����λ����ǻҡ��ä��Żҥ���å���ǽ�Τ���CCD�ǻҤǤϿ�ʿ���ո��̤��㲼�������꤬�����Ƥ��ޤ��ޤ���
- �ե륵����CCD�ǻҤ�Ȥä���¬�����Ǥϡ��ǻҤ˥ޥ�����������夷�Ƥ���ˤ⤫����餺���Фᤫ�����ͤ���������Ǥθ��̤��濴�����Ⱦʬ�ʲ�������Ƥ��ޤ����Ȥ��������������Ǥ��ޤ�����
- ��¬�����ϡ��㤨�й����٤αվ����ʤ���¤�����DZվ������ǻ�٥쥹�ݥ����빩���˹�����ϤΤ�Τ��Ȥ��ޤ���
- ���λ��˷�¬����������ˤʤ�Τ����ո��̤��㲼�Ǥ���
- ��������������褹�뤿��ˡ����������ˤ����������䤦�����˲ä�������礭�ʥ���������������ĥ��6x6��6x7�ʤɤ��緿������ѤΥ�ˤ�Ȥ����ȤǼ��ո����㲼���к���Ω�ƤƤ��ޤ�����������
- ��
- ���塢�ǥ����륫�����ͭ��������������褦�ʥ����ȯ����ƹԤ��Ȼפ��ޤ���
- ����������ϡ��ǥ������ǻ����ѡʤ�äȸ����Х�����������Ѥ��������ǻ����ѡˤȤʤ뤿�ᡢ���������¾�Υ�����ή�ѤǤ��ʤ��������äƤ��뤫�⤷��ޤ���
- ��
- ��
- ��
- �����ӥǥ�������ѥ��CCTV Lenses�ˡ�����2006.07.16�ɵ���
- ���塢�ǥ����륫�����ͭ��������������褦�ʥ����ȯ����ƹԤ��Ȼפ��ޤ���
- ���塼���ѤΥӥǥ����������夵��Ƥ����ϡ������˥�������ͽ�����դ����Ƥ��ƥ����ȥ���ڤ�Υ���ƻȤ����ȤϤǤ��ޤ����ƻ��ѤΥӥǥ��������¬�ѥ���顢��®�٥����ʤɤˤϡ�����Ū�ˡ�C�ץޥ���ȥ����פΥ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��ǽҤ٤�35mm�ե����Υե륵���������Υ����٤ƾ��֤�ʤΤ���Ĺ�Ǥ���
- ��
- ������������ǽ
- CCTV��Closed Circuit TeleVision�˥�ϡ����Ū�˸��ޤ��ȡ��ƥ�ӥ����β����Ϥ�525�ܡʲ��̤νĤ����������ˤǤ��ä����ᡢ����˸��礦������ɬ��ʬ�ʥ�Ƥ����Ф褤�Τǥե���५����ѥ����٤Ʋ�����ᤵ��뤳�Ȥ�����ޤ���Ǥ�����
- �ƻ륫���ʤɤ��ᤵ����ϡ��̤äƤ�����ɤ��Ȥ������٤Ǥ�����
- ������⡢���ʤ����֤δؿ�����Ǥ��ä��褦�Ǥ���
- 1980ǯ��ޤǤλ��ȥƥ�Ӹ���C�ޥ���ȥ�ϡ������ʤ�Ȥ��̤���ɤ��Ȥ�����ʪ�Ǥ�����
- �Dz��ѤΥ��35mm�饤���������ѥ��������٤�ȡ����ʤ��ʼ�����ʤ����äƤ��ޤ�����
- �̿�������Dz襫���˽������Ƥ�����Τ�CCTV�ѤΥ�������Ȥ��ȡ��Τ�����褦�˥ӥå��ꤷ�ޤ���
- ��������ޤ�ˤⰭ���ΤǤ���
- �褯��ޤ�����ʥ���Ȥ����Τ��ȡ��Ѥʴ�������⤷�ޤ���
- �����������ʤ�30,000�ߤ���50,000�ߤ�ʹ����Ǽ���⤷���桼����Ǽ�������ǻȤäƤ���Ȥ������������Ǥ��ޤ���
- �Dz��ѤΥ�������200���߰ʾ�⤷�ޤ���
- ��������CCTV�ѤΥ������ξ𤱤ʤ���ϡ��ե����������Ť����ȤǤ���
- �ե����������ƥԥ��Ĵ�����Ƥ�ԥ�Ȥ��礦�褦�ǹ��ʤ������Ȥ���äȤǥԥ�äȤ����ե����������褽���ʤΤ�ƨ���Ƥ��ޤ���
- �����ƥե����������碌�ƥ�������Ѥ��Ƥ����Ȥɤ�ɤ�ե����������ܥ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- �Dz��ѤΥ������Ǥϥ������ݤ˥ԥ�Ȥ������Ȥ����Τϸ�ˡ�٤Ǥ���
- ���Фˤ��äƤϤʤ�ʤ�����ǽ�Ǥ���
- �ʤ��ʤ�Dz軣�Ƥθ��̾奺���ॢ�åס������ơ�����Τ�ɤ�ɤ��礭���̤���������Ƥ�������ˡ�ˤϷ礫���ʤ�����Ǥ���
- �����ߥ���ˡ�Ǥϥ�������˥ԥ�Ȥ��Ϥ���ƤϤʤ�ʤ��ΤǤ���
- �������²��ʥ������ϥ����ष���Ȥ����ưפ˥ԥ�Ȥ�����ޤ���
- �¤ϡ������ߥ���˥ե����������Ѥ��ʤ�����߷פȤ����ΤϷ빽��ä����ǡ�����������߷ס���¤�����Ȥ��夬��Ȥ�������������Ƥ��ޤ���
- ����������̣�ǡ������ߥǥե�������������뤳�Ȥ�������Ȥ����������ƥХ�ե��������Ȥ�������Ƥ��ޤ���
- ���������ʤ��ޤ���������Υ���ѤΥ�뤷�������ΤǤ���
- ���Υ�ϡ���Ѥ��碌�������ˤˤϲ�Ѥ��Ѥ��ʤ��Ȥ���������Ū������Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �����������Υ���ڤ�̣�Ϥ��ޤ�˧������ΤǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ��
- �����Dz���C�ޥ���ȥ��
- ��ǯ�ۤ�����2005ǯ�����ˤˡ���®�٥�������Ѥ���Ƥ��뤪���ͤΤȤ����ؤ����⤷���Ȥ��������ͤ������ˤʥ��졼�������ޤ�����
- ���Τ����ͤϡ�20ǯ���®�ٻ��Ƥ˽�������16mm��®�٥���餫��Ƕ�Υǥ����륫���ޤǻȤ������줿���Ǥ�����
- ���Τ����ͤˡ��ǿ��Υǥ������®�٥�����Ǽ�������Υ�����30,000�����٤θ��������CCTV����դ����ޤ�����
 �����ͤ�20ǯ���˹��������˥�������Υ��ͥ˥å������Cine Nikkor��f25mmF1.4��f50mmF1.4��C�ޥ���ȡˡʱ��̿��ˤ����Ǥ�����
�����ͤ�20ǯ���˹��������˥�������Υ��ͥ˥å������Cine Nikkor��f25mmF1.4��f50mmF1.4��C�ޥ���ȡˡʱ��̿��ˤ����Ǥ�����- ��ϡ����Υ�ȿ�����Ǽ�ʤ���CCTV���Ȥä�Ʊ������ΤƤ������ޤ�β���˰㤤��س���Ȥ���ޤ�����
- ��⤽�β�����س���Ȥ��ޤ�����
- ���ͥ˥å������Ϥ������ڤ줬�ɤ��ä��ΤǤ���
- ���ͥ˥å�����ϡ�1995ǯ����������ߤ���C�ޥ����16mm�Dz��ѤΥ�Ǥ���
- ����80,000�ߤۤɤ��ޤ�����
- �˥���δط��Ԥ˸��碌��Ȥ��Υ�����ޤ�ʤ��߷פ��줿��Τǡ�40ǯ���ä��礭���ѹ���ʤ���¤��³����줿��Τ������Ǥ���
- �Ť���ʤΤ˰��ֿ������������ʤ�ͥ�줿��ǽ����äƤ��ޤ�����
- ���ߤϥ��ͥ˥å�����Ϥ���ޤ���
- C�ޥ���ȥ�ϻ��夬������ˤĤ�ơ�����Ū������ȼ��פ�����⤢�äƤ�¿�Ͳ��������������ʤδ֤��ʼ��ˤ��ʤ�ΥХ�ĥ������뤳�Ȥ��狼��ޤ�����
- ���ΥХ�ĥ�����ϡ��饤���������Υե���५����ʥ˥���Ȥ��ڥå����Ȥ������ѥ��Ȥ�����Υ�ˤ���ǤϤ���ޤ���
- ���η���̤��ơ���ϼ��Τ��Ȥ�ؤӤޤ�����
- ��C�ޥ���ȥ�ʤ�ʤ�Ǥ��ɤ��ʤɤ�������������ˤȤ����ͤ���ΤƤ褦��
- ���⤦����C�ޥ���ȥ���ڤ���ɤ���Τ�õ����������
- ���⤷�ʤ���о����⤯�ʤäƤ�������
- �Ȥ������ȤǤ�����
- C�ޥ���ȥ���äƤ������Ϥ�������ޤ���
- ������ǡ����ߡ��ʤ�Ȥ��Ȥ�������C�ޥ���ȥ�Ĥ������������٤ι�®�٥������¬�����˼�����˻�äƤ��ޤ���
- Ʊ�������ӤǤ�����ǽ���礭�ʰ㤤�����뤳�Ȥ�Ȥ��ä��θ���������Ǥ���
- �Ƕ�Υǥ����륫������Ƭ��ȼ�äơ�CCTV����������ή��˹�ä��ɤ�����äƤ���뤳�Ȥ����äƤ�ߤޤ���
- ��
- ��C�ޥ���ȥ���礭�ʥޡ����åȡ�
- C�ޥ���ȥ���Ȥ��Ƥ���ޡ����åȤϡ��ƻ륫����FA��Factory Automation��ʬ��Ǥ���
- ������ʬ��ϡ����λ����ǻҤ���Ѥ�������餬����ǽ������ʤˤʤäƵ�®��ȯŸ���ޤ�����
- �����μ��פ굯�������ΤǤ���
- ���μ��פ�����٤������⤿�������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ʬ��ǻȤ����ϡ����������Υ��ʾ�����Υ6mm��50mm�ˤ�����Ū��¿�����������Ϥ���ۤ�¿������ޤ���
- ˾������ѥ���������פ�¿����f100mm�ʾ��˾���뤳�Ȥ�C�ޥ���ȥ�ǤϤۤȤ�ɤ���ޤ���
- ����������ˤϡ�ENG�������ѥӥǥ��˥����������ե�����˾����ή�Ѥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ƻ륫����ʬ��Ǥϡ��⡼������¢������ư������פ������Ƥ��ޤ���
- ��Υ�줿�꤫��������Ԥ�ɬ�塢��ư��������ʥѥ����Ȳ���ˤȰ��˻Ȥ��ޤ���
- FAʬ��Ǥϡ���¤��������ʪ�θ����˥���餬�Ȥ��ޤ�������餬�²��ˤʤäƲ����������Ѥ�ʤߡ��饤��ι�����˥��������֤�����¤�ʤη�١���٥븡���ʤɡ�ñ�쥻���Ǥϥ����å��Ǥ��ʤ��ս�����Ƥ��ޤ���
- ��������ʬ��Ǥ�ʪ�Τη�¬�������βĻ벽�ʤɤ�����Ū�ˤʤ뤿�ᡢ�ƥ쥻��ȥ�å������¿���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �������˼���դ�������ѥ��Ȥʥ������ή�ˤʤäƤ��Ƥ��ޤ���
- ������Ƚ������ѥ��Large Format Lenses��
- ��Ƚ������ѥ�ϡ��饤������������հʾ�Τ�Τ�����ޤ���
- 4x5�������Υܥå���������ѤΥ��������������ޤ���
- ���Υ�ϥ�����������뤬�礭��������Τ��礭���Τ���ħ�Ǥ���
- ����������ϡ����פ����ޤ�ʤ��Τǥ�μ��ब�¤��Ƥ��ޤ����Ȥȡ�����Ǥ��뤳�ȡ�����¤��Ť��Ȥ�����ħ����äƤ��ޤ���
- �����������μ�Υ�Ϥʤ�ȸ��äƤ⥤����������뤬�礭�����ڤ���ɤ����¿�����ᡢ�����ǥ�����ü컣����Ū�˻Ȥ����åȤϽ�ʬ�ˤ���ޤ���
- �����Υ�ϡ������å�����¢����Ƥ��ޤ���
- ��
- ��
- ��
- �̿������ѥ��
- ��
- ȾƳ����¤�ѥ����ե����
- ��
- �Ҷ�¬���ѥ��
- ��
- �����糰���Ultra Violet Lenses�� ������2006.02.26�ˡ�200609.10�ɵ���
 �Ŀ��ΰ����û��Ŧ��Ʃ��ǽ�Ϥ���ä�����糰��Ǥ���
�Ŀ��ΰ����û��Ŧ��Ʃ��ǽ�Ϥ���ä�����糰��Ǥ���- 200nm��400nm�Ǥλ糰���Ʃ��ǽ�Ϥ���äƤ��ޤ���
- �糰���Ʃ�����ĸ��غ����ϡ��бѡ��եò����륷�����CaF2�����Сˤ���Ĥ����ʤ��Τǡ����κ����ޤ��Ȥ߹�碌���������Ƥ��ޤ���
- �������ϡ��������ΤȤ����Ǥ�Ҥ٤��褦����Ĺ��û���ʤ�ˤĤ�ƶ���Ψ����ʤ�Τǡ������糰��Ĺ��Ǽ������뤳�Ȥ�����Ǥ���
- 200nm��400nm�λ糰�ΰ�ȡ�400nm��600nm�βĻ��ΰ�Ǥϸ��ζ��ޤ��ٹ礤���㤤�ޤ���
- ���äƻ糰��ǿ��������ɹ����ݤĤΤϻ���ζȤǤ���
- ���衢�糰��ϡ����ڥå�����Takumar�ʥ���ȥ饢�����ޥ��å������ޡ���f85mm��F4.5�ˤ����ܸ��ؤΥ˥å������UV Nikkor f105mm��F4.5�ˡʼ̿����ˤ������ʤȤ��������ǽ�Ǥ�����
- �����Υ�ϡ�220nm�λ糰����900nm���դ��ֳ��ޤǿ�����������Ƥ��ơ��糰�ΰ�Τߤʤ餺���ֳ��ΰ�ޤǤλ��Ƥ���ǽ�Ǥ�����
- ���Υ�ϡ���¤ʸ��δ��ꡢ���衦���Фθ����������¤ʤɤΰ�ؼ̿�ʬ���ʪ��ưʪ�����ִѻ��ʤɤ˻Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �������������ü�ʥ�ϼ��פ�����ۤ�¿������櫓�ǤϤʤ��ä�����ˡ�1970ǯ�溢����¤����ߤ��Ƥ��ޤ��ޤ�����
- 1990ǯ�����äơ��˥��Ƥ�UV�˥å��������Ϥ��ΤΡ�1996ǯ�ˤϤޤ��ޤ���¤����ߤ��Ƥ��ޤ��ޤ�����
- ���ߤǤϡ����ڥ˥���Ʊ��λ糰�����¤���䤷�Ƥ��ޤ���
- ��ǯ��FA��Factory Automation��ʬ��ˤ����ơ��糰�����ˤ�����ʸ������Ӹ�����Ӥ�褦�ˤʤꡢFA������ѥ�뤷�Ƥ���Pentax Cosmicar���顢C �ޥ�����Ѥ�UV������뤵���褦�ˤʤ�ޤ�����f25mmF2.8���ڤ�f78mmF3.8�ˡ�
- CCD �ǻҵڤӥ������äƤ���ƥ��������ĥ���ļҤ�CCTV �������1�����UV���f23.95mmF4.09�ˤ����䤷�Ƥ��ޤ���
- �ޤ����ʳ��˥�������CCTV�Ѥ�UV��Ȥ���f25mmF2.8�Υ�����䤵��Ƥ��ޤ���
- UV��ϡ��Ļ����ˤ�Ʃ����ǽ����äƤ��ޤ�����¿���Υ�Ͽ��������äƤ��ʤ�����ˡ������Υ����Ѥ���ˤ����äƤϥ�����̤�UV�ե��륿�����夹�뤳�Ȥ�����ȤʤäƤ��ޤ���
- ���Υե��륿�ˤ�ä�;ʬ����Ĺ�åȤ��ƥ��㡼�פ���������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- UV�˥å������ʸ����ڥ˥���UV-105mm F4.5�ˤϡ�220nm��900nm�ޤǿ��������ä����ݥ����ޡ��ȥ�Ǥ��ꡢ�Ļ���ǥե�������Ĵ���Ƥ�糰��Υԥ�Ȥ��礦��Ǥ���
- F4.5�ȰŤ���ǤϤ����ΤΡ�������碌�����ǤϻȤ�������ɤ���Ǥ���
- ��
- �ڻ糰����ȯ����
- �糰����ȯ���ϡ��ֳ�����ȯ�������٤�뤳��1ǯ��1801ǯ�˥ɥ��Ĥβ��ؼԥ�å�����Johann Wilhelm Ritter: 1776-1810�ˤˤ�äƤʤ���ޤ�����
- ��ϡ��ѹ��ŷʸ�ؼԥϡ��������Sir Willam Herschel��1738-1822�ˤ�ȯ�������ֳ������ɻ��ԤäƤ���Ȥ��ˡ��Ŀ��γ�¦�ˤ⡢�ͤδ�ˤϸ����ʤ�����ɱ����䤬ȿ������������뤳�Ȥ��ͤ��Ȥ�ΤǤ���
- ������������Ĺ�˰�¸���ƿ����Ѥ��Ȥ������ȤϤޤ����ΤˤʤäƤ��ޤ���Ǥ�����
- ��å������糰����ȯ������1801ǯ�˥����ꥹ�Υ��Thomas Young��1773-1829�ˤ����δ��ġ�����������ȯɽ���Ƥ��ޤ���
- �������äƤ��κ��Ϥޤ��˥塼�ȥ�θ���γ��������ή�Ǥ��ꡢ������Ĺ����������ΤǤϤʤ��ä��ΤǤ���
- ���λ���Ǥϡ��˥塼�ȥԤä��ץꥺ���ȤäƸ���ʬ�������Ļ���γ�¦�ˤⲿ�����ᤤ����Τ�����Ȥ���ȯ���ǽ�ʬ���ä��Τ��Ȼפ��ޤ���
- ����ǯ�ۤɤ��ơ����ʻҤ��ä��ɥ��Ŀͤο��ͥե饦��ۡ��ե��������۸���ʬ�Ϥ��ư��������뤳�Ȥ�ȯ�����ޤ�����
- ���줬�ե饦��ۡ��ե������ȸ������ΤǤ���
- 1814ǯ�Τ��ȤǤ�����
- ���λ��ˤϲ��ʻҤϤޤ���ǽ�������ä��Τǥץꥺ���ȤäƤ��ޤ�����
- �ե饦��ۡ��ե����ϡ����ΰ������ɤ����Ĺ�Ǥ���Τ���Ĵ�٤뤿��ˡ�1817ǯ�˲��ʻҤ�Ȥä����ꤷ�ޤ���
- ���κ��ˤϸ�����Ĺ�ȿ��δط�����ʬ��ǧ�Τ���Ƥ����Ȼפ��ޤ���
- �����ֳ����IR = Infra Red Lenses�� ����2006.07.21�ɵ���
- �ֳ���ϡ��Ļ�����ϰϳ��ˤ������ֳ����Ȥä������뤿��Υ�Ǥ���
- ���̤μ̿���Ǥ�900nm���٤ޤǤ��ֳ�����Ʃ�ᤷ�ޤ���
- ����ʾ��Ĺ����Ĺ���㤨��1um��10um�Ǥϸ��إ��饹���Τ�Τ�Ʃ���������ʤ�����ˡ����Ѥθ��غ�����Ȥ��ޤ���
- ���غ����Τ������äѤ���ĹƩ��������ʲ��˼����ޤ���
- ��
- �������եò����륷�����CaF2�ˡ���0.2um��7um������ʬ����˾���˻��ѡ�
- �������եò���������LiF�ˡ���0.12um��7um���ʥ����ƥ���Ȥ��ƻ��ѡ�
- �������եò��ޥ��ͥ������MgF2�ˡ���0.12um��7um���ʥ����ƥ���Ȥ��ƻ��ѡ�
- �������бѥ��饹��SiO2�ˡ���0.22um��2um�����ʵ��������ɹ���
- ���������ե�������Al2O3�ˡ���0.25um��3um�����ʵ��������ɹ���
- ���������ꥳ���Si�ˡ���1.5um��6.5um���ʵ���Ū�����ɹ����ⲹ���Ѥ��롢�ֳ������غ����Ȥ��ƻ��ѡ�
- ��������������ZnSe�ˡ���0.7um��15um�����ֳ������غ����Ȥ��ƻ��ѡ�
- ����������ޥ˥����Ge�ˡ���2um��20um�����ֳ������غ����Ȥ��ƻ��ѡ�
- �����������NaCl�ˡ���0.2um��21um�����ֳ�ʬ�����֤˻��ѡ�Ĭ�������ꡣ�Ȥ���
- ���������ಽ���ꥦ���KRS-5�ˡ���0.5um��40um�������ϤǤ��뤬���餫�����ֳ���������ɥ��ѡ�
- ���������������ꥦ���KRS-6�ˡ���0.4um��34um�������ϤǤ��뤬���餫�����ֳ���������ɥ��ѡ�
- �������������ꥦ���KBr�ˡ���16um��40um����ʬ���ץꥺ��Ȥ��ƻ��ѡ��ۼ��������
- �������������ꥦ���KCl�ˡ���15um��30um��ʬ���ץꥺ��Ȥ��ƻ��ѡ��ۼ��������
- �������ಽ���������CsI�ˡ���0.25um��70um�ʤ�äȤ�Ĺ��Ĺ�ޤ�Ʃ�ᡣX���ηָ��Ĥˤ����ѡ�
- ����
- �����θ��غ����Τʤ��ǡ����ꥳ���3um��5um�Ӱ���ֳ������ˡ�����ޥ˥����10um�Ӱ�Υ����ˤ�����Ѥ˻Ȥ��ޤ���
- �ֳ���ϡ��Ļ���Υ����λ��Ķ��ֳ���δ������������Ѥ�����Τȡ����ֳ���3-5um�Ӱ��Ǯ�������֡ʥ����ޥ륫���ˡ�����˱��ֳ���10um�Ӱ��Ǯ�������֡ʥ����ޥ륫���ˤ�ʬ�व��ޤ���
- Ǯ�������֤ϡ�ʪ�Τ������ͤ�����ֳ������Τ�Τ��Τ��Ʊ����������Τǡ��������֤�ɬ�פ���ޤ���
- �ŰǤǤ�Ǯ����äƤ���ʪ�ΤǤ�������Ȥ��ƲĻ벽���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �㤤���١��ݻ�20�١ˤǤ�Long Wave��10um�Ӱ�Υ����ޥ륫��餬ͭ���ǡ��ݻ�100�����٤ˤʤ�ޤ���Short Wave��3-5um�Ӱ�Υ����ޥ륫��餬ͭ���Ǥ���
- ������ͳ�ϡ��㤤���٤Ǥ϶��ֳ���θ����ͥ륮����¿�����ͤ��ʤ��ΤǰŤ�ʪ�ΤȤʤäƤ��ޤ�����Ǥ���
- ʪ�Τ��ݻ�400�����٤ˤʤ�ޤ��ȡ��Ļ�������ޤǤ��ֳ��������ͤ���褦�ˤʤ�ΤǴ��ؤ��ֳ�CCD�����DZ������Ǥ�褦�ˤʤ�ޤ���
- �ֳ���ϡ����äƶ��ֳ��ΰ��700nm��900nm�ˤǤ�����̾�βĻ��������Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����������ɽ�̤˥ޥ�������Ȥ�ܤ��Ƥ�����ˤϡ������ƥ��ˤ�ä��ֳ��ΰ褬���åȤ���Ƥ��ޤ��Τ����դ�ɬ�פǤ���
- ���ֳ��ΰ�Υ����ϡ�������λ����ǻҤ�ޤ�²�������Ǥ���Τǡ��ƻ륫���ˤ褯�Ȥ��ޤ���
- ��
- ��
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
- �������������Microscope lenses�� ����2006.03.04�ˡ�2006.07.03�ɵ���
- ��������Microscope�ˤϡ�������ʪ�Τ���礷�Ƹ��뤿��θ��شﳣ�Ǥ���
- ����Ū�ˡ��롼�ڤ�Ȥä�ǧ���Ǥ��ʤ�������ʪ�Τ����ѻ�����Τ˻Ȥ��ޤ���
- ���ߤμ�ή�θ������ϡ���ʪ���Objective lens�����ܴ���Eyepiece����2�ĤΥ����ݡ��ͥ�Ȥǹ������졢��ĤΥ��������礷�ޤ���
- ��ʪ��ϡ���Ψ��1/2�ܤ���250�ܤޤǤ��ꡢ���Υ�dz��礵�줿���Ϥ�����ܴ��dz��礵��ޤ���
- �ܴ�����Ψ�ϡ�10�ܤ�����Ū�Ǥ���
- ���äơ���ʪ����ܴ�����ĤΥ��Ȥä�������Ψ�ϡ�ξ�Ԥ��ѤǼ�����5�ܤ���2500�ܤȤʤ�ޤ���
- ���ظ���������Ψ�³��ϡ�����������Ĺ�Ǥ��ޤꡢ���ޤˤ�����Υܥ�����1000�ܤ��³��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ������Ψ�³��ϡ��ɥ��ġ��ĥ������ҤΥ���ȡ����å٤����Τˤ��ޤ�����
- �����ǽ�Ǥ�äȤ�����ˤʤ�Τϡ�������뤵��N.A. = Numerical Aperture���������ˤ�ʬ��ǽ�Ǥ���
- ���������Ǥ�������ϡ��դ��ĤΥ���Ȥ߹�碌��ȼ������Ҥɤ������ܤ��Ƥ��ޤä��Τ�ñ��Υ�ʾ����ʥܡ����ˤǺ���Ƥ��ޤ�����
- �������ܡ����Ǥϳ���˸³������뤿�ᡢ�����ʣ�縲��������ή�κ¤�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���θ������β���ȯŸ�ˡ��ɥ��Ĥ�Zeiss�����礤�˹����ޤ���
- �ʲ��˸������δ���Ū�ʹ������ޤ������ߤθ������ϡ���ʪ���ɸ�ܤ˶ᤤ���ʪ�Τ��Ф�����ˤ��ܴ��ʴ�˶ᤤ��������ԡ����ˤ��Ȥ߹�碌������Ū�Ǥ���

- ��θ������ϡ���ɽŪ�ʸ�������Ʃ��ޤǤ���
- ���θ���������ʪ�������ǡ�ɸ�ܤ˸���Ʃ�ᤵ���������Ǥ���
- �������ˤϤ��ä���Ȥ������줬���äơ����֤��濴�ˤ�ɸ�ܤ��֤�����Υ��ơ���������ޤ���
- ɸ�ܤ�Ǿ�Ⱦ���ˤ���ʪ���ܴ��θ��طϤ����ꡢ��Ⱦʬ�ˤϾ����������طϤ�����ޤ���
- ��ʪ��ϤȤ⤫���������طϤ�¿���Υ���Ȥ��Ƥ���Τ϶�̣����Ȥ����Ǥ���
- �������Ǥϡ��������طϤ����ڤ����ǤǤ��뤳�Ȥ����Τ��Ȥ�������Ǥ��ޤ���
- �������ξ������طϤȤ��Ƥϡ������顼������ͭ̾�Ǥ���
- ��˼������������ˤ⤳�ξ������طϤ����Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���ξ���ˡ�ϡ�����������ɸ�ܤ��Ф��Ƹ����Ψ�褯���Ƥ���ʪ��θ��¤��Ф��Ƥ��Ψ�褯����������ߡ��ʤ�����;ʬ�ʸ��åȤ��빩�פ��ʤ���Ƥ��ޤ���
- ������ϡ�ʿ�Ը�«��ɸ�ܤ���ư��Ƥ˽���Ǥ���褦�˽��������Ƥ��ޤ���
- ɸ�ܤ��Ф��Ʋ���������ʤ��Τǡʥ���ɥ�����ո��طϤΰ��ƥ쥻��ȥ�å��ʸ����Ǥ��뤿��ˡ�ɸ�ܤ����˥���ȥ饹���ɤ��ѻ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��

- ��
- ��
- ��οޤ����������δ���Ū�ʸ���Ū�쥤�����ȤǤ���
- ɸ��AB�� = ����Ρ��о�ʪ�ˤϡ���ʪ���Lo�ˤζ�ˤ�����ޤ���
- ��ʪ��ξ�����Υ��û���Τϡ�������Թ礬�ɤ��ΤȤ�������θ���뤳�Ȥ��Ǥ��뤫��Ǥ���
- ������Υ��Ĺ���ʤ�ȸ�������뤳�Ȥ����ʤ�ޤ���
- ��ʪ��ϡ�ɸ��AB��A'B'�˳��礷�ޤ���
- ���γ���Ψ����ʪ��˹������Ƥ���X20�ʤɤ���Ψ�Ȥʤ�ޤ���
- ��ʪ���Lo�ǤǤ�����A'B'����ܴ���Le��ȤäƳ��礷��A"B"�ε������ꡢ������Ǵѻ����ޤ���
- ��ʪ���Lo�ˤ�����γ���ΨMo�ϡ�
- ��οޤ����������δ���Ū�ʸ���Ū�쥤�����ȤǤ���
- ��
-
- ������Mo = A'B'/AB ����������Lens - 43��
- ��ɽ���졢
- �ܴ��γ���ΨMe�ϡ�
- ��
-
- ������Me = A"B"/A'B' ����������Lens - 44��
- ��ɽ����ޤ���
- �ǽ�Ū�ʸ������γ���ΨM�ϡ���ʪ��γ���ΨMo���ܴ��γ���ΨMe��ݤ���碌����Τˤʤꡢ
-
- ������M = Mo x Me = ��A'B'/AB�� x ��A"B"/A'B'�� = A"B"/AB ����������Lens - 45��
- �Ȥʤ�ޤ���
- ��
- ��ʪ��Υ����ü����ɸ�ܤޤǤε�Υ����ư��Υ�ʤ��ɤ�����ꡢWork Distance��W.D.�ˤȸ����ޤ���
- ��������Ǥϡ���ʪ��ξ�����Υ��û������ɤ����Ƥ��ư��Υ��û���ʤ�ޤ���
- Ʊ������Υ�ʤɤ����礦�Ƥ�ꡢParfocal Distance�ˤȤϡ���ʪ��μ���դ��̤���ɸ�ܤޤǤε�Υ������ޤ���
- Ʊ������Υ��Ʊ����ʪ���Ȥ��С��������Υ�����åȡʥ�ܥ�С�����ž�����դ������ˤ�ʣ������ʪ������դ��ƲƤ⤽�����٥ե�������Ĵ����Ԥ�ɬ�פ�����ޤ���
- ����Ĺ�ʤ��礦�Ȥ����礦��Mechanical Tube Length�ˤȤϸ��������Τ�����Ĺ��������ʪ�����դ��̤����ܴ�����Ȥ����������̤ޤǤε�Υ�Ȥʤ�ޤ���
- �������ν���Τ�Τϡ����ε�������Ĺ������줿��ʪ����Ȥ��Ƥ��ơ���A'B'�����������֤����褦�˷����Ƥ��ޤ�����
- �������ʤ��ȡ�����Ĺ�ΰۤʤä���ʪ����Ѥ���ȥե������������������ʤ��ä��ꡢ��Ψ��������ȿ�Ǥ���ʤ��ʤ�ޤ���
- ����Ĺ�ϡ�ͭ��������ʪ��ˤ����ƽ��פ����ǤȤʤ�ޤ���
- ͭ��������ʪ��Ȥϡ��������ν���κ�����ʪ��Ǿ�θ��إ쥤�����ȤǼ������Ȥ������ΤǤ���
- ��ʪ��ˤ�ä�A'B'�μ�����ͭ�µ�Υ�ˤǤ���ΤǤ����ƤФ�Ƥ��ޤ���
- ���������Ƕ�θ�������ϡ�̵�±�������ʪ��������Ƥ��ơ���ʪ��ζ����ˡ�∞�פΥޡ������Ĥ��Ƥ��ޤ���
- ���Υ����פΥ�ϡ��������ε�������Ĺ����ͳ�����֤��Ȥ��Ǥ���Τǡ���;������֤Ȥ��и��Ҥʤɤθ�����°�ʤ�ͳ���ɲä��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ̵��������ʪ��ϡ���A'B'��̵�±�˺��Τ���ʪ���ñ�ȤǤϷ����Ǥ��ޤ����Υ�����Ǥ��ܴ���A'B'������礷�Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ΤǤ���
- ���äơ�̵��������ʪ���Ȥ��������Ǥϡ���������˷������Tube Lens�ˤ��Ȥ߹��ޤ�Ƥ����ܴ���A'B'��������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���Τ��ᡢ̵��������ʪ�������������Ψ�ϡ�������ξ�����Υ���̣���Ƶ����Ƥ��ޤ���
- �ʲ��ˡ���ʪ����ܴ�����ǽ�ˤĤ��ƽҤ٤ޤ���
- ��
- ��
- ����ʪ���Objective lens�ˡ�
- ��
- ��ʪ��ϡ��������ǺǤ����ڤʸ������ǤǤ���
- �������Υ�ϡ��ͤޤ�Ȥ����̥�ΰ�ĤʤΤǤ��������Ѥ�����Ū����Ū�ʤ������͡��ʸ���Ū���ɤ��ܤ��츽�ߤΤ褦�ʷ��ˤʤ�ޤ�����
- ����������ʪ��ϡ����̻����ѤΥ�����Ȥϰۤʤä���ǽɽ�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��������ˤϹʤ��ʤ���Хե�������Ĵ���Τ���Υե���������⤢��ޤ���
- ��������ˤ��������ʵ��椬�������Ƥ��ޤ���
 ������ʪ��γ��Ѥ��ޤ���
������ʪ��γ��Ѥ��ޤ���- �ʲ�������ΰ�̣�μ̿��ͤ˸��Ƥ����ޤ��礦��
- ��
- ���֥���ɽ����
- ɽ���κǾ��ʤˤ���Τ�����������ʪ����äƤ�������ɽ���Ǥ���
- ����Ū�˸��Ƹ�������ʪ����äƤ������Ϥ���ۤ�¿������ޤ���
- ���ܤ�Nikon��OLYMPUS���ɥ��Ĥ�Zeiss��Leica����ʤȤ����ǡ���������ʬ��Ǥ����ܤ�Mitsutoyo����˥�����ؤ����ꡢ�������ʥ�����Ǥϡ�Edmund�ҡ����������Newport�Ҥʤɤ�����ޤ���
- ��
- �����������ʥץ�������ޡ��ȡ����ݥ����ޡ��ȡ��ե륪��ȡ�
- ���μ̿��������ܤ˹������Ƥ���ʸ���ϡ���ʪ��Υ��졼�ɤ�ɽ���ޤ���
- �ɤΤ��餤�θ����������ܤ���Ƥ��뤫���ܰ¤Ȥʤ�ޤ���
- ���μ̿��Ǥϡ�Plan Fluor��ɽ������Ƥ��ơ�����������Ѷʡ�Plan�ˤȵ��̼�������������Fluor�ˤ��褯��������Ƥ����Ȥ�����̣�ˤʤ�ޤ���
- Fluor�ϡ��������ΰ�̣�ǤϤʤ����Фΰ�̣�ǡ���ʬ�����غ�����ȤäƤ���Τǿ������������Ǥ��Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ���ι��ܤǤ�¾�˰ʲ��Τ褦�ʹ��������ޤ���
- ��Acro��Acromat����2��Ĺ�Ǥο������ʥ������ޥ��å��ˡ�
- ��Fluor��FI��Fluar��Neofluar��Fluotar�������Ф�Ȥä�����������
- ��Apo����3��Ĺ�Ǥο������ʥ��ݥ����ޥ��å��ˡ�
- ��Plan��PI��Acroplan, Plano���������Ѷ�������
- ��EF��Acroplan����Extended Field (field of view less than Plan�ˡ������̩�������Ѷ�������
- ��N��NPL����Normal field of view Plan���̾�������Ѷ�������
- ��Plan Apo����3��Ĺ�������������Ѷ�������
- ��UPLAN���������ѥ��Ҥ����������Ѷ�������Universal Plan�ˡ�
- ����Ψ/��������N.A.��
- ���μ̿��λ����ܤˤ�������ϡ��������κǤ��������ǽ�Ǥ�����Ψ�����뤵��ɽ���ޤ���
- 10x�Ȥ��������Ψ��10�ܤǤ��뤳�Ȥ�������å���ʲ��ο��ͤϳ��������Ƥ��ޤ���
- ��������sinθ�����ؿ��͡�θ�ϥ���ۤ��Ф�����«�γ��١�θ =<90°�ˤǤ��Τǡ����������Ǥ�����ϡ�1.0������Ȥʤ�������뤤��Ȥʤ�ޤ���
- ����������������Ǥϱտ��Ȥ�Ф����Τ���ǻȤ���Τ����ꡢ���ξ��γ������ϡ����Τζ���Ψ���⤤�Τ�1.0�ʾ�ˤʤ�ޤ���
- ��ʪ�����Ψ�ϡ�x1/2����x250�ޤdzƼ�Υ������Ƥ��ޤ���
- ������Ψ��ɽ���ܰ��Ȥ��ưʲ��˼�����ɽ���ʥ��顼�����ɡˤ⤢�ꡢ�����ǥ����Ψ���ǧ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- �������������ץ����
- ��Ψɽ���β��˰�������Ƥ���ɽ���ϡ����������Υ��ץ����ǥ���ɤΤ褦����Ū��Ŭ���Ƥ��뤫���Ƥ��ޤ���
- ������μ̿��Ǥϡ�DIC�Ȥ���ɽ��������Ƥ��ޤ���
- DIC�ϡ�Differential Interference Contrast��ά����ʬ���ĥ����פΥ�Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- DIC�μ��˹������Ƥ���ɽ��L�ˤĤ��Ƥϡ��ʲ��Ρ֢���ư��Υ�פν�ǿ���ޤ���
- ��CF��CFI����Chroma - Free��Chroma - Free Infinity-Corrected��
- �����������������˥���ҤΥ֥��ɤǡ��������ѤߤΥ�Ȥ�����̣�Ǥ���
- ����������������CFI�ϡ�̵�±�������ä�����������Ǥ���
- ���������������������ϡ���ʪ����ܴ�����������Ω������������
- �����������������ʤ���Ƥ��뤿��ߴ���������ޤ���
- ����������������Ʊ�ͤΤ�Τ˥ĥ�������ICS��Infinity Color - Corrected System�ˤ�����ޤ���
- ����������������CFI�ϡ�̵�±�������ä�����������Ǥ���
- ��DIC��NIC����Differential Interference Contrast��Nomarski Interference Contrast��
- ��������������������ʬ���ĸ������ΰ�̣�Ǥ���
- ��Oil��Oel����������ˤ��տ���ɽ���ޤ�����ʪ���ɸ�ܤδ֤�����������ޤ���
- ��Glycerin�������ꥻ���ˤ��տ���ɽ���ޤ�����ʪ���ɸ�ܤδ֤ꥻ�����������ޤ���
- ��Water��WI��Wasser������ˤ��տ���ɽ���ޤ�����ʪ���ɸ�ܤδ֤����������ޤ���
- ��HI����Homogeneous Immersion���Ѱ���Τˤ��տ���ɽ���ޤ���
- ��������������ʪ���ɸ�ܤδ֤�Ѱ���Τ��������ޤ���
- ��ͭ��������̵������������Ĺ = Mechanical Tube Length��
- ���ͼ̿��ΰ��ֲ����˼����줿�ͤϡ�����Ĺ���Ƥ��ޤ���
- ��∞�פ�̵�±������ʤΤǤ��Υ��̵��������Infinite Corrected�ˤ���ʪ��Ȥʤ�ޤ���
- ���Ū�ˤߤޤ��ȡ�ʣ������������ʪ����ܴ����Ȥ߹�碌�Υ�ˤ��Ǥ����Ȥ��ˡ���ʪ����ܴ��ε�Υ����ơʤĤޤ긲����������Ĺ�����ꤷ�ơˡ���ʪ����ܴ��κݤ������������Ǥ���褦�ˤ��ޤ�����
- ���줬������Ĺ���Ȥʤä�RMS��Royal Microscopical Society�ˤˤ�ä�160mm�Ȥ��Ƶ��ʤ���ޤ�����
- 160mm�ϡ�����Ū����Ĺ��Mechanical Tube Length�ˤȸƤФ�Ƥ����Τǡ���ʪ������դ����ܥ�С��̤����ܴ������դ������ξ��̤ޤǤ�����Ĺ����ɽ���ޤ���
- ���ߤǤ�Nikon��OLYMPUS��Zeiss��160mm����Ѥ���Leica��170mm����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- �ޤ���°�������ε�������Ĺ�ϡ�210mm����ή�Ǥ���
- ��ǯ�θ������ϡ������֤˥ӡ��ॹ�ץ�å������줿���и��Ҥ����줿�ꤹ��ɬ�פ��顢������Ĺ����������ФƤ��Ƥ��ޤ���
- ����������˱����뤿��˸��������̵��������∞�פˤ��뤳�Ȥˤ�ꡢ������Ĺ���ˤ��뤳�Ȥʤ������������ƥ���ۤ��뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ̵�������Υ������̵�±�˷�Ф��뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ�������Ĺ���ˤ��뤳�Ȥʤ��ɤΰ��֤��ܴ����֤��Ƥ���������Ψ���������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���äơ������������������ƥ�Ǥ�̵�������ˤ����ʪ�����ή�ȤʤäƤ��ޤ���
- �ʲ���ͭ��������̵�������θ������Υ����ƥ�ޤ��ޤ���
 ��
��
- ��
- ��οޤޤ��ȡ�̵�±������֡�פ���ʪ��Ǥϡ���ʪ��������֤�ɸ�ܤ��֤�������̵�±�˺�äƤ��ޤ���
- ���ϡ����äơ���������Ѥ��ƺ��ʤ��ƤϤʤ�ޤ���
- ̵��������ˤ�븲�����ϡ�������ɬ����������Ĥ��Ƥ��ޤ���
- ������ˤ�äƺ��줿��A'B'���ܴ��ǤΤ������������Ȥ��Ƹ��뤳�Ȥ�ͭ��������Ȥ����ޤ���
- ̵�±����������ʪ���Ȥ����Ȥˤ�ꡢ��ʪ��ȷ�����δ֤ε�Υ�˼�ͳ�٤�������뤳�Ȥ��Ǥ���������������������Ȥ��Τ���ޤΤ褦���Ѥ߽ŤͤƤ��������ʸ��طϤ��������뤳�Ȥ���ǽ�Ȥʤ�ޤ���
- ��
- �������饹�ץ졼�ȸ�������
- ��οޤޤ��ȡ�̵�±������֡�פ���ʪ��Ǥϡ���ʪ��������֤�ɸ�ܤ��֤�������̵�±�˺�äƤ��ޤ���
- ��∞����ȡ�/�פǶ��ڤ�줿���ο��͡�0.17�פϡ�ɸ�ܤ����륬�饹�ץ�ѥ顼�Ȥθ����λ����ͤǤ���
- ���ߤ�ɸ��Ū�ʥ��饹�ץ졼�Ȥθ�����0.17mm�Ǥ���
- ���饹�ץ졼�Ȥθ������Ѥ�äƤ������Ǥ�����ʪ��⤢�ꡢ����������ϡ������Ĥȸ����������ͤ���ޤ�Ƥ��ơ����Ѥ��륬�饹�ץ졼�Ȥθ����˱����������ĤåȤǤ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����ĤΤĤ�����ϡ��ʲ��ι�����ܤ���Ƥ��뤳�Ȥ�����ޤ���
-
- ��Corr��W-Corr��CR������������
- ����ư��Υ��Work Distance��
- �Dz��ʤ�∞/�α���ɽ������Ƥ���WD 16.0�ϡ���ư��Υ��ɽ���Ƥ��ޤ���
- WD��Work Distance��ά�ǡ�����16.0mm�Ϻ�ư��Υ���ͤ��Ƥ��ơ���ʪ�����ü��������ޤǤε�Υ��=��ư��Υ�ˤ�16.0mm�Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��ư��Υ��Ĺ����˴ؤ��Ƥϡ������������ץ������ʤα��˰ʲ��Τ褦��ɽ��������ޤ���
- ��μ̿��Ǥ�DIC�α���L�Ȥ���ɽ�������ꡢĹ��ư��Υ��Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��L��LL��LD��LWD����Ĺ��ư��Υ
- ��ELWD����Extra-Long Working Distance
- ��SLWD����Super-Long Working Distance
- ��ULWD����Ultra-Long Working Distance
- �����顼������
- ��ʪ�����ü���ˤ���Ψ�ȱտ����ѤǤ��뤫�ɤ����Υ��顼��ɽ��������ޤ����ʲ�������Ψ�δط����ޤ���
- x1/2�������ʤ�
- x1��x1.5������
- x2��x2.5������
- x4��x5������
- x10������
- x16��x20������
- x25��x32��������
- x40x50�����饤�ȥ֥롼
- x60��x63�������Х�ȥ֥롼
- x100x250������
- Oil�տ�������
- Glycerol�ʥ��ꥻ���˱տ����������
- Water�տ�������
- �ü�տ�������
- ��������դ��ͥ�
- �������μ���դ��ͥ��ˤĤ��Ƥϡ������Ư��������������ν�ǿ���ޤ�����
- ����դ��ͥ��ˤĤ��Ƥ�140ǯ�����θŤ����ʤ�RMS��Royal Microscopical Society�˥ͥ�������ޤ���
- ����¾��M25�ʥ�ȥ�å�25mm���¡ˡ�M32�ʥ�ȥ�å�32mm�ˤε��ʤ�����褦�Ǥ���
- ����դ��ͥ��˴ؤ��Ƥϡ���ˤ��ä�ɽ��������ޤ���
- Ʊ�������Τ�Τ�Ȥ�������ʤ����ѤǤ���ΤǤ�����ɽ���Ϥ���Ƥʤ��Τ����Τ�ޤ���
- Nikon��OLYMPUS�Ǥϥͥ��¤��㤤�ޤ���
- �����Ѹ��������äƤ��������ϡ��ߴ�����������褦�Ȥ��ơ��Ť����ʤ�RMS�ͥ���ȤäƤ��ޤ���
- ��
- ��
- ���ܴ���Eyepiece��Ocular�ˡۡ���2006.09.04���ˡ�2006.11.01�ɵ���
- ��
 �ܴ��ϡ���������������������ˤ��äƿͤ��ܤ�¦�ˤ����Ǥ���
�ܴ��ϡ���������������������ˤ��äƿͤ��ܤ�¦�ˤ����Ǥ���- ���Υ���̤�����ʪ��ˤ�äƺ��줿����˳��礷�ޤ���
- ���äơ����Υ����ᥬ���ΰ��Ȥ������٤���ΤǤ���
- ��ᥬ�ͤϡ���ñ���̥�ǤǤ��Ƥ��ư²��ʤ��Ȥ����פ����ǤǤ������������˻Ȥ���ᥬ�� = �ܴ��ϡ���ʪ��Ǥ��ä�����礵�줿����˳��礹��Ư�����Ĥ�����̾����ᥬ�ͤȹ�¤���㴳�ۤʤ�ޤ���
- �������Ǥ���ʪ�����ǽ���������ڤǤ���
- ����������ʪ��Ƿ�Ф줿����˳��礵���ơ��ͤ˸��䤹��������Ư��������ܴ������ڤ����ܤ�ô�äƤ��ޤ���
- �����ǡ�ñ�����ᥬ�ͤȸ������ǻȤ����ܴ��ΰ㤤�ˤĤ��ƽҤ٤Ƥ����ޤ��礦��
- 1.����ᥬ�ͤ��о�ʪ�������ˤ��뾮����ʪ�ΤǤ���Τ��Ф���
- ���������ܴ��ϸ�������ʪ���ФƷ�Ф줿���������
- ����������ʪ�Ȥ�������������礹��Ư������äƤ��롣
- ����2.����ʪ��ˤ��������Ƥ��뤿�ᡢ�ܴ�������
- ������������������ʤ��������濴��ʬ��������Ǥ�������
- ���������������ʤ롣
- ����3.���������˼���դ��뤿�ᡢ���ʲ����줿��Ĺ�������ˤʤ�
- ���������Ƥ������������롣�礭�����¤ϵ��ʳ��Ȥʤ롣
- ����4.����ʪ��Ǻ��줿������礹�뤿��ˡ����μ�����ʪ
- ���������ΤȤϰۤʤä���ΤȤʤ롣�ܴ�����ʪ����
- ��������θ��������������Ƥ�����
- ����������ʪ�Ȥ�������������礹��Ư������äƤ��롣
- ����������ͳ�����뤿��ˡ����������ܴ������̤���ᥬ�ͤȤϰ�äƤ�������Υ�ǹ������줿��¤�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ܴ��Υ�����
- �������˻Ȥ����ܴ��ˤ��礭��ʬ���ơ��ۥ��إ����ס�Huygenian Eyepiece�ˡ���ॹ�ǥ��ס�Ramsden Eyepiece�ˡ�����ʡ������ס�Kellner Eyepiece�ˡ��ڥ�ץ���ס�Periplan Eyepiece�ˤ�����ޤ���
- ˾����ǤϤ�äȤ���������ܴ�������Ƥ��ޤ���
- �ܴ��οʲ��ϡ���˿������ʤɤθ�����������Ū�䡢����γ��ݤˤ���ޤ�����
- ���Ū�ˤϡ����Ҥ٤������̤�˺�����褿�Τǡ������̤����ǽ���夬�ä��Ȳ�ᤷ���ɤ��Ȼפ��ޤ���
- �������ܴ��ϡ����å١�1840ǯ���ˤ����ޤ���������ͰƤ���Ƥ����ΤʤΤǡ��������ѤȤ�������ŷ��˾������д�����Ƽ���ط�¬���֤Υ����ԡ����Ȥ��ƹͰƤ��졢���줬ʣ����������ȯã�ȤȤ��Ƴ�����ʲ������ȹͤ����ɤ��Ȼפ��ޤ���
- ŷ��˾������д���Ǥ��ܴ������ϤȤƤ���פǤ���
- �д���ǤϤǤ�����������ϰϤ���٤˸������Τǻ���ι����ܴ�������졢¿���Υ����פ��ͰƤ���Ƥ��ޤ�����
- ˾������ܴ����ˤĤ��Ƥϡ�˾����ν�Ǥ��Ƥ��ޤ���
- �ܴ��δ���Ū�ʹͤ����ϡ���ᥬ�͡ʥ롼�ڡˤǤ���
- ��������������ᥬ�ͤǸ������Ȱ�äơ�ʪ�Τ���θ����Τ�ΤǤϤʤ���ʪ��Ǻ��줿�����Ǥ���
- �������ϸ¤�줿��«�ˤ�äƷ�������Ƥ��뤿��ˡ����ˤϤ������˼������ĤäƤ��ޤ���
- �Ĥޤꡢ���̤�ʪ�Τ���礹��ΤȤϾ��꤬�㤦�ΤǤ���
- ���äơ��̾����ᥬ�ͤ�ȤäƸ��������ܴ��Ȥ����ΤǤϡ��������Τ�ѻ�����ͤ��ܤ˽���뤳�Ȥ��Ǥ������������Ť��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �������������μ��������ڤ�Ƥ��ޤ���
- �ޤ����ܴ��ζ����ˤ��礭����������Τǡ���ᥬ�ͤ����Ѥ�������θ��¤������礭�������¤���Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���������Զ���ʤ�������ˡ��������Ρ�˾����Ρ��ܴ��ʥ����ԡ����ˤ�����ޤ�����
- �ܴ��Ǥϡ���ʪ�����θ�«���Ψ�褯����뤿����������ʤ�����Field Lens�ˤ��Ȥ߹��ޤ�Ƥ��ơ�ȯ�����Ƥ������θ�«��ʤ��ƴ��ʤ�����Eye Lens�ˤ��������Ǥ��ޤ���
- ���οޤ��ܴ��λ��Ȥߤ��ޤ���
- ���οޤ��������Ư�����褯�狼��Ȼפ��ޤ���
- �����Ϥ��Ф餷����ǽ����äƤ���ȿ�̡���ʪ������������Ƥ��ޤ��ޤ����顢����Ψ�ϲ����äƤ��ޤ��ޤ���
- ����Ψ�������äƤ⡢����礭���Ȥ�뤳�ȤΤۤ������פǤ��뤳�Ȥοޤ϶����Ƥ���Ƥ��ޤ���
- ��

- .
- ����ޡ�������Ū���ܴ��λ��Ȥ�
- .
- �����ۥ������ס�Huygenian Eyepiece��
- ��������ʪ���ؼԥۥ��إ�1703ǯ�˹ͰƤ��������ԡ����Ǥ��ʾ���ȡˡ�
- ���Υ����פ��ܴ�������ʬ��Ǥϥۥ�����ȸƤӡ�˾���ʬ��Ǥϥϥ�����ȸƤ�Ǥ��ޤ���
 2���ʿ�̥�����̤Ϥ��������ʪ���¦�˸����Ƥ��ޤ���
2���ʿ�̥�����̤Ϥ��������ʪ���¦�˸����Ƥ��ޤ���- 2��Τ�������¦�ˤ���Τ������ǡ�������ˤ���Τ����Ǥ���
- ���Υ����פ��ܴ��Ǥϡ���ʪ�����������ܴ�����λ����θ����ˤǤ��ޤ�����
- �ۥ������פϡ�������ܴ��Ǥ��ꡢ˾������ܴ��Ȥ��ƺ���ޤ�����
- ���Ū����Ψ����Ū�����Ѥ��ޤ���
- ����������ʤ�����²��Ǥ���
- 2��Υ�δط��ϡ�������f1�ˤ�����f2�ˤ�3�ܤξ�����Υ����äƤ��뤳�Ȥȡ�2��Υ�ֵ�Υ��������f2�ˤ�2�ܤˤʤäƤ��뤳�Ȥǡ����줬���ä��ξ��Ȥʤ�ޤ������ξ��λ��������ܴ����Թ��ɤ������ޤ���
- �ޤ���f1 = 2 x f2�ǡ���ֵ�Υ��f2��1.5�ܤǤ������ä���郎����Ω���ޤ���
- �ڿ��ä�����
- ���ä����Ȥϡ�ʬ����ν1��ν2�ˤΰۤʤä��̥�ȱ����f1 ��f2�ˤ��Ȥ߹�碌�ơ�f1 x ν1 + f2 x ν2 = 0�Ȥ�����P������Ω�ĤȤ������������ʤ��ʤ�Ȥ�����ΤǤ���
- Ʊ�������2��Υ��Ʊ������ǵ�Υ����֤������֤�����ˤ������μ�������Ω���ޤ���
-
- ����d = ��f1 + f2��/2����������Lens - 46��
- ��������d������ֵ�Υ
- ��������f1��f2�����������Υ
- �������弰�ϡ�
- �������� = ��f1 x ��1 + f2 x ��2��/�ʦ�1 + ��2�ˤ�����μ��Ǥ��뤬��
- ���������饹�κ����Ʊ���ʤΤǡ���1=��2 �Ȥ���Ƴ����롣
- �ۥ������פ��ܴ��Ǥϡ������ξ�����Υ��Ĺ������3�ܡ�f1=3 x f2 �ˤʤΤǡ�d =��3 x f2 + f2��/2 = 2 x f2 �����ä����Ȥʤ�ޤ���
- ������ॹ�ǥ��ס�Ramsden Eyepiece��
- ��ॹ�ǥ��Jesse Ramsden: 1735 - 1800���ѹ���ؼԡ�ŷʸ�ؼԡˤ�1783ǯ�˹ͰƤ��������ԡ����Ǥ���
- �ۥ������פ��ܴ������줿80ǯ�θ���о줷�ޤ�����
- ��ॹ�ǥ�48�ͤλ��κ��ʤǤ���
- ��ॹ�ǥ�ε�������ơ����ʤ����α�����ο��㤵�ɥ������John Dollond��1706-1761���Ȥ����ͤǡ������ǻϤ�ƥ�ο��ä���ͰƤ����õ�����������ͤǤ���
- �ɥ���ɤϥᥬ�Ͳ��ǡ�����ɥ�Ǽ깭���ᥬ�ͤ��ä����䤹��˵�鿧�ä���ΤǤ��뤳�Ȥ�����ʹ�������饹�����Ѻ�ˤ����Ѥ��ƿ��ä������¤��Ϥ�ޤ�����
- ���줬����Ū���礤����������ʤ��ޤ�����
- �����������ͤ�Ĺ�����ɥ���ɤȤϰ�äơ�̼̻�Υ�ॹ�ǥ�ϼ�ľ��Ű�����ʤ��ä��褦�Ǥ���
- ��ϵ������Ѳ��Ȥ�����������ǥ䥹�꤬������̩�������֤��äƤ��ޤ�����
- ��κ��ʤˤϡ���̩ϻʬ�������ꡢ����1um����̩�ʿƥͥ���15ǯ�֤����äƺ��夲�Ƥ��ޤ���
- ���ȳ�̿���Ϥޤ����λ��塢�����ʹ�������Ǥ������λ���˥䥹���ȤäƤ��Ф餷����̩�������äƤ��ޤ�����
- �ब�ܴ���������Τϡ��ब�꤬��������¬���ܡʥե����顼���ޥ����������Filar Micrometer�ˤȸƤФ��ŷ�δ�¬�Ѹ������֤˻Ȥ�����Ǥ�����
- ��ॹ�ǥ��פϡ�������Υ��Ʊ��2���ʿ�̥�����̤����ߤ��˸�����äƤ��ޤ���
- ���Υ��ۥ�������Ʊ�͡������ȴ�����Ĥǹ�������Ƥ��ޤ�������ʪ�����������������������ˤǤ���Τ��礭����ħ�Ǥ���
- ����ϥۥ������פȰ�ä��ܴ��γ�¦�������֤����Ȥ��Ǥ���Τǡ����ΰ��֤˥�ƥ���������ޥ�����ͳ���֤����Ȥ��Ǥ��������Ǥ�����
- �ޤ������Υ����פ��ܴ��ϡ�����������뤳�Ȥ��鹭�����ܴ���Wide Field type�ˤȤ����Τ��Ƥ��ޤ���
- �������ɤ��Ȥ�Ƥ���Τǹ���Ψ����ʪ��˻Ȥ��ޤ���
- ��ॹ�ǥ��פ��ܴ��ο��ä����ϡ���ĤΥ��Ʊ��������Υ�Τ�Τ�ȤäƤ���Τ�f1 = f2�Ȥʤꡢ�����ꡢd =��f1 + f1��/2 = f1���Ĥޤꡢ��ֵ�Υd�������Υʬ����Υ���ƺ���ޤ���
- ��������Ȼ�����˴�������������뤳�Ȥˤʤ�ޤ������ξ����ȡ��������̤����夷�������ۥ��ꡢ��Υ��������å��긫���Ƥ��ޤ������Թ礬�����ʤ�ޤ���
- ���Τ��ᡢ���������餷�ơ��Ĥޤꡢd = 0.85f1 �Ȥ��ƴ��ξ������֤���������˻��äƤ���褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ��������ȿ��ä���狼�餺���Τǿ��������㴳�Ф�褦�ˤʤ�ޤ���
- �����Զ����ä�����Τ����Υ���ʡ������פȤʤ�ޤ���
- ��������ʡ������ס�Kellner Eyepiece��
- ����ʡ���Carl Kellner��1826 - 1855���ɥ��ĸ����߷ԡ�Leitz�Ҥ����Ȥβ�Ҥ����ߡ�29�ͤ�¾���ˤ�1849ǯ�˹ͰƤ��������ԡ����Ǥ���
- ��ॹ�ǥ��פ��ܴ�¦ = ����Eye Lens�ˤ˼��������������������ޥƥ��å������Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ���ä������˽���Ǥ��ä�����ˡ������볦�������ܴ����ѤȤ��ơ��ޤ�������Ψ�Υ������ޡ�����ʪ����Ѥ��ܴ��Ȥ��ƻȤ��ޤ�����
- ����ʡ����ܴ��ϡ���ȯ���顢���ݤ��볦��40°���٤Ǥ��ä������Ǥ���
- ����ʡ��ϡ�1849ǯ��23�ͤλ���Wetzlar�˾����ʸ��ز�ҡʸ��ظ���� = Optical Institute�ˤ���Ω���ޤ���
- Ernst Leitz�Ҥ����ȤǤ���
- ���������β�Ҥ�12̾�ν��Ȱ����ä������Ǥ���
- ���1855ǯ����ˤ�29�ͤμ㤵��˴���ʤ�ޤ���
- ��˴���塢���̤˴�ͤ������Ѥ��Dz�Ҥ�¸³��������������³���ޤ���
- Kellner��˴���ʤä�ǯ�������롦�ĥ�������39�͡�����ȥ��å٤�15�ͤǤ�����
- �����ϡ��ĥ������Ҥ⾮����Į����Ǥ�����Kellner�β�Ҥ⾮����Į����Ǥ�����
- ���β�Ҥ���®����Ĺ����Τϡ�1864ǯ��21�ͤ���̩������ Ernst Leitz��1843 - 1920�ˤ���ή���Ƥ���Ǥ���
- ��ή��5ǯ�塢1869ǯ�˥饤�Ĥϥ���ʡ��β�Ҥ������ꡢ����ȡ��饤�ļҤȼ�̾���Ѥ��ޤ���
- ��β�Ҥ�ͭ̾�ˤʤä��Τϡ��д㥿���פθ��������礤�������äƤ���Ǥ���
- �ޤ���1913ǯ��Ʊ�Ҥε��ե����������Х�ʥå��μ�ˤ��ե���५���ʥ饤���ˤ�����ǿ͵�����Ƹ��礤��ͭ̾�ˤʤ�ޤ���
- �����ڥ�ץ���ס�Periplan Eyepiece��
- ���ؼ�����˽���������פΥ����ԡ����ǡ�4��7��Υ�ǹ�������Ƥ��ޤ���
- ����ʡ��θ�Ѳ��Leitz�Ҥ��߷פ��ޤ�����
- �����ܴ��ϡ����ߥץ���פ�ץ���פι���Ψ��ʪ����ѤȤ��Ƴ�ȯ����ޤ�����
- ���Υ����ԡ����Ǥϡ������濴����Υ�줿�������ο������ν���ȡ�»���Ѷʤν������Ψ�ǤγƼ�����ν������Ū�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����������ͳ�ǽ�����ܴ�����٤ƥ��¿���ʤäƤ��ޤ���
- ��
- ����������Field Lens��
- ������������褦�ˡ��ܴ��Τ�äȤ��礭����ħ�ϻ����Ȥ�����Τ��Ȥ��Ƥ��뤳�ȤǤ���
- ���������ܴ�����Ф�����ᥬ�ͤȤ��ƻȤ����Ȥ��Ƥ�ԥ�Ȥ����ޤ��礤�ޤ���
- �롼�ڤȤ��ƻȤ����Ȥ���ȡ�ʪ�Τ��֤����֤��ܴ����Τ������äƤ��ޤ��ޤ���
- �¤ϡ����ʪ�Τ������äƤ��ޤ��Τϡ��ܴ��������Ƥ��������Field Lens�ˤ�ʪ�Τ��֤����ֶ�˵�����֤���Ƥ��뤫��Ǥ���
- �������ʤ��ܴ��Ǥϡ���ʪ��ˤ�äƳ��礵�줿�����濴���Τߤ���������äƤ��ޤ���
- �����������ܴ��������«���Ȥ��äƤ���Τǡ����¤θ¤�줿�ܴ����Υ�Ǥ���館����ʤ��ΤǤ���
- ���Τ��ᡢ��«��ʤ����ܴ����Υ�˸����碌�빩�פ�ɬ�פˤʤꡢ������Ū�Τ���˻������Ȥ���ΤǤ���
- ���ޡ��ܴ��λ��Ȥߡ�������
- �����������Field of View��
- ���������ܴ�����ǽ�����ͤΰ�Ĥˡ��������Field of View�ˤ�����ޤ���
- ���ο��ͤϡ��ܴ��Ǹ����������礭�����Ƥ���̵��������ɽ������ޤ���
- 20�Ȥ�30�Ȥ������Ǥ���
- ���λ�����ϡ��¤ϡ��ѻ��Ԥ����뤳�ȤΤǤ�������ɽ���Ƥ��ơ��ܴ��η����̤λ�����礭�����Ƥ��ޤ���
- 20�Ȥ����ΤϷ����̤�20mm�λ���Ǹ��뤳�Ȥ��Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���äơ�x20�ܤ���ʪ��Ȼ����20���ܴ����Ȥ߹�碌�Ǥϡ���ʪ��ˤ�ä�20�ܤ������������̤ˤǤ��ơ������Ǥ�φ20mm�λ�����ݤ���Ƥ���Τǡ�φ1mm��ʪ�Τ�φ20mm�����Ȥʤäơ����줬����Ȥ��Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ����Ĥޤꡢ
- ʪ�Τλ����mm�� = �����/��ʪ�����Ψ��M o�ˡ���������Lens - 47����
- �Ȥ����ط��ˤʤ�ޤ���
- ��������礭�����������ϰϤ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��������礭���ۤɴѻ����Ԥ��䤹���ʤ�ޤ���
- ��������礭���ܴ��Ϲ���Ǥ���
- ˾����Ǥϸ��ݤ�����ѤȤ����������dz��٤ǻ�����礭����ɽ���Ƥ��ޤ���
- ����������Ψ
- �ܴ�����Ψ�Ǥ���
- ����Ū�ˤ�x5��x10��x20���٤���Ψ��¿���褦�Ǥ���
- �ܴ�����Ψ���礭����и�������������Ψ���夬��ޤ�������ǽҤ٤���������������ʤ깭����������ʤ��Τǡ�����Ū�ˤ�x10��x20��¿���褦�Ǥ���
- ��������������Ψ�ϡ�
- ������������Ψ��M�� = ��ʪ�����Ψ��Mo�� x �ܴ�����Ψ��Me�ˡ��������ʴ��ҡ�
- �Ȥʤ�ޤ���
- ��ʪ����礭������������ΨM0�ˤ���ܴ����礭���������ΨMe�ˤȤ�����̣����μ���ɽ����Ƥ��ޤ���
- ���������顼������Koehler Optics�� ����2006.03.01��
 ��2006.06.21�ɵ���
��2006.06.21�ɵ��� - �����顼�����ϡ�Ʃ�᷿����������ʪ����������Ω�������ˤ˻Ȥ��Ƥ��������ˡ�ǡ��ɥ��Ŀͼ¸��ʳؼԥ����顼��August K��ler��1866-1948�ˤ�1893ǯ���Ԥ߽Ф�����ˡ�Ǥ���
- �����������顼�ϡ�����������ء�Geissen��ưʪ�ظ�����J.W.Spengel�����ν���Ȥ���Ư���Ƥ��ޤ�����
- ����Ԥ߽Ф���������������ˡ�ϡ����������Ƶ��Ѥ���Ѥ������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���������Ǥλ��Ƥϡ���Ψ��夲�Ƥ����Ȥɤ����Ƥ���̤���ʤ��ʤꡢ����������ľ������Τ˾ȼͤ��륯��ƥ�����������餶������ޤ���Ǥ�����
- ����ƥ���������Ǥϸ�������ľ������Τ���Ƥ����Τǡ���������ǻø����������˽ŤʤäƶѰ�ʾ��������뤳�Ȥ����ʤ�ޤ���
- �����顼�ϡ�����ƥ��������ˡ�η�����ȴ�����Ѱ�ʾ����Ǥ�����ɸ�ܾ�˶����������Ƥ���ˡ��ͰƤ��ޤ�����
- �����顼����ˡ�δ���Ū�ʤ��Ȥϰʲ��λ����Ǥ���
- ��
- ��1�ˡ������ʥե�����ȡˤä��������������طϡʥ��쥯����ˤ��ߤ��ơ������ʤ����˸��������롣����������������˥�ʥ���ǥ�ˤˤ�ä�ɸ���̤���Ƥ����롣
- �����������ʤ�����뤵��Ĵ����Ԥ���
- ��
- ��2�ˡ��������λ����Ĵ���������ʤ�ϡ�ɸ���̤˷������Ƥ��뤳�ȡ�
- ����������ʤ��ɸ���̤˾ȼͤ�����������礭����Ĵ�����롣
- ��
- ��3�ˡ�����ʤ�ȳ����ʤ�Ϥ��줾����Ω���Ƥ��줾���Ư���롣
- �����������ʤ�����뤵��Ĵ����Ԥ���
- ��
- �����顼�����ϡ��������ä������ʤ�ˤ����Ƥ����ǥ��Ŭ�ڤ�ɸ���̤���Ƥ����뤳�Ȥˤ�ꡢ�Ѱ�ʾ�������ݤ��ޤ�����
- ����ʤ�θ������ϡ�����ιʤ��Ĵ�����뤳�Ȥˤ��Ѱ�����뤵��ɸ���̤����뤵��Ĵ�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ޤ�ɸ���̤˷�������褦�˻���ʤ���֤�������ʤ��Ĵ�����뤳�Ȥǻ���˴ط��Τʤ����åȤ��뤳�Ȥ��Ǥ������������ˤ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �����顼�����ϡ�110ǯ�Фä�����Ѱ��پ���ˡ�Ȥ��Ƹ��������³���Ƥ��ޤ���
- �����顼�����ϡ��������ä������ʤ�ˤ����Ƥ����ǥ��Ŭ�ڤ�ɸ���̤���Ƥ����뤳�Ȥˤ�ꡢ�Ѱ�ʾ�������ݤ��ޤ�����
- �����顼�ϡ�1900ǯ��34�ͤλ��˸�������¤��ͭ̾�ʥĥ������Ҥβ��ǥ��˥��Ȥ���Ư���Ϥᡢ������Zeiss�ҤDzᤴ����������������ȯ�Τ���˿��Ϥ��ޤ�����
- 1900ǯ�Ȥ����С������롦�ĥ������Ϥ������ˤʤ������å٤���ǯ�ˤ�����ǯ�Ǥ���
- �������ǰ������ۤ����ĥ������������θ������˰��ؤ�������Τ������顼��Τˤ�����ˡ���ä��ΤǤ���
- ��
- �桹���������θ��طϤ�ͤ���Ȥ�����������θ���뤳�Ȥ��դ꤬���Ǥ���
- ���οޤϡ���������Ф������ɤΤ褦�ʷ�ϩ���̤ä��ܤ����뤫���Ƥ��ơ�������������ڤʾ������طϤι������ǤȤʤäƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �ޤ˼������褦���ظ��ʵո���Ʃ����˾����Ǥϡ���������ʪ��������Ĥ����طϤˤ�äƤɤΤ褦�ˤǤ��뤫�����տ�������ɬ�פ�����ޤ���
- �ޤǤϸ������ˤĤ��ƤΤߤθ�ϩ�������Ƥ�������Ρ�ɸ�ܡ����ˤĤ��ƤϿ���Ƥ��ޤ���
- �桹���������θ��طϤ�ͤ���Ȥ�����������θ���뤳�Ȥ��դ꤬���Ǥ���
- ���οޤƤߤ�ȡ��������ϥ���ǥ����������֤˰�ö�������ơ�ɸ�ܾ�Ǥ�̵�±����Ȥʤ�ʿ�Ը��ˤʤäƤ��ޤ���
- ���Τ��Ȥϡ�ɸ�ܾ��Ʃ�᤹������϶ˤ�ƥԥ奢�ʸ��Ǥ��ꡢɸ�ܾ�α��Ƥ��ɹ�����ã���ޤ���
- ����ǥ�����ˤ��볫���ʤ����Ǥϸ����������졢���γ����ʤ��Ĵ�����뤳�Ȥˤ�����뤵��Ĵ���Ǥ��ޤ���
- �����ʤ��ʤ��ɸ�ܤ����ͤ�����γ��٤�Ω�ġʱԳѤˤʤ�ˤ��ᡢɸ�ܾ��ʪ�Τα��Ƥ��Ϥä���Ȥ��ʾ������٤������ʤ�˥ԥ�Ȥι礦�ϰϤ������ʤ�ޤ���
- ɸ�ܾ��Ʃ�ᤷ���������ϡ���ʪ��θ�������֤Ǻ��ٷ������ޤ���
- ���ΰ��֤��ͽ�Ʒ���֤Ȥʤ�ޤ���
- ���οޤ��֤��������Ĥ������ǡ�Ʊ�����θ��ä��꤬�������ΤǤ�����֤Ȥʤ�ޤ���
- �֤��������Ĥ�������������������֤Ǥϡ������ϰϤ����¤���ޤ���
- �������äƤ��ΰ��֤˹ʤ���֤��Ƹ������¤���Ȼ����ޤäƤ��ޤ��ޤ���
- �ޤ�������������������ݥ���Ȥ������֤������֤Ȱ��פ������ʤ����ɸ�ܾ塢��������֡������ϥե�����������Ѱ�ˤʤ�ʤ��줤�˥ܥ��Ƥ���ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
- ����˾������Telescope Lenses�� ����2006.03.09�ˡ�2006.10.04�ɵ���
- ˾����ϡ��Τ�Τ��˰����Ĥ��Ƹ��뤿��Υ���طϤǤ���
- ������ʪ�Τ����Ȥ��顢ʪ�Τ������ͤ������ϡ�ʿ�Ը�«�Ȥ�����ʪ�������ޤ���
- ���ä����Ͼ������֤ˤǤ��ޤ���
- �������֤ˤǤ�������˳������ܴ��ˤ�ȤäƳ��礷��������Ȥ�����Ĥμ���Ф�˾��������Ω�äƤ��ޤ���
- ���μ��ϡ��������ȶˤ�ƻ��̤äƤ��ޤ���
- ���̶��ν�Ǥ��ޤ�������ʿ�Ը�«������¸��طϤˤϱ��̶������Թ�ʤΤ�˾�������ʪ��ˤϤۤȤ�ɤȸ��ä��ɤ����餤���̶����Ȥ��ޤ���
- ���̶��ʤɤζ���Ȥä�˾�����ȿ�ͷ�˾����ȸ�����˾����Ȥä���Τ����˾����ȸ��äƤ��ޤ���
- ������ΤۤȤ�ɤ�ŷʸ��ǻȤ��Ƥ���ŷ��˾����ˤϡ�ľ��1��ȥ뤫��10��ȥ�α��̶����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �̥�Ǥϡ�ľ��5��ȥ����礭�ʸ��إ��饹���ʼ����ɤ���ΤĤ館�뤳�Ȥ⡢�����Ƥ��������Ȥ⤪������������Ǥ���
- ȿ�ͷ�����˻Ȥ�����ͳ�������ˤ���ޤ���
- ˾����θ��طϤϡ���������Ʊ���褦����ʪ����ܴ��ǹ�������Ƥ��ޤ���
- ��ʪ���ܴ��ξ���ʪ�Τ���礷�Ƶ�����Ȥ������Ǥϸ�������Ʊ���Ǥ���
- �����������˾�������Τ���Υ�Ǹ��뤿�ᡢ��ʪ��˾�����Υ��û����Τ��Ȥ�����Ф��ơ�˾����Ǥϱ�ʪ�Τ뤿��˾�����Υ��Ĺ������Ȥ���Τ��礭�ʰ㤤�Ǥ���
- ���äơ�˾����Ǥ��礭�����ٹ礤����Ψ��M�ˤϡ��������ȤϾ����ۤʤäơ�ξ�ԤΥ�ξ�����Υ�����ɽ���ޤ���
- �ޤ�����Ѥ��ٹ礤��ɽ�����Ȥ⤢��ޤ�����˾�������Ψ���ȡˡ�
- ��
- ����̵�±��ͭ�µ�Υ��Infinity Optics��Finite Optics��
- ���ؤ������Ǥ�̵�±�Ȥ������դ��褯�ФƤ��ޤ���
- ̵�±�ȤϤɤΤ��餤�ε�Υ����äƤ���ΤǤ��礦��
- ���ۤ�̵�±�ˤ���ȸ��ʤ��ƺ����٤��ʤ��Ǥ��礦��
- ����˸�������ʸ��ʤ�̵�±�ˤ���ȸ��ʤ��ƺ����٤�����ޤ���
- �ٻλ������ʤ��������Υ��̵�±�Ȥ����ɤ��褦�Ǥ���
- �̿���Ƥߤ�ȡ����Ƶ�Υ��5m�ʾ�ˤʤ�ȥե����������֤ϡ�∞�ס�̵�±�ˤȤʤꤳ�ΰ��֤ǻߤޤäƤ��ޤ��ޤ���
- �����ͤ���ȡ�����ʬ��Ǥ�̵�±�Ȥ����Τ�10m�ʥ�ȥ�˰ʾ�ȸ��äƤ��ɤ��褦�Ǥ���
- ����˾���ˤĤ��Ƥ⤽�줬�����뤫�Ȥ����ȵ���Ǥ���
- ���ؤ�������̵�±�ȸƤ٤�Τϡ����ƺ���ߡʤ���褦�������allowable image blur�����������Ƥ���褦�Ǥ���
- ���ƺ���ߤϸ��طϤκ��ܥ����̤������Υܥ��Ⱦ�����Υ���ڤӸ�����Dz������Υ�ʤ����礦�Ƥ��ˤ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������Υ�Ǥϡ����ε�Υ����ˤ���ʪ�ΤˤĤ��ƤϤ��٤ƺ���ߤ����äƤ��ޤ�������黣�ƤǤϥԥ�Ȥ���äƤ���Ȥߤʤ���ޤ���
- �Ĥޤꡢ�������Υ���������θ��طϤ�̵�±����ʤΤǤ���
- �������Υ�ˤĤ��Ƥϡ����Ǥ˽Ҥ٤ޤ��������⤦�����������ޤ���
- H = f2/(δxF) ��������Lens-21�ˡʴ��ҡ�
- ����H�����������Υ
- �����桧���������Υ
- ����δ�������ƺ����
- ����F�����������
- ��μ��Ƥߤ�ȡ�̵�±�Ȥ����Τϥ�ξ�����Υ�ʤ����Ƶ��ƺ���ߤ��ͤμ�����ȥ������ˤˤ�ä��Ѥ�äƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �������ȤäƲ������Υ����Ƥߤޤ���
- ������Υ��f50mm�Υ�ǹʤ��F1.4�Ȥ������ƺ���ߤ����ǻҤ�2����ʬ��24um�Ȥ��Ʒ�����ȡ�74.4m��̵�±�Ȥʤ�ޤ���
- �ͤδ�Ǥϡ�������Υ��f17.1mm�Ǥ��ꡢ������F3.4������Ф�ʬ��ǽ2.4um�ʤΤǡ�35.8m��̵�±�Ȥʤ�ޤ���
- �������f50mm��ʪ�Τ�74.4m��= a�ˤε�Υ�ǤȤ館��Ȥ���������λ�����Ψ�ϡ�a = ���1 + M�ˤ�ꡢM = 1/1,487�Ȥʤ�ޤ���
- ���褽��������Ψ��1/1000�ʲ��ˤʤ�Ȥ���ʪ�Τ�̵�±�ˤ���ȹͤ��Ƥ褤�Ǥ��礦��
- ������Ψ��1/1000�λ������ϥ�ξ�����Υ���֤��0.1%Υ�줿���֤ˤǤ��ޤ���
- 0.1%�Ȥ����ͤϡ�f50mm�Υ�Ǥ�0.05mm��50um�ˤ�������������ʬ�����������֤��饺�줿���֤ˤǤ��ޤ���
- �����̤ϡ��ե�������Ĵ���Τ���Υ����Ф��ԥå���2mm�Ȥ���Ȳ�ž��9°���������ޤ���
- ���ΰ��֤�����ǤΥե�������Ĵ������̯�ʤ�ΤȤʤ뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ¿���Υ�Ǥϡ���ξ�����碌�ι����5m������ޤǤ����ʤ������ˤ�∞�Υޡ����ˤʤäƤ��ơ����δ֤Υե�������Ĵ���ϡ��ե���������β�ž��1/24��ž��15°�����٤Ȥʤ�ޤ���
- �ˤ���ʪ�Τ�15°�β�ž�Ѥǥե�������Ĵ������ΤϽ�����ɬ�פˤʤ�ޤ���
- ������㤨�С�F16���٤˹ʤ�ȡ��������Υ��6.5m�Ȥʤ�Τǡ���ե���������∞�ΰ��֤˹�碌�Ƥ����Ƥ⡢6.5m����̵�±�ޤǵ��ƺ������Υܥ��˼���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��äȤ⤳�Υܥ��ϥ������21��/mm�����������ΤʤΤǡ��ʤꤳ�ळ�Ȥˤ�ä��濴���β����Ϥ�»�ʤ�졢����˼������Υܥ����������줿����Ū��ʿ�Ѳ����줿�����Ȥʤ�ޤ���
- ����˾�������Ψ��Magnification of Telescope��
- ˾�������ǽ��ɽ�����ͤ���Ψ������ޤ���
- �������Ǥ�ʪ�Τγ�����Ψ����Ψ��ɽ���������ο��ͤ�Ĺ��������������ޤ���˾����ξ�硢����������Ψ�Ⱦ�����äơ���ʪ�Τ��˰����Ĥ����ٹ礤����Ψ�ȸ��äƤ��ޤ���
- �ޤ��ϡ�ʪ�Τ�Ʊ�����֤�˾���������줿�����ä���硢�����礭�����ٹ礤����Ψ�ȸ��äƤ��ޤ���
- ˾����ˤĤ��ƽ줿���ͽ���˾�������Ψ�������Ȥ��ưʲ��μ����Ҳ𤵤�Ƥ��ޤ���
- M = fo / fe����������Lens48��
- ����M�� ˾�������Ψ
- ����fo�� ��ʪ��ξ�����Υ
- ����fe�� �ܴ��ξ�����Υ
- �ޤ��ϡ���Ѥ��ٹ礤����ʲ��μ��Ǥ�ɽ����ޤ���
- M = tan ω'/tan ω����������Lens49��
- �����͡���˾�������Ψ
- ����ω’����˾����ˤ�����λ��
- ����ω��������Ǹ���ʪ�Τλ��
- â��������ϡ�M = ω’/ω�Ǥ�����tanω→ω��tanω’→ω’�ȶ���Ǥ��������Ω���ޤ���
- ξ�Ԥϡ����˥���ץ�ʼ��Ǥ���
- ��ξ�����Υ���������Ψ�θ����Ǥϡ���ʪ��ξ�����Υ��fo�ˤ��ܴ��ξ�����Υ��fe�ˤdz�äƤ�����Ψ����ޤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����Ū��˾����˻Ȥ�����ʪ��ξ�����Υ��f400mm��f1,000mm���٤�¿�����ܴ���f50mm��f25mm���٤�¿���Τǡ������Ȥ߹�碌���餹���˾�������Ψ��8�ܡ�40�ܤȤʤ�ޤ���
- ������������Ψ��˾�������Ψ�����ΰ㤤
- ��ι���塢ʪ���ؤμ��ȤǸ������θ��طϤ�˾����θ��طϤˤĤ��ƽ����ޤ�����
- ����������������Ψ��˾�������Ψ�θ������礭���ۤʤäƤ��ơ����ʤ�Ȥޤɤä����Ȥ����Ƥ��ޤ���
- ��������ξ�硢��ʪ���fo�ˤξ�����Υ��2mm���٤Ȥ����ܴ��ξ�����Υ��fe=25mm�Ȥߤʤ��ȡ�200�����٤���Ψ�������ޤ���
- �����˾�������Ψ������ñ������ƤϤ��ȡ�M=2/25=1/12.5 �Ȥʤꡢ�ȤƤ����ʤ�˾����ˤʤ��ͤȤʤ�ޤ���
- �����λ�ϸ��ؤˤ��ޤ궽̣����äƤ��ʤ��ä��Τǡ�˾�������Ψ�����ȸ���������Ψ�����ϱ��ݤߤˤ�����ޤ���Ǥ�����
- �����������Ѥʵ���Ȥ��ơ��ʤ�ξ�Ԥ���Ψ�����ˤ��Τ褦�ʰ㤤������ΤǤ��礦��
- ��������˾�������Ψ�����ΰ㤤�ϡ��ʲ�����ͳ������Ƥ��ޤ���
- ��
- ����1.������ΤΤ�����Ƥ�����֤��㤦��
- ����������������������ʪ��ζ�ξ������֤ˤ����졢˾����Ǥ�̵�±���֤��줿����Τ���
- ����2.�����äơ�ξ�ԤǤ���ʪ��ˤ�äƤǤ������ΰ��֤��㤦��
- ����������������������ʪ������� 10f��50f��f����ʪ��ξ�����Υ�˰��֤˼������Ǥ���
- ������������˾����Ǥϡ���ʪ��ξ������ֶ�˵�ʤ�����ˤ�ƶ�ˤ������Ǥ��롣
- ����3.����ʪ��ǤǤ����������ܴ��Ǥ�����礷�Ƶ�������Τ�ξ�ԤȤ�ۤ�Ʊ����
- �����������������������Ǥ�250mm�ε�Υ�˳��������֤����Ȥ���Τ��Ф���
- ��������˾����Ǥ�̵�±�ʼºݤ�����Ʊ�����֡ˤ��֤����Ȥ��롣�ʤ�����������ϸĿͺ������ꡢͭ�µ�Υ�˳���������֤��ͤ⤤�롣��
- ��
- ����˾�������Ψ
- ����1.������ΤΤ�����Ƥ�����֤��㤦��
- ˾�������Ψ�ϡ��ͤ�����ʪ�Τ����ѡ�ω�ˤ�˾����Ǹ����Ȥ��λ���ѡ�ω'����ǵ�����Ȥ���⤦��Ĥθ��������ꡢ¿���λ��ͽ�ǾҲ𤵤�Ƥ��ޤ���
- ����Ѥȥ�ξ�����Υ�ˤ�����ط�������Τǡ�˾����θ�����¤�Ʊ�����Ȥ���äƤ��ޤ���
- ������Ψ�ˤĤ��ơ����֤δ��ܤǤ��륬�����Υ������1/a+1/b=1/f�ˤ�Ȥäơ�˾����λ��Ȥߤ�˾�������Ψ��Ƴ���Ƥߤ뤳�Ȥˤ��ޤ���
- ����Ƴ�����ϡ�¾�Τɤλ��ͽ�ˤ�ܤäƤ��ʤ���ΤǤ���
- ���ޤ�˾����θ��إ쥤�����Ȥ��ޤ���
- ���οޤϡ���ʪ���Ư�����ܴ���Ư���줾���̡����ڤ�Υ����2�ʤ�ʬ���Ƽ����ޤ�����
- ��

- ��˾����θ����ޡ����ץ顼��˾������ʥ��ץ顼��˾�����������
- ��
- ˾�����Ȥ���硢����Τ����˱ˤ���ޤ���¿���ξ�硢��ʪ�������Υ��fo�ˤ�1000������Υ�줿���֤ˤ����̵�±��Υ�Ȥ��ƺ����٤��ʤ��褦�Ǥ���
- �����ͤϡ���ʪ���fo�ˤ�f400mm�ʤ�400m��=a�ˤȤʤ�ޤ���
- ��������ΰ��֤�����ʪ���������ϡ���ʪ��ξ������֡�fo�ˤȤʤ�ޤ������λ���������Ψ�ϡ�
- ˾�����Ȥ���硢����Τ����˱ˤ���ޤ���¿���ξ�硢��ʪ�������Υ��fo�ˤ�1000������Υ�줿���֤ˤ����̵�±��Υ�Ȥ��ƺ����٤��ʤ��褦�Ǥ���
- Mo��=��fo/a����������Lens50��
- ��ɽ����ޤ���
- ���äơ�����Ρ�H�ˤ�����h�ˤϡ���ʪ�����ΨMo��ݤ���碌��
- h = H x fo / a����������Lens51��
- ���礭���Ȥʤ�ޤ���
- ��������h�ˤ��ܴ���fe�ˤdz��礵���ޤ���
- ��������h'�ˤ�����Τ�Ʊ����Υ��a�ˤ˺��Ȥ���ȡ���������h'�ˤϡ�
- h' = h x a/fe����������Lens52��
- �Ȥʤ�ޤ���
- �ޤ����ܴ�������Ψ��Me�ˤϡ�
- Me = h'/h����������Lens53��
- �Ǥ����顢
- Me = h'/h = a/fe����������Lens54��
- ��ɽ����ޤ���
- ˾�����������Ψ��M�ˤϡ�
- M = Mo x Me�������������ҡ�
- �Ǥ��뤳�Ȥ��顢��˵��ط������������ơ�
- M = Mo x Me =��fo/a�� x ��a/fe��= fo / fe ����������Lens55��
- �Ȥʤꡢ��˾������Ψ�δط�����Ƴ�����Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ���θ����Dz����Ƴ���������ܤϰʲ����̤�Ǥ���
- ��
- ��������1.��a ����ʪ�������Υ��1000�ܤȤ������ȡ�
- ��������2.�����η����ʪ�������������h�ˤϾ�����Υ fo �ΰ��֤˷�Ф�뤳�ȡ�
- ��������3.���������ܴ��Ǻ����ǽ�����h'�˰��֤ϡ�����ΤΤ���Ʊ�����֡� a�ˤˤǤ���Ȥ�����
- ��
- ��Τ褦�˶������Ǥ��ȡ�̵�±�Τ�Τ�̵�±�Ǥߤ뤳�ȤϤĤ餤�Τǡ��⤦�������䤹�����֤Ǹ��褦�Ȥ��ޤ���
- �⤷���ܴ��ˤ�äƤǤ�������ʺǽ����ˤ���ᥬ�ͤ���Ψ���� Me = 250/fe �����ƤϤޤ���֤ˤ��ä��Ȥ���ȡ���ʪ�����ΨMo�Ȥ������碌��������ΨM�ϡ�
- ��������1.��a ����ʪ�������Υ��1000�ܤȤ������ȡ�
- M = ��fo/a�� x��250/fe��=��250/a�ˣ���fo/fe�ˡ���������Lens56��
- ��
- �Ȥʤꡢ��Ψ������ȸ��äƤ��ޤ��ޤ���
- ����ϡ����������Ψ���������˰�����ʬ��250/a�ˤ����礭������Ψɽ�������뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����100mΥ�줿10m��η�ʪ����25cm������ε�Υ�ˤ��äơ���������fo/400fe���礭���Ǹ����Ƥ��롢�Ĥޤ�10�ܤ���Ψ��fo/fe=10�ˤ���ä�˾����Ǥ���ʤ�С�10m�ι⤵�η�ʪ��25cm��=10m/400�ˤι⤵�˸����뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ������ѤǸ���ȡ�ω = tan-1��10m/100m��= 5.71°��ω' = tan-1��25cm/25cm�� = 45°�Ȥʤꡢ7.9�ܤۤ��礭�������ޤ�����ѤǸ���Ȥ���ۤ��礭�����Ѥ�äƤ��ޤ���
- �Ȥʤꡢ��Ψ������ȸ��äƤ��ޤ��ޤ���
- �פ���ˡ�˾����θ����Ǽ����줿��Ψ�ϡ�ʪ�Τ�̵�±�ˤ���Ȥ�������ʪ�Τ�Ʊ��̵�±�ΰ��֤˳��礷���Ȥ���ξ�Ԥ��礭�������ɽ���Ƥ���ΤǤ���
- ������Ǥϡ�100mΥ�줿10m�η�ʪ��ᥬ�ͤǶ��������䤬10�ܤ�˾������������Ȥ���ȡ�100m���100m�η�ʪ�����äƤ���褦�˸�����Ȥ�����ޤ���
- 100mΥ�줿10m�η�ʪ�λ�Ѥϡ�tan-1��10/100��= 5.71°�ǡ���Ψ10�ܤ�˾����������Ƹ���100m�����ϡ�tan-1��100/100��=45°�Ȥʤ�ޤ���
- 5.71°�Τ�Τ�45°�˳��礵�줿�ΤǤ���
- ������ϡ�45/5.71=7.88�Ǥ���
- �����ͤ��ȡ�˾�������Ψ10�ܤ��ͤȤޤ�Υ��Ƥ��ޤ���
- 1000mΥ�줿����10m�η�ʪ�Ϥɤ��Ǥ��礦��
- ���λ�������λ���ϡ�tan-1��10/1000��=0.573°�ǡ�˾����Ǥϡ�tan-1��100/1000��=5.711°�Ȥʤ�ޤ���
- ������ϡ�5.711/0.573=9.967�Ȥʤ�10�ܤ˶�Ť��ޤ�����
- ���λ���tanω'/tanω�ϡ�10�Ȥʤꤳ�μ����Ѥ���¤���Ψ��10�ܤǤ���
- �Ǥ�����Ѥ��̣����Ȱۤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢω→tanω�˶��������Ȥ���̵�������ä��ΤǤ���
- ���Τ��Ȥ��顢˾�������Ψ�����ϡ�̵�±�ǡʤĤޤꡢ̵�±��ʪ�Τ�̵�±�˳��礷�Ƹ�����ˡ����ƤϤޤ뼰�Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ����Ź���д�������ʡ�����Ψ8�ܤ��д�����ˤ��ơ�10m����Υ�줿�ͤδ�乭����ĤƤ�8�ܤ��礭���˸������ԻĤʵ����������Ƥ����ΤǤ�������Ψ�ˤϤ���������«��̵�±�Ǥʤ�ʪ�Τ��Ф��Ƥ���Ψ��ɬ�������������ʤ��Ȥ������ȡˤ����ä��ΤǤ���
- ŷ��˾����Ƿ����������ʻ��Ϥοͤ��ѻ�����Ȥ��ϡ��ݤ��ͤʤ�����Ψ�����礭���Ǹ����ޤ���
- ��
- �����ʰ�˾�����-���д����Binoculars�ˡ���2006.09.25���ˡ�2006.10.13�ɵ���
- �д�����äѤ�˾����Ǥ���
- �д���ϡ�ŷ��˾����Ȱ�ä��Ͼ��ʪ�Τ�ѻ����뤳�Ȥ������Ū�Ǥ��뤿�ᡢ��Υ��50m�����km���ϰϤǻȤ����Ȥ�¿���ȹͤ��ޤ���
- �д������Ψ�ϡ��������äưʲ��˼����ͤ���������䤹���Ȼפ��ޤ���
- �Ĥޤꡢ�д���λ��äƤ�����ΨM�ϡ���Ψ���ܿ�ʬ����ʪ�ε�Υ������Ĥ���Ȥ����ͤ����Ǥ���
- ���ιͤ������餹��ȡ�10�ܤ��д���ϡ��Τ�Τ�1/10�˰����Ĥ��Ƹ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- 1000m�Τ�Τʤ�100m�ˡ�500m�Τ�Τʤ�50m�ˡ��Ȥ������Ǥ���
- �������ʤ��顢10�ܤ��д����10�ܤϤ��٤Ƥξ�������Ω�Ĥ櫓�ǤϤ���ޤ���
- ��Υ��10m�λ��Ǥ⡢���οͤ����Ƥ⡢�ܴ������ܤ�Υ���Ƹ��Ƥ�����10�ܤ���Ψ�������뤫�Ȥ����Ȥ����Ϥʤ�ʤ��ΤǤ���
- �����Ҥ٤ޤ������д���ʤɤǼ��������Ψ��̵�±�ˤ���ʪ�Τ��Ȥ������ƤϤޤ���ͤǤ��ꡢ�ºݤˤϤ⤦�����������ä�������ɬ�פȤʤ�ޤ���
- ������������Ψ����ʾ������ƤϤ��ΤϻȤ��������ѤʤΤǡ��ص�Ū��̵�±�Ǥ�ʪ�Τ��оݤȤ���������Ψ��ȤäƤ��ޤ���
- ��
- ����

- �����ݥ����ץꥺ��
- �д���˻Ȥ���ץꥺ��ˤϥݥ����ץꥺ��ȥ��ϡ��ץꥺ���2���ब��ή�Ǥ���
- �ݥ����ץꥺ��ϡ�1850ǯ��ȯ�����������ꥢ���͡�ˤʼ�δ��Υݥ���Ignazio Porro��1801�� 1875�ˤˤ��ʤ��̾�դ���줿��Τǡ�ľ�ѥץꥺ���2�Ĥʤ���3�ĻȤä���ΤǤ���
- �ݥ��ϡ����ͻ���˸��ط�¬���֤δ��������˴�����˾����⥳��ѥ��ȤǻȤ��䤹����Τ�˾��Ǥ��ޤ�����
- ����쥪��˾�����������������������ȿ�̡�����������������ꡢȿ�̡����ץ顼���ϥ���쥪���������Ϲ����Ȥ���Τ���Ω���ȤʤäƤ��ޤ�����������ޤ�����
- �ݥ��ϡ����ץ顼��˾����θ��طϤδ֤˥ץꥺ����������Ω������Ω�����Ѵ�������ˡ��פ��Ĥ����õ����ꡢ���������ȶ��ˡ������ꥢ�ȥե�˼���θ��ع����Ω�Ƥ�˾������д�����濴�Ȥ������ص������¤����˾��Ф��ޤ�����
- ����������λ��ȤϤ���ۤɤ��ޤ��Ԥ��ޤ���Ǥ�����
- ���¸̿������ȯ�������ݥ����ץꥺ��ˤ���д�����ۤ��ܤʤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���Υݥ����ץꥺ���Ȥä��д����֥졼���������Τϡ������롦�ĥ������ҤǤ���
- �ĥ������ҤΥ��å���Τϡ�1894ǯ�ʥݥ���ȯ����44ǯ��ˤ˸���20��������Ψ8�ܤ���ĥݥ����ץꥺ����д�����������Ƥ��줬�礭���ҥåȤ��ޤ�����
- �ҥåȤ��������ϡ��ĥ��������д������ǽ���ܲȤΥݥ������ʤ��ɤ��ä�����Ǥ���
- 1890ǯ�������ĥ������Ҥϥ���åȼҤȶ�Ʊ�ǡ����Ū�ʻ��ȤȤʤ��ɼ��ʸ��إ��饹��¤���Ѥ��Ω����BK7���Τ�����غ��������ȤΥۥ������ǥ��饹���﷾���饦�饹�ˤ��������Ƥ��ޤ�����
- ���θ��إ��饹���д���Υץꥺ��˺��Ѥ����ΤǤ���
- �ĥ��������д�����������뤯�����Ǥ��ä��Τǡ��֤��֤˷����Ϥ�Ȥ����Ծ���ʴ����ƹԤ��ޤ�����
- �ݥ��β�Ҥ��д���ϡ��ץꥺ��κ��������Ʃ���٤������ä�����������饹���̤ä��ݤ����ܤ���Ȥ������äƤ����ȸ����ޤ���
- ���ʤߤˡ��Ƕ���д���˻Ȥ���ץꥺ��κ���ˤϡ�Bak4�ȸƤФ��Хꥦ�९�饦����إ��饹���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- BaK4�ʶ���Ψ1.571��at �п��ϡ���ȿ�ͳ�39.53°�ˤ�BK7�ʶ���Ψ1.518���Сϡ���ȿ�ͳ�41.72°�ˤ���٤ƶ���Ψ���⤤�Τǡ��ץꥺ�����ȿ�ͤ���������٤�;͵�����ꡢ��ȿ�ͤ�����������������ޤǽ�ʬ�˸���ȿ�ͤ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ޤ�����Ψ���⤤�ΤǸ��ص�Υ��Ĺ���ʤꡢ���֤�ѥ��Ȥˤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- BaK4�Ϲ���ʸ��إ��饹�Ǥ���������ι����д���ˤϽ��פʤ�ΤȤʤäƤ��ޤ���
- ��
 ����
����
- .
- .
- .
 �����ϡ��ץꥺ��
�����ϡ��ץꥺ��- ���ϡ��ץꥺ��ʥ��åϡ��ץꥺ��ˤΥ��ϤȤϡ��ɥ��ĸ��Dach�Ƚ����Ȥ�����̣�Ǥ���
- �Ѹ�ɽ����Roof Prism�ȸƤ֤��Ȥ⤢��ޤ���
- �������ץꥺ��ϡ�ľ�ѥץꥺ��μ������������η������������ˤʤäƤ��ơ����������ˤ�ä����ͤ����������ȿ�ͤ�����������ȿž������ħ����äƤ��ޤ���
- ����ץꥺ��Ǹ���ȿ�ͤ���������������ʺ���ȿž�ˤˤʤäƤ��ޤ��Τˡ����ϡ��ץꥺ���Ȥ�������ȿ�ͤ��Ƥ�����ˤʤ�ʤ��ΤǤ���
- ���Υץꥺ��ϡ��д���ʤɤοͤδ��𤷤����ص�����ܴ����̤˻Ȥ��뤳�Ȥ�¿���������ꥢ��ŷʸ�ؼԤǸ��ؼԤǤ⤢�ä�G.B.���ߥ���Giovanni Battista Amici :1786 - 1863�ˤˤ�ä�1843ǯ��ȯ������ޤ�����
- ���ߥ��ץꥺ��ϡ�ľ�ѥץꥺ��μ��̤����ˤ�����ΤǤ��ʲ����ޡˡ�
- ���ߥ��ϡ����ϡ��ץꥺ���¾�������ʥ��塼�֡����ͤ�������Ʊ�������˼ͽФ���ץꥺ�ࡢ¬���Υ������åȤ˻Ȥ���������ʡˤ�ȯ�������ꡢ����������ʪ���Ⱦ�����ñ����Ȥ߹�����ꡢ�������θ�������ʪ���ͰƤ����ꡢ����ץꥺ�������β��˲�ž������Ȳ�ž�Ѥ�2�ܤ�������ž���뤳�Ȥ�ȯ��������ȡ����ؤ������ǤϤ��Ф餷�����Ӥ�Ĥ��Ƥ��ޤ���
- ����ץꥺ��ϡ������ºݤ�������ץ������ε���ʪ���ؼ�Dove��Heinrich Wilhelm Dove : 1803 - 1879�ˤˤ��ʤ�ǥɡ����ʥ��֡˥ץꥺ��Ȥ�ƤФ�Ƥ��ޤ���
- ���ϡ��ץꥺ���Ȥä��д���ϡ��ݥ����ץꥺ���Ȥä���Τ���٤ơ������ȥ졼�Ȥˤ��뤳�Ȥ��Ǥ�������ѥ��ȤˤޤȤ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����������礭�ʸ��¤���ʪ��˻Ȥ��ȡ�ɬ��Ū�˥��ϡ��ץꥺ����礭���ʤ��д�����֤ε�Υ�������ʤäƤ��ޤ����ͤ�ξ�������ʤ��Զ�礬�ФƤ��ޤ���
- ���äơ����ϡ��ץꥺ�༰���д���ϡ������١�����Ψ������¡ˤΤ�Τ�¿�����Ѥ���ޤ���
- �ޤ������ϡ��ץꥺ��ˤ��ȿ�ͤϤ��٤Ƥ���ȿ�ͤȤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����ᡢ��ʬŪ�˥����ƥ���Ȥä�ȿ�ͤ����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ����ϡ�ȿ�ͤ����٤���ȿ�ͤǤ���ݥ����ץꥺ����礭���ۤʤ�ޤ���
- �����ƥ����Ѥ����⤷���ȤϤ��������Υץꥺ��Ǥ���ȿ�ͤ���٤Ƹ���»��������Ť��ʤ�Τ�����Ǥ���
- ������ͳ����ץ��ե��å���ʥ�桼���ǤϺ����ݥ����ץꥺ�༰���д�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ϡ��ץꥺ������ϡ������γ��٤��������٤ȥХ���ˤ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����γ��٤�90°�ˤǤ��������Ť��ƺ��ʤ������˥��֥꤬�����Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���٤��������٤ϡ���ʪ��θ���30mm����Ψx12���٤��д���Ѥ�3.2"�ȸ����Ƥ��ޤ���
- 3�äȤ����������٤Ϥ��ʤ긷����������ͤǤ���
- �ޤ������ϡ��ץꥺ���������ɡ�ڤ��ӥ��ä��̤äƤ��ʤ��ƤϤʤ�ޤ���
- �����˴�̣�����������������������褦�ˤʤ�ޤ�����Ψ���礭���ʤ�Фʤ�ۤɡ����ϥץꥺ��������������٤˹⤤��Τ��ᤵ��ޤ���
 ��
��
- ��
- �屦�ޤϡ��ºݤ��д���˻Ȥ��Ƥ�����ϡ��ץꥺ��ΰ�ĤǤ���
- ���Υץꥺ���2�ĤΥץꥺ��ǹ������졢ĺ��45�٤������̤�������̤����Ϥˤʤä��ץꥺ��ȡ�22.5°�ζ����̤��ĥץꥺ����Ȥ߹�碌���Ƥ��ޤ���
- ���Υץꥺ��ϡ��߷Ԥˤ��ʤ�ǥ���ߥåȡ�Schmidt�ˡ��ץꥺ��ȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- �ޤ�Ʊ���褦�ʥץꥺ��ι����Υڥ�����Pechan�˥ץꥺ��Ȥ�����Τ⤢��ޤ���
- ���Τۤ������å١�Abbe�ˤ���Ω�ץꥺ�ࡢ�饤�Ĥ���Ω�ץꥺ��ʤɤ�����ޤ���
- �����д������ǽ

- ������2006.09�ˡ��Ȥ�����Ū���д����������ޤ�����
- ����Ź�˽и�����Ū�˹�ä���Τ��ˤȤäƼ�ʬ���ܤdzΤ���Ʒ��ޤ�����
- ��������Ω�äƵ��ˤ����Τ�ͽ���Ǥ���
- ͽ����50,000�߰���ȷ��Ƥ��ޤ�����
- ����ͽ������Ω�Ƥ����̤���ͳ�����ä��櫓�ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �����餯�������ʤǽ�ʬ�����Ǥ����Τ���ˤϤ��������������ʾ���ɤ���Τ����äƤ⤽��ͽ����Dz������褦�ȷ��Ƥ��ޤ�����
- �д���ϲ����ǻȤ����Ȥ�¿���������ߤä��괨���ä���ȴĶ��˸������Ȥ����ޤ���
- ���ΰ�̣���顢�ѴĶ��ˤ����줿�ɿ��ɽ����Τ�Τ����ˤ����ޤ�����
- �����ơ���������Ȥ�����뤯����Ψ��x8����x10���٤��äơ��Ǥ�������ڤ��ơ�1000��ʲ��˥���ѥ��Ȥʤ�Τ����Ӥޤ�����
- �����ƥᥬ�ͤ����ޤޤǻ��ѤǤ��뤳�ȡʥϥ��������ݥ���ȡˤ����Ǥ�����
- ���ξ��ˤ��ä���Τ����μ̿��˼������д���Ǥ���
- ����Ź�ˤϡ�x8����x10���٤��д���������������Ƥ���ޤ�����
- ���ʤ�3,000�ߤ���300,000�ߤ��ϰϤǤ��������ʤ�Τ�����ޤ�����
- �����ʥݥ����ץꥺ���Ȥä���Ρ����ϡ��ץꥺ�����Ѥ�����Ρ����ڥ饰�饹�������ൡǽ����ä���Ρ��������å�������Τʤ������ˤ�������ޤ�����
- ��ϡ��������Ӥδ������顢�ݥ����ץꥺ�༰���д�����礭���ʤ꤬���ʤΤǡ����˼����褦�ʡ����������ȥ졼�Ȥˤʤä����ϡ��ץꥺ�ॿ���פ����Ӥޤ�����
- ���ϡ���Ψ�Ǥ���
- x8��x10�Ǥϳ���Ψ��25%�ۤɰ㤤�ޤ���
- ��������x10�ˤ���ȡ��Ť��ʤä����������ʤä��ꡢ��֤줬�֤��䤹���ʤä��ꡢ���Υ��줬�����ʤ��ǽ�����ФƤ��ޤ���
- ���Τ��Ȥˤ��ʤ��顢x8����x10�ܤ��д���������ȸ���٤ơ��ǽ�Ū�˰ʲ�����ǽ�Τ�Τ�������ޤ�����
- ��
- �ڼ�ʻ��͡�
- ����ʪ��θ��¡�����42mm
- ��������x10
- ���ץꥺ�ࡧ�����ϡ��ץꥺ��
- ���ץꥺ��������BaK4
- ���������ա�Ʒ��Υ�ˡ���16mm
- ����ʪ��θ��¡�����42mm
- �ʥϥ��������ݥ���ȡ��ܴ�����16mm�ܤ�Υ���Ƥ���Ѳ�ǽ��
- ���»볦����6.1����д���λ�����١�
- �����ݤ��볦����61.0��ʼ»볦����Ψ�����͡��д�����礭���Ǥ��Ф��������
- ��1,000m��볦����107m��1,000����ˤ���107m�ޤǤ�ʪ�Τ���٤˴ѻ���ǽ��
- �����ݤ��볦����61.0��ʼ»볦����Ψ�����͡��д�����礭���Ǥ��Ф��������
- ����ϡ�1000 x tan6.1��ǵ����롣
- ���ҤȤ߷¡�����4.2mm����ʪ��θ���42mm����Ψ10�dz�ä��͡�
- �����뤵����17.6�ʤҤȤ߷�4.2mm������͡�
- �������ƥ������ե����������ȡ�PHC��Phase-Coated�˵ڤӥա���ޥ�������ȡ�FMC��Fully Multi-Coated��
- �����뤵����17.6�ʤҤȤ߷�4.2mm������͡�
- �ץꥺ��ϡ����Ȥ˰��ꥺ��������Ȥ����ꡢ���Τ���˲������������Τǡ�
- ������ɤ���̣�ǰ��꺹���������ƥ���Phase-Coated�ˤ��ܤ���Ƥ��롣
- ��ʪ��ʤɤˤϡ�ξ�̤��٤Ƥˤ錄�ä�¿���쥳���ƥ����ܤ���Ƥ��롣
- ������ɤ���̣�ǰ��꺹���������ƥ���Phase-Coated�ˤ��ܤ���Ƥ��롣
- ���ե���������Υ����2m����
- ���礭������153mm x 134mm x 49m
- ���Ť�����670g
- ���ѴĶ������ɿ������������ϴ������ǥѡ��������Τ���С���ʤ����°����Ϫ�Ф��Ƥ��ʤ����ᴨ���ϤˤƤ�Ȥ��䤹����
- ���礭������153mm x 134mm x 49m
- ��
- ���������д�������ʤϡ�ɸ����ʤ�38,000�ߤΤ�ΤǤ�����
- �����˺ݤ��ơ������д���ȺǸ�ޤ��¤ä��Τϡ�Ʊ���������Ʊ����������Ψ���㤤x8�Τ�ΤǤ�����
- x8�Τ�Τϡ���Ψ���㤤��Τ����뤤����ȤƤ�Ȥ��䤹�����Ǥ�����
- �����������뤵�������������Ǥ���ΤǤ����x10�Τ�Τ�����������ä��Τǡ��Ȥ��䤹����Τ����x10�Τ�Τ˷��ޤ�����
- ���������д�������ʤϡ�ɸ����ʤ�38,000�ߤΤ�ΤǤ�����
- �����������ͤ�����
- �д������ǽ������ɽ���������ˡ���ǥ�̾�ˤ�ʤ�10 x 42�Ȥ���ɽ��������ޤ���
- ����ϡ���X�פȤ���ʸ����Ǻ�����Ψ��ɽ����������ʪ��θ��¤��ޤ���
- ��ι��������д����ɽ���ϡ�10 x 42�Ȥ���ޤ�������Ψ��10�ܤ���ʪ����¤�42mm�Ȥʤ�ޤ���
- ����ɽ�������Ǥϻ�����礭���Ϥ狼��ޤ���
 �Τ�Τ�1/10�˰����Ĥ��Ƥߤ뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ������Ȥ����狼��ޤ���
�Τ�Τ�1/10�˰����Ĥ��Ƥߤ뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ������Ȥ����狼��ޤ���- �ޤ�������ɽ������Ʒ�¤�4.2mm�ˤʤ뤳�Ȥ��狼��ʸ��¤���Ψ�dz�ä���Τ�Ʒ�¤Ȥʤ�ˡ������������뤤��Ǥ��뤳�Ȥ�狼��ޤ���
- �ʲ������������˼��������ܤˤĤ��ƽҤ٤ޤ���
- ��
- �� ���뤵
- ���뤵�ϡ����������ͤǤ�Ʒ�¤��������뤵�Ȥ���ɽ�����Ƥ��ޤ���
- ���������д���ϡ�Ʒ����4.2mm�ʤΤǡ����뤵��17.6�ˤʤ�ޤ���
- �����ͤ��礭���ۤ����뤤�д���ȸ����ޤ���
- ��Ʒ��
- Ʒ�¤ϡ���ʪ��θ��¤���Ψ�dz�ä��ͤǤ���
- Ʊ����Ψ�ʤ���ʪ��θ��¤��礭���ۤ�Ʒ�¤��礭���ʤꡢɬ��Ū�����뤤�д���Ȥʤ�ޤ���
- ��ʪ��θ��¤��礭����Τϡ�����ǽ��̤�Ť��ʤ뤿���갷�������ѤǤ���
- ���ޥ��奢��Ū�ʤ�φ25mm��φ50mm���٤�Ŭ���Ȼפ��ޤ���
- �ͤ�Ʒ�ϡ����뤤���2mm���٤��礭�������ꡢ�Ť��ʤä�Ʒ����������7mm���٤ˤʤ뤽���ǡ��Ť��Ȥ�������Ū�Ǥ���С��д����Ʒ�¤�Ʒ���ΰ��ֳ��������֤С�����7mm��˾�ޤ������Ȥˤʤ�ޤ���
- �Ȥ�������Ʒ�¤�7mm����Ĥ�ΤϤʤ��ʤ�����ޤ���
- Ʒ�¤�7��������Ψ��8�ܤ���10�ܤȤʤ�ȡ���ʪ��θ��¤�56mm����70mm�Ȥʤ�ΤǤȤƤ��礭���д���ˤʤ�ޤ���
- ������������д���ϡ���ʪ�����42mm����Ψ10�ܤǤ��뤿��Ʒ�¤�4.2mm��42/10 = 4.2mm�ˤǤ��ꡢƷ�����������ä�7mm���⾮����Ʒ�¤Ǥ���
- �������������д���Ƿ��ߤ��ꡢ���Ƥ⽽ʬ�˸����ޤ�������ϥ��졼�������Ф餷�����쥤�˸����ޤ�����
- ����ܤ�Ʒ���¤ϡ���Ǥ�4�������٤ʤΤ��⤷��ޤ���
- ŷʸƱ��������ξ���ˤ��ޤ��ȡ��ͤ�Ʒ����ǯ�ȤȤ�˽̾���50����Ǥ���5mm���٤ˤʤ뤽���Ǥ���
- ��ʪ�ˤ褯�Ƥ���7mm��Ʒ���¤�20�ͤ���ǯ���礭���������Ǥ���
- �������Ƥߤ�ȡ������д���ϻ�ˤ��礦�ɤԤä�������뤵����äƤ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ǯ�����ܤ������ʤ��ʤ�Ť����طϤˤʤäƤ��ޤ���ʪ�����뤯�Ȥ餵�ʤ��Ƚ�ʬ�˸����ʤ����Ȥ��褯����Ǥ��ޤ���
- �Ρ��䤬�㤫�ä���������ν�Ϸ�ο��ͤ���ȻŻ�����ˤ����Ȥ����������ϥǥ������ס���Ǯ�ŵ�ˤ��䤨���긵�ˤҤ��褻���ʤ�Ȥ餷�ƺ�ȤƤ����Τ�פ��Ф��ޤ���
- �����λ��20����ˤϾ����ޤ֤������餤�����뤵�Ǥ�����
- ��μ̿��ϡ��д�����ܴ���������ߤ���ΤǤ���
 �ܴ��θ��¤ϡ�21mm�⤢��ޤ���
�ܴ��θ��¤ϡ�21mm�⤢��ޤ���- Ʒ�¤�4.2mm�ʤΤˤ���5�ܤ���礭�ʥ���ܴ�����ޤäƤ���ΤǤ�������Ϥ���äȹͤ�����ԻĤʵ������ޤ���
- �ɤ����Ƥ���ʤ��礭���ܴ����Ĥ��Ƥ��뤫�Ȥ����ȡ�������ͳ�ϰʲ��ǽҤ٤�볦�γ��ݤˤ���ޤ���
- �ܴ��θ��¤��礭���Ȥ������ȤϹ����ϰϤλ볦�������뤳�Ȥ��̣���Ƥ��ޤ���
- ��ʪ����Ȥ館��ʪ������Ǥ�������������褦�Ȥ����硢�ܴ��θ��¤��礭����Τˤ��ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ��ưפ������Ǥ��ޤ���
- Ʒ��4.2mm�ϡ�����������Ǥʤ��Фᤫ��ߤƤ�Ʊ���礭����4.2mm�����ݤ���Ƥ��ʤ���С��ܴ��ˤ��äĤ���Ʒ��ư���ơʴ�夬��ž���ơ˻����õ�ä��Ȥ��ˡ�����������θ�����ʤ��ΤǰŤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ����������ͳ���顢����ι����ܴ��Ǥ�Ʒ�¤����礭�ʸ��¤ˤʤäƤ���ΤǤ���
- ���μ̿��ϡ�Ʒ��4.2mm���ܴ��θ��¤�21mm�Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �д���������ƼФᤫ���ܴ��������Ƥ⡢Ʒ�¤��礭�����Ѥ����˸����ޤ���
- ���η�����+/-3�٤ۤɤǡ����줬�»볦6.1�٤κ���ȤʤäƤ��ޤ���
- �볦�������ΤϤʤ�ȸ��äƤ�Ȥ��䤹����ΤǤ���
- ��
- �����������д���ϡ������Υ��줬���Ф餷���ɤ������뤯�������ƻ���ι�����ΤǤ�����
- �д���Ϻ��ޤǤ��ޤ�Ȥä����ȤϤʤ���������30ǯ�ʾ�����ˤ�ι�Ԥ����ޡ�ͧ�ͤλ��äƤ����д����ڤ�Ƹ����������������ˤ��ꡢ���ΤȤ�����˾������������뤤ʪ�Τβ��Ǥ��Ŀ����ֿ����鷺���ˤˤ���Ǥޤ�����
- �뺧���ơ��������Ҷ���Ϣ��ơ�����������ɥޡ���������̤ȤԤ������Ϥ�ι���Ϥ�ˬ�줿�ݤ˾��ߤ���Ƥ��륳�����д����Ȥ碌�Ƥ��ä����⡢����Τ褤���Ȥ�������������ޤ���
- ������������Τ����д�������Υ��줬�褯�ƿ��礤�����Ф餷���褫�ä���
- ����ܤǸ�����⡢�д�����̤��Ƹ��������ֿ����Ŀ������䤫�Ǥ�����
- �д���⤳���ޤ�ͥ���ˤʤä��Τ��Ȼפ����ˤ��ޤ�����
- �����餯BaK4�ץꥺ��Ȱ��꺹���������ƥ��ˤ��꤬�礭���ȴ����ޤ�����
- ��
- ��
- ����˾������ܴ���Eye Piece��Ocular������200610.12�ɵ���

- �����������д���ϡ������Υ��줬���Ф餷���ɤ������뤯�������ƻ���ι�����ΤǤ�����
- �ܴ��ϡ��������ν�Ǥ��ޤ�����
- �ܴ�����ˤϡ�˾������д����¬�����ʤɤμ��פˤ�ä���ǽ���褯�ʤ�ޤ�����
- �ܴ�����ǽ�ϡ���Ρֻ볦�פν�Ǥ�Ҥ٤��褦�ˡ��Ǥ�����������ϰϤλ볦�С��Ǥ��뤳�ȡ��������ʤɤμ�������������ȡ��Ǥ���������뤤���ȡ��ᥬ�ͤ��Ƥ��Ƥ⽽ʬ�˻�ǧ�Ǥ���Ʒ��Υ��Ĺ����ΤǷ����ޤ���
- �ܴ��ϡ����Ū�˸���ȡ���������ŷʸ�ؼԥۥ��إˤ�äƸ��������졢���˥����ꥹ�ε������Ѽԥ�ॹ�ǥ��Ȥ�����Τ褤��Τ��ꡢ����˥ɥ��Ĥθ��ص��Ѽԥ���ʡ����������θ��������äư���δ����ޤ���
- �����������θ塢�볦�ι�����Τ��ͰƤ��줿�ꡢ���뤤���طϤκ��Ѥ�Ʒ��Υ��Ĺ���ϥ��������ݥ���ȡ�high eye point�ˡ�high eye relief�ˤΥ�������褦�ˤʤꡢ���ߤ����Ǽ����ξ��ʤ���γ�ȯ��³�����Ƥ��ޤ���
- ���Υ����ϡ�35mm�Dz��ѤΥ����ʥ���ե�å����ˤǤ���
- ���Υ����ο����椫��Ф����ͤ��ФƤ��������Τ�Τ������ե���������ʥ����ԡ����ˤǤ���
- �����ե�������Ϲ⤤��Ψ���ᤵ��ʤ������ԡ����Ǥ��������������뤤�����ԡ��������̤��Τ褦��Ĺ����������ΤˤʤäƤ��ޤ���
- �ޤ������˼�����ŷ��˾����ѤΥ����ԡ����ϡ��ƹ�TeleVue�ҡʼ�Ĺ��Albert Nagler��1939���ϡ�1977ǯ����Ω�ˤΥʥ��顼 ������5�ȸƤФ��
 ��ΤǤ���
��ΤǤ��� - �����ܴ��ϡ�2�������φ50.8mm�ˤ��ܴ�����˼���դ����Τǡ��ᥬ�ͤ����ޤޤ��������Ȥ��Ǥ���Ʒ��Υ12mm���ϥ��������ݥ���ȥ����סˡ��������볦82°����Ĺ������ΤǤ���
- ������Υ��f20mm�Ǥ����������٤���Ψ����äƤ��ޤ���
- ���Υ�ϡ��礭����2�������φ50mm�ˤǽŤ��� 1kg �⤢�뤿�᤺����Ȥ����礭�ʤ�ΤǤ���
- ����ϡ��˥å�������f180mmF2.8���٤��礭���ȽŤ���ɤŨ�����ΤǤ���
- ���Υ��ȡ������������ԡ����ȤϤ��ʤ�㤦���Ȥ��狼��ޤ����������ǤϤ����������������������Ǥ��ޤ���
- ��������Ȥ����Τϡ����Τ��餤���礭���ܴ���ɬ�פǤ��뤳�Ȥ��Ƥ���Ƥ��ޤ���
- ���θ��طϤϡ��ʥ��顼5���Τ�ΤǤϤ���ޤ���Ʊ��������Υ�����Ǥ���ʥ��顼�ι��볦�ܴ����إ쥤�����ȤǤ���
- ������������ϥ�����ʥۥ�����˥����פ��ॹ�ǥ���ʡ����ܴ�����٤�ȿ�ʬ�Ȱ㤦���Ȥ��狼��Ȼפ��ޤ���
- �ޤκ�ü�ˤ�������������Υ�ˤʤäƤ��ޤ���
- ����ϥϥ��������ݥ���Ȥˤ��������Υ��Ȥ��Τ������Ǥ���
- ���ϡ������볦�����뤿������¥�ˤʤäƤ���Τ��狼��ޤ���
- ��

- ��
- ��
- �����볦��Field of Vision��Field of View��Visual Field��
- ��������Ψ���⤯�Ƥ���ϰϤ������ʤ��褦�Ǥ�˾�����̥�Ϥ�Ⱦ���Ǥ���
- ������������Ψ�����뤯�����ơ��������갷�����ڤǤ���Ȥ����Τ�˾������д���ˤ����ۤǤ���
- �볦�ϡ�˾����������Ƹ����������ϰϤǤ���
- �볦���礭������礭���ۤɹ����ϰϤ���٤˸��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �볦�ϳ��٤�ɽ���졢�볦��˾�������Ψ��ݤ���碌��ȸ��ݤ���λ볦����ޤ�ޤ���
- �볦�ζ���˾�������Ū���о�ʪ��õ�����Ƥ�Τ˶�ϫ���ޤ���
- �ޤ��д���Ǥϡ��С��ɥ����å��Ȥ����ϡ����ݡ��Ĵ���ʤɤ˻Ȥ����������Τ�ư����Τ�¿�����볦�����������Ȥ��䤹���ʤ�ޤ���
- �볦�ϡ��ܴ�����ǽ�ˤ�ä��礭���Ѥ��ޤ���
- ˾������ܴ��ϡ��������볦�γ��ݤ�Ʒ��Υ�ʤҤȤߤ���ꡢeye relief��eye clearance��= �ܴ��δ�¦�Υ���̤����ܴ��μͽ�Ʒ�ޤǤε�Υ�ˡ�����ȳ�����Ψ���礭����ǽ���ǤȤʤ�ޤ���
- �ͤλ볦�ϡ����뤹�����50������λ��������ޤ���
- �������äơ����λ��˾��������֤Ȥ��ΰ�Ĥ��ܰ¤ˤʤ������Ȼפ��ޤ���
- ���ݤ��볦��50�٤��ⶹ���Ǥ��ȡ������꤫�������Ƥ���褦�ʴ��Ф������50�ٰʾ�Ǥ��ȥ��ȥ쥹̵��˾�����������褦�ˤʤ�ޤ���
- �ߤ�����Ф�äȻ�������ʤ��˾�����ȤäƤ��봶�����ʤ��ʤäƤ��ޤ���
- �볦�ϡ��������ʤ�����Ψ��夲��ȶ����ʤ뷹���ˤ���Τ�̵�Ǥ˹����Ȥ뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ���ݤ��볦��50���������Ψ��8�����٤��д����˾�ޤ����ǽ���ܰ¤Ȥʤ�ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
- �����»볦�ȸ��ݤ��볦����
- �»볦��˾�����ȤäƸ�����ºݤλ볦��ω�ˤǤ��ꡢ���ݤ��볦��˾����dz��礵�줿���λ볦��ω'�ˤǤ���
- ξ�Ԥˤϡ�
- ���ݤ��볦��ω'�� = M x �»볦��ω��
- �δط�������ޤ���
- ���μ����ľ���С�
- ��
- ����M = ��'/�ء���������Lens57��
- ��
- �Ȥʤ�ޤ���
- ���δط������鸫��ȡ���Ψ10�ܤ�˾����Ǥϡ�3��μ»볦��30��θ��ݤ��볦�Ǹ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ºݤˤϡ���ʪ����ܴ����Ȥ߹�碌�Ǥ������������ޤ�Τǡ��ޤ����ܴ��λ����ω'�ˤ����äơ������˾�������ΨM����̣����Ƽ»볦��ω�ˤ���ޤ�ޤ���
- �ܴ��λ����ω'�ˤ�������й����»������ݤǤ��ޤ���
- ���ݤ��볦�Ͽʹ֤�ɸ��Ū�ʻ���Ǥ���40-50����ߤ����Ȥ����Ǥ���
- ����ʲ��Ǥ��ȡ�������ޤ�˾����α�ʱ߷��ˤ�������褦�ˤʤ�ޤ���
- ���ݤ��볦�������ȴѻ����ڤǤ���
- ˾������ܴ��ˤϡ���˽Ҥ٤��ʥ��顼�Τ褦��80°��90°�ι��볦����Ĥ�Τ����Ƥ��ޤ���
- ������������ȥ�������Ƥ���Ȥ��������������ʤ��Ǥ��礦��
- ��
- ����Ʒ��Υ��Eye Relief��
- �ܴ�����ѻ�����Ʒ�ޤǤε�Υ��Ʒ��Υ�ȸ����ޤ���
- Ʒ��Υ��û���ȴ���ܴ��ˤԤä���Ȥ��äĤ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- ���Τ褦���ܴ��ϡ��ᥬ�ͤ������֤Ǥ������Ť餯�ᥬ�ͤ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- Ʒ��Υ��Ĺ�����ܴ�������Υ���ƽ�ʬ�ʻ볦�������ޤ���
- ���������դ�Ʊ���褦�˻Ȥ�����դ˥������ݥ���ȡ�eye point�ˤ�����ޤ���
- �����ݥ���Ȥϡ�Ʒ��Υ�ΰ��֤������դǤ�����Υ�ǤϤʤ����֤Ǥ���
- ������ˤ��Ƥ�ξ�Ԥϻ����褦�ʸ��դǡ������褦�ʾ����ǻȤ��ޤ���
- Ʒ��Υ��Ĺ���ܴ���ϥ����������դȤ��ϥ��������ݥ���ȤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ���������ܴ��ϥᥬ�ͤ����ޤޥ���������Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- ����Ʒ�¡ʤҤȤߤ�����exit pupil��
- �����Ѹ�μͽ�Ʒ��Ʊ����̣�Ǥ���
- �ͽФ���������Ʒ�ΰ��֤Ǥ��٤ƽ��ޤ��«�η¤�ҤȤ߷¤ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ���äơ����ΰ��֤˿ͤδ����äƤ����˾����ǤȤ館�����٤ƤȤ館�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����������ܤ���äƤ��Ƥ⡢���˻��äƤ��Ƥ⡢Ʒ���������«�ϥ����Ƥ��ޤ���������Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���礦�ɸ������������������Τ˻��Ƥ��ơ����˶�Ť��ʤ��ȸ���˼פ�������ͻҤ���ʬ�˸����ޤ���
- ����ΰ��֤�Ʒ���֤Ǥ��ꡢ������礭����Ʒ�¤Ȥʤ�ޤ���
- ��ˤ�Ҥ٤ޤ������ͤ�Ʒ����7mm������ǡ�ǯ���Ϥ�����⾮����5mm���١ˡ���������礭��Ʒ�¤���ä��ܴ����äƤ�Ʒ���֤ǤϿͤ�Ʒ���¤������Ѥ��ޤ��餢�ޤ��̣��ʤ��ޤ���
- �ͤδ�λ��Ѥ˸¤ä��ܴ��Ǥ���ʤ�Ʒ�¤�7mm����н�ʬ�Ǥ���
- ��ʤ��ǯ���ʤΤ�5mm�ǽ�ʬ�Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- Ʒ�¡ʣ�ˤϾ�����������������Ǥ�Ҥ٤ޤ����褦�ˡ�˾�������ʪ��θ��¡�D�ˤ���Ψ��M�ˤdz�ä���ΤǤ���
- ��
- ����d = D / M����������Lens58��
- ��
- �ޤ����ܴ�������ˤ���������ʪ��������ä��ܴ���ȴ�������«�Ƥ�Ʒ�¤��礭�����Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
- ����˾�����ʪ���Objective��������200610.16�ˡ���200611.19�ɵ���
- ˾�������ʪ��ϡ�����ʪ�Τ��������־�˼����Τʤ��ɹ������Ȥ��Ʒ��������뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ʪ�Τ������ˤ��뤿�ᡢ��ʪ��ξ�����Υ��Ĺ���ʤꡢ¿����f400mm��f2000mm���٤Ȥʤ�ޤ���
- ���Ф�ŷ��˾�����ϥå֥뱧��˾����˻Ȥ��Ƥ������ξ�����Υ�ϡ��⤦����礭����f15,000mm��f57,600mm�ȤʤäƤ��ޤ���
- �����������äƤ���ʪ�θ��ϡ��������٤����������ʪ�������Ť��ʤ�ޤ���
- ���Τ��ᡢ���ͤ������Ǥ���������������ɬ�פ������¤��礭�����ʤ���Фʤ�ޤ���
- �����������¤��礭�������������������ɽ���Τǡ����������������ʤ���Ǥ���������뤤����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ޤ������¤��礭�����φ200mm�ʾ�ˤǤ��ɼ��ʸ��إ��饹�����꤬���Τǡ�¿���ξ�硢Ʃ��������ȿ������˴ط��ʤ�ȿ�Ͷ��ʱ��̶��ˤ��Ȥ��ޤ���
- �Ͼ��ʪ�Τ���Ū�ˤ϶����ʥ��˾������褯�Ȥ��ޤ��������ʤɤ�ŷ�δ�¬�Ѥˤ�ȿ�Ͷ��ʱ��̶��ˤ��Ѥ���ŷ��˾������Ȥ��ޤ���
- ȿ�Ͷ��ϡ����������Фʤ�ȿ�̡����̼�������äƤ��ޤ���
- �����Ǥ����������������⸽��ޤ���
- ���μ����ϡ����̶��ν�̿���ἴ�����ι�ȡˤǤ���
- �������äơ����̶��ϸ�������㤯�����뤤���طϤˡˤ��뤳�Ȥ��Ǥ�������Ѥ��礭����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���η����ϡ��������ʤ���ŷ��˾����Ǥϲ����Ǥ���ʲ������ʤ���Фʤ�ʤ��ˤ�ΤǤ��뤿��ˡ��礭��ŷʸ���˾����ǤϤۤȤ�ɤȸ��ä��ɤ����餤�˱��̶���ȿ�ͷ�������Ƥ���ΤǤ���
- ��˻��ܤ�Ĥ��ʤ��緿ȿ��˾����Ǥϡ���������ǵ��̼����νФʤ���ʪ�̶����Ȥ�줿�ꡢ�������طϡ��ޥ����ȥա����������������ߥåȥ���ʤɡ˺��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- �ʲ�����ɽŪ��ŷ��˾����μ�����ޤ���
- ��������˾����ʥ��ץ顼����
- ˾����κǽ���������ޤ�ɽ���������פǤ���
 ���Υ����פϡ�2�Ȥ��̥���ǹ�������Ƥ���Τ���ħ�Ǥ���
���Υ����פϡ�2�Ȥ��̥���ǹ�������Ƥ���Τ���ħ�Ǥ���- ���Ū�˸���ȡ�����˾�����Ʊ��������°���륬��쥪��˾�����ȯ���θ塢1615ǯ�˺���ޤ�����
- ����˾����Ǥ���ɽŪ�ʤ�ΤʤΤǡ��ǽ���������ޤ���
- �д�������Ū�ˤϤ��Υ����פ�°���ޤ���
- ����˾�����ºݤ˺�ä��Τϥ��ץ顼�ǤϤʤ�����������դ��������ǡ����㥤�ͥ뤬�����������˾�������ޤ�����
- ���ץ顼���Դ��Ѥ��ä��褦�Ǥ���
- ���ץ顼��Johannes Kepler, 1571 - 1630���ȡˤϡ�1609ǯ�˺��줿����쥤��˾���������ǽ�Ϥ����ܤ��Ƹ��ؤθ����Ϥᡢ2ǯ���1611ǯ�ˡض����ء٤Ȥ����ܤ�Ф��Ƥ��ޤ���
- �����ܤˤ��Ͼ�˾�������ʪ����ܴ��θ��طϤ˴ؤ����ϩ�ޤε��Ҥ�����ޤ�����
- ���ץ顼��˾����ϡ�����쥪���η����Ǥ����������Ȥ�ʤ����Ȥ�������Ƥ��ޤ�����
- ������������˾����Ǥ�����ȿž���Ƥ��ޤ���Ω���η���������ޤ�����
- ��������ŷ�ΤϤ���ۤ�®��ư����ΤǤϤʤ��Τǡ����η�������¾��Ĺ�꤬�褫����Ƹ��ߤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ץ顼�ϡ���ʬ�ιͤ���˾�������Ω���ˤʤ�����ˤ��Ƥ��ơ�ɬ�פǤ�����̥��˲ä�����Ω�����Ѵ������ˡ��ض����ء٤���˽���路�Ƥ��ޤ���
- �д���Ǥϻ�����Ȥꤿ���ط��奱�ץ顼����˾��������Ѥ��졢����Ȥʤ���Ω���˴ؤ��Ƥ������˥ץꥺ��ʥݥ��ץꥺ�����ϥץꥺ��ˤ��������Ω�����������Ƥ��ޤ����д�������ˡ�
- ������˾����ϡ��˥塼�ȥ��ȯ������ȿ��˾����������褦�ˤʤäư��ټ�®���ޤ���ȿ�Ͷ��Τۤ��������Ȥ��Ƥ�������¿���ä�����Ǥ���
- ��������1757ǯ�����ꥹ�Υɥ���ɡ�John Dollond����ॹ�ǥ�ε���ˤ����ä����ȯ���ơ��������Υ�ɤ�Ω�Ĥȶ���˾����Υ֡��ब�����ơ�1900ǯ�ޤǤ��緿�ζ���˾���������ƹԤ��ޤ���
- �ɥ��ĤΥե饦��ۡ��ե����ϡ�����˾�������ǽ������礭�������ޤ�����
- ���ʤߤˡ�����˾����Ǻ���Τ�Τϡ�1897ǯ�˺��줿�ƹ��������°�䡼������Yerkes��ŷʸ��Τ�Τǡ�����40�������101.6cm�ˡ�������Υf1,935.494cm��F19.05�Ǥ�����
- ���ε���ʶ���˾����ϡ����ߤ�ޤ�����ǻȤ��Ƥ��뤽���Ǥ���
- 1��ȥ�⤢�����ʥ��饹��ϡ�����ŷ��˾������о줹�뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ������ͳ�ϡ�1850ǯ��˥��饹�˶��å������ˡ����Ω��������˾�����������¤�ȿ�Ͷ�����Υ�ɤ����ä�����Ǥ���
- ̮���ʥ��饹�����θ���Ū��١ˤξ��ʤ�����¤θ��إ��饹�������Τϡ�1��ȥ�¤��³��Ǹ�¸�������ŷ��˾�����1��ȥ���¤�����ȤʤäƤ��ޤ���
- ��
- �����䡼����ŷʸ��
- �䡼������Yerkes��ŷ��˾����η��ߤ��äƤϡ����⤷�������ԥ����ɤ�����ޤ���
- 19�������˲в֤餷�Ƥ�������¶���˾����η��߶���ϡ��������Ѥ����ޤ�ˤ����ꤹ���뤿����Ŀ���©�ξ��֤ȤʤäƤ��ޤ�����
- �䡼����ŷʸ��˻Ȥ�줿��⡢��ظ��浡�ؤ��ʤ�Ƥ���˾������߷ײ褬ͽ��DZ�к���ˤʤä��ܺä���������Τ�������ؤ�24�ͤμ㤭���������硼�����ء����George Elley Hale��1868 - 1938�ˤ�����Ū������Ӥˤ�ä�Ω��ľ�뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- �ء���ϡ����˶��迴����������Ū��ŷʸ�ؼԤǡ�ŷʸ�ؤΤ��Ȥʤ������狼��ʤ����������⤤�Ƶ������ʧ�碌��ŷ��Ū�ʼ��Ӥ���äƤ��ޤ�����
- ��ϥ�������Ŵƻ����ɴ��Ĺ�ԤΥ��㡼�륺���䡼������Charles Tyson Yerkes�ˤ���⤭���緿˾������ߤ�ɬ�פ�30�����ɥ������褦�ݤ���ߡ������������ꤷ���Ǹ�ˤ϶�����������Ʊ�դ����ޤ�����
- �䡼�����ϡ��Ϥ����Ȳ���������Ĥޤ�˾����Τߤλ����Ʊ�դ��������Ǥ��ä������Ǥ������ء���ˤ���˸��⤫���ŷʸ�����Τη�������34��9000�ɥ�����������Ǥ���
- ����������ꥫ�ʤ�ǤϤ��äǤ���
- �ء���ϡ����θ����������ȸ��⤭����ե���˥��Υ����륽��ŷʸ���1908ǯ���л���ٹ�John D. Hooker�ˡ��ѥ��ޡ�ŷʸ���1928 - 1948ǯ���л�ϥ��å��ե��顼���ġ�1,250���ɥ�ˤʤɤ��緿���ߤ��ȷ��ߤ��Ƥ����ޤ�����
- ��
- ��������˾����ʥ���쥪����
- ����˾����ϡ�˾���������Ȥ������٤���ΤǤ���
- ����쥪��Galileo Galilei��1564 - 1643�ˤ�ȯ��������ΤǤϤʤ���1608ǯ�˥������Υᥬ�Ͳ��ϥ���ڥ륷����Hans Lippershey��1570 - 1619�ˤ��õ��������ƻ��β�������Τ�1609ǯ��ŷʸ��ʬ��˱��Ѥ��٤��ब���ɤ��ơ�ŷ�δ�¬�˽��ƻȤä��ΤǤ���
- ���פ�ȯ�Ƥ����ꡢ�ϳؤ��ۤ����굡���ųݤ�������깥�����ä�����쥪�Ǥ����������ؤ˴ؤ��ƤϿ����Τ����ޤ��˷�¬���ʤȤ��Ƥ�����Ϳ���Ƥ��ޤ���
- ��������̾��ŷʸ�ؼԤ����ؤ�縦��ơ��ޤȤ����Τ��Ф��ơ���Ͽ����ؤ�뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ����쥪���Ѥ���ŷ��˾����ϡ�����42mm��Ĺ��2.4��ȥ����Ψ9�ܤΤ�ΤǤ�����
- ��ϡ�������60�ܰʾ��˾������ꡢ�ǽ�Ū�˸���56mm��32�ܤ�˾�������ޤ�����
- ȯ��������˾����θ��¤�42mm�Ǥ��ä��Ȥ����Τϡ����ߤΰ���ե����Υ�����٤��礭���ǡ����ߤ���ߤ�Ⱦ��������¤Ǥ���
- �����⡢�ब�����˾�����κ���ϡ��ӥ�䥳�åפ˻Ȥ������٤Υ��饹���ä��Τǡ�Ʃ���٤�Ѽ���������������������ʤ�¿���ƤޤȤ�˻Ȥ���˾�����1�����٤��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����쥪����ä�˾����ϡ��Ȥ��Ƥ���2�ĤΥ�Τ�������ʪ����̥��Ȥ����ܴ��ϱ�����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ������٤ư���Υ�ǹ�������Ƥ��ơ����ä��ʿ����������ˤȤϤʤäƤ��ޤ���
- ��λ���ˤϿ��ä��Ȥ�����ǰ���ʤ��ä��ΤǤ���
- ���˾����Ǥϡ��ܴ�����Υ��Ȥ����Ȥˤ�ꡢʪ�����ȳ�������Ʊ�����֤������Ȥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �������������������Ȼ볦�������ʤ�Τǡ���ǯ��ŷ��˾����ϡ���Ω���ˤʤ�˥��ץ顼��˾�����¿������ޤ�����
- ����쥪�������˾����ΰ�ĤǤ������37.5mm��Ĺ��1,280mm��15�ܤΤ�Τϡ��»볦����6'��6ʬ�ˤǤ��ä������ǡ�����Ϸ�λ�ľ�¡�30' = 30ʬ�ˤ���1/5�����ʤ�ʤ����ᡢ�����Τ뤳�Ȥ�����Ǥ�����
- ����Ū�˥���쥪��˾����Ǥ���Ψ���夬��ˤĤ졢�볦�Ϥ�������ȿ���㤷���ɤ�ɤ�볦���������ʤ�ޤ���
- ���ץ顼���Ǥϡ���������ǤϤʤ����Ǥ���ΤǤ��κ��������Ǥ���
- ��Ψ��夲��о夲��ۤɥ���쥪���������ˤʤ�ޤ���
- ��λ��äƤ����д���ϸ��¤�42mm����Ψ10�ܡ����ݤ�����Ѥ�61�٤���ޤ���
- ����쥪���ǽ�˺�ä�˾�����Ϥ뤫��ο������ǽ�Ǥ���
- ����д���ǤϷ�٤Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ������뤯�����������Ȥ��ƴѻ��Ǥ��ޤ���
- ���졼���ʤɤϤ��ä�����⤭�夬�äƸ����ޤ���
- ;�̤Ǥ���������쥪�ϼ�ʬ�Ǻ�ä�ŷ��˾��������ۤ�ѻ����ƹ�����ȯ�����Ƥ��ޤ���
- �����餯��������ۤ������ƹ����ʤɤδ�¬��Ĺ���֤�����ΤȻפ��ޤ���
- ���Τ�������ǯ��1637ǯ���Ҵ����1638ǯ�ˤ�ξ�ܤ�������Ȥ����Թ����ܤˤ��äƤ��ޤ���
- ��
- ����ȿ�ͼ�˾����ʥ˥塼�ȥ�
- ����쥪�䥱�ץ顼��˾����η������Ĥޤ��ʶ����طϡˤ�Ȥä��ΤǤϿ�����������ʬ��ǽ����⤷����ǽ���夬��ʤ����Ȥ���Ѥ�����ƤȤ��ƹͤ��Ф��줿�Τ�ȿ�Ͷ��ʥߥ顼�˼�˾����Ǥ�����
- �˥塼�ȥ����ͰƤ��ƺ��夲���Τ�1668ǯ�ǡ����ץ顼������˾������äƤ���30ǯ�ʾ��ФäƤ��ޤ���
- ���˾����ϡ�ȿ�Ͷ���ľ�¤�1�������25.4mm�ˡ�������Υ��6�������152.4mm�ˤ���Ψ��30 - 40�ܤǤ��ä������Ǥ���
- �������F6�ȤʤäƤ��ޤ���������������������ȿ��˾����Ǥ�����
- �˥塼�ȥ�ϡ�3ǯ���1671ǯ12��ˡ������礭������34mm��������Υ159mm����Ψ38�ܤΤ�Τ������Ω�ز��Royal Society�ˤ˴�£���Ƥ��ޤ���
- ȿ�ͼ�˾����Ǽºݤ����Ω�Ĥ�Τ��ä��Τϡ��˥塼�ȥ��ȯ������55ǯ�Фä�1723ǯ�ǡ��ϥɥ쥤��J. Hadley 1656 - 1742�ˤˤ�����6�������������Υ5�ե����ȡ�������F10����Ψ230�ܤΤ�ΤǤ�����
- �˥塼�ȥ������17�����ϡ����٤ι⤤���إ��饹����¤���Ѥ���Ω����Ƥ������ä����ʤ��ä��Τǡ���μ�ä������������Ȥ��Ƥ��ɤ������ǥ��Ǥ��ä��ȸ����ޤ���
- ��������19�����ˤʤ�ȸ��إ��饹��¤���Ѥ����⤷���������ص���⤹�Ф餷�������뤲�ޤ�����
- �ߥ顼��Ȥä�ȿ���طϤϡ�����¤Τ�Τ�����Ǥ���Ȥ������åȤ�����ȿ�̡������볦�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����������������ä��Τǡ���������Ͼ�˾������д���ʤɤˤ�ȿ�Ͷ��ˤ���ϤۤȤ�ɤʤ��ʤ�ޤ�����
- ȿ�Ͷ���Ȥä�ŷ��˾����ϡ�19�����θ�Ⱦ�˥��饹��ɽ�̤˶��å����Ǥ���褦�ˤʤä�����²����ʤߤޤ���
- ���ߤ�ŷʸ���ŷ�δ�¬�˻Ȥ���˾����ϤۤȤ�ɤ�ȿ�Ͷ����Ǥ���
- �礭��ŷ��˾����Ǥϸ���10m�Τ�Τ����Ƥ��ޤ���
- �����Υ�ǤϤ���ۤ��礭�ʤ�Τ��Բ�ǽ�Ǥ���
- ��
- ����ȿ�ͼ�˾����ʥ��������
- �˥塼�ȥؤ�ä�ȿ�ͼ�˾���������ˤϡ������åȥ��ɤο��ؼԡ�ŷʸ�ؼԥ��쥴���James Gregory��1638��1675�ˤαƶ����礭���ä��褦�Ǥ���
- ���쥴���1661ǯ��ȯɽ������Optica Promta�ʿ��⤷�����ءˡ٤˥ҥ�Ȥ����ơ��˥塼�ȥ�ȿ��˾�����������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���쥴����Ȥ��������ꤷ�ޤ��������ޤ�����Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- .
- ����������Laurent Cassegrain��1629 - 1693��ʩ�ˤ⥰�쥴����ͰƤ���ȿ�ͼ�˾�����1672ǯ������ޤ�����
- ���������˾����ϡ�ȿ�Ͷ����濴���˹�����������������̶��ˤ�ᥤ��ȿ�Ͷ��ʱ��̶��ˤ���������¦�ˤˤ����Ƹ�ϩ���ޤ�ʤ���褦�ˤ������֤��Ƥ���ޤ���
- �������뤳�Ȥˤ�ꡢ������û��������åȤȸ��������פ���Ȥ�������������ˤʤˤ��⡢����Ǥ�����̶��ε��̼����������Ǥ�����̶�������뤹�빽¤�Ȥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ������ħ���褫����Ƹ��ߤμ��ŷ��˾����ϡ��������������ӥ�������β��ɷ��ˤʤäƤ��ޤ���
- ��
 ���ޥ����ȥա�����������Maksutov-Cassegrain��˾���
���ޥ����ȥա�����������Maksutov-Cassegrain��˾���
- ���������˾�����ͭ̾�ʤ�Τˡ��ޥ����ȥա�D. D. Maksutov��1896-1964�����ӥ��Ȥθ���ʪ���ؼԡˤ��߷פ������������˾���������ޤ���
- ����˾��������줿�Τϡ�1941ǯ�ȸ����Ƥ��ޤ����顢��������������γ�ȯ�Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ȿ�ͼ�˾����ϡ��������� �������˸����ΤǤ��������Τ���ˤ��������ʹ��פ��ʤ���Ƥ��ޤ�����
- �ޥ����ȥդ�ȿ�Ͷ������˶��ޥ�ʥ�˥�������ˤ��֤��ơ������طϤ�ȿ���طϤ��������Ȥ߹�碌�Ƽ�������������F10���٤����뤵���ǽ�Ȥ��ޤ�����
- ����˾����ϡ�������û���Ǥ���Ȥ�����ħ�ʳ��˶��������������˥��������ʤ�����Ȥ��Ǥ��뤿��ˡ��������̩�����뤳�Ȥ��Ǥ������ⵤή���ޤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �ޤ���˥����������������ƥ�������������������뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ�������٤��륹�ѥ������ʻٻ����ˤ��ӽ����뤳�Ȥ��Ǥ������Υܥ��������ͤȤʤ餺����ľ�����Ȥʤ�ޤ���
- �ޤ�������˾����Ϥ��٤Ƶ��̤θ���Ǻ�뤳�Ȥ��Ǥ���¾��˾����Τ褦������̸���Ȥ��ж��̸����ɬ�פ��ʤ��Τǡ�����䤹���²��ˤǤ���Ȥ�����ħ����äƤ��ޤ���
- ���Τ���ˡ��Ƕ�Υ��������˾����Ϥ��٤Ƥȸ��ä��ɤ����餤�˥ޥ����ȥա����������˾����ˤʤäƤ��ޤ���
- ȿ���طϤ�˾����˶����طϤ����줿�ϥ��֥�å�˾������ǥ����ץȥ�å���Catadioptoric��˾����ȸ����ޤ���
- ���ʤߤˡ������ǥ����ץȥ�å��Ȥ�ȿ�Ͷ����ؤȤ�����̣�Ǥ��ꡢȿ���ؤ�cataoptrics�������ؤ�dioptrics�ȸ����ޤ���
- �ʲ��˼�������ߥå�˾����⥫���ǥ����ץȥ�å����Ǥ���
- ��
- ��
- ��������¾��ȿ��˾���1�ʥʥ��ߥ�����
- ��
- �ʥ��ߥ���ȿ��˾������ä��ʥ��ߥ���James Hall Nasmyth��1808 - 1890�ˤϡ������åȥ��ɤΥ��˥��ʵ������Ѽԡˤǥ��ƥ�����ϥ�ޡ���ȯ���ԤȤ���ͭ̾�ʿͤǤ���
- �����������åȥ��ɤϡ���åȡ�James Watt: 1736 - 1819�ˤʤ���̾�ʾ������ؤε��ѼԤ��ڽФ������ȳ�̿��¿��ʤ��Ϳ�Ƥ��ޤ�����
- �ʥ��ߥ��ϵ������ѼԤȤ���̾���ڤ�¿�����٤����ơ�48�Фǰ��ष�Ƥ���ϼ�̣��ŷ�δ�¬�Ƿ��ѻ�����褦�ˤʤ�ޤ���
- ��ϡ����魯���������̣��ŷ��˾�������ŷ�δ�¬��ԤäƤ��ơ�1840ǯ����1842ǯ�ˤ����Ƽ�����10�������13�������20�������φ508mm�ˤΥʥ��ߥ���ȿ��˾�������ޤ�����
- �����˾����Ƿ��̤��¬�����ܤ�Ф��Ƥ��ޤ���
- �����ȷ��ϲ�ȤǤ�����������κ�ǽ�����ä��ΤǤ���
- ��μ�ˤ��ŷ��˾����ϡ��������ѼԤ餷����Υ����ǥ���������ޤ졢ŷ��˾�������ƻ���˱�ä�ư�����Ƥ��ܴ������䤨������ˤʤ�褦�˹��פ���Ƥ��ޤ�����
- ����ˤ�ä�ŷ��˾�����ư�����Ƥ⡢��¬�ԤϤ��Ĥ����δ�¬���֤�ŷ�Τ��¬�Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���ε��������������ʤ�Τǡ����ߤ��緿˾����ˤ�ɬ����������Ƥ����ΤǤ���
- ��
- ��
- ������¾��ȿ��˾���2�ʥ���ߥåȼ���
- ��
- ȿ��˾����ϡ�ȿ�Ͷ��ʵ��̶�����ʪ�̶��ˤ���������̼������Ф䤹�����������ȤȤ���˼����������Ƥ��ޤ����ṭ������Ǥδѻ����Ǥ��ʤ�û�����äƤ��ޤ���
- ����ζ���ŷ��˾����ϡ���갷��������¬�˻پ���褹���Ȥ�����ޤ���
- �ޤ��顼���ե����ޥåȥ�����70mm�ե���५����̿����ġˤ�Ȥä�ŷ�ΤƤ����硢�����μ��դ������ˤ�ä��������Ƥ��ޤ����줬����ޤ���
- �������������������ʼ����ˤε��̼����������������طϤ�����ߥåȼ�ŷ��˾����Ǥ���
- ����˾����ϡ������ȥ˥����ޤ�Υɥ��ĸ����߷ԥ٥��ϥ�ȡ�����ߥåȡ�Bernhard Schmidt, 1879 - 1935�ˤˤ�ä�1931ǯ�˹ͰƤ���ޤ�����
- ����ߥåȤϡ��������ѼԤǡ������������������������ä������Ǥ���
- ����ȿ�Ͷ��ϸ��������ʤ�����Ǥ�����
- ��ǯ����˻��Τˤ�äƱ��Ӥ�̵���������Ӥ����Ȥʤ�ޤ����������Ӱ��ܤ���夲����̤Ϥ��Ф餷������Ǥ��ǥɥ��ij��Ϥ�ŷʸ���ͥ����˾��������Ƥ����ޤ�����
- ����ߥåȡ������ϥϥ�֥륯ŷʸ�椫��ΰ���ˤ�äơ�������뤯��깭�����˾������뤿��˳�ȯ����ޤ�����
- ����ߥåȤϡ��ϥ�֥륰ŷʸ�����˱����뤿��ˡ�ȿ�Ͷ��ζ�Ψ�濴���֤�����̤�Ʃ�᷿�����Ĥ��֤��Ƶ��̼����ȥ���������������˾�����ȯ���ޤ�����
- ����˾����ϡ�ȿ�͡ʵ��̡˶��θ��¤�440mm�������Ĥθ��¤�360mm�Ǥ��ꡢ������Υf625mm��������F/1.75������16°����ǽ����äƤ��ޤ�����
- �������뤯�ƻ���ι���˾����Ǥ���
- ��������Ǥ狼��褦�˥���ߥåȼ�˾����ϡ��ɤ����ȤŤ���Τ褦�Ǥ��������̤�ʿó�Ȥʤ餺���ѶʤȤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ���Τ��ᡢ�ե�����̤����̤˱�ä��Ѷʤ�����ɬ�פ�����ޤ�����
- ����ߥå�˾����ϡ������Ǥλ��Ƥ�����Ū�Ǥ��ä�����ˡ�����ߥåȡ������Ȥ���������������Ū�Ǥ���
- ����ߥåȥ�������Ū�ϡ����������ŷ�μ̿����Ƥ�Τ���������Ǥ��ꡢ��ϷϤθ���˻��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ��ˤ�Ҥ٤ޤ����褦�ˡ�����ߥåȡ������Ǥϻ����̤������Ѷʤ��ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ��顢���ߤǤ�ե����ʴ��ġˤ��Ȥ��뤳�Ȥ�¿����CCD�����ǻҤ�Ȥ����ϡ������Ѷʤ��������������Ĥ��ǻҤ������֤��ƻ��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ��
- ������¾��ȿ��˾���3�ʥ�å���������ƥ�����
- ��å���������ƥ������Ritchey-Chretien�˼�ŷ��˾����ϡ��Ƕ���緿ŷ��˾����μ�ή�ˤʤäƤ��������ǥ�������������β��ɤȤ������٤���ΤǤ���
- ����˾����ϡ�1920ǯ����о줷�ޤ���
- ���ܤ��緿ŷ��˾����֤��Ф�פ��ƹ���˾����ϥå֥�⤳�Υ����פ�ȿ��˾����ˤʤäƤ��ޤ���
- ����˾����ϡ������������Ȥ����ʪ�̶���¤�Ȥ��뤳�Ȥˤ�ꡢ�ɹ��ʵ��̼������������ν�����������Ƥ��ޤ���
- ���äơ����Υ����פ�˾����Ǥϡ��������������볦�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��å�����George Willis Richey��1864 - 1945�ˤϡ�����ꥫ��ŷ��˾�����¤�ȼԤǤ��ꡢ����ꡦ����ƥ������Henri Chretien��1879 - 1956�ˤϡ��ե����ܥ����ؤζ����Ǥ�����
- ����ƥ�����Ϥ����줿�����߷ԤǤ⤢�ꡢ���ʥ�ե��å���ʱDz��ѤΥ磻�ɥ�������ѤΥ��ȯ���ԤȤ���̾��Ĥ��Ƥ��ޤ���
- ��å����ϡ��ƹ��緿ŷʸ����Ĥء�����Ρ�George Ellery Hale��1868 - 1938�ˤȶ���1900ǯ���Ƭ���ƹ�ŷʸ����ߤ˷Ȥ�ꡢ�����륽��ŷʸ��ʤɿ�¿����ŷ��˾������߷ס���¤��꤬���Ƥ��ޤ�����
- ����ζ������������������Τ��ṭ����δѻ����Ǥ���˾����������ꤵ�졢ͧ�ͤΥ���ƥ���������̤��ޤ�����
- �ե�Υ��������Ȥϡ���å������ѥ�ŷʸ��ǻŻ��Ƥ����Ȥ����Τ�礤���Ȥ�˸����Ԥä������Ǥ�����
- ����ƥ�����ϡ��������ж��̤Ȥ������������ж��̤ˤ���м������Ȥ�ƹ�����Τ�Τ�����ȥ��ɥХ������ޤ�����
- ���������ж��̤�����ȤƤ����ƥ��Ȥ������Ƥ⤵�������ΤǤ�����
- ��å����Ϥ���������������1923ǯ��50cm��˾������ꡢ1936ǯ�ˤϡ�����ꥫ����ŷʸ��˸���1m�Υ�å���������ƥ�����˾�����Ǽ��ޤ�����
- �ʸ塢�緿ŷ��˾����Ϥ��Υ����פ�˾��������Ѥ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ȿ�Ͷ��Ǻࡡ��2006.08.06���ˡ�2006.11.19�ɵ���
- �緿˾����������褦�ˤʤä����ϤȤ��ơ�ȿ�Ͷ����Ǻ��ȯŸ������ޤ���
 ȿ�Ͷ����Ǻ�ˤɤΤ褦�ʤ�Τ��Ȥ��Ƥ���Τ��Ƕ�Τ�Τ�������ˤ��ΤܤäƤߤ����Ȼפ��ޤ���
ȿ�Ͷ����Ǻ�ˤɤΤ褦�ʤ�Τ��Ȥ��Ƥ���Τ��Ƕ�Τ�Τ�������ˤ��ΤܤäƤߤ����Ȼפ��ޤ��� - ��ULE��Ultra Low Expansion��
- ���θ����Ǻ�ϡ��ƹ��˥�Corning�˼Ҥ���ȯ������ĥΨ���㤤���إ��饹�Ǥ���
- ����ĥΨ�� 30x10-9/���0��300��ˤȾ������ͤ������ߤνꡢ����ĥ���饹�Ǥϥɥ��ĥ���åȼҤΥ����ǥ奢��������ʤ���ΤǤ���
- �����ϡ�����������ǡ�SiO2��92.5%��������������7.5%�ˤǺ��졢����������Ǥ��ץ饹����ĥ�������������������ޥ��ʥ�����ĥ�����Ǥ��뤿�ᡢ�껦���������ĥΨ�Ȥʤ�ޤ���
- ULE����¤�ϡ��ⲹ������ʮ�Ф�������Ĥκ������Ϥ����ʤ���ʮ�Ф���1�ߥ�����ʲ��ξ�����γ���Ȥ��ƺ���ޤ���
- ���Τ��ᡢ�����Ʒ�1.5m������16cm�Υ֡���ʴݤ���ʿ�٤ä����ե�Υѥ�Υ֡����ͳ��ˤ���ޤ��ʱ����ȡˡ�
- ���α��Ĥ�2�ĽŤͤ����ܤ������줫��1��73.3cm��������30cm����ϻ�ѷ����ġ�Hex = �إå����ˤ���ޤ���
- ���Υإå����������1��˥åȤȤʤ�ޤ���
- ���Υإå����줤���ߤ��ͤ��ϧ������Ʋ�Ǯ������ȸߤ��ˤ��äĤ���1��ζ���Ȥʤ�ޤ���
- 8��ȥ����礭���Ǻ�ϰ쵤�˺��ʤ��Τǥ֡����Ĥʤ���碌��ϻ�ѷ��Υ����������¤��Ǻ���äƤ����ޤ���
- ULE���й��ϤǤ��를���ǥ奢�ϡ�������Ǯ�������Ǥ��ʤ��Τǡ�Ǯ�����ˤ�ä���ĥΨ��Ĵ������Τǡˡ����ܤȤ�����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ULE�ǤϤ��줬�Ǥ���Τ�����¤Τ�Τ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���
- �礭�ʸ��¤��Ǻ�����ϡ��������Ĥߤ�Ĥ��ʤ��褦�˺��ʤ���Фʤ�ʤ�����2ǯ����4ǯ��������֤�ɬ�פȤ��뤽���Ǥ���
- �����Ǻ�ϡ��֤��Ф�ס֥ϥå֥�ס֥����ߥˡפ˺��Ѥ���ޤ�����
- ����
- �������ǥ奢��Zerodur��
- ���θ��غ����ϡ��ɥ��ĤΥ���åȡ�SCHOTT�˼Ҥ���ȯ������ĥΨ���㤤���إ��饹�Ǥ���
- ���إ��饹����ߥ����Ȥ�Ƥ�Ǥ��ޤ���
- ���������ϡ����饦�饹K4�˶�����إ��饹�Ȥΰ㤤�Ϸ뾽�����饹�ˤʤäƤ��뤳�ȤǤ���
- �̾���饹�Ȥ����Τϸ��إ��饹��ޤ�Ʒ뾽��¤�Ƥ��餺��Ǵ�ڤι⤤���ΤǤ��������Ρʤ��褦�����ˤȤ�����ޤ���
- �����ǥ奢�ϡ��尻���Υ��饹�ǤϤʤ���¤�Τ��ä��ꤷ���뾽���֤Υ��饹��ȤäƤ���ΤǤ���
- ���äơ����̤�70%���뾽������γ���뾽�бѡ��礭������50nm�ˤ�ޤ�Ǥ��ޤ���
- ������γ���뾽�бѤβ��饹���бѤ���߹��ߡ�ξ�Ԥ���ĥΨ�ΰ㤤�ʷ뾽�бѤ��ޥ��ʥ��ǥ��饹���бѤ��ץ饹�ˤǥȡ��������ĥΨ��¤�ʤ��������ޤ��Ƥ��ޤ�������ĥΨ�ϡ�0��50��� 20x10-9/�� �Ǥ���
- �衼���å���ŷŷʸ���ESO = European Southern Observatory�ˤ��緿ȿ��˾���VLT��Very Large Telescope�ˤ˺��Ѥ���ޤ�����
- ��
- ���ܥ����ꥱ���ȥ��饹��borosilicate glass���ۤ��������饹��PYREX��
- �����Ǻ�ϡ���Ǯ���饹��ͭ̾�ʥѥ���å����Τ��ȤǤ���
- �����ҡ������С��Υ��饹�ݥåɤ�������Ǯ�˻ҡ��ѥ���å����Ǻ���Ƥ��ޤ���
- Ǯ��ĥ���㤤���Ȥ���ULE�䥼���ǥ奢���и�����ޤǤδ֡��緿ȿ�Ͷ��μ�ή�Ǥ�����
- ���ߤǤ⡢��갷�����ɤ����Ȥ�������Ȥ��ޤ����뤳�Ȥ���ѥ���å����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ä˥ϥ˥��¤�Ȥ���ȿ�Ͷ��ǤϤ��κ������ή�Τ褦�Ǥ���
- �ѥ���å�����PYREX�ˤϡ��ƹ��˥ҡ�Corning�ˤ���ȯ�����ۤ��������饹�Υ֥���̾��1915ǯ��ȯ�䤵��ޤ�����
- 1934ǯ�˷��Ƥ�줿�ƹ�ѥ���ŷʸ���200�����˾����μ���˽��ƻȤ��ޤ�����
- �ѥ���å������Ȥ�줿�аޤϡ��ƹ��ŷʸ�ؼԤء�����Ρ�George Elley Hale��1868 - 1938�ˤˤ��ޤ���
- 1917ǯ�ν��������륽��ŷʸ�����ߤ����ء�����Τ���2�ͤΥ����åդ�ȼ�äƿ�����ŷ��˾���������ѻ����뤿��˥����륽���Фä����Τ��ȤǤ���
- �ѻ��Ͽ���˵ڤӡ��뤬�����Ʋ��٤��ɤ�ɤ��äƤ���ˤĤ�ơ�˾�������ǽ������夬�äƤ��뤳�Ȥ˵��Ť��ޤ�����
- �Ĥޤ���֤˶�����ʬ���䤨�����Τʱ��̤���äƤ����ΤǤ���
- ���ηи����̤��Ƥء�����ΤȤ��Υ����åա������ॹ�ϡ������Ǯ��ĥ���㤤��Τ�Ȥ�ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ��˴������ΤǤ���
- ���ηи����Ȥˡ����ʤ��緿ŷʸ��ʥѥ��ޡ��ˤ�˾����ζ���ˤ�����ĥΨ�Τ�Τ�Ȥ����Ȥ��ᡢ��������ˤϤ���ޤ�����
- ������GE����¤���Ƥ�����ͻ�бѤ���äȤ���ĥΨ���㤤��ΤǤ��������礭����������ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- ��餬�������ꤷ���Τϥ����˥Ҥ���¤���Ƥ���ѥ���å����Ǥ�����
- �����˥ҤϤء�����Τ�����������ơ�1931ǯ���緿�Υѥ���å������������ץ��������Ȥ�Ω���夲��5ǯ�κз��Ф�200�������20�ȥ�������������ޤ�����
- �ѥ���å����Ǻ���礭���ƽŤ��Τǡ��䶯��¤�ѤȤ��ƥ�֡�Ͼ��ˤ��դ����ޤ�����
- �������䤵�줿���Ѥ�34���ɥ�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ߡ��ܥ����ꥱ���ȥ��饹��Ȥä��緿������߷���¤�Ƥ��뵡�ؤ˥������ء�The University of Arizona�ˤ�����ޤ���
- �������ؤϡ���ظ��浡�ؤǤ���ʤ����緿ŷ��˾����ζ�������ߤ���äƤ����ˡ����ʸ��浡�ؤǤ���
- �������ؤ�ŷʸ������ζ��������㡼����������Ρ�Prof. Roger Angel�ˤϡ��ѹå����ե�������ؽпȤ�1974ǯ�˥���ʤˤ�äƤ���ŷ��˾���������˷Ȥ�ꡢ6.5��ȥ�μ�����������ᤤ�Ƥ��ޤ���
- �����ȼ��Υϥ˥��¤�Υ��饹��¤�������äƤ��ơ�����˻Ȥ��Ƥ��륬�饹���������ܤΥ��ϥ��E6�ȸƤФ��ܥ����ꥱ���ȥ��饹�Ǥ�����
- ���Υ��饹��Ǯ��ĥΨ��Ŵ��1/10�Ⱦ�������ΤΡ���˾Ҳ𤷤�ULE�䥼���ǥ奢����٤��1000�ܤ��礭���ʤ�ޤ���
- ��������ULE�䥼���ǥ奢�Ǥϥϥ˥��¤�ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ��������κ����Ȥ�����Ͻ�ʬ�ˤ���褦�Ǥ���
- �������ؤǿʤ�Ƥ����緿ŷʸ��LBT�䡢��MMT�ˤϤ����Ǻब���Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���ܤǤ⡢���ԡ�����3.8m��˾����ǥܥ����ꥱ���Ȥζ��ब�Ȥ��뤳�ȤˤʤäƤ��ޤ���
- ��
- ����ͻ�бѡ�Fused Silica��
- �ѥ���å������Ȥ���ޤǡ�Ǯ��ĥ���㤤�����Ǻ����ͻ�бѤǤ�����
- �����������κ���������¤Τ�Τ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ǽ�μ���Ȥߤϡ�1920ǯ��ˤء�����Τ�������������ƹ�GE�Ҥ�3ǯ�κз����60�������152.4cm�ˤ��Ǻ���ä��Τ˻Ϥޤ�ޤ���
- �����������줬������Ǻ�Ȥ��ƤϺǽ�ǺǸ�Ǥ��ꡢ�ʹߡ��ѥ���å����˼�ä�������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- �����ĥ��饹��Soda-lime glass��
- 1910ǯ��ޤǤζ����Ǻ�ϡ��̾�Υ��饹�Ǻ���Ƥ��ޤ�����
- ���إ��饹�ǤϤʤ��̾�Υ��饹��ȿ�Ͷ��˻Ȥ��Ƥ�����ͳ�ϡ�ȿ�Ͷ��Ǥϥ��饹������̮����Ʃ��Ψ���ʼ�������ʤ��ä�����Ǥ���
- ���饹���Ȥ�������ȿ�Ͷ��ϡ���°�����Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ��°���Ȥϡ���°���Τ�Τ��ᤤ�Ʊ��̡ʵ��̡˾��ˤ�����ΤǤ���
- �˥塼�ȥ�λ���ϡ����ζ�°���Ǥ�����
- ���饹��Ȥä�ȿ�Ͷ��ϡ����饹�ξ�˶��å����Ǥ���褦�ˤʤä�1850ǯ���Ⱦ�����о줷�ޤ���
- ���ΤȤ��˻Ȥ�줿���饹���������ĥ��饹�ȸƤФ���ΤǤ���
- ���ĥ��饹�ϡ����ߤǤϰ���Ū�ˤʤäƤ����륬�饹��ǡ��Το�²�ۤ�������˻Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �����Ǻ��Ȥä���ϸ���������Ĥ������ޤ����Ĥ�������Τϡ����饹��Ŵʬ���������Ƥ��뤿���ֿ���ʬ��ۼ����뤫��Ǥ���
- �Ƕ�ο�²�ۤ���ϥ���������Ѥ��Ƥ���Τǡ��Ĥ��ϸ����ޤ���
- ���ĥ��饹��Ȥä��緿��ŷ��˾������ǽ�˺��줿�Τϡ��ե�Υѥ�ŷʸ��ǡ�φ120cmF6.5��ȿ�Ͷ��Ǥ�����
- ����ˤϡ��ե�θ��ز�ҥ����Х��Saint-Gobain�ˤ����ĥ��饹���Ȥ�졢�ա�������Leon Foucault: 1819 - 1868�ˤν���A.�ޥ륿���ᤤ�ƶ��å�������ܤ��ޤ�����
- ���å��������줿ȿ�Ͷ��ϡ�����ζ�°���Τ�Τ��������ȿ�Ͷ�����٤�Τˤʤ�ʤ����餤���뤤��ΤǤ�����
- ����˾�����Ȥä�M.P.������Mathieu Prosper Henry: 1849 - 1903�ˤϡ������ˤ��������2��ȯ�����ޤ�����
- �緿���饹�Ǻ�γ�ȯ�ȶ��å��ʸ�˥���ߥ�å��˽����ε��ѳ����ʤ���С����ߤ�ȿ��˾����λ���Ϥʤ��ä������Τ�ޤ���
- ���ˡ�ȿ��˾�����1800ǯ��Ͽ���Ǻ�ߡ����غ����ε��ѳ��ʿ��ä�����о졢���ʼ��ʸ��إ��饹��¤�γ�Ω�ˤ⤢�ꡢ����˾������ֳ�����1900ǯ�ޤǤ�40�������101.6cm�ˤޤǤ��緿˾���������Ƥ����ΤǤ���
- �����������θ�ϡ���å����Ѥ���Ω���줿�ΤǤդ������緿��ȿ�Ͷ��������褦�ˤʤ�ޤ�����
- �������˻Ȥ�줿�Τ����ĥ��饹�Ǥ�����
- �������ե�Υ����Х�Ҥ����뤹���緿�������ĥ��饹����ή�ǡ��ƹ�Υ����륽��ŷʸ���60���������ˤ⤳�β�ҤΤ�Τ��Ȥ��ޤ�����
- ��
- ����°����Metal Reflection Mirror��
- �˥塼�ȥ�ȿ�Ͷ��ˤ��˾������ä��Ȥ���ȿ�Ͷ��ϥ֥��ʿ����夦�ˤǺ���Ƥ��ޤ�����
- �����夦�Τޤ��ᤤ��������˾����Ǥ�����
- �����夦�ϥ��ڥ�������ʶ���ˤȤ�ƤФ�Ƥ��ơ����������Ȥ��ƻȤ��Τ˽�ʬ�ʹŤ���ȿ�ͤ���äƤ��ޤ�����
- �˥塼�ȥ��Ѥ��������夦�ϡ�Ƽ66%����22%������11%������˶侯���Ȥ������Ǥ�����
- ���Ǥ����줿�ΤϹ�����Ȥ��˼�Ω�ä��饹���Ǥ��ˤ����ä�������ä������Ǥ���
- ȿ��Ψ�Ϥ����餯40%���٤Ǥ��ä������ȹͤ����ޤ���
- ��°���ϡ����Ѥ���ˤĤ�ƻ��Ǥ˿�����ޤäƤ��ޤ���
- ���ä�ȿ�Ͷ������Ū���ľ��ɬ�פ�����ޤ�����
- ����Ǥ�ȿ�ͼ�˾����ϡ�����˾���������ǽ���ɤ��ä��ΤǤ���
- ���Τ��Ȥϡ�17�����λ���Ǥ϶���˾����˻Ȥ����إ��饹�ˤ����ʤ�Τ��ʤ��ä����Ȥ�ʪ��äƤ��ޤ���
- ȿ��Ψ�������Ƥ⥳��ѥ��ȤˤǤ������¤��礭�����뤳�ȤǺ��ޤǸ����ʤ��ä�ŷ�Τ�������褦�ˤʤ�ΤǤ��������ܤ���Ӥʤ��Ϥ��Ϥ���ޤ���Ǥ�����
- ��°���Ͽʲ���³����1800ǯ����溢�ˤϡ������ꥹ�Υ��å���Rosse�ˡ�����̾�ϥ����ꥢ�ࡦ�ѡ��������å�William Parsons Rosse��1800 - 1867�ˤ�ȿ��Ψ�ι⤤�����夦�ʥ֥��ˤ椷��Ƽ70����30�ι�����ޤ���
- ���ι���ȿ��Ψ67%��ã�������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���˥��Ǥ�����ʤ��ä��Τϡ����Ǥ������ȹ�⤬�Ȥ��ʤä��ѵ������ʤ��ʤ�����²��ˤϸ����ʤ�����Ǥ�����
- ���å���Ʊ���˿����夦������¤ˡ���Ω���ޤ���
- �Ĥޤꡢ�礭�ʹ����Ȥ���¤����dz��䤹�����������뤿��ˡ���������䤷�Ƥ������ˡ���ʾ��ߡˤ���ˡ��ȯ�����ΤǤ���
- ��ϡ����ε��ѤǸ���6�ե����ȡ�183cm�ˡ�������F8.83������7�������17.8cm�ˡ�����9,000�ݥ�ɡ���4�ȥ�ˤμ������˾�������ޤ�����
- ����˾����ϡ���ϷϤ�ȯ�����������Ǥ���
- 1835ǯ�˥ɥ��Ĥβ��ؼ� J. �ե���ӥåҡ�Justus von Liebig��1803-1873�ˤ����饹�Ĥ˶�إ�å�������ˡ��ȯ�����ޤ�����
- �������Ѥ��ơ��ɥ��ĥߥ��إ�θ��ص������Ǥ��륹����ϥ����Steinheil�ˤ�100�������¤α��̶��˶��å���ܤ��ޤ�����
- ���å���ȿ��Ψ�ϡ�����ζ�°������ٳ��ʤ��ɹ��ǡ������⥬�饹ɽ�̤ˤ��å����Ǥ��뤳�Ȥ��顢��°�����ؤ��Ƹ��إ��饹��˥�å�����ȿ�Ͷ����Ӹ��Ӥ�褦�ˤʤꡢ����ϸ��إ��饹��ȤäƤ��ξ�˥�å��ʥ����ƥ��ˤ�ܤ����ؤ��Ѥ�äƹԤ��ޤ�����
- �緿ȿ�Ͷ������٤褯�Ǥ���褦�ˤʤä����ѳ�����ǡ��ե��ʪ���ؼԥա�������Jean Bernand Leon Foucault��1819 - 1868�ˤ����߽Ф������̸���ˡ�ʥա��������ƥ��ȡˤθ��Ӥ��ʤ��櫓�ˤϤ����ޤ���
- �ա��������ƥ��Ȥ�ȯ���ˤ���緿�ε��̶��Ǥ������ɤ����̤�Ф���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ա������ιͤ��Ф�������ˡ�����˥���ץ�ǡ�����������̶��˾ȼͤ�����ȿ�ͤ������������ְ��֤˥ʥ��դ��ڤ����Ǽ������פꡢ���Ƥ��ɤΤ褦���Ѥ�뤫���ܻ�Ǹ������������Ǥ���
- ���̶������������ᤵ��Ƥ���С��ʥ��ե��å����ڤ���ߤDZ��Ƥ��Ѱ�˾ä��Ƥ����ޤ���
- ���̶����Ĥߤ�����ȥʥ��ե��å����ڤ���ߤ�äƱ��̤�����ޤ���
- ���ξ������ܻ�dz�ǧ���ʤ��顢���̤��ᤷ�Ƥ����Ѱ�ʱ������ˤʤ�ޤǤ�����֤��ޤ���
- ���μ�ˡ�ϡ����������طϤθ����ˤ�ʤä���ΤǤ���
- ��
- ����ȿ�Ͷ���å���Front Silvered Mirror��
- ȿ�Ͷ���ŷ��˾����μ�ή�ˤʤä��Τϡ���ɽ�̤�ȿ��Ψ���ɤ���䥢��ߤ������ɤ���å����Ǥ���褦�ˤʤä�����Ǥ���
- ��å����Ѥϲ��إ�å������ȯ�������嵻�Ѥ���Ω����Ƥ����ʬ�ҥ�٥�Ǥ��������ǽ�ˤʤ�ޤ�����
- ��������쵻�Ѥˤʤ��ƤϤʤ�ʤ���ˡ�ǡ����ߤθ���ʬ������ڤʤ�ΤˤʤäƤ��ޤ���
- ȿ�Ͷ��Ǥϡ���ȥ���ߤˤ����夬ȯŸ���ޤ�����
- ��ϲĻ������Ф�93 - 98%��ȿ��Ψ�����������ߥ˥����92 - 86%�Ǥ���
- �������������ȿ��Ψ���⤯�ֳ����Ǥϥ���ߤ����ɤ�ȿ����������äƤ��ޤ���
- �ޤ�����ϲ���Ū���ñ�˥�å��Ǥ���ΤǼ¸�����٥�Ǥ褯���Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ����������߾������٤��ѵ������ʤ�����ˡ����ߤ�ȿ�Ͷ��ˤϥ���ߥ˥��ब¿���Ȥ��ޤ���
- �ѵ��������륢��ߥ˥���Ǥ⡢����Τ褦�ʤȤ����ǻ��Ѥ��Ƥ����3ǯ���餤���ܤ˸�����ɽ�̤����äƤ��ޤ���
- �桹���褯�Ȥ�ɽ�̶��䥷�������طϤα��̶��ϡ�����ߥ˥�������ܤ�����������ǡ�SiO�ˤ��ݸ���Ȥ��ƾ��夹��Τ����̤Ǥ���
- �����ݸ���ϤȤƤ����Τǽ������ޤ���
- ������������϶������Ƶդ��������Τ���ä����ʤΤǡ�ŷʸ����緿ȿ�Ͷ��ǤϤ����ݸ������Ѥ��ʤ������Ǥ���
- �ݸ���Ȥ��̤ˡ�����ߥ˥����ȿ��Ψ����뤿��˻��Ѥ�����Ĺ��1/4��Ĺ��0.1um��0.2um�ˤ������¿���쥳���ƥ���ܤ��ޤ���
- ���Ѥ����������ϡ�������������TiO2������Ψ2.35�ˡ���������ǡ�SiO2������Ψ1.38�ˤʤɤǡ�������ؤˤ��Ϥäƾ��夷���Ļ��ΰ���Ϥä�97%��ȿ��Ψ�����Ƥ��ޤ���
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
-
- �������ܤκǿ���ŷ��˾�����-�����Ф��Subaru������2006.08.�ˡ�2006.11.23�ɵ���
- �Ͼ夫����ؼ�ˡ��Ȥä����٤Τ褤ŷ�δ�¬������
- ����������Ū�Ƿ��ߤ��줿ŷ��˾����ΰ�Ĥ����ܤΡ֤��Ф�פ�����ޤ���
- �Ͼ�Ƿ��ߤ����ŷ��˾����ϡ��絤�αƶ�������Ƥ����ɤ餮�ǽ�ʬ��ʬ��ǽ�������ʤ��ȸ����Ƥ��ޤ�����
- ���������絤���ɤ餮�������Ĥߤ��������뵻�ѡ�Adaptive Optics = ǽư���طϵ��Ѥ���Ω����ơ����ʤο����뤲�ޤ���
- ���ι��ܤǤϡ������ץƥ��֥��ץƥ������ιͤ������濴�ˤ��Ф�ץ��������Ȥ�Ҳ𤷤����Ȼפ��ޤ���
- �����ץ���������ȯ
- �������ŷ��˾����ϡ�1970ǯ�夫��1980ǯ���ˤ����ƻϤޤ�ޤ�����
- �������������ƤǤ�3m�ʾ�θ��¤����˾����������ȷ��ߤ���Ƥ��ޤ�����
- ���ܤǤϡ����������̤ä�20ǯ����1960ǯ�˥����ꥹ����͢������1.88m���¤β�����¬���˾���������Ǥ�����
- ����ŷ��˾����ϡ�Ƴ�����줿������������10�̤Ǥ��ä������Ǥ��������θ�������˾������ߥ֡������ˤ��äƼ��Ĥ���Ƥ��������ݤ�ʤ��ä������Ǥ���
- 1982ǯ�˿�����ŷ��˾������ߤηײ褬ư��������1990ǯ��˴���������ץ��������Ȥ�Ω���夬��ޤ�����
- ���줬�֤��Ф��˾����ײ�����ΤǤ���
- ���Ф�ϡ�1998ǯ12��24�����ϥ磻 �ޥ��ʡ���������ɸ��4,139m�ˤ˴��������ե������ȥ饤�ȡ�first light��������κǽ�θ�������뤳�ȡˤ��Ԥ��ޤ�����
- ������ά��ǽ
 ���Ф�ŷ��˾����Τ�äȤ��礭����ħ�ϡ��ʲ������ˤ���Ȼפ��ޤ���
���Ф�ŷ��˾����Τ�äȤ��礭����ħ�ϡ��ʲ������ˤ���Ȼפ��ޤ���- ��������礭���������ǹ��٥롧������8.2m����å����������������
- �������ǽư�ǻҡ�Adaptive Optics�˲��Dz����Ϥ����塣
- ��ŷʸ�����־�ꡧ���絤�����ꤷ���������Τʤ��ϥ磻�ޥ��ʥ����������֡�
- ����¬���֡���������CCD�����ڤ�ʬ�����֤κ��ѡ�
- �������Primary Mirror��
- �����ŷ�Τ���θ�������ڤʤȤ����ǡ�����Ū�˸��¤��礭���ۤɤ�������θ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �Ƕ�κ���ü�μ���ϡ�10m�¤Τ�Τ���ή�ȤʤäƤ��ޤ���
- ����������礭�ʶ���Ĥ���Τ�������ǤϤ���ޤ���
- ���Ф�Ǥϰʲ�����ǽ����ļ�������Ѥ���Ƥ��ޤ���
- �����¡���8.2m
- ������������15m
- �������桧��F1.8���������뤤���طϡ�
- �������������������������
- ���������ULE���ƹ��˥ҡ�
- ����������200mm�ʸ��¤ȸ������桧��42:1��������
- ���Ť�����22,800kg
- ���������١���0.012um
- ������ʬ��ǽ����0.23"��23/360000°��
- ���μ���ϡ��������ƹ�˥塼�衼�����ˤ��륳���˥Ҥ������餤��4ǯ�κз��������ߡ�������ƹ�ڥ�Х˥�������ȥ�ӥ��Ҥ˻�������ǡ������3ǯ�κз����䤷�ƴ������ޤ�����
- ����ˤϡ���ȴĶ����٤����ˤ��뤿��ˡ��ƹ�ԥåĥС����ˤ����г�����ѹ���η���ľ����30m�ο����η�ꡢ�����˸������֤����֤��ƺ�Ȥ��Ԥ�줿�����Ǥ���
- 7ǯ�κз����䤷�����ˤʤ�ޤ���
- ��
- ����AO��Adaptive Optics = ��������������֡�Active Optics = ǽư�������֡�
- �����礭������褦�ˤʤä��Τϡ������Ĥߤ���̯��Ĵ���Ǥ���ޥ������������奨�����������֤γ�Ω�����ä�����Ǥ���
- �����礭������ȡ����μ��ŤȲ����Ѳ��Ƕ����Ĥ�Ǥ��ޤ��ޤ���
- ���������ޥ������������奨�����ˤ�äƶ����Ĥߤ��������뵻�Ѥ��Ǥ�������ȡ������������Ƥ���̤������̤���ݻ����뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ������������ȷڤ��ʤ����ڤˤʤ�ޤ���
- ���Ф�ξ�硢�����ʤä��������̤���261�ܤΥ������奨�����Dz�������������ꤷ�ƶ��˱��Ϥ�Ϳ���ơ�������ž���ư��֤��Ѥ����˼��Ťˤ�ä��Ĥ���̤�������������Ū�ʶ��̤���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���������������Ȥǡ������ä����٤��ɤ���ΤˤǤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ޤ����Ͼ夫��ŷ����˾��˾����ν�̿�Ȥ����絤���ɤ餮�ˤ�������㲼�����ʤ���̿�ȤʤäƤ��ޤ�����
- �������̤����֤��줿261�ܤΥ������奨�����϶���Ū�ˡ�ǽưŪ�ˡ˶����������ơ��絤���ɤ餮�ޤǤ���������Ư������äƤ��ޤ���
- ���Τ褦���Ѷ�Ū�ʸ���������֤�����������طϡʥ����ץƥ��֡����ץƥ�������Adaptive Optics��AO�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �ʤ���AO�ˤϡ�Adaptive Optics����������������֡ˤ�Active Optics��ǽư�������֡ˤ���Ĥΰ�̣�����ߤ���ۣ��ˤʤäƤ��ޤ���
- �ߥ顼��ߥ顼�ݻ���ǽ��������Ԥ����ȿ����㤤������Active Optice�ȸ������絤���ɤ餮�Τ褦��10Hz����1,000Hz���٤μ��ȿ��θ���������Ԥ����Ȥ�Adaptive Optics�ȸƤַ���������ޤ���
- �����������奨����������������������
- ����̤��������륢�����奨�����ο�¡���ˡ��������Υ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ������ݻ����뵡���ϡ���ɩ�ŵ��ʳ��ˤ��߷ס���¤��ô�����ޤ�����
- �������奨�����˻Ȥ��Ƥ��밵�ϥ����ˤϡ����⤷�����������Ȥ��Ƥ��ޤ���
 ����ϡ������Żҡʳ��ˤ�1983ǯ��곫ȯ����¤���Ƥ��벻���������ȸƤФ���ΤǤ���
����ϡ������Żҡʳ��ˤ�1983ǯ��곫ȯ����¤���Ƥ��벻���������ȸƤФ���ΤǤ���- �����Żҡʳ��ˤϡ���̩�Ż�ŷ��γ�ȯ����¤�Ƥ����Ҥǡ��Ť����̤륻���Ȥ�����餬��ȯ������������������̩�Ż�ŷ����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ���Ф���ߤε��Ѽ�ã������Υ������奨���������Ȥ����ܤ�Ĥ����Τ������β����������Ǥ�����
- ��������������ħ�ޤ˼����ޤ���
- ���Υ����ϡ��ٽŤθ��е����˹�¤ʪ�λ��ĸ�ͭ��ư�������Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ʪ�ˤϺǤ�褯���������ͭ�ο�ư�����äƤ��ޤ���
- �����Ϥ�����ɽŪ�ʤ�Τǡ�U�λ���¤�ˤ��ˤ�ư��ꤷ����ͭ��ư����ȯ���ޤ���
- ���θ�ͭ��ư�������ȯ��������������Ϥ�ä�����Ȳ������Ĥߤ��Ǥ��ƶ������ȿ����Ѳ����ޤ���
- ���μ��ȿ����Ѳ��Ф��ƲٽŤФ��ޤ���
- ���Ф�˺��Ѥ��줿�����������ϡ����̡ʤҤ礦��礦��1500N����150kgf�ˤˤ�0.01N�ФǤ���ʬ��ǽ����äƤ��ޤ���
- ����ϡ�150kg���Ϥ��ä�ä����������Ϥ�1g�����٤�¬��Ǥ����1/150,000��ǽ�ϤȤʤ�ޤ���
- ���Ϥ��Τ���¬�����֤ϡ�������������¾�ˡ��Ĥߥ�������Ȥä������ɥ�����������������ż��ϡ�ʬƼ������ˤǽŤ����̤�ե������Х������ʿ�ռ��ˤ�����ޤ���
- �Ż�ŷ��Ϥ����λ��Ȥߤ�Ȥä����ʤǤ���
- ���������Ť����̤�����٥����������फ������ǡ����Ф�Υ������奨�����Υ����˲������Τ�Τ����Ф줿��ͳ�ˤĤ��ơ������������ϡ�
- ����ϴ�ʹ�¤��
- ������ץ�Ǿ�����
- ����ư���������ߥ��åפ����פʤ��ȡ�
- �������Ѳ����Ф�����������ɤ���
- ���������Ϥ����ʤ���
- .
- �ʤɤ���ħ���äƤ�������Ǥ���
- ����˼����������������ϡ�U����������Ļ��Ѥ�����¤�ȤʤäƤ��ޤ����������������ꤷ�����ȿ���ȯ�����Ǥ��뤽���Ǥ���
- ���ζ�°������ư�Ҥ�Ƥ�����������Υ�Υ֥��å���¤���������Ƹ���3mm���٤ΰ��ι�¤�Ȥ��ƿ���������Ƥ��ޤ���
- ���ι�¤ʪ�ϥ磻�����Ųù��ˤ��ù�����ޤ���
- ���Υ������Ÿ�����������ȡ�������ư�Ҥ˼���դ����Ƥ��밵���ǻҤ��Ű����ä�ꡢ����μ��ȿ�����2,000Hz�ˤǿ�ư����褦�ˤʤ�ޤ���
- ������𤷤��������˲ýŤ��ä��Ȼ�����𤷤ƺ������ˤ��벻����ư�Ҥ˲ýŤ��������Ʋ�����ư�Ҥ�ȯ�����ȿ����Ѳ�����200Hz�ˤ��ޤ���
- �����Ѳ�����ȿ��ԥå����å��Ѱ����ǻҤˤ�ä��ɤ�ꥳ��ԥ塼���������ʤ���ޤ���

�̿�������Ωŷʸ�� - �� �졼�������ɥ����������ƥ��Laser Guide Star System��
- �絤���ɤ餮���������륷���ƥ�ϡ����������������ɤäƥ��ƥåפ��夲���Ƥ��ơ��Ĥ��Ƕ��2006.11.21��ī����ʹȯɽ�ˤǤϡ��絤�Υʥȥꥦ���Ӱ�������Ȥ����졼�������ɥ����������ƥ�Ƴ���δ����ơ���ŷ�ˤ錄�����������Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Ф뤬����ޤǹԤäƤ����絤���ɤ餮�����������ˡ�ϡ�������ŷ�ζ�����뤤���������Ȥ��Ƥ�������ˡ����������Τʤ���Ϥ�Ķ�����δ�¬���Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- ����Υ졼�������ɥ����������ƥ�ϡ���¬������ŷ�Τ˲��ۤ�����12�������٤����뤵�ˤ��äƤ�������Ȥä��絤��������Ԥ��Ȥ�����ΤǤ���
- �������ʥ����ɥ������ˤ���Τ˥졼����Ȥ��ޤ���
- ���ܤ���������Ҥ٤ޤ��ȡ����Ф�ŷʸ��������˥졼���������ͤ�����ɽ90km��ˤ����絤�Υʥȥꥦ���Ӱ�Υʥȥꥦ�ึ�Ҥ��嵯������ȯ��������������ۤ����Ȥߤʤ��ơ��絤���ɤ餮���¬����AO����������������֡ˤˤ�ä���������Ȥ�����ΤǤ���
- AO���Ѥ���ȡ�������ǽ��10�ܸ��夹�뤽���Ǥ���
- ����ȯɽ�����ä������ƥ�ϡ�589nm��ȯ�������4W���ϤΥ졼�����Ȥ��Ƥ��뤽���Ǥ���
- �ʥȥꥦ����嵯����589nm�Ǥ���Τǡ�������Ĺ��ȯ�����Ԥ����Ψ���ɤ��졼��ȯ����γ�ȯ����Ωŷʸ��������ظ����ǹԤ��ޤ�����
- ���Υ����졼�� ��10W��+ ���ǥ졼���ˤ����ø���θ�ˡ�2�Ĥ�Nd;YAG�졼����1319nm��1064nm����Ĵȯ�����589nm������ˤ��Ȥ߹�碌��589nmȯ����4W���Ϥ����֡�YAG�¼��ȥ졼���ˤ���ȯ����ޤ�����
- ���Υ졼����Ȥäơ���¬����ŷ�Τ˸��������ͤ�90km����ˤ����絤�Υʥȥꥦ���ؤ��̲ᤵ���ơ���500mm�����Ԥ�5,000m���Ϥ�ʥȥꥦ��ȯ����D����589nm�ˤ���12���������ε���Ū��������夲�ޤ���
- ���ε������ʥ����ɥ������ˤФ�Ǹ����硢�����絤���ɤ餮�ˤ�äƤܤ������ȤʤäƤ���Τǡ��������Ȥ������ˤ��뤿���AO��Adaptive Optics�ˤ�Ȥä����������ˤʤ�褦���������ޤ���
- �������֤ϡ����̶��Ȥ��̤�����������طϡʲ��Ѷ��ˤǹԤ���188�Ĥ�ǽư�ǻҤˤ�ä�2,000Hz�μ��ȿ������̤����������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����˻Ȥ����θ��¤ϡ�130mm��ͭ�����¤�90mm�Ǥ���
- ���ζ���2mm�����������ǡ����ˤϰ����ǻҤ��Ȥ߹��ޤ�Ƥ����Ű��ˤ�ä��ѷ�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����ϡ��絤������äƤ���589nm�Υʥȥꥦ��ȯ���������Ǽ�����188�ĤΥޥ��������쥤���Ƴ���졢�����188�ܤθ��ե����С��ǹ�®�����ⴶ�ٸ������ʥ��Х���ե��ȥ��������ɡ�APD�ˤ�Ƴ���ơ����������̤�ʬ�Ϥ��Ԥ����Ѷ��˥ե����ɥХå�����ޤ���
- �����ϥ磻 �ޥ��ʥ�������Mt. Mauna Kea in Kona Hawaii��
- �緿��ŷ��˾��������֤ˤϡ��絤����������dz���������ʤ�����ǯ����̤����絤�ΰ��ꤷ����꤬˾�ޤ�ޤ���
- ������������������Ǥ��¿������櫓�Ǥʤ�������ȥϥ磻��2�ս꤬����Ŭ������������Ǥ���
- ���Ф뤬���֤��줿�ϥ磻�Υޥ��ʡ��������ϡ��ƹ���緿ŷʸ��ʹ��13��ˤ��Ҥ���緿ŷʸ���¤Τ褦�ʽ�Ǥ���
- �ޥ��ʥ�����ĺ��ɸ��4,200m���ꡢ�Ͼ��ŷ���˺������줺��ǯ���̤������줿����¿�������ⴥ�礷�Ƥ��ޤ���
- �����礭���ԻԤ��ʤ���������⾯�ʤ��Ķ��Ǥ���
- ��
- ������¬����
- ���Ф�ˤϡ��ʲ��˼����褦�ʸ��ش�¬�ﵡ����ܤ���Ƥ��ޤ���
- �����Ǥϲ桹����äȤⶽ̣���äƤ���CCD�����ˤĤ���������ä������Ȼפ��ޤ���
 ��
��
- ����CCD����顧���Ф��������������Suprime-Cam��Subaru Prime Focus Camera��
- ���Ф�˻Ȥ��Ƥ����¬��CCD�����ϡ�Suprime-Cam�ȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- �桹������¬���ˤȤäơ�����ü��ŷ��˾����ˤɤΤ褦��CCD����餬�Ȥ��Ƥ���Τ����Τ뤳�ȤϤȤƤⶽ̣����Ȥ����Ǥ���
- Suprime-Cam�˻Ȥ��Ƥ���CCD�����ϡ�10���CCD���åפǹ�������Ƥ��ޤ���
- 1���CCD���åפϡ�2,048x4,096���ǤΥ��åפǹ������졢���줬���������2���5��=10���¤٤�졢�����̤����֤���⥶�������β��������ޤ���
- ���äƤ��Υ����Ϲ��10,240���ǣ�8,192���Ǥξ������Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���
- ����CCD�ϡ����������Τ� -98�����Ѥ������Υ������ޤ���16�ӥåȡ�65,000��Ĵ�ˤβ�����������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- CCD�Υ����פϡ����̾ȼͷ��ե졼��ȥ�ե�������Back-illuminated Frame Transfer CCD�ˤȸ��äơ�����CCD�����̤������ͤ��Ƽ������ޤ���
- �������Ѥ�100%�ǡ���������ȤäƲ��Ǿ���ž���������ȤߤˤʤäƤ��ޤ���
- �����ե졼��ȥ�ե���CCD�ȸ����ޤ���
- CCD�ϡ�����Ū�˥��ꥳ����ľ�˥ե��ȥ�������������ž���Ŷˤʤɤ�����Ƥ��ޤ��������������������Ŷ�������٤ƥ��ꥳ����Ĥ����������ꥳ����Ĥ���������������˿�������Ǯ�Υ�������������˺�������S/N�ι⤤�����������ޤ���
- ���̾ȼͷ��ϡ�CCD�λٻ��ΤǤ��륷�ꥳ����Ĥ����äơ�����ä��̡����ʤ�������̤���������ͤ�������ΤǤ���
- ������ˡ�ˤ��������ʸ������Υ����˼��⤵�줺��16�ӥåȳ�Ĵ������ͭ���˼������뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ���
- �ޤ�������CCD�ˤϲ���ž�������ʤ�����������Ȥä�ž�����������ʤΤǡ�������ž��������ˤϻ����ǻ���������ʤ���Фʤ�ޤ���
- ���Τ��ᡢ�ᥫ�˥��륷��å���ɬ�פˤʤ�ޤ�������ž����ž���Υ������ޤ��뤿��ˤ�ä���Ԥ�졢ž�����פ�����֤�1ʬ�Ȥʤ�ޤ���
-
- �ڻ��͡�
- ������������֤��줿10������̾ȼͷ�CCD���åפǹ�������륫���
- �������ǻҿ�����2,048 x 4,096���ǡ���10��
- ������������������ס�10,240 x 8,192����
- �����ǥ���������15um x 15um
- ���������ѡ���153.6mm x 122.9mm��10���CCD��ס�
- ������������300nm��1,100nm
- ��ǻ�١���16�ӥå�
- ���������̡���168MB/1�����
- ������������ƹ�SITe�ҡ��ѹ�EEV��E2V�˼ҡ��ƹ�MIT-LL
- ����ѡ�����������������륨���3W x 2unit��176K = -98���
- �����ƻ������30'��30/60��ˡ����ľ�¤�Ʊ�����
- ���ɤ߽Ф����֡�60��
- ��˰���Ų١���80,000e-
- ���ɤ߽Ф��Υ�������10e-��
- ������å������ᥫ�˥��륷��å���1�á�
- ���ե��륿����ͭ����������192mm��158mm����10����Ʊ����Ǽ
- �ڻ��͡�
 ŷ�δ�¬�˻Ȥ��Ƥ���CCD���åפϡ����ߤβ桹�����Ƥ��륤���饤��CCD�Ȱ�ä��Żҥ���å���ǽ������ޤ���
ŷ�δ�¬�˻Ȥ��Ƥ���CCD���åפϡ����ߤβ桹�����Ƥ��륤���饤��CCD�Ȱ�ä��Żҥ���å���ǽ������ޤ���
- ���Υ����˺��Ѥ���Ƥ���ե�ե졼��ȥե�����CCD�ǻҤ��Ǥ�������Υ����פȸ��äƲ���ǤϤ���ޤ���
- �ޤ�������CCD��Ȥ��ȷ������1990ǯ����Ⱦ�Ǥ��ꡢ�����ᥬ�ԥ����륵�����η�¬��CCD�����ϤۤȤ�ɤ��Żҥ���å��Τʤ��ե�ե졼��ȥ�ե����Ǥ�����
- ��������ŷ�δ�¬��CCD���åפ�����������ϡ��ѹ��EEV��English Electron Valve����E2V��Marconi�Ҥλ����˼ҡ��ƹ���å����ɼһ�����SITe�ҡ��ƹ�ޥ����塼���åĹ�����إ����MIT-LL�Ǥ�����
- �����ε��ؤ�Ǯ����ŷ�δ�¬�Ѥ�CCD�ǻҤ�ȯ���Ƥ��ޤ�����
- ���ߤ⡢�����ε��ؤ��濴�ˤʤä�ŷ�δ�¬�Ѥ�CCD�ǻҤ�ȯ���Ƥ��ޤ���
- ���ߡ��桹������˻ȤäƤ���ǥ�����ˤ�4,000��3,000�������٤λ����ǻҤ��Ȥ��Ƥ��ơ����Ǥ�����Ф��ޤ��ܿ����������ϼ����ޤ���
- ��������ŷ�δ�¬�Ѥ˻Ȥ��륫���ϡ����ǿ��⤵�뤳�Ȥʤ��顢����1��1�Ĥ������䡢�Ż���Ѥˤ��Υ������㸺��ž�����ˤ�����Υ������㸺���������Ȥ館�뤿��ιⴶ�٤Ǥ��뤳�Ȥ����ڤ���ǽ�Ȥʤ�ޤ���
- ���˼������ޤϡ�φ150mm�Υ��ꥳ���ϡ���������CCD�����ǻҤΥѥ�����ޤǤ���
- ���Υ����Ϥ���6�Ĥ�CCD�����ǻҤ��Ǥ��ޤ�����α�ޤ꤬�ɤ���Сˡ�
- ���Ф�ǻȤ��Ƥ��뻣���ǻҤϹ��10�ĤǤ����顢���δ��ĤǺ����6�Ĥ�CCD�ˤ���ˤ⤦����δ��Ĥ��������ǻҤƤ���ɬ�פ�����ޤ���
- ���̤�CCD�ǻҤ����˾������Τǡ�Ʊ��φ150mm�Υ����ϡ����餳�����Ϥ뤫�ˤ���������ǻҤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���Ф�˾����˻Ȥ��Ƥ���Suprime-Cam�ϡ����������Ų٤�80,000e-�ȸ���졢�ɤ߽Ф��Υ�����10e-�ȤʤäƤ���Τǡ�S/N�Ǹ�����78dB��8,000:1�ˤ�ǽ�Ϥ���äƤ��ޤ���
- ���̤�CCD��256��Ĵ��10���٤ΥΥ�������äƤ��ޤ����顢����ǽ�Ϥϡ�310�ܤ⤹����Ƥ��ޤ���
- ���Υ�����10ǯ�ۤ�����1990ǯȾ�Сˤ��߷��ۤǺ���Ƥ��ޤ���
- ���ǤϤ���ۤ��ܿ������ʤ�������ǻҤǤ⡢�����ϻ���κ���ü��Ԥ����ѤǤ�����
- �����ϡ�1,000 x 1,000���Ǥ����̷�¬�˻Ȥ��Ϥ����ǡ�������礭�ʲ�����ǥ������������ѥ�����⤢��ޤ���Ǥ�����
- RAM�����32MB���٤�HDD��1000MB�������������ä��Τǡ�¿���ϥӥǥ�����Dz�����������ơ��ӥǥ��ơ��פ�ӥǥ��ǥ���������¸���Ƥ������Ǥ�����
- ����ʻ����168MB�β����ˤ�륫��餬����Ƥ����ΤǤ���
- ��
- ���Ф�ŷ��˾����Ǥϡ����Τۤ����ʲ��˼����褦�ʸ��ش�¬���֤���������Ƥ��ޤ���
- ��
- ���������ʥ���ջ������֡�CIAO��Coronagraphic Imager with Adaptive Optics��
- ������˼���դ���줿�Ť�ŷ�Τ��ֳ����ǻ��Ƥ��뤿������֡�
- ���뤤ŷ�Τ˥ޥ����������뤤ŷ�Τζ�ˤ���Ť�ŷ�Τ��¬�����Τǡ����۰ʳ���������¸�ߤ�õ��Τ���Ū����
- ��
- ��������ŷ�λ���ʬ�����֡�FOCAS��Faint Object Camera And Spectrograph��
- ���˰Ť�ŷ�Τ�ѻ�����ʬ�����֡�1���֤�Ϫ����28������ѻ���
- ʬ����ǽ�������Ƥ��ƶ�Ϸ��������θ�������ѡ�
- ��
- �����������ֳ�����ʬ�����֡�COMICS��Cooled MidInfrared Camera and Spectrometer��
- 10um��20um�Ӱ���ֳ����Ǥ�ŷ�δ�¬�����֡�����Ĺ����Ĺ�θ��Ф�Ԥ����ᡢ���֤�4K��-270��ˤޤ���䤵��ƻȤ��롣
- �����η���������ϳ���Ϥη����������¬��
- ��
- ��
- �������Ф�ʳ����緿˾���
- ��
- �ʲ��ˡ������ε���ŷ��˾����ΰ������ޤ���
- ����ɽ���顢�緿ŷ��˾����ϡ�����10ǯ�δ֤˼����˺���Ƥ������Ȥ��狼��ޤ���
- �����ñ�ΤǸ���10m���饹�ޤǺ����褦�ˤʤꡢʣ���ζ����Ȥ߹�碌��10m�ʾ�Τ�Τ��Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���������¤�˾����������褦�ˤʤä��طʤˤϡ����إ��饹������ĥΨ�Τ�Τ������褦�ˤʤä����Ȥȡ�AO��Adaptive Optics�ˤο���ˤ���緿�������μ���Ǥ⽽ʬ�ʲ����Ϥ���Ĥ��Ȥ���ǽ�ˤʤä����Ȥ����ޤ���
- ��
- ���
- �Ƥ�̾
- ������礭��
- �����ס�������
- ŷʸ��ڤӽ����
- ������ǯ��
- 1
- VLT
- ��Very Large Telescope��
- ����˾�����
- ��Very Large Telescope��
- 1620��cm
- ��820cm x 4���
- ���������F13
- �ʥ��ߥ���F15
- ������
- �ʥ��ߥ���F15
- �衼���å���ŷŷʸ��
- ��European Southern Obserbatory, ESO��
- �������ѥ�ʥ�
- ����
- ��European Southern Obserbatory, ESO��
- 1998
- 2
- ���å�I�����å�II
- ��KECK��
- 1460��cm
- ��996cm x 2���
- ���������������
- ������̡�F1.75�����뤤��
- ��å������������������̡�F15
- ������̡�F1.75�����뤤��
- ����ե���˥���ء�����ե���˥��������
- �ޥ��ʡ��������ϥ磻
- ����ꥫ
- �ޥ��ʡ��������ϥ磻
- 1993
- 3
- LBT
- ��Large Binocular Telescope,
- �����д�˾�����
- ��Large Binocular Telescope,
- 1180��cm
- ��840cm x 2���
- ������̡�F4�ڤ�F15
- �罰�����ꥢ���ɥ��Ķ�Ʊ
- ����ϥ�������
- ����ꥫ
- ����ϥ�������
- 2004
- 4
- GTC
- ��Gran Telescopio CANARIAS��
- ���������˾�����
- ��Gran Telescopio CANARIAS��
- 1040��cm
- ��������������������
- ��������������
- �ʥ��ߥ������̡�F15
- ��������������
- Roque de los Muchachos Observatory
- ���ʥ��
- ���ڥ���
- ���ʥ��
- 2006
- 5
- SALT
- ��Southern African Large Telescope��
- ��եꥫ��˾�����
- ��Southern African Large Telescope��
- 1020��cm
- -
- ����������ŷʸ��
- ��եꥫ
- 2005
- 6
- HET
- ��Hobby-Eberly Telescope��
- �ۥӡ������Х˾�����
- ��Hobby-Eberly Telescope��
- 920��cm
- -
- �ޥ��ɥʥ��ŷʸ��
- �ե������������ƥ�����
- ����ꥫ
- �ե������������ƥ�����
- 1996
- 7
- ����
- 820��cm
- ������̡�F1.8
- �������������̡�F12.2
- �ʥ��ߥ������̡�F12.6
- �������������̡�F12.2
- ���ܡ���Ωŷʸ��
- �ޥ��ʡ��������ϥ磻
- ����ꥫ
- �ޥ��ʡ��������ϥ磻
- 1999
- 8
- �����ߥ���
- 800��cm
- ��å������������������̡�F16
- ����ꥫ���濴�Ȥ���7����ζ�Ʊ����
- �ޥ��ʡ��������ϥ磻
- ����ꥫ
- �ޥ��ʡ��������ϥ磻
- 1999
- 9
- �����ߥ���
- 800��cm
- ��å������������������̡�F16
- ����ꥫ���濴�Ȥ���7����ζ�Ʊ����
- �������ѥ����
- ����
- �������ѥ����
- 2002
- 10
- �ޥ������1��
- 650��cm
- ���쥴������̡�F11
- �������������̡�F15
- �������ޥ�
- ����
- 2000
���������緿ŷʸ��
- �緿ŷ��˾����ϡ�����¾�ˡ�����ꥫ��Ω����ŷʸ��ʥ���ʽ��ˤǤϡ�25m�μ�������ELT��Exremely Large Telescope�ˤη��ߤ��ײ褵��Ƥ��ơ����å�˾����Ǥϡ�30m�μ�������CELT��California Extra Large Telescope������ե���˥�Ķ����˾����ˤηײ褬����ޤ���
- �����ε���ʸ��¤���Ķ��ϡ������г���1m����ϻ�ѷ��ε��̶��������Ȥ�˪��������Ȥ߹�碌�ư�Ĥ��礭�ʶ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ELT�Ǥϡ�91����Ѥ���CELT�Ǥ�1,080���Ȥ��Ȥ����ײ�Ǥ���
- CELT�ϡ����θ�2004ǯ������Ƥ�ȯɽ�����������ȥߥ顼���礭�����г���1.4m�Ȥ���614��ˤ���30m�μ������Ƥ�Ф��Ƥ��ޤ���
- ����˾�����10m��ۤ����礭�ʤ�Τ��о줹�����ˤʤ�ޤ�����
- ������������ӽФ����ǿ���ŷ��˾�����-���ϥå֥뱧��˾�����Hubble Space Telescope��HST�ˡ���2006.08.04��(2009.05.15�ˡ�2020.01.21�ɵ���
- �錄���Υϥå֥뱧��˾������Ф���פ�����ϡ�������Τ�����ޤ���
- �礭��˾������絤�����˻����Ф����Ȥ������ۤ⤵�뤳�Ȥʤ��顢�����¹Ԥ˰ܤ����桹�˿���ʱ���α��������äƤ��줿�ϥå֥뱧��˾����˴�ò�ȷɰդ�ɽ�����ˤϤ����ޤ���
- 1980ǯ�塢�ƹ�θ��ػ���ˤ��Ӥ��ӥϥå֥�μ����Primary Mirror�ˤ���������Ҳ𤵤졢����Ȥ��ᤫ�����ɤ�Ǥ��ޤ�����

- �ϥå֥뱧��˾����Υץ��������Ȥϡ��������������ΤǤ��ꡢ���������ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ����˲ä������ߤǤ⤽�α��Ѥ��äƤ�����������Ƥ��ꡢ��̿�ν����2013ǯ�ޤǤ˽������ˡ����ꤷ�ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǤ���
- ������������ޤߤΥϥå֥뱧��˾����ǤϤ����ΤΡ����ޥ������������˾������Ǵ��Ҳ𤹤�Τϲ��ͤ�����Ȼפ��ޤ���
- �����餯���ܤǤϷ褷���ǹԤ����ʤ��ä��ץ��������ȤǤ��ꡢ����Ϥ��������ץ��������ȤϤ⤦�ʤ��Ǥ��������Ȥ�ͤ���ȡ��ϥå֥�˾����Υץ��������Ȥ��˵�Ͽ���Ƥ������Ȥ�̵�̤ǤϤʤ��ȹͤ��ޤ���
- �ϥå֥뱧��˾����ץ��������Ȥϡ�������ʤ����⤬������ޤ�����
- ����������
- �ϥå֥뱧��˾����ϡ����賫ȯ����ȶ��˻�����夲�ޤ�����
- ����˾����ι��ۤ�1946ǯ���ƹ�ŷʸ�ؼ�Lyman Spitzer����Ƥ����絤���������֤���˾�����Astronomical advantages of an extra-terrestrial observatory�ˤ˻Ϥޤ�ޤ���
- �ƥ�ξ��DZ��賫ȯ���Ϥޤä�1950ǯ����20ǯ���970ǯ���Ⱦ�˥���ꥫ�Ҷ�����ɡ�NASA�ˤ����졼�ȡ����֥����Хȥ���ײ���Ǥ��Ф��ޤ�����
- �ϵ��Ǥϴ�¬����ʥ��������X��������˲Ļ���ʶ�糰�����ֳ���ޤ�ˤ��ֳ����С������礭��ŷʸ������4���Ǥ��夲��Ȥ����ײ�Ǥ�����
- �Ļ���ϡ������Τ��Ȥʤ����Ͼ�ޤ��Ϥ������ǤϤ���ޤ������絤���ɤ餮�Dz�����������뤿��ˡ��絤�����ǤβĻ���ѻ���˾�ޤ�Ƥ��ơ����ΰ�̣�DzĻ��˾����ϥå֥�δ��Ԥ��礭���ä��ΤǤ���
- ���ηײ�ϡ�1977ǯ�ˤޤ�ͽ�����Ĥ����Ļ���ȥ��������ŷʸ�������ߤ�ǧ�Ĥ�����ޤ�����
- ���줬�ϥå֥뱧��˾����ȥ���ץȥ���������Ǥ�����
- �ϥå֥�ȸ���̾����ͳ��ϡ���ϷϤ��ä��٤�®�٤ǰ�ư���Ƥ��뤳�Ȥ�ȯ����������ꥫ��ŷʸ�ؼԥ��ɥ����ϥå֥���Ρ�Edwin Hubble��1889 - 1953���ϳ���Ϥ��ԡ��ء�����Τ���ҡˤˤ��ʤߤޤ���
- �ƹ����ܤˤ��ϥå֥�˾����ץ��������Ȥ�ǧ�Ĥ����ꤿ��ΤΡ��ϥå֥�˾������ºݤ˱��������Ω�ĤޤǤ�13ǯ��ǯ�������ޤ�����
- ��ȯ���٤�ϡ��ץ饤�ޥ�ߥ顼�ʼ����������٤�˲ä����������֤��Զ�硢����ԥ塼�����եȥ������ΥХ������ڡ�������ȥ롦�����㡼�����ȯ���Τ��Ťʤä����Ȥˤ��ޤ���
- ������Ū��ǽ
- �ϥå֥뱧��˾����ϡ��礭��φ4.3�����������Ӥ�Ȥ���ȶ�12.0���ˡ�Ĺ��13.3m�ǽŤ���12�ȥ�ޤ���
- ˾����η����ϡ���å���������ƥ������Ritchey-Chretien�����ǥ��������˲��ɤ��ƻ������ä���ΤǤ���
- �ϥå֥�μ���ϡ��ƹ�Perkin-Elmer�ҡ�Danbury, Connecticut�ˡʸ��ߤϡ� Hughes Danbury Optical Systems��) �������餤���߷�����Ԥ��ޤ�����
- ����ϡ�����2.5m�Ǹ�����300mm���濴����600mm�η꤬�������ɡ��ʥåľ��ˤʤäƤ��ޤ���
- �Ť���900kg�Ǥ�����
- �����ȸ��¤����1��8.33�Ǥ��ꡢ����Ū�ˤ��ʤ��������Ǥ���
- ���ܤ��ϥ磻�Υޥ��ʥ��������֤���ŷ��˾����֤��Ф�פθ���8.2m����٤Ƥ��ʤ꾮�������¤Ǥ���������˻��äƹԤ��ˤϤ����礭���������äѤ����ä��Τ����Τ�ޤ���
- ���˻Ȥ�줿�����ϡ��ƹ��˥ҡ�Corning�ˤ���ȯ����Ķ����ĥ���饹ULE��Ultra Low Expansion���Ǥ��ꡢ�֤��Ф�פζ������ˤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ϥå֥�θ��¤Ǥϡ����κ����ȤäƤ�ϥ˥��¤�ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ���褦�Ǥ���
- �֤��Ф�פΤ褦������¼���Ǥϥϥ˥��¤�Ȥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����ˡ��̤���ˡ�Ǻ���Ƥ��ޤ���
- ���ζ����ԥ塼������ȥ졼����¬��ˡ�ˤ�ä�1/20��Ĺ���١�30nm�ˤ��ж��̾��˸��ᤷ�Ƥ����ޤ�����
- ����ˤ��ζ��ξ�ˡ�75nm�ʥʥΥ�ȥ�˸��Υ���߾����25nm���Υեò��ޥ��ͥ�����Υ����ƥ����ʤ���ޤ�����
- ����2.5m��30nm�����٤θ���ù��ȸ����ȡ�����ɡ�����Υ����ɡ�100m x 100m�ˤ�0.12mm�ʲ��α��̤Ǥʤ餹�褦�ʤ�ΤǤ���
- ���Τ��餤�ˤ��ʤ��Ȼ糰�������ֳ��ޤǤθ������٤褯�����˽���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ������μ�ʻ���
- �����¡���2.4m��94.5�������
- ������������57.6m��189ft��
- �������ס�����å���������������Richey-Chretien�˷�
- ���������ѡ�����4.3m2��46ft2��
- �������桧��F/24
- ��������������300mm
- ���������ULE��Ultra Low Expansion��
- ���ߥ顼����Υȥ�֥�
- �ϥå֥����θ����Ȥϡ�1979ǯ�˻Ϥޤ�1981ǯ�ޤ�³���ޤ�����
- ���θ����Ȥβ����ǡ�NASA�ϥѡ�����ޡ��Τ�����˰۵Ĥ������ᡢ���줫�餵��˺�Ȥ��٤졢�絬�Ϥ��ɲ�ͽ�����;���ʤ�����ޤ�����
- NASA�ϡ�ͽ�����ͽФ���Τ��ɤ�����˥��ڥ��ѤΥߥ顼����¤���뤳�Ȥ���ߤ����ϥå֥���Ǥ��夲��1ǯ�٤��1984ǯ10��˱�������뤳�Ȥ���ޤ�����
- �����Ȥ��ʤ���������٤줿�Τ��Ȥ����ȡ��㤷��������ư�Τ���˥ѡ�����ޡ��Ҥ���ʬ�ε������礬��Ф������Ѥ��⤵����㤤���Ѥ�û����������Ƥ��Ƽ������Ƥ��ޤä�������ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ޤ��������Υѡ�����ޡ��Ҥϡ����Ū���֤����̩���ص�����߷���¤�ϼ��Ӥ������ΤΡ��ϥå֥�Τ褦���緿�����̤����٤��᤹�����ʤ�����Ͻ��ƤǤ�����
- ���Υץ��������Ȥ��Ԥ��뤿��˥ѡ�����ޡ��Ҥϡ�����ü�Υ졼��¬�굡��ȸ���ù����Ĥ館����������ä��ΤǤ��������줬���ޤ��Ԥ����������٤��NASA���Ϣ���ؤ��餫�ʤ궯���ץ�å��㡼��������줿�����Ǥ���
- ���Υץ�å��㡼��ޤ�Ǽ���٤�ˤĤʤ��ä��Ȥ��������Ƥ��ޤ���
- �ѡ�����ޡ��ҤȤ��̤ˡ��Хå����å��ѤȤ���Kodak�Ҥ�Ʊ���ߥ顼����¤����������Ǥ��ơ�����μ�ˡ�ˤ�ä�NASA���᤹����ͤ����������ߥ顼��ײ��̤������Ǽ�ʤ��ޤ�����
- �����ѡ�����ޡ��Ҥ˶����ץ�å��㡼��Ϳ�����褦�Ǥ���
- Kodak�ҤΥߥ顼�ϡ����ߥ��ߥ��˥���ؽѶ��� (Smithsonian Institution)��Ÿ�����Ƥ��뤽���Ǥ���
- �ѡ�����ޡ��Ҥμ��������ߥ顼�ϡ��ºݤˤϤ�����٤줿���ᡢ�ǽ�Ū�ˤ��Ǥ��夲��1986ǯ9��ޤDZ������ޤ�����
- �Ǥ��夲ͽ���8��������1986ǯ1��˥����㡼�λ��Τ����ꡢNASA�α���ײ褽�Τ�Τ��٤�Ƥ��ޤ��ޤ�����
- �ϥå֥�˾������ǽ�Ū���Ǥ��夲��줿�Τϡ����줫��4ǯ�٤줿1990ǯ4��Ȥʤꡢ�ǥ������Х�ˤ�äƱ���˱��Ф�ޤ�����
- 4ǯ�α��������ϥå֥�ϥ����롼����ݴɤ��졢�Ǥ��夲�ν��֤��ԤäƤ��ޤ�����
- ��
- ��������
- 1990ǯ���Ǥ��夲��줿�ϥå֥�˾����ϡ������˳����Ф������Ȥ����Ȥ����ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �Ǥ��夲���2�����ܤǥϥå֥�˷���Ū�ʷ�٤����뤳�Ȥ��狼��ޤ�����
- ǰ����˺��줿����Ǥ��ä��Τˤ⤫����餺�����̼���������ԥ�ȤΥܥ����������������ʤ����Ȥ��狼�ä��ΤǤ���
- �ܤ䤱�����θ����ϡ�����2.4m�μ����ü�����߷��ͤ��⤿�ä�0.002mm��2�ߥ������ʿ�ˤʤäƤ�������Ǥ�����
- ���Τۤ�Τ���äȤ�����¤�ߥ�������50mm�˥ܥ������������Ȥ��Ʒ�Ф��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����Ƥ��ޤä��ΤǤ���
- �礭�ʥץ��������Ȥ��Ԥ˽���餻�����ʤ�NASA��ŷʸ�ؼԥ�����ϡ������������եȤ�ȯ���Ƶ��̼�������������������ˡ��ͤ������ޤ�����
- ���β����������եȥ������ϡ���������̤����ʤ�Ȥ���Τˤʤ������������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Υ��եȥ�������ͥ���ʤ�Τǡ��̤����ӤǤ���������θ��Ǥ�ή�Ѥ����Ȥ�������ʪ�����ޤ�����
- �ޤ����ϥå֥�˾����ϡ����餫�饹�ڡ�������ȥ�ˤ�����Ū���ݼ顢���������åץ��졼�ɺ�Ȥˤ�뱿�Ѥ��ײ褵��Ƥ��ޤ�����
- ���åץ��졼�ɤˤϡ���¬���֤�ǿ��Τ�Τ˸��륵���ӥ����ߥå����䡢˾����λ��������ʤ른�㥤����������������ӥѥͥ�θ��ޤޤ�Ƥ��ޤ�����
- ���Υץ��������̤��ơ�ȴ��Ū�ʥϥå֥����ǽ�����ν����ץ�����ब�Ȥޤ�ޤ�����
- 1993ǯ�˹Ԥ�줿�ǽ�Υ����ӥ����ߥå�����Servicing Mission 1��SM1�ˤϡ�4�ͤα������ԻΤˤ�äƽҤ�5���֡����35����28ʬ�˵ڤ�������ư���ʤ��졢����ε��̼�������������������֤ȼ������֤��Ȥ߹��ޤ�ޤ�����
- ���Υ����ӥ����ߥå����ϡ�COSTAR = Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement�ȸƤФ�Ƥ��ޤ������ƥ�����2���ܤ�WFPC2��Wide Field and Planetary Camera 2�����֤��������ޤ����������顼�ѥͥ��04���Υ��㥤���������פ���쥳��ԥ塼���⥢�åץ��졼�ɤ��ޤ�����
- ���κ�Ȥˤ�ꡢ�ϥå֥�Ϥޤ��ˡ��Ի�Ļ�פ�ǡ����ߤ�����ޤ�����
- �����礭�ʼ�Ѥ�Фƥϥå֥�ϡ�����ޤǤˤʤ����ꥢ��ŷ�β�����桹�˶��뤷�Ƥ����褦�ˤʤ�ޤ�����������ˤϡ��Ͼ�˾����ǤϷ褷�Ƹ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ä��٤������ʤ�Τ�¿������ޤ�����
- �ޤ����ϥå֥뱧��˾����θ��Ӥϡ������ǯ����137��ǯ�Ǥ��뤳�Ȥ��դ����¬�䡢�ϵ夫��Ǥ�֥���ȥ顦�ǥ����ס��ե�����ɡס�Ķ������ˤˤ����Ϥ�ȯ���������ưŹ�ʪ���δġ�a ghostly ring of dark matter���ϵ夫��50����ǯΥ�줿����Ĥ�ȯ�����줿��Τǡ�ľ�¤�260����ǯ��10����20��ǯ������Ĥζ���Ĥ����ͤ������ξ�Ǽ��ϤΰŹ�ʪ��������Τ褦�˹����ä��Ȥ����ˤʤɤ����ꡢ¿�������̤��Ƥ��ޤ�����
- ��
- �������� ��2020.01.21�ɵ���
- �ϥå֥�ϡ����θ岿�٤��Υ����ӥ����ߥå����������¬���֤κ����䱿�����֤θ��Ԥ��Ƥ��ޤ���
- SM1����1993ǯ��COSTAR�� = Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement�ˡ�WFPC2�����ؤθ�
- SM2����1997ǯ��GHRS�θ�FOS�θ���¬�ѥơ��ץ쥳������ȾƳ�Υ���쥳�����˸��Ƽ���Ǯ������
- SM3A����1999ǯ��6���Υ��㥤���Τ���3�����ξ㤷������θ�6���ˤΤ���ζ۵�ư��
- SM3B����2002ǯ��FOC���֡�NICMOS�����衣���ۥѥͥ�θ�2���ܡˡ�
- SM4����2009ǯ���Ǹ�ν����ߥå����6���Υ��㥤����ACS��STIS���˥å�����ǥХåƥ��3�����ܤΥ����WFC3��COS��
- ���Υϥå֥��2013ǯ�Ǹ������ह��ȸ����Ƥ��ޤ������ʤ����ºݤϡ�2020ǯ�����ǤⱿ�Ѥ��졢2030ǯ����2040ǯ�ޤǻȤ��³����ͽ��ȸ����Ƥ��ޤ�����
- ���θ�ϡ�������Υ������ॺ�������åֱ���˾�����James Webb Space Telescope��JWST�ˤ�2013ǯ���Ǥ��夲���ʼ¹Ԥ��٤��2021ǯ�Ǥ��夲ͽ��ˡ�����˾����˥Хȥå���ͽ��ˤʤäƤ��ޤ���
- �������ॺ�������å֤ϡ�NASA����2��Ĺ���ǥ��ݥ��ײ��䤷�ʤ��ʪ�Ǥ���
- ��Ϻ�Ǥ�桢����õ����ޤ75��ˤ�ڤֲʳإߥå������Ԥ�����1965ǯ���ᤤ�����˱���˾�����ɬ�������ʤ��ƥϥå֥�˾����μ¸���¿��ʤ���Ӥ�̤����ޤ�����
- ���θ��Ӥ����ơ��ϥå֥�θ�ѵ������̾�����դ����뤳�Ȥˤʤä��ΤǤ���
- ���������������ॺ�������å�˾������ֳ�˾����Ǥ��ꡢ�ϥå֥�Τ褦�˲Ļ��˾����ǤϤ���ޤ���
- ������ͳ���餫���ϥå֥�α�̿��˾�����϶�������ޤ���
- �����������Ӥ�Ĥ��Ƥ���ϥå֥�ˤ⽪��λ�����ޤ���
- ���ν���ϡ�����Ū�ˤϥϥåԡ�����ɤˤʤꤽ���⤢��ޤ���
- ���賫ȯ�ˤϤ��⤬������ޤ���
- ������¿���λ��Τ�ȼ���ޤ���
- ���ڡ�������ȥ�λ��Τζ������衢NASA�ϥ��ڡ�������ȥ�ײ�˽�������Ǥ���2008ǯ�ޤǤ˥��ڡ�������ȥ������ͭ��õ������CEV�ˤ�ȯ��������ˤ�äƱ��襹�ơ������η��ߤ�ʤ�Ƥ������ˤ��Ǥ��Ф��Ƥ��ޤ���
- ���襹�ơ������ϡ��ϥå֥�˾����Ȥ��̤μ���ƻ�DZ��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���äơ��ϥå֥�Τ��������ͽ����夷�ƥ����ӥ��ץ��������Ԥ��뤳�Ȥ�����ˤʤäƤ��ޤ��ޤ�����
- �ϥå֥�Υ����ӥ����ߥå����ϡ�������ư���濴�Ȥʤ뤿�����˴�����ȼ���ޤ���
- �ե����롦�����ա�Fail - Safe Program��������Τ������ä��Ȥ����ԻΤ䥹�ڡ�������ȥ������˵��Ԥ�����Ȥ����Хå����åץץ������ˤ���ʬ�ˤʤ���ʤ������ӥ����ߥå����Ϸײ褬Ω�Ƥ��ʤ��Ȥ�����ͳ���顢���ڡ�������ȥ�ϥϥå֥�ΰݻ��ʥ����ӥ����ߥå����ˤ�Ԥ�ʤ����Ȥ���ꤷ���ΤǤ���
- ���������ϥå֥��;����ʤ�Ȥ���̿���������Ȥ�������Ȥ���̻�̱�������礭�ʳ�ư��ԤäƤ��ޤ��������¤ˤϹ�ۤ�ͽ��������������ि�����Ū���ɰƤϼ�����Ƥ��ޤ���→���θ��ȯɽ2006.11��2009.05.15��
 ��
��
- �����ϥå֥�κ��������
- 2013ǯ�ˡ��ϥå֥����䤬����뤳�Ȥ����餫��ηײ��̤���Ȥ��Ƥ⡢���ν���ޤǤˤ�¿�������꤬�Ĥ��ޤȤ��ޤ���
- �ϥå֥�ϡ����ڡ�������ȥ�Υ����ӥ����ߥå��������ƹ���Ƿ��ߤ���Ƥ��뤿�ᡢ�ݻ�������Ȥ��䤿���ȼ�̿��̤ᤫ�ͤޤ���
- �ϥå֥�ˤϡ�6�ĤΥХåƥ�����ꡢ����ƻ���֡� = 96ʬ�ˤΤ����������ʬ�ʺ�Ĺ��36ʬ�ˤǻȤ��ŵ��ϡ��������ӥѥͥ�Ǥν��ŤǤޤ��ʤäƤ��ޤ���
- ���ΥХåƥ�ˤ��̿�����ꡢ100,000�����٤ν����Ť�̿���Ĥ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���μ�̿�ϡ�2007ǯ����2008ǯ��ˬ�����ˤʤꡢ���δ֤˿������Хåƥ�˸��ʤ��ȡ��ϥå֥�μ�̿�ϿԤ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- �ޤ����ϥå֥�λ��������椹�른�㥤���ϡ�6���Ȥ߹��ޤ�Ƥ��ơ����Ѥˤϡ�3�ĤΥ��㥤����Ȥ����Ĥ�3�ĤϥХå����å��ѤȤ��Ƥ��ޤ��������Υ��㥤���ϡ��Ǥ��夲���2�Ĥ��ξ�ǻȤ��ʤ��ʤ�4�ĤDZ��Ѥ�³���Ƥ��ޤ�����
- 2005ǯ�ˤϡ�4�ĤΥ��㥤����2�ĤŤĤ�ʬ���ơ�2�ĤDZ��Ѥ�����ˡ���ڤ��ؤ��ޤ�����
- �Ĥ�2�ĤϥХå����å��ѤǤ���
- ����ʤ�3�ĤΥ��㥤����Ȥ�ʤ�������٤��ɤ������ݻ����Ǥ��ʤ��ΤǤ�����ɡ����ˤ�ޤ�����֤Τ褦�Ǥ���
- ����4�ĤΥ��㥤���Τ���1�Ĥϡ�2008ǯ��̿���Ԥ���ȸ����Ƥ��ޤ�����
- 6���Υ��㥤����2009ǯ�κǸ�ν����ߥå����SM4���Ǹ�Ȥ��Ԥ��ޤ����������٤�Ʊ�������פǤϤʤ���û���ּ�̿����50,000���֡ˤ��߷פν��跿���㥤����3�Ĥȿ��������֤μ�̿���IJ��ɷ����㥤��3�Ĥ�2����Ǥ�����
- SM4�θ塢�ϥå֥�Ͻ��跿���㥤��3���DZ��ѤƤ��ޤ��������Τ�������Ĥϥ��㥤���μ�̿���褿������ߤ������跿���㥤��1���Ȳ��ɷ����㥤��2���DZ��Ѥ���Ƥ��ޤ�����
- 2018ǯ10��Ѥ��Ƥ������㥤���ΰ�Ĥ���̿���Ԥ����Τ��̤Υ��㥤�����ڤ��ؤ����Ȥ��������ư��ʤ��Ȥ������꤬�����ޤ�����
- �����Ͼ夫��ν����˼���Ȥߡ��ǽ�Ū�˲��ɷ����㥤��3�ĤǤα��Ѥ�Ϥ�ޤ�����
- ������6���Υ��㥤����2009ǯ�˸��줿��ΤΡ����Τ�����3�ĤΥ��㥤���ϼ�̿���Ԥ��Ƹ��ߤ�3���ΤߤȤʤä�11ǯ�ܤ�ޤ��褦�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- NASA�Ǥϥϥå֥�α��Ѥ�Ǥ������Ĺ�������뤿��㥤��1���Ǥα��Ѥ�;���ʤ������ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ϥå֥�ϡ�Ĺ��13��ȥ롢����12�ȥ�ε����¤ʪ�Ǥ���
- ���줬���Ͼ��600km�������㤤��ƻ�Ǽ��Ƥ��ޤ���
- 2013ǯ�˥ϥå֥��̿���Ԥ����Ȥ����ϥå֥���絤�������������̰���56�٤Τɤ���������ޤ���
- ����ʷ�¤ʪ�ϡ�������dz���Ԥ��뤳�ȤϤʤ�����ij��������줫���Ͼ������ޤ���
- ���λij������ʾ����Ǥ���Ȥ�����ε�ƻ������Ԥ�ʤ���Фʤ�ޤ���
- ����NASA�ϡ����賫ȯ�ǽ���ʶ��̤�Ω������Ƥ��ޤ���
- ����ϼ��ͽ���Ǥ������賫ȯ�ˤϡ�����ʤ����ɬ�פȤ��ޤ���
- ���Υϥå֥�ץ��������Ȥ˴ؤ��Ƥ⡢Ω���夲�����4���ɥ��500���ߡˤ���Ǥ����Τˡ��ºݤμ��٤������15�ܤ�60���ɥ��7200���ߡˤˤ�ʤ������ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����ͽ����ɤΤ褦�˷夷�Ƥ������ˤĤ��Ƥ⡢�ƹ�Ǿ�����Ĥ������פʲ���ˤʤäƤ���ΤǤ���
- ��
- �����θ��ȯɽ - SM4 ������2006.11.01�ˡ�2009.05.15�ɵ���
- 2006ǯ11��1����ī����ʹ��ͼ���ǡ��ƹ�NASA�ϡ����̤ˡ����ڡ�������ȥ�ˤ��ϥå֥뱧��˾�����HST�ˤν����ץ������ʥ����ӥ��ߥå����SM4�ˤ�¹Ԥ����ȯɽ����ޤ�����
- �ƹҶ�����ɡ�NASA�ˤΥޥ����롦����ե���Ĺ���ϡ�10��31����ȯɽ����ǡ�2008ǯ5��˥��ڡ�������ȥ���Ǥ��夲�ơ�7�ͤα������ԻΤ��ϥå֥뱧��˾����˶�Ť���Ϸ�ಽ���ʤ�Ǥ������Ӥ�����������֤��ʤȸ���ۤ�������������WFC3�ˤʤɤ������֤���Ȥ��ޤ�����
- ����ޤǡ�NASA�ϡ��ϥå֥�ν������Ԥˤϡ���ݱ��襹�ơ�������ISS�ˤ˸������̾�����ԤȤϱ��Ԥ��ۤʤ뤿�ᡢ����ȥ�˲��餫�Υȥ�֥뤬ȯ��������硢����ȥ�ξ��Ȱ���ISS�˶۵�����Ȥ��������к����Ȥ�ʤ����ᡢ�ϥå֥�ν����ץ��������������ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �ޤ���NASA�ϡ�ISS�η��ߤ�ޤ��ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ�������������Ƥ��ޤ�����
- �������Ԥ����ͳ�ˤĤ��ơ�����ե���Ĺ���ϡ�2006ǯ���̤�������3��Υ���ȥ�����Ԥǥ���ȥ뱿�Ĥΰ��������夬��ǧ�Ǥ������Ȥ�夲�Ƥ��ޤ�����
- ����ȥ�����Ԥ�ޤ�����ץ������ˤ��������Ѥϡ���9���ɥ����1050���ߡˤȸ��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ����ޤǻȤä������Ѥ�15%�� = 60���ɥ� x 0.15�ˤ��˷夹�뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��
- ��2009.05.26�ɵ��ˡ�2008ǯ5��˹Ԥ���Ϥ����ä������ӥ��ߥå�����SM4�ˤϡ�11��˱�����졢����˥��ȥ��ƥ������Ǥ��夲ľ���ˡ��ϥå֥�¦�˿���ʸξ㤬����������ʥ���ȥ����롦��˥å�/�ʳإǡ����ե����ޥå��� = CU/SDF �θξ�Τ��ᡢ���ȥ��ƥ����ǽ�������ɬ�פ��ФƤ�������ˡ��Ǥ��夲�����ٱ������ޤ�����
- SM4�ϡ��ǽ�Ū��2009ǯ5��11���˥��ڡ�������ȥ롦���ȥ��ƥ����ˤ�äơ������åȡ�����ȥޥ���Ĺ�ʲ�7̾�Υ��롼��������Ǽ¹Ԥ˰ܤ���ޤ�����
- SM4�ϡ�11���֤�Ǥ̳�ǡ�5���������ư�ȡ����ѥ�����WFC3�ˤμ���ؤ����ξ㤷���ǡ����������֤θʤɤ��Ԥ��ޤ���
- ���Υߥå�����ޤ��Ԥ��ȡ��ϥå֥��2014ǯ�ޤDZ��ѤǤ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ��2009.05.26�ɵ��ˡ�2008ǯ5��˹Ԥ���Ϥ����ä������ӥ��ߥå�����SM4�ˤϡ�11��˱�����졢����˥��ȥ��ƥ������Ǥ��夲ľ���ˡ��ϥå֥�¦�˿���ʸξ㤬����������ʥ���ȥ����롦��˥å�/�ʳإǡ����ե����ޥå��� = CU/SDF �θξ�Τ��ᡢ���ȥ��ƥ����ǽ�������ɬ�פ��ФƤ�������ˡ��Ǥ��夲�����ٱ������ޤ�����
- SM4�ϡ�̵���˿�Ԥ��졢����ȥޥ���Ĺ�ʲ�7̾�Υ��롼�ϡ����ϻ���5��24������8�����ƹ�ե���˥������ɥ���������Ϥ˹ߤ�Ω���ޤ�������2009.05.26��
- �ϥå֥����ˤ�Ҥ٤ޤ����褦�ˡ�NASA�����߿ʤ�Ƥ��뱧�襹�ơ������ײ�Ȥϰ㤦��ƻ�Τ��ᡢSM4����¬�λ��֤��������Ȥ��ˡ���̳���ʥ��롼�ˤ�����������뤿��ν��֤Ȥ��ơ��Ͼ�ʥ��ͥǥ����襻���ˤǾ�̳���߽��ѤΥ��ڡ�������ȥ�֥���ǥС��פ��Ե����Ƥ��ޤ�����
- ����������ʥ����ӥ��ߥå����ȸ��虜������ޤ���
- �ޤ����ϥå֥뱧��˾����ο͵��ȡ�Ǥ̳�ι⤵�������˴�����������Ǥ�����
- �����ϥå֥����ܤ���Ƥ�����إ��������2006.11.09���ˡ�2009.05.02�ɵ���
- ��WFPC2��Wide Field Planetary Camera 2��1993ǯ���
- ��2004ǯ����ϡ�3�浡��WFC3 = Wide Field Camera 3 �α��Ѥ�ͽ�ꤵ��Ƥ�������������줿����2009ǯ5��ޤ��Ե���SM4�Ǹ�ȴ�λ��
- CCD������ȯŸ����٤Ʊ���˻��äƤ��������Ϥ�������ȴ�ñ�ˤϸǤ��ʤ�����ˡ����ߤΥϥå֥��1993ǯ���Ǥ��夲��줿2���ܤ�CCD������16ǯ�֤���Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ���ߤ�CCD������ȯŸ����٤ơ��ϥå֥��CCD�����ϸŤ�����������ޤ���
- ������������Ǥ�ϥå֥뤫�������Ƥ��������©���ݤ�ۤɤ��줤�Ǥ���
- ���Υϥå֥��CCD��������ǽ��ʲ��˾Ҳ𤷤ޤ���
- ��WFPC2�λ��͡�
- �������ס���MPP��Multi-pinned phase�����̾ȼͷ�CCD x4�繽��
- �����ǡ���800x800����
- ������������4���CCD��⥶�������˹������뤿�ᡢ���1,600x1,600���ǡ�
- �����������Loral Aerospace��
- ���ǻҥ���������15um x 15um
- ����Ĺ���١���120nm��1,100nm
- �������ǻ��̽�������Lumogen�����ƥ���UV�˴��٤����������Ρ�
- ������ѡ���150"��150"��2ʬ30�óѣ�2ʬ30�óѡ�
- ����¢�ե��륿����48��
- ���ɤ߽Ф��Υ�������5e-
- �������������ȡ���0.0045e-/s/pixel��-88���
- ��˰���Ų١���53,000e-
- ��A/D�Ѵ�����12�ӥå�
- ��Ϫ�л��֡���0.11�á�10,000�á�2����46ʬ��
- ���ᥫ�˥��륷��å�����Ϫ�������椹��2�籩����������å���
- �������ɤ߽Ф����֡���60��
- ���Ż���ѡ���-88��
- ����ħ�������ѻ��Ƥ���ħ��4�Ĥ�CCD�ǻҤˤ��⥶�������ơ�
-
�ϥå֥����ܤ���Ƥ��륫����WFPC2�ˡ�2009.05��ޤDZ��ѡˤˤϡ��ե�ե졼��ȥ�ե�����CCD������Full Frame Transfer Charge Copuled Device�ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
 ���äơ�ž����ϸ�������ʤ��褦�˥ᥫ�˥��륷��å����ǻ����̤�ʤ��ʤ���Фʤ�ޤ���
���äơ�ž����ϸ�������ʤ��褦�˥ᥫ�˥��륷��å����ǻ����̤�ʤ��ʤ���Фʤ�ޤ��� - �ޤ�����®���ɤ߽Ф��ȥΥ���������Τǡ���ä�����ɤ߽Ф��ޤ���
- �ɤ߽Ф��Υ��������뤿��ˡ�CCD������MPP��Multi-pinned phase�˥⡼�ɤǹԤ��Ƥ��ޤ���
- MPP�Ȥϡ��ե�ե졼��ȥ�ե���CCD��Ĺ����Ϫ���ǹԤ����ɤ߽Ф��⡼�ɤǡ�Ϫ����˰����Ű������Ų٤˿��äƤ���������Ǥ���
- �������뤳�Ȥˤ��������ž����ΥΥ������㸺����ޤ���
- �ǻҤϡ�1����15umx15um�ǡ����ߤ�CCD����٤��礭����ΤǤ���
- ���줬800x800���Ǥǰ�Ĥλ����̤��äƤ��ޤ����顢�����ǻ��̤�12mmx12mm���礭���ˤʤ�ޤ���
- ���λ����ǻҤ�4��Ȥäƹ����ϰϤ�ŷ�ΤƤ��ޤ���
- 4���CCD��������Ȥ߹�碌�ơ�1600x1600���ǡʼºݤϥ����С���å�ʬ������Τ�1500���������ˤβ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- CCD�������Ȥ߹�碌��Ƚޤ��������ºݤϡ���Ʊ�Τ�Ž���碌�Ƥ���櫓�ǤϤ���ޤ���
- ��������������Ž���碌���Ԥ��ޤ����������Ƴ���줿�ᥤ��ӡ���ϡ��ԥ�ߥåɥߥ顼��4ʬ�䤵�줽�줾��4�Ĥ�CCD������ޤ���
- ���δ֤ˡ�����Ĵ�������ȥ�졼���طϤ����ꡢ��Ѥ�Ĵ�����ե�������Ĵ�����Ԥ��Ƥ��ޤ���
- �ϥå֥�β������礭����ħ�ˡ����������ŷ�λ��Ƥ��夲���ޤ���
- �ϥå֥뱧��˾����ȥ�����WFPC2�ˤ��Ȥ߹�碌�Ǥϡ�1���Ǥ�0.1�á�1/36,000°�ˤλ���ˤʤ�褦�˺���Ƥ��ޤ���
- 800x800���Ǥ�CCD��4���Ȥ߹�碌�ޤ��Τǡ����礷��1600x1600���Ǥβ����Ȥʤ�ޤ�����1600���ǤΤ���100����ʬ�������Х�åפ�����ʬ�ʤΤꤷ���ˤȤʤ뤿��˥⥶�������Ƥ���������150�á�2ʬ30�óѡˤȤʤ�ޤ���
- ����ϡ�ŷ��˾����Ѥ�CCD�����Ȥ��ƤϹ�����Ǥ���Wide Field�ʹ�����ˤ�̾�����դ����Ƥ����ʤǤ���
- ���οޤ�WFPC2�λ��Ƥ������ = ����Ǥ���
- 4�Ĥ�CCD����餬���줾��α�����֤�ʬô���ƻ��Ƥ��ޤ���
- �����PC��Planetary Camera�ˤ����ϡ������虜�Ⱦ��������ơ��Ĥޤꡢ1���Ǥ�����λ���Ѥ�0.048"���ܰʾ�˾���������ʬ��ǽ��夲�Ƥ��ޤ�������黣�ƤǸ����Ȥ����Υ����ॢ�å��ƤȤʤ�ޤ���
- WF��Wide Field��2��3��4�����ϡ������ϰϤλ��Ƥ������������Ϸϻ��Ƥ˻Ȥ���PC�����ϡ���ˤ������۷Ϥ������Ƥ�����Ū�˻Ȥ��ޤ���
- ��
- ���������������WFC3������2006.11.09���ˡ�2009.05.15�ɵ���
- �ϥå֥뤬1990ǯ���Ǥ��夲���ơ�2009ǯ��19ǯ���Ф��ޤ���
- CCD�����ϡ����δ֡�1993ǯ��2�浡�ȸ���ޤ�����
- ���Υ�����16ǯ���Ф��ޤ�����
- CCD�����ȳ���16ǯ�ϤȤƤ�Ĺ�����ѥ�Ǥ���
- ���δ֡��Ͼ�ˤ��뻣���ǻҤ϶ä��ۤɿ��⤷�ޤ�����
- �ϥå֥�ˤ⡢������CCD�ǻҤ������ؤ������Ȥ�������䤨�����ꡢ�ײ�ˤ�褻���Ƥ��ޤ����������ڡ�������ȥ�λ��Τ䡢ͽ���κ︺���ײ���ѹ��ʤɤǼ¹Ԥ���ӱ�ӤˤʤäƤ��ޤ�����
- 3���ܤ�CCD�����ϡ�2009ǯ5�SM4�ʥ����ӥ��ߥå����4�ˤ�2���ܤΥ�����WFPC2�ˤȸ���ޤ�����
- WFC3��Wide Field Camera 3�˥����ϡ�1997ǯ�˥ץ��������Ȥ�ȯ����2004ǯ�˴��������Ե����Ƥ��ޤ�����
- ���Υ����ϡ����Τ��ϥå֥�˼���դ���1�浡��WF/PC1 = �ǽ���Ǥ��夲�����Υ����ˤ�Ʊ���Ǥ��ꡢ��ͭ�Ǥ������ʤ�ή�Ѥ��Ƥ��뤽���Ǥ���
- 2006ǯ10�����ˤϡ����Υ�����ϥå֥�˻��äƹԤäƸŤ���Τȸ��뤳�Ȥ���ޤ�ޤ�����
- �����ӥ��ߥå�����SM4�ˤ�ǧ�Ĥ����2008ǯ5��˼¹Ԥ���뤳�Ȥˤʤä��ΤǤ��ʼºݤϡ���ǯ�٤��2009ǯ5��˿�ԡˡ�
- ���Υץ��������Ȥˤϡ��ƹ�Ball Aerospace�ҡ�¾�ˡ�NASA Goddarad Space Flight Center��STSci��JPL�ˤ����褷�Ƥ��ޤ���
- Ball Aerospace & Technology Corp. ��BATC�˼Ҥϡ�Ball Corporation�Ҥδ�Ϣ��Ҥǡ����賫ȯ�ط��ε����ȯ���Ƥ���50ǯ����ˤ���ä���Ҥ������Ǥ���
- ���β�Ҥϡ��ϥå֥뱧��˾����θ���Ū�ʷ�٤��狼�ä��Ȥ���1993ǯ�ˤ����к������餤��COSTAR��Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement�˺�Ȥ�Ԥäƥϥå֥�������褵������ҤǤ���
- ���θ��Ӥˤ�ꡢ��������������ˤ�Ȥ�뤳�ȤˤʤꡢWFC3�������Ǥ����ޤ�����
- WFC3�ϡ�����ޤǤ�4�Ĥ�CCD�ǻҤ��夨�ơ�2�Ĥ��ǻҤˤ��Ƥ��ޤ���
- ��Ĥ϶�糰������ֳ��ޤǤ��������CCD�ǻҤǡ��⤦��Ĥ��ֳ���˴��٤����IR�ǻҤǤ���
- ��
 �ڻ��͡�-���Ļ�襫����
�ڻ��͡�-���Ļ�襫����
- �������ס����������̾ȼ�CCD��2�ǻ�1�繽��
- �����ǡ���2,051x4,096���� x 2�ǻ�
- �����������ʹ��4,102x4,096���ǡ�
- �����������E2V - Marconi ��
- ���ǻҥ�������15um x 15um
- ����Ĺ���١���200nm��1,000nm
- �������ǻ��̽�������UV �������ե쥯������ƥ���
- ������ѡ���164"��163"����0.04"/���ǡ�
- ����¢�ե��륿����62��
- ���ɤ߽Ф��Υ�������3.1e-
- �������������ȡ���0.00014e-/s/pixel��@-88���
- ��˰���Ų١���85,000��e-/pixel
- ��A/D�Ѵ�����16 �ӥå�
- ��Ϫ�л��֡���0.5�á�10����
- ���Ż���ѡ���-100��
- ��
- ��
- �ڻ��͡�-���ֳ�������
- �������ס���HgCdTe���쥤�ǻҡ���ǥ� Hawaii
- �����ǡ���1,024 x1,024����
- �����������Rockwell Scientific��
- ���ǻҥ�������18um x 18um
- ������ѡ���123"��137" ��0.13"/���ǡ�
- ����Ĺ���١���800nm��1700nm
- ����¢�ե��륿����15��
- ���ɤ߽Ф��Υ�������30e-
- �������������ȡ���0.2e-/s/pixel��-88���
- ��˰���Ų١���100,000 e-/pixel
- ��A/D�Ѵ�����16 �ӥå�
- ��Ϫ�л��֡���4.3�á�10����
- �������ɤ߽Ф����֡�����8��
- ���Ż���ѡ���6�ʼ��Ż���Ѥˤơ�145K��-123���
- ��
- �����ǻҤ�����Ǥˤʤä����Ȥˤ�ꡢ1���Ǥ�����λ���Ѥ�0.04"�Ƚ����WFCPC2������ܰʾ�ˤʤ�ޤ�����
- ���ƻ����164"�Ȥʤꡢ�����150"�ˤ�꾯�������ʤ�ޤ�����
- �ɤ߽Ф��Υ����⡢�����������ȡʰ���ή�ˤ⽾��Τ�Τ���㸺����Ƥ��ޤ��Τǡ����Υ����ˤ������Ͻ���ʾ�β�����������Τȴ��Ԥ���ޤ���
- ��
- ����WFC3�������
- WFC3�����ι���ǽ�ʰ��̤�Ҳ𤷤ޤ�������ϡ������̤ȥΥ��������S/N�ˤǤ��ꡢ����˲ä��Ƽ����Ǥ���������̤Ǥ���
- ����ϡ���λ��ͤǤ����Ȥ����Ρ�
- ���ɤ߽Ф��Υ�������3.1e-
- �������������ȡ���0.00014e-/s/pixel��-88���
- ��˰���Ų١���85,000��e-/pilxel
- �������������ȡ���0.00014e-/s/pixel��-88���
- �Ǽ�����Ƥ��ޤ���
- WFC3�����ϡ�1�ԥ�����������85,000e-���Ų٤�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������ΥΥ����ϡ�1�ô�������0.00014e-�������äƤ��ޤ���
- �����ơ����������Ų٤�ž������ݤˤϡ�3.1e-�ΥΥ�����ʶ�����Ǥ��ޤ���
- �����ɽ���ȥ����ΥΥ����ϰʲ��μ���ɽ����ޤ���
- ������e-�� = 0.00014 x T + 3.1����e-/pixel����������Lens59��
- �����ǡ�T�ϻ��֡��áˤ�ɽ���ޤ���
- ���μ��Ǥϡ�10�ä�Ϫ���Ǥ�Υ�����0.0014e-������������6���֤�Ϫ�����֤Ǥ�ä��ɤ߽Ф��Υ�����Ʊ����3e-�ˤʤ뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- 6e-�ΥΥ�������ä�80,000e-�μ����ϡ�������ʬ������Ū��¿���ȸ����ޤ���
- ���ʤ����S/N���ɤ������ȸ����ޤ���
- 80,000e-���Ų٤�16bit���Ѵ�����ȡ�65,000������Ȥ��뤦���ΥΥ�������������Τ�5������ȤȤʤ�ޤ���
- �̾��8bit������256������Ȥ����10������Ȥ��Υ����ˤ��줿��ˤȤäƤϡ����ɤ����٤����ͤǤ���
- �Υ������ޤ��뤿����ǻҤ���Ѥ����Υ����νФʤ�CCD���åפ���������ä�����Ф��Ƥ��뤫�餳���Ǥ��뤳�Ȥ��ȸ��虜������ޤ���
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
- �����ե�ͥ��� �ʢ���ñ���-���ե�ͥ������ι�ȡˡ�
- �ե�ͥ��ϡ����Ǥ˽Ҥ٤ޤ������ե�ͥ���������طϤ˻Ȥ����Ȥ�����ޤ���
- �ե�ͥ���Ȥ����̤ϡ��ե�ͥ������ߤ�����ʤ�����礭�����¤Τ�Τ��Ȥ��뤳�ȤǤ���
- ���Υ�ϡ����������ѤȤ��ƻȤ��ˤϲ�����ɤ��ʤ��ΤǤ�����Ū�˻Ȥ����ȤϤ��ޤꤢ��ޤ���
- �ե�ͥ��ˤĤ��Ƥϡ��ե�ͥ����ι�Ȥ��Ʋ�������
- �������ե����С�Fiber Optics�� ����2006.11.26�ˡ�2007.05.13�ɵ���
- ���ե����С��ϡ��ʤ��꤯�ͤä��ɤ���������ͳ�˹Ԥ���Ǥ����ƻ�ɤ������Τ褦�ʤ�ΤǤ���
- ���ե����С��ϡ�����ľ�ʤȤ���������ǰ����ۤ������⤷�����������äƤ��ޤ���
- �ޤä����ˤ����ʤޤʤ��ȻפäƤ��������ޤ�ʤ��ä����塼�֤���������ͳ�˹Ԥ��褹��ΤǤ���
- ���ߤθ��̿��μ���ˤʤäƤ���Τ����ե����С��Ǥ���
- �����ޤ�ʤ��ä�Ƴ���ɤ����ʹԤ��뤳�Ȥϡ�1854ǯ���ѹ��ʪ���ؼ�John Tyndall�ʥ�����븽�ݤ�ȯ�������ؼԡ��졼����β��աˤˤ�äƼ�����ޤ�����
- ��ϲ�Ω�����Royal Society�ˤιֱ�ǡ��夬ʮ���Ф��ή�˸�������ƿ�ή�˱褦�褦�˸���Ƴ����뤳�Ȥ�¸����ޤ�����
- 1881ǯ���ƹ�ޥ����塼���åĤΥ��˥�William Wheeler�ϡ���°�ѥ��פ����̤���̤��ᤤ�Ʋ�����γ��������۴ɤ�����ή�����饢����������Ƴ������ƾ�������ʬ�ۤ������֤�ͰƤ����õ�����ޤ�����
- �����ϡ�����ȿ�ͤ��֤��и��϶ʤ���褦�˿ʤळ�Ȥ����Ƥ��ޤ�����
- �äˡ�������ȿ�ͤˤ��Ƴ���ɤΥ����ǥ��ϡ����Υ������ʤ�̵�±����ã�Ǥ�����������ǽ�Ϥ���äƤ��ޤ�����
- ���θ塢���������ʸ����ã�ˤ�äƥ��饹���åɡ����饹�ե����С���Ȥä�������ã��ˡ�����椵��ޤ�����
- 1960ǯ�ˡ��٤����饹�ե����С��������褦�ˤʤ�ȼ���Ū�ʸ��ե����С������Ӥ�Ω�Ĥ褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����θ��ե����С��ϡ���¤����٤ι⤤��Τ������ʤ��ä��ΤǼ��Ѥˤ��Ѥ����ޤ���Ǥ�����
- �����������٤ι⤤���饹�ե����С��γ�ȯ�ȥ���⡼�ɥե����С���ȯ���ˤ�ä�Ĺ��Υ����������ǽ�Ȥʤ�ޤ�����
- ���ե����С��ϸ��ο�ƻ�ɤΤ褦�ʤ�Τǡ���ƻ�ɤ�ή����Τ褦�˸���ͳ��ή�����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��ͳ��ή���ȸ����Ⱦ������������뤫���Τ�ޤ���
- �ե����С������ͤ��뤹�٤Ƥθ�����ã�Ǥ���櫓�ǤϤʤ��������������������Τ�������ã����ޤ���
- ���¤���������Ǥϡ��ե����С������ͤ�����٤Ȥ������Ĺ�Ǥ���
- �����ϰϤ���ե����С�������äƤ�����϶��Ǥ������糰���Ȥ��ֳ��������ʥե����С��⤢��ޤ���
- ���ե����С��ϡ�����ž�����ʤȤ���ñ���ݤǻȤ����Ѱʳ��ˡ����ݤ�«�ˤ������̤θ�����ã����饤�ȥ����ɤȤ��ƻȤ����Ȥ�����ޤ���
- �ޤ����饤�ȥ����ɤ�Ʊ���褦�ˡ����ݤ�«�ˤ���������ã���륤��������ɤ�����ޤ���
- ���Τۤ����ե����С���«�ͤƥץ졼�Ⱦ��ˤ��ơ��֥������פ⤷����˪��������Τ褦�ʷ��ˤ����ե����С��ץ졼�Ȥ�����ޤ���
- ��
- �ڸ��ե����С���ž��������
- �������ͤ��ͤȶʤ��ä����ݤ����ʤ�ž������Ƥ����ΤǤ��礦�����ե����С��θ����ޤ�ޤ˼����ޤ���
- ���ե����С��κ��ܸ����ϡ�������ȿ�ͤǤ���
- ���ե����С��ϡ�2����θ��غ����Ʊ���߾��˷������줿��ΤǤ���
- �濴������core�ˤȸƤӡ���������åɡ�clad = ��ʤ�ˤȸƤӤޤ���
- ����ξ�Ԥζ���Ψ�ΰ㤤��nc��nd�ˤ���ȿ�ͳ��٤������ޤ���
- ��ȿ�ͳѰʾ�����ͤ�����ϡ����ե����С������ȿ�ͤ��֤��ƿʤߤޤ���
- ��ȿ�ͳ��ٰʲ��θ�����ȿ�ͤ��Ǥ��ʤ��Τǡ����ե����С�����ȴ���Ƥ��ޤ��ޤ���
- �������äơ����ե����С��ϡ���������ͳ��١ʦȡ˰ʲ������ͤ����������ã�Ǥ��ʤ��Τǡ��������ե����С������뤵�ȸƤ֤��Ȥ⤢��ޤ������γ��١ʦȡˤ�������N.A.�Ȥ��ơ��ʲ��μ���ɽ���ޤ���
- ��
- ����N.A. = sin�ȡ������������ҡ�
- ������������N.A. ������������Numerical Aperture
- �������������ȡ������ե����Фؤ����ͳ���
- ��
- ������������N.A. ������������Numerical Aperture
- N.A.�ϡ�����������ʪ�����ޤˤ�褯�о줹��ñ�̤Ǥ���N.A.�ϡ����ե����С��μ���ˤ�äưۤʤ�ޤ�����N.A. = 0.40 �� 0.80���٤�����Ū�Ǥ���
- �����ͳѡʦȡˤ��ٹ礤�ϡ��ե����С�����������غ���ζ���Ψ�Ƿ�ޤꡢ�ʲ��μ��Ǽ������Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- ���� = sin-1���nc2 - nd2�ˡ���������Lens60��
- �������ȡ������ե����Фؤ����ͳ���
- ������nc�����������ζ���Ψ
- ������nd��������å����ζ���Ψ
- ���� = sin-1���nc2 - nd2�ˡ���������Lens60��
- ��μ���ꡢ���ե����С������ͤ����ƥե����С���������ȿ�ͤ��뤿������ͳ��٦Ȥϡ��������ȥ���å����ζ���Ψ�ˤ����ꤵ��뤳�Ȥ��狼��ޤ�������Ū�˥������ζ���Ψ���⤯�ơ�����å����ζ���Ψ���㤤��ΤۤɦȤ��礭���ʤꡢN.A.���礭���ʤ�ޤ���
- N.A.���礭��������ǽ���ɤ����Ȥ�����ɬ�����⤽���Ǥ���Ȥϸ����ڤ�ޤ���
- ����ž���ѤΥ���������ɤ�饤�ȥ����ɡ��ե����С����ץƥ��å��ץ졼�ȤǤϡ�N.A.���礭���ۤɤ�������θ����������������Ǥ���Τǥ��åȤ�����ȿ�̡����ե����С��Τ褦�ʥǡ����̿��ˤ�ɬ��������åȤ��Ф�Ȥϸ¤�ʤ��ΤǤ���
- ������ͳ�ˤĤ��Ƥϡ��ʲ��Ρ��⡼���פǽҤ٤ޤ���
- ����
- �����ե����С��κ����-���бѥ��饹
- N.A.���礭��������ǽ���ɤ����Ȥ�����ɬ�����⤽���Ǥ���Ȥϸ����ڤ�ޤ���
- ���ե����С��ˤϡ�¿���ξ���бѡ�SiO2�˥��饹���Ȥ��ޤ���
- �бѤϡ��糰�����ֳ��ޤ��ɹ���Ʃ����ǽ����äƤ��Ƶ������٤�⤯���⤤���٤ˤ��Ѥ��뤳�Ȥ�����ե����С��μ���Ū¸�ߤǤ���
- ���ե����Ф˻Ȥ����бѤϡ��뾽�бѤǤϤʤ����饹�ʥ����ե������бѤ�Ȥ��ޤ���
- �ե����С��ϡ����⤽�������(�ĤȤ��� = flexibility�ˤ���Ĥ��Ȥ������Ǥ���
- ���ͤ��ͤȶʤ���ʤ���и��ե����С��ΰ�̣���ʤ��ΤǤ���
- ���ΰ�̣���顢�뾽�бѤǤϺ�����Τ�Τ��ꥸ�åɡʸ��ΡˤǤ�����ʤ��뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ���䥬�饹�� = �����ե�����̵������ˤϡ��뾽�Ȱ�äƸ��ΤǤϤ���ޤ���
- �륬�饹�ʤɸ��Τ˸����ޤ������¤ϸ��ΤǤϤʤ����Ǥޤ꤫�������� = �����Ρʤ��褦������solid solution�ˤǤ���
- ���ξڵ�ˡ����饹�ˤ������Ȥ���ͻ��������ޤ���
- Ǯ��ä��Ƥ����ȿ尻�Τ褦�˽����˽��餫���ʤäƤ����ޤ���
- ��ʤɤΤ褦�ˤϤä���Ȥ���ͻ�����ʤ��ΤǤ���
- �����鼼�����֤Υ��饹�Ȥ����Τϡ��¤�Ǵ�٤���ü�˹⤯�ʤä����֤ˤ���ΤǤ���
- ���Υ��饹�����������Ѥ��Ƹ��ե����С�������ޤ���
- ���饹�Ȥ����ȡ��Ť��Ƴ��䤹���Ȥ������ݤ�����ޤ���
- ���ե����С��˻Ȥ���φ125um���٤Υե����С����ݤϡ������������饹�γ�ǰ�Ȥϰۤʤ������2�ܤΰ���ĥ��ٽš���7kg�ˤ��Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- FRP�ʥ��饹���ݤζ����ץ饹���å��ˤʤɤ˥��饹�ե����С����Ȥ�����ͳ�������ˤ���ޤ���
- ���Τ褦�˥��饹�ե����С��ϡ����פǰ���ĥ���ʤ����Ф��Ƥ��ʤ�ζ��٤���Ĥ��Ȥ��狼�äƤ��ޤ���
- ������Ȥ��äƸ��ե����С��μ谷�˵���Ĥ���ʤ����ɤ��櫓�ǤϤ���ޤ���
- ���饹�ˤ�ɽ�̤����٤ʷ�١ʺ٤��ʥ����䵤ˢ�ˤ����äƤ����˱��Ϥ����椹��ȵ�����ȯ�����Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���饹ɽ�̤˵����ʤɤη�٤��ʤ���Х��饹�ե����С���������ζ��٤���Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���
- ���äơ����ǡ����̿��˻Ȥ�����ե����С�����¤�ϸ������ʼ������å����ݤ����ޤ���
- Ĺ��Υ�ǡ���ž���θ��ե����С����߹����ϡ���ۤ��������Ѥ��������ݼ���ưפˤǤ��ʤ����ᡢ���ե����С���٤��Ф�����¤����ʼ������å������Ԥäơ��ե����С���¤������ʤ��Ĥ��ƥե����С����ݸ������˥ե����С���ĥ�Ϥ�Ϳ���ƶ��٤���ʤ��ե����С������Ǥ�����Ȥ���������˥���»ܤ���Ƥ��ޤ���
- ���ե����С��δ��ܺ����ϡ��бѤǤ��뤳�Ȥ�Ҥ٤ޤ�����������å����ȥ������϶���Ψ��ۤˤ��ʤ���Фʤ�ʤ����ᡢ���������Խ�ʪ��ɡ��ԥ��ƶ���Ψ����Ƥ��ޤ���
- �ɡ��פ�������ϡ��бѤȺǤ��������ɤ�����ޥ˥���Ge02�ˤ��Ȥ��ޤ���
- ����ޥ˥����Ge�ˤϡ�����Χɽ�奷�ꥳ���Si�ˤ�Ʊ��IVB²��°�����������Ƥ��뤿�ᡢSiO2ʬ�Ҥ���ñ��GeO2���֤��������뤿��Ǥ���
- GeO2����Ψ��0 - 25���%���Ѥ��Ƥ�뤳�Ȥˤ�ꡢ�б�ñ�Ρ�n = 1.458@λ1.3um�ˤȤ������Ψ��Δ��0 - 2.0%���Ѳ������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���Τۤ��ɡ��פ�������ˤϡ�����ޥ˥����¾�˥���P�ˤ�ä��뤳�Ȥ����ꡢ����Ψ������Ū�ˤ����Ǥ�ե��Ǥ��Ȥ��ޤ���
- ��
- ����¿��ʬ���饹���ե����С���Multi-component Glass Optical Fiber��
- ���ե����С��˻Ȥ������ˤϾ嵭���бѤ�¾�ˡ��̾�Υ��饹�Ǥ��륽�����г����饹��soda-lime glass��Na2O-CaO-SiO2�ˤΤ�Τ⤢��ޤ���
- ���κ���ϡ��ǡ����̿��Ѥ�Ĺ��Υ���ե����С��Ȥ��ƻȤ��ˤ�»���δط���Ŭ�ڤǤϤ���ޤ�������������ɤ�饤�ȥ������ѤȤ��ƤϽ�ʬ�ʲ��ͤ�����²��Ǥ⤢��ΤǸ��ߤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��
- �����ץ饹���å��ʥݥ�ޡ��˥ե����С���Plastic Optical Fiber = POF��
- �ץ饹���å��ե����С��ϡ����ꥳ�����䥢��������ʥݥ������������ = PMMA�ˤǺ���Ƥ��ޤ���
- �бѥե����С�����ٰ²��Ǥ��뤿�ᡢû��Υ���ե����С��̿��ʼ���Ǥ�LAN�ˤʤɤ˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ޤ��������Ѥθ��ե����С��䥪���ǥ����Ѥθ��̿��ѥե����С�����ư�֤Υϡ��ͥ��ʤɤˤ�Ȥ��ޤ���
- �����������ѤˤϻȤ����꤬�ɤ��²��ʥץ饹���å��ե����С����������褫����Ƥ��ޤ���
- �ץ饹���å��ե����С��ϡ�����Ū�˥�����250um��980um����������åɤ������Τ���ħ�Ǥ���
- ��
- �����������Ѹ��ե����С�
- ���ե����С���Ȥä��ǡ���������Ԥ��Ȥ����ե����С��������̲ᤷ�ʤ����������뵡ǽ�������Ĺ��Υ������ɤ����ͭ���ˤʤ뤫¬���Τ�ޤ���
- ��������ǽ����ĸ��ե����С��ϡ��������˴����ี�ǡʥ���ӥ��� = Erbium��Er3+���ץ饻�������� = Praseodymium��Pr3+���ĥꥦ�� = Thulium��Tm3+�ˤ�ɡ��פ�������Τǡ����Υե����С����嵯������0.98um - 1.48um�ˤ�Ŷ����ȿžʬ�ۤ��ꡢ�������ͶƳ���ʥǡ���������ˤ���������ȡ��ե����С���������ϩ�˱�äƸ������������Ȥ������ȤߤˤʤäƤ��ޤ���
- ���ߤǤϡ�����ӥ����Ȥä����ե����С��������Erbium-Doped Fiber Amplifier��EDFA�ˤ�����Ū�ǡ�1.55um�θ�������Ԥ������ƥब����������ǡ����̿������֥�˺��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- �ޤ������θ��ե����С�������ϡ��졼���Ȥ��ƤλȤ�����⤢�ꡢ�ե����С��졼���Ȥ��ƻ��Τ���Ƥ��ޤ���
- ��
- �ڸ��̿��ѥե����С���
- ���ե����С��ΰ����礭�ʥޡ����åȤ����̿��Ծ�Ǥ���
- �����ͥåȤ����ò����⡢����LAN����ե����С���Ȥä��̿�����®�˿��ӤƤ��ޤ���
- ���̿����礭����ħ�ϡ��ʲ��˽Ҥ٤�Ȥ���Ǥ���
- ��
- ������������»�����㤤��0.2dB/km@1.55um�ˡ�
- ���̿����礭����ħ�ϡ��ʲ��˽Ҥ٤�Ȥ���Ǥ���
- ������Ĺ1.55um�Ȥ����ֳ����ȾƳ�Υ졼����Ȥä�1km��4.5%�θ����95.5%��Ʃ��ˤ�����ޤ���
- ���������Ƽ����Ȥä��ŵ��̿���99%�θ��ꡢ1%��Ʃ��ˤ���٤Ƹ����̤���100�ܾ��ʤ����ˤʤ�ޤ���
- ����������������Υǡ����������ʹ�®�����Ӱ衢10Gbit/s & WDM = Wavelength Division Multiplexing�� ��
- �������ե����С��Ǥ�1�ô֤�10Gbit�Υǡ���������ޤ������ξ塢¿���������Ѥ�Ȥ���ʣ���ܤΥǡ����������Ǥ��ޤ���
- �������μ��ȿ��ϥƥ�إ�Ĥǿ�ư���Ƥ���Τǡ�Ƽ���������Ӱ�Ǥ������GHz����٤�1,000�ܰʾ������ǽ�Ϥ�����ޤ���
- ���������к�Ū�����߹�����
- �����Ť�Ƽ���������������٤�ȡ����ե����С�����Ӥˤʤ�ʤ��ۤɤη��̤ʥ����֥����Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������ե����С��ϡ�Ƽ���Τ褦�˿�����ã�˹⤤���Ϥ�ɬ�פȤ��ޤ���
- �����ޤ������Ϥ鷺����»�����㤤���Ȥ���������ʤ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������ե����С��ϡ�Ƽ���Τ褦�˿�����ã�˹⤤���Ϥ�ɬ�פȤ��ޤ���
- ���������ż�ͶƳ���Ф��ƶ�����
- �������ǡ����������������Ȱ������ߤ��Ƥ��ż��Υ����ˤ��ǡ���������ʤ��ʤ뤳�ȤϤ���ޤ���
- �����������ȶ�¸�Ǥ��ޤ���
- ��������ϳ�ä�������ˤ�����
- ���������ŵ�ϳ�š����硼�Ȥ������ʤ���
- ��
- ���̿�����®��ȯŸ�����طʤˤϡ���Ȥ��ʣ���ޤ������ʲ�����ͳ�����ޤ���
- ���������ŵ�ϳ�š����硼�Ȥ������ʤ���
- ��������Ĵ���뵻�ѡ�ȾƳ�Υ졼�����ե��ȥ��������ɡˤ���Ω�������ȡ�
- ������ξ��ʤ����ե����С��γ�ȯ���Ǥ������ȡ�
- �����̿����ż��Υ����˶������ȡ�
- ����������Υǡ�������®���������Ǥ��뤳�ȡ�
- �������֥뤬Ƽ������٤ƺ٤��Ʒڤ��ʤ�Τ����ߤ��ڤ����Ѥ��㸺�Ǥ��뤳�ȡ�
- ���̿��ѤΥե����С��ϡ����ֳ���0.85um��1.3um�Ӱ褬�Ǥ⸺�꤬���ʤ�����¤���䤹���ä����Ȥȡ������Ӱ��ȾƳ�Υ졼�������䤹���ä����Ȥ��顢�ֳ���θ��ե����С��γ�ȯ���ᥤ��˹Ԥ��Ƥ��ޤ�����
- ���λ��¤ϡ��Ļ�����濴�Ȥ�����������ե����С��ȤϾ����㤦��ΤǤ��뤳�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �̿��Ѹ��ե����С��ϡ�Ĺ��Υ�����ȹ��Ӱ�������������֤δؿ����Ǥ���Τǡ�����»������äȤ��㤤��Τ�˾�ޤ�ޤ���
- ������ͳ���顢�̿��ѤȲ���ž���ѥե����С��Ǥϰ�����Ĺ�Ϥ������Τ��ȥե�����ñ���ݤ������ˤĤ��Ƥ⤽�줾���Ŭ�ʤ�Τ�����졢������ե����С��Τ褦�˺٤��ƲĻ���ΰ�˸���Τʤ����뤤��N.A.���礭�������ݤȤ������Ȥϰۤʤä���ΤˤʤäƤ��ޤ���
- ��
- �����⡼�ɡ�Mode��
- �����ѥե����С��ǤϤ��ޤ��礭������Ȥ��줺���̿��ѥե����С����礭������Ȥʤ��Τˡ��ե����С����������������Υ�ΰ㤤�������륺�줬����ޤ���
 ���ե����С��ϡ�������ȿ�ͤ�������Ȥäƥե����С�������¤��뤳�Ȥ�Ҥ٤ޤ�����
���ե����С��ϡ�������ȿ�ͤ�������Ȥäƥե����С�������¤��뤳�Ȥ�Ҥ٤ޤ�����- �ե����С������θ������¾����ϡ����οޤΤ褦�ˤʤ�ޤ���
- ����������ϩ��⡼�ɤȸƤӤޤ���
- �⡼�ɤϡ���ȿ�ͤ������٤������礭���� = ���ͳѤ�����ˤ�Τ���ܥ⡼�ɤȸƤ�Ǥ��ơ����ܥ⡼�ɤ�0���Ȥ��ơ��ʲ�1����2��������������Ȥʤ�ޤ���
- ���ͳ��٤�������ɽ�����ΤϤʤ����Ȥ����ȡ����ե����С���Ǥϡ�Ĺ����Υ���������뤿��ˤ�����ȡ�Standing Wave�ˤ�¸�ߤ�ɬ�פǡ�����Ȥ�Ϣ³�ǤϤʤ��������ӤȤʤ뤿��Ǥ���
- ���ե����С��Τ褦������������¤��������ʸ�����Ĺ��100�ܰʲ��ˤǤ��ȡ�Υ��Ū�ʥ⡼��ʬ�ۤ������˸���ޤ���
- ���ե����С��ˤϡ���������θ�ϩ��������ĥޥ���⡼�ɥե����С��ȡ����̤��������ϩ���������ʤ�����⡼�ɥե����С�������ޤ���
- ����ˡ��ޥ���⡼�ɥե����С��ˤϡ��������ζ��ޤ������ˤ�äƥ��ƥåץ���ǥå�����SI��Step Index�˷��ȥ��졼�ƥåɥ���ǥå�����GI��Graded Index��Gradient Index�˷�������ޤ���
- �⡼�ɤϡ����������Ѥ˻Ȥ��ե����С��ǤϤ���ۤɽ��פʰ�̣����Ĥ�ΤǤϤ���ޤ����ǡ��������Ѥθ��ե����С��ǤϽ��פʰ�̣������ޤ���
- �Ĥޤꡢ�ǡ����̿��ѤȤ��Ʊ��ޡ�a�ˤΥ��ƥåץ���ǥå������ޥ���⡼�ɥե����С���Ȥ��ȡ����������ʳ��٤���ä���ȿ�������¤��졢ȿ�ͳѤ��礭����Ρ�θ2�ˤϸ�ϩ��Ĺ���Τǡ�Ĺ����Υ�����¤���ȿ�ͳѤξ�������Ρ�θ1�ˤȤθ�ϩ�����ǤƤ��ޤ��ޤ���
- �����⡼�ɤ�ʬ����mode dispersion�ˤȸƤӤޤ���
- �⡼�ɤ�ʬ���ϡ����ȿ��ι⤤���ǡ��������������˺����θ����Ȥʤ�ޤ���������褹�뤿��ˤϡ�
- 1.���⡼�ɤ��Ѥ�äƤ����»��֤�·���褦�ˤ��롣
- 2.��ñ��⡼�ɤ����������¤Ǥ��ʤ��褦�ˤ��롣
- �Ȥ�����Ĥ���ˡ���ͤ����ޤ���
- 1.��ʣ���⡼�ɤ����»��֤�·������ˡ�Ȥ��ơ����ޤΡʣ�ˤ˼������GI���ޥ���⡼�ɥե����С�������ޤ���
- ���θ��ե����С��ϡ��������ζ���Ψ����¦�˹Ԥ��˽�������Ψ���������ʤ�褦�ʶ���ʬ�ۤ���äƤ��ơ������γ�¦���̤�����������̤������®�����¤Ǥ���褦�ˤ��Ƥ���ޤ���
- ���Τ褦�������ʶ���Ψ����ʪ��ʬ�ۡˤˡ��������ζ���ʬ�ۤ��Ŭ�������ʣ���Υ⡼�ɤ����¤�������Ф����٤줬�ʤ��ʤ�ޤ���
- GI�����ե����С��η����ϡ������̤�ζ���ʬ�ۤ���ĥե����С���¤�������ˤ���ޤ���
- ���äơ�Ĺ��Υ�ǡ���ž���ˤϡ����ߤΤȤ���2.��ñ��⡼��ž���θ��ե����С����Ĥޤꡢ���ޤ˼����ʣ�ˤΥ���⡼�ɥե����С���Single Mode optical Fiber��SMF�ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����⡼�ɥե����С��ϡ������¤�ɤ�ɤ�٤����Ƥ��ä���ȿ�ͤ�Ԥ������ϰϤ�ɤ�ɤ�Ƥ�����ˡ��Ȥ�ޤ���
- ��������ȥե����С�������¤����ϩ�ϰ��̤ꤷ����ꤨ�ʤ��ʤꡢ���ܥ⡼�ɤ������Ĥ�褦�ˤʤ�ޤ���
- ����⡼�ɥե����С��Υ����¤�10um���٤ǡ��ޥ���⡼�ɥե����С���50um����٤�1/5���٤˺٤��ʤäƤ��ޤ���
- ����⡼�ɤΥ����¤ϡ����Ѥ�����Ĺ��10�ܰʲ��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����⡼�ɥե����С��Ǥϡ������¤��������ơ��������ͤǤ�����γ��٤����¤���뤿�ᡢN.A.���㤯�����������������ӤȤ��ƻȤ��ˤ�������Ψ�������ưŤ����طϤȤʤäƤ��ޤ������ޤ�˾�ޤ�����ΤȤϸ����ޤ���
- ����⡼�ɥե����С��ϡ��ǡ���ž���ѤǻȤ����Ȥ�¿����ΤΡ�����ե����С���������Τ����������Ȥη�����ե����С�Ʊ�Τ��ܹ�˺ٿ������դ�ʧ��ɬ�פ�����ޤ���
- .
- ����⡼�ɸ��ե����С��ϸ��ߤθ��ǡ����̿��ǤϺǤ�Ŭ������ΤǤ��뤿��ˡ����ܤ������������ե����С���90%�ʾ夬����⡼�ɸ��ե����С��Ǥ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��
- ��
- �ڥ饤�ȥ����ɤȥ���������ɡۡ�Light Guide and Image Guide��
 ���ե����С��ϡ����饹�ν��٤��ɤ����ɹ��ʲ�����(�ĤȤ��� = flexibility�ˤ�����ޤ���
���ե����С��ϡ����饹�ν��٤��ɤ����ɹ��ʲ�����(�ĤȤ��� = flexibility�ˤ�����ޤ���- �ե����С���ʤ��Ƥ⤽�ζ�Ψ����ȿ�ͤ�»�ʤ�ʤ����٤ζʤ�����Ǥ���С����ͤ�����������ʤ���ȿ�ͤ��֤��ƼͽФ��Ƥ����ޤ���
- �٤����ߤ�ȡ��ե����С��ζʤ�����ˤ�äƤ�¿��ϳ�줬��������ã���ʤ����Ȥ�����ޤ������������ʤ�������������ʤ���ã�Ƥ����ޤ���
- �饤�ȥ����ɤ䥤��������ɤϡ����ե����С�ñ���ݤ�«�ˤ�����ΤǤ���
- ����¦�Ƚ���¦�ΰ��ִط������������줿��Τ�����������ɤˤʤꡢ���ִط����θ���Ƥ��ʤ���Τ��饤�ȥ����ɤȤʤ�ޤ���
- ����������ɤϥե����С��������פȤ��ƻȤ�졢�饤�ȥ����ɤϸ��ե����С������Ѥθ������Ѹ������ʤȤ��ƻȤ��ޤ���
- ����������ɤϡ�����θ��塢���뤵�θ��塢�����ƥե����С��¤κǾ����������ޤ���
- ����ޤǤΤȤ�����200x200�������٤�40,000�ܤΥե����С���«�ͤ���Τ��³��Ǥ���
- �饤�ȥ����ɤϡ��츫�ʤ������ι�θ��ʤ���Ƥ��ʤ��褦��«�����Ƥ���褦�˸��������ޤ������Ƕ�Ǥϸ����μ���ˤ�ä�������θ������Τ⤢��ޤ���
- ���Ȥ��С��ե����С������ͤ���������˥�餬���ä�����������뤯�Ƽ��������Ť����ˡ��ͽ�¦�Ǥ�����������ƥե����С����Τ˶Ѱ�ʸ��ˤʤ�褦�ˤ�����Τ⤢��ޤ���
- �ե����С���«�ͤ��硢���ޤˤ���褦�ʤ���������«����������ޤ�������ü�Τ�Τ��Ǥ⥪�����ɥå����ʤ�Τ�ñ���ݤ�ñ��«�ͤ������ι�¤�Ȥʤ�ޤ���
- ������ˡ�ˤ��ե����С��Х�ɥ�ϡ�ñ�����¤���ڤʤΤǰ²��ˤǤ�����åȤ�����ȿ�̡����ݴ֤η�֤��礭���Ʋ����٤����뤵�����꤬�����ޤ���
- Ʊ���ޤ˼�����������Ĥϡ���¤���˥ե����С���������Ƽ��ʤ褦�˲����Ĥ�������������ˡ�Ǥ���
- ������ˡ�ϡ��ե����С��Х�ɥ�ν����٤��夬�ä����뤯�ʤ�ޤ��������ݤ��߷��Ȥʤ�ʤ�����˥ե����С��������Ǹ���ϳ���Ȥ������꤬����ޤ���
- ���Τ���˥���å������¤��Ф�����ۼ������������ơ�����ȥ饹���㲼���ɤ����פ���Τ⤢��ޤ���
- ��
- ��

- ��
- ��
- �ڥե����С��¡�
- ��
- ����ž���Ѥθ��ե����С������ݷ¤ϡ����ݿ���¿���ۤɲ�������夹��Τǡ��٤����Ƥ�������«�ͤ뷹���ˤ���ޤ���
- �ե����С��¤�φ50um���٤Τ�Τ�Ȥäƥ���������ɤ���Ȥ���ȡ�200x200���Ǥ���ã�ˤ�10mmx10mm�Υե����С�«���礭����ɬ�פȤʤ�ޤ���
- ���Υ������ϡ��빽�������Ǥ���ߥ����Τ褦�ʥե����С��������פȤ��ƤϻȤ��ʤ��Τǡ����ݷ¤���ߥ������3um���١ˤ˾��������ơ�«�¤����ߥ�Υե����С��������פ������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��������CCD������ǻҤ������ˤʤäƿ��ߥ�Ѥ�640x480���ǤΤ�Τ��Ǥ���ȡ��ʤˤ�ե����С�������ž�����ʤ��Ƥ�ľ����ü�ˤ��äĤ��������ե����С����������ɼ��ʲ����������뤿��ˡ����ߤǤ��ü����Ū�ʳ��ʹ�®�٥����˼���դ�����Ū�ʤɡˤˤϥ�����ե����С���Ȥ鷺��Ķ����CCD����������ü�ˤĤ��������Τ�Τ���ή�ˤʤäƤ��Ƥ��ޤ�����
- ��
- ��
- �ڥե����С����ץƥ��å��ץ졼�ȡ�Fiber Optic Plate��FOP�ˡ�
- ��
 �ե����С��饹�ĤΤ褦��ʿ�ľ��ʤ⤷���ϥơ��Ѿ����Ѷʾ��ˤˤ�����Τ�FOP��Fiber Optic Plate�ˤȸƤФ���ΤǤ���
�ե����С��饹�ĤΤ褦��ʿ�ľ��ʤ⤷���ϥơ��Ѿ����Ѷʾ��ˤˤ�����Τ�FOP��Fiber Optic Plate�ˤȸƤФ���ΤǤ���- ȯ�����ǻҤ����̡�CCD�ǻҤ�ե�����̡ˤ�ľ����³�ʥ��ץ��coupling�ˤ�����˻��Ѥ��ޤ���
- FOP��Ȥ����Ȥˤ�ꡢǤ�դ����������ͤ�������Ϥ�����ǥ����쥯�Ȥ˼����̤ޤ�Ƴ�����Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤꡢ��졼��Ϥǥ��ץ�����������뤤���طϤˤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- FOP�ϡ����äơ������̤�ָ��̤˻Ȥ��뤳�Ȥ�¿�������������ƥե�������Image Intensifier��I.I.���������������֡ˤ�CCD��������³��ݤ˻Ȥ�줿�ꡢX��������졼����CCD�����⤷���ϥե�������³�ʤɤ˻Ȥ��ޤ��ʲ������ȡˡ�
- FOP�η����ϡ��ե����С����ݤ��礭�������ݿ��ˤ�äƲ����Ϥ����ä��ꡢ����ϳ���¾�����ݤ�ʶ�����ǥ���ȥ饹�Ȥ�����Ʋ�������äƤ��ޤ����Ȥ��������ޤ���
- FOP�ϡ�¿���ξ�硢�ե����С��¤�3um��25um�Τ�ΤǤǤ��Ƥ��ơ�10mmx10mm����100mmx100mm���٤��礭���Τ�Τ�����Ƥ��ޤ���
- ��
- �ڥե����С����ץƥ��å��ơ��ѡ���Fiber Optic Taper��FOT�ˡ�
- ��ǽҤ٤�ʿ�Ĥ�FOP��ե������ץ졼�ȤȸƤӡ��ե����С���ϳ�͡ʤ����ȡ����礦���˾��ˤ��������פΤ�Τ�ơ��ѡ��ե����С��ʥե����С����ץƥå��ơ��ѡ���FOT�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ��ʲ����ˡ�
- �ơ��ѡ��ե����С��ϡ������̤ȼͽ��̤��礭�����ۤʤ��ΤǤ���
- ���������ƥե������ʸ������������֡ˤʤɤ�����¤Τ�Τ���Ͼ�������������CCD�ǻҤ�ľ����³�ʥ��ץ�ˤ���Ȥ��ˡ��ơ��Ѿ��Υե����С��ǻҤǽ̾�������������ã�����ޤ��ʲ��ޱ��ˡ�
- �������뤳�Ȥˤ����������Ϥ���Ȥ����ˤ��������뤤�������ǻҤ���ã���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ե����С����ץƥå��ơ��ѡ��ϡ��������и���ե����Фο����Ѥ�餺�˥ե����С�ñ���ݷ¤��Ѥ��ޤ���
- ���Υե����С��η����ϡ����λ����ǻҤ��Ȥ߹�碌��ȡ��ե����С�ñ���ݤȻ����ǻҤβ��Ǥΰ��ִط��ˤ�äƥ⥢����μʡʥ�����磻���ˤ��Ф䤹���ʤ�ޤ���
- �ޤ�����¤�塢�����̤ȼͽ��̤˴������Ĥߤ��Ф䤹����ˡ���٤��᤹���¬��Ū�ˤ����դ�ɬ�פȤʤ�ޤ���
- ����
- ��
 ��
��
- ��
- �ơ��ѡ��ե����Фϡ�ñ���ݥե����С���Ʊ���������ȤäƤ��ޤ��Τǡ�������Ƚи��Ǥ����ݷϤ��������ۤʤ�ޤ���
- �ơ��ѡ��ե����С��ϡ��̾��礭���̤�φ20mm��φ30mm�ǡ��������̤�φ8mm��φ11mm���⤵��15mm��25mm�Τ�Τ�����Ū�Ǥ���
- ����ϡ��ơ��ѡ��ե����С��μ��פ���ޱ��˼����褦��I.I.��CCD���λ����ǻҤ���³������Ū��¿������Ǥ���
- �̾�Ψ�ϡ�1:1.6��1:3.0���٤Ȥʤ�ޤ���
- �ơ��ѡ��ե����С���ñ���ݤϡ����ݷ¤�6um��25um�ǡ�����Ψ��N.A.�ˤ�1.0�Τ�Τ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �����ϰϤθ��ä������Ǥ��빽¤�ȤʤäƤ��ޤ���
- �������ȥ���å��������Ѥ���ϡ�1�������̾�Υե����С����⥯��å����������ʤäƤ��ޤ���
- ���Τ��Ȥϡ������鹭�����٤Ǹ������ͤ��Ƥ��줬���٤������Ǥ����Ȥ��Ƥ⡢����å��������ͤ�����������Ǥ��ʤ��Τǡ�50%���������������Ǥ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ����å������֤�������������Ǥ����¸��Ȥʤ�Τǡ�������������ۼ�����ϳ����Ȥʤ�ʤ��褦�˷�֤ˤ�EMA��Extramural Absorption�˽������ܤ�����¸���ۼ�������֤��ܤ���ޤ���
- �ڥե����С����åɡ�Fiber Rod��Image Conduit��
- �ơ��ѡ��ե����Фϡ�ñ���ݥե����С���Ʊ���������ȤäƤ��ޤ��Τǡ�������Ƚи��Ǥ����ݷϤ��������ۤʤ�ޤ���
- �ե����С����åɤϡ������θ��ե����С��Ǥ���
- �ż����إ��饹�ˤ�äƤǤ����ե����С����ץƥ������ǡ�FOP����Ĺ����Υ����ã�����������˻Ȥ��ޤ���
- �ե����С��¤ϡ�φ12um����φ100um���٤Τ�Τ�«�ͤƳ��¤�3mm����10mm���٤Ȥ���Ĺ����25mm����300mm���٤Τ�Τ����Τ���Ƥ��ޤ���
- �������åɳ��¤Τ�Τ��ʤ������������ꥢ�ǻ��Ѥ���Τ�����Ū�ȤʤäƤ��ޤ���
- �ե����С����åɤˤ������ã�����Ϥϡ�42��/mm����5��/mm�Ȥʤ�ޤ���
-
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
-
- �����ü�ʥ���ط� ��
- �����ƥ쥻��ȥ�å����طϡ�Telecentric Optics�ˡ� ��2006.07.17�ˡ�2007.07.01������
 �ƥ쥻��ȥ�å����طϤϡ���ǯ�������ѥ�����ȯŸ�ȶ��˻��Ѥ���Ƥ���ݥԥ�顼�ʷ�¬�ѥ�Ǥ���
�ƥ쥻��ȥ�å����طϤϡ���ǯ�������ѥ�����ȯŸ�ȶ��˻��Ѥ���Ƥ���ݥԥ�顼�ʷ�¬�ѥ�Ǥ���- �ƥ쥻��ȥ�å��δ�ñ�������ϡ���ˡֹʤ�ε�ǽ - ���ƥ쥻��ȥ�å������פǤ����ʤ��ޤ�����
- �ƥ쥻��ȥ�å���ΰ��֤���ħ�ϡ����Ƶ�Υ��¿���Ѳ����Ƥ�����Ψ������Ǥ��뤿�ᡢ�����������ػ��Ƥ��Ǥ��뤳�ȤǤ���
- ����������褫���ơ����ʸ����ѤȤ������Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���ߤǤϡ�CCD��������ɽ�Ȥ������ʸ����������ֻԾ�μ��פ⤢�äơ�¿���Υ������ƥ쥻��ȥ�å����꤬���Ƥ��ޤ���
- ���衢�ƥ쥻��ȥ�å����طϤ����Ѥ������ص���ȸ����С���ǽ��Ƶ���Profile Projector�ˤ���ɽŪ�ʤ�ΤǤ�����
- �ޤ���ȾƳ�λ��Ȥ�ȯŸ��ȼ�ä�IC��ϩ��������ե����Lithography Optics�ˤˤ⤳�θ��طϤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��ǽ��Ƶ��ϡ����ơ����ξ�˻��֤�ͥ��ʤɤε����������ʤ��֤��Ƹ���Ū�˳��礷�����ڤ�Υԥå���ͥ����η��������١�ɽ�̤Υ����ʤɤ�¬�ꤹ���ΤǤ���
- ���֤�ͥ��ơ������֤����Ȥ�������θ����DZ���������Ψ���Ѳ���������Τʷ���¬�꤬�Ǥ��ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å����طϤ�Ȥ��ȡ�����Τ���������������äƤ���������Ψ���Ѥ�餺�����Τ���ˡ¬�꤬��ǽ�Ȥʤ�ޤ���
- ��
- ��ʪ�Τ����ˡ
- ����˼������ޤϡ������������ʤ���������ˡ��ɽ������ΤǤ���
- ������Ω��Ū��ɽ���ơ�������ˡ���İ�����Ω�ο�ˡ�Ȥ��Ƥϡ���������ѿޡ�isometric drawing�ˤ�����ޤ���
- ����ϵ������ʤ������ˤ褯�Ȥ����ΤǤ����̾�Υǥ����륫�������ʤƤ���ȡ�¿���Ͽޤκ����Υѡ����ڥ��ƥ��֤Τ����ΤȤʤ�ޤ���
- �²��ʥǥ����륫���Ǥϡ����������������������뤿��˥ѡ����ڥ��ƥ��֤ζ������¿���褦�˸��������ޤ���
- �²��ʥǥ���������ʤ�ȻͳѤ���Τ��ͳѤ��̤�ʤ����Ȥ�¿������ޤ���
- �������������Ǥϥ�˶ᤤʪ�Τۤ��礭���̤ꡢ�˹Ԥ��ۤ���Ψ���������ʤ�ޤ���
- ���äơ�Ʊ��Ĺ���Ǥ���Τ˻��Ƥΰ��֤ˤ�ä��礭�����Ѥ�äƤ��ޤ�������Ĵ���줿��ΤȤʤ�ޤ���
- ��¬�����Ǥ��Τ褦�ʥ���Ѥ���ȡ�Ƚ�Ǥ��礤�˸��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �������̤ϡ���ޤα��˼���������ˡ��third angle projection�ˤǼ�����ޤ���
- ���ο�ˡ����ħ�ϡ�ʪ�Τ�Ȥ餹������ʿ�Ը��Τߤ˸��ꤷ�ơ����줾�������̡�X�̡�Y�̡�Z�̡ˤ˱Ǥ��Ф��줿��Ʒ�������̤ˤ�����ΤǤ���
- ���̤���Ƥ������������̤��Ф��ƿ�ľ�Τ�Τ����ʤΤǡ��������ˡ�ϰ��Υƥ쥻�åȥ�å���ˡ�Ȥʤ�ޤ���
- ����ˡ�ϡ�ʪ�Τ���ˡ���ˤ�����Τˤ������ݤ褯ɽ������ޤ���
- ����黣�Ƥˤ��μ�ˡ�������줿��Τ�ƥ쥻��ȥ�å����Ƥȸ����������¸�������ƥ쥻��ȥ�å���ȸ����ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å���ˤ���ǽ���ɤ���ΤȰ�����Τ�����Τ������Ǥ���
- ���ߤǤϡ����������ʥ������¿����Υ�����ʲ�����Ƥ��ޤ���
- ��
- �����ƥ쥻��ȥ�å��ιͤ���
- ��

- �ƥ쥻��ȥ�å��δ���Ū�ʹͤ������ޤ˼����ޤ���
- ���οޤϡ�2����θ�������������������ΤǤ���
- ���ޤϡ�����������Ф����������ʿ�Ը��ˤ�����ΤǤ��ꡢ���ޤ����������Τ�Τ�����Τ����ƤƳ���������ˤ�����ΤǤ���
- ���������Τ褦���������Ǻ��������������ޤγ�����Ƥ������������۸��Τ褦��ʿ�Ը��κ��Ƥ����ޤ�������Ƥ��������ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å����طϤϡ����ޤ�ȯ�ۤ��Ȥ˺��줿���طϤȸ����ޤ��礦��
- �Ĥޤꡢ���Ƥ���ʪ�Τ������ͤ������Τ���ʿ�Ը�����ʬ�������������˻��Ѥ���С�����̤˶ᤤ�ˤ�����餺��ΔL�κ������ä��Ȥ��Ƥ������Τ���¤��������������Ȥ�����ΤǤ���
- ��
- ��������ץ�ʸ��طϤǤιͻ�
- �����ǡ�����ץ�ʥƥ쥻��ȥ�å����طϤ�ͤ������ΤǤ����Ƥߤޤ��礦��
- ���ޤˡ���ñ�ʥƥ쥻��ȥ�å����طϡ�ξ¦�ƥ쥻��ȥ�å����bilatelal telecentric lens�ˤ��ޤ���
- ����ϡ�2��Υ�ǹ�������Ƥ��ޤ���
- ���̥�ξ�����Υ��f1����̥�ξ�����Υ��f2�Ȥ��ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å��δ��ܤ����ϡ����̥��f1�θ����������֤˹ʤ���֤����ȤǤ���
- ���ιʤ�ˤ�äơ�ʪ�Τ������ͤ���������Τ����������ʿ�Ԥʸ�«��ʬ�����٤Ƥ����ϰϤ˴ޤޤ��褦�ˤʤ�ޤ���
- ���ζ��֥ե��륿��Ư���ޤ�����
 ��
��
- �����ʤ�ΰ�̣��-���ɤ��ޤǹʤ���ɤ�����
- ��οޤǤϡ��ʤ��ʤ�йʤ�ۤ�ʪ�Τ���θ���ʿ�Ը�����Ʃ��Ǥ��ʤ��ʤꡢʪ�Τ�ɤΰ��֤ˤ����Ƥ�ԥ�Ȥ��礦���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �����Ƥޤ���ʪ�Τ�ɤΰ��֤ˤ����Ƥ�����Ψ���Ѳ����ʤ��Ȥ�����äƤ�ʤ����طϤˤʤ�ޤ���
- �����������ιͤ��˽��äƹʤ��ʤꤹ����Ȱդ�ȿ������̤Ȥʤ�ޤ���
- �ʤꤹ����ȡ������ܥ��Ƥ��ޤ��ΤǤ���
- ����ϡ���β����ݤ˵��������ΤǤ���
- ���ޤϸ��κ���Ū�������Ǥ����顢������ӽ����뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- �ʤ�йʤ�ۤ����Ϥܤ��ޤ���
- F/16�θ��طϤˤ��Ǿ����ݥåȤ�20um�ʥߥ�����ˤˤʤ�ޤ���
- ����ϡ���CCD������3x3����ʬ�����������礭���Ǥ���
- 7umx7um�Υԥ����륵��������ĸ��λ����ǻҤ˺�Ŭ���������Ф���ˤϡ��ʤ��F/5.6���٤ˤ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- F/5.6�θ��������ĥ�ϡ��㤨�о�����Υ��f80mm�Ǥ���Ȥ���ȡ��ʤ���¤���14mm�ˤʤ�ޤ���
- ������οޤιʤ�����ƤϤ�Ƹ���ȡ���ʬ�ȷ���礭�ʹʤ�ˤʤ뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ����DZ��̤Τ���ʱ��Ԥ������Τ����ʪ���̤㡼�פ����Ȥ��ƤȤ館����ΤǤ��礦����
- �ʤ���礭�����Ƥ������ʹʤ���Ƥ������ˡ��ե��������ä���Ԥ�ʤ��Ȥ��줤�ʲ��������뤳�ȤϤǤ������ޤ����ե��������ι礦�ϰϤⶹ���ʤ뤳�Ȥ����ۤ���ޤ���
- �Ĥޤꡢ�ʤ����ȡ����Ƶ�Υ���դ��������ԥ�Ȥ����ʤ��ʤ�ޤ���
- �Ǥ������ƥ쥻��ȥ�å�����̾�Υ�Ȱ�äơ��ԥ�Ȥ��ܥ��Ƥ�ܥ��ˤ����Ψ�Ѳ��Ϥ���ޤ���
- �ʤ��ʤ�С�����Ǥ�դ����ˤϡʤɤ����ˤ�˼�����Ȥ��Ƹ�����ʿ�Ԥʸ�«���ޤޤ�Ƥ��뤫��Ǥ���
- ���줬�ƥ쥻��ȥ�å����礭����ħ�ʤΤǤ���
- ��Ψ���Ѳ����ʤ�����ɡ��ʤ���Ƥ��������ϥܥ��䤹���ʤ�ޤ���
- �����ˤ��Ƥ�������̳����٤������ʤ뤫��Ǥ���
- ����ϡ����̤Υ�������Ѥ��ޤ������ΤȤ����ϡ���ʬ�����Ƥ���ɬ�פ�����ޤ���
- ��
- ������̳�����
- �ƥ쥻��ȥ�å����Ȥ��ȡ�����Το��٤Ϥɤ����٤ˤʤ�ΤǤ��礦����
- �ƥ쥻��ȥ�å������̳����٤ϡ����̤ǤΥܥ����̡�δ�ˤ���ջ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���̤ǵ��Ƥ����ܥ��̡�δ�ˤϡ������ǻҤ�1����ʬ�Ȥߤʤ��٤��Ǥ���
- ���ξ��ϸ������Ȥ������Ȥ�2x2���ǤȤ�����⤢��褦�Ǥ��������Ƥ�ˤ��Ф�������ʼ��ΰ��������Ȥʤ�ޤ���
- ��οޤϡ��ƥ쥻��ȥ�å���θ�̤���ʬ�ˤ�����������ͻҤ�����Τǡ��������˴�Ϳ����������ɤΤ褦�����äƤ��뤫��ɽ���Ƥ��ޤ���
- ���οޤǤ��äˡ��ܥ���δ�ˤ�������뿼�١ʣ�ˤ��ɤ����٤���Τ����Ƥ��ޤ�
- ������Ψ
- ���ƺ����
- ���ʤꡡ
- ��̳�����
- ���³�
- M=1
- �������8.8mm
- at 2/3��CCD��
- �������8.8mm
- 12um
- F2.8
- 34um
- 3.4um
- F8
- 96um
- 9.6um
- F16
- 190um
- 19um
- F64
- 760um
- 77um
- M=1/2
- �������18mm at
- 2/3��CCD��
- �������18mm at
- 12um
- F2.8
- 140um
- 3.4um
- F8
- 0.4mm
- 9.6um
- F16
- 0.8mm
- 19um
- F64
- 3.0mm
- 77um
- M=1/4
- �������36mm at
- 2/3��CCD��
- �������36mm at
- 12um
- F2.8
- 0.5mm
- 3.4um
- F8
- 1.5mm
- 9.6um
- F16
- 3.1mm
- 19um
- F64
- 12mm
- 77um
- ������Ψ�ȥ�ʤ�ˤ��ƥ쥻��ȥ�å����
- ��̳�����
- ��������Ҥ٤ޤ��ȡ��������١ʣ�ˤϰʲ��μ��ǵ�ޤ�ޤ���
- �ޤ���̳����١ʦ�L�ˤ�ʲ��Τ褦�˵�ޤ�ޤ���
- ��
- ���������� d = ��F����������Lens61��
- �����������������䡧����������
- �����������������ġ������ƺ����
- ����������������F������ʤ�
- ��
- ��
- ���������� ��L = ��F/M2����������Lens62��
- ������������������L����̳�����
- ����������������M�����ƥ쥻��ȥ�å���Ψ�� = f2/f1��
- ��
- �ƥ쥻��ȥ�å���Ǥ���̳����٤���뼰�ϡ����̥��ɽ�������̳����٤μ��ȰۤʤäƤ��ޤ���
- ����ϡ��ƥ쥻��ȥ�å������2�ĤΥ����f1�����f2����ˤ�����Ω�äƤ��ơ���«�����ʿ�Ը���ȼ�äƤ��뤳�ȤȻ��Ƶ�Υ������f1����ξ������֤����ꤵ��뤳�Ȥ���嵭�μ���Ŧ�פǤ��ޤ���
- �ޤ���̳����١ʦ�L�ˤ�ʲ��Τ褦�˵�ޤ�ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å����Ȥä����ܻ��ơ�¨��9mm���٤�����Τ�2/3��CCD�Dz��̤��äѤ��˻��ơˤ�����ϡ�M=1�Ȥʤ�ΤǾ������١�d�ˤϵ��ƺ���ߡ�δ�ˤ˥�ʤ�ʣơˤ�ݤ�����ΤȤʤꡢ��̳����٤�����ܤǤ�����˾������٤�Ʊ���ͤˤʤ�ޤ���
- ���٤ϡ����Ƥ����ܥ��̤�¿�����Ѥ��п������뤳�Ȥ��Ǥ����ޤ��ʤ�ۤɿ����ʤ뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �ޤ������ϰϤ�̾����ƻ��Ƥ�����M�����������طϡˤϡ����٤����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������Ƥߤ�ȡ��ƥ쥻��ȥ�å���ϥե��������ܥ��ˤ�ä�����Ψ���Ѳ����ʤ��Ȥ��������Ϥ����ΤΡ����٤Ϥ���ۤɿ����Ȥ�ʤ����Ȥ��狼��ޤ���
- �������ʤ���ºݤ˻ȤäƤߤ�ȿ��٤������褦�ʺ��Ф˴٤�ޤ���
- ����ϡ��ե����������ܥ��Ƥ���Ψ���Ѥ��ʤ�����ˡ��ԥ�Ȥ�3��4���Ǥ��Ϥäƥܥ��Ƥ��Ƥ�ԥ�Ȥ���äƤ���ȴ��㤤���Ƥ��뤿��Ǥ���
- ��
- ����ͭ�������ϰ�
- �ƥ쥻��ȥ�å���Ǥϡ����̥�θ��°ʾ�ι�����ʪ�Τ�Ȥ館�뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ���̥�θ��¤�φ30mm�Ǥ���ʤ顢����Τ�30mm�ʲ��Τ�Τ������ƤǤ��ޤ���
- ����ϡ�ʪ�θ���ʿ�Ԥ˥�����뤳�Ȥ����Υ�δ��ܤˤʤäƤ��뤳�Ȥ�����Ǥ���Ȼפ��ޤ���
- ���äơ��ƥ쥻��ȥ�å����ƤȤ����Τ����Ū��Ψ�ι⤤���ơ�= ���绣�ơˤ˸����Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ������Ψ��1/10�Υƥ쥻��ȥ�å���ϡ�����¤����ʤ��礭�ʤ�Τˤʤ�ޤ���
- �㤨�С����λ�����Ψ�ǡ�2/3����8.8mmx6.6mm�ˤ�CCD������ѤΥƥ쥻��ȥ�å�����ä��Ȥ���ȡ����̤�110mmɬ�פȤʤ�ޤ���
- ����������ϡ�ɬ��Ū���礭�ʥ�Ȥʤ����ˤ�ʤ�ޤ���
- ��
- �������Ƶ�Υ
- �ƥ쥻��ȥ�å����ʹ���ȡ��ʤ�Ȥʤ����Ƶ�Υ�Ϥɤ��Ǥ�礦�褦�ʰ��ݤ�Ϳ���ޤ���
- ���������ºݤΤȤ����ƥ쥻��ȥ�å���ˤ�ե���������ɬ�פǤ��ꡢ�ե��������ι礦�ϰϤϸ¤��Ƥ��ޤ���
- ��Ψ��������Ȥ����Τϡ���̳��������ʪ�Τ˸¤ä����ȤʤΤǤ���
- ��̳����٤����Хե��������ϰϤϹ������ޤ���
- ���μ�ˡ����ȥ���Ť��ʤꡢ����ˤϲ��ޤΤ���������Τ��ܥ���Ȥ��������ȯ�����ޤ���
- �ƥ쥻��ȥ�å���ǿ侩����뻣�Ƶ�Υ�ʳ��λ��ѡ��Ĥޤꡢ��ʪ�Τ⤷���϶��ʪ�Τ��֤������Ƥξ����������ƥ쥻��ȥ�å�����������ΤǤ��礦����
- �����ϡ֥Ρ��פǤ���
- ¿���Υƥ쥻��ȥ�å���ϡ��ԥ�ȵ�ǽ����ˤĤ����Ƥ��ޤ���
- ������夷����������Τ����夵���ƥե����������碌��褦�ˤʤäƤ��ơ���Υե������å��ϸ���ˤʤäƤ���ΤǤ���
- �������������䤹���ƥ쥻��ȥ�å������ݤƤ뤫��Ǥ���
- �ƥ쥻��ȥ�å�������Ǥä������ˤϡ����ʤ깭�ϰϤ˥ե����������礦���ͤˤʤäƤ����Τ�����ޤ���
- ������������������λ��ͤ�ܺ٤˸���ȡ������ƥ쥻��ȥ�å��ȸ����褦��â�����Ĥ��Ƥ��ޤ���
- ����������С��ƥ쥻��ȥ�å����ݤƤ��ϡ���δ�ñ�ʸ��ؿޤ˼�����ǡ�������̤ξ������֤�ʪ�Τ��֤��Τ���äȤ�����Ū�ȸ����ޤ���
- ���äơ�����������W.D��Working Distance����ư��Υ�ˤȽ�Ƥ���Τϡ��ۤȤ�ɤξ�����̤ξ�����Υ���֤ȤʤäƤ��ޤ���
- ���λ��Ƶ�Υ�ǹʤ�ȵ��ƺ���ߤ����������̳����٤��ϰϤǥƥ쥻��ȥ�å�����telecentricity�ˤ��ݤ���ޤ���
- ��
- �������Υƥ쥻��ȥ�å���Υ��������θ���
- �������������μ�����äƻ��Τ���Ƥ���ƥ쥻��ȥ�å��λ��ͤƤߤޤ��礦��
- ���˼��夲���ƥ쥻��ȥ�å���ϡ��ɿ�Ū�ʸ������ʥ�������������˷Ǻܤ��Ƥ���ƥ쥻��ȥ�å���λ��ͤΰ����Ǥ���
- �ƥ쥻��ȥ�å���ϡ����������ʥ������Ф���Ƥ����ΤΡ������ǡ����Ϥޤ��ޤ��Ǥ���
- ����������Ƥ���ǡ�������ˤϡ���ιʤ���ư��Υ����̳����٤��������Ƥʤ���Τ⤿�����������ޤ���
- ���ɾ������¦���鸫��ȡ�����礭���ȽŤ����ɤΥ����פΥ����˻Ȥ��뤫��������Ψ�Ⱥ�ư��Υ������˹ʤ���ϰϡ���̳����٤���������Ƥ��뤳�Ȥ������ɬ�פʹ��ܤȹͤ��ޤ���
- ��
- ������Ψ
- x 1
- x 0.25
- �ʤ��ϰ�
- F6 �� 25
- ��
- ��ư��Υ
- 98 �� 123mm
- 161 �� 186mm
- �»���
- ��2/3���ǻҡ�
- 8.8mm
- 35.2mm
- ����Τ��礭���᤹���ƥ쥻��ȥ�å���ϡ�����Ū
- ��10mm����40mm���٤�¿����
- Ʊ��
- ��1/2���ǻҡ�
- 6.4mm
- 25.6mm
- �����������ǻҤΥ����ϡ�Ʊ��������Ψ�Ǥ⾮�������ꥢ����
- ���ƤǤ��ʤ���
- �ƥ쥻��ȥꥷ�ƥ�
- <0.1��
- ��
- �����ֲ�����
- ��at F/10��
- 40��/mm�ʾ�
- ��12.5um��
- ��
- ���ֲ����Ϥ��⤤�����٤��������뤳�Ȥ��Ǥ��롣
- ���ܻ��ƤǤϡ�1�������٤ޤǤ�ʬ��ǽ����Ԥ�������
- �ǥ����ȡ������
- =<0.1%
- =<0.5%
- ��̳�����
- ��at F/10��
- ��0.6mm
- ��8.5mm
- �����ϰϤˤ�������Τ˥ե����������礦��
- ���ʤ�п��٤Ͽ����ʤ뤬��ʬ��ǽ�������롣
- �ե��륿�ޥ����
- M62 x 0.75
- M72 x 0.75
- ���ѥ����
- 2/3���ʲ��λ����ǻ�
- ��
- ������ˡ
- ��68x200mm
- ��79x196mm
- ����
- 1.2kg
- 1.6kg
- ���ͥǡ�����
- ��Edmund Optics
- �����ǥ����륫������¦�ƥ쥻��ȥ�å����
- �Ƕᡢ��ή�ˤʤäƤ���ǥ��������ե����Υ�ˤ�ƥ쥻��ȥ�å�����Ȥ��뷹���ˤ���ޤ���
 �ƥ쥻��ȥ�å���ȸ��äƤ⡢��¦�ƥ쥻��ȥ�å���Ǥ���
�ƥ쥻��ȥ�å���ȸ��äƤ⡢��¦�ƥ쥻��ȥ�å���Ǥ���
- �����ΤΤ褦�˥ǥ����륫���ϡ�����ե����Ȱ�ä�1���Ǥμ���������ϩ�α��˰��ù�������ܹ�¤�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ι�¤�Τˡ������μ������������������̤���ʬ����ã�Ǥ����������㲼�θ������äƤ��ޤ���
- ��������β��Τ������¦�ƥ쥻��ȥ�å����ȯ����ư�����ФƤ��Ƥ��ޤ���
- �����ѥ����ƹ�Kodak���濴�Ȥʤäơ��ե�����������Four Thirds�ˤȤ�����������夲�ơ������ȥ���������Ƥ��ޤ���
- ���ε��ʤι��ʤϡ�����Ȥ��Ƥ����ʶ���˥ե���५����ѤΥ���̤����ƥǥ����륫����˺�Ŭ�����������Ȥ������䤫����Ƥ��ޤ���
- �����ǻҤα��ܤ��б����뤿��ˤϡ��ǥ����륫����ѥ���˺��ɬ�פ�����������Ȥ����ΤǤ���
- �����ơ������������ǻҥ���������ƤǤ���
- ���ϡ����λ����ǻҤ��礭����4/3����3ʬ��4�������������3ʬ��1���ͤġ�������four thirds�ˤȤ��ޤ�����
- �����ǻҤϡ�17.3mmx13mm���礭������äƤ��ޤ���
- �ե�����Ⱦʬ���г���Ĺ��φ43.27mm→φ21.64mm�ˤ��礭���Ǥ���
- �IJ���ʥ����ڥ�����ˤϡ�1:1.33�Ǥ���
- ����ϡ��ե����ʱDz�ˤΥ����ڥ��ȤǤϤʤ����ƥ�Ӳ��̡�4:3�ˤΥ����ڥ��ȤǤ���
- ����������¦�Υޥ��������ˤ�äơ��ե���५����3:2��ϥ��ӥ�����16:9���б��Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ߡ����Υ��롼�פˤϡ�Kodak��Olympus��Panasonic��Leica��SIGMA��FujiFilm��SANYO�����ä��ơ�����ǻҡ���������Τ뤷�Ƥ��ޤ�����
- ����̵�±���طϡ�Infinity Optics��
- ��ĤΥ�������������ݤ˻Ȥ�����������ˡ�Ǥ���
- �������Ǥ���ʪ����ܴ���������ѷ�����Ǥ������֤��뤳�Ȥ�¿�����������֤Ǥ���ʪ�����ƤⲼή�Υ�����֤��뤳�Ȥʤ��Ȥ���Τ������Ǥ���
- ��
- �����졼���饤�ȥ����ȡ�Laser Light Sheet��
- �졼���饤�ȥ����ȤˤĤ��Ƥϡ�
- �֥졼���饤�ȥ����Ȥκ�����ס�http://www.anfoworld.com/LLS.html��
- �Ǿܤ����������Ƥ��ޤ���
- ��
- �������������طϡ�Schlieren Optics��
- ���������طϤˤĤ��Ƥϡ�
- �֥������ˡ�ס�http://www.anfoworld.com/scliettl.htm��
- �Ǿܤ����������Ƥ��ޤ���
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- .



������Ψ����x0.25�ϡ������̤�4�ܤΥ��ꥢ�Ƥ��롣 ��ιʤꡣ�������뤯��F6�����꤬�Ǥ��롣 �����ü��������ΤޤǤε�Υ�������ϰϡ� 0�뤬���ۤǤ��뤬�����¤�ʿ�Ը�«���餺��Ƥ��ޤ��� ��¬�ѤʤΤ������Ĥޤʤ��������ޤ����� �����ü�����夹��ե��륿���礭����0.75�ϥͥ��ԥå��� ���Υ�Ǥϡ��礭���ǻҤ���ĥ����ϻ��ѤǤ��ʤ��� ��γ�����ˡ�� ��νŤ��� ��ɽŪ�ʥƥ쥻��ȥ�å���λ��� .
- ��
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
��
|
|
||||
|
|
||||


















